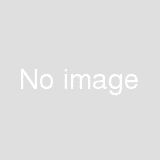Copilotを業務で使い始めた多くの方が抱く疑問のひとつに、
「入力した情報が勝手に学習されて外部に漏れないか?」 という不安があります。
実際、Microsoft Copilotはユーザーごとのデータをそのまま基盤モデルに再学習させる仕組みではありません。
しかし、利用履歴や診断データが保存される場合があり、設定や運用を誤れば情報漏えいリスクを高めてしまうのも事実です。
特に法人利用においては、
- 機密情報を入力してよいのか
- 「学習されない」状態をどう担保すればいいのか
- 管理者や利用者が取るべき具体的な対策は何か
といった観点で、明確なルールと設定が求められます。
本記事では、Copilotに学習させないための具体的な設定方法と、法人での安全な運用ルールを徹底解説します。
個人利用の方はもちろん、社内展開を検討する管理者の方にとっても、今日から実践できる実務ガイドとなるはずです。
AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。
■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする
※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Copilotは本当に学習しているのか?(誤解の整理)
「Copilotは入力した情報を勝手に学習してしまうのでは?」という声をよく耳にします。
しかし、ここで整理しておくべき重要なポイントは、CopilotはChatGPTのように個人の入力を直接モデル学習に利用しているわけではないという点です。
個人の入力が基盤モデルに再学習されることはない
Microsoft Copilotは、ユーザーが入力したテキストをそのまま基盤の大規模言語モデル(LLM)に学習させる仕組みではありません。
あくまで既存のモデルを利用して応答を生成するため、「自分の発言がそのまま学習データ化される」ことは基本的にありません。
ただしログ保存や診断データ利用は残る
一方で、利用履歴や診断データは残る点には注意が必要です。
- 利用状況を把握するためのログ
- エラー検知や改善のための診断データ
- 管理者が確認できる操作記録
これらはMicrosoft側や管理者環境で参照される場合があり、入力内容によってはリスクにつながります。
したがって「学習されないから安全」ではなく、「ログや診断データに残るから入力内容には配慮が必要」という理解が正解です。
個人利用と法人利用での扱いの違い
- 個人利用:利用履歴が残るのは主にユーザー自身。設定画面で「Chat history & training」をオフにすることで履歴保存を抑制可能。
- 法人利用:Microsoft 365 管理センターでのポリシー設定により、履歴保存やデータ共有を制御可能。管理者がログを確認できる環境も整備されている。
この違いを理解せずに利用を始めると「安全だと思っていたのに、実は管理者が確認できる状態だった」といった誤解やトラブルが起こりやすくなります。
さらに、Copilotの仕組みを理解しておくと、なぜこうした差があるのかが明確になります。
詳しくは、内部リンクとして以下の記事をご覧ください。
Copilot APIとは?ChatGPTとの違いと導入ステップをわかりやすく解説【2025年最新】
学習させないための基本設定(ユーザー向け)
Copilotは「入力がそのままモデルに学習される」ことはありませんが、利用履歴やログが残る点には注意が必要です。
ここでは、個人ユーザーでもすぐに実践できる「学習させないための基本設定」をまとめます。
Chat history & training をオフにする手順
CopilotやBing Chatなど一部の生成AI機能では、会話履歴を保存・学習改善に利用する設定がデフォルトでオンになっていることがあります。
これをオフにすることで、入力内容が診断データに使われるリスクを大幅に減らせます。
- 設定画面で「Chat history & training」を選択
- 「利用履歴を保存しない」「学習に利用しない」をオフにする
この設定は個人ユーザーに特に有効です。
商用データ保護(Commercial Data Protection)を有効化
法人アカウントでMicrosoft 365 Copilotを利用する場合は、商用データ保護(Commercial Data Protection)の有効化が必須です。
- 管理者がMicrosoft 365 管理センターで制御可能
- 有効化すると、入力データがMicrosoftのモデル改善に使われない
- 会話データが保存されず、外部のAIサービスと切り分けて利用できる
この設定があるかどうかで、法人導入時のリスクレベルは大きく変わります。
Webコンテンツ参照を無効化する方法
Copilotは必要に応じてWeb検索を参照し回答を補強しますが、これが不要な場合やセキュリティリスクが懸念される場合は、オフにすることができます。
- アプリやブラウザの設定で「Webコンテンツ参照を許可しない」を選択
- 特に法人環境では、外部サイト経由でのデータ流出リスクを防止
社内データのみで回答を生成したい場合に有効です。
設定チェックリスト(ユーザー用)
| 設定項目 | 推奨アクション | 効果 |
| Chat history & training | オフにする | 入力内容が診断データに残りにくくなる |
| 商用データ保護 | 有効化 | データがMicrosoftモデルに利用されない |
| Webコンテンツ参照 | 無効化 | 外部経由での情報漏えいを防止 |
法人利用での追加対策(管理者必見)
個人ユーザーであれば「Chat historyオフ」などの設定で十分な場合もありますが、法人利用ではそれだけでは不十分です。
全社的にCopilotを安全に使うためには、管理者による追加対策が欠かせません。
Microsoft 365 管理センターでのデータ共有制御
- Microsoft 365 管理センターから、ユーザーのデータ共有やクラウド保存の範囲を制御可能
- 「商用データ保護(Commercial Data Protection)」を有効にすることで、
- ユーザーデータがMicrosoftの学習用に使われない
- 会話データが保存されず、外部に流出しない
- 部門やユーザー単位で制御できるため、機密性の高い部門だけ利用制限をかけるといった柔軟運用も可能
ポイント:初期導入時に必ず管理者側で確認すべき設定です。
DLP(Data Loss Prevention)で入力データを制限
- DLP(Data Loss Prevention:データ損失防止ポリシー)を設定することで、ユーザーが機密情報をCopilotに入力すること自体を防止できます。
- 例えば:
- 顧客個人情報(氏名・住所など)の入力を禁止
- 社外秘ラベルが付いた文書は自動でブロック
- 「人が間違えて入力してしまうリスク」を仕組みで防ぐのがDLPの強みです。
法人利用における「最後の砦」として必須の設定です。
ログ監査で利用状況を定期確認
- 管理者はMicrosoft 365 の監査ログを通じて、
- 誰がどのアプリでCopilotを利用したか
- どの言語・どの環境で使われているか
を確認できます。
- これにより、入力ルール違反や利用の偏りを早期に検知可能。
- 定期的に監査レポートを作成し、経営層に報告することで、利用リスクの見える化も進みます。
差別化ポイント:競合記事ではあまり触れられていない「監査の仕組み」まで解説することで、法人読者に刺さります。
学習させないために利用者が守るべきルール
管理者がどれだけ設定を整えても、現場の社員が不用意に機密情報を入力すればリスクは残ります。
Copilotを安全に活用するためには、利用者一人ひとりが「守るべきルール」を理解し、徹底することが欠かせません。
機密情報や顧客情報を入力しない
- 社外秘文書・設計図・顧客の個人情報などを直接入力するのは厳禁
- たとえ「学習されない」とはいえ、ログや監査データには残るため、情報漏えいにつながる恐れがある
- 入力するのは公開可能な情報や、業務効率化のために加工されたデータに限定する
入力禁止情報を明文化し社内で周知
- 「何を入力してはいけないか」を曖昧にすると、社員ごとに判断が分かれてしまう
- 例:
- 顧客の氏名・住所・電話番号
- 契約条件・価格交渉の詳細
- 製品開発の未公開情報
- これらを社内ガイドラインに明文化し、全社員が共通認識を持つことが重要
生成AIの理論やノウハウだけでなく、「実際の現場で生成AIがどう活用されているか」気になりませんか?
■生成AI法人活用事例データベースで「自社に合う事例を知る」
各社が「なぜその生成AI・LLMを選んだのか」「どうルール化したのか」。ツール選定や運用設計の迷いをなくすための「他社の意思決定プロセス」がわかります。
研修で「どこまで入力OKか」を教育
- 実際には「どこまで入力してよいのか」が最も迷いやすいポイント
- 研修を通じて、具体的なケースごとに入力の可否を判断できるスキルを身につけることが必要
- 成功企業は、導入初期から「技術設定+研修」を両輪で進めており、利用ルールが自然に定着している
こうしたルールを社内に浸透させるには、初期から研修を組み込むことが効果的です。
ケーススタディ:学習制御で安全に運用した事例
「学習させない設定やルール」を導入すると、どのように業務に影響するのか。
ここでは実際の企業のケースを参考に、成功例と失敗例を対比して紹介します。
金融業:顧客データを入力禁止にしても活用できた事例
ある金融機関では、顧客情報を誤って入力してしまうリスクを防ぐために、顧客データは絶対に入力禁止と明文化。
代わりに「匿名化したデータ」や「一般的な商品説明文」を活用し、Copilotにレポート草案を作成させました。
結果、顧客情報を守りつつ、社員の資料作成時間を大幅に削減。
「入力禁止ルール=使えない」ではなく、ルールの工夫次第で十分に活用できることを示した成功例です。
製造業:設計情報を遮断しつつ、事務系部門で利用
製造業の企業では、設計図面や製品仕様といった極秘情報はDLPで入力ブロック。
その代わりに、経理や人事部門では日常的な文書作成やデータ集計にCopilotを積極活用しました。
結果、研究開発のセキュリティを守りながら、バックオフィスの生産性を高めることに成功。
「どこで使うか」「どこでは使わないか」を切り分けたことが定着のポイントでした。
IT企業:教育+商用データ保護で安全活用を定着
あるIT企業では、導入当初に「商用データ保護を有効化」するだけでなく、社員研修を同時に実施。
- どの情報を入力してよいか
- NG情報は何か
- 万が一入力してしまった場合の対応方法
これらを教育によって浸透させた結果、利用定着率が高く、経営層も安心して全社展開を承認しました。
失敗事例:ルールを決めず「社員任せ」にしたケース
一方で、ある企業は「とりあえず導入してみよう」と社員任せにした結果、
- 機密情報を入力してしまうケースが発生
- 利用方法が社員ごとにバラバラ
- 結果的に「リスクが高い」と経営層判断 → 利用停止
教訓:設定や教育を軽視すると、せっかくの投資が水の泡になる。
設定が効かない・反映されない時のトラブル対処
「Chat historyをオフにしたのに反映されない」「商用データ保護を有効化したのに効いていないように見える」――。
Copilotの設定を変更しても、期待どおりに反映されないことがあります。
ここではよくある原因と確認すべきポイントを整理します。
Chat historyをオフにしても反映されない場合の確認項目
- サインアウト/再ログインをしていない → セッション情報が残り、設定が反映されないことがある
- ブラウザキャッシュのクリアをしていない → 古いUIが表示され続けるケース
- 利用アプリごとの設定不一致 → 例:Edgeでオフにしたが、TeamsやOfficeアプリ側はオンのまま
対処法:一度ログアウトし、再ログイン。キャッシュをクリアし、アプリごとに設定を確認する。
管理者権限が不足している場合
- 個人ユーザーが設定しても、テナント全体のポリシーで上書きされるケースがある
- 特に法人環境では、管理者が「Chat history有効化」を強制している場合、ユーザー側での無効化は反映されない
- 利用者権限と管理者権限のどちらで設定する必要があるかを確認することが重要
法人利用では「反映されない=個人の設定ミス」ではなく、管理ポリシーが優先されている可能性が高い。
機能展開フェーズ(英語先行)の可能性
- Microsoft Copilotの新機能は、英語環境で先行提供 → 順次日本語化されるケースが多い
- そのため、「設定自体は存在するが、日本語環境ではまだ反映されない」という状況が起こり得る
- 最新の機能展開状況は、Microsoft公式ドキュメントや管理センターの更新情報で確認可能
対処法:日本語で反映されない場合は、英語UIに切り替えて確認するのも一つの手。
まとめ|設定と運用ルールで「学習させない環境」を作る
Copilotはユーザーの入力をそのまま自動学習する仕組みではありません。
しかし、利用履歴や診断データは残るため、安心して活用するには「学習させないための設定」と「運用ルールの徹底」が欠かせません。
特に法人利用では、
- 管理者による制御設定(データ共有・DLP・監査ログ)
- 社員教育によるルール定着(入力禁止情報の周知・研修による判断力向上)
この両輪を揃えることで、リスクを抑えつつCopilotを最大限活用できます。
成功している企業は、導入初期から「技術設定+教育」を同時に進め、安心して全社展開へとつなげています。
- QCopilotは私が入力した情報を自動的に学習しますか?
- A
いいえ。Microsoft Copilotは、入力内容をそのまま基盤モデルに学習させる仕組みではありません。ただし、利用履歴や診断データは残るため、入力内容には注意が必要です。
- QCopilotに学習させないための設定はありますか?
- A
はい。ユーザー側では「Chat history & training」をオフにする、法人利用では「商用データ保護」を有効化するなどの設定が可能です。
- Q法人利用で社員が情報を入力しても安全ですか?
- A
管理者がMicrosoft 365 管理センターでデータ共有や履歴保存を制御すれば安全性は高まります。ただし、入力禁止情報をルール化し、社員教育と併せて実施することが必須です。
- QChat historyをオフにしたのに反映されません。どうすればいいですか?
- A
サインアウト/再ログイン、ブラウザキャッシュのクリア、アプリごとの設定確認を行ってください。法人環境では管理者ポリシーが優先され、個人設定が無効化される場合もあります。
- Q一部の機能で英語しか反映されず、日本語設定が効かないのは不具合ですか?
- A
不具合ではなく、機能展開が英語優先のプレビュー段階である可能性があります。順次日本語に対応するので、最新情報を確認してください。
- QGitHub Copilotも同じように学習させない設定が必要ですか?
- A
はい。GitHub Copilotも履歴やコード提案に関する学習設定があるため、必要に応じてオプトアウトが可能です。利用環境ごとに設定を確認してください。