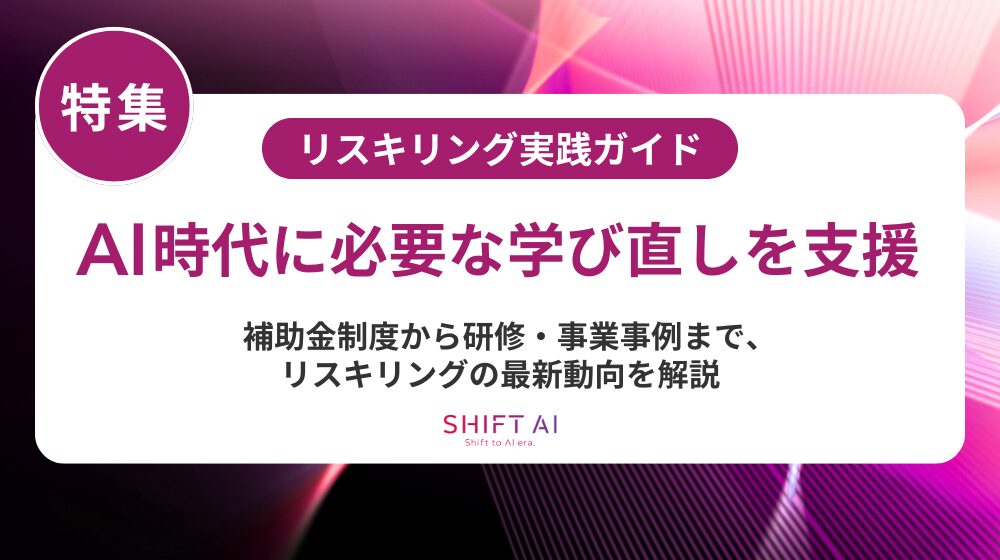DXやAIの普及、ビジネスモデルの転換が進む中で、多くの企業や自治体が「リスキリング事業」を打ち出しています。政府は補助金や研修支援を通じて人材のスキル転換を後押しし、自治体も地域産業に即した育成プログラムを展開。さらに企業独自の取り組みも広がり、リスキリングはもはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる業種にとって欠かせないテーマとなっています。
とはいえ、「どの制度が自社に合うのか分からない」「国と自治体の支援の違いが知りたい」「実際に導入するにはどう進めればいいのか」といった疑問を持つ担当者も少なくありません。
本記事では、国や自治体が実施している代表的なリスキリング事業を整理し、自社での導入に役立つポイントをわかりやすく解説します。制度を理解するだけでなく、実際の研修やスキル習得につなげるための視点も取り入れているので、導入を検討している企業担当者の方はぜひ参考にしてください。
AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。
■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする
※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
リスキリング事業とは?制度の定義と注目の背景
リスキリングとは、単なる「学び直し」ではなく、新しい業務や役割に対応するために必要なスキルを体系的に身につけることを指します。経済産業省も「新しい職務に移行するための能力習得」と定義しており、単発の研修やスキルアップとは一線を画しています。
では、なぜいま「リスキリング事業」がこれほど注目されているのでしょうか。背景には以下のような要因があります。
- DX・AIの普及:従来の業務プロセスやスキルでは対応できない領域が急増している。
- 人材不足の深刻化:国内の労働人口減少により、一人ひとりのスキル転換が欠かせない。
- 雇用構造の変化:ジョブ型雇用の広がりにより、職務内容ごとのスキル適合性が求められる。
- 国際競争の激化:デジタル人材の不足が企業の成長スピードを制約している。
こうした課題に対応するため、政府や自治体はリスキリングを「国を挙げて推進すべきテーマ」と位置づけ、制度や補助金を整備しています。企業にとっても、制度を理解した上で自社戦略と結びつけることが競争力強化の第一歩になります。
リスキリングの基本的な意味や導入メリットをさらに知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
リスキリングとは?意味・背景・企業導入のメリットと成功ポイントを徹底解説
国が進めるリスキリング事業と支援制度の比較
国は「人への投資」を成長戦略の柱に掲げ、複数のリスキリング支援事業を展開しています。代表的な制度を整理すると、対象者や補助内容に違いがあることが分かります。ここでは主要な支援をまとめます。
経済産業省|リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業
- 内容:キャリア相談、リスキリング講座の受講支援、転職マッチングまでを一体で提供
- 補助額:受講費の最大70%(上限56万円)が補助される
- 対象者:キャリアチェンジを前提に学び直す社会人
- 特徴:学びから転職までを包括的にサポートする点が他制度にない強み
厚生労働省|キャリア形成・リスキリング推進事業
- 内容:キャリアコンサルティングやジョブカードを活用したキャリア形成支援
- 対象者:企業の従業員・求職者など幅広い層
- 特徴:全国各地に相談窓口があり、無料で利用できる点が大きな魅力
人材開発支援助成金
- 内容:企業が社員に職業訓練を実施する際の経費を助成
- 対象者:企業とその従業員
- 特徴:OJTや集合研修など企業内研修に幅広く使える
教育訓練給付金
- 内容:個人が指定講座を受講する際、受講料の一部が返還される制度
- 対象者:雇用保険加入期間が一定以上ある労働者
- 特徴:個人の自主的な学びを支援する制度で、リスキリングにも活用可能
制度比較表(例)
| 制度名 | 主な対象 | 補助・給付内容 | 特徴 |
| 経産省:キャリアアップ支援事業 | 転職を目指す社会人 | 受講費最大70%(上限56万円) | 学び~転職支援を一体提供 |
| 厚労省:リスキリング推進事業 | 求職者・企業従業員 | 無料相談、ジョブカード活用 | 全国窓口で利用可能 |
| 人材開発支援助成金 | 企業・従業員 | 研修費用の一部を助成 | 企業内研修の実施に適用 |
| 教育訓練給付金 | 雇用保険加入者 | 受講料の一部返還 | 個人の自主的学びを支援 |
このように国の制度は「対象者」と「支援範囲」に違いがあり、どの制度を活用すべきかは目的によって異なります。
企業として制度を活かす場合は「人材開発支援助成金」、個人のキャリアチェンジなら「キャリアアップ支援事業」など、自社や従業員の状況に応じて最適な制度を選ぶことが重要です。
関連記事:
リスキリング補助金・助成金まとめ【2025年版】対象条件・申請方法と最新制度を解説
自治体によるリスキリング支援制度
国の制度に加え、各自治体も独自にリスキリング事業を展開しています。地域の産業構造や雇用ニーズに即した支援が多く、国の制度と組み合わせて利用できる点が特徴です。
東京都の事例
- デジタル人材育成支援事業:中小企業向けにデジタルスキル習得を支援
- 助成金制度:社内でデジタル研修を実施する際に一部費用を補助
- 特徴:都内企業のDX推進を強化する内容が中心
大阪府の事例
- 職業訓練校やリカレント教育プログラムの拡充
- デジタル関連講座の提供:ITスキルやAI基礎を学べる講座を実施
- 特徴:府内企業・求職者双方に向けて実践的な研修を整備
その他の地域
- 福岡県:スタートアップ支援と連動したデジタル人材育成
- 愛知県:製造業の高度化に対応した技能習得支援
- 北海道:観光・地域産業に特化したリスキリングプログラム
自治体支援の特徴
- 地域産業と密接に連動:製造、観光、ITなど地域の強みを活かした研修が多い
- 中小企業向け支援が手厚い:研修費補助や専門家派遣など、国の制度では拾いきれないニーズに対応
- 国制度との併用が可能:経産省や厚労省の支援と組み合わせ、費用負担を最小化できる
自治体のリスキリング事業は、自社の所在地や業種に直結する内容が多く、活用メリットが大きい領域です。国の制度と併用することで、研修導入のコストを大幅に下げることが可能になります。
関連記事:
【2025年版】リスキリング支援の全体像|国・自治体・企業の取り組みと補助金活用
企業がリスキリングを進める際のポイント
国や自治体の制度を理解しても、実際に企業で導入・定着させるには工夫が必要です。ここでは、制度活用を前提にしたリスキリング推進のポイントを整理します。
1. 社員のスキルマップを把握する
- 現状のスキルと今後必要になるスキルを可視化する
- 部門ごとに「強みと不足」を洗い出すことで、投資すべき領域を明確にできる
2. 制度を組み合わせてコストを抑える
- 国の助成金や教育訓練給付金、自治体の助成金を併用する
- 制度ごとに対象や条件が異なるため、複数の制度を比較し最適な組み合わせを選ぶ
3. 研修プログラムは「実務直結型」にする
- 一般的な知識習得にとどまらず、業務の中で実際に活かせる内容を重視
- 例:社内システムを題材にしたデータ分析研修、生成AIを活用した業務効率化演習など
4. 定着を意識した仕組みづくり
- 研修後のフォローアップ(ワークショップやOJT)を用意する
- 評価制度やキャリアパスと連動させることで、社員のモチベーションを維持できる
企業がリスキリングを進める上で重要なのは、「制度を活用してコストを下げつつ、社内に定着する仕組みを整えること」です。
単なる研修実施に終わらず、日々の業務と結びつけることで初めて成果につながります。
注目スキルと研修領域|特に生成AIの習得が必須に
リスキリング事業で取り上げられるスキル領域は幅広いですが、近年特に注目されているのが デジタル・データ・AI関連スキル です。これらは国や自治体の制度でも重点的に扱われており、企業にとっても競争力を左右する重要領域となっています。
注目されるスキル領域
- DX基礎スキル:業務プロセスのデジタル化に対応する基本知識
- データ分析・統計:意思決定の迅速化やマーケティング高度化に直結
- プログラミング・IT基盤:AIやシステム開発の基礎を担うスキル
- 語学・グローバル対応:海外市場や多国籍人材との協働に必要
特に重要な「生成AIスキル」
生成AIの普及はビジネスのあらゆる領域に影響を与えています。
- 文章生成・資料作成の効率化
- データ要約・分析を高速化
- アイデア創出・ブレストの支援
- 業務マニュアルやFAQの自動化
これらは既存の業務に直結するスキルであり、習得することで社員の生産性を飛躍的に高められます。
制度だけではカバーしきれない領域
国や自治体の制度では、基礎的なITスキルや一般的な研修が中心で、最新の生成AIスキルに特化したプログラムはまだ限られています。
そのため、多くの企業では 公的支援を活用しつつ、実務直結型のAI研修を別途導入する必要 があります。
生成AIを業務に定着させたい企業の方は、ぜひ以下から詳細資料をご確認ください。
リスキリング事業を活用する際の注意点
リスキリング事業は魅力的な支援制度ですが、活用にあたってはいくつかの注意点があります。事前に理解しておくことで、「思ったより使えなかった」というミスマッチを防ぐことができます。
1. 利用条件や対象者の制限
- 経産省の「キャリアアップ支援事業」は、転職やキャリアチェンジを前提とする人が対象。
- 厚労省の制度や助成金は、企業や在職者向けであるケースが多い。
- 申請前に「自分(自社)が対象になるか」を必ず確認することが必要です。
2. 補助が出ないケースもある
- 講座によっては対象外となる場合がある
- 自己都合退職や受講中断など、条件を満たさないと補助金が支給されない
- 制度利用の際は「対象講座の確認」「修了条件の把握」が欠かせません
3. 制度だけでは成果につながらない
- 国や自治体の支援は「きっかけ」や「費用補助」にとどまることが多い
- 学んだ内容を実務にどう結びつけるかは企業の仕組み次第
- 評価制度やキャリア設計と連動させないと、せっかくの学びが定着しないリスクがあります
制度の概要や補助額に目を向けるだけでなく、利用条件・対象範囲・定着の仕組みまで含めて検討することが大切です。これらを意識することで、リスキリング事業を「実際の成果」に変えやすくなります。
とめ|リスキリング事業+社内研修で競争力を高める
国や自治体が提供するリスキリング事業は、補助金や講座支援を通じて人材育成の大きな助けとなります。
しかし、制度を知るだけで終わらず、自社の戦略や現場業務にどう結びつけるかが成果を左右します。
- 国や自治体の制度を比較・理解し、自社に合ったものを選ぶ
- 社員のスキルマップを整理し、投資すべき領域を明確にする
- 制度利用と同時に、社内定着の仕組み(研修→実務応用→評価連動)を構築する
- 特に生成AIなど新しい領域は、公的支援だけでなく企業独自の研修導入が不可欠
いま、企業に求められているのは 「制度 × 実務研修」 を組み合わせて、持続的な競争力を育むことです。
生成AIを中心とした研修プログラムを導入し、リスキリングを確実に成果につなげたい方は、以下より詳細資料をご覧ください。

リスキリング事業に関するよくある質問
- Qリスキリング事業は誰でも利用できますか?
- A
制度ごとに対象が異なります。経産省の「キャリアアップ支援事業」は転職を前提とする社会人向け、厚労省の制度は企業や在職者を含めて幅広く対象としています。利用条件を事前に確認することが重要です。
- Q国のリスキリング事業と自治体の支援制度は併用できますか?
- A
はい、併用可能なケースがあります。国の補助制度で受講費を抑えつつ、自治体の助成金を組み合わせることで、研修コストをさらに軽減できます。ただし制度によっては重複が認められない場合もあるため、各窓口での確認が必要です。
- Q中小企業がまず活用すべきリスキリング支援はどれですか?
- A
企業内研修に使いやすいのは「人材開発支援助成金」です。従業員に合わせて研修内容を設計でき、OJTや集合研修など幅広い形態に対応しています。加えて自治体の助成金を組み合わせると効果的です。
- Q生成AIスキルはリスキリングの対象になりますか?
- A
はい。近年では国や自治体の講座にもAI・データ関連分野が増えています。ただし、最新の生成AIスキルに特化した講座はまだ少ないため、公的制度+実務直結型のAI研修 を組み合わせるのが効果的です。