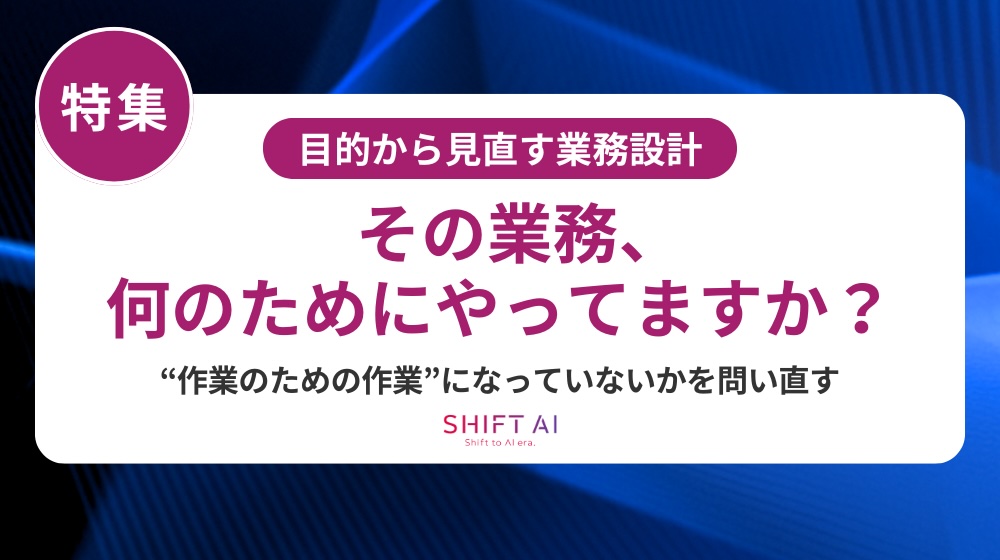「この仕事の目的って何だろう?」
上司の指示が曖昧で、何のためにやっているのかわからずモヤモヤしたことはありませんか。
聞きたくても「そんなこともわからないのか」と言われそうで聞けない……。
その悩み、実はあなただけの問題ではありません。
本記事では、上司の指示が伝わらない根本原因から、角を立てずに聞き返す「魔法の質問フレーズ」、さらにはAIを使って指示を翻訳する最新テクニックまで徹底解説します。
明日から自信を持って仕事を進めるためのヒントが満載です。ぜひ最後までご覧ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
上司の目的が伝わらない…よくある「指示出し」の3パターン
「この資料、適当にまとめといて」
「あれ、どうなった?」
このように、目的や詳細がわからないまま指示を出され、困惑した経験はないでしょうか。
実は、伝わらない指示にはいくつかの典型的なパターンが存在します。
まずは、あなたの職場の上司がどのタイプに当てはまるのか、よくある3つのパターンを見ていきましょう。
【丸投げ型】「とりあえずやっといて」で目的が見えない
最も困るのが、具体的な指示が一切ない「丸投げ型」です。
「とりあえず進めておいて」「いい感じにしておいて」といった言葉だけで、目的や期限、期待するクオリティが示されません。
これは、上司自身もタスクの全容を把握していないか、部下を信頼しすぎて「言わなくてもわかるだろう」と思い込んでいる場合によく起こります。
この状態で作業を進めると、後になって「思っていたのと違う」とちゃぶ台返しをされるリスクが高まります。
まずは「とりあえず」の中身を具体化するところから始めなければなりません。
【言葉足らず型】主語や背景が抜けていて意図が不明
次は、指示の中に重要な情報が欠落している「言葉足らず型」です。
「例の件、A社に連絡しておいて」と言われても、「例の件」が何を指すのか、連絡して何を伝えるべきかがわかりません。
上司の頭の中では文脈がつながっていますが、それを言語化せずに発言してしまうのが原因です。
特に、忙しい上司やチャットツールでのやり取りが多い職場で発生しやすい傾向があります。
このタイプの場合、部下が勝手に解釈して動くと、「そういう意味じゃなかった」というミスコミュニケーションが発生しやすくなります。
【朝令暮改型】指示がコロコロ変わり、ゴールが定まらない
最後は、言うことが頻繁に変わる「朝令暮改(ちょうれいぼかい)型」です。
昨日は「A案でいこう」と言っていたのに、翌日には「やっぱりB案がいいな」と平気で指示を覆します。
これでは、部下はいつまでたっても作業を完了させることができません。
上司自身の考えが整理されていなかったり、さらに上の上層部の意見に振り回されていたりすることが主な理由です。
ゴールが動いてしまうため、作業に入る前に「現時点での決定事項」を記録として残し、言質を取っておく自衛策が必要になります。
📌 関連リンク
若手がすぐ辞めるのはなぜ?早期離職を防ぐ職場づくりの対策と事例まとめ
なぜ上司は目的を伝えないのか?背景にある心理と構造
上司はなぜ、わかりにくい指示を出してしまうのでしょうか。
単なる「意地悪」や「能力不足」と片付けてしまう前に、その背景にある心理や組織構造を知ることが大切です。
上司が置かれている状況を理解することで、対策の糸口が見えてきます。よくある3つの原因を解説します。
上司自身も目的を理解していない「伝言ゲーム」の弊害
まず考えられるのは、上司自身もその仕事の目的を理解していないケースです。
経営層やさらに上の上司から、「とにかくこれをやって」と指示が降りてきた場合、中間管理職である上司も背景を知らされていないことがあります。
これは、組織内での情報共有が不足し、悪い意味での「伝言ゲーム」状態になっていることが原因です。
目的が不明確なままタスクだけが降りてくるため、部下に説明しようにもできません。
この場合、部下がいくら上司に質問しても明確な答えは返ってきません。
「一緒に目的を確認する」というスタンスで、上司を巻き込んで上位の意図を探るアプローチが必要になります。
プレイヤー思考が抜けず「阿吽の呼吸」を求めている
次に、上司が優秀なプレイヤーだった場合に多いのが、「言わなくてもわかる」という思い込みです。
自分ができることは部下もできると考え、最低限の指示しかしません。
これは、マネジメントよりもプレイヤーとしての思考が強く残っていることが原因です。
「1を言えば10を知る」ような阿吽(あうん)の呼吸を、無意識に部下へ求めてしまっているのです。
例えば、「資料作っといて」の一言で、過去の経験から最適な構成を組めることを期待します。
しかし、部下にはその経験値がありません。
このギャップを埋めるには、「私はその経験がないので、具体的に教えてほしい」と率直に伝えることが大切です。
忙しすぎて「言語化する時間」を惜しんでいる
最後は、単純に忙しすぎて丁寧に説明する時間がないパターンです。
プレイングマネージャーとして多くの業務を抱えている上司によく見られます。
「目的を説明する時間があるなら、早く手を動かしてほしい」という心理が働き、指示が雑になります。
チャットで「これ確認して」とURLだけ送ってくるようなケースが典型です。
しかし、これでは部下が間違った方向に進み、結果的に手戻りが発生して余計に時間がかかってしまいます。
「急がば回れ」であることを理解してもらうためにも、最初の5分で認識合わせを行う時間を確保してもらうよう働きかけることが重要です。
【実践】曖昧な指示を「明確なタスク」に変える5つの質問テクニック
上司の指示がわかりにくい時、ただ待っていても状況は変わりません。
自分から質問をして、不明点をクリアにする「質問力」が武器になります。
しかし、聞き方を間違えると「いちいち聞くな」と思われかねません。
ここでは、上司の機嫌を損ねずに、曖昧な指示を明確なタスクへ変換する5つの実践テクニックを紹介します。
「背景」を聞き出す:なぜこの業務が必要なのかを確認する
まずは、その業務が発生した「背景」を確認しましょう。
なぜなら、背景を知ることで、作業の方向性が大きく変わる可能性があるからです。
例えば「競合調査をして」と言われた場合、それが「新商品開発のため」なのか「営業トーク強化のため」なのかで、調べるべき項目は全く異なります。
背景が見えないまま作業を始めると、的外れなアウトプットになりかねません。
「この調査は、どの会議で使う資料でしょうか?」と用途を聞くだけでも、背景にある目的が見えてきます。
目的さえわかれば、自ずとやるべき作業も明確になります。
「ゴール」をすり合わせる:完成イメージのズレをなくす具体例
次に、最終的な「完成イメージ(ゴール)」を上司とすり合わせます。
「とりあえず資料作って」と言われた時、上司は「箇条書きのメモ」で良いと思っているのに、部下は「完璧なパワポ」を作ろうとしてしまう。
こうした認識のズレが、無駄な残業を生みます。
これを防ぐには、具体的なアウトプット形式を確認することです。
「Excelで一覧化すれば良いですか?」「WordでA4・1枚程度でしょうか?」と具体例を出して聞いてみましょう。
過去の似た資料を例に出し、「これと同じ形式で良いですか?」と確認するのが最も確実で効率的です。
「優先順位」を確認する:期限と重要度を数値で握る
複数のタスクを抱えている場合、「いつまでにやるべきか」という優先順位の確認が必須です。
上司の「なるべく早く」は、今日中なのか、今週中でいいのか、人によって感覚が違うからです。
曖昧な期限はトラブルの元です。必ず数値で期限を握りましょう。
「今抱えているA案件よりも優先すべきでしょうか?」と、既存タスクと比較して聞くと判断しやすくなります。
「明日の15時までに提出します」と自分から宣言してしまうのも有効です。
期限と重要度を数値で合意しておけば、急な割り込みタスクにも冷静に対処できるようになります。
「中間報告」を約束する:早い段階で軌道修正する仕組みを作る
作業を始めたら、完成する前に一度「中間報告」を入れる約束をしましょう。
最初に完璧な指示をもらうことは難しいため、早い段階で方向性が合っているか確認するためです。
具体的には、着手して2〜3割進んだ段階で「構成案を作ったので、方向性が合っているか5分だけ確認させてください」と依頼します。
もし認識がズレていても、初期段階なら修正は容易です。
逆に、完成直前で「全然違う」と言われるリスクをゼロにできます。
この「クッション」を入れるだけで、手戻りのストレスは劇的に減ります。
【コピペOK】角が立たない「確認フレーズ」テンプレート
最後に、明日からそのまま使える「確認フレーズ」を紹介します。
上司に質問する際、「理解できない」と伝えるのではなく、「より良い成果を出したい」という姿勢を見せるのがポイントです。
以下のフレーズをチャットやメールで活用してください。
- 背景を聞く時
「本件の目的を正しく理解し、最適なアウトプットを出したいので、背景を少し詳しく教えていただけますか?」 - 期限を聞く時
「現在抱えている〇〇の件と調整したいため、優先順位をご教示いただけますでしょうか?」 - 具体化したい時
「認識のズレを防ぐため、私の理解が合っているか確認させてください。〇〇という認識でよろしいでしょうか?」
【AI活用】上司の「わかりにくい指示」をAIで翻訳・補完する方法
「上司に何度も聞き返すのは気が引ける……」
そんな時は、生成AIをあなたの「専属アシスタント」として活用しましょう。
AIは、曖昧な情報を整理したり、足りない情報を推測したりするのが得意です。
ここでは、ChatGPTなどのAIツールを使って、上司のわかりにくい指示を「実行可能なタスク」に翻訳・補完する3つのテクニックを紹介します。
ChatGPTに「壁打ち」して、指示の意図を仮説立てする
まずおすすめなのが、AIを相手に「壁打ち」をして、指示の背景や目的を仮説立てする方法です。
上司の言葉足らずな指示でも、一般的なビジネスの文脈から「おそらくこういう目的だろう」と推測してくれます。
具体的には、「上司から『A社の競合調査をして』と言われました。この指示の背景として考えられる目的と、調査すべき項目をリストアップしてください」と入力します。
すると、AIが「新商品開発のためなら機能比較が必要」「営業資料用なら価格比較が必要」といった仮説を提示してくれます。
この仮説を持って上司に確認に行けば、「どれが正解ですか?」と聞くだけで済み、ゼロから聞くよりもスムーズに話が進みます。
曖昧なメモや議事録をAIで構造化し、抜け漏れを発見する
次に、上司との打ち合わせメモやチャットの履歴をAIに読み込ませ、情報を構造化させる方法です。
断片的なキーワードの羅列だけでは、何が決定事項で、何が未定なのか判別できません。
そこで、AIに「以下のメモを整理し、5W1H(いつ、誰が、何を、なぜ、どこで、どのように)で分類してください。不足している情報は『不明』と明記してください」と指示を出します。
AIが情報を整理し、「期限」や「担当者」が不明であることを可視化してくれます。
「不明」と判定された項目だけを上司に確認すればよいため、確認漏れを防ぎ、的確な質問ができるようになります。
上司への確認メールをAIに推敲させ、心理的負担を減らす
最後は、上司に質問するためのメール文面をAIに作成させる方法です。
「聞き方が悪いと怒られるかも」と不安になり、メール作成に何十分も悩んでしまうことはありませんか。
AIを使えば、失礼のない丁寧な表現を一瞬で作ってくれます。
「上司に指示の意図を確認したいのですが、角が立たない丁寧なメール文面を作ってください」と頼んでみましょう。
「恐れ入りますが、認識の齟齬がないよう確認させてください」といった、ビジネス枕詞を適切に使った文面が生成されます。
心理的なハードルが下がり、すぐに確認行動に移れるようになるため、業務スピードが格段に上がります。
関連記事
生成AIにうまく質問するコツ5選|プロンプトの質が成果を変える
それでも伝わらないなら「組織の仕組み」に問題があるかもしれない
「自分が聞き返せば解決する」と努力しても、一向に状況が改善しない場合もあります。
もし、あなただけでなく周囲の同僚も同じ悩みを抱えているなら、それは個人の問題ではなく、「組織の構造的な欠陥」かもしれません。
ここでは、目的共有がされない職場の特徴と、根本的な解決策について解説します。
個人のコミュニケーション能力だけで解決しようとしない
まず大切なのは、「指示がわからないのは自分の理解力が低いせいだ」と自分を責めないことです。
上司の指示が曖昧なのは、上司個人の資質の問題だけでなく、組織全体の「情報伝達の仕組み」が機能していないことが原因のケースが多いからです。
例えば、経営層の方針が現場まで正しく降りてこない、部署間の連携が取れていないといった環境では、誰が上司になっても同じ問題が起きます。
個人のコミュニケーションスキルでカバーするには限界があります。
「伝わらない」を組織の課題として捉え直し、チーム全体で解決策を探る視点を持つことが、メンタルを守るためにも重要です。
目的共有がされない職場に共通する4つの危険サイン
では、どのような職場が危険なのでしょうか。
目的共有が機能不全に陥っている組織には、共通する4つのサインがあります。
- 会議で「決まったこと」が曖昧なまま終わる
- チャットツールでの連絡ばかりで、対話の機会が極端に少ない
- マニュアルや業務フローが存在せず、全てが属人化している
- 「失敗」を過度に恐れ、誰も質問や提案をしない雰囲気がある
これらが当てはまる場合、情報が遮断されやすく、指示の背景や目的が現場まで届きません。
結果として、誰も責任を取りたくないため、指示が曖昧になり「とりあえずやって」という丸投げが横行するのです。
組織全体で「言語化スキル」を高める研修・教育の必要性
この状況を根本から変えるには、組織全体で「言語化スキル」を高める取り組みが欠かせません。
上司は「正しく指示を出すスキル」を、部下は「的確に質問するスキル」を、共通の言語として学ぶ必要があります。
最近では、生成AIを活用した研修を取り入れる企業も増えています。
AIを使って指示内容を整理したり、論理的な伝え方をトレーニングしたりすることで、組織全体のコミュニケーションコストを劇的に下げることができます。
もしあなたがリーダーや推進者の立場なら、こうした「仕組み」としての解決策を会社に提案してみるのも、現状を打破する一つの有効な手段です。
📌 関連リンク
現場が動かない企業必見|生成AIによって業務目的を可視化する効果
【比較】指示が伝わる職場 vs 伝わらない職場
目的が共有されている職場と、されていない職場。両者には、日々の会話・動き方・成果の出方にいたるまで、驚くほどの違いがあります。
「うちの職場はどうだろう?」と気になった方は、以下の比較表をチェックしてみてください。
<伝わる職場と伝わらない職場の違い>
| 項目 | 目的が伝わらない職場 | 目的が伝わる職場 |
| 指示の内容 | 抽象的/丸投げ(例:「適当にやっといて」) | 目的・背景・優先度が明示される(例:「A社の営業提案用として、明日までに必要」) |
| 認識のすり合わせ | なし。やり直しや齟齬が頻発 | チャットやミーティングで都度確認しながら進行 |
| 成果物の精度 | 上司の“イメージ次第”で合否が決まる | 期待値の共有があるため、ズレが少ない |
| メンバーの意識 | 「怒られないために動く」「正解が分からず不安」 | 「なぜやるか」が理解できているので納得感を持って取り組める |
| チームの雰囲気 | 不信感・属人化・指示待ち文化 | 対話・改善提案が活発。心理的安全性も高い |
同じタスクでも、目的があるかないかで、ここまで違ってしまう。この比較からも明らかなように、指示が伝わる状態をつくることは、チームの成果と働きやすさの両方に直結する構造的な問題です。
曖昧な指示を構造で変える:目的を可視化するための3つの仕組み
ここまで見てきたように、上司の指示が曖昧なのは、個人の性格や能力の問題ではなく、“構造”の問題でもあります。
目的が見えない仕事を根本から改善するには、属人化された「言い回し」や「経験値」に頼るのではなく、組織全体で“目的を共有する仕組み”をつくる必要があります。
ここでは、AI時代における3つの実践策をご紹介します。
① 目的言語化フレームを導入する
目的が不明確なまま業務が走るのは、言語化の土台が曖昧だから。だからこそ、“目的→手段→成果”の構造を明確にするフレームを活用することが重要です。
たとえば
- Why(なぜやるのか)
- What(何をやるのか)
- How(どのように進めるのか)
このような構造をフレームとして全体で共有しておくことで、指示出しがぶれにくくなり、成果のズレも防げます。
また、ピラミッドストラクチャーやロジックツリーを使った「意図の構造化」トレーニングも有効です。
② 生成AIで上司の指示を整理・構造化する
人がいきなり「わかりやすく伝えよう」としても、うまくいかないことは多いもの。
そこで有効なのが、生成AIによる指示の構造化です。
たとえば
- 会議議事録をGPTで要約 → 背景・目的を抽出
- 上司のSlackやメール文を入力 → 意図を分析・補完
- 指示文をAIに分解させ「目的・手段・成果」に自動整理
これらは人間の認知限界を補いながら、コミュニケーションの精度とスピードを同時に高めるツールとして注目されています。
③ SHIFT AIの研修で、目的共有の「型」をチームにインストール
構造やAIツールの活用は効果的ですが、現場全体に定着させるには研修という“共通体験”が必要です。SHIFT AIでは、生成AI研修を提供しています。AI活用で成果を出すための内容になっていますので、興味のある方はお問い合わせください。
まとめ:上司の目的が伝わらない悩みは解決できる!AIと対話力を武器に現状を変えていこう
上司の目的が伝わらないのは、決してあなたの理解力不足ではありません。
組織の構造的な問題や、多忙によるコミュニケーション不足が主な原因です。
まずは今回紹介した「確認フレーズ」や「AI活用」を試し、自分から一歩踏み込んでみてください。
曖昧な指示が明確になれば、あなたの仕事はもっとスムーズになり、正当な評価もついてくるはずです。
もし、個人の努力で改善しない場合は、組織全体の仕組みを見直すタイミングかもしれません。
一人で抱え込まず、便利なツールや新しい学びを取り入れ、働きやすい環境を少しずつ作っていきましょう。
だからこそ、SHIFT AIは現場で使える「目的共有」の仕組みづくりを、AI活用の側面から支援しています。

よくある質問(FAQ)
- Q上司に「目的は何ですか?」と聞くのは失礼ではないですか?
- A
言い方次第で印象は大きく変わります。
たとえば「目的を理解してから進めたほうが、成果物のズレを減らせると思いまして」といった言い回しであれば、前向きな意図が伝わりやすく、むしろ信頼を得られるケースが多いです。
- Q指示が曖昧でも、自分で考えて動くべきでは?
- A
自主性は重要ですが、目的が不明なまま動くと“的外れな努力”になってしまうリスクがあります。
曖昧な指示に対しては「たたき台を出して確認を取る」など、能動的な“すり合わせ”が効果的です。
- Q自分の理解力が足りないだけなのでは?
- A
そう思い込んでしまう人は多いですが、実際には「構造的な目的共有の欠如」が原因のことが多いです。
属人的な感覚ではなく、“仕組み”で情報のズレをなくす視点を持つことが重要です。
- QSHIFT AIの研修は、どんな人に向いていますか?
- A
主に以下のような方々に向いています
- 管理職やプロジェクトリーダーで、チームへの指示に自信が持てない方
- 若手社員との会話がすれ違いがちで悩んでいる中間管理職
- 認識齟齬や属人化の改善に、本気で取り組みたい現場責任者・経営層
- Q研修で本当に現場は変わるのでしょうか?
- A
多くの導入企業で「成果物のズレ減少」「修正回数の大幅削減」「目的共有の習慣化」が実現しています。
研修×生成AIの組み合わせによって、再現性のある変化を支援しています。