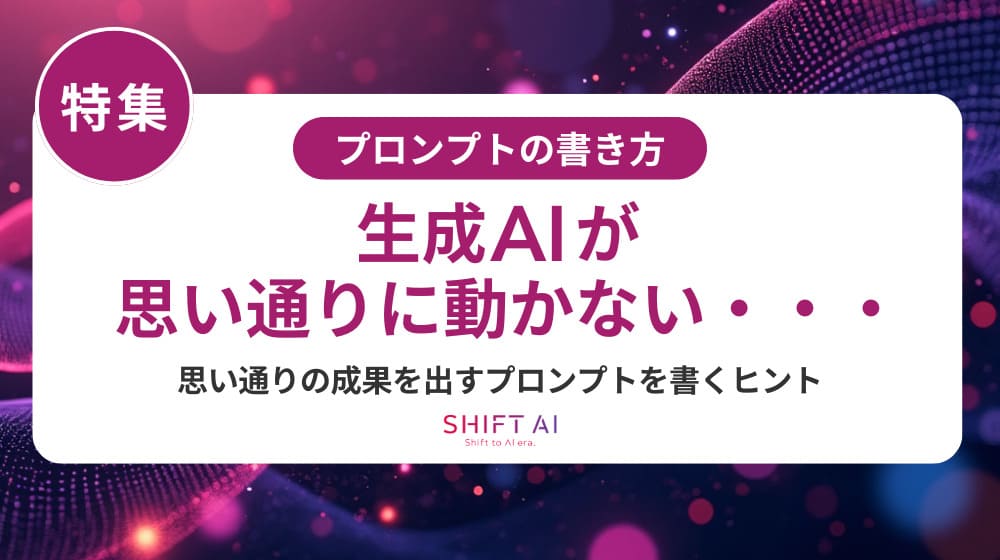ChatGPTなどの生成AIが「もっともらしい嘘」を自信満々に語る──
それが「ハルシネーション」と呼ばれる現象です。
AIの出力精度は年々向上しているものの、誤情報や根拠のない回答は依然として避けられません。
とくにビジネス利用の場では、誤情報=判断ミスやブランドリスクにつながる重大要素。
「AIが間違えた」では済まされないケースも増えています。
では、どうすればAIの誤情報を最小限に抑え、“正確に動くAI”を設計できるのか?
その答えは、AIへの指示文=プロンプト設計にあります。
本記事では、
- なぜハルシネーションが起きるのか(仕組みと原因)
- 誤情報を減らすためのプロンプト設計5原則
- RAGや温度設定など技術的アプローチ
- 企業での運用・教育による「誤情報を減らし続ける仕組み化」
を体系的に解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
ハルシネーションとは?AIが“それっぽい誤情報”を出す理由
生成AIを使っていると、ありそうで実は存在しない情報をもっともらしく提示されることがあります。
それが「ハルシネーション(Hallucination)」です。
ハルシネーション=AIの「もっともらしい誤回答」
ハルシネーションとは、AIが存在しない情報を事実のように生成してしまう現象のことです。
単なる“誤変換”ではなく、論理的な文脈の中に誤情報を自然に混ぜ込む点が特徴です。
たとえば、以下のようなケースが典型です。
- 実在しない企業名を提示する
- 日付や統計データを勝手に補完して出す
- 存在しない論文や出典URLを作る
人間が読むと「それっぽく見える」ため、気づかないまま引用・使用されてしまうことも少なくありません。
つまり、AIのハルシネーションは“誤情報の生成+誤信頼”の二重リスクをはらんでいます。
なぜ発生するのか?
AIのハルシネーションは、仕組み上の「癖」ではなく、明確な発生要因があります。
① 学習データに含まれるノイズや偏り
AIは膨大な公開データを学習していますが、その中には誤情報や古い情報も混ざっています。
AIはそれらを「正しい可能性のある文」として扱うため、結果的に誤回答が再現されます。
② 確率的出力(“最も自然な文”を出そうとする仕組み)
生成AIは、与えられた文脈の中で「次に来る確率が最も高い単語」を予測して出力します。
この“確率ベース”の仕組みにより、正確さよりも“自然さ”が優先されることがあり、
根拠のない情報でも「一貫した文」として生成されるのです。
③ コンテキスト不足(質問が曖昧・条件が足りない)
プロンプトの指示が曖昧だと、AIは不足情報を“想像で補完”します。
質問の範囲・時期・出典などを指定しないと、AIは学習データ全体から“それっぽい答え”を作り出してしまいます。
企業利用で問題になる3つのリスク
ビジネスの現場では、ハルシネーションは単なる「誤回答」では済みません。
場合によっては、経営判断や顧客対応に直結する深刻なリスクになります。
1. 誤情報による意思決定ミス
AIが生成した誤ったデータをもとにレポートや提案書を作成すれば、
上層部の判断を誤らせる可能性があります。特に市場データや業界分析などでは致命的です。
2. 顧客・社内への誤説明リスク
AIを使ったチャット対応やレポート生成で誤情報が混入すれば、顧客や社員への誤認を招きます。
一度拡散された情報を修正するのは難しく、信頼失墜の要因になります。
3. 信頼性・ブランド価値の低下
「AIを使っている会社なのに間違った情報を出した」と認識されれば、
ブランドへの信頼は大きく損なわれます。AI活用の目的である“効率化”が“信用損失”に変わるリスクです。
ハルシネーションはAIの性格的な“欠点”ではなく、設計・運用の課題です。
AIの仕組みを理解し、正確性を保つルールとプロンプト設計を整えることこそが、
企業のAI活用を成功させる第一歩になります。
ハルシネーションを防ぐプロンプト設計の5原則【例文付き】
ハルシネーションを完全に防ぐ「魔法の一文」は存在しません。
しかし、AIが誤情報を生みやすい条件を“設計段階で取り除く”ことは可能です。
ポイントは、AIに「何を」「どの範囲で」「どのように考えさせるか」を明確に伝えること。
この章では、AIの精度と再現性を高めるためのプロンプト設計5原則を、実際に使える例文とともに紹介します。
① 目的と前提を明示する
狙い: AIに“何のための回答か”を先に伝えて誤推論を防ぐ。
プロンプト例
あなたは【B2Bマーケティング】の専門家です。目的は「役員会向けの検討材料作成」です。
読者は非技術系の役員。専門用語は避け、比喩で補足してください。
まず要点を3つに要約し、その後に詳細説明を続けてください。
NG:「AI活用の効果を教えて」…(誰向け/何のため/深さ不明で誤答誘発)
補足(AI経営視点): “役割・対象・目的”の三点セット(Role/Audience/Goal:RAG)を毎回固定化すると再現性が上がります。
② 情報範囲を制限する
狙い: AIの“想像で補完”を抑え、検索空間を狭める。
プロンプト例
対象は「2023年1月〜2025年9月の日本国内事例」に限定してください。
統計は総務省・経産省・独立行政法人の公開資料のみを参照し、古い情報は採用しないでください。
該当がない場合は「該当なし」と明記してください。
NG:「最近の成功事例」…(“最近”の定義が曖昧)
補足: 期間・地域・ソース種別(官公庁/学術/一次情報)まで指定するのがコツ。
③ 出典・根拠を提示させる
狙い: “検証可能性”を担保し、捏造出典を減らす。
プロンプト例
主張ごとに根拠を1つ以上挙げ、参照URLを3件以内で提示してください。
URLは一次情報(公式発表・公的統計・原論文)を優先し、アクセス不能なURLは除外してください。
URLの後に簡潔な要約(30字以内)を添えてください。
NG:「参考もつけて」…(“参考”の定義が曖昧=ブログや生成文を混入しがち)
補足: “一次情報優先→二次→三次”の優先度を明記。URLの死活や要約も要求して“それっぽい出典”を牽制。
④ 思考プロセスを可視化させる
狙い: 結論だけでなく、推論の妥当性を点検できる形にする。
プロンプト例
次の順序で回答してください:
1) 前提条件の整理(箇条書き3点)
2) 情報の適合性チェック(前提と矛盾する点があれば列挙)
3) 代替仮説の提示(2案まで)
4) 最終結論(100字)
5) リスク・不確実性(3点)
NG:「結論だけ簡潔に」…(過剰圧縮は推論の粗さを隠す)
補足: “前提→検証→結論→不確実性”の型を固定。レビュー時間が短くなり、誤り検出率が上がります。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
⑤ 不明点がある場合は“回答を保留”する指示を出す
狙い: 無根拠の埋め草回答(ハルシネーション)を止める最後のガード。
プロンプト例
不明確・未確認・情報不足の場合は推測せず、
「わかりません/追加情報が必要です」のいずれかを明記してください。
必要な追加情報(3点まで)も提案してください。
NG:「できるだけ埋めて」…(創作を促す危険ワード)
補足: “保留可”を明文化すると、AIが無理に穴埋めする動機を下げられます。
使い回せる統合テンプレ(例)
狙い: チームで標準化し、毎回の品質を底上げ。
あなたはの専門家です。目的は「{目的}」。読者は「{対象}」です。
対象期間は「{期間}」、地域は「{地域}」、ソースは「{一次情報の種類}」に限定。
出力手順:
1) 前提条件(3点)
2) 適合性チェック(矛盾・欠落)
3) 代替仮説(最大2案)
4) 結論({文字数}字)
5) リスク・不確実性(3点)
6) 参照URL(最大3件、一次情報優先。URL後に30字要約)
不明点は推測せず「わかりません/追加情報が必要です」と明記し、
必要な追加情報を3点提案してください。
ミニNGワード集(社内ルール化の例)
- 「できるだけ盛って」「創造的に補って」→ 捏造を誘発
- 「何でもいいから」「ざっくりで」→ 範囲無制限化
- 「ネットの情報で」→ 三次情報混入リスク
チェックリスト(配布しやすい短版)
- 目的・対象・用途は先頭で宣言したか
- 期間/地域/ソース種別を限定したか
- 出典URLは一次情報か/死活確認したか
- 推論手順(前提→検証→結論→不確実性)を明示したか
- 「わからない」と言える余地を与えたか
誤情報を減らすための技術的アプローチ【+プロンプト補完法】
プロンプトの工夫だけでは、AIの誤情報(ハルシネーション)を完全に防ぐことはできません。
なぜなら、AIの出力は“内部の確率モデル”に依存しており、設計だけで制御できる範囲には限界があるからです。
そこで効果を発揮するのが、技術的アプローチとの組み合わせです。
検索連携(RAG)や温度設定、思考連鎖(Chain of Thought)などの手法を併用すれば、
AIの回答を外部情報で補強し、正確性・一貫性・再現性を同時に高めることができます。
この章では、誤情報を“減らし続ける”ために押さえておきたい4つの補完アプローチを紹介します。
① RAG(検索連携)で回答精度を補完する
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、AIが回答を生成する前に外部データベースやWeb検索から最新情報を取得する仕組みです。
これにより、AIは学習時点の古い知識に頼らず、根拠付きの回答を出せるようになります。
たとえばChatGPTの「ブラウジング機能」や企業独自の社内ナレッジ連携がRAGの一例です。
プロンプト補完例
「回答する際は、検索結果や公式データベースの内容を優先して参照してください。
出典URLを併記し、推測ではなく根拠ベースで説明してください。」
ポイント:
企業利用では、社内データを連携したRAG構築が最も確実。
プロンプトで「どのソースを優先するか」を明示することが誤情報対策の鍵になります。
② Temperature設定で出力の“安定性”を制御する
AIには「Temperature(温度)」というパラメータがあり、
値が高いほど自由で創造的な出力に、低いほど安定・保守的な出力になります。
ハルシネーションを防ぐ目的なら、Temperatureを0〜0.3程度に設定し、
“確率のブレ”を最小限に抑えるのが基本です。
プロンプト補完例
「創造的な回答よりも、事実ベースの正確な説明を優先してください。
不確実な情報は出力しないでください。」
ポイント:
特に報告書・議事録・教育用途では、温度低設定+根拠指示の併用が効果的。
創造性を求める場面(コピー案・企画など)は逆に高温度で使い分けるのがコツです。
③ 思考連鎖(Chain of Thought)で論理の一貫性を保つ
Chain of Thought(CoT)とは、AIに「結論に至るまでの思考過程を言語化させる」手法です。
AIがステップを踏んで考えることで、推論の飛躍や矛盾が減り、一貫した回答が得られやすくなります。
プロンプト補完例
「結論に至るまでの根拠を3ステップで説明してください。
各ステップでは“前提→分析→小結論”の順に整理してください。」
ポイント:
CoTを明示すると、AI内部の“推論過程”が可視化されるため、
人間側でも誤りを検知しやすくなります。
とくにレポート生成や要約タスクでは、説明責任を果たす設計として有効です。
④ モデル選択(GPT/Gemini/Claude)の違いを理解する
同じ質問でも、AIモデルによって回答の傾向は大きく異なります。
| モデル | 特徴 | 向いている用途 |
| GPT-4/GPT-5系 | 理論的・構造的な出力に強い。英語圏情報が豊富。 | ビジネス資料、分析・推論タスク |
| Gemini(Google) | 最新情報・マルチモーダル入力に強い。検索連携が自然。 | リアルタイム情報分析、調査業務 |
| Claude(Anthropic) | 長文処理と要約が得意。倫理・安全性指向が強い。 | 教育・マニュアル文書・議事録生成 |
プロンプト補完例
「あなたはClaudeを使用しています。出力は長文の要約に最適化してください。
文章構造を明示し、重要箇所は箇条書きで整理してください。」
ポイント:
AIの“得意・不得意”を理解した上でプロンプトを最適化すると、
同じ質問でも精度は数倍変わります。
モデル選択×プロンプト最適化=誤情報を減らす最短ルートです。
Tip:
「RAG(外部情報補完)+正確性指示+再確認プロンプト」の三点セットで、AI出力の信頼性は飛躍的に向上します。
プロンプト設計だけに頼らず、技術的な“多層防御”を設計に組み込むことがハルシネーション対策の本質です。
企業で取り組むハルシネーション対策|“防ぐ”から“減らし続ける”仕組みへ
ハルシネーション対策は、1人の「上手な使い方」で完結するものではありません。
AIを組織全体で活用するなら、属人化を防ぎ、精度を継続的に改善できる仕組みづくりが欠かせません。
ここでは、企業が取り組むべき3つの実践ステップを紹介します。
プロンプトの“品質管理”から“人材育成”までを仕組み化することで、誤情報リスクを最小化しながら成果を最大化できます。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
① 成功プロンプトを共有・標準化する(属人化防止)
多くの企業では、「誰か一人が上手に使っているが、他の人が再現できない」という問題が起こります。
これを防ぐには、“成功したプロンプト”を組織で共有・テンプレート化する仕組みが必要です。
たとえば以下のような取り組みが効果的です。
- 履歴管理ツールの活用:PromptLayer、Promptableなどを使い、出力履歴と結果を保存
- テンプレート共有:部署ごとに「良質プロンプト集」を蓄積し、用途別に再利用
- 改善記録の管理:「成功率」「使用条件」「改善履歴」を併記しPDCAを回す
プロンプトは“言語のノウハウ資産”です。
属人化させず、ナレッジとして再利用できる形で管理することが、AI精度の組織的向上につながります。
② 情報ガバナンスを設計する
プロンプト共有と同時に重要なのが、情報リスクを管理するガバナンス設計です。
AIは入力情報をもとに出力を生成するため、「何を入れてはいけないか」をルール化しておくことが不可欠です。
企業における代表的な設計項目は以下の通りです。
- 入力禁止ワード:機密情報・個人情報・顧客データなどをリスト化し、プロンプトに含めない
- 承認フロー:AI出力を外部に使う際は、上長・情報管理担当者のレビューを義務化
- 外部API利用範囲:RAGやブラウジング機能を使う際のデータ送信範囲を明記
例:社内ルール文テンプレ
- ChatGPT利用時に社外非公開資料を貼り付けないこと
- 出力文を対外資料に使用する際は、上長承認を得ること
- 生成物の著作権・出典を確認すること
ポイント:
ガバナンスを“禁止”ではなく“安全な使い方のガイドライン”として設計すれば、
社員の活用意欲を下げずに安全性を担保できます。
③ 教育・研修で正確性リテラシーを育成する
プロンプトやツールを整備しても、使う人が“正確性の考え方”を理解していなければ成果は安定しません。
そのため、ハルシネーションを防ぐための教育・研修設計が重要です。
おすすめのステップは以下の3段階です。
- 基礎理解研修:AIの仕組み・ハルシネーション発生原理・禁止ワードを学ぶ
- 社内演習:実際の業務文脈でプロンプト改善を繰り返す
- プロンプト検証会:部署横断で成功例・失敗例を共有し、精度改善ノウハウを蓄積
内部リンク: AIを正確に動かす!プロンプトの設計5つの方法と業務別活用法
教育とは「使い方を教える」ではなく、「AIをどう正確に使い続けるかを組織で学ぶこと」。
これが誤情報リスクを“減らし続ける文化”につながります。
AIを安全・正確に運用するには、“教育 × ルール”の設計が不可欠です。
組織全体でAI活用を定着させる仕組みを知りたい方は、以下の資料もご覧ください。
ハルシネーションをゼロにできる?AIとの“共創チェック”がカギ
AIのハルシネーションを完全に排除することは、現時点では不可能です。
生成AIは「最も自然な答え」を出そうとする“確率モデル”であり、 常にわずかな誤差や推測が混ざる仕組みを持っています。
重要なのは、「間違えないAI」を目指すのではなく、 “間違っても気づける仕組み”を人とAIの双方でつくること。
ここからは、誤情報リスクと正確性を両立するための“共創的チェック”の考え方を整理します。
AIは確率的に“最も自然な答え”を出す仕組み上、誤りはゼロにできない
生成AIは、過去の膨大なデータから「次に続く可能性が高い単語」を予測して文章を生成します。
つまり、AIは「正しい情報」を出そうとしているのではなく、“自然に見える文章”を構築しているにすぎません。
この構造上、常に誤情報が紛れ込む余地が存在します。
たとえば「出典を答えて」と指示しても、AIが根拠データを直接参照しているわけではなく、
“それらしい形式”で文章を再構築しているだけのケースも多いのです。
AIを安全に活用する第一歩は、 「AIは正解を知っている存在ではなく、“言語予測システム”である」という前提を持つことです。
だからこそ「AIを疑う力」を育てることが重要
AIが出す回答は、参考情報であって、最終判断ではない。
この意識を全社員が持つことが、誤情報対策の基礎になります。
とくに生成AIを業務で使う際には、以下の3つの“疑いポイント”を持つのが有効です。
- その情報は一次情報に基づいているか?
- 出典や根拠が明示されているか?
- 内容に矛盾や飛躍はないか?
この「AIを疑うリテラシー」は、人間側のスキルとして育成できる能力です。
AIを信じないのではなく、“検証的に信頼する”という姿勢が、正確性を担保する鍵になります。
AIと人間が補い合う“ダブルチェック文化”が鍵
ハルシネーションをゼロにすることはできませんが、
“気づける仕組み”を組織に埋め込むことは可能です。
たとえば、次のような“人×AI”の二重確認体制が有効です。
| チェック対象 | AIによる一次出力 | 人間による最終確認 |
| 事実関係 | データベース検索/要約 | 出典・公式情報で照合 |
| ロジック構成 | 推論・整理 | 妥当性・矛盾点の検証 |
| トーン/表現 | 自然言語生成 | 意図・ニュアンスの最終調整 |
このように、人がAIを“補う”ではなく、AIと協働で品質を保証する文化を育てることが、
長期的なハルシネーション対策になります。
AIを「正確に動かす仕組み」として教育・研修に組み込み、
組織全体で“検証文化”を根づかせることが、最終的な誤情報リスクの最小化につながります。
AIを正確に活用するには、“検証の文化”を教育から始めることが大切です。
実際の企業研修やリスク対策の設計事例をまとめた資料を、以下より無料でご覧いただけます。
まとめ|AIの信頼性は“設計力×検証力×教育力”で決まる
AIのハルシネーション(誤情報)は、“AIの欠点”ではなく“設計の問題”です。
どんなに高度なモデルを使っても、曖昧なプロンプトや不十分な検証体制のままでは、誤情報は必ず発生します。
誤情報を減らすには、次の4つの柱を組み合わせることが不可欠です。
- 設計(Prompt Design):AIが誤解しないよう、目的・範囲・形式を明確に伝える
- 検証(Verification):出力の根拠・矛盾・再現性を常に点検する
- 共有(Knowledge Sharing):成功事例・テンプレートをチームで再利用する
- 教育(Education):社員一人ひとりが“AIを疑う力”を持つ
これらを仕組みとして組み合わせることで、AIは単なるツールから“共に考えるパートナー”へと変わります。
企業にとって今求められているのは、AIを導入することではなく、AIを正確に活かせる人材を育てること。
そのためには、「設計力×検証力×教育力」の三位一体でAIリテラシーを底上げする必要があります。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
- Qハルシネーションとは何ですか?
- A
生成AIが、実際には存在しない情報を事実のように出力してしまう現象を指します。
英語の「Hallucination(幻覚)」に由来し、もっともらしい誤情報を自然な文章で生成する点が特徴です。
AIが「嘘をついている」のではなく、確率的に“自然な文章”を予測しているために起こります。
- Qハルシネーションはなぜ起こるのですか?
- A
主な原因は次の3つです。
- 学習データの偏りやノイズ
- 確率的出力(自然さを優先する仕組み)
- プロンプトの曖昧さや情報不足
つまり、AIの「知識不足」ではなく、「設計と運用の課題」によって発生します。
- Qプロンプトを工夫すればハルシネーションは防げますか?
- A
完全に防ぐことはできませんが、発生率を大きく減らすことは可能です。
目的・範囲・出典・思考手順・不明時の対応を明示することで、AIの誤補完を防げます。
たとえば次のような構文が効果的です。「不明な場合は“わかりません”と答えてください」
「根拠と出典URLを明記してください」
- QRAGやTemperatureなどの設定は難しいですか?
- A
基本的な理解があれば難しくありません。
- RAG:AIに検索・データ連携機能を持たせ、最新情報で補強する仕組み
- Temperature:出力の“自由度”を決める設定(低いほど安定、高いほど創造的)
これらをプロンプト設計と併用することで、誤情報をさらに減らせます。
- Q企業でハルシネーション対策を導入する際のポイントは?
- A
個人対応ではなく、組織全体で「正確性の文化」を作ることが重要です。
具体的には以下の3ステップを推奨します。- 成功プロンプトの共有・標準化(属人化防止)
- 情報ガバナンス設計(禁止ワード・承認フロー)
- 教育・研修によるリテラシー育成
詳しくは
AIを正確に動かす!プロンプトの設計5つの方法と業務別活用法
をご覧ください。