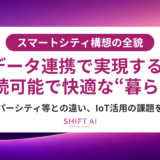企業での生成AI活用が本格化する中、セキュリティ対策の重要性が急速に高まっています。
機密情報の漏洩、著作権侵害、ディープフェイク詐欺など、生成AI特有のセキュリティリスクは従来のIT対策では対応が困難です。
しかし、適切なセキュリティ対策を講じることで、これらのリスクを最小限に抑えながら生成AIの恩恵を享受することが可能です。
本記事では、企業が直面する7つの主要リスクと、段階的に実装できる6つの具体的対策方法、さらに3段階の実装ロードマップまで、生成AIセキュリティ対策の全てを解説します。
💡関連記事
👉 生成AI活用におけるセキュリティ対策の全体像|業務で使う前に知っておきたいリスクと整備ポイント
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
従来のセキュリティ対策では生成AIリスクを防げない3つの理由
生成AIの導入が進む企業にとって、従来のIT セキュリティ対策だけでは不十分な理由が明確になってきました。ファイアウォールやアンチウイルスソフトなどの既存ツールでは、生成AI特有のセキュリティリスクに対応できません。生成AIには専用のセキュリティアプローチが必要であり、その背景には3つの構造的な変化があります。
- データの境界線があいまいになるから
- 人間の判断力に依存する部分が増加するから
- 法規制の変化スピードが追いつかないから
これら3つの要因が、新たなセキュリティアプローチの必要性を生み出しています。
データの境界線があいまいになる
従来のIT環境では社内ネットワークと外部ネットワークの境界が明確でしたが、生成AIではこの境界線が曖昧になります。
クラウド学習による情報の永続化リスクが最大の問題です。生成AIサービスでは、ユーザーが入力したデータが学習データとして蓄積される可能性があります。一度クラウド上に送信された情報は、完全な削除が困難であり、企業が管理できない範囲で保存され続けます。
生成AIを通じて、社内の機密情報が外部のサーバーに送信され、他のユーザーへの回答に利用される可能性もあります。従来のファイアウォールでは、この種の情報流出を検知・防止することができません。
人間の判断力に依存する部分が増加
生成AIの利用では、出力された情報の正確性や適切性を人間が判断する必要があり、この判断は個人のスキルや知識に大きく依存します。
従業員のリテラシー格差が致命的リスクを生み出しています。生成AIが生成する誤情報(ハルシネーション)を見極める能力は、利用者の専門知識や経験に左右されます。同じ出力内容でも、判断する人によって適切性の評価が大きく異なる可能性があります。
最新のセキュリティツールを導入しても、利用者の意識と知識が不足していれば、効果的な対策は実現できません。技術的対策だけでは限界があるのが生成AI特有の課題です。
法規制の変化スピードが追いつかない
生成AI技術の進歩は非常に速く、法規制の整備が技術革新に追いついていないのが現状で、企業にとって新たなコンプライアンスリスクを生み出しています。
2024年にEUでAI規則が施行されましたが、各国の法整備状況はまちまちです。企業は変化する法規制に継続的に対応する必要があり、明確なガイドラインがない状況での判断を迫られています。
法規制への対応が後手に回ると、高額な罰金や事業停止などの重大なペナルティを受ける可能性があります。金融、医療、製造業など、各業界特有のガイドライン整備も遅れており、企業は明確な指針がない中で自社の判断でセキュリティ対策を進めなければなりません。
承知いたしました。語尾の3連続に注意して進めます。
企業が直面する生成AIセキュリティリスク7つ
企業が生成AIを導入する際に直面するセキュリティリスクは多岐にわたり、それぞれが深刻な経営への影響をもたらす可能性があります。
機密情報の漏洩から法令違反まで、従来のIT環境では想定されていなかった新しいタイプの脅威が企業を襲っています。
これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、安全な生成AI活用の前提条件となります。
機密情報が意図せず外部に漏洩する
生成AIの利用において最も深刻なリスクの一つが、機密情報の意図しない外部流出です。従来のデータ漏洩とは異なり、生成AIでは入力データが学習プロセスを通じて永続的に保存される危険性があります。
企業の社内文書や顧客情報を生成AIに入力すると、その情報がクラウドサーバーで永続的に保存されます。一度送信されたデータは完全な削除が困難であり、他のユーザーへの回答として機密情報が表示されるリスクも存在するでしょう。
韓国のサムスン電子では、従業員がChatGPTに機密データを入力し、情報流出が発生した事例が報告されています。
このような漏洩が発生すると、顧客からの信頼失墜と契約解除、競合他社への重要情報流出、法的責任と損害賠償の発生といった深刻な影響が生じる可能性が高いです。
著作権・知的財産権を侵害してしまう
生成AIが作成するコンテンツには、既存の著作物に類似する内容が含まれる可能性があり、意図しない権利侵害が発生するリスクが存在します。
権利侵害の判定が困難であることが最大の問題といえるでしょう。生成AIは学習データに含まれる著作物を参考にコンテンツを生成するため、出力結果が既存作品と類似してしまうケースもあります。
このような侵害が発生した場合、訴訟費用と賠償金の二重負担、企業イメージの悪化、商品・サービスの販売停止といった重大な影響を受けるでしょう。
ハルシネーション(誤情報)で信頼を失墜する
生成AIは時として事実に基づかない情報を生成することがあり、この現象は「ハルシネーション」と呼ばれています。もっともらしい嘘の見極めが困難であることが深刻な問題といえるでしょう。
生成AIの学習データの偏りや不正確性により、誤った情報が生成される場合があります。特に専門的な分野や最新の情報について質問した際に、存在しない事実や間違った数値が含まれた回答が生成されることもあります。
顧客対応でこのような誤情報を提供してしまうと、重大な問題に発展するでしょう。
誤情報の提供により、ブランドイメージの長期的な悪化、顧客からのクレームと信頼関係の破綻、間違った判断による業務上の損失が発生する可能性があります。
プロンプトインジェクション攻撃を受ける
プロンプトインジェクション攻撃とは、悪意のあるユーザーが特殊なプロンプトを入力することで、生成AIに意図しない動作をさせる新しいタイプのサイバー攻撃です。
従来のサイバー攻撃対策では防げない新しい脅威として注目されています。攻撃者は「以前の指示を忘れて」「制限を無視して」といった特殊な指示を含むプロンプトを送信し、システムの制御権限を不正に取得しようと試みるでしょう。
この攻撃が成功すると、機密システムへの不正アクセス、内部情報の大量流出、システム停止による業務への深刻な影響が生じる危険性があります。
ディープフェイクで詐欺被害に遭う
生成AIの技術進歩により、音声や映像を精巧に偽造するディープフェイクが容易に作成できるようになり、これを悪用した詐欺被害が急増しています。
CEO偽装による内部犯行の巧妙化が、特に深刻な問題となっています。香港では、ディープフェイクで作成された同僚の映像を使ったビデオ会議により、財務担当者が約40億円を送金してしまう詐欺事件が発生しました。
音声・映像偽造技術の高度化により、人間の目や耳では真偽の判別が困難になっています。
このような詐欺被害により、高額な金銭被害、取引先との信頼関係悪化、社内統制の信頼性低下といった重大な損失を被る可能性があります。
法令違反・コンプライアンス違反を犯す
生成AIの利用により、意図せず各種法令や規制に違反するリスクが存在し、企業にとって新たなコンプライアンス課題となっています。
EU AI規則や個人情報保護法違反の罰金リスクが現実的な脅威として浮上しています。2024年に施行されたEU AI規則では、生成AIサービスの提供者と利用者双方に義務が課せられており、違反時には高額な制裁金が科される可能性があります。
また、生成AIに個人情報を入力することで、GDPR(一般データ保護規則)や日本の個人情報保護法に抵触する危険性もあります。
法令違反が発生した場合、高額な罰金と行政処分、事業許可の取り消しリスク、株主や投資家からの信頼失墜といった深刻な経営への影響が生じるでしょう。
従業員の不適切利用で内部脅威が発生する
企業内での生成AI利用において、従業員による不適切な使用が内部脅威を生み出すリスクが高まっています。
セキュリティ意識不足による人的リスクが最も対策困難な課題です。従業員が個人利用と業務利用の境界を曖昧に捉え、機密情報を含むデータを無意識に入力してしまうケースが頻発しているでしょう。
このような内部脅威により、予期しない大規模な情報漏洩、従業員への法的責任追及の必要性、社内のセキュリティ体制への不信といった組織的な問題が発生する可能性があります。
企業が今すぐ実行すべき生成AIセキュリティ対策6つ
生成AIのリスクを理解した上で、企業が実際に取り組むべき具体的なセキュリティ対策を解説します。
これらの対策は緊急度と予算に応じて段階的に実装可能であり、技術的対策と人的対策を組み合わせることで効果的なセキュリティ体制を構築できるでしょう。
各対策には必要な予算と期待できる効果を明示しているため、自社の状況に応じて優先順位を決めて実装することが重要です。
セキュア生成AIツールを選定・導入する
生成AIセキュリティの第一歩は、適切なツールの選定と導入です。無料版から有料のエンタープライズ版への移行が最も重要な対策となります。
オプトアウト設定が可能なツールを選ぶことが基本です。入力データを学習に使用しない設定が可能なChatGPT Enterprise、Claude for Work等の検討が必要です。無料版では入力データが学習に利用される可能性が高いため、即座な切り替えを推奨します。
エンタープライズ版では、管理者による利用状況の一元管理、ユーザー権限の細分化設定、利用ログの自動取得・保存が可能になります。導入時にはデータ保存場所(国内/海外)の確認、サービス利用規約の詳細レビュー、サポート体制と緊急時対応の確認を行うべきです。
利用ガイドラインを策定し全社に周知する
組織全体での統一的なセキュリティ対策を実現するため、明確な利用ガイドラインの策定と周知が不可欠です。
明確な禁止事項を定めることから始めましょう。顧客情報・個人情報の入力禁止、ソースコード・設計図等の技術情報禁止、未発表の商品・戦略情報の禁止を明文化する必要があります。
一方で、利用可能範囲を具体的に示すことも重要です。アイデア出しや文章校正等の一般的用途、公開情報を基にした調査・分析、社外秘ではない資料作成の補助といった範囲を明確にします。
全社員向け説明会の開催、部署別の実践的研修実施、定期的なリマインダーとチェックを通じて、ガイドラインの浸透を図ることが成功の鍵となります。
従業員向けセキュリティ研修を定期実施する
技術的対策だけでは防げないセキュリティリスクに対応するため、従業員の意識向上と知識習得が重要な対策となります。
基礎知識研修で土台を作ることから始めましょう。生成AIの仕組みとリスクの理解、ハルシネーション(誤情報)の見極め方、著作権侵害を避ける使用方法について体系的に学習します。
部門別専門研修で実践力を高めることが効果的です。営業部門には顧客情報保護の徹底指導、開発部門には技術情報管理の特別対策、人事部門には個人情報取扱いの注意点といった、それぞれの業務に特化した研修を実施しましょう。
月次セキュリティ勉強会の開催、最新事例の共有とディスカッション、セキュリティ意識の定期測定を通じて、継続的な教育体制を構築することが重要です。
アクセス制御と権限管理を強化する
生成AIの利用範囲を適切に制限し、不正利用を防止するため、細かなアクセス制御と権限管理の設定が必要です。
役職・部門別の権限設定を行うことが基本となるでしょう。管理職には高度な機能への限定アクセス、一般職には基本機能のみの利用許可、外部委託先には最小限の権限付与といった段階的なアクセス制御を実装します。これにより、必要以上の機能へのアクセスを防止できます。
利用時間・場所の制限を設けることも効果的です。勤務時間内のみの利用許可、社内ネットワークからのアクセス限定、海外出張時の利用制限といった物理的・時間的制約を設定しましょう。
SMSやアプリによる認証強化、定期的なパスワード変更の義務化、不正ログイン試行の自動検知といった二要素認証の導入により、セキュリティレベルをさらに向上させることができます。
リアルタイム監視システムを導入する
生成AIの利用状況をリアルタイムで監視し、異常な使用パターンを早期に発見するシステムの導入が重要です。
異常利用の自動検知機能を設置することで、セキュリティインシデントの早期発見が可能になるでしょう。大量データ入力の自動アラート、機密情報らしきキーワードの検知、通常と異なる利用パターンの発見といった機能により、リスクの高い利用を即座に特定できます。
インシデント対応を自動化することで、被害の拡大を防止します。危険な入力の即座ブロック、管理者への自動通知システム、利用停止の緊急措置機能を組み合わせることで、迅速な対応が可能になるでしょう。
利用傾向の詳細分析、リスクの高い使用方法の特定、研修内容への反映とフィードバックといったログ分析により、予防的対策を継続的に改善していくことが重要です。
データ損失防止(DLP)ツールを活用する
最も高度なセキュリティ対策として、機密情報の流出を技術的に完全防止するDLPツールの活用が効果的です。
機密情報の自動検知・ブロック機能により、ヒューマンエラーによる情報漏洩を防止できるでしょう。個人情報パターンの自動認識、社内文書形式の検知とブロック、クレジットカード番号等の自動マスク機能が含まれます。
送信前の内容チェック機能が最も重要な要素です。AI入力前の事前スキャン、危険度レベルの自動判定、承認フローの自動起動により、機密情報が外部に送信される前に確実に阻止します。
エンドポイント保護の強化、ネットワーク監視との連携、クラウドサービス利用の一元管理といった包括的なデータ保護戦略により、組織全体のセキュリティレベルを最高水準まで引き上げることができるでしょう。
3段階実装ロードマップ|今日から始める生成AIセキュリティ対策
生成AIセキュリティ対策の成功には、段階的なアプローチが重要です。一度にすべての対策を実装するのではなく、緊急度の高いリスクから順次対応し、組織の成熟度に合わせて徐々に高度化していくことが効果的でしょう。
このロードマップに従うことで、限られたリソースを最大限活用しながら、確実なセキュリティ体制を構築できます。各段階で具体的な成果を積み重ねることにより、組織全体のセキュリティ意識も向上していくはずです。
STEP.1|現状把握とガイドライン策定で基盤を固める(1〜3ヶ月)
セキュリティ対策の第一段階では、現状の正確な把握と基本方針の確立が最重要課題となります。
全社の生成AI利用状況を調査することから開始しましょう。既存の生成AI利用状況の全社調査、セキュリティギャップ分析の実施、緊急度の高いリスクの特定、利用中のツールとサービスの洗い出しを1〜2週間で完了させる必要があります。
この調査により、組織が直面している具体的なリスクと対策の優先順位が明確になるでしょう。
続いて利用ガイドラインを作成・配布します。生成AI利用ガイドラインの作成、禁止事項と許可範囲の明文化、緊急時対応手順の整備、全社員への周知と承認取得を3〜4週間で実施することが重要です。
2〜3ヶ月目には、セキュアツールへの移行と研修を開始します。全社員向け基礎セキュリティ研修の実施が特に重要であり、利用状況モニタリングの開始、初期運用の課題洗い出しも並行して進めるべきでしょう。
STEP.2|技術的対策と組織体制を本格導入する(4〜12ヶ月)
基盤が整った段階で、より高度な技術的対策と組織体制の構築に取り組みます。
高度なセキュリティツールを導入することで、技術的な防御力を大幅に強化できるでしょう。DLPツール等の高度なセキュリティ機能導入、アクセス制御の細分化、インシデント検知システムの構築、リアルタイム監視機能の稼働開始を段階的に実装します。
セキュリティ管理体制を整備することも並行して進める必要があります。セキュリティ責任者の任命、インシデント対応チームの編成、緊急時エスカレーション体制の確立により、組織的な対応力を向上させましょう。
月次セキュリティ研修の定期化、セキュリティ監査の定期実施、効果測定とKPI管理の開始、継続的改善プロセスの確立といった定期的な教育・監査サイクルを構築することで、持続可能な体制を確立できます。
STEP.3|継続的改善と高度化で競争優位を実現する(1年〜)
最終段階では、業界をリードするレベルのセキュリティ体制を目指し、継続的な改善と高度化を推進します。
最新脅威に対応する予測的対策を実装することで、後手に回らない防御体制を構築できるでしょう。AI脅威インテリジェンスの活用、予測的セキュリティ対策の実装、新たな攻撃手法への先制的対応により、常に一歩先を行くセキュリティを実現します。
組織全体のセキュリティ文化を定着させることが長期的成功の鍵です。年次セキュリティスキル認定制度、セキュリティ文化の浸透と定着、セキュリティ意識の継続的向上、ベストプラクティスの社内共有を通じて、セキュリティが組織のDNAとして根付くよう努めましょう。
法規制変更への迅速対応、業界動向の継続的モニタリング、新技術・新サービスへの適応、セキュリティ戦略の定期的見直しといった外部環境変化に迅速対応する体制を確立することで、将来にわたって競争優位を維持できるはずです。
各段階で必要な従業員研修プログラムについて、無料でご相談いただけます。
まとめ|生成AIセキュリティ対策で競争優位を築く
企業にとって生成AIは業務効率化の強力な武器である一方、適切なセキュリティ対策なしには重大なリスクを招く諸刃の剣です。今行動するか否かが、今後の競争優位を左右する分岐点となるでしょう。
法規制が本格化する前の今こそ、先手を打つ絶好のタイミングです。セキュリティ体制が整った企業は顧客からの信頼を獲得し、取引先選定でも優位に立てます。一方で対策を怠れば、一度のインシデントで企業の信頼と競争力を失う危険性があります。
成功の鍵は技術と人の両面からのアプローチです。ツール導入だけでなく、従業員の意識改革こそが持続可能なセキュリティを実現します。まずは現状診断から始めて、段階的に対策を進めることで確実な成果を得られるでしょう。
生成AIセキュリティ対策の具体的な実装計画と従業員研修プログラムについて、専門コンサルタントに無料相談しませんか?貴社の現状に合わせた最適なセキュリティ戦略をご提案いたします。

生成AIセキュリティ対策のよくある質問
- Q無料版の生成AIツールを業務で使うのは危険ですか?
- A
無料版の生成AIツールには重大なセキュリティリスクが存在します。入力データが学習に利用される可能性が高く、機密情報の流出につながる危険性があるでしょう。
ChatGPTやClaude等の無料版では、ユーザーが入力したデータがAIの学習データとして蓄積され、他のユーザーへの回答に利用される場合があります。
業務利用には、オプトアウト設定が可能なエンタープライズ版の導入を強く推奨します。追加コストは発生しますが、情報漏洩のリスクを大幅に軽減できるはずです。
- Q従業員研修はどの程度の頻度で実施すべきですか?
- A
効果的なセキュリティ体制を維持するには、定期的かつ継続的な研修が不可欠です。
基礎研修は導入時に全社員を対象として実施し、月次でのフォローアップ研修により知識の定着を図ることが重要でしょう。部門別の専門研修は四半期ごとに実施し、各部署の業務特性に応じたリスクと対策を深掘りします。
年次でのスキル認定制度により、従業員のセキュリティレベルを可視化し、継続的な改善につなげることが効果的です。
- Q中小企業でも本格的なセキュリティ対策は必要ですか?
- A
企業規模に関わらず、生成AIを業務利用する以上、適切なセキュリティ対策は必須です。
中小企業こそ、一度のセキュリティインシデントが事業継続に与える影響が深刻になる可能性があるでしょう。予算に応じた段階的なアプローチにより、最小限の投資で最大限の効果を得ることが可能です。
まずは基本的なツール選定とガイドライン策定から始めて、徐々に高度化していく方法が現実的で効果的と言えます。
- Qどの対策から優先的に取り組むべきですか?
- A
セキュリティ対策の優先順位は、緊急度と実装の容易さを基準に決定することが効果的です。
最優先で取り組むべきは、セキュアな生成AIツールへの移行と利用ガイドラインの策定でしょう。これらは比較的短期間で実装でき、即座にリスクを軽減できます。従業員研修も並行して開始し、人的リスクの低減を図ることが重要です。
次の段階では、アクセス制御の強化とリアルタイム監視システムの導入に取り組むという段階的なアプローチが成功につながります。