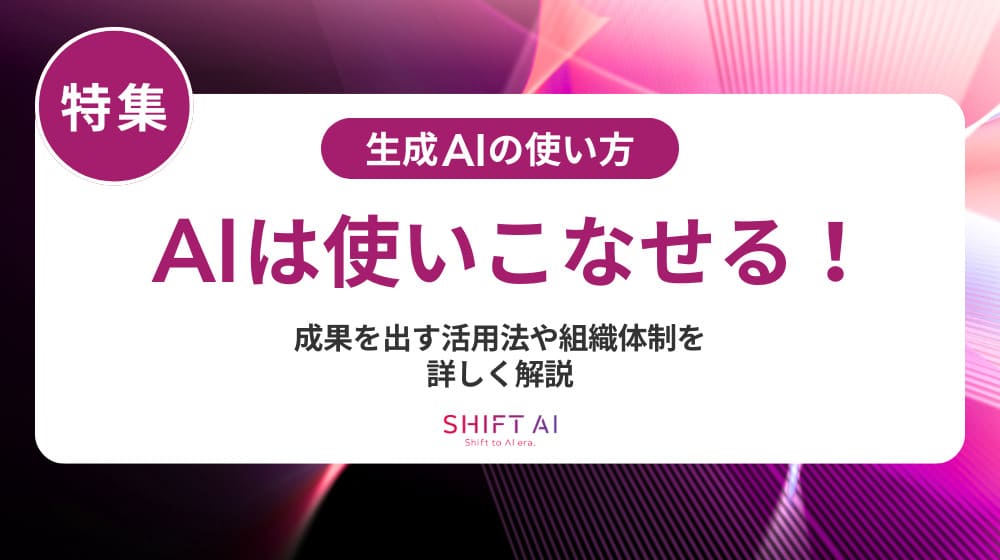生成AIの企業導入が急速に進む中、適切なリスク管理を行わずに導入すると、機密情報漏洩や法的トラブル、業務品質の低下など深刻な問題を引き起こす可能性があります。
実際に、大手企業での情報流出事例や著作権侵害による訴訟も発生しており、組織として慎重な対応が求められています。
本記事では、生成AIを安全かつ効果的に活用するために企業が押さえるべき9つの注意点と、具体的なリスク対策を体系的に解説します。法務・セキュリティ・人材育成の観点から実践的な対応方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AI利用で企業が注意すべき9つのリスク
企業が生成AIを導入する際は、機密情報漏洩や法的トラブルなど9つの主要なリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
これらのリスクを軽視すると、企業の競争力低下や深刻な損害につながる可能性があります。
💡関連記事
👉【2025年最新】生成AIの使い方完全ガイド|基本操作から組織導入まで実践的に解説
機密情報が漏洩する
生成AIサービスに入力した情報は、他社や第三者に漏洩する危険性があります。
多くの生成AIサービスでは、ユーザーが入力したデータをAIの性能向上のために学習データとして利用しています。そのため、企業の機密情報や顧客データを入力すると、その情報が他のユーザーの回答に表示されたり、サービス提供者によって保存・分析されたりする可能性が高まります。
特にクラウド型の生成AIサービスでは、入力された情報が海外のサーバーに送信・保存されることが多く、データの管理体制や法的保護の範囲が不明確になりがちです。
ハルシネーションで誤った判断をする
生成AIは事実と異なる情報を正確に見える形で出力するため、重要な業務判断に悪影響を与える恐れがあります。
ハルシネーション(幻覚)とは、生成AIが学習データに基づかない虚偽の情報を、あたかも事実であるかのように生成する現象です。特に専門性の高い分野や最新の情報について質問した場合、もっともらしい回答が返ってくることが多く、ユーザーが真実と誤認しやすくなります。
財務データの分析や法的判断、技術仕様の決定など、正確性が求められる業務でハルシネーションに基づいた判断を行うと、企業に深刻な損害をもたらす可能性があります。
著作権侵害で訴訟される
生成AIが出力したコンテンツが既存の著作物と類似している場合、著作権侵害として損害賠償請求される可能性があります。
生成AIは膨大な著作物を学習データとして使用しているため、出力されたテキストや画像が既存の作品と酷似することがあります。この場合、類似性と依拠性が認められれば著作権侵害が成立し、権利者から差止請求や損害賠償請求を受ける恐れがあります。
特に商用利用する場合は、著作権法の権利制限規定の適用範囲が限定的になるため、より慎重な対応が必要です。生成されたコンテンツをそのまま商品やサービスに使用することは避けるべきでしょう。
個人情報保護法に違反する
個人情報を含むデータを生成AIに入力することは、個人情報保護法の第三者提供規制に該当する可能性が高いです。
生成AIサービスの利用は、個人データをサービス提供者(第三者)に提供する行為と解釈される場合があります。本人の同意を得ずに個人情報を入力すると、個人情報保護法違反となり、行政処分や社会的信用の失墜につながります。
また、海外の生成AIサービスを利用する場合は、個人データの越境移転に関する規制も適用されるため、より厳格な対応が求められます。事前に利用目的の特定と本人同意の取得が不可欠です。
プロンプトインジェクション攻撃を受ける
悪意あるプロンプトによって、生成AIが意図しない動作を行い、機密情報が漏洩する危険性があります。
プロンプトインジェクションとは、特殊な指示文を入力することで、生成AIの制限を回避し、本来出力すべきでない情報を引き出す攻撃手法です。攻撃者がシステムの脆弱性を突くことで、社内の重要な情報や他のユーザーのデータにアクセスされる可能性があります。
特に生成AIを社内システムと連携させている場合、この攻撃によって業務データベースの情報が不正に取得される恐れがあるため、適切なセキュリティ対策が必要です。
差別的・偏見的な内容が出力される
学習データの偏りにより、生成AIが差別的な表現を出力し、企業のブランドイメージを著しく損なう可能性があります。
生成AIの学習データには、インターネット上の膨大な情報が含まれており、その中には人種・性別・宗教などに関する偏見や差別的な内容も混在しています。そのため、特定の質問に対して不適切な回答が生成され、それを企業が公開すると炎上や社会的批判を招く恐れがあります。
特に顧客対応やマーケティング分野で生成AIを活用する場合は、出力内容の事前チェック体制を整備することが重要です。
従業員のスキルが低下する
生成AIに過度に依存することで、従業員の思考力や専門性が低下し、長期的な競争力を失う可能性があります。
生成AIの便利さに慣れてしまうと、従業員が自ら考える機会が減り、批判的思考力や問題解決能力が衰退する恐れがあります。また、専門知識を習得する意欲も減少し、人材の付加価値が低下することで、企業全体の競争優位性が失われる可能性があります。
生成AIは効率化ツールとして活用しつつも、従業員の能力開発を継続的に行う体制を維持することが不可欠です。
サイバー攻撃の標的になる
生成AIサービスやそれを利用する企業システムが、サイバー攻撃の新たな標的となる可能性が高まっています。
生成AIサービスには膨大な企業データが集積されるため、攻撃者にとって魅力的なターゲットとなります。サービス自体が攻撃を受けた場合、複数の企業の機密情報が同時に流出する大規模な被害が発生する恐れがあります。
また、生成AIを社内システムと連携させている企業では、AI経由で基幹システムへの不正アクセスが行われるリスクも考慮する必要があります。
法規制の変更に対応できない
AI関連の法規制は急速に変化しており、対応が遅れると重大なコンプライアンス違反を招く可能性があります。
世界各国でAI規制法の制定や業界ガイドラインの更新が相次いでおり、企業は常に最新の規制動向を把握し、適切に対応する必要があります。規制への対応が遅れると、事業停止命令や多額の制裁金などの重い処分を受ける恐れがあります。
特に複数の国や地域で事業を展開している企業では、各地域の規制要件を満たすための体制整備が急務となっています。
生成AI利用時の法的注意点
生成AI利用時は著作権侵害、個人情報保護法違反、人格権侵害の3つの法的リスクに特に注意が必要です。
これらの法的問題を軽視すると、訴訟や行政処分、社会的信用失墜につながる可能性があります。
著作権侵害を避ける方法
生成AIの出力物を商用利用する際は、既存著作物との類似性チェックが不可欠です。
生成AIが出力したコンテンツには、学習データに含まれていた著作物の表現が反映される場合があります。商用利用時は著作権法の権利制限規定(30条の4)の適用が限定的になるため、類似性と依拠性の両方が認められれば著作権侵害が成立します。
対策として、生成物を利用する前に既存作品との比較検証を行い、類似度が高い場合は修正や差し替えを検討しましょう。また、権利者への事前確認や利用許諾の取得も有効な手段となります。
個人情報保護法に適切に対応する方法
個人データを生成AIに入力する行為は第三者提供に該当するため、事前の本人同意取得が必要です。
生成AIサービスの利用は、個人データをサービス提供者に提供する行為と解釈されます。本人の同意なく個人情報を入力すると個人情報保護法違反となり、最大1億円以下の罰金が科される可能性があります。
まず利用目的を明確に特定し、本人から適切な同意を取得してください。海外サービス利用時は越境移転の規制も適用されるため、より慎重な対応が求められます。
人格権侵害を防ぐ方法
実在する人物の画像や情報が生成された場合、肖像権やプライバシー権の侵害リスクが発生します。
生成AIが実在する人物に関する内容を出力した場合、その人の肖像権、パブリシティ権、名誉権、プライバシー権を侵害する可能性があります。特に著名人や公人の場合、損害賠償請求や差止請求のリスクが高まります。
人物に関する生成物を利用する前に、必ず事実確認と権利関係の調査を行いましょう。疑義がある場合は利用を控えるか、当該人物からの許諾を得ることが安全な対応となります。
生成AIの注意点に対するリスク管理対策
効果的なリスク管理には、利用ガイドラインの策定、セキュリティ対策の強化、定期的なリスク評価の3つが不可欠です。
これらの対策を組み合わせることで、生成AI利用に伴うリスクを大幅に軽減できます。
💡関連記事
👉【2025年版】生成AI導入リスク7選と対策完全ガイド|中小企業でも実践できる安全な始め方
利用ガイドラインを策定する
明確な利用ガイドラインの策定により、従業員の不適切な利用を防止し、組織全体のリスクを軽減できます。
ガイドラインでは利用目的、対象業務、禁止事項を具体的に明文化しましょう。機密情報の入力禁止、個人情報の取り扱い制限、商用利用時の事前承認プロセスなどを詳細に規定することが重要です。
また、違反時の対応手順や責任者を明確に設定し、全従業員に周知徹底を図ってください。定期的な見直しを行い、新たなリスクや技術動向に応じてガイドラインを更新することも必要です。
💡関連記事
👉生成AI社内ガイドライン策定から運用まで|必須7要素と運用失敗を防ぐ方法
セキュリティ対策を強化する
オプトアウト設定とアクセス権限管理により、情報漏洩リスクを最小限に抑制できます。
生成AIサービス利用時は、必ずオプトアウト設定を有効にして、入力データが学習に使用されないようにしましょう。また、利用者のアクセス権限を適切に管理し、業務上必要な人員のみがサービスにアクセスできる体制を構築してください。
さらに、利用ログの監視体制を整備し、不審なアクセスや大量データの入力を早期に検知できる仕組みを導入することが重要です。インシデント発生時の対応手順も事前に策定しておきましょう。
💡関連記事
👉生成AIのセキュリティリスクとは?企業が知っておくべき主な7大リスクと今すぐできる対策を徹底解説
リスク評価を定期的に実施する
月次でのリスクアセスメント実施により、新たな脅威や変化する規制要件に迅速に対応できます。
生成AI技術や関連法規制は急速に変化しているため、定期的なリスク評価が不可欠です。利用状況の分析、インシデントの発生状況、法規制の動向などを総合的に評価し、リスクレベルの変化を把握しましょう。
評価結果に基づいて、ガイドラインの改訂、セキュリティ対策の見直し、追加の従業員教育などを実施してください。外部の専門家やコンサルタントの知見も活用し、客観的な評価を行うことが重要です。
生成AI利用で重要な従業員研修と教育方法
生成AIの安全な活用には、全従業員への基礎研修と部門別の専門教育が不可欠です。
適切な教育により、リスクを理解した従業員が生成AIを効果的に活用し、組織全体の生産性向上と安全性確保の両立が可能になります。
全社員向けの基礎研修を実施する
全従業員が生成AIの基本的な仕組みとリスクを理解することで、不適切な利用による事故を防止できます。
基礎研修では、生成AIの動作原理、ハルシネーションの発生メカニズム、情報漏洩のリスクなどを分かりやすく説明しましょう。利用時の禁止事項、機密情報の取り扱い方法、適切なプロンプトの作成方法も具体例を交えて教育してください。
また、インシデント発生時の報告手順や対応方法を明確に伝え、問題が起きた際の迅速な対応体制を構築することが重要です。定期的な理解度テストで習得状況を確認しましょう。
部門別・役職別の専門研修を行う
各部門の業務特性に応じた専門研修により、実務での適切な活用方法を身につけることができます。
経営層には戦略的活用方法とリスクガバナンスを中心に教育し、現場担当者には日常業務での具体的な利用方法と注意点を重点的に指導してください。法務・情報システム部門には、より高度な法的対応やセキュリティ対策の知識が必要です。
営業部門では顧客情報の保護、開発部門では知的財産権の管理など、部門固有のリスクと対策を詳しく解説することで、実践的なスキルを習得できます。
継続的な学習体制を構築する
技術進歩と法規制の変化に対応するため、定期的な知識更新とスキルアップが欠かせません。
四半期ごとの更新研修を実施し、新機能や新たなリスク、法規制の変更点について情報共有を行いましょう。外部セミナーや専門研修への参加を奨励し、最新の知見を組織内に取り込む体制を整備してください。
社内でのナレッジ共有プラットフォームを構築し、成功事例やトラブル対応事例を蓄積・共有することで、組織全体のリテラシー向上を図ることが重要です。
まとめ|生成AI導入の注意点を理解して安全な活用を実現しよう
生成AI導入時に企業が注意すべき9つのリスクは、適切な対策により回避できます。機密情報漏洩やハルシネーション、著作権侵害などの技術的リスクに加え、個人情報保護法や人格権に関する法的リスクへの対応が重要です。
成功の鍵は、明確な利用ガイドラインの策定、セキュリティ対策の強化、そして従業員への継続的な教育にあります。段階的な導入とモニタリング体制により、リスクを最小化しながら生成AIの効果を最大化できるでしょう。
技術の進歩とともに新たなリスクも生まれるため、専門家との連携や最新情報の収集を怠らず、組織全体で生成AIリテラシーを高めることが持続的な活用につながります。
安全で効果的な生成AI活用の実現には、体系的な研修プログラムによる組織的な取り組みが欠かせません。

生成AIの注意点に関するよくある質問
- Q生成AIの利用で最も注意すべきリスクは何ですか?
- A
最も注意すべきは機密情報漏洩リスクです。生成AIサービスに入力したデータは学習に利用されたり、他のユーザーに表示されたりする可能性があります。企業の重要な情報や顧客データを入力すると、競合他社や第三者に流出する恐れがあるため、機密性の高い情報の入力は避けましょう。オプトアウト設定の確認も必須です。
- Qハルシネーションによる被害を防ぐ方法はありますか?
- A
生成AIの出力内容を必ず人間がファクトチェックすることが重要です。ハルシネーションは完全に防げないため、特に重要な業務判断や専門的な内容については、複数の情報源で事実確認を行ってください。生成AIの回答を鵜呑みにせず、あくまで参考情報として活用し、最終的な判断は人間が行うことが被害防止の鍵となります。
- Q生成AIで著作権侵害を避けるにはどうすればよいですか?
- A
商用利用前に既存作品との類似性チェックを必ず実施してください。生成されたコンテンツが既存の著作物と類似している場合、著作権侵害のリスクがあります。特に画像やテキストを商品・サービスに使用する際は、事前に権利関係を調査し、疑義がある場合は修正や差し替えを検討しましょう。権利者への確認も有効な対策です。
- Q個人情報を生成AIに入力することは法的に問題ありますか?
- A
本人の同意なく個人情報を入力すると個人情報保護法違反となります。生成AIサービスの利用は第三者提供に該当するため、事前に本人から適切な同意を取得する必要があります。同意なしに個人データを入力した場合、最大1億円以下の罰金が科される可能性があります。海外サービス利用時は越境移転の規制も適用されるため、より慎重な対応が求められます。
- Q社内で生成AI利用のガイドラインを作る際のポイントは?
- A
利用目的、禁止事項、承認プロセスを具体的に明文化することが重要です。機密情報の入力禁止、個人情報の取り扱い制限、商用利用時の事前承認など、詳細なルールを設定してください。違反時の対応手順や責任者も明確にし、全従業員への周知徹底を図りましょう。技術や法規制の変化に応じて定期的な見直しも必要です。
- Q生成AI導入時の従業員研修で重要なポイントは?
- A
全従業員への基礎研修と部門別の専門教育の両方が不可欠です。基礎研修では生成AIの仕組み、リスク、適切な利用方法を教育し、部門別研修では各業務特性に応じた具体的な注意点を指導してください。技術進歩に対応するため、定期的な知識更新研修も実施しましょう。継続的な教育により組織全体のリテラシー向上を図ることが重要です。