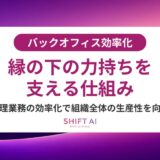「Copilot Studioって、具体的に何ができるの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。Microsoft 365 Copilotの名前は知っていても、Copilot Studioが“自社専用のAIエージェント”を作れる環境だと知っている人はまだ限られています。
Copilot Studioを活用すれば、社内のFAQ対応を自動化したり、営業や人事部門の定型業務を効率化したりと、業務フロー全体を最適化する仕組みを構築できます。しかもローコード/ノーコード対応のため、エンジニアだけでなく現場部門の担当者も扱えるのが大きな特徴です。
本記事では、
- Copilot Studioでできること(機能一覧)
- ユースケース(具体的な活用シーンと効果)
- 導入メリットと注意点
- 他のAIツールとの違い
- 導入ステップと料金感
を徹底解説します。
まず基本概要を押さえたい方は、こちらもご覧ください。
Copilot Studioとは?できること・特徴・料金・導入効果を徹底解説
また下記のリンクからは、「全社員のCopilot活用」「Copilot活用人材育成」をテーマにした複数の事例を含め、AI導入・活用に成功し成果をあげている様々な業種の実際の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どうやってAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
- Copilot Studioとは?
- Copilot Studioでできる主なこと(機能一覧)
- 差別化要素:機能 × 活用例 × 効果
- 実際に何ができる?ユースケースと効果
- Before/Afterで見る業務負担の違い
- Copilot Studioを導入するメリット
- 注意点と「できないこと」
- よくある失敗例と改善ルールまとめ
- 導入ステップ(成功までの流れ)
- 他のAIツールとの違い
- 差別化要素:比較表(汎用LLM vs Copilot Studio)
- 導入事例(業界別活用イメージ)
- 差別化要素:業界別Before/After表
- 料金体系とコスト感
- 差別化要素:ROIシミュレーション例
- 今後の展望
- まとめ:Copilot Studioを効果的に活用するために
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Copilot Studioとは?
Copilot Studioは、Microsoftが提供するローコード/ノーコード開発環境です。専門的なプログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップや簡単な設定で自社専用のAIエージェント(Copilot)を構築できます。
従来の「Microsoft 365 Copilot」がWordやExcel、Outlookなど各アプリに組み込まれた支援機能であるのに対し、Copilot Studioは「自社固有の業務やナレッジに最適化したAIを設計できる」のが大きな特徴です。
さらに、TeamsやPower Platformとのシームレス連携によって、社内チャットでのFAQ応答、業務フローの自動化、外部データソースの統合など、全社レベルでの業務効率化を実現できます。
Copilot Studioでできる主なこと(機能一覧)
Copilot Studioは、単なるチャットボット作成ツールにとどまりません。
自社専用AIエージェントを設計し、社内外のデータやアプリと連携させ、業務フローを自動化できる総合プラットフォームです。ここでは代表的な機能を整理します。
自社専用のCopilotエージェントを作成
- 部門や業務ごとの目的に応じたAIエージェントを構築可能
- 例:人事部門向けの「社内手続きヘルプCopilot」、営業部門向けの「提案資料サポートCopilot」
ナレッジソース接続(SharePoint、Web、ファイル、外部システム)
- 社内のSharePoint、Teamsファイル、公開Webサイト、外部DBを参照して回答可能
- 例:最新の規程やマニュアルを学習させ、FAQに即答
トリガー・アクション・条件分岐によるワークフロー設計
- 「ユーザーが○○を聞いたら→△△の処理を実行」といった自動フローを設計可能
- 例:経費精算の問い合わせが来たら、フォームリンクを提示し、入力状況を確認する処理を実行
TeamsやPower Platformとのシームレス統合
- Teamsに組み込んで社内チャットから直接呼び出し
- Power AutomateやPower Appsと連携し、外部システムと双方向のやり取りも可能
セキュリティ/ガバナンス対応
- Microsoftの認証基盤(Azure AD)と統合し、権限やアクセスを管理
- 監査ログやデータ保持ポリシーを組み込み、安心して社内展開可能
差別化要素:機能 × 活用例 × 効果
| 機能 | 活用例 | 期待できる効果 |
| 自社専用エージェント作成 | 部門別AIヘルプデスク | 問い合わせ対応時間▲30% |
| ナレッジソース接続 | 社内規程・FAQ検索 | 回答スピードUP/情報の属人化解消 |
| ワークフロー設計 | 経費精算・勤怠申請サポート | 手続き遅延防止/社員満足度向上 |
| Teams連携 | チャット内で提案資料の生成 | 会議準備工数削減/意思決定迅速化 |
| Power Platform統合 | CRMや在庫システムと連携 | データ活用度UP/業務自動化推進 |
| セキュリティ管理 | 権限別アクセス制御 | 情報漏洩リスク軽減/コンプライアンス対応 |
実際に何ができる?ユースケースと効果
Copilot Studioの強みは、業務に直結したAIエージェントを柔軟に作れる点です。ここでは代表的なユースケースと、その効果を紹介します。
社内ヘルプデスク(FAQ自動応答 → 問い合わせ対応時間▲30%)
- 社員からの「パスワードを忘れた」「経費精算の手順は?」といった質問に、自動で回答。
- 担当者の対応時間を削減し、問い合わせ対応時間を約30%短縮。
営業・マーケティング(提案資料・顧客対応支援 → 商談スピードUP)
- 過去の提案書や成功事例を元に、資料のたたき台を自動生成。
- 顧客対応の下準備にかかる時間を削減し、商談スピードが向上。
人事・総務(手続き支援・問い合わせ対応 → 定型業務削減)
- 入社手続きや休暇申請のフローを案内するエージェントを構築。
- 煩雑な定型業務が自動化され、人事・総務部門の負担を軽減。
情シス部門(ITサポート自動化 → チケット処理効率化)
- PC設定方法やソフト不具合の対応を自動化。
- 問い合わせチケットの処理効率を大幅に改善。
データ分析・レポート生成支援
- 売上データや人事データを基に、自動で要約やグラフを生成。
- 分析担当者の作業時間を削減し、経営判断のスピードを加速。
Before/Afterで見る業務負担の違い
| 業務シーン | Before(導入前) | After(Copilot Studio導入後) | 効果 |
| 社内FAQ対応 | 人事・情シス担当が繰り返し対応 | AIが自動応答、担当者は複雑案件に集中 | 対応時間▲30% |
| 営業準備 | 提案資料をゼロから作成 | 過去事例を活用しAIが草案を生成 | 商談準備時間短縮 |
| 入社手続き | 担当者が都度案内 | AIが手順を自動で提示 | 定型業務削減 |
| ITサポート | チケット処理に時間がかかる | 自動回答&処理フロー設計 | 処理効率UP |
| レポート作成 | 手作業で集計・整形 | AIが要約と可視化を実行 | 判断スピードUP |
Copilot Studioを導入するメリット
Copilot Studioは「自社専用AIエージェント」を構築できるだけではなく、現場の生産性向上や経営全体の効率化に直結するメリットがあります。ここでは導入によって得られる主要な利点を解説します。
ノーコード/ローコードで誰でも使える
- 専門的なプログラミングスキルが不要。
- 現場部門の担当者でも、自社業務に合わせたCopilotを設計可能。
- 「現場主導のAI活用」を実現できる。
Microsoft製品との強力な連携
- Teams、SharePoint、Outlook、Power Platformなどとシームレスに統合。
- 社内に既に浸透しているMicrosoft環境の延長線上で活用できる。
- 新規ツール導入コストを抑えつつ効果を発揮。
業務効率化・コスト削減効果
- 定型的な問い合わせや資料作成を自動化。
- 例:FAQ対応時間 30分 → 5分 に短縮(1件あたり)。
- 社員100人の利用で、年間数百時間の削減効果につながる。
セキュリティ・ガバナンスで安心
- Azure AD認証、アクセス権限管理、監査ログに対応。
- 外部生成AIと異なり、企業利用に適したガバナンス基盤を持つ。
- コンプライアンスリスクを低減できる。
拡張性・カスタマイズ性
- 部門ごとのニーズに応じてCopilotを設計・追加可能。
- Power Automateや外部APIと連携し、業務フロー全体を自動化できる。
- 「まずはFAQ対応から → 業務プロセス全般へ」とスモールスタートから全社展開が可能。
注意点と「できないこと」
Copilot Studioは強力なツールですが、導入すればすぐに全ての課題が解決するわけではありません。精度や運用面での注意点、導入に伴う制約を理解しておくことが成功のカギです。
ナレッジ更新が止まると精度が落ちる
- AIは最新データを基に学習・回答します。
- FAQやマニュアルの更新が滞ると、誤った情報をそのまま社員に回答するリスクがあります。
- 改善ルール:ナレッジ管理担当を明確化し、更新サイクルを月次で回す。
社員リテラシー差で活用にバラつき
- プロンプト(指示文)の工夫次第で成果は大きく変わります。
- 部門や社員ごとの使いこなし度合いによって、「便利/使えない」の差が顕著になることも。
- 改善ルール:全社員に共通の使い方研修やプロンプト例を共有する。
運用体制(誰がメンテナンスするか)
- Copilot Studioは導入して終わりではなく、継続的な改善・調整が不可欠。
- 運用責任者が不明確だと、ナレッジが陳腐化し、利用率が低下します。
- 改善ルール:「IT部門+現場担当」の二重体制でメンテナンスを担当する。
ライセンス費用の負担
- Copilot Studioは追加ライセンスが必要で、全社導入すると年間数百万単位の投資になるケースも。
- ROI(投資対効果)のシミュレーションなしで導入すると、「コストだけ増えて効果が見えない」失敗例もある。
- 改善ルール:PoCで効果を数値化 → 段階的に拡大するのが現実的。
よくある失敗例と改善ルールまとめ
| 失敗例 | 何が起こるか | 改善ルール |
| FAQ更新を怠る | 誤回答が増え社員の信頼低下 | ナレッジ管理担当を明確化し月次更新 |
| 教育不足 | 部門によって活用度に差 | 共通研修・プロンプト例を配布 |
| 運用体制不明確 | 利用率が徐々に低下 | IT部門+現場で二重管理 |
| コスト試算不足 | 「費用倒れ」で撤退 | 小規模PoCで効果を検証 |
導入効果を安定して出すには“社員教育”がカギ
導入ステップ(成功までの流れ)
Copilot Studioを導入する際は、いきなり全社展開するのではなく、小規模で効果を検証しながら段階的に広げていくプロセスが欠かせません。以下のステップを踏むことで、スムーズに定着させることができます。
小規模PoCから始める(効果検証)
- 最初は問い合わせ件数の多い部門(例:人事、情シス)に限定して導入。
- KPI例:FAQ対応時間削減率、社員満足度、チケット処理スピード。
- 成果を数値で示すことで、社内理解と経営層への説得材料になる。
社内ナレッジ整備
- Copilot Studioの精度は、参照できるナレッジの鮮度に依存。
- マニュアル・規程・FAQを整理・最新化してから接続する。
- 「AIが答えやすいデータ構造」にすることが効果最大化のカギ。
セキュリティ・権限設計
- どの部門がどのデータにアクセスできるかを明確化。
- Azure ADやTeamsのセキュリティ基盤を利用し、最小権限でのアクセス制御を設計する。
- 情報システム部門と連携し、監査ログや利用状況をモニタリング。
全社展開ロードマップ
- フェーズ1:小規模PoCで効果検証
- フェーズ2:主要部門へ展開(営業・人事・IT部門など)
- フェーズ3:全社利用に拡大し、定着のための教育・運用体制を強化
Copilot導入ステップをさらに詳しく知りたい方はこちら
Copilot Studioとは?できること・特徴・料金・導入効果を徹底解説
他のAIツールとの違い
Copilot Studioを理解するうえで、多くの人が気になるのが「ChatGPTやGeminiとどう違うのか?」という点です。ここでは主要なAIツールとの違いと、Microsoft 365 Copilotとの関係を整理します。
ChatGPTとの違い:社内データ連携・ガバナンス対応
- ChatGPTは汎用的な生成AIで、外部知識に基づいた回答が得意。
- 一方、Copilot Studioは社内データ(SharePoint、Teams、ファイル)を安全に参照できる点が強み。
- セキュリティやガバナンス(権限管理・監査ログ)に対応しているため、企業利用に適している。
Geminiや他社AIツールとの比較
- Gemini(Google)は検索・マルチモーダル機能に強みがある一方、Microsoft 365環境との統合性は弱い。
- Copilot Studioは、TeamsやPower Platformなど既存のMicrosoft製品との親和性が高く、「既存環境にAIを組み込む」用途に最適。
- 他社ツールは柔軟性は高いが、セキュリティ・運用設計を自社で担う必要があるケースが多い。
Copilot for Microsoft 365との補完関係
- Microsoft 365 Copilotは「WordやExcelに組み込まれたAI支援ツール」。
- Copilot Studioは「自社専用AIを作る基盤」であり、365 Copilotを拡張する存在。
- 例:Wordで作成した文書をTeamsに共有し、Copilot Studioエージェントが部門別FAQに基づいて回答する、という使い分けが可能。
差別化要素:比較表(汎用LLM vs Copilot Studio)
| 項目 | ChatGPT/Gemini(汎用LLM) | Copilot Studio |
| 主な用途 | 一般的な文章生成、検索 | 自社専用AIエージェントの構築 |
| データ連携 | 公開データ中心 | 社内データ(SharePoint、Teams、ファイル)に接続 |
| セキュリティ | 標準の外部利用向け | 権限管理・監査ログ・ガバナンス対応 |
| 開発難易度 | プロンプト操作中心 | ローコード/ノーコードで設計可能 |
| 利用シーン | 個人利用、汎用作業支援 | 部門横断の業務フロー効率化 |
| Microsoft製品との連携 | 弱い | Teams/Power Platformと強力に統合 |
導入事例(業界別活用イメージ)
Copilot Studioは、業種を問わず幅広い業務に適用できます。ここでは代表的な業界ごとの活用イメージを紹介します。
製造業:社内FAQ効率化
- Before:生産ライン担当者が「マニュアルはどこ?」「設備トラブル時の対処は?」と都度問い合わせ。
- After:CopilotがFAQやマニュアルを即座に提示。現場の停止時間を最小化。
流通・小売:顧客対応迅速化
- Before:店舗スタッフが顧客からの質問に答える際、本部へ確認が必要で対応が遅れる。
- After:Copilotが商品情報・在庫・キャンペーン情報を即検索。顧客満足度を向上。
金融業:業務プロセス自動化
- Before:法令・社内規程に基づく確認作業を人手で実施 → ミス・工数増。
- After:Copilotが規程を参照しチェックフローを自動化。リスク低減と工数削減を両立。
教育機関:学内サポートデスク
- Before:学生・教員からの「履修登録の手順」「施設予約方法」などの問い合わせが集中。
- After:Copilotが24時間自動応答。職員の負担を大幅軽減。
差別化要素:業界別Before/After表
| 業界 | Before(導入前) | After(導入後) | 効果 |
| 製造業 | マニュアル確認に時間がかかり現場停止 | Copilotが即回答 | 生産効率UP/停止時間削減 |
| 流通・小売 | 顧客対応で本部確認が必要 | Copilotが商品・在庫情報を即提示 | 顧客満足度向上/対応スピードUP |
| 金融業 | 法令確認・チェック作業が属人化 | Copilotが規程参照で自動化 | リスク低減/工数削減 |
| 教育機関 | 学生・教員の問い合わせが集中 | CopilotがFAQ自動応答 | 職員負担軽減/24時間対応可能 |
料金体系とコスト感
Copilot Studioを導入する際には、ライセンス体系・追加費用・企業規模ごとのコスト感を理解しておく必要があります。ここでは代表的なポイントを整理します。
ライセンス体系(利用条件・追加費用)
- Copilot Studioは Microsoft 365 Copilotライセンスに含まれる形で提供されるケースが多い。
- ただし、ナレッジソース接続や拡張機能の利用には追加費用が発生する場合がある。
- 利用には 対象となるMicrosoft 365プラン(E3/E5、Business Standard/Premiumなど) が必要。
無料トライアルの有無
- Microsoftや一部のパートナー経由で、PoC(概念実証)環境を期間限定で提供するケースがある。
- 無料期間中に効果検証を行い、「本格導入に値するか」を見極めるのがおすすめ。
中小企業 vs 大企業のコスト試算
- 中小企業(利用者50名規模)
- 月額数十万円程度の追加投資で導入可能。
- FAQや定型業務の自動化で、年間数百時間の削減効果が見込める。
- 大企業(利用者1,000名以上)
- 年間数千万円規模の投資になるケースも。
- ただし、会議・問い合わせ対応・資料作成の削減効果は年間数万時間規模に達し、ROIは十分に見合う。
差別化要素:ROIシミュレーション例
| 項目 | 導入前 | 導入後(Copilot Studio活用) | 削減効果 |
| FAQ対応 | 30分/件 × 500件/年 = 250時間 | 5分/件 × 500件/年 = 42時間 | ▲208時間 |
| 会議議事録作成 | 60分/会議 × 200回/年 = 200時間 | 15分/会議 × 200回/年 = 50時間 | ▲150時間 |
| 合計効果 | – | – | 年間▲358時間(約45人日)削減 |
※1人日あたりの人件費4万円換算 → 約180万円相当のコスト削減
今後の展望
Copilot Studioは現在も進化を続けており、MicrosoftのAI戦略の中で重要な位置を占めています。今後のアップデートや拡張によって、さらに幅広い業務活用が可能になると考えられます。
最新機能(例:“computer use”機能)
- Microsoftは「computer use」と呼ばれる新機能を発表。
- Copilotがユーザーの代わりにPC上の操作を実行できるようになり、従来は人手で行っていた作業をAIが代替できるようになる。
- 例:Webアプリでの情報入力、複数システム間のコピー&ペースト作業を自動化。
MicrosoftのAI戦略における位置づけ
- Microsoftは「Copilot」をOffice製品やTeamsだけでなく、あらゆる業務領域に広げる戦略を掲げている。
- Copilot Studioはその中核を担い、「企業ごとに最適化されたCopilot」を作る基盤として位置づけられている。
- 今後はAzure OpenAI Serviceとの統合も強化され、マルチモデル対応(GPT、Gemini、Claudeなど)が進む可能性もある。
拡張可能性と将来シナリオ
- マルチモーダル対応:テキストだけでなく、画像や音声データも取り込んで処理できる機能の拡張。
- 業務アプリ連携の拡大:SalesforceやSAPなど、Microsoft外のシステムともより強固に統合。
- 全社的なAI基盤化:各部門ごとのPoCから全社導入へ進み、「全社員がAIを使うのが当たり前」な環境へ。
今後のCopilot Studioは「社内専用AIの構築ツール」から「企業全体を動かすAI基盤」へと進化していくと予想されます。導入を検討するなら、将来の拡張性も見据えて早期にPoCを始めることが有効です。
まとめ:Copilot Studioを効果的に活用するために
Copilot Studioは、企業が「自社専用AIエージェント」を構築できる環境です。社内FAQや業務フロー自動化など、幅広いシーンで効率化を実現できる可能性を持っています。
導入を成功させるためのカギは、
- 事前準備(ナレッジ整備・ルール策定)
- 社員教育(AIリテラシー向上)
- 段階的導入(小規模PoCから全社展開へ)
この3つのステップを押さえることです。
Copilot Studioは単なる便利機能ではなく、業務効率化・生産性向上の中核ツールになり得る存在です。早期に取り組む企業ほど、競争優位を築けるでしょう。
また下記のリンクからは、「全社員のCopilot活用」「Copilot活用人材育成」をテーマにした複数の事例を含め、AI導入・活用に成功し成果をあげている様々な業種の実際の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どうやってAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
- QCopilot Studioで具体的に何ができますか?
- A
自社専用のAIエージェントを作成し、FAQ対応や業務フロー自動化、データ参照、Teams統合などが可能です。部門ごとの定型業務を効率化するのに有効です。
- QChatGPTなど他のAIとCopilot Studioは何が違いますか?
- A
ChatGPTは汎用的な生成AIですが、Copilot Studioは社内データや業務システムと連携できる点が大きな違いです。セキュリティやガバナンス面でもエンタープライズ利用を前提としています。
- QCopilot Studioを使うのにプログラミングスキルは必要ですか?
- A
基本的に不要です。ノーコード/ローコードの操作環境で、条件分岐やワークフローをGUIで設計できます。高度なカスタマイズを行う場合は開発者のサポートがあるとより効果的です。
- QCopilot Studioで作ったAIエージェントはTeams以外でも使えますか?
- A
はい。Teamsとの統合が代表的ですが、Power PlatformやWebサイト、外部システムとも連携可能です。利用用途に応じて展開範囲を広げられます。
- Q導入にあたって注意すべきことはありますか?
- A
よくある失敗は「ナレッジ更新を怠る」「運用担当者を明確にしない」ことです。精度維持には定期的な情報更新と運用体制の整備が不可欠です。
- QCopilot Studioはどのくらいコストがかかりますか?
- A
Microsoft 365 Copilotのライセンスに含まれるケースが多いですが、拡張機能や接続先によって追加費用が発生します。中小企業なら月額数十万円規模から導入可能です。