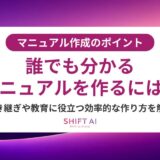近年、Microsoft Copilotの進化の中で注目を集めているのが「Copilotエージェント」です。単なるAIアシスタントではなく、ユーザーの指示に応じて自律的にタスクを実行する仕組みとして位置づけられ、業務の在り方を大きく変えつつあります。
しかし、「CopilotとCopilotエージェントは何が違うのか?」「実際にどんな業務に使えるのか?」「導入にはどんな準備が必要か?」といった疑問を持つ方も少なくありません。とくに情シス部門や経営企画の担当者にとっては、導入効果とリスクを正しく理解しておくことが欠かせません。
本記事では、Copilotエージェントの概要や仕組みをわかりやすく整理したうえで、具体的な活用事例、導入ステップ、注意すべきリスクや最新動向までを解説します。読み終えるころには、自社でどのようにCopilotエージェントを活かせるか、次のアクションが明確になるはずです。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Copilotエージェントとは?概要と位置づけ

Copilotエージェントとは、Microsoft Copilotに組み込まれた「自律的に動くAI機能」のことを指します。従来のCopilotはユーザーの指示に応じて回答や提案を返す“アシスタント型”でしたが、エージェントはさらに進化し、あらかじめ設定されたゴールに向けて複数のタスクを自動的に進める役割を担います。
たとえば、通常のCopilotは「会議の議事録を要約して」と依頼すれば即座にまとめを提示してくれます。一方、Copilotエージェントは「会議記録を整理して、担当者ごとのアクションリストを作成し、共有フォルダに保存、関係者にメールで通知」という一連の流れを自律的に処理できます。
Microsoftが提唱する位置づけとしては、Copilotが「人の横に並ぶ共同作業者」であるのに対し、Copilotエージェントは「特定の役割をもつ代理人」として働く存在です。ユーザーが逐一指示を出さなくても、あらかじめ定義したタスクやルールに基づき、業務を代替・補助できる点が大きな特徴です。
さらに、近年注目を集めるChatGPTの「カスタムGPT」やGoogle Geminiの「AIエージェント」と比較すると、Copilotエージェントは Microsoft 365環境との親和性 が強みです。メール、Teams、SharePoint、Power Platformなど既存の業務基盤と連携できるため、導入ハードルが低く、実務への定着が進みやすいのが特徴といえるでしょう。
仕組みと役割|Copilotエージェントの動き方
Copilotエージェントは、大規模言語モデル(LLM)を基盤に、Microsoft 365のアプリケーションや外部データと連携しながら動作します。ポイントは「指示に応じて動く」のではなく、「目的達成のために必要なステップを自律的に組み立て、実行できる」ことです。
1. 自然言語による指示理解
ユーザーは専門的なコマンドを覚える必要はなく、自然な文章で依頼できます。エージェントはこれを解析し、意図をタスクに分解します。
2. ナレッジソースの参照
エージェントは社内文書、会議記録、クラウド上のナレッジベースなど、必要な情報にアクセスします。これにより単なる情報生成ではなく「社内データを踏まえた実務的な回答」が可能になります。
3. アクション実行
Teamsのチャネルにメッセージを投稿する、Outlookでメールを送信する、SharePointにファイルを保存するなど、複数のアプリをまたいだ処理を自動的に行えます。従来のCopilotが「提案」に留まる場面でも、エージェントは「行動」まで踏み込みます。
4. 権限管理と安全性
業務利用で欠かせないのがセキュリティ。CopilotエージェントはMicrosoft Entra ID(旧Azure AD)の認証を活用し、ユーザーごとに適切なアクセス権限の範囲でのみ動作します。これにより情報漏洩や不正アクセスのリスクを抑えられます。
まとめると、Copilotエージェントは「意図を理解 → 情報を探索 → 実行する」という流れを自動化し、人の“代理人”として業務を遂行する仕組みを持っています。
Copilotエージェントの活用シーン
Copilotエージェントの強みは、単なるAIチャットを超えて「具体的な業務を肩代わりできる」点にあります。部署や役割ごとに、さまざまなユースケースが広がっています。
営業・マーケティング部門
顧客データをもとにした商談準備や提案資料の下書きを自動生成できます。例えば、CRMに登録された取引履歴を整理し、「次回の提案に役立つ要点」をまとめてTeamsで共有する、といった一連の作業をエージェントが代行できます。
人事・総務部門
社内からの定型的な問い合わせ(休暇制度、福利厚生、勤怠ルールなど)に対し、FAQボットとして対応可能です。また、勤怠データやアンケートの集計を自動化し、レポートを生成する役割も担えます。
経営企画・管理部門
市場調査や競合動向の要約、定例会議向けのダッシュボード更新など、情報収集と整理を自律的に進められます。経営層が意思決定に必要な資料をタイムリーに受け取れるようになることで、判断スピードが向上します。
情報システム部門
システム利用者からの一次問い合わせに自動応答したり、障害報告を整理・分類して担当部署へ振り分けたりといったヘルプデスク的な役割を果たします。パスワードリセットやアクセス権申請など、繰り返し発生する処理の自動化にも向いています。
こうしたユースケースはあくまで一例ですが、共通するのは「定型業務を自律的にこなすことで、社員が本来の付加価値業務に集中できる」点です。
導入のメリットと注意点
Copilotエージェントを導入すると、多くの企業にとって大きな業務改善効果が期待できます。ただし、利点だけに目を向けるのではなく、注意すべきポイントも理解しておくことが重要です。
導入メリット
- 業務効率化と時間削減
定型的な事務作業や情報整理を自動化できるため、社員は付加価値の高い業務に集中できます。たとえば「週次レポート作成にかかる2時間が15分に短縮」など、具体的な時短効果が得られます。 - ナレッジの標準化
属人的に行われていたタスクをエージェントに任せることで、処理方法が統一され、品質が安定します。 - 社員満足度の向上
煩雑なルーティン業務から解放されることで、モチベーションが高まりやすくなります。
注意点
- 誤回答や判断ミスのリスク
AIが出力する内容は常に正しいとは限りません。誤情報をそのまま利用すると、業務に悪影響を与える可能性があります。 - 情報漏洩への懸念
社内データを利用する以上、権限設定やアクセス管理を適切に設計しないと、機密情報が意図せず共有される恐れがあります。 - 社員のAIリテラシー不足
使いこなせなければ効果は限定的です。AIに過度に依存したり、逆に不信感から利用が進まないこともあります。
つまり、Copilotエージェントは大きな効果を発揮する一方で、リスクを理解し、適切なルール設計と教育を伴わなければ成果につながりにくいのです。
Copilotエージェントの作り方
Copilot Studioを使えば、自社のナレッジや業務内容に合わせた「独自のCopilotエージェント」を簡単に作成できます。
ここでは、初めての方でも迷わず進められるよう、作成の基本ステップを順番に解説します。
Copilot Studioにサインインする
まずは Copilot Studio にアクセスし、MicrosoftアカウントまたはEntra ID(旧Azure Active Directory)でサインインします。
Microsoft 365 Copilotの契約がある場合、そのテナント内で利用可能です。
管理者がアクセス権を付与していない場合は、事前に組織の管理者に利用を申請しておきましょう。
新しいエージェントを作成する
ダッシュボードの「+ 新しいCopilotを作成」をクリックします。エージェント名、説明、使用言語を入力して作成を開始します。
名前はユーザーに分かりやすいものを設定し、説明欄には目的(例:「経費精算に関する質問に答える」など)を簡潔に書くのがポイントです。
作成後は自動的に編集画面に移動します。
トピック(会話の流れ)を設計する
エージェントの応答ロジックは「トピック」と呼ばれる単位で構成されます。トピックは、ユーザーの質問 → AIの回答 → 次のアクション、という流れを定義する部分です。
Copilot Studioでは、ノーコードのフローチャート形式で設計できるため、プログラミング知識は不要です。
まずは「よくある質問」などの基本トピックから作り、テストしながら少しずつ拡張していくと良いでしょう。
知識ソースを追加する
エージェントに自社独自の知識を持たせるために、SharePointやOneDrive上のファイル、Webページ、データベースなどを「ナレッジソース」として接続します。
設定画面の「ナレッジ」から、参照させたい情報源を選択します。ここで注意したいのは、アクセス権限とデータの更新頻度。社内ファイルをつなぐ場合は、閲覧権限を持つユーザーのみが利用できるように設定する必要があります。
テストチャットで動作確認する
エージェントの初期構築ができたら、右側の「テストウィンドウ」で動作を確認しましょう。実際にユーザーとして質問を入力し、返答内容や流れをチェックします。
回答が不自然な場合は、トピックの条件分岐やキーワード設定を見直します。このテストを繰り返すことで、より正確で自然な会話ができるエージェントに仕上がります。
公開設定を行う(Teams・Webサイトなど)
テストを終えたら、エージェントを公開して利用を開始します。「公開」メニューから、利用チャネル(Teams・Webチャット・独自Webサイトなど)を選択できます。
社内向けであればTeamsへの公開が最も簡単で、Microsoft 365ユーザー全員が利用可能になります。社外向けにWeb公開する場合は、管理者権限と有料ライセンスが必要です。
成功導入のステップ|ロードマップで理解する
Copilotエージェントは「導入すればすぐ成果が出る」わけではありません。試行錯誤を経て全社に浸透させるプロセスを踏むことで、初めて効果が最大化されます。ここでは代表的な導入ロードマップを整理します。
1. 小規模パイロット導入
まずは一部部署や限られた業務にエージェントを試験的に導入し、効果と課題を検証します。たとえば「会議議事録の要約自動化」や「勤怠データ集計」など範囲の小さいタスクが適しています。
2. 社員研修とガイドライン整備
試験導入で得られた知見をもとに、利用ルールや活用ガイドラインを作成します。同時に社員向け研修を実施し、エージェントの正しい使い方やリスク認識を浸透させることが重要です。
3. 全社展開とユースケース横展開
業務効果が確認できたら、他部署にも適用範囲を広げていきます。営業、人事、情シスなど各部門で共通する定型業務を中心に展開すると、効果を横に広げやすくなります。
4. 改善サイクルの定着
導入後は終わりではなく、利用状況をモニタリングし、エージェントの機能を改善・追加していく必要があります。KPIを設定し、定期的にレビューを行うことで、持続的な成果につながります。
Copilotエージェントのリスクと対策
Copilotエージェントは強力な業務パートナーとなりますが、その自律性ゆえにいくつかのリスクも存在します。導入効果を高めるためには、リスクを正しく理解し、事前に対策を講じることが欠かせません。
セキュリティリスク
エージェントは社内データにアクセスして動作します。権限設計が甘いと、閲覧権限のない情報まで処理してしまう可能性があります。対策として、Microsoft Entra ID(旧Azure AD)による厳格な認証管理や、最小権限の原則を徹底することが重要です。
誤回答・バイアスのリスク
AIが生成する内容は常に正確とは限らず、誤情報や偏りが含まれることがあります。対策としては、エージェントの出力結果を人が確認するフローを組み込み、重要な意思決定には必ずダブルチェックを行う仕組みを導入すべきです。
運用リスク
エージェントの構築・設定を担当者任せにすると、属人化やブラックボックス化が起こりやすくなります。対策として、ガイドラインやマニュアルを整備し、複数人でメンテナンスできる体制を整えることが必要です。
法的リスク
著作権に関わるコンテンツ利用や、顧客情報の取り扱いには法的リスクが伴います。対策として、コンプライアンス部門や法務部門と連携し、利用範囲やデータの扱いに関するルールを明文化しておくことが求められます。
リスクを軽視した導入は“便利なはずのAIが新たなトラブルを生む”結果につながります。
企業が安全にCopilotエージェントを活用するためには、ガバナンス設計とリスクマネジメントを同時に進めることが必須です。
最新動向と今後の展望
Copilotエージェントは、まだ登場して間もない機能ですが、すでに進化のスピードは加速しています。今後のアップデートや市場動向を踏まえると、エージェントの活用領域はさらに広がっていくでしょう。
Copilot Studioによるカスタムエージェント構築
Microsoftは「Copilot Studio」を通じて、企業独自のエージェントを設計できる仕組みを提供しています。これにより、部署ごとの業務プロセスや社内規定に合わせたカスタマイズが可能となり、利用の幅は大きく拡大しています。
マルチエージェント協調の時代へ
複数のエージェントが連携し、プロジェクト単位で役割分担を行う「マルチエージェント」構想も注目されています。たとえば「調査エージェント」と「レポート作成エージェント」が連動することで、より高度な自動化が実現します。
外部システムとの統合
CRMやERP、BIツールなど外部アプリケーションとの統合も進んでいます。これにより、エージェントは「情報収集・分析・レポーティング」までを一貫して担える存在へと進化しています。
今後の方向性
将来的には、エージェントが完全自律的にタスクを遂行し、利用者がゴールだけを設定すれば業務が進む世界が見えてきます。Microsoft以外のプラットフォーム(Google、OpenAIなど)との競争も激化しており、「どのAIエージェントを選び、どのように組み合わせるか」が企業戦略の新たなテーマ となるでしょう。
まとめ|Copilotエージェントで業務の自律化を進める
Copilotエージェントは、これまでの「AIアシスタント」を超えて、自律的にタスクを遂行する業務パートナー として進化しています。
Copilotエージェントは単なるツールではなく、業務変革の起点 となる存在です。
導入効果を最大化するためには、社員一人ひとりがAIの可能性とリスクを理解し、正しく使いこなす力を育てる必要があります。
Copilotエージェントを“社内で本当に使える仕組み”にするために生成AI研修の資料をダウンロードして、導入を成功に導く第一歩を踏み出してください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
FAQ|Copilotエージェントに関するよくある質問
- QCopilotエージェントと通常のCopilotは何が違うのですか?
- A
通常のCopilotは「質問に答える」「提案を行う」といったアシスタント的役割に強みがあります。一方、Copilotエージェントは「目的達成のために複数のタスクを自律的に実行する」点が特徴です。言い換えると、Copilotが“会話パートナー”なら、エージェントは“業務代理人”といえます。
- QCopilotエージェントを利用するのにCopilot Studioは必要ですか?
- A
標準的な機能はそのまま利用できますが、業務に合わせたカスタマイズや独自エージェントを構築する場合は「Copilot Studio」が必要です。Studioを使うことで社内データや外部アプリと連携した高度なエージェントを設計できます。
- QCopilotエージェントは日本語に対応していますか?
- A
はい、日本語での利用が可能です。Microsoft 365アプリ(Outlook、Teams、Wordなど)ともシームレスに連携でき、日本語業務環境でも問題なく活用できます
- Q導入コストはどのくらいかかりますか?
- A
利用にはMicrosoft 365 Copilotのライセンスが必要です。さらにカスタムエージェントを構築する場合はCopilot Studioの追加利用料が発生することがあります。企業規模や導入範囲によってコストは変動するため、事前に見積もりを取ることが推奨されます。
- Qセキュリティ面で不安はありませんか?
- A
エージェントはMicrosoft Entra IDを活用した認証基盤上で動作するため、ユーザー権限に沿った範囲でのみ処理を行います。ただし、アクセス権の設計や利用ルールを誤ると情報漏洩リスクが高まるため、社内ポリシーの策定が欠かせません。
- Qどの業務から導入するのが効果的ですか?
- A
まずは「定型的で繰り返し発生する業務」から始めるのが成功の近道です。たとえば会議議事録の要約、FAQ対応、データ集計などは効果が見えやすく、社員も利便性を実感しやすい領域です。