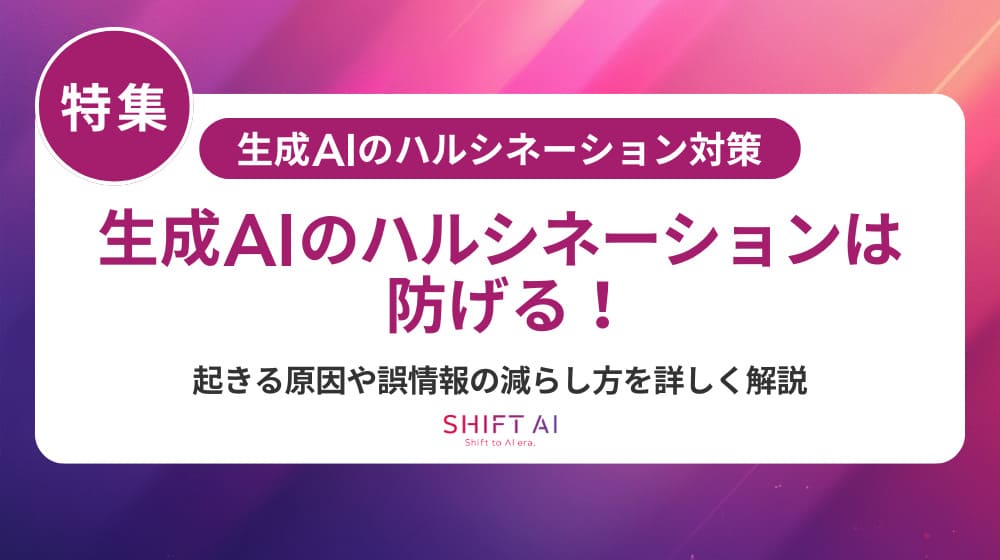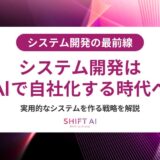ChatGPTを業務に取り入れる企業が増える一方で、避けられない課題として指摘されるのが「ハルシネーション(もっともらしい誤情報の生成)」です。
例えば存在しないURLを提示したり、実在しない法令や事例を引用したりと、誤った情報をあたかも事実のように回答するケースは珍しくありません。
もし業務でそのまま活用すれば、企業の信頼低下や法的リスクにも直結します。
そこで本記事では、ChatGPTのハルシネーションを抑制するための最新対策を整理します。
- なぜ誤情報が発生するのか
- 今すぐ実践できるプロンプト例と最新機能
- 企業で取り組むべき運用ルールや研修のポイント
これらを体系的に解説し、誤情報リスクを最小化しながら安心して業務活用できる方法をご紹介するのでぜひ最後までお読みください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
ChatGPTの「ハルシネーション」とは何か?
ChatGPTを使うと、もっともらしいが実際には誤った情報を返してくることがあります。これが「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、AI活用の最大のリスク要因のひとつです。
ハルシネーションの定義
ハルシネーション(hallucination)とは、生成AIが事実とは異なる情報を、あたかも正しいかのように生成してしまう現象を指します。
ChatGPTに限らず、大規模言語モデル(LLM)に共通する性質であり、「幻覚」「でっちあげ」と表現されることもあります。
この現象は「意図的な嘘」ではなく、AIが膨大なデータから統計的に最もらしい回答を導き出す仕組みの副作用です。
つまり、AIは“本当かどうか”を判断していないため、誤情報が紛れ込むリスクが常に存在します。
よくある誤情報の事例
実際にChatGPTで確認されている典型的なハルシネーションの事例には、以下のようなものがあります。
- 存在しないURLや論文を提示する
→ 研究や調査で引用すると大きな誤解を招く - 法律や制度を誤って説明する
→ 法務・コンプライアンス領域で致命的リスクに - 人物や企業に関する誤情報を生成
→ 風評被害や信頼性の毀損に直結 - 医療や製薬に関する不正確な説明
→ 健康被害や安全性リスクを生む可能性
このように、ハルシネーションは単なる誤回答にとどまらず、ビジネスや社会的信用に直結する重大なリスクを含んでいます。
詳細なリスク解説については、以下の記事もご覧ください。
生成AIのハルシネーションとは?企業導入で知るべきリスクと研修による効果的な対策方法
なぜChatGPTは誤情報を出してしまうのか
ChatGPTのハルシネーションは、単なるミスではなく仕組みに起因する必然的な現象です。原因を理解することで、効果的な対策を講じる第一歩となります。
確率的生成モデルの仕組み
ChatGPTは「文脈上もっともらしい単語」を統計的に選んで文章を組み立てています。
つまり「正しい情報かどうか」を判断しているのではなく、「次に来そうな単語」を選んでいるだけです。そのため、実在しないURLや架空のデータを自然に混ぜ込んでしまうことがあります。
学習データの偏りや不足
ChatGPTはインターネット上のテキストや公開データを学習しています。
しかし、学習データに存在しない情報や偏った内容しかない場合、AIが事実を正しく補えず誤った出力をしてしまいます。特に法律・医療・最新ニュースのような分野では注意が必要です。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
曖昧なプロンプト入力が誘発するケース
「具体的に条件を指定していない」「曖昧な表現で聞く」といったプロンプトでは、ChatGPTがもっともらしい回答を生成してしまう確率が上がります。
例えば「この法律について教えて」とだけ入力すると、存在しない法律名を挙げることすらあります。ユーザーの指示の仕方次第で、誤情報リスクは大きく変わるのです。
関連記事:ChatGPTのデメリットと対策|企業が陥りがちな失敗を生成AI研修で解決する方法
個人利用でもできるハルシネーション対策
ChatGPTを日常的に使う場合でも、ちょっとした工夫で誤情報を減らすことができます。
ここでは企業だけでなく個人ユーザーもすぐに実践できる、プロンプトの工夫や外部ツール併用のポイントを紹介します。
プロンプトの工夫で精度を高める
曖昧な質問は誤情報を誘発します。そこで、以下のような工夫が有効です。
- 「根拠や出典を明示してください」と指定する
- 「答えられない場合は“不明”と答えてください」と指示する
- ステップごとに回答させる(例:①前提の整理 → ②解答 → ③根拠)
これらの工夫により、ChatGPTの出力の曖昧さを減らし、検証可能な回答を得やすくなります。
コピペで使える実践プロンプト例
例えば以下のようなプロンプトを入れるだけで、ハルシネーションを抑制できます。
あなたは専門家として回答してください。必ず根拠や出典を示し、答えられない場合は“不明”と回答してください。
より詳しいテンプレートや応用例は以下の記事で解説しています。
ChatGPTのプロンプト完全ガイド|基礎から応用テンプレート・組織活用まで
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
外部リソースや検索連携の活用
ChatGPT単体に依存せず、外部の検索エンジンやRAG(Retrieval-Augmented Generation) を組み合わせることも効果的です。
マイクロソフトが開発した対話AI型検索エンジン「Bing」で最新の情報を参照すれば、誤情報のリスクを大幅に減らせます。
RAGは、ChatGPTが回答を生成する際に外部の検索結果やデータベースを参照しながら文章を組み立てる仕組みです。
- Retrieval(検索):まず外部の情報源(Web検索、社内ナレッジベース、論文データベースなど)から関連する情報を取得する
- Augmented Generation(拡張生成):取得した情報を参照しながらChatGPTが回答を生成する
ChatGPTの最新機能でできるハルシネーション抑制
近年のChatGPTは、単なる会話AIにとどまらず、誤情報を減らすための新機能や仕組みが続々と追加されています。ここでは最新機能を活用した具体的な対策を解説します。
「根拠を提示」オプションや検証モードの利用
最新モデルでは「根拠を提示する」オプションが提供されており、AIが回答の背景にある情報源や理由を明示できるようになっています。
これにより、回答の信頼性をユーザー自身が確認できる仕組みが整いつつあります。
RAG(検索補強)の導入
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、外部データベースや検索結果を参照しながら回答を生成する手法です。これにより、ChatGPTが持たない情報も補完でき、誤情報の可能性を大幅に減らせます。
特に企業では、自社のナレッジベースを組み合わせることで、組織固有の正確な情報を反映した回答が可能になります。
ファインチューニング・カスタム知識ベース活用
ChatGPTをそのまま使うのではなく、業務に合わせてファインチューニングしたモデルやカスタム知識ベースを利用することも有効です。
法務部門であれば最新の法令データを組み込む、営業部門であれば自社製品情報を学習させるといった形で利用すれば、誤情報を最小化しつつ現場に即した活用が実現します。
企業でChatGPTを活用する際に必要なハルシネーション対策
企業全体での安全な活用は、個人利用の工夫だけでは難しいのが現実です。組織としてChatGPTを導入する際には、ルールづくりと体制整備を行ないましょう。
AI利用ガイドラインの策定
企業でのAI活用において最初に必要なのは、利用範囲と禁止事項を明文化したガイドラインです。
例として、法務・医療など高リスク領域では利用を制限する、生成物は必ず人間の確認を経て使用するといったルールを定めることでリスクを最小化できます。
人間によるレビュー体制の整備
生成AIの回答は、そのまま業務成果物として使用してはいけません。
必ず人間によるレビューや承認プロセスを設けることで、誤情報によるトラブルを未然に防げます。
特に法務文書や対外資料などは、専門知識を持つ人材が必ず確認する仕組みが求められます。
利用用途の切り分け
ChatGPTの強みは「アイデア発想」や「文章生成」ですが、正確な事実確認や統計データの参照には不向きです。
創造系タスクと正確性が必須のタスクを切り分けることで、ハルシネーションによるリスクを抑えられます。
関連記事:ChatGPTを社内導入するには?失敗しない進め方と定着の仕組みを徹底解説
業界別リスクと具体的な対策例
ChatGPTのハルシネーションは、利用する業界や業務領域によってリスクの深刻度が異なります。ここでは代表的な業界ごとのリスクと対策を整理します。
法務(誤引用・判例捏造のリスク)
法務領域では、ChatGPTが存在しない判例や誤った法令条文を生成するケースが報告されています。
これをそのまま契約書や顧客への説明に使えば、企業の信頼を損ね、法的トラブルに直結しかねません。
生成AIはあくまで補助とし、法務専門家によるレビューを必須化する
医療・製薬(安全性リスク)
医療や製薬業界では、誤った診断補助や存在しない研究論文の引用が発生する危険性があります。これは患者の安全や企業のレピュテーションに直結する重大リスクです。
RAGを用いて信頼できる論文データベースと連携させるほか、医師・薬剤師による最終確認を欠かさない体制をつくる
教育・社内研修(誤情報による学習阻害)
教育や研修の場で誤情報が提示されると、受講者が誤った知識をそのまま覚えてしまうリスクがあります。特にAIリテラシー研修では正確性が求められるため注意が必要です。
教材作成段階で複数の情報源で検証し、AIが生成した情報には必ず正誤確認を加えるプロセスを導入する
製造・IT(仕様誤認によるトラブル)
製造やIT分野では、存在しないAPI仕様や間違った手順を生成するケースがあります。これにより開発の遅延や品質事故につながる恐れがあります。
自社の公式ドキュメントや技術ナレッジベースをAIと連携させることで、誤情報を排除しつつ効率的に業務に活用する
関連記事:生成AIのハルシネーション対策|企業が実践すべきリスク回避から研修まで徹底解説
研修で身につけるハルシネーション対策スキル
ハルシネーションを完全に防ぐことはできません。だからこそ、社員一人ひとりが適切にAIを扱えるリテラシーを身につけ、組織全体でリスクをコントロールすることが不可欠です。
社員に求められるAIリテラシーの必須ポイント
研修ではまず、AIが「万能な答え製造機ではない」という理解を浸透させます。
- AIの仕組みと限界を理解する
- 誤情報を前提にチェックする習慣を持つ
- 「そのまま使わず、人間が検証する」姿勢を徹底する
この基礎リテラシーが、誤情報による重大リスクを防ぐ第一歩になります。
研修で学べる実践的スキル
実際の研修プログラムでは、以下のようなスキルを実践形式で習得できます。
- ハルシネーションを減らすプロンプト設計
- 出力内容を検証するためのチェックリストの活用
- 自社のナレッジベースを連携させる運用ルールづくり
これにより、現場で即活用できる実務直結型スキルを身につけられます。
全社的なAIリスクマネジメントとの関係
個人のスキル習得だけでなく、全社的な運用ルールとの連携も研修の重要テーマです。
例えば「利用禁止領域」「承認フロー」「レビュー体制」といった仕組みを理解することで、組織として誤情報リスクを最小化する文化が根付きます。
まとめ|ChatGPTの誤情報は“ゼロ”にできない。だからこそ組織的対策を
ChatGPTのハルシネーションは、仕組みに起因するため完全に防ぐことはできません。
しかし原因を理解し、個人の工夫・最新機能の活用・企業の運用ルールと研修を組み合わせることで、誤情報リスクを大幅に低減できます。
本記事で解説したように、
- 個人レベルではプロンプト設計や外部リソース活用
- 企業レベルではガイドライン策定や人間によるレビュー体制
- 全社浸透のための研修によるリテラシー強化
これらを体系的に整えることが、生成AIを安全に業務へ活かすための最短ルートです。
加えて、社員一人ひとりのスキル強化が欠かせません。当社が提供する「生成AI研修」ではハルシネーション対策をはじめ、業務で再現性高く活用するための具体的な方法を体系的に学べます。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
ChatGPTのハルシネーション対策に関するよくある質問
- QChatGPTのハルシネーションを完全に防ぐことはできますか?
- A
完全に防ぐことはできません。ChatGPTは確率的に文章を生成する仕組みのため、誤情報をゼロにするのは不可能です。ただし、プロンプト設計・外部データとの連携・人間によるレビューを組み合わせることで、発生率を大幅に下げることができます。
- Q「ハルシネーションしないで」と指示すれば効果はありますか?
- A
限定的な効果はありますが、十分ではありません。「ハルシネーションを避けて」と指示すると、回答のトーンが慎重になる場合はありますが、誤情報そのものをなくすことはできません。根拠提示や出典参照を求めるなど、より具体的な指示が必要です。
- QChatGPTの回答を社内で共有する際に注意すべきことは何ですか?
- A
そのまま共有せず、必ず人間による事実確認を挟むことが重要です。特に法務・医療・経営判断に関わる情報は誤りが致命的になるため、社内ルールとしてチェックフローを明文化すると安心です。
- QChatGPTのハルシネーションは最新モデルでも発生しますか?
- A
はい。最新モデルでも仕組み上ゼロにはできません。ただし、根拠提示モードや外部検索との連携を活用することで、従来よりも精度の高い情報が得られるようになっています。
- Qハルシネーション対策を簡単に社内に浸透させる方法はありますか?
- A
まずは「AIは事実を保証しない」という前提を全社員に理解させることです。その上で、短時間のAIリテラシー研修やチェックリストの配布など、現場ですぐ使える形に落とし込むと浸透しやすくなります。