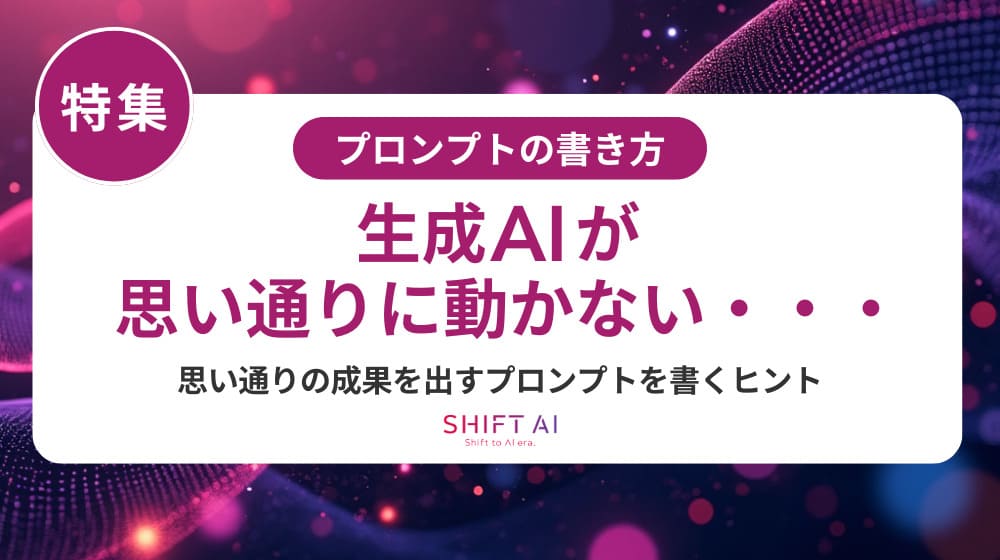「ChatGPTを使っているけれど、思ったような答えが返ってこない」「もっと効率的に成果を出せる方法はないのか」。そんな悩みを持つビジネスパーソンは少なくありません。実は、ChatGPTの出力精度や活用効果の大部分は「どんなプロンプト(指示文)を入力するか」で決まります。
しかし、いざ調べてみると「例文は多いけれど業務に直結しない」「フレームワークは知っていても実務に落とし込めない」と感じた方も多いのではないでしょうか。
本記事では、すぐに使えるChatGPTプロンプト例とともに、成果を出すための書き方のコツ、さらに深津式・ReAct・ゴールシークといった代表的なフレームワークまで徹底解説します。さらに、SEOライティングや文章作成、議事録や報告書の効率化など、BtoB業務で役立つ具体的な活用事例も紹介。
最後には、単なる個人のスキル習得にとどまらず、社内全体で生成AIを定着させるための研修ノウハウもあわせて解説します。
こちらもおすすめ:生成AIプロンプトとは?正確な回答を引き出す書き方・成功事例・研修導入のポイント
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
ChatGPTプロンプトとは?基礎から理解する
ChatGPTを効果的に活用するうえで欠かせないのが「プロンプト(指示文)」です。入力する言葉の違いだけで、出力結果の精度や活用範囲が大きく変わるため、まずはその基本をしっかり理解しておきましょう。ここでは、プロンプトの定義と役割、そして成果を分けるポイントを順に解説します。
プロンプトの定義と役割
プロンプトとは、ChatGPTに「どんな役割を担い」「どのような形で答えてほしいか」を伝えるための指示文のことです。単なる質問文ではなく、条件や制約、出力形式を含めた設計図として機能します。
たとえば「レポートを書いて」と指示するよりも、「あなたは人事コンサルタントです。300字程度で人材育成の最新トレンドをまとめてください」と入力する方が、はるかに業務に使える答えを得られます。つまり、プロンプトはAIを単なる会話相手から実務に役立つパートナーへと変えるための鍵なのです。
なぜ成果がプロンプト設計で変わるのか
同じChatGPTでも、入力の仕方によって「浅い回答」と「深い考察」が出力されます。これは、AIが文脈をどのように理解し、出力の幅をどう調整するかがプロンプトに依存しているからです。
- 曖昧な指示 → 回答も表面的になりやすい
- 具体的な制約や条件を提示 → より精緻な、業務に直結する答えが得られる
この違いを理解することで、思った通りの出力が出ないという悩みを根本から解消できます。
基本の型(命令+前提+制約+出力形式)
成果につながるプロンプトには、一定の共通パターンがあります。
- 命令:何をしてほしいのかを明確に伝える
- 前提:背景情報や状況を補足する
- 制約:文字数や語調、対象読者などを指定する
- 出力形式:箇条書き、表、レポートなど希望する形式を明示する
この4つを組み合わせることで、ChatGPTはユーザーの意図を的確に理解し、業務に使える品質の高い出力を返せるようになります。次章では、この型を実際の活用シーンにどう落とし込むかを見ていきましょう。
ChatGPTプロンプトの書き方|成果を出す4つのコツ
プロンプトは「なんとなく入力する」だけでは十分な成果を引き出せません。業務に直結する答えを得るには、設計の精度を高める工夫が欠かせないのです。ここでは、数あるテクニックの中でも特に効果が大きい4つのコツを紹介します。
役割を明確に指定する
ChatGPTは「誰の視点で答えるか」によって出力の質が大きく変わります。たとえば「営業担当者として」「経営コンサルタントとして」といった役割を指定するだけで、回答が専門性を帯び、実務にすぐ使える内容になります。
役割指定は単なる飾りではなく、AIに思考の方向性を与える重要な要素です。
出力形式や粒度を具体的に伝える
人間同士の会話と違い、AIは「どのようにまとめるか」を自動では判断できません。「箇条書きで」「表形式で」「300文字程度で」など出力形式や粒度を指定することで、求める形に最短でたどり着けます。
これは単なる見やすさのためではなく、そのまま業務文書に転用できる精度を担保するための工夫でもあります。
前提条件を提供する(背景情報・制約条件)
AIはゼロから正解を推測するのが得意ではありません。むしろ、背景や制約を与えた方が、精度は飛躍的に高まるのです。
たとえば「中小企業の人事担当者向けに」「最新の統計を踏まえて」と条件を補足すれば、回答は具体性を増し、現場でそのまま活用できるレベルに近づきます。
タスクを段階的に指示する(ステップバイステップ)
複雑な依頼を一度に投げると、回答が散漫になりがちです。そこで有効なのが「ステップごとに指示を出す」方法です。
- まずは要点を整理させる
- その後に詳細化を依頼する
- 最後に形式や文体を整える
この流れを意識することで、ChatGPTは人間の思考プロセスに近い形で作業を進め、精度の高いアウトプットを返してくれます。
以上の4つを意識するだけで、ChatGPTの回答は大きく変わります。
【用途別】すぐに使えるChatGPTプロンプト例
ここからは、日々の業務で役立つ具体的なプロンプト例を紹介します。「何のために使うのか」という用途に合わせて整理することで、読者は自分の状況に最も近いものをすぐに試せるようになります。
SEOライティングで使えるプロンプト例
記事執筆や構成作成は、ChatGPTの得意分野のひとつです。ただし、曖昧に「SEO記事を書いて」と頼んでも思った成果は出ません。
例文
あなたはSEOに詳しいWebライターです。
指定のキーワードを使い、検索意図に沿った見出し構成案を作ってください。
条件
- H2とH3を含む構成
- 導入文は100〜150字で
- 競合記事との差別化ポイントも提示
これにより、ただの文章生成ではなく、検索上位を狙える構成案が即座に得られます。
文章作成・要約・校正のプロンプト例
メールやレポートなど、日常的に発生する文章業務にもChatGPTは有効です。特に「要約」や「校正」は、作業時間を大幅に削減できます。
例文
あなたはビジネス文書の校閲者です。
以下の文章を200文字程度に要約し、敬語表現を整えてください。
【本文】:~~~~
単なる短縮ではなく、「トーンを整える」「目的に合わせる」まで反映されるため、社内外にそのまま出せる品質の文章になります。
業務効率化(議事録作成・メール文・報告書)のプロンプト例
議事録や日報の作成は、多くのビジネスパーソンが頭を悩ませる業務です。ChatGPTを使えば、情報整理と定型フォーマット化を一気に自動化できます。
例文
あなたは経営企画部のアシスタントです。
以下の会議メモを基に、議題ごとに整理した議事録を作成してください。
条件
- 箇条書きで簡潔に
- 決定事項と宿題を明確に分ける
この形式で依頼することで、会議直後に配布できるレベルの完成度を実現できます。
アイデア出し・ブレストに役立つプロンプト例
新規企画や商品開発で求められる「アイデア出し」も、ChatGPTの強みです。特に多角的な視点を加えたいときに効果を発揮します。
例文
あなたはイノベーションコンサルタントです。
テーマ「社員教育を効率化する新しい仕組み」に対して、5つのアイデアを提案してください。
条件
- 現場で実現可能な内容
- メリットとデメリットをセットで提示
思考の幅を一気に広げられるため、ブレストのたたき台づくりに最適です。
これらのプロンプト例を活用すれば、業務の質とスピードを同時に引き上げることができます。ただし、単発での利用だけではなく、フレームワークに沿って設計することでさらに安定した成果を得ることが可能です。次は、代表的なプロンプト設計フレームワークを見ていきましょう。
代表的なプロンプト設計フレームワーク
プロンプトは「ただの例文」だけではなく、設計の型(フレームワーク)を理解しておくことで、あらゆる業務に応用できるようになります。ここでは代表的な3つのフレームワークを紹介します。
深津式プロンプト(役割+制約+出力条件)
深津式は、日本のデザイナー深津貴之氏が提唱した有名な型です。特徴はシンプルでありながら応用範囲が広い点にあります。
- 役割指定:「あなたは〇〇の専門家です」
- 制約条件:「〜の条件で、〜文字以内で」
- 出力指定:「表形式で」「箇条書きで」
この3つを組み合わせるだけで、業務利用に十分耐えうる精度が得られます。特にBtoB文書やSEO記事の構成作成に強みを発揮します。
ReAct式プロンプト(思考と行動を分離する)
ReAct(Reason + Act)は、ChatGPTに「考える」と「答える」を分けて処理させる手法です。曖昧な依頼をした際にありがちな“表面的な回答”を避け、より論理的で実務的な出力を引き出すことができます。
例「まずはステップごとに考えを整理し、その後に最終回答を提示してください」
これにより、AIは中間的な思考プロセスを踏んでから答えるため、抜け漏れが少なく、再利用性の高い成果物になります。
ゴールシーク式プロンプト(ゴールから逆算する)
ゴールシークは、「最終的にどんな成果を得たいか」から逆算してプロンプトを設計する手法です。
たとえば「経営層に提出する3ページの提案資料を作りたい」というゴールを先に示すと、ChatGPTはその目的を踏まえた出力を返すようになります。
この手法は特に、経営企画や新規事業の企画書づくりなど、完成物に明確な要件がある場面で力を発揮します。
深津式・ReAct・ゴールシークはいずれも有効なフレームワークですが、重要なのは「どれを選ぶか」ではなく業務に合わせて使い分けることです。
BtoB業務でのChatGPTプロンプト活用事例
ここまで紹介してきたプロンプト例やフレームワークを、実際のビジネスにどう落とし込むのか。ここでは、法人企業で特に効果を発揮する3つの活用領域を取り上げます。単なる効率化にとどまらず、組織全体で成果を生み出すヒントとしてご覧ください。
人材育成・研修での活用
教育コンテンツの作成やケーススタディの設計は、人事部門にとって負担の大きい業務です。ChatGPTを活用すれば、短時間で研修資料のドラフトを作成でき、担当者は内容の精査や補強に集中できます。
プロンプト例「あなたは人材開発の専門家です。新入社員向けに“生成AIの基本概念”を分かりやすく説明する研修資料の構成案を作成してください。」
この活用は研修の質を高めつつ、準備時間を半減させる効果があります。
関連記事:「生成AIプロンプト研修とは?ChatGPT活用を成功させる方法と実践事例」
社内ドキュメント・マニュアル整備
マニュアルや業務フローの整備は、多くの企業で「更新が追いつかない」課題になっています。ChatGPTを活用すれば、既存の資料を整理・要約し、標準化されたマニュアルに落とし込むことが可能です。
プロンプト例「あなたは業務改善コンサルタントです。以下の社内手順メモを、誰でも理解できる標準マニュアルに再構成してください。条件:①手順を箇条書きで②新人でも理解できる表現で。」
これにより、属人化しやすいナレッジを組織全体で共有できる形に変えられます。
関連記事:「生成AIプロンプトを社内共有する方法|失敗しない仕組みと成功事例」
営業資料・提案書作成の効率化
営業担当者にとって提案書作成は時間を奪われる業務です。ChatGPTを活用すれば、顧客ごとのニーズに合わせた提案書のドラフトを短時間で生成できます。
プロンプト例「あなたは法人営業のプロです。以下の顧客情報に基づき、3ページ以内の提案資料のアウトラインを作成してください。条件:①課題→解決策→効果の順②専門用語は最小限に。」
こうした活用により、提案準備にかかる工数を削減し、顧客対応や戦略立案に時間を回せるようになります。
関連記事:「コード生成AIの使い方を徹底解説!初心者向け手順・ツール比較・実践活用法」
このように、ChatGPTプロンプトは単なる便利ツールではなく、研修・ナレッジ共有・営業支援といったBtoBの重要領域に直接的な価値をもたらすことができます。
プロンプト設計でよくある失敗と解決策
ChatGPTを使う際、多くの人がつまずくのが「プロンプト設計の甘さ」です。便利なはずのツールも、誤った使い方をすれば期待通りの成果は出ません。ここでは、特にありがちな失敗例とその解決策を整理します。
曖昧な指示で期待外れの出力になる
失敗例:「レポートを作って」など漠然とした依頼をする→ 結果:表面的で使いづらい回答になる
解決策:役割や条件を明確に与える
例「あなたは経営コンサルタントです。300文字以内で人材育成の最新動向をまとめてください」
このように具体化すれば、現場でそのまま活用できるレベルの出力が得られます。
情報漏洩リスクを意識していない
失敗例:顧客情報や機密データをそのまま入力してしまう→ 結果:セキュリティリスクが高まり、社内利用が禁止されるケースも
解決策:情報は必ず匿名化・抽象化する
加えて、社内で「利用ルール」や「研修」を設けることでリスクを抑えられます。生成AIを社内で安全に活用する仕組みづくりが欠かせません。
社内で定着しない(属人化・教育不足)
失敗例:一部社員だけが試験的に使い、他の社員にノウハウが広がらない→ 結果:効率化の効果が限定的で、組織全体では成果が出ない
解決策:プロンプトの共有フォーマットを作る/教育を仕組み化する
研修を通じて「全社員が共通の型で活用できる状態」にすることが、長期的な成果につながります。
これらの失敗は、いずれも「個人頼み」で運用していることが原因です。プロンプトを社内に定着させ、全社で活用できる仕組みを整えることこそが本質的な解決策です。
SHIFT AIでは、こうした課題を解決するための「生成AI研修」を提供しています。実際の業務に即したプロンプト例を学び、社内展開まで仕組み化する方法を解説した資料をご用意しています。
まとめ:プロンプト例は“入口”、本質は「仕組み化」と「教育」
ここまで、ChatGPTで成果を出すためのプロンプト例やフレームワーク、そしてBtoB業務に役立つ実践事例を紹介してきました。重要なのは、プロンプト例を知ること自体がゴールではないという点です。
確かに、例文をコピペすれば一時的に便利さは感じられるでしょう。しかし、それだけでは「個人スキル」にとどまり、組織全体としての成果にはつながりません。
本当に成果を出すには、次の2つが欠かせません。
- 仕組み化:社内で標準化されたプロンプト活用ルールを作ること
- 教育:社員一人ひとりが自信を持って生成AIを使えるようになること
この2つを組み合わせてこそ、ChatGPTは「一部の便利ツール」ではなく、企業全体の競争力を底上げする仕組みへと進化します。
SHIFT AIでは、法人研修を通じてこうした課題を解決しています。
- 実務に直結するプロンプト設計を学べる
- 業務シーンに合わせたユースケースをカスタマイズできる
- 社内展開を見据えた研修設計で、属人化を防げる
下記から資料をダウンロードしていただければ、研修の具体的なプログラム内容や成功事例をご確認いただけます。
ChatGPTのプロンプトに関するFAQ(よくある質問)
- QChatGPTのプロンプトは無料で使えますか?
- A
ChatGPT自体は無料版でも利用可能ですが、高精度な回答を求める場合は有料プラン(ChatGPT Plus)の利用がおすすめです。無料版では制限が多く、業務利用では物足りないケースもあるため、目的に合わせて選びましょう。
- Qプロンプトはどのくらい具体的に書く必要がありますか?
- A
「背景情報・役割・出力条件」の3点が明確であることが最低条件です。曖昧な依頼では表面的な回答しか得られませんが、条件を具体化すれば業務にそのまま使える出力が得られます。
- QChatGPTを業務で使うときに注意すべき点はありますか?
- A
最大の注意点は情報漏洩リスクです。顧客情報や機密データをそのまま入力することは避けましょう。匿名化・抽象化した情報で依頼するのが基本です。さらに、企業としての利用ルールや研修体制を整備することが不可欠です。
- Qプロンプト例は他部署やチームでも共有できますか?
- A
もちろん可能です。ただし、個人が独自に作成したものをそのまま共有すると品質がばらつき、逆に混乱を招く場合もあります。社内標準のフォーマットを決め、教育とセットで共有することで、全社的な効率化が実現します。
👉関連:「生成AIプロンプトを社内共有する方法|失敗しない仕組みと成功事例」
- Q社内でのプロンプト教育はどのように始めればいいですか?
- A
最初は「代表的なフレームワーク(深津式・ReAct・ゴールシーク)」を社内研修で共有し、共通言語を作ることから始めるのがおすすめです。SHIFT AIの研修では、こうした基礎から業務活用まで体系的に学べます。