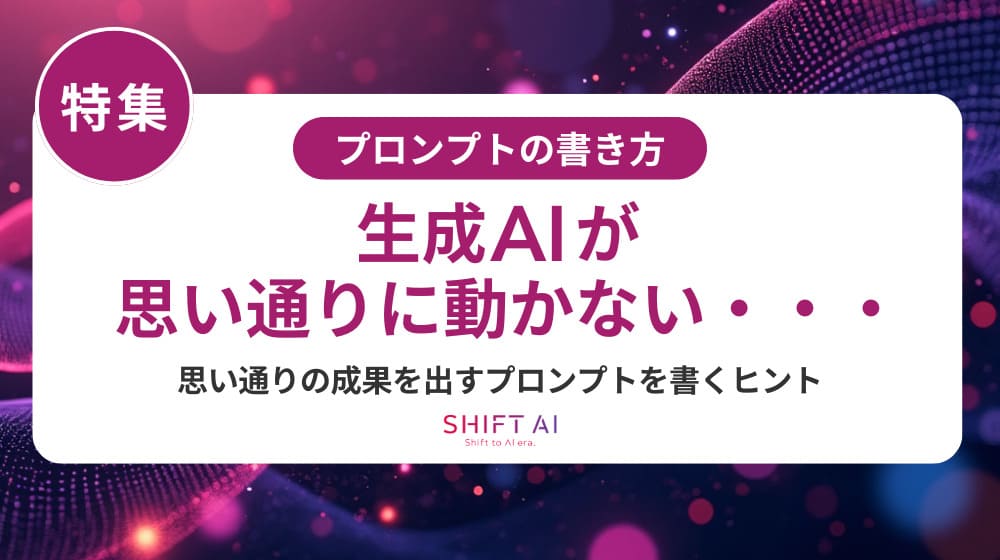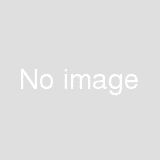生成AIを使いこなすうえで欠かせないのが「プロンプト(指示文)」です。
同じ質問をしても、書き方ひとつで結果がまったく変わる──これはChatGPTやGeminiなど、どんなAIでも共通する原則です。
とはいえ「具体的にどう書けばいいのか」「どんなプロンプトが効果的なのか」と悩む方は少なくありません。
本記事では、目的別にそのまま使えるプロンプト例と、成果を引き出す書き方のコツを徹底解説します。
さらに、他サイトではあまり語られない“業務で使う”ための工夫や改善のプロンプト術まで紹介。
個人のアイデア出しだけでなく、社内研修・ナレッジ共有にも活かせる内容です。
「生成AIの力を、チーム全体の生産性に変える」。
そんな一歩を踏み出したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AIの「プロンプト」とは?意味と重要性を理解する
生成AIを動かすための“指示文”をプロンプト(Prompt)と呼びます。
「何を」「どのように」「どんな形式で」出力してほしいかを伝える文章であり、AIにとっては思考のスタート地点です。
人間でいえば「依頼書」や「設計図」にあたるものと言えるでしょう。
近年の生成AIは高精度ですが、万能ではありません。
同じテーマでも、プロンプトの書き方ひとつで出力内容の質が大きく変化します。
たとえば曖昧な指示では一般論しか返ってこず、明確な指示では具体的で使える成果物を得られます。
なぜプロンプトの質が成果を左右するのか
生成AIは文脈や目的を推論して応答を作ります。
そのため、曖昧な言葉や条件不足があると、AIは“推測”で補ってしまい、意図から外れた出力をしてしまうのです。
一方、前提・目的・形式を具体的に伝えるほど、AIはより的確にゴールへ導かれます。
つまり、AIの出力精度は「質問力(=プロンプト設計力)」で決まる。
この考え方は、ビジネスの現場でも非常に重要です。
業務マニュアル作成・報告書作成・研修教材づくりなど、生成AIが支援する領域は広がっていますが、最終的な成果物の質は“どう聞くか”にかかっています。
「曖昧な指示」と「明確な指示」で出力はこう変わる
| 指示の種類 | プロンプト例 | 出力傾向 |
| 曖昧な指示 | 「プレゼン資料の作り方を教えて」 | 一般的な流れのみ。実践では使いにくい。 |
| 明確な指示 | 「新入社員向けに、社内プレゼン資料作成の基本ステップを5項目で整理し、各項目に注意点を1行ずつ添えてください。」 | 具体的・実務で使える内容。再利用性が高い。 |
同じテーマでも、明確なプロンプトほどAIが“理解の軸”を持ち、ブレの少ない出力を返します。
これは「AIに考えさせる」のではなく、「AIを導く」という姿勢の違いです。
[例文比較]良いプロンプト/悪いプロンプト
悪いプロンプト
「マーケティング戦略を考えて」
良いプロンプト
「中小企業がSNSを活用して認知度を高めるためのマーケティング戦略を、3つの段階(調査→実行→検証)に分けて整理してください。」
前提・目的・構造・出力形式を明示すると、AIは“どの方向に考えるか”を理解できます。
この“思考の補助線”を引くことが、プロンプト設計の第一歩です。
さらに深く理解したい方へ
AIを的確に動かすには、単なる「書き方」だけでなく、設計思考(Prompt Design)が重要です。
→ AIを正確に動かす!プロンプトの設計5つの方法と業務別活用法
プロンプトの基本構造と書き方のコツ
生成AIに正確な指示を出すためには、プロンプトの構造を理解して書くことが重要です。
単に「質問する」だけでは、AIは文脈を補完できず、意図とは異なる回答をすることがあります。
以下の4要素を意識するだけで、出力の質は格段に変わります。
プロンプトの基本構造(目的+条件+出力形式+役割設定)
AIに伝える内容は、次の4つで整理するとわかりやすくなります。
| 要素 | 説明 | 例 |
| 目的 | 何をしたいかを伝える | 「新製品の紹介文を作成したい」 |
| 条件 | 制約や前提条件を指定する | 「ビジネス向けトーンで」「300文字以内」 |
| 出力形式 | どんな形で出してほしいかを明記 | 「箇条書き」「表形式」「見出し付き文章」 |
| 役割設定 | AIにどんな立場で考えてほしいか | 「あなたはマーケティングの専門家です」 |
これらを組み合わせると、次のような形になります。
例文:「あなたはマーケティングの専門家です。
新製品『AI経営ナビ』の紹介文を、ビジネス向けトーンで300文字以内、見出し付きで作成してください。」
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
コツ①:AIに「役割」を与える
AIは“人格”を持たないため、指示の解釈に幅が出ます。
そこで「あなたは〇〇の専門家です」と役割を与えることで、回答の軸を明確化できます。
たとえば同じ質問でも、次のように出力の質が変わります。
| プロンプト | 出力傾向 |
| 「会議のまとめを作成して」 | 単なる要約文。文体が定まらない。 |
| 「あなたは経営コンサルタントです。会議内容を経営層に報告する要約文を作成して」 | 重要ポイントを整理したビジネス文調の要約。 |
コツ②:「目的・前提・出力形式」を明示する
AIに期待する結果を具体的に伝えるほど、再現性が高まります。
特に「誰に」「何のために」「どの形式で」出すかを明示しましょう。
悪い例:「SNS投稿文を考えて」
良い例:「20代社会人向けに、AI研修を紹介するSNS投稿文を3案作ってください。
各案は100文字以内で、絵文字を使わずビジネスライクにしてください。」
出力形式を定義することで、社内でも再利用しやすくなります。
コツ③:曖昧語を避け、定量的に指示する
AIは「わかりやすく」「しっかり」「できるだけ」などの曖昧語を苦手とします。
これらを数値や条件に置き換えることで、意図した精度に近づけられます。
| 曖昧な指示 | 改善された指示 |
| 「わかりやすく説明して」 | 「専門用語を使わず、中学生にも理解できるように説明して」 |
| 「詳しく解説して」 | 「3つの観点から、各観点を200文字ずつ説明して」 |
コツ④:出力の粒度を指定する(文字数・フォーマットなど)
出力の粒度がバラつくと、使い勝手が悪くなります。
特に社内文書や資料作成では、「文字数」「構成」「フォーマット」を指定することで、整った結果を安定的に得られます。
例文:「以下の内容を200文字以内で要約し、タイトル・概要・結論の3段構成で出力してください。」
こうした指示をテンプレート化しておくと、チーム全体で“AI出力の品質”を一定に保つことが可能です。
コツ⑤:「改善依頼プロンプト」を使い、反復して精度を上げる
多くの人が“1回の質問で完結”させようとしますが、実際は反復的に改善を指示することが最も重要です。
これを「自己改善プロンプト」と呼びます。
たとえば──
1回目の出力を読んで「トーンが硬い」と感じたら、次のように伝えます。
改善指示例:「この内容を、より柔らかく親しみやすいトーンにリライトしてください。」
あるいは、出力の根拠を確認したいときは:
検証指示例:「上記回答の根拠や引用元の信頼性について説明してください。」
このように「評価→改善→再出力」を繰り返すことで、AIをチームメンバーのように育てることができます。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
目的別・そのまま使える生成AIプロンプト例集
生成AIをビジネスで活かすためには、「どんな場面で」「どんな目的で」使うかを整理することが大切です。
ここでは、現場で頻繁に登場する5つのシーン別に、そのまま使えるプロンプト例を紹介します。
すべてChatGPT・Gemini・Claudeなどの主要モデルで機能する構文になっています。
① 情報整理・要約に使えるプロンプト例
会議の議事録や長文レポートなど、情報を整理する作業は時間がかかるもの。
生成AIは「要約+分類+視点変換」が得意なため、指示を明確に出すだけで効率化できます。
活用シーン
- 議事録の要約
- 顧客アンケートの傾向分析
- 報告書の要点抽出
プロンプト例
「次の文章を3つのポイントで要約し、それぞれを『課題』『要因』『解決策』に分類してください。」
ポイント
- 「分類」を含めることで、単なる要約ではなく“意思決定に使える整理”が可能に
- 長文を複数視点で切る場合、「◯◯視点で」などの指定を追加するとさらに精度UP
② 企画・アイデア創出に使えるプロンプト例
新規事業や販促企画など、「0→1発想」が求められる業務にも生成AIは有効です。
ただし、抽象的な指示では凡庸なアイデアしか出ないため、「対象」「目的」「制約条件」を必ず入れましょう。
活用シーン
- 新商品・サービスの企画立案
- キャッチコピーやタイトル案出し
- 社内イベントや研修テーマ設計
プロンプト例
「中小企業向けに“生成AI研修”を告知するキャッチコピーを5案出してください。
トーンは信頼感があり、ビジネス層に響く内容にしてください。」
ポイント
- 「対象×目的×トーン」を指定すると汎用的な提案が“使える企画案”に変化
- 出力後に「さらに具体的に」「デジタルマーケ担当の視点で」など改善プロンプトを重ねると精度が上がる
③ マーケティング/広報向けプロンプト例
SNS投稿文・プレスリリース・顧客メールなど、“トーンと媒体に応じた表現調整”が必要な場面で効果を発揮します。
活用シーン
- 公式SNS投稿・PR文作成
- メルマガや社内報の文案
- 製品説明文のトーン調整
プロンプト例
「次の製品説明文をビジネス向けに、LinkedIn投稿用としてリライトしてください。
文章トーンは“落ち着いた専門性重視”で、140文字以内にまとめてください。」
ポイント
- 「媒体」「読者層」「文体」を指定することで出力がメディア最適化される
- 同一文を複数トーン(公式・カジュアル・教育的など)で生成させると社内比較にも便利
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
④ 営業・顧客対応で使えるプロンプト例
営業やカスタマーサポートは、最もプロンプトの再現性が高い分野です。
文章構成をテンプレート化すれば、提案資料やフォロー文の品質を一定に保てます。
活用シーン
- 提案資料の章立て作成
- 問い合わせメールの初期対応
- フォロー文・謝罪文・お礼文生成
プロンプト例
「顧客の課題が“業務効率化”のとき、提案資料の章立てを5項目で作ってください。
各項目には説明文を2行以内で添えてください。」
ポイント
- 「章立て+要約」構成は、AI出力の整理力を最大限に活かす定番形式
- この段階で作成した構成をもとに、後続の生成指示(例:“章1を300字で執筆”)を続けると精度が安定する
⑤ 人事・研修・教育で使えるプロンプト例
教育・人材育成分野では、生成AIが「教材作成」「ケーススタディ生成」「評価設計」などに活用できます。
特にAI研修設計との相性が高く、知識伝達型から“考える研修”への転換を促します。
活用シーン
- 新人・管理職研修教材の作成
- ケーススタディ・ディスカッション題材の生成
- 人事評価基準や行動指標の草案作成
プロンプト例
「新人研修向けに“AIの業務活用例”を説明するスライド構成案を出してください。
各スライドにタイトル・要点・発話メモを付けてください。」
ポイント
- “構成+要点+発話メモ”まで指定することで、研修設計を丸ごと自動化できる
- 複数パターンを生成して比較することで、講師資料の作成時間を短縮
実際にこれらのプロンプトを社内で体系的に使いこなすには、“研修設計”がカギになります。
個人のスキルに留めず、部門全体で共有できる形にすることで、生産性向上の効果が何倍にも広がります。
出力を改善するための“リビジョン・プロンプト”の使い方
生成AIの真価は、「一度の出力」で終わらせず、改善を重ねて精度を高めるサイクルにあります。
この改善の指示を行うプロンプトを「リビジョン・プロンプト(Revision Prompt)」と呼びます。
AIを“部下”や“共同編集者”のように扱う意識で、指示と評価を繰り返すことで、成果物の品質は格段に向上します。
「1回で終わらせない」プロンプト最適化サイクル
多くの利用者は、「質問 → 回答」で完結させてしまいます。
しかし実際の業務では、AIの出力を何度も磨き上げる工程こそが価値を生みます。
AIを使った改善の流れは、次のように整理できます。
| フェーズ | 目的 | 例文プロンプト |
| ①初期出力 | ベースとなる回答を作る | 「次の資料を要約し、経営層向けの報告文を作成してください。」 |
| ②評価・指摘 | 改善点をAI自身に考えさせる | 「上記回答の弱点を3つ挙げ、それぞれ改善案を提案してください。」 |
| ③リビジョン | 指摘を踏まえて再出力 | 「指摘された改善案を反映した改訂版を作成してください。」 |
| ④検証 | 信頼性・精度を確認 | 「出力に含まれる不確実な要素を箇条書きで説明してください。」 |
このように、「生成→評価→改善→検証」を一連の流れとして回すことで、AIを自己改善させる仕組みが完成します。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
改善のための再指示テンプレート例
出力を整える際には、改善の方向性を明確に伝えるのがポイントです。
以下のテンプレートをそのまま使えば、業務文書の精度を簡単に上げられます。
- 「上記の出力を、経営層向けに要約し、300文字以内に整えてください。」
- 「前回の出力を、新人研修向けにやさしい言葉で言い換えてください。」
- 「次の視点(コスト・リスク・実現性)で内容を再構成してください。」
- 「具体例を1つ追加し、説得力を高めてください。」
これらのように「誰に向けた・どの方向の改善か」を指示すると、AIは自己リライト能力を最大限に発揮します。
“ハルシネーション”を防ぐ検証プロンプト
AIがもっとも苦手とするのが、事実に基づかない回答(ハルシネーション)です。
特にビジネス文書では、誤情報が信頼を損ねるリスクがあります。
出力後に検証用のプロンプトを組み合わせることで、信頼性を確保できます。
検証プロンプト例
「あなたの回答に含まれる不確実な要素を箇条書きで説明してください。」
「回答内容のうち、根拠を示せない主張があれば指摘してください。」
「出力内の数値や事例の真偽を確認できる情報源を3つ提示してください。」
これにより、AIの“自信過剰な誤答”を自動であぶり出し、再現性のある信頼情報だけを残せます。
より詳しい検証手法は、こちらの記事も参考に
→ ハルシネーション対策プロンプト完全ガイド|誤情報を減らす設計・検証・教育の実践法
出力精度を高めるフィードバックループの構築
組織的に生成AIを活用する場合、リビジョン・プロンプトを共有化することで、チーム全体の生産性が向上します。
これは「プロンプトのPDCAサイクル」として機能し、社内ナレッジとして蓄積できます。
構築ステップ例:
- 各部門でよく使うプロンプト+改善プロンプトをテンプレート化
- 出力と修正版を社内共有ツールで比較
- “改善事例集”としてリビジョン履歴をストック
- 次回以降、最も成果の高い構文を再利用
このサイクルが確立すると、AIは「質問に答えるツール」から「組織知を磨く共同編集者」へと進化します。
業務別プロンプトの応用事例|社内展開に活かすポイント
生成AIを日常業務で定着させるには、「誰がどんな場面で使うか」を具体化することが重要です。ここでは、各部門で成果に直結する活用パターンを紹介します。
営業部門:顧客理解 × 提案書生成
顧客情報や過去の提案履歴を要約し、顧客課題に即した提案文案を自動生成。
たとえば「過去3回の商談メモをもとに提案書を要約・再構成」といったプロンプトで、提案スピードと内容の的確さが両立します。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
人事部門:研修・評価・採用原稿の自動化
研修計画の立案や評価コメント作成、採用広報原稿の初稿づくりなど、「考える」より「整理する」作業が多い人事業務とも好相性。
統一フォーマットでのプロンプト活用により、情報の抜け漏れや表現ブレを防げます。
管理部門:文書要約・報告書作成の効率化
社内報告や会議資料、メール文面などの文書整備にかかる時間を短縮。
「議事録を要約し、5項目で報告書を作成」などの定型プロンプトを共有すれば、担当者間の品質差を小さくできます。
社内ナレッジ化のポイント
生成AIの成果を一過性で終わらせないためには、ナレッジの蓄積と共有が欠かせません。
- 共有フォーマットの設計:部署横断で使えるテンプレート化
- AI利用ガイドライン整備:情報管理・倫理・精度チェックのルール策定
この2点を押さえることで、「個人が使うAI」から「組織が活用するAI」へと進化します。
“属人化しないプロンプト文化”の作り方
属人化を防ぐ鍵は、成功したプロンプトを全社で共有・再利用できる仕組み。
具体的には、成果を出した社員が使用したプロンプトをナレッジツールで共有し、改善を重ねる「社内プロンプトライブラリ」の構築が効果的です。
実際に成果を出す企業の特徴
AI活用が定着している企業に共通するのは、「スキル」ではなく「仕組み」に投資している点です。
研修を起点に業務別プロンプトを設計・共有し、現場での活用PDCAを回していく体制が整っています。
AI活用を個人スキルで終わらせないために──
社内全体で“使えるプロンプト”を共有する仕組みを作りませんか?
よくある失敗プロンプトと改善例
生成AIを使っても「思ったような回答が返ってこない」と感じる原因の多くは、プロンプトの設計ミスにあります。
ここでは、よくある失敗パターンと、成果につながる改善方法を具体例で見ていきましょう。
① 曖昧な指示:「分かりやすく説明して」
改善前プロンプト:
「この資料を分かりやすく説明して」
問題点:
「誰に」「どのように」分かりやすくするのかが不明。AIが意図を読み取れず、要点がズレやすくなります。
改善後プロンプト:
「この資料を、AIに詳しくない管理職向けに、3分で説明できる内容に要約してください」
ポイント:
対象者・目的・時間軸を指定することで、“分かりやすさの基準”が明確化します。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
② 情報過多:前提が多すぎて焦点がぼやける
改善前プロンプト:
「新規事業の説明資料を作りたい。市場動向、顧客分析、競合比較、SWOT、KPIも入れてスライド構成を考えて」
問題点:
複数要素を同時に要求しすぎると、AIが情報整理を優先して肝心の構成意図が埋もれます。
改善後プロンプト:
「新規事業説明資料の構成案を作りたい。まず“顧客分析”パートの見出し案だけを出してください」
ポイント:
段階的に依頼することで、AIの出力精度と一貫性が高まります。
③ 目的不明:「とりあえずまとめて」
改善前プロンプト:
「会議メモをとりあえずまとめて」
問題点:
“まとめる”目的(議事録なのか、報告書なのか)が不明確。出力形式も曖昧になります。
改善後プロンプト:
「会議メモを、上司への報告用に“3項目の要約+次のアクション”形式でまとめてください」
ポイント:
目的+形式を伝えることで、AIが期待するアウトプット像を正確に再現できます。
NGワード集:AIを迷わせるあいまい表現
| NGワード | 問題点 | 改善例 |
| 適当に | 意図が不明確で出力が不安定 | 「3案出して」など具体的に数を指定 |
| 自由に | AIの判断基準が揺れる | 「創造的に」「ユニークに」など方向性を指定 |
| ざっくり | 詳細度の判断が難しい | 「200字以内で要約」など条件を数値化 |
| 分かりやすく | 対象者・目的が曖昧 | 「初心者向けに」「経営層向けに」などを補足 |
| いい感じに | 感覚依存ワードで学習無効化 | 「営業資料として説得力のある形に」など具体化 |
プロンプト設計をチームで活用するには
生成AIを一部の社員だけが使う段階から、チーム全体で成果を出す段階へ移行するためには、プロンプト設計を“組織のスキル”として共有する仕組みが必要です。
社内テンプレート化とナレッジ共有の流れ
個人の試行錯誤に任せると、「誰がどのプロンプトを使っているか」が分からず、効果検証が進みません。
そこでおすすめなのが、次の3ステップです。
- 成功プロンプトをテンプレート化
─ 各部署で効果があったプロンプトを共通フォーマットで整理。
例:目的/入力例/出力例/改善メモを1セットに。 - ナレッジ共有ツールで公開
─ 社内ポータルやNotionなどで共有し、検索・再利用可能に。 - 定期レビューで更新
─ 月1回の“プロンプトレビュー会”を設け、改善サイクルを回す。
このプロセスを通じて、属人的なノウハウが「社内の知的資産」へと変わります。
教育・研修におけるプロンプト設計演習
プロンプトは座学では身につきません。
効果的な研修では、自社業務を題材にした設計・改善演習を取り入れます。
例:
- 営業チーム → 「顧客要望を踏まえた提案文の生成」演習
- 管理部門 → 「会議議事録から報告書を作成」演習
- 人事部門 → 「評価コメントを自動生成」演習
こうした実務ベースの演習を通じて、“現場で使える”プロンプト設計力が育ちます。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
生成AI研修の設計例(講義+演習+改善)
AI経営総合研究所が実施する法人向け研修では、以下の3ステップ構成を推奨しています。
| ステップ | 内容 | 狙い |
| 講義編 | 生成AIの仕組みと活用事例を理解 | 誤解をなくし、基礎リテラシーを統一 |
| 演習編 | 部署別プロンプト設計ワーク | 実務課題をベースにスキルを定着 |
| 改善編 | 共有+フィードバック+再設計 | PDCAで“使える形”に磨き上げ |
講義で理解し、演習で実践し、改善で仕組みに落とし込む。
この構成により、AI活用が「一過性のイベント」ではなく「現場の仕組み」として定着します。
現場で定着するためのPDCAサイクル
AI活用は導入して終わりではありません。
研修後も以下のPDCAを継続することで、成果が組織に根づきます。
- Plan(計画):活用テーマ・対象業務を明確化
- Do(実行):テンプレートに沿って実践
- Check(検証):出力結果と効果をレビュー
- Act(改善):プロンプトを修正し再共有
この循環を仕組み化できる企業ほど、AI導入のROI(投資対効果)が高まっています。
まとめ|良いプロンプトは「習慣化」と「共有」で成果が変わる
生成AIを業務に活かせるかどうかは、知識量ではなく「使い続け、改善を重ねる習慣があるか」で決まります。
一度作ったプロンプトを放置するのではなく、日々の業務で検証し、修正し、共有する。
この小さな積み重ねが、やがて組織全体の成果を変えていきます。
AI活用はもはや個人のスキル競争ではありません。
属人化を防ぎ、チーム全体で使いこなす時代へと進んでいます。
営業・人事・管理部門など、あらゆる領域でプロンプトが「共通言語」となれば、組織の生産性と意思決定の質が飛躍的に向上します。
まずは、日報作成や提案書要約など、身近な業務から一歩ずつ始めてみましょう。
AI活用の効果は、導入よりも“定着”にあります。
日常業務の中で「使う→見直す→共有する」文化を作ることが、長期的な成果への最短ルートです。
- Q良いプロンプトを作るコツは何ですか?
- A
最も重要なのは「目的・対象・出力形式」を明確にすることです。
「何のために」「誰向けに」「どんな形で出したいか」をセットで伝えると、AIが意図を正確に理解しやすくなります。
たとえば「新人研修の概要を管理職向けに3分で説明できる要約にして」といった形が効果的です。
- Qプロンプトを社内で共有すると、情報漏えいのリスクはありませんか?
- A
外部への情報送信を制限した社内環境(社内限定AIツールやセキュアなチャット環境)で共有すればリスクを最小化できます。
また、社内ガイドラインで「入力してよい情報の範囲」を明確化しておくこともポイントです。
- Q生成AI研修ではどんなことを学べますか?
- A
AI経営総合研究所の研修では、基礎知識の講義に加えて、実際の業務を題材にしたプロンプト設計演習を行います。
その場で出力結果を比較・改善しながら、チームでAIを活用するための“再現性のある型”を身につけます。
- Qプロンプトをチームで使うメリットは何ですか?
- A
一人の成功体験を全員で再現できるようになる点です。
属人化が減り、業務の品質が均一化されるほか、改善のスピードも組織全体で加速します。
テンプレート化やナレッジ共有がその基盤となります。AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
- QAI活用を社内で定着させるには、まず何から始めればいいですか?
- A
いきなり全社導入を目指すより、1つの業務テーマを選び、小さく試すことが最適です。
たとえば「議事録の要約」「提案書のたたき台作成」など、成果が見えやすい領域からスタートすると、社内理解が得やすくなります。