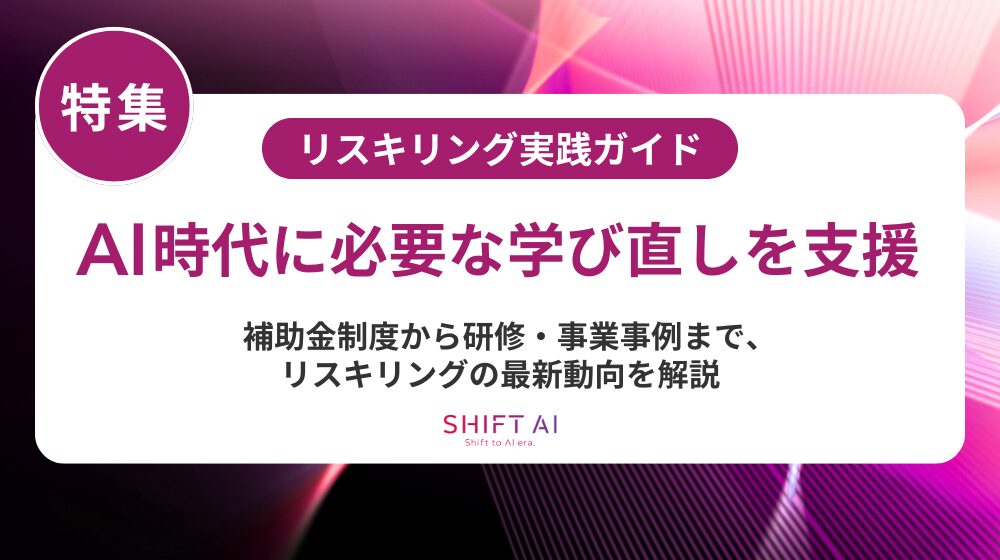DXや生成AIの普及により、企業も個人も「学び直し=リスキリング」が避けられない時代になっています。
しかし、研修や教育には費用がかかり、「コストが重荷になり実施できない」という声も少なくありません。
こうした課題を解決するために、政府や自治体は 補助金・助成金制度 を整備し、リスキリングを強力に後押ししています。
例えば、厚生労働省の「人材開発支援助成金」や、経済産業省の「キャリアアップ支援事業」など、デジタルスキルや生成AI研修に特化した支援も登場しています。
本記事では、2025年版の最新制度を網羅的に紹介するとともに、
- どんな企業・個人が対象になるのか
- 申請の流れや必要書類
- よくある失敗と注意点
を整理して解説します。
補助金を上手に活用すれば、リスキリングは「負担の大きな出費」から「将来の投資」へと変わります。
まずは自社・自分が対象になる制度を確認し、最適な学び直しをスタートしましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜリスキリングに補助金・助成金が用意されているのか
リスキリングを支援する補助金・助成金は、単なる福利厚生ではなく、日本の社会課題と産業競争力に直結した政策です。
DXや生成AIの進展、少子高齢化による人材不足などを背景に、国は「人への投資」を成長戦略の中心に据えています。ここからは、補助金制度が整備される理由を3つの観点から解説します。
DX・生成AIの普及でスキルの陳腐化が加速
テクノロジーの進化はこれまで以上のスピードで進んでいます。特にDX推進や生成AIの普及により、従来の業務スキルは短期間で陳腐化する傾向があります。
企業が競争力を維持するためには、社員が新しいデジタルスキルを身につける「リスキリング」が欠かせません。
少子高齢化による人材不足 → 政府が「人への投資」を成長戦略に据える背景
日本は少子高齢化により労働人口が減少し、人材不足が深刻化しています。新規採用だけでは補えず、既存社員のスキルアップ・スキル転換が国家的な課題となっています。
このため政府は成長戦略の柱に「人への投資」を掲げ、予算を投じてリスキリングを支援しています。
補助金・助成金を使うことで、企業の学び直しの負担を軽減できる
研修や教育はコストがかかりますが、補助金・助成金を活用すれば企業・個人の負担を大きく抑えることが可能です。これにより「費用がネックで研修を実施できない」という企業でも、実現性が高まります。
リスキリングそのものの意義や背景については、リスキリングとは?意味・背景・企業導入のメリットと成功ポイントを徹底解説 で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
リスキリングに使える代表的な補助金・助成金【2025年版】
リスキリングを進めるにあたり、費用面を大きく支援してくれるのが各種補助金・助成金制度です。ここでは、2025年時点で注目すべき代表的な制度をまとめます。厚労省・経産省の全国制度から、地域ごとの独自支援まで網羅的に紹介します。
厚労省「人材開発支援助成金」
最も広く活用されている制度が、厚生労働省の「人材開発支援助成金」です。
- 対象分野:デジタルスキル、資格取得、専門研修、リスキリング全般
- 助成内容:受講費用(経費助成)+研修中の賃金の一部を助成
- 支給率・上限額:中小企業は経費助成率が最大75%に拡大(2025年改正点)、大企業は55%程度
- 特徴:幅広い分野をカバーし、特にデジタル分野の研修は優遇される傾向
制度を使うことで「研修費用+人件費」の両面をカバーでき、企業にとって最も実用性が高い制度です。
経産省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」
経済産業省が推進する制度で、近年注目が高まっています。
- 対象:個人・企業の双方(個人は受講費の直接補助あり、企業は社員研修に活用可能)
- 対象分野:DXスキル、生成AI活用、データ分析など成長分野に直結するスキル
- 助成内容:研修受講費の補助(上限額あり)、条件を満たせば個人も利用可能
- 特徴:特に「生成AIやデジタルリテラシー」に対応する講座が対象になる点が新しい
AI研修や先端分野を学ぶ際に非常に有効な制度で、他の補助金との差別化ポイントです。
IT導入補助金
「ツールの導入」を通じて学び直しを実現できる制度です。
- 対象:中小企業・小規模事業者
- 対象分野:eラーニングシステム、SaaS型学習プラットフォーム、クラウド業務効率化ツール
- 助成内容:導入費用の最大2/3を補助
- 特徴:研修そのものというより、「学習環境の整備」に強みがある
リスキリング研修をeラーニングで全社展開する場合に相性が良く、実務で使いやすい制度です。
自治体の独自支援制度
国の制度に加えて、自治体も独自の支援を行っています。
- 東京都:「中小企業人材スキルアップ支援事業」など、研修費用の一部を助成
- 大阪府:「中小企業デジタル化支援」など、デジタル分野に重点を置いた補助金あり
- その他自治体:愛知県、福岡市などでも独自の人材育成助成を実施
地域ごとに制度が異なるため、自社所在地の自治体情報を確認することが必須です。商工会議所や自治体公式サイトで最新情報をチェックしましょう。
補助金・助成金の対象条件を整理
補助金や助成金は「誰でも使える」わけではなく、対象条件が細かく定められています。ここでは、中小企業と大企業の違い、雇用形態ごとの扱い、そして近年強化されている「デジタル分野研修の優遇傾向」を整理します。
中小企業と大企業の違い
- 中小企業:助成率が高く設定されており、研修費用・賃金補助の両面で優遇されやすい
- 大企業:助成率が低め。ただし対象研修は同様に利用可能で、DX・デジタル分野の研修であれば支援を受けやすい
対象従業員(正社員/契約社員/パート/個人事業主)
- 正社員:基本的に対象。研修費・賃金補助ともに利用しやすい
- 契約社員・パート:一定条件を満たせば対象(雇用保険の適用があるかが判断基準)
- 個人事業主:法人向け助成金は対象外だが、経産省の「キャリアアップ支援事業」や自治体の補助制度を通じて利用できる場合あり
デジタル分野の研修が優遇される傾向
- DX推進・生成AI活用・データ分析など、成長分野の研修は補助対象になりやすい
- ITリテラシーやAIリテラシーは、2025年度の制度改正でも重点領域として明記されている
「汎用的なスキル」よりも「産業競争力につながるスキル」が優先される傾向にある
補助金・助成金の対象条件まとめ(比較表)
| 区分 | 中小企業 | 大企業 | 個人事業主 | 備考 |
| 助成率 | 高い(最大75%) | 低め(〜55%) | 制度による | 中小企業は優遇傾向 |
| 正社員 | 対象 | 対象 | – | 雇用保険加入が前提 |
| 契約社員 | 一部対象 | 一部対象 | – | 雇用保険の有無で変動 |
| パート | 条件付き対象 | 条件付き対象 | – | 週の労働時間などが要件 |
| 個人事業主 | 一部制度対象外 | 一部制度対象外 | 利用可能な制度あり | 経産省・自治体制度が中心 |
| デジタル分野 | 強く優遇 | 強く優遇 | 強く優遇 | DX・生成AI関連が重点分野 |
申請の流れと必要書類【図解フローチャート】
補助金・助成金の申請は複雑に見えますが、基本の流れは共通しています。以下のステップを押さえれば、初めての企業でもスムーズに進められます。
Step1:対象制度を選ぶ
- 自社の研修内容や目的に合う制度を選定
- 「厚労省の助成金か」「経産省のキャリアアップ支援か」「自治体制度か」をまず判断する
Step2:研修計画・見積書を準備
- 研修カリキュラム、受講人数、実施期間を明記した研修計画書を作成
- 講座費用の見積書も必要になるケースが多い
- 事前に研修機関と調整しておくとスムーズ
Step3:申請 → 審査
- 申請書を所管機関(労働局・経産局・自治体窓口など)へ提出
- 書類審査で「要件を満たしているか」が確認される
- 申請期限に余裕を持つことが重要(直前は混雑・不備対応で遅れる可能性あり)
Step4:研修実施 → 実績報告
- 計画どおりに研修を実施
- 実施後、出席記録・請求書・領収書などを添付して実績報告
- 内容が計画と異なると不支給のリスクあり
申請に必要な書類(一例)
- 研修計画書
- 見積書・契約書
- 受講者リスト
- 出席簿・タイムカード等(実施証明)
- 請求書・領収書
- 賃金台帳(賃金助成がある場合)
注意点
- 提出期限を過ぎると不支給(猶予なし)
- 書類不備で差し戻されるケースが多い
- 実施内容と計画の乖離は不正受給と見なされるリスクあり
申請時の注意点・よくある失敗
補助金・助成金の申請は要件が細かく定められており、ちょっとした不備で不採択になってしまうこともあります。ここでは、よくある失敗例とその対策をまとめます。
要件を満たさず不採択になるケース
- 失敗例:「研修時間が要件を満たしていなかった」「対象従業員の条件が合っていなかった」
- 対策:事前に募集要項を熟読し、不明点は労働局や自治体窓口に確認。対象条件を満たす研修を選ぶことが重要。
計画と実施内容の乖離
- 失敗例:「計画書には40時間研修と記載したが、実施は30時間で報告した」
- 対策:計画と実施内容を一致させる。やむを得ず変更する場合は、事前に変更申請を提出しておく。
申請期限・書類不備でのトラブル
- 失敗例:「締切を過ぎて提出」「必要書類が不足して差し戻し」
- 対策:申請期限は余裕を持って準備し、チェックリストを活用。書類は複数人でダブルチェックする体制を作ると安心。
補助金申請は「細かいルールを守れるかどうか」が合否を分けます。制度のメリットを最大限に享受するためには、失敗事例を事前に知り、対策を取っておくことが不可欠です。
最新の改正情報・トレンド【2025年版】
リスキリング関連の補助金・助成金は、毎年のように制度改正が行われています。ここでは、2025年版の注目すべき改正点とトレンドを整理します。
支給対象の拡大(デジタル分野強化)
2025年度は特に 生成AI・データ分析・サイバーセキュリティ など、DX分野の研修を重点的に支援する方向性が打ち出されています。
従来の一般的なビジネス研修よりも、「新しい産業競争力を生むスキル」 に対して優先度が高まっているのが特徴です。
助成率の変更点(中小企業優遇)
- 中小企業の経費助成率が 最大75%に拡大
- 大企業は55%程度に据え置き
- 特に デジタル人材育成分野では中小企業が手厚い支援 を受けられるようになっています
中小企業にとっては「今が導入のチャンス」といえる改正内容です。
個人向けリスキリング支援制度の動き
これまで企業単位が中心だった制度ですが、2025年度は 個人が直接申請できる支援 が広がりつつあります。
- 経産省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」で、個人受講費用への補助が強化
- 一部自治体でも、求職者やフリーランス向けの支援制度が登場
「会社に頼らず学び直しを進めたい個人」にとっても活用しやすい環境が整いつつあります。
補助金を活用したリスキリング事例
補助金や助成金を活用すれば、「費用が高くて研修が実施できない」という課題を乗り越えることができます。ここでは実際に制度を活用した企業の取り組みを例に紹介します。
IT企業:生成AI研修を補助金で導入 → 生産性UP
あるIT企業では、厚労省の「人材開発支援助成金」を活用し、社員向けに生成AI活用研修を実施しました。
- 補助金で受講料の大部分をカバー
- 社員がAIを業務に取り入れ、資料作成や顧客対応の時間を大幅削減
結果として、全社の生産性が10%以上向上し、残業削減にもつながりました。
製造業:IoTスキル研修に活用 → 設備稼働率改善
ある製造業では、経産省の支援事業を活用してIoTデータ活用研修を導入。
- 設備稼働データの可視化・分析を学習
- 稼働効率を改善し、ダウンタイムを大幅に削減
補助金活用で研修コストを抑えつつ、現場改善の即効性を実感しています。
中小企業:外部eラーニング導入費用を補助金でカバー
従業員数50名ほどの中小企業では、IT導入補助金を利用してeラーニングシステムを導入。
- 研修環境をオンライン化
- 従業員が自分のペースで学べる体制を構築
「研修のために業務を止める必要がなくなった」ことで、学び直しが日常的に定着しました。
まとめ|補助金を活用してリスキリングを加速する
リスキリングに取り組む上で、補助金・助成金は研修を実現するための強力な後押しとなります。企業も個人も、制度を上手に活用することで費用負担を抑えながら、将来につながるスキルを習得できます。
ただし、補助金制度は毎年改正され、助成率や対象条件が変わることも少なくありません。常に最新情報をチェックし、自社や自身に合う制度を選ぶことが成功のカギとなります。
AI経営総合研究所では、補助金対象となる生成AI研修プログラムを多数ご用意しています。まずは資料をご覧ください。
費用面のハードルを下げつつ、次世代に必須のAIスキルを最短で身につけることができます。
- Qリスキリングの補助金・助成金は誰でも利用できますか?
- A
制度によって対象が異なります。多くは雇用保険に加入している企業の従業員が対象ですが、経産省の制度や一部自治体では個人やフリーランスも利用できる場合があります。
- Q補助金と助成金の違いは何ですか?
- A
一般的に、補助金は公募型で審査があり競争的、助成金は要件を満たせば原則支給されます。リスキリング関連は助成金の比重が大きく、比較的利用しやすいのが特徴です。
- Qどのような研修が対象になりますか?
- A
DX・デジタルスキル・生成AI活用・データ分析など、成長分野に直結する研修が優遇されます。語学や一般的なビジネスマナーよりも、「産業競争力を高めるスキル」が重点領域です。
- Q申請にはどのくらい時間がかかりますか?
- A
制度によりますが、申請から採択まで1〜2か月程度かかることが一般的です。余裕を持って準備することが重要で、締切直前は書類不備による差し戻しが増える傾向にあります。
- Q個人事業主やフリーランスでも利用できますか?
- A
企業向け助成金は対象外が多いですが、経産省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」や自治体の制度で個人も対象となるケースがあります。地域や年度によって条件が異なるため、最新情報を確認しましょう。