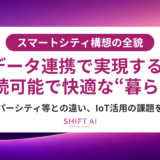「朝から忙しく働いているはずなのに、なぜか今日もタスクが終わらない」
「周りは定時で帰っているのに、自分だけ残業が続いている」
こうした状況に心当たりはありませんか?
仕事に真面目に取り組んでいるにもかかわらず、予定どおりに進まない。そんな状態が続くと、焦りや自己嫌悪につながり、さらなる業務効率の低下を招くこともあります。
本記事では、「仕事が進まない本当の原因」と「具体的な改善策」を解説します。
単なる精神論ではなく、業務の進め方・思考習慣・職場の仕組みまでを踏まえた内容です。
さらに、「仕事の遅れを防ぐデジタル活用法」や「個人では限界を感じたときの組織的対策」まで、AI経営の視点からも提案します。
仕事が前に進まないストレスから抜け出し、日々の業務にゆとりと成果を取り戻すヒントを、今日から一緒に見つけていきましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
仕事の進みが遅いとどうなる?放置のリスクとは
仕事の進みが遅い状態を放置していると、単に「ちょっと効率が悪い」では済まなくなります。
自分のタスクだけでなく、周囲や組織全体に波及する深刻なリスクを招く可能性があります。
以下に代表的なリスクを紹介します。
信頼の低下と評価への悪影響
どれだけ努力していても、タスクの完了が遅れれば「仕事が遅い人」という印象は避けられません。
報連相が遅れれば、上司やチームメンバーの意思決定にも支障が出ます。
結果として、プロジェクトから外されたり、責任ある業務を任されなくなるといった評価面の影響が出始めます。
チームの生産性を下げるボトルネックに
仕事は個人戦ではなく、チームプレイです。
自分の作業が遅れることで、次の工程を担う同僚や他部署の業務が止まるケースもあります。
「自分だけの問題」として片づけてしまうと、気づかぬうちにチーム全体のパフォーマンスを阻害してしまいます。
残業の常態化・心身への悪影響
業務が予定どおりに終わらず、毎日のように残業が続くと、慢性的な疲労やストレスが蓄積します。
睡眠不足や集中力の低下により、翌日の仕事効率はさらに落ちる──という悪循環に陥る危険もあります。
ひどい場合は、心身の不調やメンタル不全につながる可能性もあるため、早めの対処が重要です。
組織の成長スピードが鈍化する
「仕事の遅さ」は、組織の意思決定や市場対応のスピードをも遅らせます。
特に今のような変化の激しい時代においては、対応の遅れが機会損失につながりかねません。
個人の仕事の遅れが、組織全体の生産性や競争力に直結する時代だといえるでしょう。
関連記事:会社の生産性を向上させるには?意味・メリット・施策まで徹底解説
仕事が遅くなる5大原因をチェックしよう【セルフ診断付き】
「なんでこんなに仕事が進まないんだろう?」
そんな悩みには、明確な“原因”があります。
しかも多くの場合、それは「自分では気づきにくい」ものです。
ここでは、仕事の進みが遅くなる代表的な5つの原因と、改善に向けたヒントを紹介します。
まずは以下のセルフチェックから、ご自身の傾向を見つめてみてください。
セルフ診断:あなたはいくつ当てはまりますか?
- タスクの優先順位があいまいで、どれから手をつけるか迷う
- 完成度にこだわりすぎて、なかなか提出できない
- 同時に複数のことを進めているうちに、どれも終わらない
- やるべきことがあるのに、気づくと別のことをしている
- 上司や同僚に確認をとるのが後回しになってしまう
ひとつでも当てはまる方は、以下の各項目をチェックしてみましょう。
①タスク管理ができていない
- 優先順位がつけられず、常に「目の前のこと」に振り回される
- スケジュールを立てても実行できない
対処法
- タスクを細かく分解し、「重要度×緊急度」で整理
- 朝イチでタスクの見積もりと配分を行う「15分設計タイム」の導入
②完璧主義で時間をかけすぎる
- 納得できるまで何度も見直し、修正を繰り返す
- 「もっと良くできるのでは」と考え、終わりが見えない
対処法
- 「8割完成で提出、あとで直せる」が基本思考
- 納期や目的に応じて「こだわるべき点/省略できる点」を分ける習慣を持つ
③マルチタスク思考で集中が分散している
- 複数の案件を行ったり来たりして、結果どれも進まない
- 頭の中が常に“タスク渋滞”している
対処法
- 1タスクに集中する「シングルタスクタイム」の確保(例:25分集中+5分休憩)
- 着手前に「次にやること」をメモしておき、切り替え時に迷わないようにする
④先延ばし癖・着手力の低さ
- 頭ではやらなきゃと思っているのに、なかなか動けない
- 完了のイメージが湧かずに、最初の一歩が重い
対処法
- 着手ハードルを下げる「5分だけやる」ルール
- 過去資料やテンプレを使い、「ゼロから作らない」仕組み化
⑤判断・報連相の遅れ
- 方針に迷ったまま、手が止まってしまう
- 誰に相談すべきか考えるうちに、時間だけが過ぎていく
対処法
- あらかじめ「どこで誰に相談するか」を業務フローに組み込む
- 小さな判断は“その場で5秒ルール”で対応し、悩みすぎを防止
ワンポイント補足
これらは「性格の問題」ではなく、仕組みや習慣の問題です。
つまり、直せます。改善できます。そして、1つ改善するだけでも、日々の業務効率は大きく変わっていきます。
【ケース別対処法】業務シーンごとに見る「仕事が進まない」を解決するには?
「仕事の進みが遅い」と感じる場面は、人によって異なります。
ここでは、多くのビジネスパーソンがつまずきやすい具体的なシーンを4つ取り上げ、それぞれの改善策を紹介します。
自分に当てはまる場面を見つけて、今日から実践できるヒントを得てください。
ケース1:メール・チャットの返信が遅れてしまう
よくある状況
- 気づいたら未返信がたまっていて、後でまとめて対応している
- 返信文をじっくり考えすぎて、1件に時間がかかる
- 「すぐ返したほうがいいのは分かってるけど、なんとなく後回しに…」
対処法
- 定型文テンプレートを事前に用意しておく(例:「承知しました」「資料確認後、再度ご連絡します」など)
- 時間を決めてまとめて対応(1日3回:9時・13時・17時など)
- 「即レスしないと信頼を失う」という思い込みを捨てる
→“丁寧な即レス”より“誠実な対応”の方が重要です
ケース2:資料作成や報告業務に時間がかかる
よくある状況
- 1つの資料を仕上げるのに何時間もかかってしまう
- スライドの見栄えや表現をこだわりすぎて終わらない
- 報告内容を整理するのに時間がかかる
対処法
- 8割完成でまず提出→フィードバックで修正のスタンスに切り替える
- 過去資料を再利用して「ゼロから作らない」
- 構成テンプレート(例:「結論→背景→補足」の型)を使って思考時間を短縮
ケース3:突発対応が多くて、本来の仕事が進まない
よくある状況
- 「今ちょっといい?」の対応で毎日予定が崩れる
- イレギュラー対応ばかりで、本来の業務が後回し
- 気づけば1日が“緊急対応”で終わっている
対処法
- 突発業務用のバッファ時間(30分×2など)をあらかじめ予定に組み込む
- 「緊急」と「重要」の判断基準をチーム内で明文化する
- 対応後すぐにログを残して、「あの件どうなった?」の再確認を防ぐ
ケース4:集中力が続かず、作業が中断されがち
よくある状況
- SNSやメール通知が気になって集中できない
- タスクに入り込めるまでに時間がかかる
- 頻繁な会話や電話で作業がぶつ切りになる
対処法
- ノイズカット環境を物理的・デジタル両面で整備(通知オフ・イヤホン活用など)
- 集中が高まりやすい時間帯(朝一・昼食後など)を「集中タイム」として固定
- 作業途中で離れるときは、次にやることをメモしておく(「戻ったら◯◯する」)ことで再起動時間を短縮
ワンポイント
こうした対処法は、一つ一つは小さな工夫でも、組み合わせることで圧倒的な時短効果を生みます。
何より大切なのは、「これは改善できる」と自覚すること。そして、“完璧な解決”ではなく、“前に進む工夫”を重ねていくことです。
個人努力に限界を感じたら?チーム・組織でできる改善策
ここまで紹介してきた方法で一定の改善は見込めますが、それでも「やっぱり一人では限界がある」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、仕事の進みが遅い原因の多くは、本人の努力やスキル不足というよりも、組織やチームの構造に起因していることがあります。
このようなときこそ、個人の工夫にとどまらず、チームや組織全体で業務の流れを見直すことが、根本的な解決につながります。
属人化を防ぎ、情報を共有しやすい仕組みをつくる
「あの業務は◯◯さんにしか分からない」といった状態が続くと、業務の属人化が進み、誰かが不在になっただけで作業全体がストップしてしまいます。これは、業務停滞の温床となる危険な状態です。
こうした事態を防ぐには、日々の業務手順や判断基準、対応の流れをドキュメント化し、誰が見ても理解できる状態にしておくことが大切です。GoogleドキュメントやNotionなどのナレッジ共有ツールを活用すれば、場所や担当に関係なく必要な情報へアクセスできる仕組みがつくれます。
業務の可視化・棚卸しで「無駄」や「ムリ」を発見する
仕事が進まない背景には、「タスクが多すぎて手が回らない」「不要な作業に時間を取られている」といった、目に見えない業務のムリ・ムダが潜んでいることがあります。
こうした非効率を解消するためには、まず業務の中身を洗い出す、いわゆる「業務棚卸し」を行うことが効果的です。誰が、どの業務に、どれだけの時間を使っているかを可視化することで、優先順位の見直しやタスクの再配置といった組織全体での最適化が可能になります。
関連記事:業務棚卸しのやり方を徹底解説|5ステップでムダを洗い出し改善につなげる方法とは?
チーム内のコミュニケーション設計を見直す
業務の進みを妨げている要因のひとつに、コミュニケーションの滞りがあります。
報連相が遅れがちだったり、相談しづらい空気感があったり、タスクの役割分担が曖昧だったりする場合、チームとしての動きが鈍くなってしまいます。
こうした問題を解決するには、コミュニケーションのあり方そのものを設計し直すことが必要です。たとえば、定例ミーティングの目的を進捗確認から「課題共有とボトルネックの解消」へとシフトさせることで、チーム全体が業務の本質に集中できるようになります。
また、チャットツールに「相談OKの時間帯」や「気軽に話しかけてよい窓口」を設けることで、心理的ハードルを下げる工夫も有効です。心理的安全性のある空気づくりが、結果としてチーム全体の仕事の進みを後押しします。
「成長を支える研修」の導入も一つの手段
業務改善を継続的に進めていくには、個人任せではなく「学びの仕組み」と「共通認識」が欠かせません。属人化を防ぎ、全体の底上げを図るうえで、組織としての研修導入は非常に有効なアプローチとなります。
特に近年では、生成AIをはじめとしたデジタルスキルに特化した研修が注目されています。これらは、業務効率の大幅な改善に直結するだけでなく、社員一人ひとりのスキルを底上げすることで、組織の対応力そのものを高める効果も期待できます。
「もう個人の努力ではどうにもならない」と感じたときこそ、職場全体の仕組みや考え方に働きかけるタイミングです。
組織での改善こそが、仕事の進みを大きく変える一歩になるはずです。
AIやデジタルの力を借りて、進みの遅さを根本改善する方法
「努力しても、なぜか仕事が終わらない」
「毎日頑張っているのに、思うように進まない」
こうした悩みは、本人の努力や能力だけで解決するには限界があります。
そこで注目されているのが、AIやデジタルツールを使った“業務の根本見直し”です。
ここでは、日々の業務スピードを上げるために活用できるデジタル施策をご紹介します。
生成AIで「考える時間」「書く時間」を短縮する
報告書・議事録・マニュアルなどの文書作成は、思いのほか時間を奪います。生成AI(例:ChatGPTなど)を活用することで、以下のような支援が可能です。
| 活用シーン | 具体的な使い方 |
| 議事録作成 | 録音データの要約や発言内容の整理をAIが自動化 |
| 報告文作成 | 箇条書きの要点をもとに、AIが文章を整形 |
| マニュアル作成 | 手順・注意点を入力すれば、AIが構成+文章化 |
特に「書くのが遅い」「言語化に時間がかかる」人にとって、AIは非常に心強いパートナーになります。
RPA・自動化ツールで繰り返し作業を減らす
日報転記、請求処理、データ集計などの定型作業は、RPA(業務自動化ツール)で効率化が可能です。例えば以下のようなことができます。
- Excelのフォーマット統一作業をボタン1つで実行
- 毎朝のレポートを自動で生成&送信
- アンケート結果を自動で集計・グラフ化
定型業務に追われる時間が減れば、本来注力すべき業務に集中できる環境が生まれます。
タスクの可視化・共有で「止まる時間」を減らす
TrelloやNotion、Backlogなどのタスク管理ツールを使えば、チーム全体の作業状況が見える化されます。
「誰が今、何をやっていて」「どこが詰まっているか」をリアルタイムで把握できるため、無駄な確認・重複作業を大幅に削減できます。
AI活用は、個人だけでなく組織全体の生産性を変える
生成AIや自動化ツールの導入は、個人の業務スピード改善にとどまらず、組織のワークフロー全体を見直す契機になります。
特に中小企業やバックオフィス部門では、「少人数でも回る仕組み化」が重要です。
関連記事:事務作業を減らすには?定型業務の効率化・自動化を実現する5つの方法と進め方を解説
職場全体で「仕事の進みが遅い」体質から脱却するには?
ここまでご紹介してきた改善策は、いずれも効果的ですが、本質的な解決には「組織全体の体質」を変えていく視点が欠かせません。
一人の努力やスキルアップではどうにもならない「職場文化」「慣習」「仕組み」が、仕事の進みの遅さを生み出しているケースも少なくないからです。
属人化から脱却し、「仕組み」で回る組織へ
業務が特定の人に偏っていたり、「やり方は口頭で伝える文化」が根付いていたりすると、誰かが抜けた瞬間に仕事が止まってしまいます。
そうならないためには、ノウハウや業務の進め方を形式知として共有する仕組みが必要です。マニュアル化・可視化・デジタルツールの活用を通じて、属人化からの脱却を図ることで、仕事の進みは格段に安定します。
成果に直結する「集中できる環境づくり」を優先する
多くの企業では、「やることを増やす」方向の施策が中心になりがちです。
しかし実際には、不要な業務を減らす・集中を妨げる要因を取り除くといった「引き算」の視点が、組織の生産性を大きく左右します。
たとえば、会議や報告の時間を見直したり、業務の目的があいまいな作業を整理したりすることで、社員が本来注力すべき業務に集中できるようになります。これは結果として、仕事のスピードと質の両立につながります。
生産性向上=働き方の仕組みを変えること
仕事の進みを速くするためには、単に「頑張る」「効率化する」だけでなく、職場全体の働き方を設計し直す発想が不可欠です。
柔軟な働き方・明確な役割分担・仕組みによる判断の自動化など、組織設計そのものを見直す視点が、長期的な成長につながります。
関連記事:会社の生産性を向上させるには?意味・メリット・施策まで徹底解説
組織的な改善には、まず“共通の行動基準”が必要
「なんとなく非効率だけど誰も言い出せない」「改善提案が個人頼り」では、全社的な変化は起きません。
だからこそ、組織全体で共通認識を持ち、行動の基準を揃える研修や教育の導入が効果を発揮します。
業務の進みを変えるには、まず“組織の考え方”を変えるところから。
そのための一歩として、次章で紹介する研修資料DLもぜひ活用してください。
まとめ:今日から1つでも実行して、「仕事が進む日常」を取り戻そう
仕事の進みが遅いと感じるのは、決してあなた一人の問題ではありません。
多くの人が、日々の業務に追われながら「なぜか終わらない」「なぜか遅れてしまう」と悩んでいます。
しかし、その原因は“能力の差”ではなく、タスク管理の仕方や思考のクセ、職場の仕組みや文化にあることがほとんどです。
だからこそ、改善の余地は必ずあります。
まずは、自分に当てはまる原因を知ること。
そして、「着手のハードルを下げる」「完璧主義を手放す」など、小さな行動改善から始めてみましょう。
それでも解決しきれないときは、職場全体の仕組みやチームの体制に目を向けることが重要です。
属人化の排除、業務の棚卸し、AIツールの導入など、環境を整えることで仕事の進みは大きく変わります。
SHIFT AIでは、仕事の進みを改善するための「仕組みづくり」や「学びの機会」をご提供しています。一人で抱え込まず、組織としての変化に取り組んでみませんか?
あなたの「今日から変えられる一歩」が、明日の成果とゆとりにつながるはずです。
- Q仕事の進みが遅いのは性格の問題でしょうか?
- A
いいえ、多くの場合、性格ではなく「タスク管理の仕方」「考え方のクセ」「仕組みの不備」などが原因です。仕組みや行動を変えれば、仕事のスピードは改善できます。
- Q業務が終わらないのは、自分の能力不足ですか?
- A
能力だけでなく、環境や職場の構造に原因があることも多くあります。属人化や不明瞭な役割分担が進みの遅さにつながっている可能性もあります。
- Q仕事を早くするためにAIは本当に役立ちますか?
- A
はい。たとえば報告書作成やマニュアル整備など、時間のかかる業務は生成AIを活用することで短時間で効率的に進めることができます。SHIFT AIでは、こうした活用ノウハウも提供しています。
- Q仕事の進みが遅い体質を改善するには、何から始めれば良いですか?
- A
まずは自分の傾向を知ること(セルフチェック)から始めましょう。そのうえで、改善しやすい部分から一つずつ変えていくのが効果的です。個人改善だけでなく、チームや組織で取り組むことも大切です。
- Qチーム全体の仕事の進みが遅いときは、どう対処すればよいですか?
- A
チーム全体に同じような停滞感がある場合は、個人の努力ではなく、組織の仕組みや働き方に課題がある可能性があります。
業務の棚卸しによるタスクの見直しや、役割分担・報連相の設計を見直すことで、進みの遅さを根本から改善できます。必要に応じて、外部の研修やコンサルティングを活用するのも有効です。