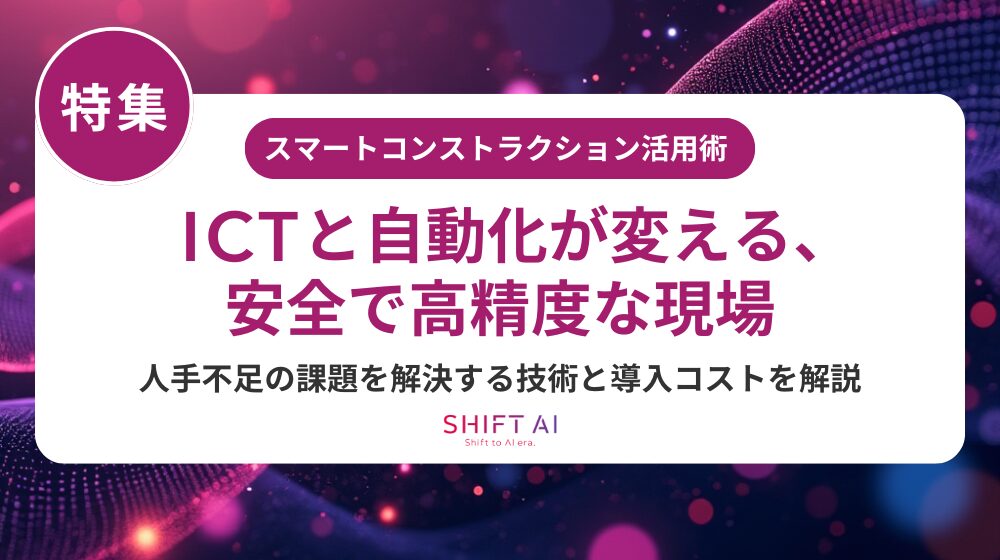建設現場のデジタル化を進めたい。
しかし、ICT建機やドローン、3D測量機器の導入コストが高く、なかなか踏み出せない──。
そうした声が、いま全国の建設会社から多く聞かれます。
近年、国土交通省や経済産業省は「建設業DX」を国策として強力に後押ししています。
特にスマートコンストラクション(スマート建設)に関しては、 機器導入だけでなく、BIM/CIM対応・デジタル人材育成までを支援対象に含める補助金が急増中です。
「導入したいのに費用が壁になっている」
「どの補助金を使えるのか、探しても情報がバラバラ」
「申請のタイミングを逃してしまった」
こうした悩みを解消するために、本記事では以下をわかりやすく整理しました。
- 2025年に利用できるスマート建設関連の補助金・支援制度一覧
- 申請の流れ・審査で評価されるポイント
- 導入効果を最大化する人材育成の戦略
そしてAI経営総合研究所ならではの視点として、 「補助金を単なる導入資金ではなく、企業変革の起点にする方法」を解説します。
まだ「スマートコンストラクションって何?」という方は、 先にこちらの記事をご覧ください。
スマートコンストラクションとは?建設業DXを加速させる仕組みと導入の全体像
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
はじめに|補助金は“導入のきっかけ”であり“変革の入り口”
建設業界ではいま、スマートコンストラクション(スマート建設)導入の機運が一気に高まっています。
ICT建機、3D測量、BIM/CIMなど、現場を効率化する技術が次々と登場し、 人手不足や2024年問題の打開策としても注目を集めています。
しかし現場からは、
「導入したいが、初期投資が高くて踏み出せない」
「どの補助金を使えばいいのかわからない」
という声が多く聞かれます。
こうした課題を後押ししているのが、国・自治体による補助金・支援制度です。
建設業DXを加速させる政策が次々に発表され、 スマート建設導入にかかる費用の一部を支援する仕組みが整いつつあります。
補助金の前提となる技術や仕組みを知りたい方は、こちらの記事もあわせてどうぞ。
スマートコンストラクションとは?建設業DXを加速させる仕組みと導入の全体像
なぜ今「スマート建設×補助金」が注目されているのか
スマートコンストラクションの導入が、いま国と企業の双方から強く求められています。
その背景には、建設業界が抱える構造的な課題と、 国交省が主導するDX推進政策の加速があります。
建設業界の3大課題──人手不足・高齢化・2024年問題
建設業は、他産業と比べて高齢化率が高く、若手人材の確保が難しい業界です。
特に技能労働者の約35%が55歳以上を占めるとされ、 現場のノウハウが継承されにくい状況が続いています。
さらに2024年には、時間外労働の上限規制が本格適用され、 「人が足りないのに、働かせることもできない」という二重の制約が発生。
この“2024年問題”を機に、業務効率化と生産性向上の両立が急務となりました。
結果として、多くの企業がICT建機や3D測量、BIM/CIMなどの導入を検討していますが、 同時に「初期投資」「操作習熟」「人材育成」の3つの壁が立ちはだかっています。
国交省が推進する「i-Construction」とDX政策の本格始動
こうした背景を受け、国土交通省は2016年から「i-Construction」を掲げ、
施工プロセス全体のデジタル化を国家プロジェクトとして推進してきました。
特に2025年以降は、これまでのICT施工推進から一歩進み、 “施工管理・設計・維持管理をデジタルで一気通貫させる”方針へと進化。
ドローンや3Dスキャナなどの機器だけでなく、 BIM/CIMやAI解析、クラウド施工管理システムといった“データを扱う基盤”への投資が支援対象となっています。
そのため、補助金制度も「機器導入支援」から「DX基盤整備支援」へと広がり、 企業のデジタル戦略全体を支える流れが強まっています。
補助金支援の拡大──ICT建機からAI・BIM/CIM・人材育成まで対象拡大
従来の補助金は、主にICT建機や3D測量機器など“ハード導入”が中心でした。
しかし近年では、AI解析、施工管理ソフト、クラウド連携、そして人材研修費までもが支援対象に含まれるようになっています。
たとえば、
- 「建設業DX推進支援事業」では、BIM/CIMやAI施工管理を支援対象に拡大
- 「ものづくり補助金」では、AI・IoT導入による業務自動化を補助対象に明記
- 自治体独自の制度でも、デジタル技術の“活用人材の育成”を対象に含むケースが増加
つまり補助金は、単なる“機器購入費の一部補助”ではなく、 企業の変革を後押しする包括的支援制度へと進化しているのです。
“補助金で機械を買う時代”から“補助金で人を育てる時代”へ
スマートコンストラクションを成功させる最大の鍵は、 導入後に“使いこなす人材”が社内にいるかどうか。
いくら最新のICT建機を導入しても、 現場でデータを活用できなければROI(投資対効果)は上がりません。
そのため今、国や自治体は「機器導入+人材育成の両輪支援」へと政策をシフトしています。
「補助金で機械を買う時代」は終わり、これからは「補助金でデジタル人材を育てる時代」へ。
この変化を正しく捉え、 補助金を“支援金”としてではなく、人と仕組みへの投資資源として活かせる企業こそ、 次の時代のスマート建設をリードしていくでしょう。
【2025年最新版】スマートコンストラクション関連の補助金・支援制度一覧
建設DXを推進するうえで、補助金の選定は成否を分ける重要ステップです。
ここでは、スマートコンストラクション導入に直結する主要5制度を中心に、 対象・補助上限・支援内容を整理しました。
※制度は年度ごとに要件や上限が変更されるため、 最新情報は各省庁・自治体の公募要領をご確認ください。
■ 建設業DX推進支援事業
- 補助上限:最大1,000万円
- 対象:中小建設業者、測量・設計関連企業
- 主な支援対象:ICT建機、BIM/CIM、クラウド施工管理システム
- 概要:国土交通省が主導する建設DX支援の中心的制度。
設備投資だけでなく、現場データの共有や工程最適化を目的としたICT施工全般を対象。 - ポイント:導入目的が「業務効率化」「生産性向上」と一貫していることが採択の鍵。
形式的な“導入ありき”ではなく、活用計画と教育体制が評価されます。
■ ものづくり補助金
- 補助上限:最大1,250万円
- 対象:中小企業・小規模事業者
- 主な支援対象:IoT・AI導入、工程自動化、施工支援アプリなど
- 概要:経済産業省が運営する汎用的DX支援制度。
建設業も対象に含まれており、AI解析や施工データ管理の自動化も補助対象。 - ポイント:IT導入補助金より採択率は低めだが、投資規模が大きい企業向け。
「中期的な生産性向上計画」を提出できると有利です。
■ IT導入補助金(A/B類型)
- 補助上限:最大450万円
- 対象:中小企業・小規模事業者
- 主な支援対象:クラウド施工管理ソフト、電子受発注、勤怠・工程管理など
- 概要:中小企業庁が実施するソフトウェア導入支援制度。
スマート建設においては、クラウド施工管理や電子帳票ツールなどが代表的対象です。 - ポイント:事前登録された「IT導入支援事業者」との連携が必須。
導入目的(効率化・情報共有)を明確化し、費用対効果を数値で示すと採択率が高まります。
■ GX建機導入支援事業
- 補助上限:最大2,000万円
- 対象:建設業全般
- 主な支援対象:電動建機、低炭素化設備、ハイブリッド重機など
- 概要:環境省・経産省が推進するGX(グリーントランスフォーメーション)支援制度。
CO₂排出削減に資する建設機械の導入を対象とし、環境対応と生産性向上を両立する狙いがあります。 - ポイント:単なる設備更新ではなく、環境貢献の定量的効果を示すことが必要。
国交省DX施策との併用も可能で、脱炭素経営のアピールにもつながります。
■ 自治体独自の補助金・支援制度
- 補助上限:50〜500万円(自治体により異なる)
- 対象:地域内の中小・建設関連企業
- 主な支援対象:ドローン・3D測量機器、実証実験、地域施工DXなど
- 概要:各都道府県・市町村が独自に実施するスマート建設支援。
例)東京都の「中小企業デジタル化支援助成金」、北海道の「建設DX推進事業補助金」など。 - ポイント:採択件数が少なく、倍率が低いため、狙い目。
申請期間が短いことが多いため、情報収集とタイミングが勝負です。
補助金選定のポイント
| 分類 | 想定規模 | 目的 | 特徴 |
| 建設業DX推進支援 | 中堅以上 | ICT導入 | 建設専用の制度で最も実務的 |
| ものづくり補助金 | 中小企業 | DX・AI化 | 幅広く活用できる定番制度 |
| IT導入補助金 | 小規模〜中小 | 効率化 | ソフトウェア中心、採択率高め |
| GX建機補助金 | 全規模 | 脱炭素・省エネ | 環境・設備更新に強い |
| 自治体補助 | 地域企業 | 実証実験 | 小規模だがスピード重視 |
補助金の選び方|自社に合う制度を見極める3つの視点
ここまで紹介した制度の中から、どれを選ぶかは企業によって最適解が異なります。
「せっかく申請したのに対象外だった」「採択されなかった」というケースも少なくありません。
そこで、補助金を選ぶ際に押さえるべき3つの視点を整理しました。
自社の状況と照らし合わせることで、最短で“狙うべき制度”を特定できます。
視点① 投資目的──「機器導入」か「業務効率化」か
まずは、自社の投資目的を明確にしましょう。
補助金は「何を達成するための投資か」で、対象制度が大きく変わります。
| 投資目的 | 該当しやすい制度 | 具体例 |
| ICT建機・ドローンなどの機器導入 | 建設業DX推進支援事業/GX建機支援事業 | ICT建機、電動重機、3D測量機器の導入 |
| クラウド施工管理やBIM/CIMによる業務効率化 | IT導入補助金/ものづくり補助金 | 施工管理SaaS、工程共有クラウド |
| 人材育成・DX教育を伴う組織変革 | 自治体補助金/建設業DX推進支援事業(教育枠) | AI・データ活用研修、操作トレーニング費用 |
ポイント:
制度は「ハード導入型」か「ソフト・教育型」かで補助率・書類が異なります。
まずは“何に投資するのか”を明確化し、目的と制度の整合性をとることが第一歩です。
視点② 組織規模──資本金・従業員数で対象が変わる
次に確認すべきは、自社の「規模要件」です。
多くの補助金は中小企業基本法に基づく定義を採用しており、資本金や従業員数で対象が区切られています。
| 区分 | 資本金 | 常時雇用人数 | 該当しやすい制度 |
| 小規模企業 | ~5,000万円 | ~20名程度 | IT導入補助金/自治体補助 |
| 中小企業 | ~3億円 | ~300名程度 | ものづくり補助金/建設業DX支援 |
| 中堅企業・大手 | 3億円超 | 300名超 | GX建機支援事業/省エネ型設備補助金 |
ポイント:
申請時に「建設業の業種区分」で定義が異なる場合もあります。
たとえば、土木業と測量業で上限が変わるケースもあるため、事業内容コード(日本標準産業分類)を確認しておくと安心です。
視点③ 申請難度──採択率・必要書類・事業計画レベル
最後に見るべきは「申請難度」。
補助金にはそれぞれ、必要書類のボリュームや採択率に差があります。
| 制度名 | 採択率の目安 | 必要書類 | 特徴 |
| IT導入補助金 | 約50〜60% | 事業計画書(簡易)・見積書 | 小規模でも挑戦しやすい |
| ものづくり補助金 | 約30%前後 | 詳細な事業計画・財務資料 | 審査が厳しく、専門家支援が有効 |
| 建設業DX支援事業 | 非公開(想定40%前後) | 技術導入計画・活用計画書 | DX実現性と波及効果が重視 |
| 自治体補助金 | 地域により異なる | 簡易報告書 | 募集枠が少なく、情報収集が鍵 |
ポイント:
申請難度が高いほど、採択時の補助額が大きくなる傾向があります。
自社の体制(経理・総務・技術担当の連携)を考慮して、無理のないレベルの制度を選ぶのが成功の近道です。
チェックリスト|あなたの企業に合う補助金タイプ診断
| 質問 | YES | NO |
| ICT建機など設備導入を検討している | 建設業DX支援/GX建機 | IT導入補助金 |
| 施工管理や書類業務の効率化を狙っている | IT導入補助金/ものづくり補助金 | 建設業DX支援 |
| 社内で操作研修やAIリテラシー教育を実施したい | 建設業DX支援(教育枠)/自治体補助 | – |
| 補助金申請に慣れていない | IT導入補助金/自治体補助 | ものづくり補助金 |
| 中期的にDX体制を築きたい | ものづくり補助金/GX建機支援 | IT導入補助金 |
ワンポイントアドバイス
複数の制度を“段階的に使い分ける”戦略も効果的です。
たとえば、
1年目にIT導入補助金で施工管理SaaSを導入 → 2年目に建設業DX支援でBIM/CIM+AI分析を展開、 という流れなら、申請ハードルを上げすぎずに着実なDX投資が可能です。
補助金申請の流れと成功のコツ【図解付き】
補助金は「制度を知っているか」よりも、「どう申請するか」で結果が決まります。
申請の流れを把握し、審査で評価されるポイントを押さえておくことで、 採択率は大きく変わります。
申請〜交付までの全体フロー(スケジュール付き図)
補助金の流れは、どの制度でも概ね以下のステップで進みます。
① 公募開始
↓
② 事業計画・見積書の作成
↓
③ 申請書の提出(電子申請システム)
↓
④ 審査・採択結果の通知
↓
⑤ 交付決定
↓
⑥ 設備・システム導入・研修実施
↓
⑦ 実績報告・証憑提出
↓
⑧ 補助金の交付(入金)
全体のスケジュール感:
- 公募開始から採択までは 1〜2か月程度
- 導入・実績報告まで含めると 全体で3〜6か月が一般的
- 自治体補助金は、受付期間が2〜3週間と短いケースもあるため要注意
ポイント:
補助金は「後払い方式」が基本です。
交付決定前に契約・発注した費用は対象外になるため、 必ず“交付決定通知”を受け取ってから着手しましょう。
審査で評価されるポイント(費用対効果・社内展開・再現性)
審査員が重視するのは、単なる「設備更新の必要性」ではなく、 企業としての“投資戦略”が明確かどうかです。
| 評価観点 | 審査のポイント | 改善のヒント |
| 費用対効果 | 投資額に対してどの程度生産性が向上するか | 導入前後の定量効果を明記(例:作業時間30%削減) |
| 社内展開力 | 現場全体に波及する体制があるか | 操作研修・社内教育計画を添付する |
| 再現性 | 他現場にも展開できる仕組みか | 「標準化」「マニュアル化」の視点を盛り込む |
| 持続可能性 | 導入後も自走できるか | 維持管理・更新計画を記載する |
審査では「ツール導入で終わらないこと」が重要。
“人・仕組み・データ”を含めた全体最適の設計図を示すことで評価が上がります。
失敗しがちな落とし穴(交付決定前の発注・書類不備など)
補助金の不採択・返還トラブルの多くは、次の3つの落とし穴が原因です。
- 交付決定前の契約・発注
→ 契約日が交付決定日より前だと、対象外扱いになります。
発注時期は必ず担当省庁のFAQで確認を。 - 見積書・領収書の形式不備
→ 書式・宛名・日付に不備があると報告書が差し戻されます。
「見積依頼書」とセットで保管しましょう。 - 事業計画書が抽象的すぎる
→ “導入効果が見えない”“再現性が低い”と判断されやすい。
数値目標・スケジュール・社内体制を明確に記載するのが鉄則。
補助金は「書類で戦うプロジェクト」です。
提出直前に第三者チェック(専門家・支援機関)を入れることで不採択リスクを減らせます。
採択後の義務(実績報告・成果提出・返還リスク)
採択後も、次の3つの手続きが義務付けられています。
これを怠ると「補助金の一部返還」になるケースもあります。
| 手続き | 内容 | 注意点 |
| 実績報告 | 導入結果・支出証憑・導入前後の比較を提出 | 写真・帳票など証拠資料が必要 |
| 成果報告 | 生産性向上・コスト削減効果を数値化 | 簡易レポートでも“定量化”が求められる |
| 保管義務 | 書類を5年間保管 | 後日監査に備え、データも保存必須 |
返還リスクの典型例
- 導入後に機器を転売・貸出
- 補助金の目的外利用
- 実績報告未提出または虚偽記載
「もらって終わり」ではなく、「報告まで完了して初めて補助金が成立」。
導入後の運用・管理を社内で共有しておくことが重要です。
補助金の“効果を最大化”する導入後のステップ
補助金を活用して設備やソフトを導入しても、 ROI(投資対効果)が出ないまま終わる企業は少なくありません。
なぜなら、制度が支援するのは「導入」までであり、 “活用フェーズ”は企業の努力に委ねられているからです。
ここでは、補助金の効果を最大化するための実践的な3ステップを紹介します。
機械を買っただけではROIは出ない
スマートコンストラクションの真価は、導入そのものではなく「使いこなす」ことにあります。
最新のICT建機や施工管理ソフトを導入しても、 現場での操作やデータ活用が定着しなければ、生産性はほとんど変わりません。
補助金で機械を買うことは“スタートライン”に過ぎず、 真のROIは、運用設計・習熟教育・継続改善によって生まれます。
「導入=成果」ではなく、「運用設計×人材育成=成果」
──この式を理解している企業ほど、補助金の恩恵を最大限に活かしています。
補助金対象外でも“社内育成”が成果を左右する
多くの制度では、「機器購入費」「外部システム導入費」は補助対象となりますが、 操作研修・教育費は対象外、または補助率が低く設定されています。
しかし実際には、補助金の有無よりも教育投資の有無がROIを決めるケースがほとんどです。
たとえば、ICT建機を導入しても現場担当者が操作を理解していなければ、 施工時間短縮どころか、ミスや非稼働時間が増えるリスクすらあります。
逆に、導入後に教育を組み込んだ企業では、3か月以内に生産性が顕著に向上。
特に若手社員や再教育層を中心に、「デジタルで仕事を設計する力」が高まっています。
補助金の対象ではなくても、“教育費こそ最もリターンが高い投資”。
現場で使いこなすためのAI・DX研修をセットで設計する
補助金を有効に使い切るには、導入直後に「人材育成ロードマップ」を並行設計するのが理想です。
たとえば──
- 導入機器の操作トレーニング
- データ共有・分析の基本教育
- 生成AIによるレポート・見積書作成支援
など、現場レベルで即効性のあるDXスキルを研修に組み込みます。
こうした教育を通じて、現場担当者は「AI・デジタル技術をツールとして使いこなす思考」へと変化します。
その結果、新しい技術導入のたびに補助金に頼らず自走できる組織が形成されます。
【事例】ICT建機導入企業がAI研修を組み合わせた結果、現場工数を25%削減
ある中堅ゼネコンでは、建設業DX推進支援事業を利用し、ICT建機を導入。
同時に、社内でAI活用・データ分析研修をセットで実施しました。
導入から半年後、
- 施工準備にかかる時間:平均25%削減
- 設備稼働の待機時間:約20%短縮
- 現場報告の作業負担:月あたり12時間削減
さらに、若手社員の提案件数が増え、“デジタル化を前向きに捉える文化”が社内に浸透。
この企業は翌年度、自治体補助金を活用してBIM/CIMとの連携も開始しました。
“補助金で導入し、AI教育で定着させる”──これが、補助金の本当の成功モデルです。
補助金で導入した技術を“使いこなす人材”を育てませんか?
AI経営総合研究所の研修プログラムでは、
建設業のDX推進を支える生成AI研修・現場DX講座を実践形式で提供しています。
【ケーススタディ】補助金を活用したスマート建設導入の成功例
ここでは、実際に補助金を活用してスマート建設を導入した3つの企業事例を紹介します。
単なる“導入成功”ではなく、補助金+教育によって定着・効果を生み出したリアルな成果に焦点を当てます。
ケース① 中堅ゼネコン:ものづくり補助金 × ICT建機
課題:
人手不足により、施工現場での重機オペレーターの負担が増大。
効率化のためICT建機を導入したいが、数千万円規模の投資がネックとなっていた。
取り組み:
経済産業省の「ものづくり補助金」を活用し、 ICTブルドーザーおよび3D測量機器を導入。
同時に、導入チームを中心に操作研修・データ活用研修を実施。
成果:
- 施工精度の誤差:従来比 −70%
- 土量算出作業:1日→2時間へ短縮
- 残業時間:月15時間削減
- 現場管理者の「次回導入意欲」:100%
ポイント:
補助金で“導入資金”を確保しただけでなく、 教育によって「機械を人が使いこなす文化」を定着させた点が最大の成功要因です。
ケース② 地方工務店:自治体補助 × 施工管理SaaS
課題:
地方の工務店では、紙中心の現場管理と電話・FAXでの指示が常態化。
現場間の情報共有に時間がかかり、1日あたり2〜3時間のロスが発生していた。
取り組み:
地元自治体が実施する「地域建設DX推進補助金」を活用し、 クラウド型の施工管理SaaSを導入。
あわせて、社内向け「クラウド業務講座」を開催し、 管理職・現場監督・職人を横断的に教育。
成果:
- 現場報告の作成時間:60%短縮
- 工期遅延率:従来比30%減
- 顧客対応スピード:2倍
- 社内アンケートで「業務改善を実感」した社員:87%
ポイント:
自治体補助金は金額こそ小規模ながら、導入から教育までスピード感を持って展開できる点が魅力。
小規模事業者でも「DX化を定着させる」成功パターンの好例です。
ケース③ インフラ企業:DX推進補助 × AI研修
課題:
大規模な設備点検を抱えるインフラ企業。
AIによる異常検知を取り入れたいが、社内にデータ解析人材がいなかった。
取り組み:
国交省の「建設業DX推進支援事業」を活用してAI点検ツールを導入。
同時に、全社横断でAI活用研修プログラムを実施。
生成AIを活用した報告書作成・進捗分析などの演習を現場業務に即して行った。
成果:
- 点検レポート作成時間:約40%削減
- データ分析レポートの自動生成率:70%達成
- 研修後6か月でAI活用提案件数:10件→68件へ増加
ポイント:
AI研修によって「現場が自らデータを活かす」文化が形成され、 導入したAIツールが“使われ続ける仕組み”に変化。
補助金と人材育成を組み合わせることで、継続的なROI向上が実現した。
補助金を最大限に活かす“教育設計”を始めませんか?
導入だけで終わらせない――AI経営総合研究所では、 建設業向けの生成AI研修・DX人材育成プログラムを多数提供しています。
まとめ|補助金は“導入の資金”ではなく“未来への投資”
補助金は、単なる「導入コストを抑えるための制度」ではありません。
それは、企業が中長期の競争力を構築するための“未来への投資”です。
いま、建設業界では「技術を持つ企業」よりも、 「技術を活かせる人材と仕組みを持つ企業」が成果を出しています。
同じ補助金を使っても、成果が出る企業とそうでない企業の差は、 “人材育成を同時に行ったかどうか”にあります。
補助金は「導入のきっかけ」を与えてくれます。
しかし、それを企業の“成長エンジン”に変えるのは人と学びの力です。
AI経営総合研究所では、補助金で導入した技術を現場で定着させるための 生成AI研修・DX人材育成プログラムを提供しています。
補助金で設備を導入した今こそ、 その技術を“使いこなす力”を社内に育てる時です。
- Qスマートコンストラクション導入に使える補助金はどれ?
- A
主に次の5つの制度が活用されています。
- 建設業DX推進支援事業:ICT建機・BIM/CIMなど導入支援
- ものづくり補助金:AI・IoT導入などの生産性向上施策
- IT導入補助金:クラウド施工管理・電子帳票などの業務効率化
- GX建機導入支援事業:電動建機など環境対応設備の導入
- 自治体独自補助金:ドローン・3D測量機器の実証実験など
制度によって対象・上限額・時期が異なるため、 自社の目的(機器導入・業務改善・教育)に合わせて選定することが重要です。
スマート建設の基本構造を知りたい方は
スマートコンストラクションとは?建設業DXを加速させる仕組みと導入の全体像
もあわせてご覧ください。
- Q中小企業でも申請できますか?
- A
はい、中小・小規模事業者でも申請可能です。
むしろ「建設業DX推進支援事業」「IT導入補助金」「ものづくり補助金」は、 中小企業を主な対象としています。ただし、資本金や従業員数などの要件(中小企業基本法に基づく定義)を満たす必要があります。
業種によって基準が異なるため、建設業の場合は「資本金3億円以下・従業員300名以下」が目安です。
- Q補助金で購入した機器を転用しても大丈夫?
- A
原則として目的外使用・転売・貸与は不可です。
補助金の交付対象として認められた機器・ソフトは、 「申請した事業計画に沿って利用する」ことが条件になっています。違反した場合は、補助金の返還や採択取り消しの対象となるため注意が必要です。
転用を検討する際は、必ず事前に事務局へ相談しましょう。
- Q補助金は人材研修費にも使えますか?
- A
制度によって異なりますが、近年は人材育成費も一部対象になりつつあります。
- 建設業DX推進支援事業:教育・操作研修を含む導入計画を評価対象に含む
- 自治体補助金:AI・デジタル研修を対象に含むケースあり
ただし、多くの制度では教育費の補助率は低めか、上限が設定されています。
それでも、教育を並行して行った企業ほどROIが高い傾向が明確です。
- Q採択後に辞退した場合どうなる?
- A
交付決定後でも辞退は可能です。
ただし、採択後の辞退理由によっては、次回以降の申請で不利になる場合があります。- 導入計画の大幅な変更
- 発注業者との契約トラブル
- 予算未達・社内方針変更 など
辞退する場合は、事務局に速やかに「辞退届」を提出し、 交付決定の取り消しを正式に行う必要があります。