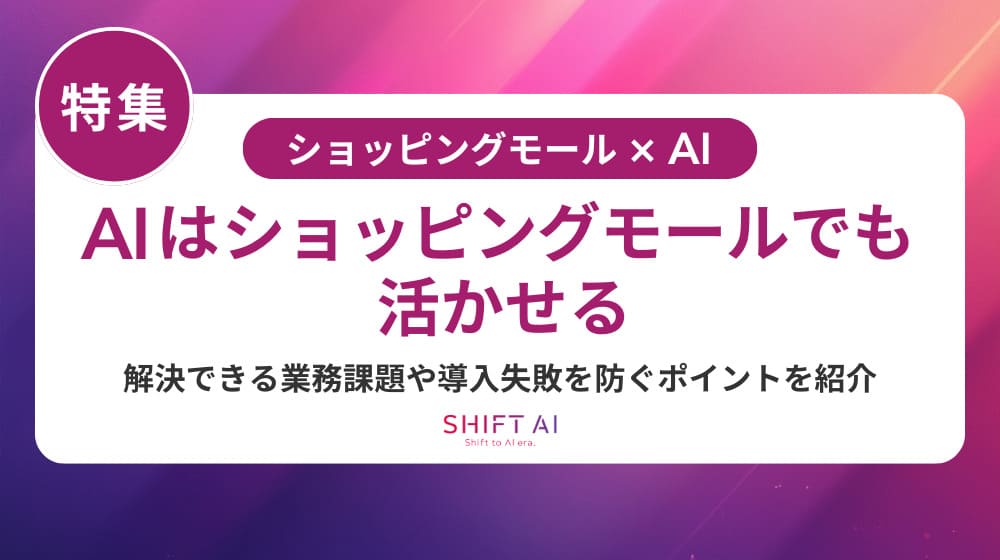来館者数が伸び悩み、テナント売上も横ばい。
多くのショッピングモール運営者が打開策としてAI導入に踏み切りました。ところが、システムを整えたはずなのに現場では思ったほど活用が進まないという声が後を絶ちません
「せっかく投資したのに、なぜ社内でAIが使われないのか」
「どこにボトルネックがあるのか、どうすれば定着するのか」
この疑問は一過性の流行ではなく、商業施設ならではの構造的な課題に根ざしています。テナントごとのデータ分断、複雑なバックオフィス業務、多店舗スタッフへの教育難――。これらはAIの恩恵を最大化するうえで避けて通れない壁です。
本記事では、ショッピングモール運営に特有の「社内利用が進まない5つの壁」を洗い出し、その解決ステップを具体的に解説します。さらに、実際に活用率を大幅に高めた商業施設の事例を紹介し、SHIFT AI for Bizによる研修プログラムがどのように定着を支援するかを詳しくお伝えします。
| この記事でわかること一覧🤞 |
| ・商業施設でAI活用が進まない主因 ・データ分断や教育難の具体的影響 ・社内定着を成功させる3ステップ ・実際に成果を上げた成功事例 ・SHIFT AI研修による定着支援 |
単なる技術導入から一歩進み、組織全体でAIを活かす文化を根付かせる方法を、ここから一緒に探っていきましょう。
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
ショッピングモールでAI活用が進まない現状
ショッピングモールでは来館者数の減少や売上の伸び悩みが続くなか、打開策としてAI導入を進める動きが広がっています。来店者動向の分析、売上予測、在庫管理などAIの活用領域は広く、投資価値も大きいはずです。ところが「システムは入れたのに現場が使わない」「定着しない」という声は後を絶ちません。ここではまず、なぜ商業施設で社内利用が進みにくいのか、その背景を整理します。
来館者減少と売上横ばいがもたらすプレッシャー
地域や景気動向に左右されやすいショッピングモールは、近年オンライン購買の拡大によって来館者数が伸び悩んでいます。結果としてテナント売上やモール全体のROI(投資利益率)が横ばいとなり、運営本部は早急な施策を求められる状況です。AI活用はこの課題を打破する切り札として期待されてきましたが、導入後に成果が出ないケースが目立ちます。
AI導入がブーム化しても社内利用率が伸びない理由
AIツールを導入しただけでは、現場スタッフが日常業務に活かせるとは限りません。目的の共有不足やデータの分断など複数の要因が重なり、現場での定着を阻んでいます。たとえば、各テナントが独自に顧客データを管理していると、モール全体での来店者分析やマーケティング自動化が進まず、投資効果が見えにくくなります。
| 課題 | 具体的な影響 |
| データがテナントごとに分断 | モール全体の来店者分析が不完全になり、戦略的施策が立てにくい |
| 現場スタッフのリテラシー不足 | AIツールを日常業務に組み込むための知識やスキルが不足 |
| 経営層と現場のKPI不一致 | 成果指標が共有されず、AI活用の方向性がぶれる |
こうした構造的な課題を解消しなければ、AI活用は一過性の施策に終わりかねません。より深い原因と解決策を理解するためには、商業施設に特有の「社内活用が進まない5つの壁」を明らかにする必要があります。
詳しくは、商業施設のAI導入が失敗する理由は?ROIを高める3つのステップもあわせて参考にすると全体像を掴みやすくなるでしょう。
ショッピングモール特有の「社内活用が進まない5つの壁」
商業施設がAIを導入しても現場での定着が進まない背景には、一般的な企業とは異なる独自の課題があります。ここでは、ショッピングモール運営に特有の5つの壁を整理し、なぜこの業界で活用が停滞しやすいのかを明らかにします。
テナントごとのデータ分断が戦略を妨げる
モール内の各テナントは独自の販売管理や顧客データを持っています。データ基盤が統一されていないため、モール全体で来館者動向を把握したり、AIによる統合的な売上予測を行ったりすることが難しくなります。結果として、経営判断に必要なインサイトが得にくく、AIの投資対効果も見えづらくなります。
バックオフィス業務が複雑で現場の余力がない
契約管理、テナント調整、在庫や販促の調整など、モール運営のバックオフィスは日々の業務負荷が大きいのが実情です。AIツールを使いこなす以前に、現場スタッフが新しい業務フローを学ぶ時間が確保できず、ツール利用が後回しになるケースが少なくありません。
こうした課題を解決するためには、ショッピングモールの事務作業をAIで効率化!人件費削減とROI向上を実現する方法など、バックオフィス向けAI活用事例の参考が役立ちます。
従業員のリテラシー格差と多店舗研修の難しさ
複数のテナントにまたがる大規模施設では、従業員のITスキルやAIへの理解度にばらつきがあります。一部のスタッフが操作に習熟しても全体の底上げが難しいため、モール全体での活用度が伸び悩みます。多店舗研修の仕組みがないままでは、教育の標準化も進みにくいでしょう。
経営層と現場のKPI不一致
経営層は来館者数増や売上向上を指標に掲げても、現場では日々の接客や運営業務が優先されます。目的の共有不足が続くとAI活用の方向性がぶれ、成果評価も曖昧になりがちです。双方が同じKPIを見据えた目標設定が不可欠です。
投資対効果(ROI)の可視化が不足
AI導入には一定の初期投資が伴いますが、効果がすぐに数値化されないと社内で追加投資や継続利用の合意を得にくいのが実情です。ROIを定量的に示すための評価指標や測定体制を事前に整えておく必要があります。
これら5つの壁を突破しなければ、AIは“導入しただけ”の状態にとどまります。次のパートでは、社内定着を実現するための具体的なステップを紹介します。
社内定着を実現する3つのステップ
ショッピングモールがAIを導入しただけで成果を出すのは難しく、「導入」から「定着」へ移す仕組みづくりが不可欠です。以下の3ステップを踏むことで、現場の活用率を着実に高めることができます。
経営層と現場が共有するAI活用戦略を策定する
まず大切なのは、経営層と現場が同じ指標を共有した上でAI活用のゴールを明確にすることです。来館者増やROI改善など、モール全体が共通して目指す成果を数値化し、その達成に必要なAI施策を洗い出します。ここで戦略とKPIを統一しておくと、現場が「自分ごと」としてAIを活用しやすくなります。
より具体的な活用イメージはショッピングモールで進むAI活用!来店者増・ROI改善の事例と導入までの流れが参考になります。
多店舗研修とリスキリングで従業員の底上げを図る
AI活用が社内で広がらない最大の要因の一つが従業員のリテラシー格差です。多店舗を横断した研修体系を構築し、初級から応用まで段階的に学べる仕組みを作ることで、どの店舗のスタッフも同じレベルでツールを使えるようになります。
SHIFT AI for Biz研修は、商業施設運営に特化したプログラムで、実務に即した演習やケーススタディを通じ、短期間で全員のスキルを底上げすることが可能です。
データ活用体制を整えROIを定量的に測定する
導入効果を社内で継続的に共有するには、ROIを定量的に測定する仕組みが欠かせません。来店者分析や売上予測のデータを一元管理し、効果測定レポートを定期的に経営層と現場へフィードバックすることで、AI活用の成果を数字で示せます。これにより投資判断や追加施策の合意形成もスムーズになります。
詳しい投資回収のポイントはショッピングモール向けAI導入費用は?投資回収までの流れ・補助金情報を参照すると理解が深まります。
これら3つのステップを着実に実行すれば、単なるAI導入から一歩進み、組織全体が自発的にAIを活用する文化を根付かせる土台ができます。次に、実際に活用率を飛躍的に伸ばした商業施設の事例を見てみましょう。
成功事例から学ぶ―社内活用率を大幅に伸ばした商業施設の取り組み
理論だけでは社内定着は進みません。ここでは実際に利用率を飛躍的に高めた商業施設の事例を通して、現場で効果が出た施策を確認します。
部門横断チームで「使う文化」を作った東急モールズデベロップメント
東急モールズデベロップメントでは、生成AIの利用率が8.5%から75%へと大きく伸びました。鍵となったのは、部署を横断した「ChatGPT研究部」の立ち上げです。経営層の後押しを得て、マーケティング部門や店舗運営チームが連携し、AIを活用した業務改善アイデアを積極的に共有。
さらに社内コンテストを開催し、優れた活用事例を表彰することで、現場のモチベーションを高めました。
このように、組織全体を巻き込んだ取り組みは「AIは特定部署だけが使うもの」という意識を変え、日常業務に自然に溶け込ませるきっかけとなります。
出典:導入後の社内生成AI利用率は8.5%→75%へ大幅アップ。
定量的な成果を可視化して投資効果を示す
この事例で重要なのは、単なるイベント開催だけではなく、効果を数値で示す仕組みを同時に整備した点です。利用率や業務効率化の改善幅を定期的にレポートし、経営層と現場双方に共有することで、AI投資のROIを社内に浸透させました。結果として、継続的な予算確保や追加施策への理解が得やすくなります。
商業施設が学ぶべきポイント
- 部門横断で「AIを使う文化」を作ることは、現場の習慣づくりに直結する
- 数値による効果測定を仕組み化すると、投資対効果の議論が建設的になり、追加投資の承認も得やすい
これらは商業施設のAI導入が失敗する理由は?ROIを高める3つのステップで指摘される課題にも直結しており、理論と実践の両面から有効性が裏づけられています。
SHIFT AI for Biz研修で社内AI活用を加速する
ここまで紹介した成功事例の裏側には、組織全体でAIを使いこなす仕組みを築く工夫がありました。これを再現する近道として注目されているのがSHIFT AI for Biz研修です。商業施設の運営課題に合わせて設計されたプログラムで、導入後の“定着”をゴールに据えている点が特徴です。
ショッピングモール運営に特化したカリキュラム
研修はモール運営に関わる多様な部署を対象に、来店者分析・売上予測・バックオフィス業務効率化など現場課題に即したケーススタディを中心に構成されています。これにより、受講者は自分たちの業務にAIをどう活かすかを具体的にイメージしながら学べます。
実務に直結する演習と成功事例の共有
単なる座学ではなく、実データを用いた演習や、他施設で成果を上げた活用事例を取り入れたディスカッションを実施。研修終了時には、各部署が自社モールに合わせた具体的な活用プランを持ち帰ることができます。
導入から定着までを支援する継続サポート
研修後も、利用状況のモニタリングや定着度を測る評価レポートなど、継続的なフォロー体制を整備。学んだ知識を現場に根付かせるためのサポートにより、AI活用の文化を長期的に維持できます。
SHIFT AI for Biz研修を活用すれば、単なる技術導入に終わらず、「AIを日常的に使う組織」への変革を現実のものにできます。詳細は下記からご覧ください。
まとめ|商業施設でAI活用を「導入から定着」へ
ショッピングモールにおけるAI導入は、来館者増や売上向上を目指すうえで欠かせない取り組みです。しかしテナントごとのデータ分断、現場スタッフのリテラシー格差、経営層と現場のKPI不一致など、商業施設ならではの課題が社内活用を阻みがちです。
本記事では、これらの課題を突破するために
- 経営層と現場が目標を共有するAI活用戦略の策定
- 多店舗研修とリスキリングによる従業員教育
- ROIを定量的に測定し投資効果を可視化する仕組みづくり
という3つのステップを紹介しました。
部門横断で「AIを使う文化」を作り、成果を数値化して共有することが、定着を成功に導く決定打となります。
SHIFT AI for Biz研修は、これらの成功要因を再現し、商業施設運営に合わせたカリキュラムでAIを日常業務に根付かせる体制を提供します。
AIを「導入しただけ」で終わらせず、モール全体が自発的にAIを活用する組織へ進化させるために、ぜひこの機会に研修プログラムの詳細を確認してください。
導入検討を始める前に押さえたいポイント(FAQ)
AI導入を「使われる仕組み」に育てるには、計画段階でいくつかの疑問を解消しておくことが欠かせません。ここではショッピングモール運営者から特によく寄せられる質問と、その考え方を整理します。
- QAI導入後、社内活用が進まない場合にまず何から始めるべき?
- A
現状の業務プロセスとデータ環境を可視化することが第一歩です。
どこにボトルネックがあるかを把握しないまま追加施策を行うと、改善効果が測定しにくくなります。現状分析には、商業施設のAI導入が失敗する理由は?ROIを高める3つのステップを参考に、課題抽出とKPI設計を同時に進めましょう。
- Q研修はどのくらいの期間で成果が出る?
- A
SHIFT AI for Biz研修では、数週間から数か月単位で基礎知識の習得と現場実装を並行して進める設計になっています。初期段階で全スタッフが最低限のスキルを身につければ、早期にAI活用を日常業務へ組み込むことが可能です。
- Q投資回収(ROI)の目安は?
- A
AIの投資回収期間は施策の規模やデータ環境によって異なりますが、来店者分析や在庫管理など即効性のある領域から着手すると1年以内に効果を確認できるケースも多いです。詳細な費用試算や補助金活用のヒントはショッピングモール向けAI導入費用は?投資回収までの流れ・補助金情報を参照してください。
- Q多店舗を横断した教育はどう進めればよい?
- A
共通カリキュラムと段階的リスキリングが不可欠です。SHIFT AI for Biz研修では多店舗を対象にした標準化プログラムを提供しており、スタッフのリテラシー格差を短期間で埋められます。あわせてショッピングモールの社員教育をAIで効率化も確認すると、研修設計の参考になります。