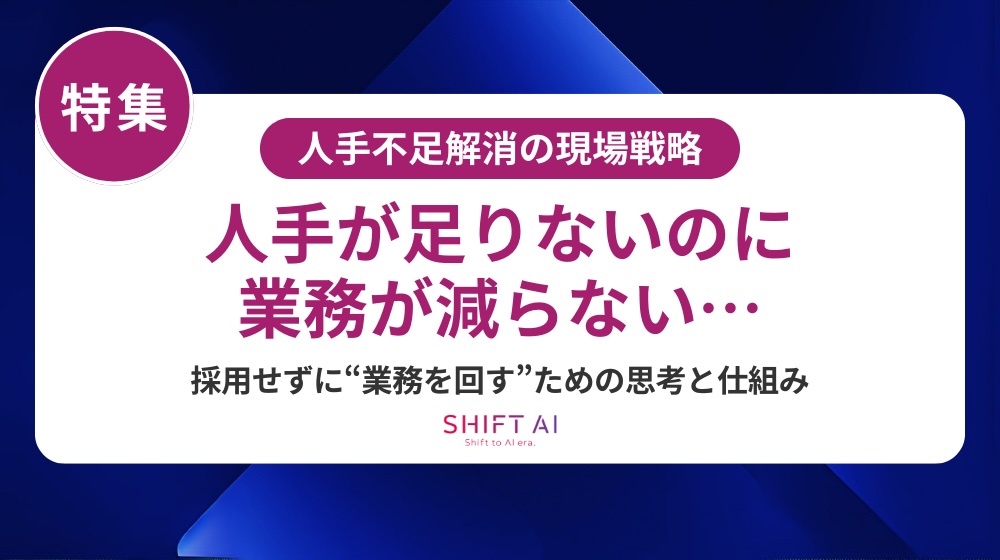「採ってもすぐ辞める」「スキルはあるのに戦力にならない」
人手不足に悩む企業にとって、これは他人事ではない現実です。
かつては「採用できればなんとかなる」と言えた時代もありました。
しかし現在は、採用市場の競争激化、ミスマッチの増加、定着率の低下など、“採るだけでは現場が回らない”時代に突入しています。
では、どうすれば限られた採用枠で、現場に貢献できる人材を採用できるのでしょうか?
キーワードは、“戦力になる人材”を見極めて採る採用戦略です。
本記事では、
- 人手不足時代に求められる「人材像」とは何か?
- 採ってはいけない人材の共通点
- ミスマッチを減らすための採用プロセス再設計
- 採用と育成をつなげて戦力化する方法
などを詳しく解説します。
「とにかく人を採る」から「活かせる人を採る」へ。採用のあり方を、今こそ再構築していきましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今、採用戦略の見直しが急務なのか
かつての採用活動は、「応募数を増やすこと」や「求人票を広く出すこと」が成功の指標でした。
しかし今は、応募数が増えても、現場で活躍できる人材に出会えないという悩みが、あらゆる業種で顕在化しています。
人手不足は「採用人数」では解決できない
人手が足りないのだから、とにかく人を採る――。
そうした考えは、今や通用しなくなりつつあります。
採用が成功したように見えても、
- すぐに辞めてしまう
- スキルがあっても馴染まない
- 教える時間がなく、戦力化されない
といった問題が起きれば、現場の混乱や管理コストがむしろ増える結果になります。
コストをかけても戦力化できない現実
採用には、求人広告、人材紹介、面接、研修など、膨大なコストがかかります。
それにも関わらず、「活躍できない人材」を採用してしまえば、投資が回収されないどころか、マイナスに働く可能性すらあるのです。
さらに、現場への“教育負荷”が高まり、ベテラン社員が疲弊するという副作用も起こりやすくなります。
「数」ではなく「質」を見極める時代へ
これからの採用戦略で求められるのは、「どれだけ採れるか」ではなく、「誰を採るか」「なぜその人を選ぶか」という視点です。
応募者のスキルや経歴を見るだけではなく、
- 自社の業務に本当に適応できるか
- 自走して学び、成長してくれるか
- 価値観や働き方が社風と合うか
といった、“活躍可能性”を見極める採用設計が必要不可欠なのです。
関連記事:人手不足を解消する15の方法|従来手法+AI戦略で効率化を実現する最新戦略
人手不足でも現場を支える“活躍人材”の3条件
「優秀なはずの人材を採用したのに、なぜか現場では活躍できない」
そんな声は、多くの現場で聞かれます。
その理由は、“優秀さ”と“現場での戦力化”は別物だからです。
ここでは、人手不足の現場でも即戦力として期待できる「活躍人材」の3つの共通点を紹介します。
①経験よりも「再現性」がある人
「前職で成果を出した」ことは確かに評価ポイントですが、その経験が自社の環境でも再現できるかは、まったく別の話です。
- 前職の成果はチームや仕組みによるものではなかったか?
- 現場の規模、商材、顧客層などが自社と一致しているか?
こうした点に目を向けると、「経験の再現性」が見えてきます。
つまり、「できた人」よりも「またできる人」を採ることが、活躍につながる鍵です。
②スキルよりも「適応力」がある人
どれだけ高いスキルを持っていても、職場の文化やスピード感に適応できなければ成果は出ません。
- 現場の進め方に合わせられるか
- コミュニケーションスタイルがマッチするか
- 「早く慣れる」力を持っているか
こうした“環境適応力”が、実は最も即戦力性に直結する要素だと、多くの企業が気づき始めています。
③モチベーションよりも「自走力」がある人
「やる気があります!」という言葉は頼もしいものですが、本当に求めたいのは、“やる気が続く人”“自ら動ける人”です。
- 目的が明確で、学び続ける意志がある
- 自ら情報を取りに行き、周囲と連携できる
- 指示がなくても主体的に動ける
こうした“自走力”を備えた人材こそが、少人数でも回る現場を支える貴重な戦力になります。
採用戦略を変える5つの打ち手
「戦力になる人材を採る」と言っても、属人的な“カン”や“相性”だけに頼っていては、再現性のある採用にはつながりません。
そこで必要になるのが、仕組みとしての“採用戦略の再設計”です。
ここでは、活躍人材を見極めて採用するための具体的な打ち手を5つ紹介します。
①“求める人物像”を明文化する(ペルソナ設計)
「いい人が来てくれれば…」という曖昧な基準では、本当に採りたい人には響きません。
まず行うべきは、
- 自社で活躍している人の共通点を洗い出す
- 求めるスキル・価値観・行動特性を具体化する
- 求人票や採用サイトに落とし込む
という採用ペルソナの設計です。
これにより、「来てほしい人に“刺さる”採用広報」が可能になります。
②「リアルな現場情報」でミスマッチを防ぐ
応募者にとって、職場環境や雰囲気は非常に重要な判断材料です。
実際に、入社後のギャップが離職理由になるケースも少なくありません。
- 一緒に働く人の紹介(動画・記事)
- 日常業務やチームの文化を発信
- 「大変なところ」も包み隠さず伝える
こうした情報発信により、応募者が自分に合うかどうかを事前に判断できるようになり、ミスマッチ採用のリスクを下げられます。
③選考評価は“現場で活躍する人”基準で設計する
よくある失敗が、「履歴書では優秀に見えるのに、現場で活躍できない」採用です。
これは、評価基準が“見栄え”や“過去の実績”に偏っていることが原因です。
- 面接での質問を「行動ベース(STAR法)」に変える
- ロールプレイや課題選考で“現場力”を見る
- 面接官の評価基準を明文化してブレをなくす
これにより、本当に“使える”人材かどうかを、選考段階で見極めやすくなります。
④オンボーディング体制を整えて離職を防ぐ
どんなに良い人材を採っても、入社直後の立ち上がりでつまずけば、離職につながることは珍しくありません。
- 研修やOJTの内容・期間を明確化
- メンター制度や1on1でのフォロー
- 期待値のすり合わせと評価の見える化
オンボーディングとは、「採用の最後」ではなく、「戦力化の最初のステップ」です。
ここが機能していないと、採用の価値は半減します。
⑤育成設計と連動することで戦力化を加速
採用は“ゴール”ではありません。
むしろ、“育てて活かす仕組み”と連動してはじめて価値が最大化されるのです。
- 採用ペルソナと育成カリキュラムを接続
- 早期フェーズでのスキルギャップを前提とした設計
- 育成の定着を測るKPIと連携したHRデータ活用
採用と育成を別々に考えるのではなく、「戦力を増やすための連続したプロセス」として捉えることが、人手不足時代の本質的な採用戦略です。
よくある“採用の失敗パターン”とその防ぎ方
「優秀な人材を採ったはずなのに、期待した成果が出ない」
――そんな採用の“ズレ”は、多くの現場で起きています。
ここでは、採用でよくある失敗パターンと、それを防ぐためのポイントを整理します。
スキル重視で採ったが、現場で浮いた
表面的なスキルに注目して採用すると、実務での対応力や周囲との関係構築がうまくいかず、現場に馴染めないケースが多発します。
▶防ぎ方
- 「できること」より「どう動くか」を確認
- チームで働く力や現場適応力を評価基準に組み込む
意欲重視で採ったが、育てる余裕がなかった
「熱意があります!」という言葉だけで採用すると、育成前提の設計ができていなければ、期待倒れになってしまうリスクがあります。
▶防ぎ方
- 入社後の成長ステップを明確にしておく
- 意欲を持続させるオンボーディング設計を重視する
文化が合わず、早期退職に至った
スキルも人柄も申し分ないのに、「この会社は合わない」と言われて辞められてしまうケースは非常に多いです。
▶防ぎ方
- 面接段階で会社の文化・期待されるスタンスを明示
- 価値観や仕事観をすり合わせる設問や面談を設計する
- 自社の「合う人/合わない人」を明文化しておく
採用失敗の多くは、“採る前”の情報設計と“見極め基準”の不在が原因です。
それらを可視化・言語化し、選考プロセスに落とし込むことが、失敗を防ぐ最善策となります。
SHIFT AI for Bizが提供する“活躍人材採用支援”とは
人手不足に悩む企業が、本当に必要としているのは――
「採れた人材が現場で活躍し、定着して、育っていく」こと。
SHIFT AIでは、採用を単なる人集めではなく、戦力化を前提とした“経営施策”としてとらえ、ペルソナ設計から育成連動型の仕組みづくりまで一貫してご支援しています。
①ペルソナ設計〜選考設計まで一気通貫支援
まずは「自社で活躍する人材像」の明文化からスタート。
既存の社員分析やヒアリングを通じて、
- 業務内容
- 評価基準
- 必要な資質・スキルセット
などを構造化し、「来てほしい人材」ではなく「活躍する人材」の条件を言語化します。
さらにその内容を、
- 求人票
- 採用サイト
- 面接評価シート
へと展開し、採用ブランディングから選考精度まで一気に整えます。
②面接官トレーニングで評価のバラつきをなくす
せっかくペルソナを作っても、面接官の評価が属人的でバラバラでは成果につながりません。
SHIFT AIでは、
- 面接の質問設計(行動評価型:STAR法)
- 評価項目ごとのガイドライン整備
- 面接官トレーニングの実施
などにより、“誰が見ても同じ基準で判断できる選考体制”を構築。
採用の再現性を高め、失敗リスクを最小化します。
③育成設計とセットで“現場が回る人材”を採用
最も重要なのは、採った人材をどう“活かすか”の視点をあらかじめ採用戦略に組み込むことです。
SHIFT AIでは、
- 採用ペルソナと育成カリキュラムの連動
- オンボーディング期間の設計支援
- 生成AIや業務マニュアルとの組み合わせ支援
を通じて、採用〜育成〜戦力化までが1本につながった“人材活用の仕組み”を提供します。
まとめ|“育てて活かす”前提で人を採る戦略が、生き残る
人手不足という課題に対し、「とにかく採る」「人が来ればなんとかなる」
という発想では、もはや企業は生き残れません。
これからの採用戦略で問われるのは、
- どんな人を採れば現場が回るのか
- 採った人をどう育てて戦力化するのか
- 採用と育成をどう“仕組み”としてつなぐのか
という本質的な問いへの答えを持っているかどうかです。
SHIFT AIでは、採用・育成・業務改善を一体で設計し、“活躍できる人材が辞めずに育つ”組織づくりをご支援しています。
採用戦略を「単発の施策」から「再現性ある仕組み」へ。その第一歩として、ぜひ下記資料をご活用ください。
- Q未経験でも活躍できる人はどう見極めればいい?
- A
前職での行動・再現性・学びへの姿勢を評価軸に入れることで、「ポテンシャル人材」の見極めが可能です。
- Qペルソナ設計って何から始めればいい?
- A
まずは「今活躍している社員」に着目し、スキル・行動・価値観の共通項を洗い出すことから始めます。
- Q採用にAIを活用できますか?
- A
面接ログの分析や、応募者傾向の可視化などに生成AIやRPAツールを組み合わせた活用が可能です。
- Q面接官の評価にばらつきがあります…
- A
質問項目・判断基準・評価フローを標準化することで、属人的な判断をなくし、再現性を高められます。
- Q採用だけでなく育成も相談できますか?
- A
はい、SHIFT AIでは採用設計と育成設計を一体でご支援しています。資料内でも詳しくご紹介しています。