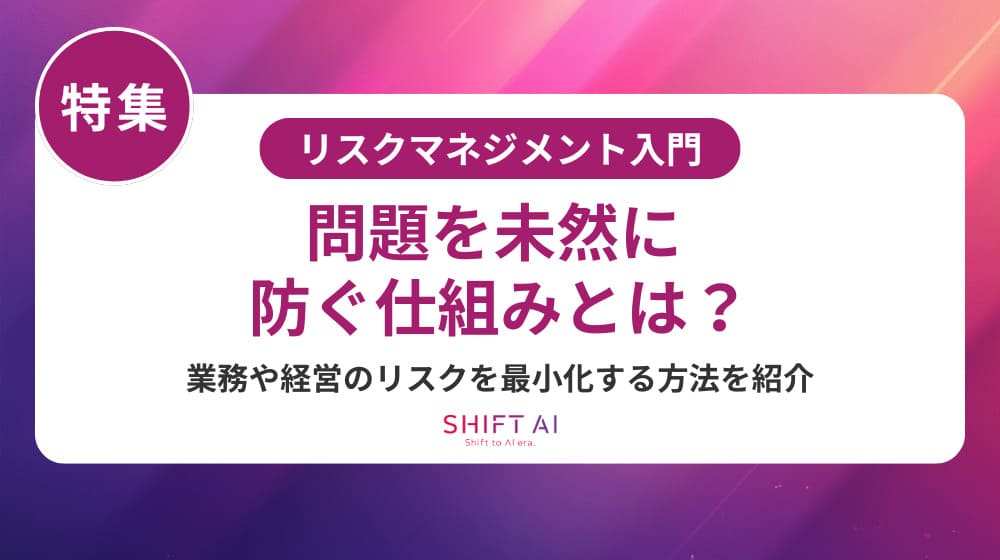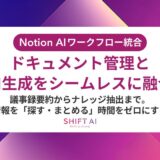リスクマネジメントの重要性は理解していても、実際に運用しようとすると「専任の担当者がいない」「他業務との兼務で手が回らない」「ノウハウが社内に蓄積されていない」といった壁に直面する企業は少なくありません。人的・時間的なリソースが不足している状況では、どうしても形だけの管理に終始してしまい、重大なリスクを見落とす危険もあります。
本記事では、リソース不足でも実効性のあるリスクマネジメントを進める方法 に焦点をあてます。限られた人員・時間の中で優先度をつけて対応する工夫、外部リソースや生成AIを活用した効率化の手法、そして社内体制の整え方まで、段階的に整理しました。
まずは「なぜリスクマネジメントはリソース不足に陥りやすいのか」を明らかにし、そこから現実的な解決策を一緒に考えていきましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜリスクマネジメントはリソース不足に陥りやすいのか
リスクマネジメントは「重要性は理解されているのに、なかなか実務で手が回らない」業務の代表格です。背景にはいくつかの共通要因があります。
専任部署を置けない
特に中小企業では、リスク管理専任の部署を設ける余裕がなく、総務や情報システム部門の担当者が兼務するケースが多く見られます。その結果、専門性が十分に確保されず、必要な施策が後手に回ってしまいます。
成果が短期的に見えにくい
リスクマネジメントは「問題が起きなかったこと」自体が成果であるため、売上やコスト削減のように数値で可視化しにくい側面があります。そのため、経営層から予算や人員を優先的に確保しづらいのが現状です。
兼務による担当者の疲弊
担当者は日常業務に加えてリスク管理まで抱えることになり、チェックやレビューが形骸化することがあります。結果として「わかってはいるけれど後回しになる」状態が常態化しやすくなります。
経営層の理解不足
「リスクは現場で何とかすればよい」という認識が強いと、リソースの割り当てが後回しになります。本来は経営戦略と直結するテーマであるにもかかわらず、現場任せになりがちな点もリソース不足を招く原因です。
リソース不足が招く具体的なリスク
リスクマネジメントに必要な人材や時間が不足していると、管理体制が表面的になり、見えないところで重大なリスクが拡大していく恐れがあります。特に注意すべき影響は次のとおりです。
重大リスクの見落とし
リソース不足でチェックの頻度や精度が下がると、潜在的なリスクを見逃してしまいます。たとえば法規制改正への対応が遅れれば、罰則や業務停止といった深刻な事態を招く可能性があります。
属人化による対応遅れ
限られた人員で管理していると、一部の担当者にノウハウや情報が集中しがちです。その結果、担当者の不在や異動で対応が滞り、初動が遅れて被害が拡大するケースがあります。
監査・規制対応での不備
外部監査や取引先のコンプライアンス調査の際、十分な記録やエビデンスを用意できずに不備を指摘されることがあります。これは信用低下や契約解消につながりかねません。
担当者の負荷増大
人手不足の中でリスク管理を押し付けられると、担当者が疲弊し、かえってヒューマンエラーを招くリスクが高まります。これは「リスクを管理するはずの仕組みが新たなリスク要因になる」という逆説的な事態です。
関連記事:
リスクマネジメントが失敗する5大理由と改善策|形骸化を防ぐ実践ステップ
限られたリソースでもできるリスクマネジメントの工夫
人的・時間的なリソースが不足している状況でも、工夫次第でリスクマネジメントの実効性を高めることは可能です。ポイントは「すべてを完璧に行おうとせず、重要な部分に集中する」ことです。
優先順位付けで集中する
リスクを一覧化したうえで、「発生確率」と「影響度」の2軸で評価し、マトリクスを用いて優先度を決めます。すべてのリスクに同じ力を割くのではなく、致命的なインパクトを持つものから対応することで、限られた時間を有効に活用できます。
チェックリストで標準化する
担当者ごとに判断がばらつかないよう、チェックリストや簡易マニュアルを整備します。これにより経験の浅いメンバーでも最低限の確認ができ、属人化を防ぐ効果も期待できます。
小さくても定期的に回す
「年に一度の大規模レビュー」ではなく、「月に1回の簡易チェック」など小さな単位で定期的に回す仕組みを作ると、負担が分散され、継続性が高まります。
部署横断でナレッジを共有する
総務・情報システム・営業など複数部署が関わるリスクは、情報が分断されやすい分、見落としにつながります。ExcelやGoogleスプレッドシートなどシンプルな共有ツールを使うだけでも、リスク情報の見える化と引き継ぎの効率化につながります。
関連記事:
リスクマネジメントの方法を完全解説|基本フロー・実務手法・AI時代の効率化
リソース不足を前提にした優先度設定の実例
リソースが限られている企業では「どこまで対応すべきか」を決める基準が重要です。
以下は、リスクの発生確率と影響度を掛け合わせたシンプルなマトリクスの一例です。
| 発生確率\影響度 | 高い | 中程度 | 低い |
|---|---|---|---|
| 高い | 最優先で対応(監査不備、法令違反リスクなど) | 優先的に対応 | 状況に応じ対応 |
| 中程度 | 優先的に対応 | 対応検討 | 後回し可 |
| 低い | 状況に応じ対応 | 後回し可 | モニタリングのみ |
このように、重大リスクに絞って対応を進めれば、人的・時間的に限られた中でも「最低限守るべきポイント」を見失わずにすみます。
表を社内で共有すれば、担当者間で判断基準が統一され、属人化の防止にもつながります。
外部リソースの活用で不足を補う
自社だけでリスクマネジメントを完結させるのが難しい場合、外部リソースを積極的に活用することが有効です。専門知識や人材を一時的に取り入れることで、限られたリソースでも効果的に対応できます。
コンサルティングや専門家の支援
リスクマネジメントの体制構築や規程づくりを、外部の専門家に依頼する方法です。初期段階からプロの知見を取り入れることで、社内で試行錯誤するよりも早く基盤を整備できます。
部分的なアウトソース
監査資料の作成やリスク評価の一部をアウトソースするなど、業務の一部だけを外部に任せる方法もあります。自社の中核業務にリソースを集中できる点がメリットです。
研修サービスの活用
「ノウハウ不足」を解消するには、外部研修が効果的です。現場社員のリスク感度を高め、日常業務に落とし込むスキルを短期間で習得できます。特に生成AIを組み合わせた最新の研修は、効率性と実効性を両立できます。
コスト・メリットのバランスを考える
外部リソース活用は費用がかかるため、コストと得られる効果を比較して判断することが重要です。社内にゼロから仕組みを構築するよりも、外部知見を取り入れる方が結果的に安価で済む場合も少なくありません。
生成AI・ツールを活用した効率化
リスクマネジメントは「情報収集・整理・報告」など定型化できる業務が多いため、ツールや生成AIを導入することで大幅に効率化できます。リソース不足に悩む企業にとっては、最小限の人員で最大の成果を出す有効な手段となります。
リスク情報収集の自動化
法改正や業界ニュース、事故情報などのリスク関連データを、AIにモニタリングさせることで担当者の負担を軽減できます。人力での調査に比べ、見落としが減り、スピードも向上します。
リスク評価表の自動生成
生成AIを活用すれば、入力したリスク事象をもとに「発生確率×影響度」のマトリクスや優先度リストを自動で作成できます。短時間で精度の高い判断材料を得られる点がメリットです。
レポート・議事録作成の効率化
会議の記録や経営層への報告資料は、AIの文章生成を活用することで作成スピードを数倍に高められます。担当者は「判断・意思決定」に集中でき、付随業務の時間を削減できます。
社内マニュアルやFAQ整備
AIを活用すれば、過去の問い合わせや事故対応の記録をもとにFAQを自動生成できます。これにより「同じ質問に繰り返し答える」工数を削減し、ノウハウ不足の解消にもつながります。
生成AIを含むリスクマネジメント全体像はこちら:
【2025年版】リスクマネジメント完全ガイド|種類・プロセス・AI活用まで徹底解説
リソース不足を前提にした社内体制づくり
外部リソースやツールを活用するだけでなく、社内の体制をどう整えるかも重要です。リソース不足を前提としながらも、継続して回せる仕組みを作ることで、リスクマネジメントを組織に根付かせられます。
経営層の理解を得る
リスクマネジメントは経営戦略と直結するテーマです。経営層に対しては「リスクが顕在化した場合の損失額」「競合他社の失敗事例」など定量・定性の両面で説明することで、リソース投資への納得感を高められます。
小さな成功事例を積み上げる
すべてを一気に導入するのではなく、まずは一部のリスクを対象に小規模に取り組み、成果を見せることが効果的です。小さな成功体験を積むことで、組織全体にリスク感度が広がり、追加リソースの確保につながります。
社員教育と研修でリスク感度を底上げ
担当者だけに任せるのではなく、社員全員に「リスクは自分ごと」という意識を持たせることが不可欠です。研修やワークショップを通じて、リスクを早期に察知・共有できる文化を根付かせると、少人数でも強い体制が築けます。
まとめ|リソース不足でも始められる一歩
リスクマネジメントは「十分なリソースが整ってから着手するもの」ではありません。むしろ限られた人員や時間の中で、優先度を明確にし、小さな仕組みから始めることが重要です。
- 優先順位付けと標準化 で最小限の労力でも確実に対応できる仕組みをつくる
- 外部リソースや専門家 を活用してノウハウ不足を補う
- 生成AIやツール を使い、情報収集や文書作成などの業務を効率化する
- 社内教育・研修 を通じて、組織全体でリスク感度を高める
こうした積み重ねが、リソース不足の環境でも実効性のあるリスクマネジメントを実現する近道です。
SHIFT AI for Biz では、
- 人的リソースが不足していても、AIを活用することで効率的にリスク情報を収集・分析
- 研修プログラムを通じて、現場社員のリスク感度を底上げし、属人化を防止
- 実践的な演習により「すぐに社内で使える仕組み」を整備可能
「リソースが限られているからこそ、最小限の力で最大の成果を出す」——その一歩を踏み出すサポートをしています。

よくある質問|リソース不足でも始められるリスクマネジメント
- Q人的リソースが少なくてもリスクマネジメントは実施できますか?
- A
可能です。すべてを完璧に管理する必要はなく、まずは優先度の高いリスクから対応すれば十分に効果があります。チェックリストやマトリクスを用いて、影響が大きいものに絞り込むのがポイントです。
- Qノウハウが社内にない場合、どう始めればよいですか?
- A
まずは外部の研修やガイドラインを活用し、基本的な枠組みを社内に取り入れることがおすすめです。少人数であっても研修を通じてリスク感度を高めることで、現場での判断力が強化されます。
- Q外部リソースを使うとコストが高くなりませんか?
- A
初期投資は必要ですが、重大な事故や規制違反が発生した際の損失額と比較すると費用対効果は大きいと言えます。部分的なアウトソースや短期の専門家支援を組み合わせれば、コストを抑えながら効果を得られます。
- Q生成AIを活用すると、どんな業務が効率化できますか?
- A
リスク情報のモニタリング、リスク評価表の作成、会議記録やレポートの自動化、社内FAQの整備などが挙げられます。特に情報収集や文書化といった定型業務の工数削減に効果的です。
- Q小規模企業でもリスクマネジメントは必要ですか?
- A
必要です。むしろ人員や資金が限られているからこそ、一度のトラブルで受けるダメージは大きくなります。小さくてもリスクを把握し、最優先のものから対応する仕組みを整えることが重要です。