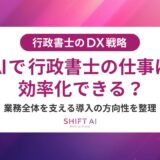自治体のDX推進は、国の方針や補助制度によって加速しているように見えます。
しかし、現場レベルでは「ツールを導入したのに成果が出ない」「職員が思うように動かない」といった課題がいまだ根深いのが現実です。
その原因は、予算や制度ではなく――“人と組織文化”の中にあります。
DXはシステム導入のプロジェクトではなく、“人の意識と行動を変える取り組み”です。
本記事では、自治体DXが進まない本質的な理由を「リーダーシップ」「組織文化」「学びの仕組み」という3つの視点から整理し、現場が自走するための実践的なヒントを紹介します。
構造的な課題を整理した基礎編はこちら:
自治体DXが進まない理由とは?7つの課題と解決策を徹底解説
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
デジタル化は進んでも、DXが進まない理由
行政の現場では、電子申請やRPAの導入など「デジタル化」は確実に進んでいます。
しかし、業務の効率化や住民サービスの改善といった“成果”につながらないという声は少なくありません。
その背景にあるのは、ツールの問題ではなく――人と組織の変化が伴っていないことです。
ここでは、デジタル化とDXの違いを整理し、自治体が“自走できない構造的な理由”をひもときます。
課題|ツール導入だけで終わる「見かけのDX」
多くの自治体では、RPAやクラウド、電子申請システムの導入が進み、一見するとDXが着実に進展しているように見えます。
しかし、実際には業務プロセスや意思決定の方法が旧来のままというケースが多く、「導入したこと」が目的化してしまっているのが現状です。
その結果、データは活用されず、職員の業務負担も減らない――
まさに“ツール導入で止まる見かけのDX”が各地で発生しています。
原因|「仕組み」ではなく「人」が変わっていない
DXとは、単にITツールを導入することではなく、人と組織が変化し続ける仕組みをつくることです。
しかし多くの自治体では、「使い方の研修」で終わってしまい、職員が自分の業務にどう応用できるかを考える機会が不足しています。
また、現場の課題を吸い上げる仕組みがなく、「誰かが決めてくれるまで待つ」という受け身の姿勢が根付いている場合も少なくありません。
こうした状況では、技術だけが先行し、人の意識が変わらないために、
“真のDX”が動き出さないのです。
解決策|職員が課題を見つけ、解決する力を育てる
DXを実現するための出発点は、職員一人ひとりが「自分の業務を変えられる」実感を持つことです。
生成AIを活用すれば、資料作成や住民対応、データ分析などの定型業務を自動化でき、
時間をより付加価値の高い業務に使えるようになります。
この「成功体験の積み重ね」が、組織に“できる”文化を生み出します。
AIリテラシーを中心としたリスキリングを進め、学びが現場で循環する仕組みを持つことで、
自治体DXは“仕組みとして続く”段階へと進化します。
関連記事:
自治体DXを成功に導く5ステップ|現場課題とAI人材育成の実践法
リーダー不在が招く“責任の空白”と停滞構造
自治体DXの現場では、「誰が推進の責任を持つのか」が曖昧なまま進むケースが少なくありません。
DX担当部署が設けられていても、最終判断を下すリーダーが不在だと、意思決定が止まり、現場の動きも鈍化します。
この“責任の空白”こそが、DXを停滞させる最大の要因のひとつです。
ここでは、リーダー不在がもたらす構造的な課題と、その打開策を整理します。
課題|意思決定が曖昧で、誰も動けない組織
多くの自治体では、「DXを進める部署」は存在しても、プロジェクトを最終的に方向づけるリーダーが定まっていないことが多いのが実情です。
そのため、各部署が自分の範囲内で動くにとどまり、全体としての統一的な方向性が失われてしまいます。
結果として、「結局、誰の判断で進めるのか」「どのタイミングで決めるのか」が不明確なまま、施策が棚上げになり、DX推進が止まってしまう――。
こうした“責任の空白”が、現場のモチベーション低下にもつながっています。
原因|「専門知識」偏重と“旗振り役”の欠如
DXのリーダーと聞くと、「ITに詳しい人」「システムに強い人」を想像しがちです。
しかし、本当に必要なのは技術を理解する力ではなく、人を動かす力です。
多くの自治体では、情報政策課やシステム担当者がDXの中心を担う一方、現場職員や管理職との連携が弱く、全庁的な推進体制に結びついていません。
また、トップ層がDXの意義を十分に理解していない場合、現場の取り組みが“点”で終わり、“線”としてつながらない構造が生まれます。
つまり、「誰が旗を振るか」が明確でないまま進むことが、DX停滞の根本的な原因になっているのです。
解決策|“共感型リーダーシップ”で人を動かす
自治体DXを前進させるには、専門知識よりも“共感”を軸に職員を巻き込む共感型リーダーシップが不可欠です。
庁内の壁を越えて人をつなぎ、現場の課題を理解しながら方向性を示せる人材――
それが、DXを動かす「変革リーダー」です。
特に重要なのは、課長・係長などのミドル層の育成。
この層が「現場の課題を理解し、上層部と現場を橋渡しできる存在」になることで、組織全体の流れが変わります。
組織文化の壁|前例踏襲と“失敗を許さない空気”
自治体DXを阻むもう一つの大きな要因が、組織文化の硬直化です。
どれほど優れた仕組みや制度が整っても、現場に「挑戦しても評価されない」「失敗は許されない」という空気があれば、職員は新しい試みに踏み出せません。
ここでは、前例主義が生む停滞の構造と、挑戦が息づく文化を育てるためのアプローチを見ていきます。
課題|挑戦が評価されず、変化が止まる文化
多くの自治体で共通するのは、「前例がないことはやらない」という姿勢です。
過去の成功モデルを踏襲することが安全とされる一方で、現場では「反対される」「無駄になるかもしれない」との不安から、新しい提案を避ける傾向が根強くあります。
結果として、職員は「指示されたことをこなすだけ」の受け身姿勢に陥り、小さな改善の芽すら摘まれてしまう――。
この“挑戦が報われない文化”が、自治体DXを最も深く停滞させています。
原因|心理的安全性とナレッジ共有の欠如
「失敗は許されない」という空気の背景には、組織の心理的安全性が確保されていないという根本課題があります。
失敗を責める文化では、誰も新しい試みに名乗りを上げません。
また、挑戦や失敗から得た学びを共有する仕組みがないため、一度起こったミスが個人の責任として終わり、組織の成長につながらない構造が続いています。
その結果、改善サイクルが回らず、「経験が蓄積しない組織」となり、DXのような継続的変革が根づかないのです。
解決策|挑戦を称え、学びを共有する仕組みづくり
DXを定着させるためには、「挑戦を称え、学びを共有する文化」への転換が欠かせません。
小さな改善や失敗の経験を共有し、それを庁内全体の知見として活かす――
そんな環境が整えば、現場の挑戦が継続的な価値に変わります。
具体的には、成功・失敗を問わず改善事例を共有する「ナレッジ会議」の実施や、AIツールを活用した事例データベースの構築が効果的です。
こうした仕組みが職員の心理的安全性を高め、挑戦が日常化する文化を生み出します。
関連記事:
自治体DX人材育成の完全ガイド|“仕組みで育てる”研修設計とスキルモデル
DXを“共創”で進める自治体が成功している理由
DXを単独で進めようとすると、自治体はすぐに限界に直面します。
人材・ノウハウ・リソースの制約を抱える中で、行政だけで完結しようとする構造が、変革を止めてしまうのです。
いま成果を上げている自治体ほど、外部との“共創”を軸にDXを推進しています。
ここでは、共創がもたらす成功のメカニズムを整理します。
課題|行政内だけで完結しようとする閉鎖構造
多くの自治体では、DXを「庁内だけで進めるべき業務」と捉えがちです。
情報政策課などの特定部署に負荷が集中し、外部の専門家や他自治体との連携が進まない――
その結果、発想が固定化し、業務改善も小さな範囲で止まってしまいます。
また、外部との関わりを「委託」「発注」として扱う文化も根強く、「共に考える」「共に実行する」姿勢が生まれにくいことも課題です。
この閉鎖的な構造こそ、自治体DXの進化を阻む大きな壁といえます。
原因|外部との協働を「委託」と誤解している
DXにおける“共創”とは、単なる外注ではなく、現場職員と外部専門家が一体となって課題を発見し、改善策を設計するプロセスを指します。
しかし、多くの自治体ではベンダー任せの導入に終始し、自分たちの課題設定や改善設計を外部に委ねてしまうケースが少なくありません。
結果として、ツール導入後に現場が動かず、「結局、何のために導入したのか」が見えなくなる。
これは、“共創の目的”を誤解していることが原因です。
DXは「誰かにやってもらう改革」ではなく、「共に進める学習プロセス」なのです。
解決策|“共創型DX”で学び合う文化を育てる
成功している自治体に共通するのは、外部パートナーと共に学び、改善を繰り返す“共創型DX”の文化が根づいていることです。
AIチャットボットやデータ分析などの導入を、単なるシステム案件ではなく「人材育成の機会」として捉えている点が特徴です。
たとえば、AI導入を進める際に、外部専門家が現場職員と一緒に業務プロセスを見直し、
改善提案を職員自身が作成する――こうした協働のプロセスが、組織に「自分たちで変えられる」感覚を定着させます。
職員が変わる仕組みづくり|AIリテラシー×リスキリングの実践
DXを進めるうえで、最も重要なのは“人が変わる仕組み”を持つことです。
一部の担当者だけが研修を受けても、現場全体の意識が変わらなければ、改革は長続きしません。
「学びが続き、行動に結びつく仕組み」を整えることこそ、DXを文化として根づかせる鍵です。
ここでは、リスキリングを中心に、職員が自ら動き出す自治体づくりの実践法を解説します。
課題|学んでも現場に定着しない“研修イベント化”
多くの自治体で実施されているDX研修は、一度きりのイベント型にとどまっています。
受講直後は意識が高まっても、日常業務に戻ると元に戻ってしまう――。
この“学びの断絶”が、自治体DXの定着を妨げています。
また、研修内容が実務に結びつかない場合、
「結局、現場では使えない」「研修で終わる」といった声も生まれやすく、職員の意欲低下にもつながっています。
研修を“学ぶ場”ではなく、“変わるきっかけ”として機能させる設計が必要です。
原因|“学び→実践→共有”の循環がない
研修が定着しない最大の理由は、学びを現場で試し、共有する仕組みがないことです。
学んだ内容を実践に活かすサイクルがなければ、知識は一過性のものになってしまいます。
また、多くの自治体では、研修を担当部署が管理し、他部署への展開が限定的です。
せっかく得た知見も組織全体に波及せず、個人の経験で終わってしまうケースが目立ちます。
“学びの循環”を生み出せるかどうかが、DXを継続できる自治体とそうでない自治体の分岐点になります。
解決策|AI研修を軸にした“自走する学び”の仕組み
職員が変わるためには、自分の業務を改善できる成功体験を持つことが不可欠です。
その実現に有効なのが、生成AIを活用したリスキリングプログラムです。
AIを活用すれば、資料作成・問い合わせ対応・集計作業などを自動化でき、日常業務の中で“変化の実感”を得られます。
この体験が「自分でもできる」という意識を生み、組織全体の行動変化につながります。
さらに、学びを共有する仕組みを持つことで、成功事例が庁内に循環し、“挑戦が日常になる文化”が育ちます。
リスキリングは、単なるスキル習得ではなく、DXを続ける組織文化をつくるための仕組みなのです。
まとめ|DXを動かすのは、システムではなく“人”
自治体DXが進まない本当の理由は、システムや制度ではありません。
変革の原動力になる“人”が育ち、挑戦を支える文化が根付いているかどうか――そこにすべてがかかっています。
成功している自治体には共通点があります。
それは、リーダーが明確で、職員が挑戦でき、学びが循環していること。
つまり「人が動く仕組み」ができているのです。
どれほど優れた技術を導入しても、それを使いこなす人が育たなければ、DXは形だけの改革に終わってしまいます。
これからの自治体に求められるのは、“ツール導入のDX”ではなく、“人が変わるDX”。
生成AIをはじめとする新しい技術を、職員一人ひとりが自分の力として使いこなせるようになることが、真の変革のスタートです。
変わるのを待つのではなく、自ら変わる。
いま、その第一歩を踏み出すときです。

よくある質問|自治体DXが進まない原因と進め方に関する疑問を解決
- Qなぜ自治体のDXは民間企業よりも進みにくいのでしょうか?
- A
自治体の場合、組織構造や意思決定のプロセスが多層的で、迅速な判断が難しい点が大きな要因です。
また、前例踏襲や法制度上の制約もあり、民間のように柔軟な改善が進みにくい傾向があります。そのため、まずは現場が自ら考え、改善できる人材を育てることが重要です。
- QDX推進のためのリーダーは、どの部署が担うのが理想ですか?
- A
「情報政策課」や「企画課」など特定部署に任せきりにするのではなく、庁内横断的な推進体制をつくるのが理想です。
特に現場を理解しているミドル層(課長・係長クラス)が、各部門をつなぐリーダーとして機能するとDXは進みやすくなります。
この層が育つことで、現場の自発的な改善サイクルが生まれます。
- QDX研修を実施しても定着しない場合、どんな点を見直せばよいですか?
- A
多くの自治体が陥るのは、「研修をイベント化してしまうこと」です。一度の講義で終わると、現場での実践につながりません。
“学び→実践→共有”を繰り返す仕組みを持つことが、DX人材を定着させるポイントです。
- Q生成AIを自治体業務で活用するメリットはありますか?
- A
はい。文章作成、問い合わせ対応、データ整理など、多くの業務で時間短縮と品質向上を実現できます。
とくに、AIをうまく使うことで職員の思考が“作業から企画へ”とシフトし、住民サービスの質を高められます。ただし、情報管理・セキュリティへの配慮は必須です。
- QDXを成功させている自治体の共通点は?
- A
成功している自治体の多くは、
- 明確なビジョンをトップが共有している
- 現場の挑戦を評価し、失敗を許容する文化がある
- 職員のスキルアップ支援が仕組み化されている
という3点を実現しています。これらはすべて、“人が変わる仕組み”を持っているかどうかに直結します。
- Q小規模自治体でもDXを進めることは可能ですか?
- A
もちろん可能です。
むしろ、意思決定が早く、部門間の距離が近い小規模自治体ほど“全庁一体の変革”が実現しやすい傾向にあります。
限られた人員でも、AIツールと外部連携を活用した共創型DXにより、効果的な改革を進められます。