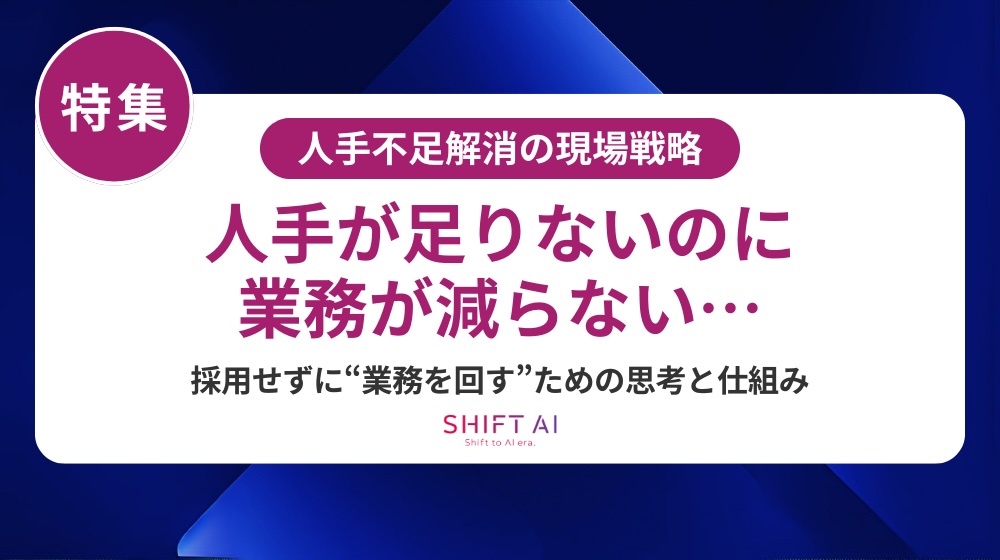「採用しても、すぐに辞めてしまう」
「そもそも応募がほとんど来ない」
「現場が疲弊し、離職が続いている」
中小企業を悩ませる「人手不足」は、もはや一時的な課題ではありません。少子高齢化、都市部への人材集中、業務の属人化など、さまざまな要因が重なり、経営・現場の両面で深刻なインパクトを及ぼしています。
しかし一方で、限られたリソースの中でも人手不足を乗り越え、成果を上げている企業が存在するのも事実です。
本記事では、製造・建設・介護・小売といった業種における実際の成功事例を7つの切り口で紹介します。
もし、業務効率化や社内スキル強化に向けて生成AIの導入・研修に関心がある方は、下記の資料をご活用ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
人手不足がなぜ今、深刻なのか?業界別の背景を解説
日本全体で人手不足が問題視されて久しい中、とくに中小企業では「対策を打ちたいが、何から始めればいいか分からない」という声も多く聞かれます。人手不足の原因は単一ではなく、業種や企業規模、地域によっても大きく異なります。
まずは、中小企業を取り巻く環境変化と、業界別の課題構造を整理してみましょう。
中小企業を取り巻く環境変化
日本の労働市場では、かつてないスピードで構造的な変化が進んでいます。とくに中小企業は、限られた経営資源のなかで、採用・定着・教育といった人材課題に向き合わざるを得ない状況です。
最大の要因は、少子高齢化による労働人口の減少です。2024年時点で15歳〜64歳の生産年齢人口は全人口の59.4%と、過去最低水準に落ち込んでおり、今後も右肩下がりが続くと予測されています。
- 都市部への人材流出
- 若年層の中小企業離れ(知名度・待遇差)
- 働き方の多様化によるマッチング難易度の上昇
といった複合的な要因により、地方・中小企業ほど採用難の影響を強く受けているのが実態です。
一方で、DXや生成AIなどの新技術が浸透するなかで、「人を増やす」以外の解決策──“業務の再設計”による人手不足解消に取り組む企業も現れはじめています。
出典:統計局ホームページ|人口推計 2024年(令和6年)1月報
業界別の人手不足の実態(製造・建設・介護・小売など)
人手不足の深刻度や要因は、業界によって大きく異なります。ここでは、とくに中小企業が多く存在する4つの業種に絞って、その特徴を見ていきましょう。
<製造業>
慢性的な人手不足に加え、技術継承が進まない「ベテラン偏重型」構造が課題に。若手人材の確保が難しく、現場では多能工化や業務自動化の導入が急務となっています。
<建設業>
高齢化率が突出しており、今後10年で団塊世代の大量離職が控えている分野です。採用は常に困難で、外国人技能実習生・協力会社依存など、外部リソースに頼らざるを得ない現状も見られます。
<介護業界>
深刻な人材不足の象徴とも言われる業界で、**離職率の高さと採用難の“二重苦”**に直面しています。人間関係や労働負荷に起因する離職も多く、「定着」を重視した職場改革が求められています。
<小売・サービス業>
コロナ禍以降、パート・アルバイト人材の流動化が進み、現場の人員計画が不安定に。営業時間の短縮や非接客化の動きも進んでおり、現場の業務設計を見直す企業が増加しています。
こうした各業界の実情を踏まえると、もはや“人を増やす”だけでは限界があることは明らかです。
関連記事
人手不足が企業に与える影響とは?5つの深刻な問題と生成AI活用による効果的な対策
成功企業に共通する【3つの成功要因】とは?
成功事例を見て「すごいけど、うちには無理そうだ」と感じた方もいるかもしれません。
ですが、実際に成果を出している企業の多くは、必ずしも潤沢な予算やリソースがあったわけではありません。
では、なぜ実行できたのか?
どのようなプロセスを踏んだから定着したのか?
ここでは、7つの事例に共通していた「成功の地盤」となる3つの要因を解説します。
① 課題を可視化し、現場の事実に向き合っていた
「なんとなく人が足りない」ではなく、「いつ・どこで・どの業務に・どれだけの人手が足りないか」を具体的に数値で把握していたことが共通点のひとつです。
日報やシフト表を集計し、業務ごとの工数を見える化することで、「増員すべき領域」と「改善で効率化できる領域」を切り分けていました。
これにより、的外れな施策ではなく“本当に効果のある打ち手”を選択できていたことが成果につながっています。
② 複数の打ち手を“組み合わせ”て実行していた
成功している企業は、単一の手法に依存していませんでした。たとえば「採用広報+社内研修」「業務効率化+定着支援」「シフト柔軟化+心理的安全性向上」など、複数の要素を同時に設計している点が共通しています。
なぜなら、人手不足の原因は一つではなく、構造的かつ複合的なものだからです。「〇〇さえやれば解決する」という単発の施策では、根本改善につながらないという教訓を活かしていたといえます。
③ 教育・研修に継続的な投資をしていた
採用が難しい時代だからこそ、「採った人を辞めさせない」「戦力化を早める」ことが重要です。
成功事例の多くでは、入社後の育成設計やリスキリング研修に力を入れており、それが定着率や業務効率の向上に直結していました。
とくに最近では、業務効率や社員の意欲を高める手段として「生成AI研修」の導入も注目されています。
関連記事
AI時代を勝ち抜くためのAI人材戦略!不足の現状や育成・活用まで
あなたの会社でもできる!【対策チェックリスト+導入ステップ】
ここまで紹介した成功企業も、最初からすべてを整えていたわけではありません。むしろ、「小さく始めて、徐々に仕組みに落とし込んでいった」事例がほとんどです。
この章では、人手不足解消に向けて自社で取れる打ち手を整理するための4ステップを紹介します。
チェックリストや実行フェーズを活用して、あなたの会社でも無理なく始められる流れを掴んでください。
ステップ① 現状把握チェックリスト:自社の詰まりポイントを洗い出す
まずは、感覚や印象ではなく、「事実ベース」で課題を把握することが第一歩です。
以下のようなチェックリストで、どこに課題が集中しているかを見える化しましょう。
<チェック項目:YES / NO>
採用募集を出しても、1ヶ月以上応募がないことがある □ YES / □ NO
業務マニュアルが整備されていない or 属人的な作業が多い □ YES / □ NO
若手社員の離職が3年以内に続いている □ YES / □ NO
シフト調整に毎週多くの工数がかかっている □ YES / □ NO
社内研修の仕組みや育成の体制が整っていない □ YES / □ NO
YESが多いほど、解決優先度が高い“構造的課題”を抱えている可能性があります。
ステップ② 自社のリソースに合った打ち手を優先順位づけする
すべてを一気に解決することはできません。以下のように、自社の「実行可能性」と「影響度」で打ち手をマッピングし、“今すぐできる”ことから始めるのが成功への近道です。
- 即実行可能かつ効果大 → 最優先(例:マニュアル整備、採用ページ改善)
- 実行には準備が必要だが効果が大 → 中期的検討(例:生成AI研修)
- 効果は限定的 or 実行負荷が高い → 除外 or 他施策と組み合わせて実施
ステップ③ 短期施策と中長期施策を組み合わせる
人手不足対策では、「すぐに効果が出る施策」と「持続可能性を高める施策」のバランスが重要です。
| 施策タイプ | 具体例 | 目安期間 |
| 短期施策 | ・シフト柔軟化・採用チャネル追加・マニュアル改善 | 1~3ヶ月 |
| 中期施策 | ・社内研修整備・ツール導入・AI活用 | 3~6ヶ月 |
| 長期施策 | ・業務再設計・組織文化の改善・人事制度改革 | 半年~ |
とくに、短期施策に中期施策(教育・効率化)を繋げる導線設計がカギになります。
SHIFT AIでは、中小企業でも無理なく導入・活用できる生成AI研修を提供しています。もし興味があれば、まずは下記の資料をご覧ください。
まとめ|人手不足は仕組みで解決できる
人手不足は、単に「人がいない」という表面的な問題ではありません。採用活動の難しさ、定着率の低下、業務の属人化、教育機会の不足など、いくつもの要素が絡み合う、構造的な経営課題です。
ですが、その一つひとつを見直し、小さくとも実行可能な改革を積み重ねていくことで、確実に状況を変えていくことはできます。実際に、今回ご紹介した中小企業の事例では、特別な予算や人材がなくても、着実に人手不足を乗り越えた取り組みが多数ありました。
共通していたのは、現場の声に向き合い、課題を可視化し、効果的な打ち手を優先的に実行する姿勢。そして、「採る」「育てる」「活かす」「辞めさせない」という一連の流れを、仕組みとして捉え直していたことです。
人手不足に悩むすべての企業にとって、本質的な解決のカギは人を増やすことだけではなく、組織の時間の使い方を見直すことにあるのかもしれません。
その意味で、SHIFT AIが提供する法人向けの生成AI研修は、単なるスキル獲得ではなく、「人が足りない現場でも成果を出せる仕組み」を作るきっかけになり得ます。
もし、今の状況を変える第一歩を探しているなら、まずは研修資料をご覧になってみてください。自社にとっての新しい可能性が、そこにあるかもしれません。

よくある質問(FAQ)
- Q人手不足はどこも深刻と聞きますが、本当に解決できるのでしょうか?
- A
はい、構造的な課題ではありますが、改善は可能です。本記事で紹介した事例のように、採用戦略の見直しや業務効率化、社内教育の強化など「仕組み」で変えていくことで、人手不足を乗り越えた中小企業は多く存在します。
- Q成功している企業は、何から取り組んでいるのでしょうか?
- A
多くの企業は、まず「現場の業務や人材課題の見える化」から始めています。その上で、採用方法の再設計や教育体制の整備、業務の属人化解消など、できるところから一歩ずつ進めています。チェックリストを使った現状把握が効果的です。
- Q生成AIは人手不足解消に本当に役立つのですか?
- A
はい、役立ちます。特にマニュアル作成、FAQ対応、定型業務の簡素化など、人ではなくAIでもできる業務の切り出しに効果的です。導入企業では工数削減や定着率改善といった成果も見られています。
- Qまず何から始めればいいか、相談に乗ってもらえますか?
- A
はい、可能です。SHIFT AIでは、資料のご提供だけでなく、具体的な課題や業務内容に応じたご相談も承っています。まずは資料をダウンロードしていただき、課題感に合うポイントをぜひご確認ください。