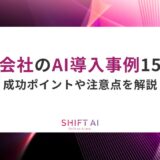介護現場ではいま、「人手不足」と「業務の複雑化」が深刻な課題となっています。
記録や報告、シフト管理、請求処理など――本来のケア以外に時間を奪われている職員も少なくありません。
こうした状況を変える鍵として注目されているのが「介護DXツール」です。
AIやIoT、クラウドなどのデジタル技術を活用することで、記録時間の短縮・夜勤負担の軽減・離職防止など、
現場の負担を減らし、ケアの質を高める取り組みが全国で進み始めています。
しかし、ツールの種類が多すぎて「どれを導入すべきか分からない」「現場に合うか不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、導入後に“使いこなせず形骸化”してしまうケースも少なくありません。
本記事では、介護業務の効率化に役立つ主要DXツールの種類・機能・効果を体系的に整理し、 さらに「導入を成功させるためのポイント」や「補助金情報」「現場の成功事例」までを徹底解説します。
ツールを“導入して終わり”にせず、「人と仕組み」で成果を生み出す介護DXを進めるための一歩を、ここから始めましょう。
介護DXの基本を知りたい方はこちら
介護DXとは?導入の進め方・メリット・補助金などを徹底解説【2025年版】
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
介護DXツールとは?|“人の時間を取り戻す”ためのデジタル化
介護DXツールとは、介護業務の中で発生する記録・報告・共有・管理といった業務をデジタル化するための仕組みです。
AIやIoT、クラウドなどの技術を活用し、職員の作業時間を減らすことで、「ケアの時間」を増やすことを目的としています。
つまりDXツールは、「人を置き換える」ためのものではなく、人の負担を軽くし、現場の力を最大化するための支援装置です。
記録の自動化や見守りセンサー、勤怠管理、請求処理まで、幅広い領域で導入が進み、介護業務の質そのものを変えつつあります。
厚生労働省も2025年に向けて「介護DX推進加速化プラン」を打ち出し、 ICT機器やAIの導入支援、職員向けのデジタル教育体制の整備などを本格化させています。
国としても、DXツールを“現場負担軽減と人材確保の鍵”と位置づけているのです。
とはいえ、ツールを導入するだけで業務が自動的に変わるわけではありません。
現場で成果を出すためには、「ツールを使いこなす人」と「仕組みを変える意識」が不可欠です。
介護DXとは、「技術導入」だけでなく、業務設計と組織文化の変革を伴うプロジェクトといえます。
AI経営総合研究所では、この“人×仕組み”の両輪を重視し、 現場が自走できる形でDXを定着させる支援を行っています。
介護DXの全体像や導入ステップを知りたい方はこちら
介護DXとは?導入の進め方・メリット・補助金などを徹底解説【2025年版】
介護DXツールの主な種類と活用領域
| 領域 | 主なツール例 | 活用技術 | 導入効果(KPI) |
| 記録・報告 | カイポケ/CareWiz/ワイズマン | クラウド・音声入力 | 記録時間▲30%、転記作業削減 |
| 見守り・安全 | パラマウントベッド(見守り)/眠りSCAN | IoT・AI画像認識 | 夜勤負担軽減、転倒事故リスク低減 |
| シフト・勤怠 | 勤次郎/ジョブカン介護 | AIシフト最適化・クラウド勤怠 | 残業▲20%、配置の適正化 |
| ケアプラン・請求 | NDソフト/ほのぼのNEXT | 自動帳票・データ連携 | ミス削減、請求漏れ防止 |
| 教育・研修 | 生成AI研修/eラーニング | ChatGPT応用・ナレッジ共有 | リテラシー定着、新人教育効率化 |
注:KPIは代表値の目安。自施設の業務量・運用設計により変動します。
各領域の“使いどころ”と導入時の注意
記録・報告
- 使いどころ:紙→クラウド化で即効性。音声入力が現場に刺さる。
- 注意:様式・語彙の標準化を先に。標準化なしの導入は“電子化された非効率”に。
見守り・安全
- 使いどころ:夜勤負担・転倒リスク対策の本命。家族満足度にも寄与。
- 注意:誤検知・死角の検証は現地で。通知設計(誰に、いつ、どう)は運用の肝。
シフト・勤怠
- 使いどころ:人手不足下での配置最適化。公平性の可視化に効く。
- 注意:ルール(資格・男女配置・夜勤回数)をAIに事前定義。例外運用の手順も決める。
ケアプラン・請求
- 使いどころ:帳票ミスと二重入力の削減。監査対応の強化。
- 注意:周辺システムとの連携テスト必須。月末月初のピーク負荷も要確認。
教育・研修(本記事の差別化ポイント)
- 使いどころ:「使える人」を増やすための土台。生成AIでQ&A・要約・手順化を内製化。
- 注意:操作研修だけでなく“なぜやるか”の理解をセットで。学びの場を継続設計する。
導入前に確認すべき3つの視点|“失敗しないDX”の準備段階
介護DXツールを導入しても、「現場が使いこなせない」「想定した効果が出ない」といった声は少なくありません。
その多くは、ツールそのものの問題ではなく、導入前の準備不足が原因です。
ここでは、失敗しないために押さえておきたい3つの視点を紹介します。
① 現場課題を“数値化”して可視化する
まず最初に行うべきは、現状の業務負担を「見える化」することです。
「どの業務にどれだけ時間がかかっているか」「誰に負担が集中しているか」をデータで把握しましょう。
たとえば、
- 記録作業:1日平均●分
- 残業時間:月平均●時間
- 夜勤中のトラブル対応回数:●件
このように定量データとして整理することで、「何を変えたいか」「どこにDXを効かせるか」が明確になります。
さらに、導入後の成果を測るために「効果指標(KPI)」を設定しておくことが重要です。
KPI例:記録時間30%削減/残業10時間減/離職率15%改善 など
「感覚的に効率化した気がする」ではなく、数値で成果を示すことで、現場も経営層も納得できるDXが進みます。
② 小規模導入で“成功体験”を作る
DXを成功させる最大のポイントは、“小さく始める”ことです。
いきなり全施設・全フロアで導入すると、トラブル対応に追われて定着しづらくなります。
まずは1施設・1チーム単位で試験導入し、現場での手応えを得ましょう。
「作業時間が●分短縮された」「職員同士の情報共有がスムーズになった」など、 具体的な成果を現場の言葉で共有することが、組織全体への拡大を後押しします。
小さな成功体験を積み重ねることで、 「DX=負担」ではなく「DX=助けになる」という認識が現場に広がります。
その成功体験が、DX推進の最大のモチベーションになります。
③ 現場リーダーへの“教育投資”を並行する
ツール導入を定着させるには、「なぜそれを使うのか」を理解している現場リーダーの存在が欠かせません。
単なる操作説明会ではなく、DXの目的や価値を共有し、現場で“伝えられる人”を育てることが重要です。
そのためには、操作教育だけでなく、
- 業務改善の考え方
- データを活用した意思決定
- チームで使いこなすコミュニケーション設計
といった“DXを進める力”を育てる必要があります。
AI経営総合研究所では、生成AIを活用した研修を通じて、 介護現場のリーダー層が自ら考え、仕組みを継続的に改善できる力を支援しています。
介護DXツール導入の成功事例【実例で見る効果と変化】
介護DXツールは、単なるIT化ではなく、現場を根本から変える仕組みです。
ここでは、実際に導入によって成果を上げた施設の事例を紹介します。
それぞれの事例から、“どんな課題にどう効いたのか”を具体的に見ていきましょう。
| 施設種別 | 導入内容 | 効果(定量) |
| 特別養護老人ホーム | 記録アプリ+クラウド共有 | 記録作業▲40分/日・離職率▲15% |
| 有料老人ホーム | AI見守り+センサー導入 | 夜勤中の事故ゼロ・入居者安心度向上 |
| 訪問介護 | 生成AI研修で教育改革 | 教育時間▲50%・定着率UP |
| 小規模事業所 | 勤怠・報告クラウド導入 | 残業削減+管理時間短縮 |
特別養護老人ホーム:記録時間を40分短縮、離職率を15%改善
紙ベースでの記録が残っていた施設に、音声入力対応の記録アプリを導入。
データをクラウドで共有することで、情報の転記・重複作業を削減し、 日々の記録時間が1日あたり40分短縮。
結果的に残業が減り、「職員が笑顔で働ける時間が増えた」と現場からも好評です。
離職率も15%改善し、採用コスト削減にもつながりました。
有料老人ホーム:AI見守り導入で夜勤負担が大幅減
夜勤者の巡回負担を軽減するため、AIカメラとセンサーを組み合わせた見守りシステムを導入。
転倒・離床検知を自動化することで、「夜勤1人当たりの巡回回数を約30%削減」。
導入後半年で夜間の事故報告はゼロに。
夜勤スタッフからも「不安が減った」との声が上がり、職員の心理的安全性も向上しました。
訪問介護:生成AI活用による“教育DX”で育成スピード倍増
経験値に頼りがちだった新人教育に、生成AIを活用した学習サポートを導入。
ChatGPTを活用したケースシミュレーションやマニュアル要約により、 教育時間を約50%削減しながら、理解度チェックも自動化。
「わからないをすぐ聞ける」「現場で学べる」環境が定着し、教育定着率が大幅に向上しました。
小規模事業所:勤怠・報告クラウドで“時間の見える化”
小規模ゆえに「紙と口頭連携」が主流だった事業所で、クラウド勤怠・報告ツールを導入。
スタッフの勤務時間・報告履歴をリアルタイムで共有できるようになり、 残業が月平均10時間削減。管理者の報告確認作業も半分に短縮。
「少人数でも無理なく回せる」体制づくりに成功しました。
失敗→再構築事例:導入初期に“使われなかった”ツールを再起動
ある中規模施設では、最初の導入で操作教育を十分に行わず、ツールが形骸化。
半年後に現場リーダー中心で改善チームを立ち上げ、「業務棚卸し+再教育+評価会議」を実施。
すると、3カ月後には「定着率80%」を達成。
ツールの価値を理解してもらうために、教育とコミュニケーションの設計が不可欠であることを再認識する結果となりました。
成功の共通項は「人が使いこなす仕組み」
- 成功事例のすべてに共通するのは、「ツール導入×教育投資」の両輪。
- 効果は時間削減・離職率低下・定着率向上というKPIで測定し、月次共有する。
- 失敗事例も“再設計のチャンス”として扱う組織文化を持つことが、DX定着の鍵。
導入を後押しする補助金・支援制度(2025年度版)
介護DXツールの導入を進めたい事業所にとって、国や自治体による支援制度の活用は大きな後押しとなります。
ここでは、2025年度に利用できる主な補助金・支援策をまとめました。
厚生労働省「介護DX推進加速化プラン」の概要
厚労省は、介護現場のデジタル化を加速させるために「介護DX推進加速化プラン」を展開しています。
このプランでは、以下の3つの柱でDX支援を強化しています。
- 介護ソフト・ICT機器の導入支援
クラウド記録システムや音声入力ツール、情報共有アプリなどへの補助。 - ロボット・センサー導入支援
夜間見守り、離床検知、移乗支援などの介護ロボットを対象。 - デジタル人材育成支援
職員のICT活用能力向上を目的とした教育プログラム・研修の推進。
特に2025年度からは、「データ連携による業務効率化」が重点テーマに位置づけられており、
ツール単体の導入よりも「複数システムをつなぐ仕組み化」に対して支援が拡大しています。
ICT機器導入・見守りロボット導入支援の具体例
| 支援種別 | 対象となる設備・ツール | 補助率(上限) | 目的 |
| ICT導入支援事業 | ケア記録システム、タブレット、音声入力ツールなど | 1/2以内(上限450万円) | 記録・報告の効率化、情報共有強化 |
| 介護ロボット導入支援事業 | 見守りセンサー、移乗支援機器、AIカメラ等 | 1/2以内(上限300万円) | 夜勤負担軽減、安全性向上 |
| デジタル活用人材育成支援 | ICT研修、生成AI活用教育など | 実費補助 | リテラシー向上、定着促進 |
ポイント:
国の補助金は都道府県を通じて交付されるため、各自治体ごとの募集時期や対象経費の確認が必須です。
東京都・大阪府など自治体別の主な補助金例(2025年度版)
| 自治体 | 事業名 | 対象 | 上限額 |
| 東京都 | 介護事業所ICT化支援補助金 | ケア記録・勤怠・請求システム | 最大500万円 |
| 大阪府 | 介護現場DX推進補助事業 | 見守りセンサー・AI勤怠管理 | 最大400万円 |
| 愛知県 | 介護ロボット導入促進事業 | 移乗・排泄・見守り支援機器 | 最大300万円 |
| 福岡県 | ICT導入支援事業 | クラウド記録・情報共有ツール | 最大250万円 |
自治体によっては、中小事業所優先枠や人材育成型補助も用意されており、「ツール+研修」をセットで支援する動きが広がっています。
申請の流れと注意点(図解イメージ)
申請ステップの基本的な流れ
① 公募要項を確認
↓
② 見積・機器選定・導入計画書作成
↓
③ 自治体へ申請(書類・データ提出)
↓
④ 交付決定通知
↓
⑤ ツール導入・実績報告
↓
⑥ 補助金交付(精算)
注意点
- 補助金は「交付決定後」に購入した費用のみ対象。
- 見積書・契約書・導入証明など、提出書類の不備があると不支給になるケースも。
- 事前相談をしてから申請書類を準備するのが確実です。
DXは「設備投資」ではなく「経営投資」。
補助金を“単年度の支援”で終わらせず、継続的に成果を生む仕組み化に結びつけることが重要です。
ツール導入を“定着”させる仕組み|運用フェーズで差がつく
DXの真価は、導入直後ではなく、「使い続けて成果を出す」運用フェーズにあります。
多くの介護事業所では、導入から半年ほどで利用頻度が下がり、「形だけのDX」になってしまうケースも。
その違いを分けるのは、“定着の仕組み化”と“人の成長”です。
ここでは、導入後に差がつく3つの仕組みを紹介します。
① 推進担当者の明確化と責任分担
DXを成功させるには、「誰が責任を持って進めるか」を明確にすることが第一歩です。
担当者が曖昧なままでは、ツール導入後の運用や改善が属人化し、 「使う人が変わると止まる」という事態に陥りがちです。
- 推進担当者(DXリーダー)を明確にし、現場・経営の橋渡し役を担う
- 役割分担を明示(入力担当・管理者・分析担当など)
- 定期的に改善ミーティングを設け、課題を共有する
組織として「DXを動かす責任者」を置くことで、ツールが“使われる文化”として根づきます。
② 成果の見える化(KPI共有会)
導入効果を定着させるもう一つの鍵は、成果を定量的に“見える化”することです。
導入しただけでは成果は感じづらく、現場のモチベーションも続きません。
- 記録時間▲30%、夜勤負担▲20%、離職率▲10%などのKPIを月次で可視化
- 職員間で「変化を共有する会」を開催し、現場の声をデータとともに共有
- 成果を“数字と実感”の両面で伝えることで、改善が継続する
特に、改善結果を可視化して経営層が評価に反映すると、現場も「やってよかった」という納得感を得られ、持続的な推進力が生まれます。
③ 継続的な教育・研修投資
ツールの定着を決定づけるのは、人材育成への継続的な投資です。
導入当初の研修で終わりにせず、半年・1年単位でリテラシー教育を継続することが理想です。
- 新入職員研修の中に「DXツール操作・活用」を組み込む
- 現場リーダー層には、データ分析・AI活用・改善提案までの教育を提供
- 生成AIを活用した“現場で学ぶ研修”を導入し、スキマ時間でも知識定着を支援
継続的に学びを仕組み化することで、 「使わされるDX」から「自ら進化させるDX」へと進化します。
参考: 介護DXとは?導入の進め方・メリット・補助金などを徹底解説
まとめ|介護DXツールは“人を支える仕組み”である
介護DXの目的は、決して「人を減らす」ことではありません。
DXツールが目指すのは、「人の時間を増やす」こと――つまり、ケアの質と働く人の余裕を取り戻すことです。
テクノロジーは、介護の現場を置き換えるものではなく、支える力です。
記録の手間を減らし、情報を正確に共有し、負担を分かち合うことで、 職員が“人と向き合う時間”にもっと集中できるようになります。
ツールを導入して終わりではなく、人と技術が共創する仕組みとして育てていくこと。
それが、これからの介護現場に求められるDXの姿です。
一歩を踏み出せば、現場は確実に変わります。
そして、その一歩が“持続可能な介護”をつくる力になります。
- Q介護DXツールとは何ですか?
- A
介護DXツールとは、介護業務をデジタル技術で効率化し、職員の負担を軽減する仕組みのことです。
記録や報告、見守り、勤怠管理、請求処理などをクラウドやAIで自動化・共有することで、 「人の時間を取り戻す」ことを目的としています。
- Q介護DXツールを導入するメリットは何ですか?
- A
主なメリットは以下の3点です。
- 業務効率化:記録・報告・勤怠などの事務時間を削減
- ケア品質の向上:情報共有がリアルタイムになり、ミスが減少
- 職員の働きやすさ改善:夜勤負担の軽減や離職率の低下につながる
導入によって、1人あたりの記録時間を1日30〜40分削減できた例もあります。
- Q介護DXツールにはどんな種類がありますか?
- A
介護DXツールは、主に以下の5領域に分かれます。
- 記録・報告系(例:カイポケ、CareWiz)
- 見守り・安全管理系(例:眠りSCAN、AIカメラ)
- シフト・勤怠系(例:ジョブカン介護、勤次郎)
- ケアプラン・請求系(例:ほのぼのNEXT、NDソフト)
- 教育・研修系(例:生成AI研修、eラーニング)
業務課題に合わせて、複数領域を連携させると効果が高まります。
- Q補助金はどんなツールに使えますか?
- A
厚生労働省や自治体が実施する「介護DX推進加速化プラン」などの補助金では、 ICT記録システム・AI見守り機器・勤怠管理クラウド・教育ツール(eラーニング等)が対象です。
都道府県によって上限額や申請時期が異なるため、早めの確認が必要です。
- Q小規模事業所でも導入できますか?
- A
はい、可能です。
最近はクラウド型ツールやサブスクリプションモデルが増え、初期費用を抑えて導入できるようになっています。
また、補助金制度を利用すれば、小規模でも実質負担を大きく軽減できます。
まずは1チーム単位でのスモールスタートがおすすめです。