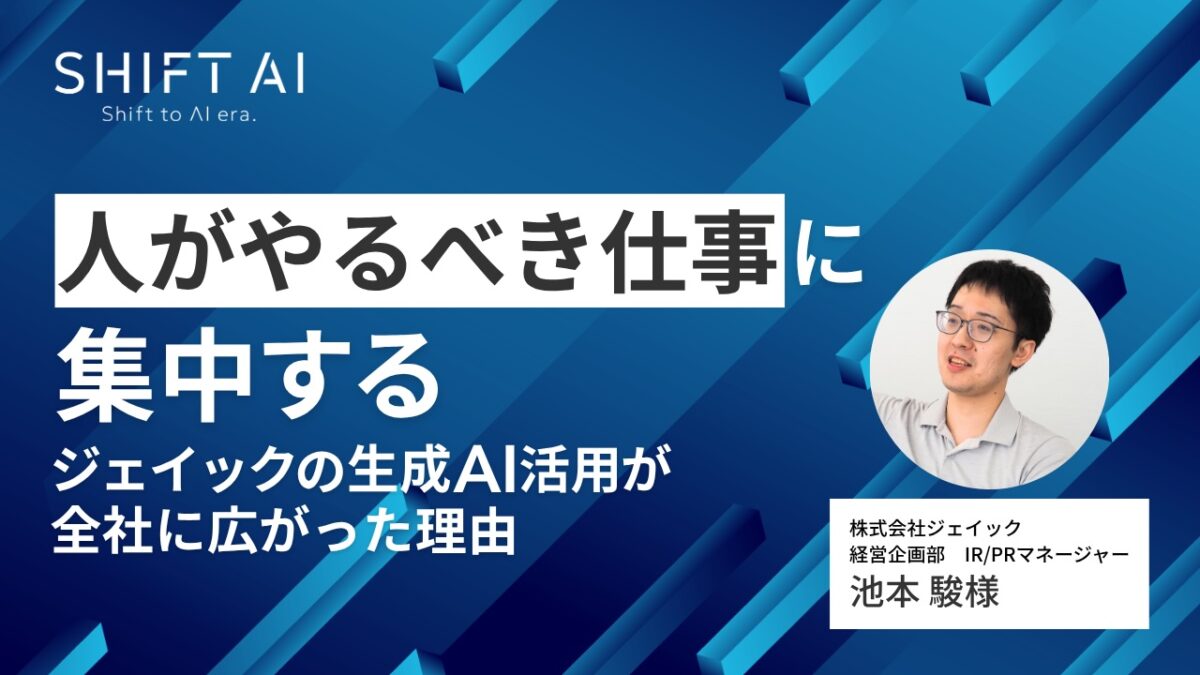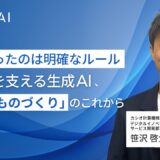生成AIを導入しても、一部の部署にとどまっていては、企業全体の競争力にはつながりません。
採用支援と教育研修を両輪とし、人事と経営者のためのメディアサイト「HRドクター」の運用も行う株式会社ジェイックでは、生成AIを積極的に活用している、社歴も職務も異なる社員を中心に、生成AIの全社的な業務活用を推進しています。
背景にあるのは「社員には人がやるべき仕事に集中してほしい」という代表の考え方です。商談や人材紹介における求職者との面談準備や内容の記録・整理、文章作成等のうち、定型業務をAIに任せることで、社員は顧客と向き合う本質的な業務に時間を割くことができるようになりました。
ジェイックには、もともと社員が自らの考えやノウハウ、気になるニュース等を主体的に発信する文化が根付いていました。その風土により、生成AIについても、Slackを通じたノウハウ共有やワークショップの実施が自然発生し、新入社員からベテランまで幅広い層で活用が広がっています。
本記事では、草の根から始まった生成AIの活用がどのように全社に浸透し、成果を生み出しているのかを、ジェイックの事例をもとにご紹介します。
※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
直面した「“人がやらなくてもよい仕事”に多くの時間を取られている」という課題
ジェイックで生成AIの活用が広がった背景には、経営陣と現場の双方に共通する強い課題意識がありました。
「商談や面談記録の入力・整理といった“重要ではあるが、本質的ではない仕事”に多くの時間を取られている」。同社の代表取締役 佐藤 剛志氏自身も現場の負担を把握し、改善を模索していたといいます。
経営企画部の池本駿さんも、その思いをこう語ります。
「経営企画部のIR責任者としての立場からも、個人的な仕事に対するスタンスからも、会社で最も重要な資産は社員であり、その社員は自分の強みを活かした仕事に集中してほしい、というのが出発点でした。営業職であれば商談や顧客との対話、キャリアアドバイザー職であれば求職者に寄り添うこと。定型業務ではなく、人に向き合うことにもっと時間を割けるようにしたかったんです」
その課題解決の手段として、性能も上がり、UI/UXも向上してきた生成AIの活用を模索し始めました。これまでは、定型業務を自動化するにしても外注をする必要がありました。外注は金銭的コストだけでなく、コミュニケーションコストも大きく、時間がかかります。ちょっとした修正をかけるにも再度打ち合わせや見積り、稟議などスピード感に欠けます。そこで生成AIを活用することで、簡単なプログラミングであれば一瞬で書け、テストも即座に実施できるようになったのです。
最初は、新しいもの好きな何名かの社員が個人的にChatGPTを使い始めたのがきっかけだったといいます。弊社のSlackには、「なんでも投稿okな雑談チャンネル」があり、そこに「こんなプロンプトで業務を効率化できた」といった投稿が出始め、関心を持った社員が次々に試し始めました。
その流れを受け、会社として、社員が生成AIを安心して使えるように、使用ルールを定め、セキュリティや個人情報の観点からもGemini Proを公認ツールとして指定しました。以降は「定型業務はAIに任せ、人が向き合うべき業務に集中する」という思想が社内に浸透していきました。
Slackの“業務効率化チャンネル”が広げた生成AI活用
ジェイックでの生成AI活用が一過性のブームに終わらず、社内に広く根づいた理由の一つが「発信する文化」です。
同社にはもともと、社員が業務効率化の工夫や便利なツールをSlackで共有し合う風土がありました。生成AIが登場した際も、その延長線上で自然と活用事例が流れ始めます。
池本さんは次のように振り返ります。
「Slackに“業務効率化チャンネル”があって、もともとショートカットや便利ツールの紹介が日常的に投稿されていました。ChatGPTが出てきたときも、同じように『こんなことができました』と発信する人が出てきて、それを見た人がまた試す。自発的にナレッジが循環していったんです」
この文化は単なる情報発信・共有にとどまらず、社内での生成AIの活用に関する社内勉強会やワークショップなどにもつながります。ある社員の投稿を見て「詳しく話してもらえませんか?」と池本さんらが声をかけ、そのまま社内勉強会で実践事例を紹介してもらう──そうした流れが社内で繰り返されています。
ジェイックでは現在、リモートワークが主流となっているため、オンライン形式での以下の取り組み等によって社内での生成AIの利活用が進んでいます。
- 月2~3回のランチタイム勉強会や月初めの全社員会議や週次朝礼でのワークショップ
- 社員による登壇形式での活用事例紹介
- Slackで拾い上げたノウハウの展開
ベテラン社員ならではの知見をAIに学ばせる
生成AIの浸透はまずITリテラシーの高い社員から始まりましたが、ジェイックではそれだけにとどまりませんでした。特徴的なのは、マーケティングや営業の現場で長年活躍してきたベテラン社員も積極的に取り組んでいる点です。
池本さんは印象的なエピソードを紹介します。
「マーケティングに20年携わってきたベテラン社員が、自分の過去のメール原稿をすべて読み込ませて、反応が良かったパターンをもとに新しいメールを生成するようになったんです。
その成果をワークショップで共有してもらったら、参加者から『ベテランがここまで活用しているなら、自分でもできるはずだ』という声が多く上がりました」
ITリテラシーの高さだけでなく、業務スキルや経験を持つ人材が生成AIを活用することで成果がさらに高まる。この成功体験の発信が、ほかの社員が生成AIを活用する強力な動機づけとなりました。
「新しいもの好きな人が飛びつくだけでなく、これまでAIやプログラミングに馴染みのなかった人も『やってみたら便利だった』と感じて、自動化や効率化の事例を発表してくれる。そうやって裾野が広がっていきました」
こうしてジェイックでは、若手からベテランまで幅広い層がそれぞれの強みを活かしながら生成AIを取り入れ、多層的に活用が進んでいます。
商談準備からデザイン修正まで、生成AIがもたらした効率化と内製化の波
ジェイックにおける生成AI活用は、単なる効率化にとどまらず、業務の内製化を大きく進めた点にも特徴があります。
営業現場では、商談前の企業リサーチやメールの一斉送信に生成AIを活用。これまで1時間かかっていた作業が10分程度に短縮されるなど、目に見える成果が出ています。
「スプレッドシートに宛先を入れてApps Scriptと連携することで、Gmailで自動送信できるようになりました。コピー&ペーストといった手作業で起こり得る宛先ミスも防げますし、社員からは『業務が一気に楽になった』という声が上がっています。もちろん、元々やろうと思えばできたことですし、数万件といった宛先であれば専用サービスもあります。しかし、例えば30件といった多くもなく少なくもないが、ツールを使うほどではないし、地味に時間がかかるところを効率化できているのは生成AI台頭による効果と言えます」
さらに大きな変化は、外注していた作業を社内で完結できるようになってきたことです。
「以前はデザインの調整や簡単なプログラム修正を外部に依頼していましたが、今ではGeminiを活用して自分たちで対応できるようになりました。結果的に依頼・内容確認・請求書発行等のコミュニケーションを含む時間短縮やコスト削減効果も大きいです」
キャリアアドバイザー業務でも、日程調整メールや面談記録の整理といった付帯業務をAIが支援。これにより、アドバイザーは求職者に寄り添う本質的な業務に集中できるようになりました。
同社では半期に1度、リアルで全社員が集まりキックオフを実施。その中で社員を表彰する制度を設けています。代表は以前から「商談後の入力や面談記録といった付帯業務に多大な時間がかかっている」という状況を課題視し、AIによる効率化の必要性を強調していました。
「キックオフでは、AI活用をリードした若手社員が表彰されました。社内で称賛される仕組みがあることで、活用へのモチベーションも高まっています
また、代表からも『人にしかできない仕事に集中すべきだ』というメッセージが常に発信されていました。現場の課題認識と経営の意向が一致していたことが、全社推進の大きな力になったと思います」
ジェイックでは効率化推進の基盤に、社員の主体性を後押しする文化と制度があります。
社員文化と経営のリーダーシップ、そして制度が三位一体となることで、ジェイックでは自然な形で全社的な生成AI活用が進んでいるのです。
次の一歩は「効果の可視化」──持続的な成長へ向けた挑戦
ジェイックでは、すでに部門を超えて生成AIが活用され、効率化や内製化の成果も生まれています。次のステップとして重視しているのは、効果の可視化です。
「まだ『どれだけ時間が削減できたか』といった全社的な効果測定までは至っていません。今後は業務工数を見える化し、AI活用による削減効果を明確にしていく必要があります」
また、今後は顧客や取引先との関係強化にも生成AIを活用していく構想があります。社内にとどまらず、顧客体験や事業価値を高めるための武器としてAIを位置づけようとしているのです。
池本さんは展望を次のようにまとめます。
「生成AIはあくまで人をサポートする存在です。だからこそ、人が人にしかできないことに時間を使えるようにする。そこに徹底して取り組めば、必ず事業成長にもつながっていくはずだと考えています」
ジェイックの生成AI活用は、草の根から始まり、文化と制度、そして経営の後押しを得て全社に広がりました。次の挑戦は、その成果を可視化し、持続可能な成長へとつなげることです。

株式会社ジェイック
経営企画部 IR/PRマネージャー
ジェイック 就職カレッジ®記事監修者
2016年に慶應義塾大学経済学部を卒業し、同大学院にて3年間で2つの修士号(経済学・工学)を取得。研究業績に、大学中退者の就業形態や賃金に着目した論文等。『池本駿・鈴木秀男. (2019). 高等教育中途退学が就業形態や賃金に与える影響. 日本経営工学会論文誌, 70(1), 1-9.』
三菱経済研究所研究員を経て、2020年4月に株式会社ジェイックに入社。マーケティング開発部にて、新規事業の立ち上げ、SNSマーケティング、労働市場調査、アンケート設計・分析、広報活動、論文執筆等に従事。著書に「教育経済学の実証分析-小中学校の不登校・高校における中途退学の要因分析」(2020年発行、出版社:三菱経済研究所)。経済産業大臣登録 中小企業診断士。
ジェイックの事例から学ぶ「真似すべき」5つのポイント
ジェイックの取り組みは、特別なシステム投資や一部の専門部署に依存するものではなく、多くの企業がすぐに応用できる実践的な工夫に支えられています。
- 「人がやるべき仕事」に集中する思想を明確に打ち出す
- Slackによる発言など、既存の発信文化を活かし、ナレッジ共有を自然発生させる
- 若手だけでなくベテラン人材の活用事例を積極的に発信する
- ワークショップや表彰制度など、制度的に全社を巻き込む仕掛けをつくる
- 成果の共有や内製化によって、実利を実感できる仕組みを整える
これらは業種や規模を問わず取り入れやすい実践例であり、生成AIを「定着」させるうえで大きなヒントになるはずです。
生成AI活用を「定着」させたい企業様へ
実際に自社で取り組もうとすると「うちの業務に合ったルールは?」「成果をどう可視化すべきか?」「推進役が見つからない」といった壁に直面することも少なくありません。
私たちSHIFT AIは、まさにこうした「導入後、定着しない」という課題解決を得意としています。
- 貴社の文化や業務に合わせたルール設計のコンサルティング
- 社員のスキルを引き上げる伴走型の研修
- 成果を可視化する仕組みづくり
生成AIの社内活用を促進させ、事業をさらに推進したい。こう考えている方はぜひとも一度SHIFT AIにご相談ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。