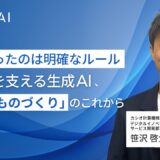生成AIを“業務効率化のツール”としてではなく、チームワークを進化させる文化の触媒として捉えている企業があります。それが、サイボウズ株式会社です。
同社は、生成AIを組み合わせることで、単なる生産性向上にとどまらず、人とAIが協働しながら進化し続ける組織文化をつくり上げています。その背景には、「技術を定着させ、使いながら磨く」という、同社らしい哲学がありました。
今回は、サイボウズ株式会社 執行役員 情報システム本部長の鈴木 秀一氏に、生成AIが生み出した“共創の現場”と、それを支える文化づくりについて話を伺いました。

サイボウズ株式会社
執行役員 情報システム本部長
早稲田大学理工学部で情報システムを学んだのち、2005年サイボウズに新卒入社。入社後は、リモートサービス、cybozu.com のインフラ運用や本社移転、社内システム基盤の刷新など広くITインフラ領域に携わる。現在は、「いつでも、どこでも、誰とでも」最高に働ける社内IT環境の提供に全力で取り組んでいます。
※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AIに見出した「チームワークを支える力」としての可能性
ChatGPTの登場は、多くのビジネスパーソンに衝撃を与えましたが、サイボウズが生成AIに注目したのは、最新技術を取り入れる企業としての好奇心だけではありませんでした。注目の背景にあったのは、同社の経営として、「新しい技術を使い、全社的に継続的な業務改善を進める文化を定着させる」という経営方針です。
同社では組織が拡大するにつれ、各部署で行われた改善活動のノウハウがチーム内に留まり、全社的な資産として共有されにくくなるという課題がありました。生成AIという新しい技術を、個人レベルの効率化に留めず、組織全体の業務プロセスをアップデートするための”変化を加速させる力”と位置づけているのです。
「生成AIだけが特別な技術というわけではありません。私たちにとっては“新しい技術の一つ”として、チーム全体でどう活用し続けるかが大切なんです」と鈴木氏は振り返ります。
クラウドやノーコードなど、時代ごとに登場する新技術を柔軟に取り入れてきたサイボウズ。社員が自ら業務を設計し、改善を繰り返す“自律的な仕組み”を築いてきた企業だからこそ、生成AIの登場も自然な流れとして受け止められました。
鈴木氏は「短期的にAIを使いこなすことが目的ではなく、組織として新しい技術を“使い続けられる状態”をつくることが大切です。その文脈の中で、生成AIは最初の取り組みのひとつになりました」といいます。
生成AIは業務効率を高めるためのツールというよりも、“変化し続ける組織文化”を実現するための触媒として位置づけられています。サイボウズが注目したのは、AIの即効性ではなく、日々の業務の中で自然と使われ、やがて文化に溶け込んでいくことでした。
「新しい技術は、導入して終わりではありません。日常の中で馴染ませ、進化させていくことが大切です。生成AIも、その一環として活用を広げていきたいと考えています」と鈴木氏は強調します。
自主自立を軸にした「考える文化」の育て方
サイボウズが生成AI活用で最も重視しているのは、「社員一人ひとりが自ら考えて動ける環境」を整えることです。その背景には、「チームワークあふれる社会をつくる」という存在意義(Purpose)を支える文化――「自主自立」があります。「ルールで縛るのではなく、各自が考え、責任を持って判断する。その主体的な姿勢こそが、サイボウズらしいガバナンスの在り方だ」と鈴木氏はいいます。
同社では、AIの活用方針を「守り」と「攻め」のみだけではなく、どちらも自律した個人が意思を持って選択できる仕組みを設計。そのために設けられたのが、横断的なチーム「生成AI活用サロン」です。これは、ガイドライン策定といった“守り”の側面と、現場への導入を促す“攻め”の側面をつなぐ組織であり、知見を共有しながら文化の浸透を後押ししています。
特徴的なのは、トップダウンでもボトムアップでもなく、“サイドウェイ”と呼ばれる横のつながりを軸にしている点です。部署や職種の枠を超え、メンバー同士が互いの実践を共有し合うことで、現場発の知見が自然に広がっていきます。各本部から集まったメンバーが、ルールの更新情報や各部署の課題、成功事例を交換し合う。こうした“横の推進力”こそが、サイボウズの生成AI活用文化を支える土台になっています。
同社は、単なる研修やトップダウンの周知ではなく、実践者同士が学び合う場を意識的に設計しています。誰かが学び、共有し、それを別のチームが改良していく。そうして繰り返される小さな試行錯誤の積み重ねが、“考える文化”を組織の中に定着させているのです。
“ルールの明文化”と“試す文化”
生成AI導入当初は、社員の反応も分かれていました。一部の社員は早々に活用を始めた一方で、慎重な姿勢をとる人も少なくありません。そのギャップを埋めたのが、“ルールの明文化”と“試す文化”です。
新しいテクノロジーの導入時には、常に組織内の温度差が課題となります。サイボウズにおいても、生成AI導入当初は、積極的に活用しようとする層と、様子見の層とで反応が二極化していました。一部の知的好奇心が高い社員が先行して個人的に使い始め、その有用性を探る動きが活発化しました。
現場の自発的な動きを受け止め、会社としても正式に業務利用を推進する方針を打ち出しました。
2024年初頭、全社的な利用ルールを策定し、本格的な業務利用への道筋をつけたのです。このルール作りで特徴的なのは、トップダウンで一律のツールを強制導入するのではなく、現場のニーズを尊重した点です。
現在も、全社員に一律でライセンスを配布するのではなく、業務上必要とする社員やチームが申請する形でライセンスを提供しています。これは、コスト最適化の観点だけでなく、「使いたい」という主体的な意欲を尊重し、ボトムアップでの活用文化を醸成するための戦略的な判断と言えるでしょう。
その結果、サイボウズでは約8割の社員が何らかの形で生成AIを日常的に利用するようになりました。会議の要約、資料作成、メール文案の下書きといった小さな改善から、問い合わせ対応やサポートメールの自動生成まで、活用範囲は広がり続けています。しかし、同社が見据えるのはその先、これらの小さな改善が組織全体で共有・連携され、大きな変革へと繋がっていく未来です。
まずは興味を持つ層から火をつけ、その成功事例を共有することで、徐々に全社へと波及させていく。サイボウズらしい、現場主導のアプローチがここにも表れています。
リスクを恐れず挑戦を支えるアジャイルなガバナンス
生成AIの導入には、情報漏洩やコンプライアンスといったリスクが伴います。しかし、サイボウズはリスクを理由に制限を強めるのではなく、「安心して挑戦できる環境づくり」を選びました。禁止事項を並べる代わりに、社員が自ら判断できるガイドラインを整備。そのうえで、試しながら改善を続けるアジャイルなアプローチを採用しています。ルールを“守るため”ではなく、“挑戦を支えるため”の仕組みとして設計しているのです。
さらに特徴的なのは、ルール策定そのものに実験的な手法を取り入れている点です。いきなり全社展開するのではなく、まずは一部のチームで「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施し、得られたフィードバックをもとに内容を磨き上げるとのこと。こうしたサイクルを繰り返すことで、変化の激しいAI技術にも迅速かつ柔軟に対応できる体制を築いています。
「完璧なルールを一度で作ることはできません。大切なのは、試しながら学び、柔軟に変えていくこと。ルールもまた、成長していく存在なんです」と鈴木氏は述べました。
この考え方の根底には、「信頼して任せる」というリーダーシップと、「アホはいいけど嘘はダメ」というサイボウズ独自の文化があります。失敗は叱責されるものではなく、学びとして共有されるべきもの。リーダーは目的と方向性を示し、メンバーが安心して挑戦できる土台を提供しているのです。
「信頼して任せることで、人は自分の頭で考えるようになります。失敗を責めるのではなく、どうすれば次に生かせるかを一緒に考える。その積み重ねが、組織の強さをつくるのです」と鈴木氏は続けます。
サイボウズにとってのガバナンスとは、行動を制限するルールではなく、“考えて動く力”を支えるための基盤です。社員が自ら判断し、互いに学び合いながら前進できる環境こそが、組織の創造性を高める原動力になっています。リスクを恐れず、変化を柔軟に受け入れる。その姿勢の積み重ねが、サイボウズが体現するアジャイルな文化の真髄だといえるでしょう。
人とAIの共創で加速する「未来のチームワーク」
生成AIは人間の仕事を奪うのか、それとも補助するのか。この問いに対し、鈴木氏は明確に、「AIは人と“協働しながら組織を支える”存在」と断言します。そして、その先に見据えているのが、人とAIがそれぞれの強みを活かして協働する「未来のチームワーク」の姿です。
「AIが得意なのは、情報の整理や分析といった論理的な処理。一方で人間は、感情を汲み取り、複雑な状況下で倫理的な判断を下したり、新しいアイデアを創造したりすることに長けています。互いの強みを生かして補い合うことが理想だと思っています」(鈴木氏)
カスタマーサポートの現場では、AIが過去の問い合わせデータを分析して最適な回答案を提示し、人間がそれをお客様の感情や状況に合わせてカスタマイズして伝えるといった連携が進んでいます。これによって、対応のスピードと質の両方を向上させることが可能です。
鈴木氏は「将来的には、AIがロジカルな部分を広く担うことで、人間の持つ優しさや想像力、多様な個性を理解する心といった、エモーショナルな価値がより一層高まっていくと思っています」と続けました。
AIと人の共存は、サイボウズの文化である“チームワーク”の延長線上にあります。違いを尊重し、役割を認め合う関係こそが、同社の理想とする働き方です。
注目すべきは、個人の作業効率化を超えた「共創」のかたちです。問い合わせ窓口の一次対応をAIが担い、サポート担当者が最終確認を実施。AIが文面を提案し、人がトーンや感情を整える。“人とAIのチームプレー”が、すでに日常の業務プロセスとして着実に広がりつつある状況です。
「AIもチームの一員として役割を意識する。そんな視点でチームを見たとき、働く風景はもっと穏やかに変わっていくはずです」と鈴木氏はいいます。AIの存在が、人の温度を際立たせていく。それこそが、サイボウズが描く「未来のチームワーク」です。
生成AIをkintoneにどう組み合わせていくか
理論やビジョンだけでなく、明日から実践できる具体的なノウハウも気になるところです。同社の「kintone」を活用している企業が多いことを受け、鈴木氏に「kintoneと生成AIを組み合わせた活用アイデア」をお伺いしました。いずれも現場業務を効率化するポテンシャルを秘めています。
アイデア1:kintoneにデータを蓄積する前作業を自動化する
会議録画からAIが自動で議事録を生成し、kintoneに登録する。あるいは問い合わせメールの要点をAIが抽出して担当者に通知するなど、人手による整理作業を効率化します。
アイデア2:kintone内のデータを活用してアウトプットを生成する
過去の対応履歴をもとに、類似ケースの返信文をAIが生成。担当者のスキルに依存せず、高品質な顧客対応を迅速に行えるようになります。
アイデア3:kintone自体のAI機能を活用する
kintoneに蓄積されたFAQやマニュアルから、AIが対話形式で回答を生成。社員は知りたい情報を即座に取得できるようになります。
これらの活用法は大規模開発を必要とせず、多くの企業で応用可能です。生成AI活用のカギは、導入後も“使われ続ける仕組み”をどう作るかにあります。研修で終わらせず、業務プロセスや文化に落とし込むことこそ、全社的な浸透への近道です。
サイボウズから学ぶ生成AI活用
生成AIを「導入するかどうか」ではなく、「どう根づかせるか」。この問いに真正面から向き合っているのが、チームワークを軸に進化を続けるサイボウズです。
同社は、生成AIを活用することで業務を効率化するだけでなく、 “人間中心の共創”という新しいチームワークの形を実現しました。
AIを単なる効率化ツールではなく、組織文化の一部として育てる——その取り組みには、他社が真似すべきヒントが詰まっています。
以下では、サイボウズから学ぶべき5つのポイントを紹介します。
1.継続的な改善文化を生む“触媒”として生成AIを捉える
生成AIを単なる効率化ツールではなく、全社的な業務改善を促す文化づくりの”変化を加速させる力”として活用している点が特徴です。短期的な成果よりも「使いながら磨く」ことを重視し、変化し続ける組織文化を実現しています。
2.現場主導のスモールスタートで浸透を進める
全社員に一律導入するのではなく、興味や意欲のある社員・チームから申請制でスタートさせたことで、現場に主体性が生まれ、自然な形で全社に広がりました。自発的な成功事例の共有による“波及型の浸透”は、多くの組織が参考にすべきモデルです。
3.ルールは“縛るため”でなく“挑戦を支えるため”に設計する
サイボウズは、リスク回避のために厳しいルールを敷くのではなく、社員が安心して挑戦できるガイドラインを策定しています。完璧なルールを一度で作るのではなく、PoCを通じて改定を重ねる“アジャイルなガバナンス”は、AI時代における理想の形です。
4.横のつながりで知見を広げる「生成AI活用サロン」
部署や職種を超えてノウハウを共有する横断組織(生成AI活用サロン)を設立。トップダウンでもボトムアップでもない“サイドウェイ”な学びの場が、社内に新たな熱を生んでいます。ルールや事例をリアルタイムで共有するこの仕組みは、文化定着の鍵となります。
5.AIが“人を支える”未来を前提に共創を描く
AIを人の代替ではなく人の創造性を支えるパートナーとして位置づける姿勢が、サイボウズの本質です。AIが定型業務を担い、人が感情や倫理、創造に集中することで、“人間らしさ”がより際立つチームワークを実現しています。
本記事で紹介したサイボウズの事例が示すのは、生成AI活用のカギは導入後の”使われ続ける仕組み”、つまり文化醸成にあるということです。単なる知識習得のための研修で終わらせず、業務プロセスや組織文化にまで落とし込むことが、全社的な活用への近道です。
しかし、自社でこれを実践しようとすると、
「どうやって社員全体に浸透させるのか」
「本社と現場の温度差をどう埋めるのか」
「教育や成果をどう可視化するのか」
といった壁に直面する企業も少なくありません。
私たちSHIFT AIは、こうした「導入したが定着しない」という課題解決を得意としています。
企業文化や業務に合わせた浸透施策の設計から、社員スキルを底上げする伴走型研修、成果を見える化する仕組みづくりまで、AI定着に必要なプロセスを一気通貫で支援します。
「生成AIを一部の社員しか使っていない」「思うように成果が出ない」──そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。