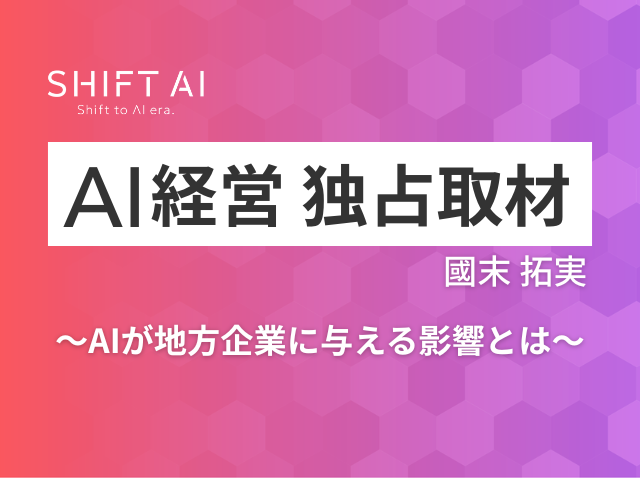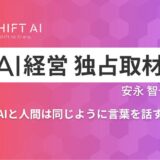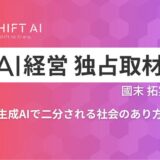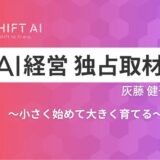「AIで会社を、経営を変えよう」。そう叫んでも、現実はそう簡単には進まない。カギになるのは「人」。AIを導入し、AIを活用するのも、やはり「人」です。
では、その「人」をどう動かせばいいのか?AI導入の最前線に立つ“AIの伝道師”が語る、「人を、会社を動かす知恵」とは。
今回は、アンドデジタル株式会社 チーフAIエバンジェリストの國末拓実氏の2度目の登場。日ごろから博報堂DYグループをはじめとする、名だたる企業のAI導入を支援している國松氏。そのかたわら、全国の地方自治体に請われて各地を飛び回っている。一体、地方の人々は彼に何を期待しているのだろうか。

アンドデジタル株式会社 チーフAIエバンジェリスト
ソウルドアウトグループ 生成AI普及分科会リーダー
博報堂DYグループ Human Centered AI Institute所属
法人向け生成AIの普及および活用推進のスペシャリストとして、全国の企業・自治体でAI導入支援および教育を推進。博報堂DYグループをはじめ、大企業から地方中小企業まで幅広く支援実績を持つ。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
20代と60代がAIをテーマに語り合う、香川県で見た感動の光景

僕が所属しているソウルドアウト株式会社は、「ローカル&AIファースト」構想を掲げ、地域、中堅・中小企業の課題を解決する事業支援を行っています。
「ローカル&AIファースト」とは、地域密着型の支援(ローカルファースト)と、生成AI技術の積極的な活用(AIファースト)を実現することです。そんな事情から、僕は全国各地を飛び回っています。
秋田市の女性の就業活動を支援する「なでしこ就労支援事業」では、生成AIを使った業務改善の講座を担当しました。また、島根県雲南市では、生成AIとライティングスキルを兼ね備えた人材育成、就職支援プログラムに講師として参加しました。
いずれも参加してくれたのは熱心な方ばかり。つい先日も香川県で「生成AIフェス2025 in Kagawa」というイベントがあったんですが、そこで忘れられない光景を目にしました。
2025年2月に行われたこのイベントは、定員の100名を超える120名が集まったんです。その顔ぶれも、行政の担当者をはじめ、会社のDX化を進めている経営者や担当者など、実にバラエティ豊かでした。
そのなかに、生成AIの導入コンサルを進める、20代の起業家の男性が東京から駆けつけていました。彼は「生まれ故郷の香川でAIのイベントがある」と聞きつけて参加していたんです。
その彼が、参加者の60代の男性と熱く語り合っていたので、なにを話しているのか聞いてみました。60代の男性は介護業界で働いていて、AIを使って人手不足を解消できないかと考えていたそうで、20代の若きAIコンサルの男性と対等に議論しているんです。
日本の地方は人口減少や高齢化、人手不足による廃業など、深刻な課題を抱えています。地元の人たちは「今すぐにでも地元をなんとかしなきゃ」という強い問題意識を持っているんですね。
彼らが年代を超えて、「AIを使って業務をどう省力化するか?」と語り合っている光景に出会い、僕はとても感動しました。
ゼロから始めたAI活用、社員の1/5がAI修行へ
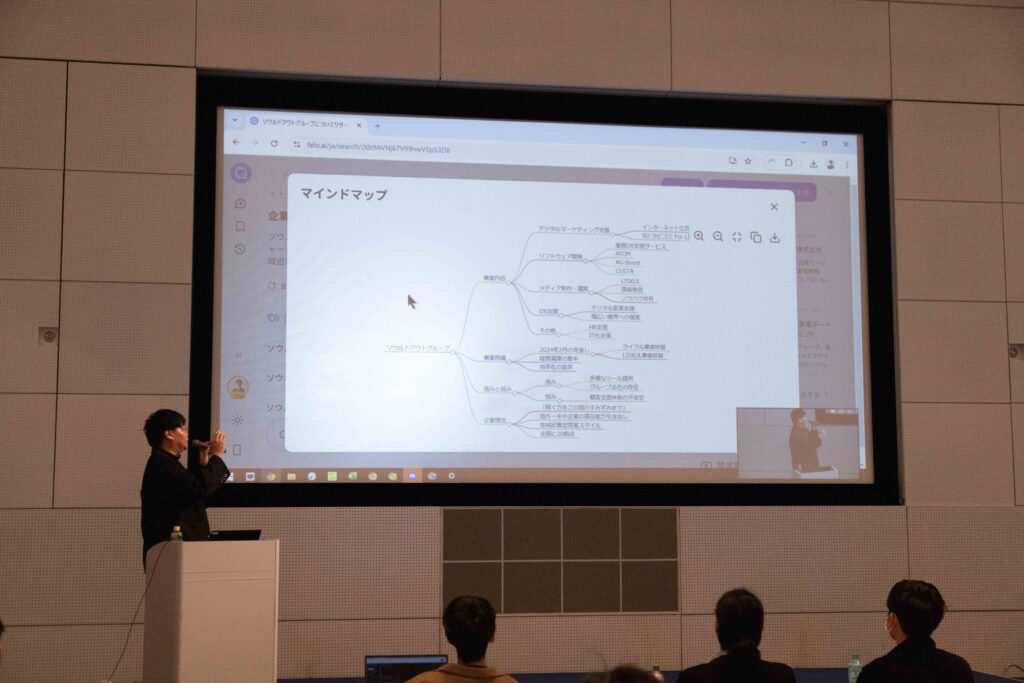
もうひとつ、僕にとって非常に印象深い、地方の中小企業のAI導入事例を紹介しましょう。
岡山県の株式会社イタミアートという、のぼり旗や幕の製造・販売を行っている印刷会社の生成AI活用プロジェクトに参加したんです。
同社が生成AIを導入した動機は主にふたつ。
2023年4月に上場したばかりで、「IT×ものづくりで世の中を変える」というビジョンをより強化して、株主にアピールしたいということ。それからもうひとつは、業務を省力化し、なんとか人手不足を解消したいという地方ならではの動機でした。
そこで、3カ月という期間を設け、1回2時間のワークショップを6回に分けて、インプットとアウトプットの両面を行う伴走型のプロジェクトを組みました。
「この指とまれ」方式で参加者を募ったところ、20人の社員が集まりました。総勢約100人の会社で、1/5にあたる社員が3カ月の間、AI習得のために仕事を止めるわけですから、かなりの覚悟だったと思います。
もっとも、参加メンバーはマーケティング部、営業部、DTP部など、同じ部署の社員がかぶらないようになっていました。まんべんなくバラけたからこそ、実現できたと言えるかもしれません。
20人のメンバーを前にして、最初に「1度でもいいからChatGPTなどのAIを使ったことがある人はいますか?」と聞いてみました。すると、手が上がったのは、わずかに2人だけ。
普通ならガクッとくるかもしれませんが、僕は逆にワクワクしましたよ。知識ゼロからの出発で、3カ月でどれだけみなさんにAIを習得してもらえるか、腕の見せどころじゃないですか。このプロジェクトを絶対に成功させよう、そう決意しました。
参加メンバーの熱意が成し遂げた「90%の省力化」

僕自身の感覚から言うと、イタミアートで実施したプロジェクトは、回を追うごとに熱気が増していった印象があります。
最初の2回は生成AIに関する基礎的な講義を行って、その後はAIを使ってどのような業務を改善したいかというアイデアを募りました。その後、具体的な課題に向けての実践的なAI活用のワークショップに移行しました。
このときに集まった改善案は50個ほど。そのなかから、AI活用に向いている事例をこちらから提示して、その課題ごとにチームに分けてアウトプットのワークショップを開きました。
具体的には、株主総会の想定問答集の作成、マニュアルの管理・運用、見積書備考欄の文章作成といったチームです。
各チームとは定期的にミーティングを実施して進捗を把握し、つまずいているポイントをサポートするために講義を追加するなど、アレンジを加えながら伴走する形をとりました。
参加した社員のみなさんは、忙しい時間のなかで精いっぱい、生成AI活用プロジェクトのために時間を割いてくれたと思います。
3カ月を終えた最後の発表会では、発表を終えたチームの報告に他チームから積極的な質問が飛び交うなど、思ってもいなかった盛り上がりを見せました。20人中18人がAIをまったく触ったことがないのが、信じられない光景でした。
実際、どのチームでも10%以上の業務コスト改善が見られ、なかでも製品に対するメールの問い合わせ業務では、90%の省力化を達成できたといいます。
プロジェクト終了後、参加メンバーとのやりとりで「社内のナレッジをNotionでまとめなおしてAPIでつなげ、GPTsと連携させたチャットボットを作りました」という、AIオタクの僕でさえ目がまわるような内容のメールが返ってくるようになりました。
僕はイタミアートの本社がある岡山県出身で、このプロジェクトを通じて就職活動の時期を思い出しました。地元の企業で働きたい気持ちがあったにもかかわらず、自分に合う会社がなくて関東で就職したことを……。
そんな僕だからこそ、故郷の岡山で先進的なAI導入企業が生まれたことを誇らしく思います。そして何より、そのお手伝いをできたことが本当にうれしかったです。