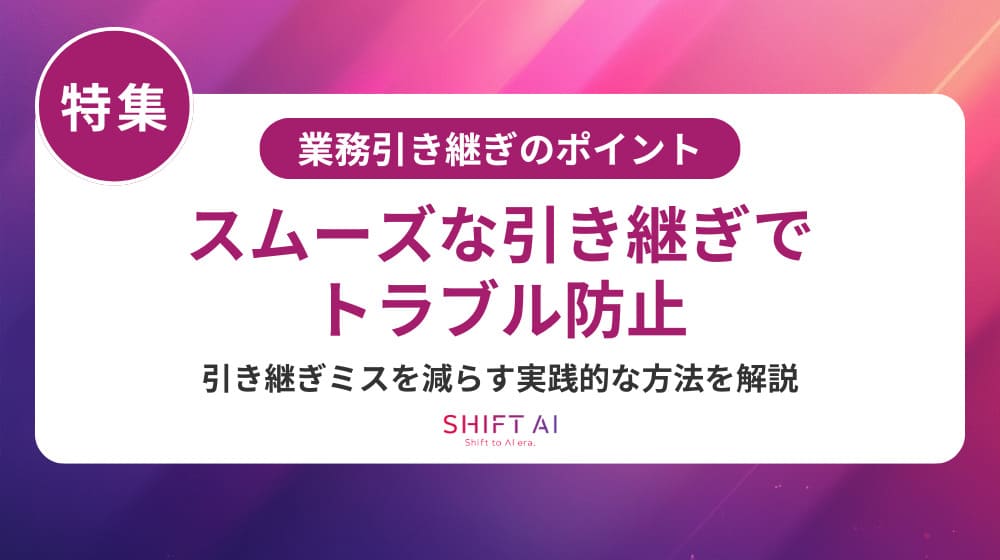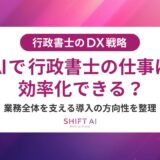異動や退職、配置転換などで業務を引き継ぐ際に欠かせないのが「引き継ぎ書」です。しかし、いざ作成しようとすると「何を書けばいいのかわからない」「どう書けば後任者に伝わるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
引き継ぎ書の書き方を間違えると、後任者が業務でつまずいたり、重要な情報が抜け落ちたりして、組織全体の生産性低下につながる恐れがあります。一方で、正しい書き方をマスターすれば、スムーズな業務移行が実現し、組織のナレッジが確実に継承されます。
本記事では、引き継ぎ書の基本的な書き方から、6ステップの作成手順、押さえるべき7つの必須項目、そしてAI活用による効率化まで、実践的なノウハウを網羅的に解説します。
この記事を読めば、後任者が迷わず業務を進められる質の高い引き継ぎ書が作成できるようになります。
AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。
■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする
※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
引き継ぎ書とは?書き方を学ぶ前に知っておくべき基本知識
引き継ぎ書とは、担当者が変わる際に業務内容や手順を後任者に伝えるために作成する文書です。異動・退職・配置転換などの場面で、業務の属人化を防ぎ、組織のナレッジを確実に継承する重要な役割を担います。
引き継ぎ書が重要な理由は、口頭での説明だけでは伝え漏れや誤解が生じやすく、後任者が業務で困った際に参照できる資料が必要だからです。
また、業務マニュアルとは異なり、現在進行中の案件や前任者独自のノウハウ、注意点などの個別情報を含むのが特徴です。
適切な引き継ぎ書があることで、後任者は安心して業務をスタートでき、組織全体の生産性維持につながります。
💡関連記事
👉業務引き継ぎの基本から応用まで|失敗しない手順とAI活用で効率化を実現
引き継ぎ書の書き方|6ステップで作成する手順とポイント
効果的な引き継ぎ書を作成するには、体系的な手順に沿って進めることが重要です。以下の6ステップで進めることで、漏れなく質の高い引き継ぎ書が完成します。
Step.1|担当業務をすべて洗い出す
まずは日常業務から年次業務まで、自分が担当するすべての業務を書き出しましょう。
毎日行う業務は思い出しやすいものの、月1回や年1回の業務は見落としがちです。カレンダーやスケジュール表を確認しながら、定期的に発生する業務も含めて洗い出してください。この段階では重要度に関係なく、どんな小さな業務でも記録することがポイントです。
業務の洗い出しが完了したら、優先順位や重要度も併せて整理しておくと、後の工程がスムーズに進みます。
Step.2|引き継ぎスケジュールを決める
引き継ぎ完了までの期間を逆算して、現実的なスケジュールを立てます。
各業務の引き継ぎにかかる時間を見積もり、余裕を持った日程を組むことが重要です。引き継ぎ期間中も通常業務は継続するため、突発的なトラブルや追加説明が必要になる可能性も考慮してください。
特に実際の業務を一緒に行いながら説明が必要な場合は、十分な時間を確保しておきましょう。スケジュールに予備日を設けることで、確実な引き継ぎが実現できます。
Step.3|引き継ぎ書の内容を決める
後任者が迷わず業務を進められるよう、記載する内容を具体的に決定します。
業務の概要や手順だけでなく、現在進行中の案件、関係者の連絡先、データの保管場所、過去のトラブル事例など、実務で必要となる情報を網羅的に整理してください。前任者しか知らない暗黙知やコツも重要な情報です。
内容を決める際は、後任者の経験やスキルレベルも考慮し、適切な詳しさで説明できるよう調整しましょう。
Step.4|実際に引き継ぎ書を作成する
読みやすさと理解しやすさを重視して、引き継ぎ書を実際に作成します。
見出しや箇条書きを活用し、情報を整理して記載してください。専門用語には注釈をつけ、複雑な業務はフローチャートや図解を用いると効果的です。文字のフォントやレイアウトを統一することで、見やすい資料に仕上がります。
作成中に新たな情報を思い出した場合は、随時追加して内容を充実させていきましょう。
Step.5|上司に確認してもらい承認を得る
客観的な視点でのチェックを受けるため、完成した引き継ぎ書を上司に確認してもらいます。
自分では当たり前と思っている情報でも、他者から見ると説明不足の場合があります。上司からのフィードバックを受けて、わかりにくい箇所の修正や不足情報の追加を行ってください。
また、会社によっては引き継ぎ書が社内文書として承認が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
Step.6|後任者に引き継ぎを行う
引き継ぎ書を活用しながら、後任者への実際の引き継ぎを実施します。
単に資料を渡すだけでなく、読み合わせを行い、重要なポイントを口頭で補足説明してください。後任者からの質問には丁寧に答え、必要に応じて実際の業務を一緒に行いながら説明しましょう。
引き継ぎ後も一定期間はフォローアップを行い、後任者が困った際にサポートできる体制を整えることが重要です。
引き継ぎ書の書き方で押さえるべき7つの必須項目
質の高い引き継ぎ書には、後任者が業務を円滑に進めるために必要な情報が網羅されています。以下の7つの必須項目を確実に含めることで、漏れのない引き継ぎ書が完成します。
業務の全体像と目的・背景
業務の目的と位置づけを最初に説明することで、後任者が全体像を把握できます。
なぜその業務が必要なのか、どのような成果を期待されているのかを明確に記載してください。業務の背景や経緯も含めることで、後任者が適切な判断を下せるようになります。
他部署との関連性や、その業務が会社全体にどのような影響を与えるかも説明に含めると、業務の重要性が伝わりやすくなります。
業務全体のスケジュールと優先順位
日次・月次・年次の業務サイクルと優先度を整理して記載します。
毎日行う業務、定期的に発生する業務、締切が決まっている業務などを時系列で整理し、それぞれの優先順位を明示してください。繁忙期や閑散期の業務量の変化も記載すると、後任者が業務計画を立てやすくなります。
複数の業務が重複する場合の対応方法や、緊急時の優先順位の変更についても説明しておくと安心です。
具体的な業務の流れ・手順
実際の作業手順を段階的に詳しく説明し、後任者が迷わず作業できるようにします。
各ステップで何をどのように行うのか、使用するツールやシステム、必要な資料などを具体的に記載してください。承認が必要な業務については、承認者や承認フローも明記しましょう。
作業のコツや注意点、よくある間違いなども含めることで、後任者のスキルアップを支援できます。
トラブル・クレームの対応方法
想定されるトラブルとその対処法を具体的に記載し、緊急時の対応力を向上させます。
過去に発生したトラブルの種類と対応方法、エスカレーションが必要な場合の判断基準と連絡先を明記してください。顧客対応が含まれる業務では、クレーム対応の基本的な流れと話法も説明しておくと効果的です。
トラブル発生時の報告ルートや、関係部署との連携方法も詳しく説明しておきましょう。
過去のトラブル・クレーム対応履歴
実際の対応事例を参考資料として記録し、後任者の判断材料を提供します。
どのようなトラブルがいつ発生し、どのように解決したかを時系列で整理してください。同様のトラブルが再発した場合の対応がスムーズになります。
顧客ごとの特別な配慮事項や、過去のやり取りで注意すべきポイントも記載しておくと、顧客満足度の維持につながります。
業務に関する資料の保管場所
必要な資料やデータのありかを正確に記載し、後任者がすぐにアクセスできるようにします。
ファイルサーバーのフォルダパス、紙資料の保管場所、データベースのアクセス方法などを具体的に明記してください。パスワードが必要な場合は、適切な管理方法も含めて説明しましょう。
資料の更新頻度や管理ルールも併せて記載することで、適切な資料管理が継続できます。
進行中業務に関する注意書き
現在進行中の案件やプロジェクトについて、詳細な状況と今後の対応を説明します。
各案件の進捗状況、関係者、今後のスケジュール、注意点を整理して記載してください。未完了のタスクや継続検討事項も明確に示し、後任者が適切に業務を引き継げるようにしましょう。
特に重要度の高い案件については、別途詳細資料を作成することも検討してください。
わかりやすい引き継ぎ書の書き方|3つのコツとAI活用術
引き継ぎ書の内容が充実していても、読みにくければ効果は半減してしまいます。以下の3つのコツを実践することで、後任者にとって理解しやすい引き継ぎ書が作成できます。
読み手が理解しやすい内容にする
構造化と視覚化を重視して、情報を整理して記載します。
見出しや箇条書きを活用し、情報の階層を明確にしてください。重要な情報は太字やマーカーで強調し、複雑な手順はフローチャートや図解で視覚的に説明しましょう。専門用語には注釈をつけ、誰が読んでも理解できる内容を心がけます。
一つの段落では一つのテーマに絞り、文章は簡潔に書くことで読みやすさが向上します。
後任者のリテラシーに合わせて作成する
後任者の経験やスキルレベルを考慮して、適切な説明レベルで作成します。
業務経験が豊富な後任者には要点を絞って記載し、未経験者には基本的な用語や背景から丁寧に説明してください。後任者が分からない場合を想定し、参考資料やマニュアルの場所も併せて記載しましょう。
必要に応じて、段階的に理解を深められるよう、基礎編と応用編に分けて作成することも効果的です。
AI活用で効率化と品質向上を実現する
生成AIツールを活用することで、引き継ぎ書の作成効率と品質を大幅に向上させられます。
業務洗い出しの段階では、AIに業務カテゴリーの提案を求めたり、抜け漏れチェックを依頼したりできます。文書作成時は、わかりやすい表現への書き換えや、構成の最適化をAIにサポートしてもらうことが可能です。
完成後の品質チェックでも、AIによる誤字脱字チェックや読みやすさの評価を活用すれば、より完成度の高い引き継ぎ書が作成できます。
まとめ|引き継ぎ書の書き方をマスターして組織の競争力を高める
引き継ぎ書の書き方は、6つのステップに沿って進め、7つの必須項目を確実に含めることが成功の鍵です。読み手目線での構造化と、後任者のレベルに合わせた内容調整により、誰もが理解しやすい引き継ぎ書が完成します。
特に重要なのは、個人の取り組みで終わらせるのではなく、組織全体で引き継ぎ書の品質向上に取り組むことです。AIツールを活用した効率化も含め、継続的な改善により業務の属人化を防ぎ、組織のナレッジを確実に蓄積できます。
適切な引き継ぎ書があることで、人材の変動があっても業務品質を維持でき、新しい担当者の早期戦力化も実現可能です。これからの時代、組織全体での引き継ぎ力向上が競争優位の源泉となるでしょう。

引き継ぎ書の書き方に関するよくある質問
- Q引き継ぎ書とマニュアルの違いは何ですか?
- A
引き継ぎ書は現在進行中の案件や前任者独自のノウハウなど、個別の業務状況を引き継ぐための文書です。一方、マニュアルは誰でも業務を行えるよう標準化された手順を記載したものです。引き継ぎ書は一時的な情報共有が目的で、マニュアルは継続的な業務支援が目的という違いがあります。両方を併用することで、効果的な引き継ぎが実現できます。
- Q引き継ぎ書の作成にどのくらい時間がかかりますか?
- A
業務の複雑さや範囲によって異なりますが、一般的には1週間から2週間程度の期間を見込んでおくことが重要です。業務洗い出しに2-3日、内容整理と作成に3-5日、確認・修正に2-3日程度が目安となります。引き継ぎ期間中も通常業務は継続するため、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。
- Q引き継ぎ書に書いてはいけない情報はありますか?
- A
パスワードや機密情報は引き継ぎ書に直接記載すべきではありません。これらの情報は別途適切な方法で共有してください。また、個人的な推測や確証のない情報も避けるべきです。顧客の個人情報や社外秘の内容を含む場合は、情報管理規定に従って適切に取り扱い、必要に応じて上司の確認を得ることが大切です。
- Q後任者が未経験の場合、どう書き方を調整すればよいですか?
- A
未経験者には基本的な用語や業務の背景から丁寧に説明することが重要です。専門用語には必ず注釈をつけ、業務の目的や重要性も含めて記載してください。複雑な手順は段階的に分けて説明し、参考資料やマニュアルの場所も明記しましょう。また、質問しやすい環境を作り、引き継ぎ後のフォローアップ期間も長めに設定することをおすすめします。
- Q引き継ぎ書作成でAIツールをどう活用できますか?
- A
AIツールは文章の構成整理や表現の改善、誤字脱字チェックなどで活用できます。業務洗い出しの段階では、抜け漏れがないかAIに確認してもらうことも可能です。また、複雑な手順をわかりやすく説明するための文章構成の提案や、後任者のレベルに合わせた表現への書き換えサポートも受けられます。ただし、業務の具体的な内容は人間が責任を持って記載することが重要です。