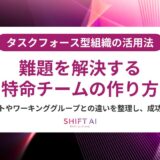行政DXの推進が全国で進む中、多くの自治体で課題となっているのが「職員のDXスキル不足」です。
ツール導入や外部委託は進んでも、現場で“使いこなす人材”が育たず、改革が止まってしまう――そんな声が少なくありません。
国もこの状況を重く見ており、総務省やデジタル庁は2025年度に向けて「デジタル人材の確保・育成」を最重要施策に位置づけました。
いま行政に求められているのは、外部依存ではなく「自走できる職員」への転換です。
本記事では、国が示すDX人材育成の方針と最新支援制度を整理しながら、 自治体がどのように職員のデジタルスキルを伸ばしていけばよいのかを具体的に解説します。
あわせて、少額の予算でも始められる生成AI研修による実践的な育成法も紹介。
DXを“掛け声”で終わらせないために――
職員が自ら変化を生み出せる組織づくりの第一歩を、ここから始めましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ行政DXの成否は「人材育成」で決まるのか
行政DXは「システムを導入すれば完了する」ものではありません。
多くの自治体がDX推進を掲げながらも、実際には“人材不足”という壁に直面しています。
総務省が公表した「自治体DX推進計画2025」でも、 職員のスキル向上と組織的な人材育成を最重要テーマに位置づけています。
つまり、DXの本質は「テクノロジーの導入」ではなく、 それを活かせる人をどう育てるかに移りつつあるのです。
“ツール導入から、活用できる人材育成へ”
これは、今まさに行政現場で起きているフェーズ転換です。
一方、DXが進まない自治体に共通する課題は明確です。
それは、「ツールに詳しい職員はいても、仕組みを変えられる人がいない」ということ。
ツールや外部コンサルに依存した改革では、担当者の異動や年度替わりのたびにプロジェクトが頓挫してしまいます。
根本的に必要なのは、“自分たちで変化を設計できる職員”を育てること。
つまり、現場が「変化を生み出す文化」を持つことこそが、真のDX推進なのです。
DXとは外部から「導入する」ものではなく、現場が「育てていく文化」です。
その出発点にあるのが、職員一人ひとりの“人材育成”です。
関連リンク: 行政DXとは?国の方針・導入状況・課題をわかりやすく解説
国が示す「行政DX人材育成」の方向性と支援制度
行政DXの人材育成は、国の政策として明確に位置づけられています。
「自治体DX推進計画2025」では、DXを支える人材を“確保・育成・定着”の三段階で支援することが明記されました。
ここでは、総務省・デジタル庁が進める主な施策と、 それを自治体がどのように“現場で活かせるのか”を整理します。
総務省の「デジタル人材確保・育成方針」
総務省は、自治体が自ら人材を育て、持続的にDXを推進できる体制づくりを目指し、 以下の3つの人材区分を明確に定義しています。
| 人材区分 | 主な役割 | 具体例 |
| 企画人材 | DXの全体戦略を描き、施策を設計する | DX推進責任者・情報政策課長など |
| 実践人材 | 現場業務でAIやRPAを活用し、改善を進める | 市民課・福祉課など現場担当職員 |
| 支援人材 | 全庁的なセキュリティ・システム基盤を担う | 情報システム課、外部ベンダー連携担当 |
また、スキルの客観評価に向けて「デジタルスキル標準(DSS)」を整備し、 全国的な職員研修体系のモデル化を進めています。
現場活用のポイント
各自治体はこの枠組みをベースに、自庁の“人材育成方針”を策定することが求められています。
DSSを活用すれば、研修の階層設計や評価指標づくりにも応用可能です。
デジタル庁の「地方DX推進人材プログラム」
デジタル庁では、民間や他自治体との人材交流を促進し、 DX推進を担う人材を育てるための各種プログラムを展開しています。
- 民間DX人材との交流機会の提供(越境学習・伴走支援)
- リスキル支援講座の整備(オンラインで受講可能)
- DXリーダー育成カリキュラム(データ利活用・AI企画・業務再設計など)
このプログラムは、“知識の習得”ではなく“組織変革を動かすリーダー育成”を目的としており、 単年度研修ではなく“継続的な人材ネットワーク”づくりが重視されています。
DXを成功させる人材とは、“他自治体や民間の知見を取り込み、変化をつなぐ人”。
つまり「デジタル庁プログラム × 庁内実践研修」の組み合わせが最も効果的です。
人材育成を支援する補助金・交付金制度
職員のスキルアップや研修実施は、国の補助制度を活用することで実現しやすくなっています。
主な支援制度
| 制度名 | 概要 | 対象経費 |
| デジタル人材育成補助事業 | 職員向けリスキル・AI研修・外部講師派遣を支援 | 研修費・教材費・講師謝金など |
| デジタル田園都市国家構想交付金(人材育成枠) | 地域DX・AI活用を担う人材育成事業を支援 | 職員教育・実証プロジェクト費用 |
| 自治体情報システム標準化支援 | 情報担当職員のスキル強化を含む基盤整備支援 | システム運用・セキュリティ研修費用 |
特に近年は、「職員向け生成AI研修」も補助対象となるケースが増えています。
文書作成支援・FAQ自動化など、業務効率化の即効性が高いテーマが好まれる傾向です。
国の制度を「情報として紹介する」だけでなく、 “どの制度で何を育てられるか”を具体的に結びつける。
補助金を単なる予算ではなく、“人材投資の第一歩”として活用することが鍵です。
これらの制度を効果的に活かすには、まず現場の職員がAIを使いこなせる状態を作ることが欠かせません。
いま、補助金を活用して始められる自治体向け生成AI研修プログラムがあります。
行政DX人材に求められるスキルモデルと育成ロードマップ
DX推進を担う人材は、単なるITスキルだけで成り立つものではありません。
行政DXでは、戦略を描く人・実践で動かす人・環境を支える人という3つの層が相互に機能して初めて成果が出ます。
総務省やデジタル庁でも、職員の役割を「企画・実践・支援」の三分類で整理しており、
AI経営メディアではこの考え方をベースに、実際の自治体育成に適用できる形で再構築しました。
行政DX人材の3階層モデル
| 層 | 役割 | 育成の方向性 |
| 戦略層(企画人材) | DX全体戦略の設計、データ活用・外部連携の推進 | 部署横断・外部との共創を意識した政策立案力を養う |
| 実践層(現場職員) | AI・RPA・業務改善を実行し、現場改革を進める | 生成AIや自動化ツールを“日常業務の道具”として使いこなす |
| 支援層(バックオフィス) | 情報基盤整備・セキュリティ・標準化対応 | 安全な運用体制とガバナンスを確立し、変革を支える |
この3層の役割が噛み合うことで、自治体DXは“単年度プロジェクト”から“持続的変革”へ進化します。
DX人材とは「ITに詳しい人」ではなく、“変化を設計し、仕組みにできる人”。
技術スキルよりも、「課題を定義し、改善を仕組み化する力」が中核にあります。
育成ロードマップ:DX人材を段階的に育てる仕組み
単発の研修では人は変わりません。
行政DXでは、「理解 → 実践 → 定着」の3段階で人材を育てるロードマップが重要です。
| フェーズ | 育成内容 | ゴール |
| ① リテラシー教育 | デジタル・AIの基礎理解。庁内共通言語をつくる | 「DXとは何か」を全職員が共有できる状態 |
| ② 実践研修・PoC(試行導入) | 生成AIやRPAツールを用いた業務改善を試験的に実施 | 職員が“自ら業務を変える体験”を得る |
| ③ 定着・横展開 | 成果を庁内で共有、他部署へ横展開 | 組織全体でDX文化を根付かせる |
実践ポイント
- “庁内共通言語”を持つことで部署間連携がスムーズになる
- 成果を“見える化”することで次年度予算が通りやすくなる
- PoCフェーズでのAI研修が、定着の最大加速ポイントになる
AI経営総合研究所が多くの自治体支援を行う中で見えてきたのは、 「AIを使える人」が1人いるだけではDXは進まないという現実です。
本当に変化を生むのは、
「職員全員がAIを理解し、業務改善を“自分ごと”として考えられる状態」。
その基礎を作るのが、リテラシー教育+AI実践研修です。
ここから、「ツールを使う職員」から「仕組みを変える職員」への成長が始まります。
DX人材育成の第一歩は、「職員がAIを理解し、使えるようになること」です。
AI研修は、単なる学習ではなく“庁内変革の起点”になります。
関連リンク: 行政DXとは?国の方針・導入状況・課題をわかりやすく解説
自治体で進むDX人材育成の最新トレンド
全国の自治体では、DXを単なるスローガンではなく、人材育成を軸にした組織変革として進める動きが広がっています。
ここでは、2024〜2025年度に注目を集めた先進自治体の取り組みを紹介します。
| 自治体 | 取り組み | 成果 |
| 岸和田市(大阪府) | 「職員デジタル人材育成方針」を策定。庁内で人材育成の基本方針を明文化し、役割と目標を可視化。 | 全庁的にDX方針を共有。部署横断でデジタル活用を推進する文化が定着。 |
| 松本市(長野県) | 職員向けに「生成AI活用研修」を導入。実際の業務データをもとにAI文書要約・住民対応自動化を体験。 | 参加職員のAI利用率が50%に到達。定常業務の効率化と人材リスキルを同時に実現。 |
| 金沢市(石川県) | 「DX推進リーダー制度」を設置。各課にDX推進担当を配置し、庁内での成果共有・相談体制を整備。 | 部署間の情報連携が加速し、横断的なプロジェクト推進が進む。 |
これらの自治体に共通しているのは、「小さく試し、成果を見える化し、学びを組織全体に還元している」という点です。
たとえば松本市のように、まず一部部署で生成AI研修を試験導入し、成果を庁内共有する動きは非常に効果的です。
これは単なる“研修の実施”ではなく、職員の行動変化 → 組織の文化変化へとつながる仕組みづくりです。
また、金沢市や岸和田市のように「リーダー制度」「方針の明文化」を行うことで、 人材育成が属人化せず、“継続的に育つ仕組み”として機能し始めています。
関連リンク :
行政DXとは?国の方針・導入状況・課題をわかりやすく解説
行政DXの課題とは?制度・組織・人材の“3つの壁”と解決策
DX人材育成を加速させる3つの実践ステップ
行政DXを「一過性のプロジェクト」で終わらせないためには、 “学びを仕組み化する”アプローチが欠かせません。
ここでは、多くの自治体が成果を上げている「人材育成の3ステップ」を紹介します。
この流れを取り入れることで、限られた予算でもDX文化を根付かせることが可能になります。
① 庁内で「学びの共通言語」をつくる
DX推進の第一歩は、職員全員が同じ“言葉”で議論できる状態をつくることです。
部署や立場によって「DX」や「AI」の理解レベルが異なるままでは、改革は進みません。
まずは庁内に、
- デジタル用語辞典
- AI・データ活用の基本ガイドライン
- 職員向けeラーニング教材
などを整備し、共通認識の土台をつくりましょう。
“学びの共通言語”があると、職員同士の連携や議論の質が一気に上がる。 DX人材育成は、まず“会話の土台”から始まるのです。
② 小規模研修からPoC(実証)へつなげる
次のステップは、“学びを実践に変える”段階です。
いきなり全庁展開ではなく、まずは小規模なPoC(試行導入)から始めます。
たとえば次のような流れが理想的です。
生成AI研修 → 実務PoC → 成果報告 → 次年度予算化
具体的には、
- 職員が生成AIを使って文書作成や住民対応を改善
- その効果(時間削減・ミス減少)を定量化
- 成果報告を庁内共有し、翌年度の本格導入につなげる
ポイント
この「PoC型育成」を採用すると、上層部への説得材料(費用対効果)が得られ、 “学び → 成果 → 予算化”の好循環を生み出せます。
③ “AI活用職員”を増やして自走体制をつくる
DX人材育成のゴールは、“AIを活かす人”を全庁に広げることです。
そのためには、各課にAI推進担当やデジタル活用リーダーを配置し、 成果やナレッジを横展開できる仕組みを整えることが重要です。
- 成功したAI活用事例を庁内ポータルで共有
- 部署間で相互レビュー・相談できる環境を整備
- 年次で「DXリーダー表彰」「職員発表会」を実施
DXは“外部研修で終わり”ではなく、“庁内文化を設計する活動”。
成功する自治体ほど、「継続的に学びを循環させる仕組み」を持っています。
庁内でDX文化を根付かせるには、まず「AIを自分で使ってみる」経験が不可欠です。
今すぐ始められる生成AI研修プログラムで、職員が自ら変化を生み出す力を身につけましょう。
生成AI研修で「自走する人材」を育てる
行政DXを進めるうえで、「職員がAIをどう使えるか」は、もはや避けて通れないテーマです。
中でも生成AIは、最も投資効果が見えやすく、“人材育成の起点”として最適な領域です。
実際、文書作成・会議要約・住民対応・データ整理といった業務の多くは、生成AIの活用で大幅な効率化が可能になっています。
導入コストが比較的低く、成果を“見える化”しやすい点も自治体にとって大きなメリットです。
「AIを理解し、使いこなせる職員」がDX推進の第一歩
多くの自治体がDXを進める中で直面している課題は、「AIを導入したが、職員が使いこなせない」こと。
技術よりも先に必要なのは、職員一人ひとりの“AIリテラシー”です。
この基礎がないままツールを導入しても、形だけのDXになってしまいます。
そこで有効なのが、「生成AI研修」を人材育成の起点に置くことです。
現場職員がAIを実際に使い、業務改善を自分の手で設計できるようになることが、DX文化を根付かせる最初の一歩になります。
生成AIの活用は、単なる業務効率化ではなく、「AIを使う力=企画を動かす力」 です。
AIを理解し、活用できる人材が増えることで、 庁内の企画提案や予算申請の質が上がり、次年度の事業化・予算確保にも直結します。
つまり、生成AI研修は「成果を出すための人材投資」であり、 “成果連動型の研修”として最もROI(費用対効果)が高い施策なのです。
DX人材育成を本格的に進めるなら、 まずは職員がAIを使いこなせる基礎を身につけることが出発点です。
今なら、補助金を活用して始められる研修プログラムがあります。
関連リンク
自治体DX人材育成の完全ガイド|“仕組みで育てる”研修設計と実践法
行政DXの課題とは?制度・組織・人材の“3つの壁”と解決策
まとめ|行政DXの未来は“人を育てる仕組み”で決まる
行政DXの本質は、システムやツールではなく「人が変わること」にあります。
どれほど最新のAIやデジタル技術を導入しても、 それを使いこなす職員がいなければ、改革は形だけに終わってしまいます。
国も、総務省やデジタル庁を中心に、DXを支える人材育成を最重要テーマに掲げています。
今後の行政運営では、「人材をどう育てるか」こそが自治体の競争力を左右する要素となっていくでしょう。
DXを持続的に進めるためには、 国の支援制度を上手に活用しつつ、自治体独自の育成体系を設計することが重要です。
- デジタル人材育成補助事業
- デジ田交付金(人材育成枠)
- 各種PoC支援プログラム
こうした制度を「単年度予算」ではなく、「継続的な学びの仕組みづくり」に転換することで、 限られたリソースでもDX文化を自走できる組織へと進化します。
そして、その第一歩として最も効果的なのが、 “生成AI研修”による職員スキルアップです。
AIを理解し、業務に活かせる人材を育てることが、行政DXの未来を切り拓く。
その積み重ねが、地域全体のデジタル力を底上げする原動力となります。
補助金を活用しながら、いま始められる取り組みとして、 生成AI研修はまさに“行政DXの実践的な第一歩”です。
DX推進の鍵は、「人を育てる仕組み」を動かすこと。 今すぐ、AIを使いこなす人材づくりを始めませんか?
関連記事
- Q行政DXにおける「人材育成」はなぜ重要なのですか?
- A
行政DXの成功は、システムやAIツールの導入よりも、職員がそれを使いこなせるかどうかにかかっています。
ツールを理解し、業務改善を自ら設計できる人材がいなければ、DXは一過性の取組みに終わってしまいます。
国も「DX推進計画2025」で、“人材育成をDX推進の中心”と位置づけています。
- QDX人材を育てるには、どのようなステップが必要ですか?
- A
段階的に「リテラシー教育 → 実践研修 → 定着・横展開」を行うのが効果的です。
まず全職員が共通理解を持ち、次に生成AIやRPAなどを活用した小規模実証(PoC)を実施。
成果を庁内で共有することで、自走型のDX文化が定着します。
- QDX推進に必要なスキルは何ですか?
- A
行政DXでは、単にIT知識があるだけでなく、課題を発見し、仕組みとして改善できるスキルが求められます。
戦略層(企画)・実践層(現場)・支援層(基盤)の3階層それぞれに必要なスキルを体系的に育成することが重要です。
詳しくは本文の「行政DX人材の3階層モデル」をご参照ください。
- Q国や自治体からの支援制度はありますか?
- A
はい。総務省やデジタル庁による以下の支援制度が活用できます。
- デジタル人材育成補助事業
- デジタル田園都市国家構想交付金(人材育成枠)
- 自治体情報システム標準化支援事業
これらを活用すれば、生成AI研修などの実践型育成を予算内で始めることも可能です。
- Q生成AI研修はどんな効果がありますか?
- A
生成AI研修は、文書作成や問い合わせ対応、庶務作業など行政現場の即効性が高い業務から改善できます。
また、研修を通じて「AIを理解し活用できる職員」が増えることで、
業務効率化だけでなく、次年度予算の獲得や企画立案の質向上にもつながります。