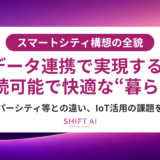ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な普及により、多くの企業が業務効率化を実現している一方で、個人情報の漏洩リスクが深刻な経営課題として浮上しています。
生成AIに入力された個人データは学習データとして活用される可能性があり、適切な対策を講じなければ個人情報保護法違反や企業の信頼失墜につながりかねません。
特に、顧客情報や従業員データを扱う企業では、一度の情報漏洩が経営存続に関わる重大な損害をもたらすリスクがあります。
本記事では、生成AIにおける個人情報漏洩の原因から法的要件、具体的な対策まで、企業が安全にAIを活用するために必要な知識を包括的に解説します。
適切なリスク管理体制を構築し、生成AIの恩恵を最大限に享受するための実践的なガイドとしてご活用ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AIで個人情報が漏洩する3つの原因
生成AIの個人情報漏洩は、主にユーザーの入力行為、システムの技術的脆弱性、データの学習・保存プロセスという3つの要因で発生します。
💡関連記事
👉AI導入に伴う情報漏洩リスクとは?経営層が知るべき対策と管理体制の構築法
ユーザーが機密データを入力するから
最も多い漏洩原因は、従業員が意図せず個人情報を生成AIに入力してしまうケースです。
ChatGPTなどの生成AIツールは使いやすさゆえに、従業員が顧客名簿、社員情報、取引先データを含む文書をそのまま入力してしまう事例が頻発しています。
特に業務効率化を目的とした文書作成や翻訳作業では、個人情報が含まれたままの資料を処理に使用するリスクが高くなります。多くの従業員は生成AIの学習機能について十分理解しておらず、無自覚のうちに機密データを外部サービスに提供している状況です。
AIシステムに脆弱性があるから
生成AIサービス自体のセキュリティホールやバグにより、保存されたデータが第三者に露出するリスクが存在します。
実際に大手生成AIサービスでは、システムの不具合により他のユーザーの会話履歴や個人情報が表示される事故が発生しました。
また、サイバー攻撃者が生成AIの脆弱性を狙った攻撃手法も確認されており、特定の質問やプロンプトを使用して本来非公開の情報を引き出す「プロンプトインジェクション攻撃」が問題となっています。
学習データとして保存・共有されるから
入力された個人情報が生成AIの学習データとして利用され、他のユーザーへの回答で出力される可能性があります。
多くの生成AIサービスは、ユーザーとの対話内容をモデルの性能向上のための学習データとして活用しています。このため、一度入力された個人情報は削除されず、将来的に別のユーザーが類似の質問をした際に出力される危険性を持ちます。
特に無料版の生成AIサービスでは、データの学習利用がデフォルト設定になっているケースが多く、オプトアウト機能の存在を知らないユーザーが大多数を占めています。
生成AIの個人情報漏洩が企業経営に与える損害
個人情報漏洩は法的制裁、顧客信頼の失墜、企業価値の毀損という形で企業経営に深刻な打撃を与えます。
個人情報保護法違反による法的制裁
個人情報保護委員会から行政処分や課徴金が科せられ、企業運営に重大な支障をきたします。
個人情報保護法に基づく改善命令や勧告を受けた場合、業務の一時停止や大幅な体制見直しが必要となります。また、悪質なケースでは刑事罰の対象となり、経営陣の責任が厳しく追及される可能性があります。
さらに、被害者からの損害賠償請求訴訟に発展するリスクもあり、長期間にわたって法的対応に追われることになります。
顧客や取引先からの信頼失墜
情報管理への不信により既存顧客の離反が進み、新規取引の獲得も困難になります。
個人情報漏洩の事実が公表されると、顧客は企業のセキュリティ体制に疑問を抱き、契約解除や取引停止を決断するケースが増加します。
特にBtoB企業では、取引先から情報管理体制の見直しや追加のセキュリティ対策実施を求められ、コンプライアンス要求が厳格化されます。一度失った信頼の回復には長期間を要し、その間の機会損失は計り知れません。
企業ブランドと市場価値の毀損
メディア報道により企業イメージが悪化し、株価下落や採用活動への悪影響が生じます。
情報漏洩事故は必ずメディアに取り上げられ、企業の危機管理能力に対する厳しい評価を受けることになります。上場企業の場合、投資家の信頼失墜により株価が大幅に下落し、企業価値の大幅な減少を招きます。
また、求職者からも敬遠される傾向が強まり、優秀な人材の確保が困難になるという長期的な影響も深刻な問題です。
生成AIと個人情報保護法の関係で知るべき法的要件
生成AIの利用は個人情報保護法上の「第三者提供」に該当する可能性が高く、適切な法的手続きが必要です。
第三者提供に該当するため本人同意が必要
生成AIへの個人データ入力は第三者提供とみなされ、原則として本人の事前同意が必要となります。
個人情報保護法では、個人データを第三者に提供する際は本人の同意を得ることを義務付けています。生成AIサービスの多くは海外企業が運営しており、データが海外サーバーに保存されるため、より厳格な手続きが求められます。
ただし、委託に該当する場合や適切なオプトアウト手続きを経た場合は例外となるケースもあるため、各サービスの利用規約を詳細に確認することが重要です。
利用目的を事前に特定して明示する
個人情報を生成AIで処理する目的を具体的に特定し、プライバシーポリシー等で明示する必要があります。
個人情報の利用目的は「できる限り特定」する必要があり、「業務効率化のため」といった抽象的な表現では不十分とされています。生成AIを使用した文書作成、翻訳、要約作業など、具体的な利用場面を明記することが求められます。
また、利用目的は個人情報を取得する前に本人に通知または公表する必要があり、既存の顧客データを生成AIで処理する場合は目的変更の手続きが必要になります。
海外AI事業者への提供は越境移転規制の対象
海外の生成AIサービスを利用する場合は、個人情報の越境移転に関する追加要件を満たす必要があります。
外国にある第三者への個人データ提供には、相手国の個人情報保護制度が日本と同等であることの確認、または適切な保護措置の実施が義務付けられています。
多くの海外AI事業者は十分な保護体制を整備していますが、利用前に当該事業者の認証取得状況やプライバシーポリシーの内容を詳細に検証することが不可欠です。契約書やデータ処理追加条項(DPA)の締結により、適切な保護措置を確保することも重要な対策となります。
生成AIの個人情報保護で企業が実施すべき5つの対策
企業は技術的対策、運用ルール、教育体制、監査機能、緊急対応の5つの観点から包括的な保護対策を実施する必要があります。
社内利用ルールを策定する
明確な利用ガイドラインを作成し、従業員が安全に生成AIを活用できる基準を設けましょう。
利用ガイドラインでは、入力禁止情報の具体的なリスト、承認が必要な利用場面、違反時の処分内容を明記する必要があります。個人情報、機密情報、取引先から受領した秘密情報は原則として入力禁止とし、例外的に利用する場合の手続きを定めることが重要です。
また、部署別・職種別の利用範囲を設定し、業務に必要な範囲でのみ生成AIを使用できる体制を構築します。
セキュアなAI環境を構築する
企業向けの生成AIサービスやAPI接続により、データの学習利用を防ぐ技術的環境を整備します。
無料版の生成AIサービスではなく、企業向けプランやAPI接続を利用することで、入力データの学習利用を回避できます。また、社内プロキシサーバーを経由したアクセス制御や、VPN接続による通信の暗号化も効果的な対策です。
可能であれば、オンプレミス環境での生成AI構築や、信頼性の高いクラウドサービスとの専用接続により、より高いセキュリティレベルを確保することを検討します。
定期的なリスク監査を行う
利用状況の定期的な監査により、ルール違反や新たなリスクを早期に発見し、対策を講じます。
監査では、生成AIの利用ログ確認、従業員へのヒアリング、実際の入力内容のサンプリングチェックを実施します。特に、個人情報を含む可能性の高い文書の処理状況や、承認手続きの遵守状況を重点的に確認することが必要です。
監査結果に基づいて利用ルールの見直しや追加教育の実施を行い、継続的な改善サイクルを確立します。
インシデント対応体制を整備する
個人情報漏洩が発生した場合の迅速な対応手順を準備し、被害の拡大を防ぐ体制を構築します。
対応手順には、事案の報告経路、初動対応の担当者、個人情報保護委員会への報告手続き、被害者への通知方法を具体的に定めます。また、生成AI事業者との連絡窓口や、削除依頼の手続き方法も事前に確認しておくことが重要です。
定期的な対応訓練の実施により、実際のインシデント発生時に適切かつ迅速な対応ができる体制を維持します。
全従業員にAI安全研修を実施する
定期的な研修により、従業員の生成AI利用リテラシーを向上させ、適切な活用方法を浸透させます。
研修内容には、個人情報保護の基本知識、生成AIの仕組みと注意点、実際の活用事例と失敗例を含める必要があります。座学だけでなく、実際の業務を想定したロールプレイング形式の訓練も効果的です。
また、新入社員研修や定期的なフォローアップ研修の実施により、継続的なリテラシー向上を図ることが重要です。
生成AIの個人情報管理体制を継続的に運用する方法
持続可能な管理体制の構築には、組織的な推進体制、定期的な見直しサイクル、外部専門家との連携が不可欠です。
経営層主導でAI推進チームを設置する
経営層がリーダーシップを発揮し、部門横断的なAI推進チームを組織して統一的な管理を実現します。
AI推進チームには、情報システム部門、法務部門、人事部門、各事業部門の代表者を配置し、技術面・法務面・運用面の全ての観点から検討できる体制を構築します。
チームの責任者は役員クラスが務め、重要な方針決定や予算承認の権限を持たせることで、迅速かつ効果的な対策実行を可能にします。月次の定例会議により、進捗管理と課題解決を継続的に行います。
月次でリスク評価と対策見直しを実行する
技術進歩や法制度の変化に対応するため、定期的なリスク評価と対策の見直しを実施します。
月次レビューでは、新たに導入された生成AIサービスの評価、利用状況の分析、発生したインシデントの検証を行います。また、個人情報保護委員会のガイドライン改訂や新たな判例についても定期的に確認し、必要に応じて社内ルールを更新します。
四半期ごとには包括的なリスクアセスメントを実施し、対策の有効性や新たな脅威への対応策を検討します。
外部専門家と連携して最新動向を把握する
法律事務所、セキュリティ会社、AI専門コンサルタントとの連携により、最新の知見を活用した対策を実現します。
特に法的要件の解釈や新たな規制動向については、個人情報保護法に精通した弁護士からの助言を定期的に受けることが重要です。また、技術的な脅威に関しては、セキュリティ専門家による最新の攻撃手法や対策技術の情報提供を受けます。
業界団体や関連学会への参加を通じて、他社の取り組み事例や業界標準の動向を把握し、自社の対策に反映させることも効果的な手法です。
まとめ|生成AIの個人情報保護は適切な対策と継続的な教育で実現可能
生成AIの個人情報漏洩リスクは、ユーザーの入力行為、システムの脆弱性、データの学習利用という3つの要因により発生し、企業経営に深刻な損害をもたらす可能性があります。
しかし、適切な利用ルールの策定、セキュアな環境構築、従業員教育の実施により、これらのリスクを効果的に管理することができます。
重要なのは、個人情報保護法の要件を正しく理解し、段階的かつ継続的な対策を実行することです。まずは緊急度の高い利用ルール策定と基礎教育から開始し、技術的対策や管理体制を順次整備していきましょう。
生成AIは適切に活用すれば企業の競争力向上に大きく貢献します。リスクを恐れて活用を諦めるのではなく、正しい知識と体制構築により安全な利用を実現することが、これからの企業経営には不可欠です。
より具体的な対策実行や社内教育の充実を検討されている方は、専門的な支援を受けることも有効な選択肢の一つです。

生成AIの個人情報保護に関するよくある質問
- Q生成AIに個人情報を入力すると必ず漏洩しますか?
- A
適切な設定と利用方法により、個人情報漏洩のリスクを大幅に軽減できます。 企業向けプランの利用、データ学習のオプトアウト設定、入力内容の事前チェックなどの対策を講じることで、安全な活用が可能です。完全にリスクをゼロにすることは困難ですが、適切な管理により実用レベルでの安全性を確保できます。
- Q無料版ChatGPTと有料版では個人情報の扱いに違いがありますか?
- A
有料版のChatGPT Plusでも、デフォルト設定では入力データが学習に利用される可能性があります。重要なのは無料・有料の違いではなく、データ学習のオプトアウト設定や企業向けAPIの利用です。 企業利用の場合は、データ処理追加条項(DPA)が締結できるChatGPT for BusinessやAPI利用を検討することが推奨されます。
- Q従業員が誤って個人情報を入力してしまった場合の対処法は?
- A
即座に該当する会話履歴を削除し、生成AI事業者への削除依頼を行うことが最優先です。 同時に、影響範囲の特定、関係者への報告、必要に応じて個人情報保護委員会への報告を実施します。被害拡大を防ぐため、迅速な初動対応と適切な報告手順の実行が重要となります。
- Q社内で生成AI利用ルールを作る際の重要ポイントは?
- A
入力禁止情報の具体的なリスト作成と、承認が必要な利用場面の明確化が最重要です。 個人情報、機密情報、取引先秘密情報の入力禁止、例外利用時の承認手続き、違反時の処分内容を明記します。また、部署別・職種別の利用範囲設定により、業務に必要な範囲での適切な活用を促進できます。