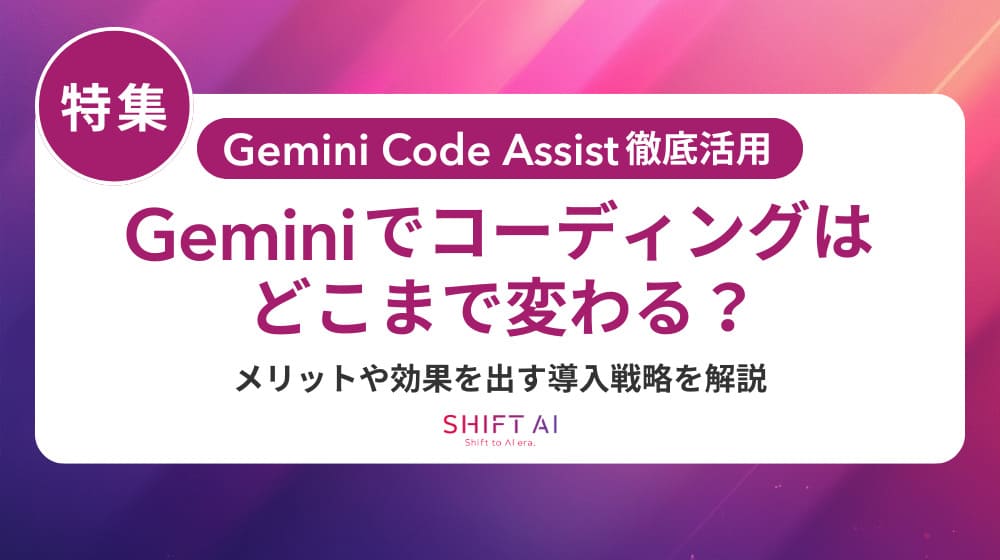「Gemini Code Assistを使うと、GoogleのAIがあなたのコードやプロンプト内容を学習してしまうのではないか」
そんな不安を抱くエンジニアや情報システム担当者は少なくありません。
実際、Gemini Code Assistは高精度なコード補完やレビューを可能にする一方で、 「入力内容がAI学習に使われる可能性がある」とGoogle公式が明記しています。
この仕組みを正しく理解し、学習させない設定(オプトアウト)を行うことが、安全にAI開発を進める第一歩です。
しかし、設定をオフにするだけでは不十分です。企業利用の場合、アカウント管理や社内ルールの整備ができていなければ、機密情報が外部に送信されるリスクは依然として残ります。
この記事では、Gemini Code Assistを学習させないための設定方法や個人利用と企業利用のリスクの違いなどを、Google公式情報と実務的な視点から徹底解説します。AIを活用することは、同時に「情報をどう守るか」を設計することでもあります。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Gemini Code Assistとは?仕組みとデータ利用の基本を理解する
Gemini Code Assistは、Googleが開発したAIコード補完ツールです。VSCodeやJetBrainsなどの開発環境に拡張機能として導入し、プログラマーが入力したコード内容から次の行を予測・提案します。つまり、AIがコードの文脈を理解して開発効率を高めてくれる存在です。
この便利な仕組みの裏側では、入力されたコードやプロンプト情報がGoogle側へ送信される場合があります。ここを正しく理解することが、「Gemini Code Assistを学習させない」ための第一歩となります。
AIがコードを「学習する」とはどういう意味か
まず整理しておきたいのは、AIの「学習」と「補完」は別の概念だということです。
AIは通常、過去に与えられた大量のデータをもとにモデルを学習(トレーニング)し、その結果を使って新しい予測を行います。一方、Gemini Code Assistが日常的に行っているのは「推論(インファレンス)」であり、入力内容をもとに即座に回答を生成するプロセスです。
ただし、一部の利用モードでは入力内容が匿名化され、GoogleのAIモデル改善に活用されることがあります。これが「学習させない設定」を行うべき理由です。
ここを誤解したまま利用すると、社内コードや機密ロジックが外部の学習プロセスに含まれる可能性が生じます。後述するオプトアウト設定を行うことで、このリスクを回避できます。
Gemini Code Assistで送信されるデータの種類
Gemini Code Assistが扱う情報は、Google公式の「Privacy Notice for Gemini Code Assist」で明確に定義されています。
主に送信されるデータには次のようなものがあります。
- 入力中のコードスニペットやプロンプト内容
- エラーやバグレポートなどの技術情報
- 補完提案に関するユーザー操作ログ(承諾・拒否など)
これらのデータはGoogleのサーバーで一時的に処理され、AIモデルの品質向上に使われる場合があると明記されています。
| “Data submitted through Gemini Code Assist may be used to improve Google services.”(出典: Google Developers「Privacy Notice for Gemini Code Assist(個人向け)」 , 最終更新:2025年9月17日) |
つまり、ユーザーのコードがそのままAIの学習素材になるケースもあるということです。これを防ぐためには、個人アカウントと企業アカウントのデータ扱いの違いを理解することが重要です。
なお、Gemini Code Assistの全体像や他ツールとの違いについては、Gemini Code Assistとは?使い方・機能・Copilotとの違いを徹底解説で詳しく解説しています。続く章では、どのような条件でAIが学習を行うのか、そしてどの利用形態なら学習を防げるのかを見ていきましょう。
Gemini Code Assistは本当に学習する?Googleのデータ利用方針を解説
Gemini Code Assistの「学習リスク」を理解するには、まずGoogleのデータ利用方針を正確に把握することが欠かせません。多くのユーザーが「入力したコードをGoogleが学習してしまうのでは?」と懸念しますが、実際には利用形態によってデータの扱いが異なります。
ここでは、個人アカウントと企業アカウント(Enterprise版)の違いを整理しながら、データがどのように処理されるのかを見ていきましょう。
個人利用では学習に使われる可能性あり
Google公式の「Privacy Notice for Gemini Code Assist」によると、個人アカウントでGemini Code Assistを利用する場合、入力データがAIモデルの品質改善に使われる可能性があると明示されています。これは、Geminiがより正確な提案を行うために、ユーザーから提供された情報を匿名化して分析する仕組みです。
つまり、コード内容・関数名・コメント・エラーログなどが、一部Googleのシステム上で保存・解析されることがあります。Google側では安全対策として暗号化や匿名化を施していますが、企業の機密情報を扱う開発環境でそのまま使用するのはリスクが高いといえます。
個人利用では、次章で紹介する「学習させない(オプトアウト)設定」を必ず実施することが推奨されます。これを行うだけでも、AIへの学習利用を最小限に抑えられます。
企業利用(Enterprise版)では学習されない
一方、Gemini Code Assist Enterprise版(Google Workspace・Gemini for Business契約)では、データ取り扱いが根本的に異なります。Googleはこの契約下で明確に、顧客データはAIモデルのトレーニングには利用されないと保証しています。
この仕組みでは、企業ごとに独立したデータ環境が用意され、コードやプロンプトがGoogleの汎用AI学習基盤に共有されることはありません。さらに、アクセス権限・ログ管理・監査機能などが標準装備されており、情報漏洩のリスクを構造的に遮断できる点が強みです。
特に、クラウドセキュリティの観点から見ると、Enterprise契約は社内開発環境をGoogle Cloud上に閉じることができるため、「生成AIを使いながらも学習を完全に遮断できる」唯一の選択肢といえます。
Gemini Code Assistを本格導入する前に、利用目的とアカウント種別を切り分けることが不可欠です。次の章では、実際に「学習させない」ための具体的な設定方法を詳しく見ていきます。
Gemini Code Assistを学習させないための具体的な設定方法
Gemini Code Assistは、設定を適切に行うことでAI学習へのデータ利用を制限できます。ここでは、個人アカウント・開発環境・CLI利用の3つのケースに分けて、学習をさせないための手順を整理します。
個人アカウントでのオプトアウト設定
Googleアカウントを利用してGemini Code Assistを使用している場合は、「モデル改善のためのデータ共有」をオフにする設定が重要です。設定は以下の手順で行えます。
- Googleアカウントにログイン
- 「データとプライバシー」タブを開く
- 「モデル改善のためのデータ共有」項目をオフにする
- 設定を保存して完了
これにより、Gemini Code Assistを通じて送信されるコードやプロンプト内容が、AI学習モデルに利用されなくなります。
なお、設定変更後も過去に送信されたデータは学習プロセスに反映される可能性があるため、必要に応じて「アクティビティ履歴の削除」も実施しておきましょう。
VSCode・JetBrains連携時の注意点
Gemini Code AssistをVSCodeやJetBrainsと連携させて利用する場合、拡張機能経由で送信されるデータにも注意が必要です。これらの統合環境では、補完精度向上のために操作ログやエラーデータが自動送信される仕組みがあります。
このリスクを軽減するには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 開発環境の「自動ログ送信」をオフにする
- キャッシュフォルダを定期的に削除する
- APIキーや環境変数に個人情報・社内固有情報を含めない
特に社内専用ライブラリや業務ロジックを扱うプロジェクトでは、AI補完機能の利用範囲を限定することが安全です。Gemini Code Assistの高機能を活かしつつ、情報流出を防ぐ設定を心がけましょう。
CLI・API利用時の設定(開発者向け)
開発者がGemini Code AssistをCLI経由で利用する場合は、設定ファイルまたは環境変数でログ送信を無効化できます。Google Cloud CLIを使う場合、以下のようなコマンドで制御可能です。
gcloud config set disable_data_logging true
この設定を有効にすると、Gemini Code Assistが送信する履歴データや補完ログがGoogle側に保存されなくなります。
CLIやAPIでの利用は、エンジニアが直接制御できる利点がある一方で、設定ミスによる情報送信リスクも高いため、チーム内での統一設定・レビュー運用を徹底することが重要です。
Gemini Code Assistの設定を整えることで、AIの恩恵を受けながらもデータ学習を完全に遮断することが可能になります。次では、こうした設定をしてもなお残る「企業利用特有のリスク」について掘り下げていきます。
学習を止めても安心できない?企業導入で見落とされがちな3つのリスク
Gemini Code Assistでオプトアウト設定を行えば、AIがコードを学習するリスクは大きく減ります。しかし、設定をしただけでは安全とは言えません。企業導入においては、運用や管理の仕組みそのものに潜むリスクを見落としがちです。ここでは、設定後も注意すべき3つのポイントを整理します。
利用者単位で設定がバラつく
最も多い落とし穴が、利用者ごとに設定状況が異なることです。部署単位で異なるGoogleアカウントを利用している場合、一部の利用者がオプトアウトを行っておらず、意図せずデータ送信が発生するケースがあります。これにより、社内のコード断片やシステム構成が外部に流出するリスクが残ります。
特に、フリーランスや業務委託エンジニアが社内環境にアクセスする場合、共通ポリシーでの統一管理が不可欠です。
社内規定が未整備のまま導入している
AI補完ツールを導入しても、利用ルールを定めていない企業は少なくありません。Gemini Code Assistがどこまでの情報を処理し、どのデータを送信するのかを明確に理解していなければ、社員が不用意に機密情報を入力する恐れがあります。
- 「プロジェクトコード名や顧客情報を入力しない」
- 「AIが提案したコードは必ずレビューする」
- 「オプトアウト設定を確認してから使用する」
こうしたルールを明文化するだけでも、リスクは大幅に軽減されます。
教育・周知不足によるヒューマンエラー
設定や規定があっても、現場のエンジニアが内容を理解していなければ意味がありません。特に、新入社員や外部委託者はAIツールの設定状況を知らずに利用するケースが多く、結果的に情報が送信されてしまうこともあります。
このようなヒューマンエラーを防ぐには、定期的な研修と社内教育が欠かせません。設定手順やリスクを共有する場を設け、全員が同じ理解を持てるようにすることが重要です。
Gemini Code Assistを学習させないための設定は、スタートラインに過ぎません。安全に運用する仕組みを作ることこそが、真のリスク対策です。次の章では、企業が具体的に取るべき安全な運用体制づくりを解説します。
企業が取るべき安全な運用対策
Gemini Code Assistを安全に活用するには、設定だけでなく運用体制の整備が不可欠です。ここでは、企業が取り組むべき3つの具体策を紹介します。これらは、AI導入時のリスクマネジメントにも直結する基本指針です。
ルールを定義する(AI利用ガイドラインの策定)
AIツールを安全に使うためには、まず社内共通ルールを定めることが最優先です。特にGemini Code Assistのようにコードを扱うAIでは、入力する情報の線引きを明確にする必要があります。ガイドラインには次のような項目を盛り込みましょう。
- 機密情報・顧客情報・内部変数名などは入力しない
- AIが提案したコードは必ず人がレビューする
- 新規導入時にはセキュリティ部門への申請・承認を経る
このようなルールを整備しておけば、個々のエンジニアの判断に依存せず、統一されたセキュリティ基準でAIを活用できます。
監査・教育を定期的に実施する
ガイドラインを作成しても、運用が形骸化すれば意味がありません。特に設定変更やツール更新によってポリシーが変わる場合は、定期的な監査が必要です。
- オプトアウト設定が有効になっているかの確認
- AIツール利用履歴やアクセス権限の点検
- 社内勉強会による意識向上
これらを継続的に実施することで、社員一人ひとりがリスクを理解し、自律的に安全運用を行えるようになります。「教育=セキュリティ」と位置づけて運用することが理想です。
Enterprise版での統制が最も確実
最も堅牢な方法は、Gemini Code Assist Enterprise版を導入することです。Enterprise契約では、AIがコードを学習することが完全に無効化され、データは企業専用環境内でのみ処理されます。さらに、アクセス権限・ログ管理・監査証跡の一元化も可能です。
| 項目 | 個人利用 | Enterprise利用 |
| データ学習 | 一部利用される可能性あり | 利用されない(保証あり) |
| ログ管理 | 各ユーザー任意 | 管理者が一元制御 |
| アクセス制御 | 個別設定 | 組織ポリシーで統制 |
| セキュリティ監査 | なし | ISMS/Cloud監査に対応 |
こうした仕組みによって、AIを活用しながら情報保護を両立できる体制を構築できます。
AI導入の本質は、ツールを導入することではなく、安全に使いこなすための組織的な設計にあります。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、こうした社内設計を支援する「SHIFT AI for Biz」研修を展開しています。AI導入・運用・セキュリティを体系的に学びたい方は、下記のページをぜひご覧ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
他のAIコード補完ツールとの安全性比較(Copilot・Cursorなど)
Gemini Code Assistの安全対策を理解したうえで、他の主要なAIコード補完ツールと比較しておくことは重要です。多くの企業が「どのツールが最も安全か」を判断材料に導入を検討しているため、この比較は検索ユーザーのニーズにも直結します。
下記の表は、代表的なAIコード補完ツール3つを「データ学習」「法人対応」「管理機能」の観点で整理したものです。
| ツール名 | 学習データ利用 | 法人利用の安全性 | 管理機能 | 備考 |
| Gemini Code Assist | 個人利用ではAI学習に使用される可能性あり。Enterprise版では無効化可 | 非常に高い(Google Cloud統合) | 管理者統制・監査証跡あり | Google製ツールとして信頼性が高い |
| GitHub Copilot | 一部データをAI学習に利用。Business契約で制御可 | 高い(Microsoft Entra統制) | ログ管理・アクセス権設定あり | コード提案品質に定評 |
| Cursor | 入力履歴が一部クラウド送信される場合あり | 中程度(個人向け設計) | 設定による制限可 | 開発効率重視ツール |
この比較からも分かるように、セキュリティ重視の企業導入にはGemini Code Assist Enterprise版が最も適しているといえます。Google Cloud環境との親和性が高く、アクセス権限やデータ統制を一元的に管理できるため、他ツールよりも情報漏洩リスクを抑えられます。
また、Gemini Code AssistはGoogle Workspaceと連携できる点も特徴です。すでに社内でGmailやDriveを利用している企業であれば、追加導入コストを抑えながらセキュアな開発環境を整備できるという利点があります。
他ツールの選定基準や導入コストについては、Gemini Code Assistの料金・機能の比較!チーム導入コストを最適化するポイントでも詳しく解説しています。続く章では、これまでの要点を整理し、Gemini Code Assistを安全に使いこなすための最終まとめを行います。
まとめ:学習させない設定と運用体制で、AIを安心して活用しよう
Gemini Code Assistは、設定と運用を正しく行えば高精度かつ安全に利用できるAIコード補完ツールです。個人利用ではオプトアウト設定を必ず確認し、企業利用ではEnterprise契約と社内ルール整備を組み合わせることで、学習リスクをほぼゼロにできます。
ここまでの要点を改めて整理しましょう。
- 個人利用:Googleアカウントの「モデル改善のためのデータ共有」をオフに設定する
- 企業利用:Enterprise版でデータ学習を無効化し、アクセス権限を一元管理する
- 運用体制:AI利用ガイドラインと教育を組み合わせ、全社的にリスクを管理する
Gemini Code Assistを導入する目的は、単なる効率化ではなく、安全にAIを使いこなす組織力の強化にあります。AIを学習させない設定を「守り」として、安心して開発を進められる環境を整えることが、結果的に企業競争力を高める最短ルートです。
Gemini Code Assistのよくある質問(FAQ)
- QGemini Code Assistで入力したコードはGoogleに保存されますか?
- A
個人アカウントで利用している場合、入力内容がGoogleのサーバーを経由し、一部がAIモデル改善のために利用される可能性があります。ただし、Enterprise契約下では顧客データがAI学習に使用されないことが保証されています。つまり、企業導入時に学習リスクを完全に回避したい場合は、Enterprise版の利用が必須です。
- Q学習を完全に止める方法はありますか?
- A
はい。Googleアカウントの「モデル改善のためのデータ共有」をオフに設定することで、Gemini Code Assist経由で送信されるデータがAI学習に使われなくなります。さらに安全性を高めるには、アクティビティ履歴の削除やログ送信の停止も行うとより確実です。
- Q社内でGemini Code Assistを安全に利用するには?
- A
まず、AI利用ガイドラインを策定し、利用範囲と禁止事項を明文化することが重要です。加えて、定期的な社員教育やオプトアウト設定の確認を行うことで、ヒューマンエラーを防止できます。SHIFT AIでは、こうした社内運用の設計から教育までを支援しています。
- QCopilotやCursorと比べてどちらが安全ですか?
- A
Gemini Code Assist Enterprise版が最もセキュリティレベルが高いといえます。Google Cloud環境内で動作し、データの取り扱いが厳格に管理されるため、企業利用に適しています。CopilotもBusiness契約で安全性を確保できますが、管理機能や統制範囲ではGeminiのほうが一歩上です。
Gemini Code Assistの最新仕様や設定方法については、Gemini Code Assistとは?使い方・機能・Copilotとの違いを徹底解説もあわせて確認しておくと理解が深まります。