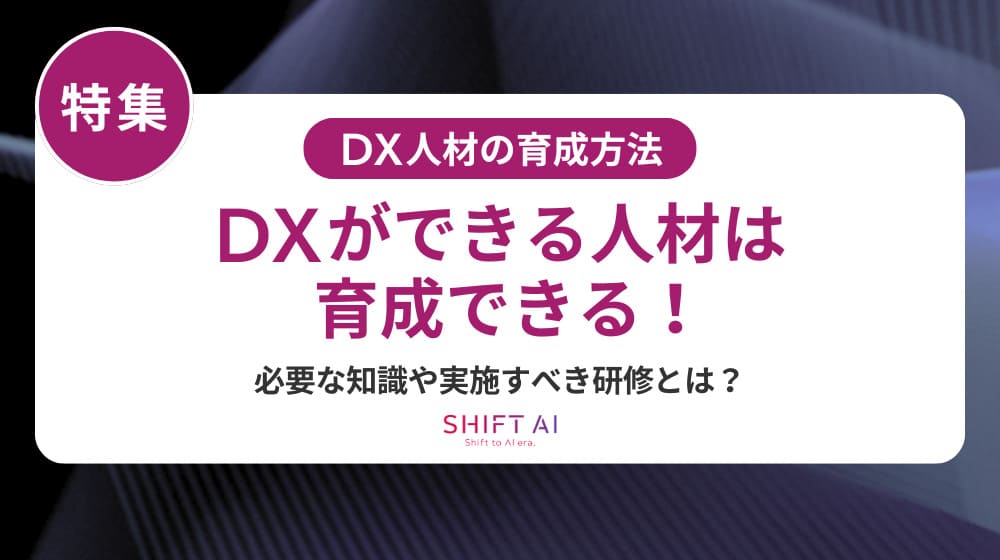2025年現在、生成AIの急速な普及により、企業におけるITリテラシーの重要性はかつてないレベルまで高まっています。
しかし、多くの会社では依然として「パソコンの基本操作ができない」「セキュリティ意識が低い」「新しいツールを使いこなせない」といった社員のITリテラシー不足に悩まされているのが実情です。
従来の「エクセルが使える」「メールができる」程度のスキルでは、もはや業務に支障をきたすレベルに達しており、情報漏洩リスクの増大や業務効率の著しい低下、さらには生成AI活用格差による競争力低下まで招いています。
本記事では、ITリテラシーが低い会社の特徴から根本的な解決策まで、2025年版の最新対策を包括的に解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
社員のITリテラシーが低い会社の特徴とは
ITリテラシーが低い会社には明確な共通点があります。これらの特徴に当てはまる企業では、業務効率の低下や深刻なセキュリティリスクが発生しやすくなります。
ITに苦手意識を持つ社員が多い
ITツールの導入を避けたがる社員が目立つのは、ITリテラシーが低い会社の典型的な特徴です。
新しいシステムやソフトウェアが導入されても「難しそう」「覚えるのが面倒」といった理由で使用を避ける傾向があります。エクセルの関数機能を使わずに手計算で作業したり、クラウドツールではなく従来の紙ベースでの管理を続けたりするケースが頻繁に見られます。
結果として、業務の自動化や効率化が全く進まず、競合他社との生産性格差が拡大していきます。
自分で調べずに人に聞く習慣がある
わからないことがあっても検索せず、すぐに周囲に質問する社員が多いことも大きな問題となっています。
Google検索やマニュアル確認といった基本的な自己解決スキルが身についておらず、システムエラーや操作方法で困るたびに他の社員に依存してしまいます。この結果、質問される側の業務が頻繁に中断され、全体の作業効率が大幅に低下します。
さらに、自分で調べる習慣がないため、ITスキルの向上も期待できません。
セキュリティ意識が著しく低い
情報漏洩につながる危険な行為を無意識に行っている社員が存在するのも深刻な特徴です。
怪しいメールの添付ファイルを安易に開いたり、パスワードを使い回したり、社外でUSBメモリを紛失したりするケースが後を絶ちません。また、SNSに社内情報を投稿してしまうような事態も発生しがちです。
一度の情報漏洩事故で企業の信頼は地に落ち、数億円規模の損失を被る可能性があります。
生成AIツールを使いこなせない
ChatGPTなどの生成AIツールの活用が全く進んでいない状況も現代特有の課題といえます。
2025年現在、多くの業務で生成AIが活用されているにも関わらず、基本的な使い方すら理解できていない社員が大半を占めています。資料作成やメール文面の作成、データ分析など、AIで効率化できる作業を依然として手作業で行っているのが実情です。
この結果、AI活用が進んだ競合他社との業務効率格差が大幅に拡大してしまいます。
ITリテラシーが低い会社で起こる深刻な問題
社員のITリテラシー不足は、企業経営に致命的な打撃を与える可能性があります。
単なる業務の非効率にとどまらず、企業の存続を脅かす深刻なリスクを生み出しているのが現実です。
情報漏洩リスクが高まる
ITリテラシーの低い社員による人為的ミスが情報漏洩の最大要因となっているためです。
フィッシングメールに騙されてログイン情報を入力してしまったり、重要なファイルを誤って外部に送信したり、USBメモリを紛失したりするケースが頻発しています。また、弱いパスワードの使用や同一パスワードの使い回しにより、不正アクセスを許してしまう事例も後を絶ちません。
一度の情報漏洩事故で企業は顧客からの信頼を失い、損害賠償や事業停止に追い込まれる可能性があります。
業務効率が大幅に低下する
ITツールを活用できない社員が作業のボトルネックになっている状況が深刻化しています。
エクセルの基本機能すら使えずに手作業で集計を行ったり、クラウドストレージの共有機能を理解できずに何度もメールでファイルをやり取りしたりする光景が日常的に見られます。さらに、新しいシステムを導入しても操作方法を覚えられず、結局使われないまま放置されるケースも多発しています。
このような状況では、どれだけ優秀なツールを導入しても生産性向上は期待できません。
DX推進が全く進まない
社員のITスキル不足がデジタルトランスフォーメーションの最大の障壁となっているのが実情です。
経営層がDXの重要性を理解してシステム投資を行っても、現場の社員がツールを使いこなせなければ意味がありません。データ分析ツールを導入してもレポートが読めない、業務自動化ツールを入れても設定できない、といった問題が次々と発生します。
結果として、DX投資が無駄になり、競合他社との差は開く一方となってしまいます。
生成AI活用格差で競争力を失う
生成AIを活用できない企業が市場から取り残される時代になっていることが最大の脅威です。
資料作成、顧客対応、マーケティング施策の立案など、あらゆる業務で生成AIが活用されているにも関わらず、ITリテラシーの低い会社では全く導入が進んでいません。競合他社が短時間で高品質なアウトプットを生み出している間に、依然として手作業で時間をかけて作業を行っています。
この技術格差は今後さらに拡大し、事業の継続自体が困難になる可能性があります。
社員のITリテラシーが低い状態が続く根本原因
なぜ多くの会社で社員のITリテラシーが向上しないのでしょうか。問題の根本には、企業側と社員側の両方に構造的な課題が存在しています。
会社側の教育体制が整っていない
体系的なIT教育カリキュラムが存在せず、場当たり的な対応に終始していることが最大の問題です。
多くの企業では、新しいツールを導入する際に簡単な操作説明を行うだけで、基礎的なITスキルから段階的に学べる仕組みがありません。また、IT教育を担当できる人材が社内におらず、外部研修も予算の都合で実施できないケースが大半を占めています。
さらに、経営層自体がITリテラシーの重要性を十分に理解していないため、教育投資の優先順位が低くなりがちです。
社員側の学習意欲が低い
「今のやり方で十分」という固定観念と新しいスキル習得への抵抗感が根深く存在しています。
特に中堅・ベテラン社員の中には、これまでのアナログな手法で業務をこなしてきた自負があり、ITツールの必要性を感じていない人が多く見られます。また、新しい技術を覚えることへの不安や、失敗を恐れる気持ちが学習を阻害している場合も少なくありません。
年齢を重ねるほど学習コストが高く感じられ、「覚えるのが面倒」という理由で避けてしまう傾向が強まります。
生成AI時代の新スキルに対応できていない
従来のIT教育では生成AIなどの最新技術に全く対応できていない状況が深刻化しています。
多くの企業のIT研修は、エクセルやパワーポイントといった基本ソフトの使い方にとどまっており、ChatGPTやCopilotなどの生成AIツールについては全く触れられていません。また、AI活用のためのプロンプト作成スキルや、AI生成コンテンツの品質評価能力といった新しいリテラシーの重要性も認識されていないのが現状です。
この結果、2025年に求められるITスキルと実際の教育内容との間に大きなギャップが生まれています。
ITリテラシーが低い会社がすべき改善方法
社員のITリテラシー向上には、体系的なアプローチが不可欠です。場当たり的な対応ではなく、段階的で継続的な改善プロセスを構築することが成功の鍵となります。
💡関連記事
👉DX人材育成の完全ガイド|AI時代に求められるスキルと効果的な6ステップ
現状のITスキルレベルを正確に把握する
全社員のITリテラシーを客観的に測定し、個人別・部署別の課題を明確化することから始めましょう。
アンケート調査やスキルチェックテストを実施して、基本的なパソコン操作から生成AI活用まで幅広い項目で現状を把握します。単に「できる・できない」だけでなく、どの程度のレベルで理解しているかを詳細に分析することが重要です。
この診断結果をもとに、優先的に改善すべき領域と具体的な教育プランを策定できます。現状把握なしには効果的な改善策は立てられません。
段階的な教育プログラムを実施する
基礎スキルから応用まで、レベル別に体系化された研修カリキュラムを構築する必要があります。
初級者向けには基本的なパソコン操作やセキュリティ意識の向上、中級者向けには業務効率化ツールの活用方法、上級者向けには生成AI活用やデータ分析スキルといった具合に、段階的に学習できる仕組みを作ります。
また、集合研修だけでなくeラーニングや個別指導も組み合わせることで、個人のペースに合わせた学習が可能になります。
重要なのは、一度の研修で終わらせるのではなく、継続的な学習機会を提供することです。
実務で使えるITツールを積極導入する
業務に直結するツールを導入し、実践的な環境で学習できる機会を創出することが効果的です。
クラウドストレージ、ビジネスチャット、プロジェクト管理ツールなど、日常業務で必須となるツールを段階的に導入していきます。ただし、一度に多くのツールを導入するのではなく、社員が慣れてから次のステップに進むことが重要です。
また、ツール導入時には十分なサポート体制を整え、操作マニュアルの作成や質問対応窓口の設置も忘れてはいけません。
生成AI研修を含む包括的教育を行う
従来のIT教育に加えて、生成AI活用スキルを組み込んだ総合的な人材育成を実施しましょう。
ChatGPTやCopilotなどの基本的な使い方から、効果的なプロンプト作成、AI生成コンテンツの品質評価まで、実務で活用できるレベルまで教育を行います。単なるツールの操作方法ではなく、AIを活用した業務プロセスの改善や新しい価値創造についても学習内容に含めることが大切です。
生成AI時代に対応できる人材を育成することで、競合他社との差別化を図れます。
ITリテラシーが低い会社が成功するための重要ポイント
ITリテラシー向上の取り組みを成功させるためには、単に研修を実施するだけでは不十分です。組織全体でのコミットメントと継続的な改善体制の構築が不可欠となります。
経営層がITリテラシー向上にコミットする
経営陣が率先してITリテラシーの重要性を発信し、十分な予算と時間を確保することが最も重要です。
トップダウンでの明確なメッセージがなければ、現場の社員は「やらされ感」を持ってしまい、真剣に取り組もうとしません。経営層自身がITツールを積極的に活用し、その効果を実感していることを社員に示すことも大切です。
また、ITリテラシー向上を人事評価の項目に組み込んだり、成果を上げた社員を表彰したりすることで、学習へのモチベーションを高められます。
継続的な学習環境を整備する
一度きりの研修ではなく、常に最新のスキルを学び続けられる仕組みを構築する必要があります。
IT技術は日進月歩で進化しているため、定期的なスキルアップデートが欠かせません。月次の勉強会開催、最新ツールの情報共有、社内での成功事例発表会など、様々な学習機会を継続的に提供します。
さらに、社員同士が教え合えるメンター制度や、疑問点をすぐに解決できるヘルプデスク体制の整備も重要な要素となります。
外部専門機関と連携して効率化する
社内リソースだけでは限界があるため、専門的な知見を持つ外部機関との連携を積極的に活用することが成功の鍵です。
ITリテラシー教育に特化した研修会社や、生成AI活用に詳しいコンサルティング会社などとパートナーシップを組むことで、より効果的で実践的な教育プログラムを実現できます。また、最新のトレンドや業界のベストプラクティスについても継続的に情報を得られます。
自社だけで全てを解決しようとせず、専門機関の力を借りることで確実な成果を上げられます。
まとめ|社員のITリテラシーが低い会社は今すぐ行動を
社員のITリテラシーが低い会社では、情報漏洩リスクの増大、業務効率の著しい低下、DX推進の停滞といった深刻な問題が発生しています。特に2025年現在、生成AI活用格差により競合他社との差は日々拡大しており、早急な対策が求められる状況です。
改善には、まず現状の正確な把握から始めて、段階的な教育プログラムの実施、実務に直結するITツールの導入が不可欠となります。そして何より重要なのは、従来のIT教育に加えて生成AI活用スキルまで含めた包括的な人材育成です。
ただし、自社だけでこれらすべてを実現するには限界があります。専門機関との連携により、効率的で確実な成果を目指すことが現実的な解決策といえるでしょう。貴社の状況に応じた最適な改善プランについて、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。

社員のITリテラシーが低い会社に関するよくある質問
- QITリテラシーが低い社員の特徴は何ですか?
- A
ITリテラシーが低い社員には、新しいツールを避けたがる、わからないことを自分で調べずすぐに人に聞く、セキュリティ意識が薄い、生成AIなどの最新技術を全く使えないといった特徴があります。特に「難しそう」という理由だけでITツールの使用を拒む傾向が強く見られます。
- QITリテラシーが低いとどんな問題が起こりますか?
- A
情報漏洩リスクの増大、業務効率の著しい低下、DX推進の停滞、生成AI活用格差による競争力低下などの深刻な問題が発生します。一度の情報漏洩事故で企業の信頼と多額の損失を被る可能性があり、企業存続に関わる重大なリスクとなります。
- Qなぜ社員のITリテラシーが向上しないのですか?
- A
会社側の教育体制不備、社員側の学習意欲低下、生成AI時代の新スキルへの対応不足が主な原因です。特に体系的なIT教育カリキュラムが存在せず、場当たり的な対応に終始している企業が大半を占めています。
- QITリテラシー向上のために最初に何をすべきですか?
- A
まず全社員のITスキルレベルを客観的に診断し、個人別・部署別の課題を明確にすることから始めましょう。現状把握なしには効果的な改善策は立てられません。アンケートやスキルチェックテストを活用して、具体的な教育プランの策定につなげることが重要です。
- Q生成AI研修は本当に必要ですか?
- A
2025年現在、生成AI活用は競争力維持に不可欠な要素となっています。ChatGPTやCopilotなどの基本操作から効果的なプロンプト作成まで、従来のIT教育だけでは生成AI時代に対応できません。包括的な人材育成により競合他社との差別化を図ることが可能になります。