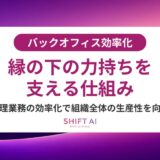Copilotを導入したものの、「思ったほど精度が上がらない」「何をどう指示すればいいのか分からない」と感じていませんか。ChatGPTと同じように見えても、CopilotはMicrosoft 365に統合された“業務特化型AI”。
成果を左右するのは、AIの性能ではなくプロンプト(指示)の設計力です。
本記事では、Copilotの特性を踏まえたプロンプトエンジニアリングの基本から実践フレーム、そして社内展開までをわかりやすく解説します。
AIを“ただ使う”段階から、“成果を出す”段階へ。業務効率化を超えて、全社的なCopilot活用を進めたいリーダーや情報システム部門の方に向けた実践ガイドです。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜCopilotで「プロンプトエンジニアリング」が成果を分けるのか
「Copilotを導入したのに成果が出ない」という声の多くは、AIの性能ではなくプロンプト(指示)の設計方法に原因があります。
ChatGPTなどの汎用AIと異なり、CopilotはMicrosoft 365の文書・メール・スプレッドシートなど、実際の業務データを参照して動作する“実行型AI”です。つまり、AIに自由に考えさせるよりも、「どの文脈で・何を・どんな形式で出力してほしいか」を明確に伝える必要があります。
たとえば、ChatGPTに「会議の議事録をまとめて」と指示すれば、要約文を自動生成します。しかしCopilotに同じ指示をしても、文書やTeamsの内容を参照し、「誰向けの要約か」「何の目的か」が指定されていなければ、実用レベルの結果は得られません。
この違いこそが、Copilotでプロンプトエンジニアリングを学ぶ最大の価値です。
AIは万能ではなく、人の指示設計力が成果を決定づける時代に入っています。
社内文書や顧客データと連携できるCopilotだからこそ、「業務理解 × プロンプト設計」を磨くことで、精度も生産性も大きく変わります。
関連記事:
プロンプトエンジニアリングとは?企業が成果を出すAI活用の実践戦略
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
Copilotにおけるプロンプト設計の基本フレーム
Copilotで思いどおりの結果を得るためには、「勘」ではなく再現性のあるプロンプト設計フレームを使うことが重要です。
Microsoft公式のベストプラクティスや現場での成功事例をもとに整理すると、効果的なプロンプトは次の4つの要素で構成されます。
① 目的を明確にする ― “何をしたいのか”を最初に伝える
AIは「目的」から逆算して出力を組み立てます。
たとえば「会議メモを要約して」よりも、「営業会議の議事録を、取締役会向けの3分要約にまとめて」と具体化することで、出力の方向性が明確になります。
目的があいまいなプロンプトほど、Copilotは迷うと理解しておきましょう。
② 文脈・条件を補足する ― “どんな状況で使うのか”を添える
CopilotはMicrosoft 365上のデータを参照できるため、条件を与えると精度が一気に上がります。
「このExcel表をもとに」「添付のWord文書の内容を踏まえて」「営業部門に共有する前提で」など、文脈情報をセットで伝えることがポイントです。
文脈が具体的なほど、“社内で使える成果物”に近づきます。
③ 出力形式を指定する ― “どんな形で欲しいか”を明示する
Copilotはフォーマット指示に非常に強いAIです。
「箇条書きで3点にまとめて」「社内メールのテンプレートに沿って」「報告書として整形して」など、完成イメージを提示するほど整った結果が得られます。
この「形式指定」が、ChatGPTとの大きな違いでもあります。
④ 検証と改善を繰り返す ― “1発で終わらせない”思考
プロンプトは1回で完璧にするものではありません。
Copilotの出力を見て「もう少し具体的に」「専門用語を減らして」など、追加指示で微調整を繰り返すことで、最短距離で理想の結果に近づけます。
この試行過程を「プロンプトエンジニアリングのPDCA」として仕組み化するのが効果的です。
Copilotの強みは「組織データへのアクセス」にあります。
だからこそ、人間の指示の明確さ × 社内文脈の具体化が成功の分岐点になります。
Copilot活用シーン別プロンプト設計のコツ
Copilotは、アプリごとに得意分野が異なります。
Wordなら文書構成、Excelならデータ要約、Outlookならメール文面、Teamsなら議事録要約といった具合です。
ここでは、それぞれのアプリで成果を出すためのプロンプト設計のコツを紹介します。
Word ― レポートや提案書の要約・再構成
Copilot for Wordは、長文要約や構成整理が得意です。
単に「要約して」ではなく、「誰に向けて」「どの目的で」「どのくらいの長さで」を指定することで、実用レベルの出力が得られます。
良いプロンプト例:
「このWord文書を基に、営業部長向けのプレゼン資料の要約を300字以内で作成」ポイント:
- 読者と目的を指定する
- 長さや形式を具体的にする
- “要約+提案要素”など、複合目的も効果的
Excel ― データから洞察を導くプロンプト
Copilot for Excelは、表データの傾向把握・分析コメント作成が得意です。
数値を並べるだけではなく、「読み解き方」を指定するとビジネス文脈に合った説明を生成します。
良いプロンプト例:
「この表の売上データをもとに、前年比の傾向と改善点を3つにまとめて」ポイント:
- 比較軸(前年比、部門別など)を明示
- 「提案型」「報告型」など出力トーンを指定
- グラフや視覚要素を使う場合は「表やグラフで」と追記
Outlook ― メール文面生成・返信効率化
Copilot for Outlookは、トーン調整に強みがあります。
誤解されやすい表現を避けつつ、適切な文体でメールを生成することが可能です。
良いプロンプト例:
「納期延期を伝えるお詫びメールを、丁寧かつ誠実なトーンで200字以内に」ポイント:
- 目的と感情トーンを明確に
- 返信文なら「相手の立場」を踏まえて指示
- 件名や署名まで自動提案させると効率が高い
Teams ― 会議議事録・ToDo抽出の自動化
Copilot for Teamsは、会話履歴を整理し、要約・タスク抽出を自動で行えます。
重要なのは「どの会議の内容を、誰向けにまとめるか」を具体的に伝えることです。
良いプロンプト例:
「昨日の営業定例会の議事録から、次回会議で確認すべきToDoを5項目にまとめて」ポイント:
- 対象の会議・日付を明記
- 出力形式を箇条書きで指定
- ToDoや決定事項の抽出指示を組み合わせる
これらのプロンプトは、どれも「目的+文脈+形式」が明確です。
Copilotに任せる範囲を意識的に設計することで、生成結果の精度と業務効率が大きく変わります。
関連記事リンク
【手順解説】GeminiをGoogle Workspaceと連携する方法|Gmail・ドライブ・カレンダー活用
GASとGeminiの連携方法を解説!API設定からスプレッドシート活用まで
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
よくある失敗プロンプトと改善プロセス
Copilotを使っていて「思うような結果が出ない」と感じる場合、その多くはAIの性能ではなく指示内容の曖昧さに原因があります。
ここでは、実際にありがちな失敗パターンと、その改善プロセスを具体的に見ていきましょう。
| よくある誤り | 問題点 | 改善例 |
| 「レポートをまとめて」 | 目的が曖昧で、誰向けか不明確 | 「営業部の週次報告を、取締役向けに200字以内で要約して」 |
| 「顧客に送るメールを作って」 | トーンや意図が伝わらず、形式が定まらない | 「納期延期を伝えるお詫びメールを、丁寧で誠実なトーンで作成」 |
| 「データを分析して」 | 何を分析するかが不明 | 「添付の売上表を基に、前年比の増減要因を3つにまとめて」 |
| 「要約して」 | 出力の形式・目的を指定していない | 「この議事録を、次回会議用のToDoリストとして整理して」 |
失敗プロンプトを改善する3ステップ
失敗を繰り返すうちに“慣れ”で対応してしまう人も多いですが、改善の仕組み化こそがプロンプトエンジニアリングの本質です。
- 出力を確認し、足りない情報を洗い出す
例:要約が抽象的 → 「誰向け」「目的」「長さ」が不足している - 再プロンプトで条件を追加する
例:「具体例を含めて」「トーンを柔らかく」「図表形式で」など - 出力を評価し、再現できるプロンプトとして保存する
例:「議事録要約プロンプト」など社内ナレッジ化このプロセスを繰り返すことで、チーム全体の出力品質が底上げされていきます。
改善を仕組み化する「プロンプトPDCA」
プロンプトエンジニアリングは、個人のスキルではなく仕組みとして育てるものです。
- Plan:目的・対象・出力形式を明確に
- Do:Copilotに指示して出力を得る
- Check:内容・表現・トーンを評価
- Act:修正し、ナレッジ化
このサイクルを社内で共有することで、プロンプト設計力は組織の資産になります。
Copilotの出力を「うまくいかない」と切り捨てるのではなく、“次に改善する材料”として扱うことが鍵です。
成果を出す人ほど、出力をフィードバック素材として活用しています。
Copilotプロンプト設計を組織に定着させる方法
Copilotの導入効果を最大化するためには、個人のスキルに依存しない仕組み化が欠かせません。
多くの企業が陥るのは、「一部の社員だけが使いこなしている」状態。
ここでは、組織としてプロンプトエンジニアリングを定着させ、継続的に成果を出すための3つのステップを紹介します。
① 「業務別プロンプト集」を社内ナレッジ化する
プロンプトは個人のメモで終わらせず、社内ナレッジとして共有する仕組みにすることで、全社の底上げにつながります。
- 部門別に「成功プロンプト」を共有(営業/人事/経理/総務など)
- 成功事例と出力サンプルを添付して再現性を高める
- Microsoft Loop や SharePoint などでの共有運用が効果的
例:営業部門の共有フォーマット
成果:顧客メール作成効率が40%改善
使用プロンプト:「顧客への謝罪メールを、誠実なトーンで200字以内に」
② 「安全利用ガイドライン」をセットで整備
Copilotは社内文書やメール内容にアクセスできるため、情報管理ルールとセットでの運用が不可欠です。
- 入力してはいけない情報(個人情報・社外秘)を明文化
- 「出力の確認責任は人間にある」ことを教育
- 情報漏洩を防ぐための研修・チェック体制を整備
AI活用は、“安全性と効率性の両立”が鍵。ルールを整えることで、現場が安心して使える文化が生まれます。
③ 研修を通じて「プロンプトリテラシー」を底上げする
実際の現場でCopilotを定着させるには、実践型研修が最も効果的です。
単なる座学ではなく、実務データを使った「演習+改善」を繰り返すことで、社員の“指示力”が確実に上がります。
- 研修で部門別ケーススタディを扱う
- 実務データを使った演習で体感的に理解
- 成果を共有してモチベーションを高める
プロンプトエンジニアリングは「属人的なスキル」ではなく、「再現可能なチームスキル」。
研修を通じて共通言語を育てることが、AI時代の生産性向上の土台になります。
CopilotとChatGPTのプロンプト設計は何が違う?
CopilotとChatGPTはどちらも生成AIですが、「どの情報を使って答えるか」が決定的に異なります。
ChatGPTはインターネット上の一般知識をベースに回答するのに対し、CopilotはMicrosoft 365内の社内文書・メール・スプレッドシートと連携して応答します。
この仕組みの違いが、求められるプロンプト設計にも大きく影響します。
Copilot ― “業務文脈”を理解して動くAI
CopilotはWordやExcel、Outlook、Teamsなどのアプリと連動しており、社内で扱うリアルデータを踏まえた実行支援AIです。
したがって、指示内容は「社内の誰向け」「どの目的で」「どの形式で」出すかを具体的に設定するのが効果的。
例:「営業部の議事録をもとに、次回ミーティングで共有する3つの改善提案を作成」
このように業務データ+目的指定を組み合わせることで、即実務に使える成果物が得られます。
ChatGPT ― “思考や構成”に強い発想支援型AI
一方のChatGPTは、幅広い知識と文章構成力に優れています。
新しい企画案のブレスト、文章の構成整理、戦略アイデアの検討など、“ゼロから考える”タスクに向いています。
例:「営業部でCopilotを活用した定例会議を行う際のアジェンダ案を作って」
汎用的な発想支援や初期アウトライン作成は得意ですが、社内データを直接扱う業務処理は不得意です。
併用戦略で成果を最大化する
CopilotとChatGPTをうまく使い分けることで、AI活用の幅は大きく広がります。
| フェーズ | 最適なAI | 活用例 |
| 構想・発想 | ChatGPT | 会議テーマの整理、研修資料構成のアイデア出し |
| 実行・文書化 | Copilot | 実際の議事録から要約を作成、レポートの清書 |
| 改善・共有 | Copilot+ChatGPT | 出力文のブラッシュアップと社内共有資料作成 |
Copilot=実行型AI、ChatGPT=発想型AIと捉えることで、業務における役割分担が明確になります。
社内ではこの違いを理解し、“発想→実行→改善”をAIで一気通貫させる運用設計を行うのが理想です。
関連記事リンク:
プロンプトエンジニアリングとは?企業が成果を出すAI活用の実践戦略
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
Copilotを効果的に運用するためのTips集
Copilotは導入しただけでは成果が出ません。
定着に成功している企業の多くは、「使い方の工夫」「社内共有」「改善文化」の3点を意識的に運用しています。
ここでは、Copilotを継続的に活用していくためのポイントを整理します。
① 社内で“プロンプトレビュー文化”をつくる
個人ごとにプロンプトを改善しても、知見が共有されなければ組織全体の生産性は上がりません。
月1回でも「プロンプトレビュー会」を設け、うまくいった指示・失敗した指示を共有する場をつくると、全社的なリテラシーが加速します。
- 成功事例を共有し、再現可能なテンプレートに落とし込む
- 改善結果をドキュメント化し、他部署でも流用できる形にする
- “失敗談”を共有することで、メンバー間の心理的安全性も高まる
② 利用ログを分析し、改善ポイントを見える化する
Copilotの利用履歴を追うと、誰がどんな用途でどの程度成果を出しているかが明確になります。
特に大企業では、活用頻度や出力精度を可視化することで、研修計画やサポート体制の最適化が進みます。
- 部署ごとの活用状況を定期レポート化
- 利用データをもとに「改善すべきプロンプト領域」を特定
- “使えていない部門”を発見し、教育支援を優先投入
③ 部署横断で成功事例を共有する
営業部・人事部・広報部など、部門によってCopilotの使い方は異なります。
それぞれの部署での成功事例を「社内AIハンドブック」などにまとめることで、横展開しやすい仕組みが整います。
- 成果事例と使用プロンプトをセットで共有
- Teamsや社内ポータルで“AI活用ナレッジ”として公開
- 新入社員や異動者への教育コンテンツにも再利用できる
④ 定期的にアップデートを追う
Copilotは頻繁に機能更新が行われます。
最新の仕様変更や新機能を把握しないと、旧来のプロンプトが効かなくなる場合もあります。
Microsoft公式ブログやSHIFT AIのような専門メディアで情報をキャッチアップし、社内の運用ルールやテンプレートを常にアップデートしていきましょう。
- 共有(ナレッジ化)
- 可視化(ログ・レポート化)
- 改善(PDCA運用)
の3つをサイクルで回すことが重要です。これができる組織は、AI導入効果が長期的に持続します。
まとめ|Copilotの価値は“プロンプトで引き出す力”にある
Copilotは、単なるアシスタントではなく業務を拡張するパートナーです。
しかし、その力を引き出せるかどうかは、AIの性能ではなく使う人のプロンプト設計力にかかっています。
明確な目的を示し、文脈を与え、形式を指定する。この基本を押さえるだけで、Copilotの出力精度は大きく変わります。
さらに、ナレッジ共有や教育を通じてプロンプトスキルを組織的に育てていくことで、全社の生産性が飛躍的に向上します。
AIを“使う人”から、“使いこなす組織”へ。その変化を生み出す第一歩が、プロンプトエンジニアリングです。
Copilotを導入したのに「使いこなせていない」と感じるなら、いまが組織を変えるチャンスです。
SHIFT AI for Bizの法人研修では、実際の業務データを使いながら、プロンプト設計から社内定着までを体系的に学べます。
“使えるAI人材”を社内で育てる第一歩を、今日から始めてみませんか?
Copilotのプロンプト設計に関するよくある質問(FAQ)
- QChatGPTとCopilotではプロンプトの書き方を変えるべきですか?
- A
はい。CopilotはMicrosoft 365のデータを参照するため、「どの文書やファイルを基に」「誰に向けて」出力するかを明確に伝えるのが効果的です。
- QCopilotのプロンプトを共有しても大丈夫ですか?
- A
内容に機密情報が含まれない限り問題ありません。再現性の高いプロンプトは、部署共有のテンプレートとして活用しましょう。
- Q社内研修をどのように始めればいいですか?
- A
まずは小規模な勉強会や演習型トレーニングからスタートし、成功体験を共有することが定着の近道です。
- QCopilotの出力を改善するにはどうすればいいですか?
- A
出力が思うようにならない場合は、「目的」「文脈」「形式」の3点を見直すのが基本です。
たとえば「誰に向けた内容か」「どのデータを基にしているか」「どんな形式で出したいか」を具体的に伝えると、精度が大幅に上がります。
Copilotの出力は一度で完璧に仕上げるよりも、「もう少し具体的に」「箇条書きで」など再プロンプトで修正していくのが効果的です。
- Q部署ごとの活用事例を共有するにはどうすればいいですか?
- A
部署別に成功したプロンプトと出力例をセットでまとめ、「Copilotナレッジ集」として社内ポータルやTeamsで共有するのが効果的です。
Microsoft LoopやSharePointを使えば、テンプレート形式での管理も容易です。
営業部・人事部・経理部など、部門別フォーマットを整備することで、再現性の高い活用が進みます。AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)