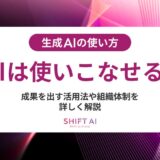Microsoft Copilotを導入したものの、思うように現場で活用されず、社内定着に悩んでいませんか?
Copilotはただツールを使えるようになるだけでは、本来の効果を発揮できません。業務効率化や生産性向上を実現するには、単なる操作説明を超えた「業務に即した実践的な研修設計」が不可欠です。
本記事では、Copilotを「使える」だけでなく「使いこなせる」状態に導くための研修設計のポイントと、成功企業が実践している具体的な定着戦略を詳しく解説します。
研修の選定で迷っている、定着に課題を感じている法人担当者様はぜひご一読ください。
また、下記のリンクでは生成AI人材育成に不可欠な研修プログラムの選び方を体系的にまとめた資料を用意しております。安全に生成AIを活用したい方はお気軽にご覧ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Copilotを導入しても定着しないのはなぜ?
Microsoft Copilotは、導入すればすぐに業務効率化が進む万能ツール、と思われがちです。しかし実際には、多くの企業で「導入後も使われない」「現場の活用が進まない」という課題が浮き彫りになっています。その背景には主に以下のような理由があります。
操作研修だけで終わってしまい、業務での活用までつながらない
単に「どう使うか」を説明する研修は増えていますが、それだけでは実務に応用できず、ツールを使う目的や価値が現場に浸透しません。
結果として、「どう使ってよいかわからない」「効果が実感できない」と感じる社員が多いのです。
社員が戸惑う理由:活用シーンのイメージが不明確
また、CopilotとChatGPTの違いや利用可能な範囲の理解不足も、活用の阻害要因です。社員は「何ができるのか」「どこまで使ってよいのか」を明確に理解できていないため、躊躇してしまいます。
定着の鍵は「業務にどう組み込むか」の設計
真に重要なのは、Copilotを単なるツールとしてではなく、業務の一部として定着させるための設計とフォロー体制です。研修内容も操作だけでなく、具体的な業務シナリオに沿った活用法や社内ルールの共有を含める必要があります。
この点を押さえない限り、どれだけ高性能なツールを導入しても「使われない」結果から抜け出せません。
▶︎ この課題の詳細と対策は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
Copilotが社内で使われない?定着させる5つの戦略と成功企業の事例を解説
Copilot研修を成功させる5つの設計ポイント
Microsoft Copilotを社内で確実に活用し、業務効率化を実現するためには、研修の設計が極めて重要です。成功企業が共通して実践している、押さえておくべき5つのポイントをご紹介します。
1. 業務部門ごとの具体的なユースケースを明示する
Copilotの活用シーンは部門や職種によって大きく異なります。例えば、
- 営業部門なら「顧客向け提案資料の作成支援」や「日報・報告書の自動生成」
- 経理部門では「データ集計の自動化」や「経費精算書のチェック」
- マーケティング部門は「キャンペーン文書作成」や「競合分析の下書き作成」
- 情シス部門は「問い合わせ対応のテンプレート作成」や「社内FAQの自動生成」
このように、受講者自身の実務に直結した具体例を提示することで研修の価値が大きく上がり、研修後の即時活用につながります。
単なる機能説明だけでなく、各部門の実際の業務課題にどう寄与するかを描くことが重要です。
2. 操作トレーニングは実務ツールごとにカスタマイズ
CopilotはMicrosoft 365の様々なアプリケーションに組み込まれているため、単一の研修では効果が薄いです。
Excelでのデータ分析や関数作成支援、PowerPointでのプレゼン資料作成補助、Outlookでのメール文面生成など、アプリ別に操作方法や活用ポイントを分けた研修を提供することで、受講者の理解と習熟度が飛躍的に向上します。
また、実際の業務データやケーススタディを用いたハンズオン形式でのトレーニングが効果的。
座学だけでなく、体験を通じて理解を深めることで、習得速度と定着率が大幅にアップします。
3. 「使ってよい」業務判断とルールの明確化
生成AIツールの活用にあたり、情報漏洩リスクや機密情報の取り扱いは大きな課題です。多くの社員は「どこまで使ってよいのか分からない」「誤った利用で問題が起きないか不安」という声を持っています。
そこで、社内で許容されるCopilotの利用範囲や禁止事項、情報セキュリティポリシーを明確に示すことが必須です。
これにより安心してツールを活用できる環境が整い、積極的な利用促進につながります。
4. フォローアップ体制の充実
研修はあくまでスタート地点に過ぎません。多くの企業で定着しない原因は、研修後のサポート不足にあります。
効果的なフォローアップとしては、
- FAQやナレッジベースの整備
- 相談窓口やチャットサポートの設置
- 定期的なフォローアップ勉強会の開催
- 社内利用状況のモニタリングと改善提案
などが挙げられます。
これにより、日々の疑問や操作でのつまずきを迅速に解消でき、継続的な利用と活用の定着が実現します。
5. 管理職・情シス・現場をつなぐ展開設計
Copilot活用を社内に根付かせるためには、管理職、情シス、現場の三者が連携した計画的な展開設計が欠かせません。
- 管理職は「利用の目的・効果理解」「推進の意思決定」
- 情シスは「技術的サポート」「運用ルール策定」
- 現場は「日常業務での実践活用」
これらがバラバラではなく、一つの目標に向かって動くことで、導入効果は最大化します。
具体的には、推進チームの設置、定期的なコミュニケーション施策、成果報告会の開催などが効果的です。
▶ より詳しくは以下の記事でも解説しています。
Copilotを使いこなせない原因とは?活用を定着させる3つの仕組み
Copilot研修の種類と比較:内製か?外部研修か?
Copilotの活用を促進する研修には、大きく分けて「社内で内製する研修」と「外部の専門機関に委託する研修」があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の状況や目的に応じて選択することが重要です。
社内内製研修のメリット・限界
<メリット>
- 自社の業務フローに完全に合ったカスタマイズがしやすい
- 社員間での情報共有がスムーズになりやすい
- 研修コストを抑えられる可能性がある
<限界>
- Copilotや生成AIに関する専門知識やナレッジが不足しがち
- 研修企画や運営にかかる負荷が大きい
- 最新の技術動向や活用ノウハウが遅れやすい
外部研修の特徴と選び方
<特徴>
- AI技術に精通した専門家による最新知見や効果的な学習法の提供
- 実務に即したシナリオやハンズオン研修が充実している場合が多い
- 研修後のフォローや効果測定支援が期待できる
<選び方のポイント>
- 自社の業種・規模・ITリテラシーに合ったプログラムか
- 操作研修に加え、業務活用や定着支援まで含まれているか
- 研修後のフォロー体制やナレッジ共有の仕組みが整っているか
研修形式別比較表
| 形式 | メリット | デメリット | 適した企業 |
| 講義型(座学中心) | 広範囲の知識伝達が可能 | 実践力は身にくい | AI基礎理解が必要な企業 |
| ハンズオン型 | 実務に近い操作習得が可能 | 準備コストが高い | 即戦力化を目指す企業 |
| eラーニング | 時間・場所を選ばず受講可能 | 受講意欲・理解度の差が出る | 多人数対象、基礎学習向け |
どの研修が最適か?5つの判断基準
- 目的が操作習得か活用定着か
- 社内リソースの充実度
- ITリテラシーのレベル
- 予算とコスト意識
- フォローアップ体制の必要性
研修選びで迷った際は、まず目的と自社の状況を整理し、必要に応じて外部専門機関への相談も検討しましょう。
Copilot研修を選ぶときに確認すべきチェックリスト
Copilot研修を検討する際、選択を間違えると効果が出ず、せっかくの投資が無駄になってしまうこともあります。以下のポイントを押さえて、自社に最適な研修を選びましょう。
1. 対象者別の設計があるか?
現場社員だけでなく、管理職や情シス部門向けの別プログラムが用意されているかを確認しましょう。各層の役割や理解度に合わせた研修設計が、組織全体の定着に不可欠です。
2. 自社業務にカスタマイズ可能か?
汎用的な操作説明だけでなく、自社の業務プロセスに即したカスタマイズが可能かが重要です。具体的なユースケースや実務シナリオを反映した研修は、理解促進と利用意欲を高めます。
3. 研修後の展開・フォロー支援は充実しているか?
研修はスタートライン。その後の社内展開支援やFAQ整備、継続的フォローアップがあるかを必ず確認しましょう。定着を促進する仕組みが整っている研修が効果的です。
4. 生成AIリテラシーも同時に高められるか?
Copilotは生成AIの一種です。技術の理解やリスクマネジメントを含む生成AIリテラシー教育もセットで提供されているかをチェックしましょう。これにより安心してツールを活用できる環境が整います。
これらの観点を踏まえた選定で、Copilot研修の効果を最大化しましょう。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
まとめ:Copilotを定着させるには、研修から変えるべき
Microsoft Copilotの導入は、単なるツール導入ではなく、業務の進め方そのものを変えるチャレンジです。
だからこそ、操作方法を学ぶだけの研修では不十分であり、業務文脈に即した実践的な研修設計と定着支援が不可欠です。
本記事でご紹介した5つの設計ポイントや成功事例は、社内でのCopilot活用を確実に進めるための道しるべとなります。
また、研修の選定やフォロー体制の充実が、使いこなしと業務効率化の成果につながることは多くの成功企業が証明しています。
まずは、自社に合った研修設計を理解し、社内定着まで見据えた包括的なプランを立てることが最初の一歩。
そして、その道筋に沿って一歩一歩着実に進めていくことが、結果的に生産性向上と業務革新を実現する最短ルートです。
▶︎ Copilotの真価を引き出す研修設計や成功事例をもっと詳しく知りたい方は、ぜひSHIFT AIの無料資料をご覧ください。
Copilot研修に関するよくある質問(FAQ)
- QCopilotとChatGPTの違いは何ですか?
- A
CopilotはMicrosoft 365アプリに組み込まれたAIアシスタントで、業務アプリケーション内での具体的な作業支援に特化しています。一方、ChatGPTは汎用の対話型AIで、幅広い質問応答や創造的な文章作成が可能です。研修では、この違いを明確に理解し、業務内でのCopilotの適切な使い方を学びます。
- Q研修期間や形式はどのくらいが一般的ですか?
- A
研修期間は数時間から数日まで幅広く、講義+ハンズオンの組み合わせが効果的です。
最近では、短時間集中型のeラーニング+フォローアップセッションを組み合わせた形式が多く、業務負荷を抑えつつ実践的なスキル習得を目指します。
- QCopilotがグレーアウトや非表示になる場合の対処法は?
- A
利用制限や設定ミス、アクセス権限の問題が原因です。研修では、こうしたトラブルの発生原因と基本的な対処方法も学習し、現場の不安を減らす内容が含まれます。
- Qどの部門から研修を始めるのが効果的ですか?
- A
まずはCopilotの効果が実感しやすい部門(営業・経理・マーケティングなど)から始め、成功体験を積み上げることをおすすめします。その後、管理職や情シス向けの研修で組織全体に展開すると効果的です。