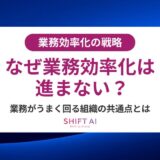ChatGPTを業務に取り入れる企業が増える一方で、「情報漏えいが怖くて許可できない」という声は中小企業で特に多く見られます。
専任の情シスがいない会社では、総務やバックオフィスの担当者が安全性の判断まで担うことになり、どこから手をつければ良いのか迷ってしまいがちです。
実際、ChatGPTのトラブルの多くは、技術的な問題ではなく入力してはいけない情報を入れてしまったという人為的なミスが原因とされています。
つまり中小企業が最初に整えるべきなのは、複雑なシステムではなく、正しい使い方と最低限のルールづくりです。
この記事では、ChatGPTを安全に使うために必要な
・入力禁止情報の基準
・無料でできる基本的な対策
・管理者が設定すべきポイント
・中小企業向けのAI利用規程の作り方
を、実務に落とし込みながらわかりやすく解説します。
この記事を読み終えた頃には、あなたの会社でも今日から安心してChatGPTを活用できる最低限のセキュリティラインが整います。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
中小企業こそChatGPTのセキュリティ対策が急務である理由
中小企業は 情シス不在・属人管理・人手不足 という構造的な弱点を抱えており、ChatGPTの導入時にはリスクが一気に高まりやすくなります。まずは背景を押さえ、そのうえで次につながる具体的な注意点を整理します。
情シス不在が引き起こす属人リスク
中小企業では、IT管理を本来の担当外である総務・経理・バックオフィスが兼務しているケースが多く、セキュリティ判断が属人的になりやすい状況があります。「入力してはいけない情報の基準」「アクセス権限」「ログ管理」など、本来であればIT部門が整備する内容が曖昧になり、誤入力や設定漏れがそのまま定着しやすい点が最大の課題です。
また担当者の異動や退職のたびにルールが引き継がれにくく、日々の運用が不安定になりがちな点も見逃せません。
サイバー攻撃の対象になりやすい構造
中小企業は「対策が甘い」「管理者が不在」という理由から攻撃者の標的になりやすく、実際にIPAの報告でも事故件数は増加傾向にあります。ChatGPTへ顧客名・財務データ・製造図面などを誤って入力すると、外部に残った情報が攻撃者に悪用されるリスクが高まります。
また共有設定のミスや外部公開の誤操作による情報漏えいも実際に起きています。こうした背景を踏まえると、中小企業こそChatGPT導入前に最低限のルール整備と安全設定を行うことが欠かせないといえます。
ChatGPTの情報が漏れる3つの経路を理解する
中小企業が適切な対策を選ぶためには、まず「どこから情報が漏れやすいのか」という基本構造を正しく理解する必要があります。技術的な脆弱性よりも、人為的な操作ミスや設定の不備が原因となるケースが多いため、ここでは代表的な3つの経路をわかりやすく整理します。
入力情報からの漏えい(モデル学習・保存データの扱い)
ChatGPTは、入力された情報を一時的に保持したり、プランによっては学習に利用される可能性があります。特にFreeやPlusではデータの扱いに制限が少なく、顧客名・見積書・図面などの機密情報を入力した瞬間に外部へ出してしまう構図が生まれます。
TeamやEnterpriseではデータの取り扱いが厳格化されていますが、設定次第では履歴が残り続けるため注意が必要です。なお、各プランのデータ保持仕様は後半の安全設定パートで詳しく解説します。
共有端末・ブラウザからの漏えい(キャッシュ・履歴・自動保存)
社内の共有PCやブラウザには、入力履歴やキャッシュが残ることがあります。ログアウトし忘れた状態で他の社員が端末を利用した場合、内部の誰かが機密情報を閲覧できてしまうケースは珍しくありません。
またブラウザの自動保存機能により、入力内容が意図せず残ってしまうこともあります。特に中小企業では「1台の端末を複数人で使う」環境が多いため、対策が必須です。
社内共有・外部共有からの漏えい(誤送信・権限設定ミス)
TeamsやSlackなどでプロンプト内容を共有する際、設定ミスによって外部ユーザーに共有されてしまう事故が実際に報告されています。
またURL形式で共有した場合、公開範囲が全員になっていることに気づかないまま送信するというミスも起こりやすいです。社内のチャットツールと生成AIを併用するほど、共有範囲の管理は重要になります。
無料でできる最低限のセキュリティ対策
中小企業では、専用のセキュリティツールを導入する前に「コストゼロでできる基本対策」を整えるだけでも、情報漏えいのリスクを大幅に下げられます。ここでは、導入直後からすぐ実行できる最低ラインをまとめます。特別なシステムは不要で、社内ルールと日々の運用で実施できる内容に絞っています。
共有PCとブラウザの管理を徹底する
複数人で1台のPCを共有している場合、ログイン履歴や入力内容がそのまま残ることがあります。これは中小企業の現場で特に起こりやすく、ログアウト忘れやブラウザの自動保存が漏えいの引き金になります。
共有端末でChatGPTを使う場合は必ず、「ログアウト」「履歴削除」「キャッシュクリア」の3点セットを徹底するだけで安全性は大きく向上します。ブラウザの自動保存機能(自動入力・自動補完)をオフにすることも効果的です。
機密作業は抽象化して入力する運用に切り替える
機密情報を直接入力せず、内容を抽象化して相談する運用に変えるだけでもリスクは劇的に減ります。たとえば、「A社との契約書のこの条文を修正したい」といった相談は、「特定の契約書における条文修正の考え方を教えてください」という形に変換するイメージです。
要約や構造化を依頼する場合も、固有名詞・金額・特定の数値を削除するだけで安全性は確保できます。
共有リンク・外部公開設定の確認を習慣化する
Teams・Slack・Google ドキュメントなどでプロンプトや結果を共有する際、外部共有がオンになっているまま送ってしまう事故は中小企業でも多く報告されています。
特にURL共有の際は、「公開範囲:組織内のみ」になっているかを必ず確認する習慣をつけることが重要です。少人数の組織ほど共有設定ミスが起こりやすいため、最初に運用ルール化しておきましょう。
無料でできる対策を整えるだけでも、ChatGPTの誤入力や設定ミスによるリスクは大幅に抑えられます。次では、より安全に使うために管理者が必ず設定すべき項目をチェックリストとして整理していきます。
管理者が必ず設定すべき安全設定チェックリスト
中小企業がChatGPTを社内で安全に使うには、管理者側の初期設定をどれだけ整えられるかが大きなポイントになります。特に情シス不在の企業では、設定漏れがそのまま事故につながるため、ここで紹介するチェック項目を導入時の標準フローとして固定しておくことが重要です。
アクセス権限とメンバー管理を明確にする
ChatGPTのアカウントを複数人で利用する場合、権限を曖昧にしたまま運用すると管理が破綻します。利用可能なメンバーの範囲を事前に決め、閲覧権限・編集権限を明確に設定することで、誰がどこまで操作できるのかを可視化できます。
また、退職者や異動者のアカウント整理を後回しにすると、意図せぬ情報閲覧につながるため、アカウント削除の運用ルールは必須です。
プロンプト履歴の保存設定を確認する
ChatGPTの利用履歴は、設定次第で保存されたり保持期間が変わったりします。FreeやPlusの場合、履歴が保持されることで機密情報が残り続けてしまうリスクがあります。履歴のオン・オフ設定や保持期間の確認を導入時に行い、必要に応じて履歴を削除する運用ルールを整えておくと安全です。
TeamやEnterpriseを利用する場合は、組織ポリシーとして統一した設定を適用できます。
共有・外部公開設定の制御
共有URLの公開範囲設定や、外部ユーザーへのアクセス制御は、最初に必ず押さえておくべきポイントです。特にTeam利用では、メンバーが誤ってプロンプトを組織外に公開に設定してしまうケースもあるため、公開範囲を組織内に限定する設定を標準化することが重要です。
共有が必要な場合も、部署ごとの権限設定を行い、外部共有を原則禁止とするルールづくりが有効です。
監査ログと利用状況のチェック体制をつくる
Team・Enterpriseでは、監査ログ(Audit Log)で利用状況を確認できます。誰がいつ、どのような情報を入力したのか、問題が起きる前に把握できるため、トラブルの早期発見と再発防止に役立ちます。定期的にログを確認する担当者を決め、月次チェックを行う運用を定着させると、情報管理レベルが大きく向上します。
管理者設定を整えることで、中小企業でもChatGPTを安全に運用できる環境が整います。次では、この設定を踏まえたうえで「中小企業向けのAI利用規程(社内ルール)」の作り方をわかりやすく整理します。
中小企業向けAI利用規程(社内ルール)の作り方
ChatGPTを安全に運用するためには、管理者設定だけでなく、社員全員が守るべきルールを文書として整備することが欠かせません。中小企業では「口頭での注意喚起」だけで済ませてしまうケースが多く、結果として誤入力や共有設定ミスが繰り返されます。ここでは、最低限押さえるべきルール項目を整理し、実務でそのまま使える形式に落とし込みます。
利用目的を明確にする
AI利用規程の最初に定めるべき項目は、「何のためにChatGPTを使うのか」という利用目的です。目的を曖昧にしたまま運用すると、社内の判断基準がバラつき、誤った使い方につながります。
たとえば、「文書作成の効率化」「企画案のたたき台」「マニュアルの要約」など、具体的な活用範囲を明記することで安全な利用ラインが明確になります。目的が明確だと、禁止事項の判断基準も自然に揃います。
禁止事項と入力基準を文書化する
ChatGPTに入力してはいけない情報は、運用担当者の頭の中だけに留めるのではなく、明文化して共有することが必要です。特に中小企業では「新人やアルバイトが知らないまま入力してしまう」という構造的な問題が起きやすいため、個人情報・財務情報・契約情報・図面などの禁止項目を一覧化して社内展開することが重要です。
また、抽象化して入力する固有名詞を削除するといった運用ルールも合わせて記載すると再現性が高まります。
プロンプト保存ルールと共有範囲の統一
プロンプトの保存やチーム共有の方法が社員ごとに異なると、意図しない外部公開や共有範囲のズレが発生します。
そこで、「プロンプトは保存しない」「必要な場合は管理者フォルダへ保存」「共有URLは組織内限定」など、統一された保存・共有ルールを設定しておくと安全です。特にクラウド共有を使用する場合は、公開範囲の初期設定も必ず明記しておきましょう。
インシデント時の報告フローを明確にする
誤入力や共有ミスが起きた際、「誰が・いつ・どこへ報告するのか」が曖昧だと対応が遅れ、問題が拡大します。情報漏えいリスクを最小化するために、誤入力に気づいた時点で即時報告するフローを作成し、社内全体に浸透させておくことが重要です。必要に応じて再発防止策までセットで記載しておくと、現場で迷いが生まれません。
AI利用規程を整備しておくと、社員の判断基準が統一されるため、誤入力や設定ミスを未然に防げます。次では、中小企業で実際に起きやすいありがち事故を具体例として取り上げ、どこにリスクが潜んでいるのか解説します。
中小企業で起きやすいありがち事故とその防ぎ方
ChatGPTの情報漏えいは「特別な悪意のある行為」ではなく、日常業務の中で起こる小さなミスがきっかけになるケースがほとんどです。中小企業では1人が複数業務を兼任していることも多く、確認不足や共有設定ミスが起こりやすい環境にあります。ここでは実際に発生しやすいパターンを取り上げ、どのように防げるのかを具体的に整理します。
顧客名や取引先名をそのまま入力してしまうケース
メールの返信文を整えたいとき、企画書の方向性を相談したいときなど、忙しい場面ほど注意が薄れやすく、固有名詞をそのまま入力してしまいがちです。
顧客名・担当者名・企業名などは、その一点だけで個人情報・企業情報としての機密性が発生するため、絶対に避ける必要があります。防止策としては、「固有名詞を一般名詞に置き換える」「文脈を抽象化して相談する」という運用ルールを徹底することで、大半のリスクを回避できます。
製造部門が図面の指示書を誤って入力するケース
製造業では、工程表や仕様書などを要約して整理したいとき、図面や内部資料をそのまま投入してしまう事例が多く見られます。図面には、製品の構造や仕様といった競合他社に漏れると致命的な情報が含まれているため、絶対に入力してはいけません。
防止策としては、「画像や図面を扱う業務はAIに投げない」「必要な場合は文章化したうえで抽象化して入力する」など、部門固有のルールづくりが有効です。
契約書や稟議資料を全文コピーして入力するケース
法務や管理部門では、契約書の文面調整をChatGPTに相談したい場面が多く、条文をまるごと入力してしまう事故が繰り返されています。契約書や財務資料は、一部でも外部に出た瞬間に重大なコンプライアンスリスクが発生します。
防止策としては、「文章そのものを入力しない」「意図と目的だけを入力する」「サンプル文面を基に一般論として質問する」など、運用の基準を最初から明確に定めることが重要です。
日々の業務の中で起こりがちなミスを把握しておけば、誤入力や共有ミスを未然に防げます。次では、安全に活用するためのプロンプトテンプレートを紹介し、具体的な使い方を整理します。
安全に使えるプロンプトテンプレート
中小企業では、社員ごとにChatGPTの使い方がバラつきやすく、「どこまで入力していいのか」が不明確なまま運用されてしまうケースが多く見られます。そこで効果的なのが、機密情報を含めない安全版プロンプトをあらかじめ用意しておくことです。固有名詞や具体的な数値を出さずに相談できる形を標準化しておけば、誤入力のリスクを大幅に軽減できます。
機密を出さずに要約を依頼するテンプレート
機密資料の内容をそのまま入れるのではなく、資料の「構造」や「意図」だけを伝える形に変換することで、内容の漏えいを防げます。特に総務・企画・営業など、文書の要約依頼が多い部門では必須の運用です。
- 「機密情報を含まない形で、以下のような文書の要約方法を教えてください。『業務上の手順書を社内向けに簡潔に説明したい』」
- 「具体的な数値や組織名を含まない想定で、文書の構造を整理するポイントを解説してください」
顧客や取引先の名前を伏せたまま文章を作るテンプレート
固有名詞を使わずに文章を生成できるテンプレートを用意しておくと、忙しい場面でも安全に文章作成ができます。営業・カスタマーサポートなど、外部とのコミュニケーションが多い部門で特に役立ちます。
- 「顧客名や企業名を特定できない前提で、クレーム対応メールの一般的な構成を教えてください」
- 「架空の取引先を前提に、提案書の導入文の作り方を説明してください」
契約書の修正方針だけを相談するテンプレート
契約書本文をそのまま入力するのは厳禁ですが、修正したい意図だけを伝えるなら安全に相談できます。法務・管理部門では、この形式を徹底するだけで重大な事故を避けられます。
- 「契約書の特定条文について、内容を具体的に開示せず、一般的な修正の考え方を教えてください」
- 「金額や期間などの具体情報を含まない前提で、条文調整のポイントを説明してください」
安全版プロンプトが社内に浸透すると、社員が迷わず同じ基準で相談できるようになり、誤入力の発生確率が大幅に下がります。次では、これらの運用を支えるための社内体制づくりについて整理します。
安全なChatGPT活用を支える社内体制づくり
中小企業では、ルールやチェックリストを整備しても「誰が運用するのか」「どこまで管理するのか」が曖昧になりやすく、継続的な安全運用が難しくなることがあります。そこで重要になるのが、最小人数でも回せる体制づくりです。担当が一人に集中しても破綻しない仕組みがあるだけで、運用の安定度は大きく変わります。
AI担当者(推進チーム)の役割を明確にする
中小企業では、多くの場合AI活用の担当者は1名、あるいは少人数で構成されます。そのため最初に必要なのは、担当者の役割を明確にしておくことです。
たとえば、「利用規程の更新」「共有設定のルール化」「社員の質問対応」「監査ログの確認」など、運用に必要なタスクを見える化するだけで責任範囲のズレを防げます。また、役割が明確だと問題の早期発見にもつながります。
社内教育(初期研修・定期研修)を仕組み化する
社員が正しい判断基準を持たないままChatGPTを使い始めると、誤入力や設定ミスが繰り返されてしまいます。そこで効果的なのが、初期研修と年数回の定期研修をセットにした教育体制です。研修では「入力してはいけない情報」「抽象化して相談する方法」「共有設定の注意点」などを扱い、社員全員の判断基準の共通化を図ります。知識が均一化されるほど、現場トラブルは減少します。
AIを社内で安全に活用するには、人とルールと運用の3点が揃っていることが重要です。
まとめ|安全に使える環境づくりがChatGPT活用の第一歩
中小企業がChatGPTを安全に活用するためには、特別なシステムや高額なツールよりも、「正しい使い方・最低限の設定・統一されたルール」が何よりも重要です。誤入力や共有設定ミスは、現場の忙しさや属人的な判断から生まれることが多く、最初に基準を整えるだけでリスクは大きく減らせます。
この記事で紹介した内容を踏まえ、まずは禁止情報と入力基準を明確にし、管理者設定と社内ルールを整えるところから始めてください。そのうえで教育体制を用意すれば、情シス不在の企業でも安全にChatGPTを導入でき、業務効率化や生産性向上といった本来のメリットを最大化できます。
「社内ルールを早く整えたい」「社員向けの研修をどう作れば良いかわからない」という企業には、SHIFT AI for Bizの法人研修が役立ちます。具体的な活用方法や研修内容については、以下のリンクから詳しい資料をダウンロードしてご確認ください。
中小企業のChatGPTのセキュリティに関するよくある質問(FAQ)
- QChatGPTに入力した情報は学習に使われますか?
- A
利用プランによって扱いが大きく異なります。Free・Plusでは入力情報が学習に活用される可能性がありますが、Team・Enterpriseではデータが学習に利用されない設定が標準で適用されます。ただし、履歴が残る場合があるため、入力する情報は常に最小限にし、固有名詞は避けるのが基本です。
- Q契約書の文面を相談したい場合はどうすれば安全ですか?
- A
契約書そのものを入力するのは避け、「どういう意図で修正したいのか」だけを抽象化して伝える方法が安全です。条文や金額、契約内容といった具体的な情報を開示しない形で相談すれば、機密性を保ったまま一般的なアドバイスを得られます。
- Q社員が誤って入力した場合はどう対応すればいいですか?
- A
まずは即時に管理者へ報告し、共有範囲や履歴の確認を行います。Team・Enterpriseの場合は監査ログで入力履歴を確認できますが、Free・Plusではログ管理が難しいため、誤入力を前提にしないルールづくりが重要です。社内での報告フローを決めておくと対応がスムーズになります。
- Qどの範囲まで共有していいのか判断できません
- A
共有範囲は「組織内限定」を原則とし、外部共有や公開リンクは使わない方が安全です。どうしても外部共有が必要な場合は、閲覧権限を最小限に絞り、期間限定で公開するといったルールで運用するとリスクを減らせます。
- Q中小企業でもChatGPTの導入効果はありますか?
- A
十分にあります。むしろ少人数で業務を回す企業ほど、文章作成・要約・企画立案などの業務効率化に直結しやすいメリットがあります。安全な運用環境さえ整えておけば、工数削減・属人化改善・情報整理の効率化など多くの効果が期待できます。導入に必要な仕組みづくりは、本記事と連動して進めていただけます