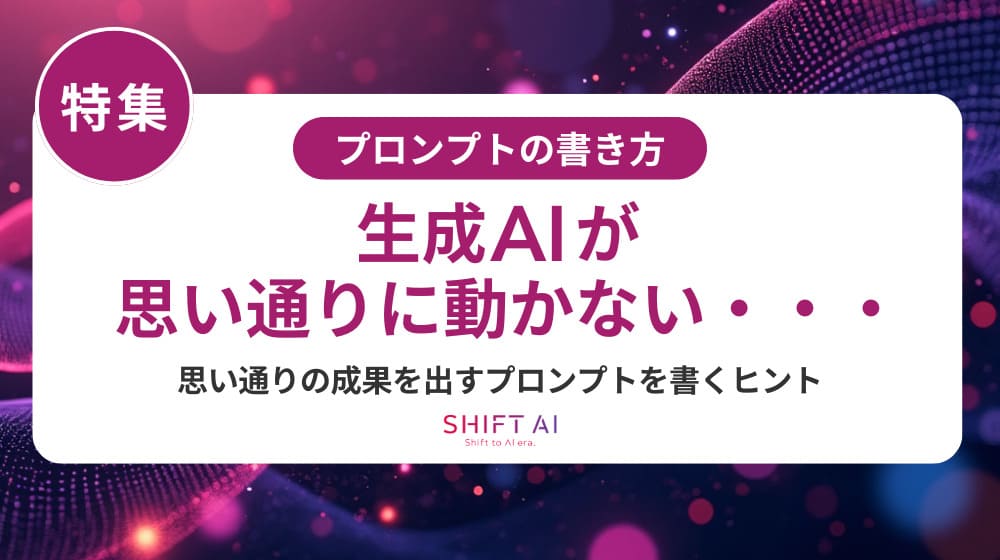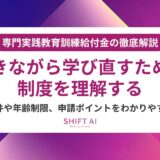企画書づくりに、何時間かけていますか。構成を考え、言葉を選び、上司の反応を想像する。そんな人間的思考の繰り返しこそが、最も時間を奪う部分です。
いま、生成AIを使えば、企画書の構成案は数分で形になります。しかし、多くの人が直面するのは「AIが作ると内容が薄い」「結局、自分で直す羽目になる」という課題。原因は、AIの出力ではなく「指示(プロンプト)」の設計にあります。
AIに通る企画書を作らせるには、単に文章を出力させるのではなく、「目的」「背景」「課題」「提案」を論理的につなぐ構造を指示しなければなりません。つまり、AIを使いこなす鍵は、書かせ方ではなく考えさせ方にあるのです。
この記事では、ChatGPTなどの生成AIを活用して、通る企画書を最短で作るためのプロンプト設計法を解説します。AI経営総合研究所の知見をもとに、現場で実践できる構造的プロンプト設計の手順と失敗しない使い方を紹介。
| この記事でわかること🤞 ・通る企画書をAIで構成する方法 ・ChatGPTに正しく考えさせる指示法 ・プロンプト設計で論理構成を自動化 ・AI出力の誤情報と独自性対策 ・チームでAI活用を定着させる仕組み |
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ「AIで企画書」を作るのか?いま求められるスピードと構造思考
企画書の価値は「時間をかけて練る」ことから、「いかに速く、論理的に構築するか」へと変化しています。多くの現場では、アイデアを練る時間よりも、資料作成や構成整理に時間が奪われているのが実情です。こうした非効率を解消し、構想から提案までのスピードを最大化する手段として、生成AIの活用が注目されています。
AIを使えば、情報整理や文章生成は一瞬です。しかし本当に効果を発揮するのは、「書かせること」ではなく、「考えさせること」。AIに構造的思考をさせるためのプロンプト設計こそ、これからの企画職が身につけるべきスキルです。
ChatGPTなどのAIが得意なのは、文章を生み出すことよりも、思考を整理することです。「目的」「背景」「課題」「提案」をセットで与え、論理の流れを明確に指示すれば、AIは人間が見落としがちな抜けや矛盾を補い、筋の通った企画構成を導き出します。AIはアイデアを磨く補助輪であり、発想と構造の両立を支える思考のパートナーなのです。
企画書作成にAIを導入するメリットは、単なる時短ではありません。
- 構成ミスや重複の削減
- 論点の抜け漏れ防止
- 多角的な視点の発掘
- KPIや成果の定量化サポート
これらはすべて、人間の思考を補完するAIの「構造力」によって実現します。AI経営総合研究所では、この構造思考を実務に落とし込むためのプロンプト設計法を体系化しています。次章では、その設計の基本構造を解説します。
AIに通る企画書を作らせるプロンプト設計の基本構造
AIに企画書を作らせる最大のコツは、「構造を指示すること」です。多くの人がプロンプトに「〇〇の企画書を作って」とだけ書いてしまいますが、それではAIは情報を羅列するだけで、筋の通った内容にはなりません。人間が考える「企画書の構造」を明確に伝えることで、AIの出力は格段に精度が上がります。
企画書の核は「目的・背景・課題・提案」の整合性にある
企画書が評価されるかどうかは、目的・背景・課題・提案の一貫性で決まります。AIにこれらを明示的に伝えると、内容が論理的にまとまり、説得力のある提案が生まれます。
たとえば、以下のように構造を指定します。
「次の要素を順番に整理してください:①目的 ②背景 ③課題 ④提案内容 ⑤期待効果」
このように「順序」を明示することで、AIは各要素の関係を理解し、抜け漏れのない企画構成を作り出します。
AIに論理の流れを理解させるためのプロンプト構文
AIは文脈に弱いが、構造には強いという特性を持っています。
そのため、プロンプトでは「文章を作る」指示よりも「構造を守る」指示を重視しましょう。
「あなたは経営企画部の担当者です。目的・背景・課題・施策・KPIの流れで企画書の構成案を作成してください。」
こうしたプロンプトは、AIに「役割」と「順序」を与えることで出力の品質を安定させます。
関連記事: AIが思い通りに動く!ビジネスで使えるプロンプトの書き方と10のコツ
ブレインストーミングと構成整理を分離する
AIは「発想」と「構造化」を同時に行うのが苦手です。したがって、プロンプトは用途別に分けるのが最適です。
- 発想支援用:自由にアイデアを出させる(「制約条件を設けずに10案」など)
- 構成整理用:アイデアを構造に落とし込ませる(「目的・背景・課題に分類して整理」など)
この二段階設計をすることで、AIの出力は論理性と創造性のバランスを両立できます。
関連記事: プロンプト作成ツールおすすめ12選|無料・業務向け比較と導入のコツを徹底解説
次章では、この基本構造をもとに、実際に使える「企画書プロンプトのテンプレート構成」を紹介します。
ChatGPTで企画書を作る実践プロンプト例(汎用テンプレート)
AIに企画書を作らせる際は、「どの要素を、どんな順序で考えさせるか」を設計することが最重要です。この章では、どの業種でも応用できる汎用プロンプトテンプレートの構造を示します。事例ではなく考え方を理解すれば、どんな企画テーマにも再利用できます。
| 項目 | 悪いプロンプトの例 | 良いプロンプトの例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 目的 | 「新しい企画書を作って」 | 「〇〇の課題を解決するための企画書を作成して」 | 目的を明確にし、ゴールを共有する |
| 背景 | 指示なし | 「現状、〇〇が課題。市場では△△の動きがある」 | コンテキストを与え、前提を整理する |
| 構成指示 | 「自由にまとめて」 | 「目的→背景→課題→提案→KPI→効果の順で構成」 | 構造を指定して出力を安定化させる |
| 出力トーン | 指定なし | 「経営層が読む前提で、ビジネスライクに」 | 対象読者を指定し、文章トーンを最適化 |
| 改善指示 | 一度きりの生成で終了 | 「この内容をもとに、改善案を3パターン提示して」 | 反復思考で精度を上げる流れを設計 |
テンプレート構造例
「あなたは経営企画部の担当者です。次の要素を順番に整理して、企画書の構成案を作成してください。
①目的(なぜこの企画を行うのか)
②背景(市場・顧客・社内課題など)
③課題(現状で何が不足しているか)
④施策(解決のための具体的提案)
⑤KPI(成果指標)
⑥期待効果(数値・定性的効果)」
このようにAIに役割と構成順序を明示することで、筋の通った構成を自動生成できます。
また、目的や課題の書き方を変えることで、マーケティング、営業、DX推進など多様な領域に応用可能です。
AIが生成した内容はあくまで叩き台として扱い、そこから人間の視点で検証・修正を行うことが重要です。
特に課題と提案のつながりやKPIの妥当性はAIが誤りやすいため、確認とブラッシュアップを怠らないようにしましょう。こうした見直しは、AIのハルシネーション(誤情報)を防ぐうえでも有効です。
関連記事: ハルシネーション対策プロンプト完全ガイド|誤情報を減らす設計・検証・教育の実践法
AIに任せるのではなく、AIと協働する。この姿勢が、通る企画書を生み出す最短ルートです。次章では、AIに伝わるプロンプトを設計する具体的なコツを解説します。
AIに伝わるプロンプト設計の実践ポイント
AIに正確に意図を伝えるためには、「何を・どの順に・どのレベルで」考えさせるかを具体的に指示することが鍵です。どれほど高性能なAIでも、曖昧な指示では正しい出力を返せません。ここでは、企画書づくりにおけるプロンプト設計の重要ポイントを整理します。
目的を定義しないとAIは迷う
最も多い失敗は、「何のために企画するのか」をAIに伝えていないことです。AIは与えられたゴールをもとに構成を展開するため、目的が曖昧だと論点がズレます。
「この企画の最終目的は、◯◯の課題を解決し、売上を△%改善することです」と明示することで、AIの出力が狙い通りになります。
AIに指示する前に、人間が目的を明文化することが最も重要です。
曖昧語を避け、判断軸を数値化する
「効果的に」「良い企画」などの抽象表現では、AIは意図をつかめません。
「顧客満足度を5%向上」「会議準備時間を半減」といった定量的な指標を与えることで、AIはより精密に企画構成を作ります。プロンプトに数値や条件を含めることが、出力の再現性を高めるポイントです。
トーン・対象読者を具体的に指定する
企画書のトーンは「誰に見せるか」で変わります。
AIには「上司に承認される前提で」「経営層が読むことを想定して」など、読者像を設定する一文を入れましょう。これにより、AIは説得力や表現トーンを自動的に最適化します。
繰り返し出力→再プロンプト→改善の流れを設計
AIの出力を一度で完結させようとせず、反復プロセスを前提に設計することが大切です。
「この出力をもとに改善案を3パターン出して」「提案をもう一段深堀りして」など、ステップを分けて指示します。
AIは反復の中で精度を高め、最終的に人間の意図を正確に反映する企画書構成を生成します。
関連記事: 生成AI研修で成果を出すプロンプト設計とは?社内展開・ナレッジ化の成功法を解説
SHIFT AI for Bizの研修では、こうした「AIへの伝え方」そのものを組織的スキルとして定着させるカリキュラムを提供しています。チーム全体でAIを使いこなす力を身につけたい方は、研修プログラムもあわせてご覧ください。
AIを使った企画書作成で注意すべき3つのリスク
AIは強力なツールである一方、扱い方を誤ると企画の信頼性を損ねる危険もあります。ここでは、AIによる企画書作成で特に注意すべき3つのリスクと、その対策を整理します。
リスク1:誤情報(ハルシネーション)への依存
AIは、論理的に見える誤情報をもっともらしく生成することがあります。特に市場データや事例をAIに任せきりにすると、事実確認を怠ったまま誤った情報が企画に反映される可能性があります。必ず信頼できる一次情報や公式データと照らし合わせ、AI出力を検証するプロセスを組み込みましょう。
関連記事: ハルシネーション対策プロンプト完全ガイド|誤情報を減らす設計・検証・教育の実践法
リスク2:機密情報の取り扱い
AIに社内データや未発表の企画情報を入力する際は、情報漏えいリスクに細心の注意が必要です。社外提供モデルに直接入力する代わりに、社内専用環境や企業契約版の生成AIを活用しましょう。SHIFT AIでは、セキュリティ基準を満たした法人向けAI環境構築も支援しています。
リスク3:独自性の欠如(AI出力の平準化)
AIの出力は平均化されやすく、「どこかで見たような企画書」になりがちです。AIが提案する構成をベースにしながらも、独自の視点・ストーリー・データを組み込むことが不可欠です。
特に提案書のWhy(なぜやるのか)の部分は、人間の経験と洞察が生きる領域です。AIを補助輪として使い、自社ならではの価値を上乗せしましょう。
関連記事: 生成AIプロンプト研修とは?成果を出す研修設計と定着の仕組みを解説
リスクを理解したうえでAIを使いこなせば、精度の高い企画構成を継続的に生み出すことが可能です。次章では、AIをチーム全体のスキルとして定着させる方法を紹介します。
AIで企画書作成をチームのスキルに変えるには
AIを一人の業務効率化ツールとして使う段階から、組織全体で活用するフェーズへ移行することが、成果の持続につながります。個人がAIで企画書を作れるようになっても、チームで再現できなければ、社内に知見は蓄積されません。重要なのは、AIを「共通言語」として使える組織設計です。
チームでAIを活用する際のポイントは3つあります。
1つ目は、プロンプトの共通化
誰が使っても同じ品質の構成案が出せるように、テンプレートや社内ライブラリを整備します。これにより、AIの活用が属人化せず、ナレッジとして共有されます。
2つ目は、検証プロセスの仕組み化
AIが生成した企画案を「事実確認」「表現精度」「目的整合性」の3軸でレビューする仕組みを導入することで、AI活用が品質管理プロセスに昇華します。
そして3つ目が、学習サイクルの定着です。
AI出力を振り返り、プロンプトを改善することで、組織としての思考力とスピードが同時に進化します。この反復の仕組みこそが、AI時代の「企画力」を支える基盤になります。
SHIFT AI for Bizでは、こうした仕組みを体系化し、「AIで通る企画書を作る力」をチーム全体に定着させる法人研修を提供しています。現場の実務シナリオを題材にした演習を通じて、AI活用をスキルではなく文化へと変えていくプログラムです。
AIを個人の武器で終わらせず、組織の競争力へ。それが、AI経営総合研究所が提唱する構造的AI活用の次のステージです。
まとめ|AIで「速く」「通る」企画書をつくる時代へ
企画書づくりの本質は、書くことではなく構造を設計することにあります。AIを正しく使えば、この構造設計をわずか数分で再現し、誰でも通る企画書を作れるようになります。重要なのは、「AIに考えさせる」ためのプロンプトを設計する力を身につけることです。
本記事で紹介したプロンプト設計の基本は、
- 目的・背景・課題・提案の一貫性をAIに理解させること
- 曖昧な指示を避け、数値や条件を明示すること
- 反復改善を前提に、AIの出力を磨き上げること
この3つを押さえるだけで、AIの出力は劇的に変わります。
AIを速さのためのツールとして使うのではなく、企画の質を高める共創パートナーとして扱うこと。それが、これからの企画職に求められるスキルです。
SHIFT AIでは、こうしたプロンプト設計をチーム単位で実務化する法人研修(SHIFT AI for Biz)を提供しています。企画力をチームで強化したい、AIを本格導入したいという企業は、ぜひ以下のリンクから詳細をご覧ください。
AIが考える、あなたが判断する。この協働こそが、通る企画書を最速で生み出す時代の標準です。
ChatGPTの企画書プロンプトに関するよくある質問(FAQ)
- QChatGPTで本当に企画書を作ることはできますか?
- A
はい、可能です。ただし、AIが自動で完成させるのではなく、人間が構造を設計し、AIが思考を補助するという関係が理想です。本記事で紹介したように、目的・背景・課題・提案の流れを明示したプロンプトを使えば、筋の通った企画構成が数分で作れます。
- QAIに任せると、内容が他社と似てしまいませんか?
- A
AI出力は平均化されやすいため、独自性を保つ工夫が必要です。提案の背景や自社のデータ・方針をプロンプトに含めることで、出力内容を自社固有の文脈に最適化できます。また、社内ナレッジを活用したプロンプトライブラリ化も効果的です。
- QChatGPTなどのAIに社内情報を入力しても大丈夫?
- A
公開モデルへの直接入力は避けましょう。SHIFT AIでは、セキュリティ基準を満たした法人向けAI活用環境や、社内閉域でのプロンプト運用支援を行っています。安全性を担保しながらAIを活用することが可能です。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
- QAIが出した提案の信頼性はどう確認すればいい?
- A
AIの回答をそのまま使うのではなく、一次情報(公的機関や自社データ)で裏付けることが基本です。また、AIの出力を「第1案」として扱い、複数回の再プロンプトで内容を検証することで、精度を高められます。
- Qチーム全体でAIを使えるようにするには?
- A
個人スキルの属人化を防ぐには、共通プロンプト設計と研修による定着が効果的です。SHIFT AI for Bizの研修では、実際の企画業務を題材に「プロンプトを組織スキルとして共有・改善する方法」を体系的に学べます。