人手不足や顧客対応の高度化に直面する企業にとって、AIコールセンターの導入はもはや選択肢ではなく現実的な解決策です。
本記事では、通信・金融・製造・自治体など幅広い業種で実際に導入された18の事例を紹介し、導入の背景から得られた成果、よくある課題を解説していきます。AI活用を検討中の方は、まずは成功企業の事例から学んでいきましょう。
AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。
■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする
※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。
- AIコールセンターとは、電話応対業務の一部または全部をAIが支援・代替するシステム
- コールセンターのAI導入事例18選を紹介
- 事例1.ソフトバンク|生成AIを活用したFAQ応答と応対要約
- 事例2.NTTテクノクロス|リアルタイム感情解析で応対品質とオペレーター支援を強化
- 事例3.楽天損保|AI音声システムで事故受付を自動化、災害時の応対遅延を解消
- 事例4.ハルメク|通販注文をAI音声で自動化し、放棄率を半減・新たな収益機会も創出
- 事例5.市役所|ChatGPTで税務電話をAI対応、生成AI活用の実証に挑戦
- 事例6.JALカード|音声認識AIで通話内容を自動テキスト化し、業務効率と応対品質を大幅改善
- 事例7.レオパレス21|音声認識AIで応対品質を均一化し、年間2,600時間の作業削減を実現
- 事例8.SBI生命保険|ボイスボットとRPAで再発行手続きを完全自動化し約300時間削減
- 事例9.京セラドキュメントソリューションズ|音声AIと有人対応のハイブリッドで24時間サポートを実現
- 事例10.日本システム技術|BIZTELとAI Voicebot連携で電話対応の半数を自動化
- 事例11.大阪ガスマーケティング|音声認識AIで応対履歴を自動記録し、業務効率と品質向上を両立
- 事例12.ベルシステム24×ソニーCSL|独自の教師データ生成でコールセンターAIの精度と実用性を両立
- 事例13.カラクリ|問い合わせ予測でFAQを自動提示し、コール抑制を実現
- 事例14.東京ガス|生成AIと音声認識で応答時間を短縮し、業務を効率化
- 事例15.小林製薬|音声でFAQを検索し、応対時間を短縮・新人教育も支援
- 事例16.ヤマト運輸|AIオペレータが集荷依頼を受付し、待ち時間を削減
- 事例17.トランスコスモス|生成AIの応対支援でエスカレーション率を低減
- 事例18.富士通 Voice BOT|金融機関向け24時間自動応答システム
- AIをコールセンターに導入する際に注意すべき4つの課題
- AIをコールセンターに導入させるための4つのSTEP
- まとめ:コールセンターのAI導入事例をヒントに、スモールスタートから始めよう
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
AIコールセンターとは、電話応対業務の一部または全部をAIが支援・代替するシステム
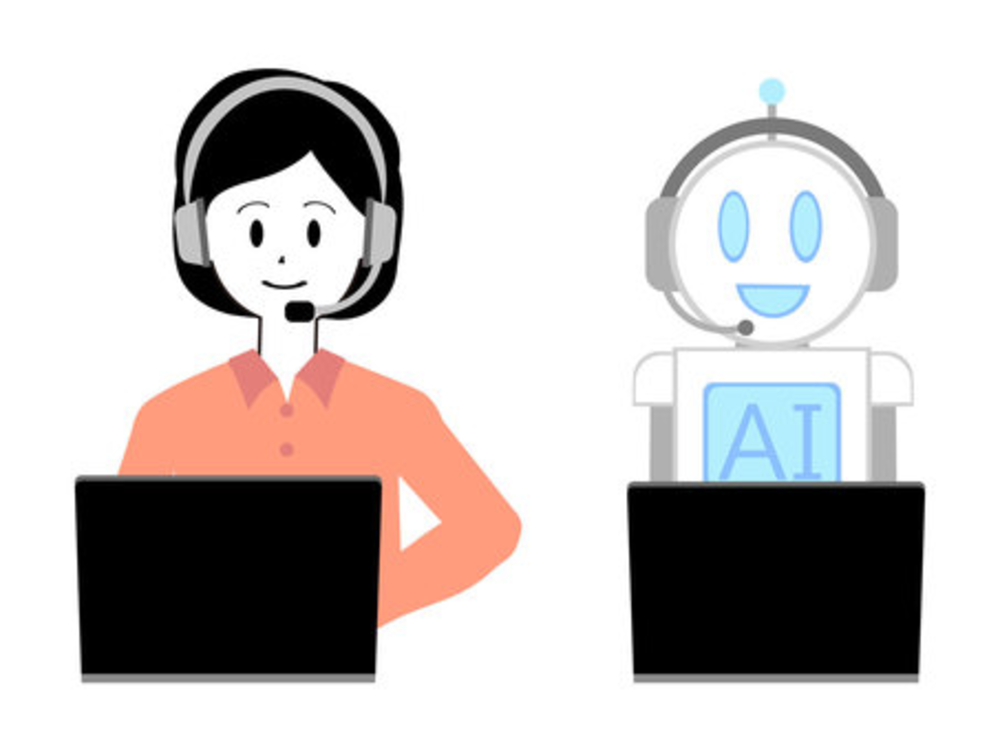
AIコールセンターとは、音声認識や自然言語処理、生成AIなどの技術を活用し、電話応対業務の一部または全部をAIが支援・代替するシステムです。顧客の質問に自動で回答したり、通話内容をリアルタイムでテキスト化したりするなど、従来オペレーターが担っていた業務をAIが効果的に補完します。
「AIに任せれば人件費を大幅に削減できる」といった誤解もありますが、実際には人とAIが役割を分担しながら協働する“ハイブリッド運用”が主流です。特に近年は、ChatGPTなどの生成AIの進化により、より自然な対話や業務効率の向上が可能になっています。
生成AIコールセンターの活用方法をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】生成AIを活用したコールセンターとは?メリットや活用事例を解説
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。
コールセンターのAI導入事例18選を紹介

AIコールセンターは、業務効率化や顧客満足度向上を目的に、さまざまな業界で導入が進んでいます。ここでは、実際の導入事例を18選を紹介し、企業がどのようにAIを活用して成果を上げているのかを詳しく解説します。
事例1.ソフトバンク|生成AIを活用したFAQ応答と応対要約
ソフトバンク子会社のGen-AXは、問い合わせ対応を支援する生成AI SaaS「X-Boost」を提供しています。マニュアルやFAQなどの社内情報を活用し、オペレーターが質問内容を入力するだけで最適な回答を自動生成。
これにより、対応品質の均一化、業務効率の向上、応対時間の短縮を実現しています。さらに、直感的なUIと堅牢なセキュリティ体制、業界別対応などを強みに、法人顧客を中心に導入が進んでいます。
今後は音声応答型AIの展開も予定しています。
出典元:ソフトバンクニュース「問い合わせ応対業務をAIで次のステージへ。企業ごとに最適化可能な生成AI SaaS「X-Boost」」
事例2.NTTテクノクロス|リアルタイム感情解析で応対品質とオペレーター支援を強化
NTTテクノクロスは、AI分析ツール「ForeSight Voice Mining(FSVM)」に、ESジャパンの音声感情解析ツール「ESAS」を連携させました。これにより、通話中の顧客とオペレーターの感情をリアルタイムに可視化する機能を実装しています。
20種類以上の感情を解析し、ストレスや集中度などを即座に検知。スーパーバイザーへ即時通知することで、クレームの早期対応や応対の質向上に貢献しています。
また、感情データと通話内容を組み合わせて分析することで、優良応対の抽出やスクリプト改善、オペレーターの離職リスク予測にも活用。感情の見える化により、現場支援と業務改善の両面で成果を上げています。
出典元:IT Leaders「リアルタイムな感情認識でコールセンターの応対品質管理や通話分析を可能に─NTTテクノクロスとESジャパン」
事例3.楽天損保|AI音声システムで事故受付を自動化、災害時の応対遅延を解消
楽天損保は、火災保険・傷害保険の事故受付にAI音声システムを導入し、本格運用を開始しました。AIが顧客の事故内容を聞き取り、対応できない場合は自動でオペレーターに引き継ぐ設計です。
大規模災害時の連絡集中や人手不足による応対遅延の解消を目的としており、待ち時間の削減や継続的な受付体制の構築にも寄与しています。今後は生成AIとの連携で、より自然な対話や複雑な事故対応への適用も視野に入れています。
出典元:コールセンタージャパン「楽天損害保険、事故受付にAI自動音声システムを利用」
事例4.ハルメク|通販注文をAI音声で自動化し、放棄率を半減・新たな収益機会も創出
ハルメクは、50代以上の女性向け通販における注文受付をAI音声で自動化し、放棄率の低下と機会損失の改善を実現しました。PKSHA Voicebotを活用することで、月間約1万件の自動応答を処理し、25%のハンドリングタイム削減にも成功しています。
さらに、営業時間外の注文対応を可能にしたことで、新たな収益機会の創出にもつながりました。シニア層との相性も良く、CX向上と業務効率化の両立を果たしています。
出典元:PKSHA「通販の注文電話を自動応答化、放棄率を約20%改善し機会損失を縮小」
事例5.市役所|ChatGPTで税務電話をAI対応、生成AI活用の実証に挑戦
ある市役所では、市民税・県民税に関する電話問い合わせの急増による回線パンクを解消すべく、ChatGPTなどの生成AIを活用した電話応対の実証事業を開始。背景には、納税通知の発送後に事業所や個人からの電話が殺到し、職員だけでは対応しきれない状況が続いていたことがあります。
今回の取り組みでは、対話型AIによって制度説明などの定型問い合わせを自動応答し、職員の負担を軽減することを目指しています。将来的には、音声入力による応答や電話対応への展開も視野に入れ、行政サービスの効率化と住民満足度の向上が目標です。
出典元:Urban Innovation JAPAN「市役所応対にもChatGPT?!新時代の行政電話AI対応を実現したい!」
事例6.JALカード|音声認識AIで通話内容を自動テキスト化し、業務効率と応対品質を大幅改善
JALカードでは、コールセンター業務の効率化と応対品質の向上を目的に、音声認識AIの導入を決定しました。導入されたのは、アドバンスト・メディアの「AmiVoice Communication Suite」です。
従来は全通話録音の聞き起こしに多大な手間がかかっていましたが、リアルタイムでの音声テキスト化によって業務負荷が大幅に軽減されました。認識精度の高さや操作性の良さが評価され、現場にもスムーズに定着。
さらに、検索機能やマニュアル連携により、FAQの素早い提示も可能となり、顧客満足度と対応スピードの向上にもつながっています。現在では、同社のコールセンター運営に不可欠な基盤となっています。
出典元:株式会社アドバンストメディア「リアルタイム音声認識でコールセンター業務が大幅に効率化」
事例7.レオパレス21|音声認識AIで応対品質を均一化し、年間2,600時間の作業削減を実現
レオパレス21は、全国5拠点のコールセンター全席にアドバンスト・メディアの音声認識AI「AmiVoice Communication Suite3」を導入しました。通話をリアルタイムで文字化することで、応対品質の均一化やFAQの自動表示によるオペレーター支援が可能となり、顧客満足度の向上にも貢献しています。
また、通話の書き起こし作業が不要になったことで業務が効率化され、年間約2,633時間の作業削減と約460万円のコスト削減を見込んでいます。
出典元:株式会社アドバンストメディア「レオパレス21 全国5拠点のコールセンター全席に 音声認識ソリューションAmiVoice® Communication Suite3を導入」
事例8.SBI生命保険|ボイスボットとRPAで再発行手続きを完全自動化し約300時間削減
SBI生命保険は、ボイスボット「MOBI VOICE」とRPAを連携させ、生命保険料控除証明書の再発行手続きを完全自動化しました。これにより、24時間365日対応が可能となり、オペレーターの負荷軽減や再発行に関する苦情ゼロを実現。
対応時間は約7割短縮され、年間約300時間の作業削減にも成功しました。顧客満足と従業員満足の向上という好循環を生み出しています。
出典元:mobilus「SBI生命保険株式会社|書類請求手続きをボイスボットとRPAで完全自動化、約300時間を削減、苦情もゼロに」
事例9.京セラドキュメントソリューションズ|音声AIと有人対応のハイブリッドで24時間サポートを実現
京セラドキュメントソリューションズは、音声AIと有人対応を組み合わせたハイブリッド体制を導入し、24時間365日のカスタマーサポートを実現しました。消耗品注文の自動受付から始まり、夜間・土日祝日の問い合わせ対応にも対応。突発的な入電集中やBCP対策としても効果を発揮しています。
現在では、音声AIでの対話完了率が5割を超え、英語対応の強化も進めるなど、さらなる利便性向上を図っています。
出典元:トランスコスモス株式会社「京セラドキュメントソリューションズジャパン」
事例10.日本システム技術|BIZTELとAI Voicebot連携で電話対応の半数を自動化
日本システム技術は、クラウド型CTI「BIZTEL」とAI音声自動対話サービス「AI Messenger Voicebot」を連携させ、電話応対業務の自動化を推進しました。2024年の導入からわずか半年で、電話対応件数の約50%をボイスボットで完結する体制を構築。
複雑な内容はオペレーターにシームレスに引き継ぐことで、対応品質を維持したまま業務負担を軽減しました。これにより、審査業務へのリソース配分が可能となり、業務全体の効率化と生産性向上に成功しています。
出典元:PR TIMES「日本システム技術株式会社 が「BIZTEL」とAI音声自動対話サービス「AI Messenger Voicebot」を連携し活用」
事例11.大阪ガスマーケティング|音声認識AIで応対履歴を自動記録し、業務効率と品質向上を両立
大阪ガスマーケティングは、応対品質と効率向上を両立すべく、音声認識AIの導入を決定しました。NTTコミュニケーションズと共同で「COTOHA Voice Insight」を開発し、導入しています。
通話音声をリアルタイムにテキスト化し、オペレーターへの支援やNGワードの監視、FAQの自動表示などを実現。これによりKPIである応答率が目標を上回る水準で維持され、クレーム件数の減少にも成功しました。
全通話を対象にした評価制度の導入で、オペレーターのモチベーションも向上しています。
出典元:docomo business「大阪ガスマーケティング株式会社」
事例12.ベルシステム24×ソニーCSL|独自の教師データ生成でコールセンターAIの精度と実用性を両立
ベルシステム24は、ソニーコンピュータサイエンス研究所(CSL)と共同で、コールセンター向けAI検索エンジン「Mopas」を開発しました。自然言語処理技術を活用し、FAQから高精度に回答を抽出する仕組みで、導入企業ではメール問い合わせの7割削減に成功しています。
特筆すべきは教師データ生成の工夫で、FAQデータをもとに数十万パターンの学習モデルを自動生成し、最適なモデルを選定する手法を採用。ソニーCSLのアルゴリズムやデータ拡張技術も組み合わせ、FAQだけでも実用レベルの精度を実現しています。
従来の検索エンジンに比べ、業種による精度差や大量の履歴データの必要性といった課題をクリアした点が大きな強みです。
出典元:日経XTECH「ベル24とソニーCSLが開発したコールセンターAI、教師データ作成に一工夫」
AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。
■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする
※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。
事例13.カラクリ|問い合わせ予測でFAQを自動提示し、コール抑制を実現
カラクリは、大規模コンタクトセンター向けにAI搭載の電話応対支援システム「KARAKURI Voice Search」を開発しました。このシステムは、通話内容をリアルタイムでテキスト化し、文脈に応じたFAQや資料をオペレーターに自動提示します。
特許技術により、日々の通話ログから質問と回答のペアを抽出・グルーピングし、高精度なFAQを自動生成する仕組みを採用。これにより、ナレッジ管理の自動化とコール抑制を同時に実現しています。
生成されたFAQは翌日には活用可能で、チャットボットやFAQサイトにもシームレスに展開可能です。現場の実践知を「育つナレッジ」として活用し、継続的な応対品質向上と組織全体の知識資産化を推進しています。
出典元:PR TIMES「ナレッジは「作る」から「育つ」時代へ カラクリがAI搭載の電話応対支援システムを開発」
事例14.東京ガス|生成AIと音声認識で応答時間を短縮し、業務を効率化
東京ガスカスタマーサポートは、音声認識とAIを活用し、コールセンターの業務効率化と応対品質の向上を図りました。会話内容をAIがリアルタイムに解析し、オペレーターに適切な情報を自動提示する仕組みを構築。
これにより、応答時間を平均10秒短縮し、年間1万1000時間の業務削減を実現しました。また、対応のばらつきやミスも軽減され、お客さま満足度も向上。今後は定型業務の自動化を進め、オペレーターが付加価値の高い業務に集中できる体制づくりを目指しています。
出典元: TOKYO GAS「AI導入で年間1万1000時間の応対時間削減◆コールセンター効率化の取り組み」
事例15.小林製薬|音声でFAQを検索し、応対時間を短縮・新人教育も支援
小林製薬は、AI検索「Cogmo Search」と音声認識を連携させたFAQ自動検索システムをコールセンターに導入しました。電話内容をリアルタイムでテキスト化し、FAQやマニュアルを自動で検索することで、応対中の検索作業を効率化。
特に、経験の浅いオペレーターでもスムーズな対応が可能となり、応対時間の大幅削減や業務負担の軽減に成功しました。2023年1月から本格導入が開始され、今後さらなる展開が予定されています。
出典元:cogmo「AI 検索と音声認識を連携しマニュアルや FAQ の自動検索を実現 」
事例16.ヤマト運輸|AIオペレータが集荷依頼を受付し、待ち時間を削減
ヤマト運輸は、電話による集荷依頼の受付にAIオペレータを導入しました。従来は法人顧客限定の対応でしたが、2021年4月より個人顧客にも対応を拡大。
集荷場所や希望時間などをAIが自動で受付し、オペレーターの対応を待つことなく手続きが完了する仕組みです。これにより、コールセンターの混雑緩和と待ち時間の削減を実現しました。
今後もデジタル技術の活用を通じて、顧客満足度の向上を目指しています。
出典元:ヤマト運輸「AIオペレータによる電話受付で、すべてのお客さまからの集荷依頼を対応へ」
事例17.トランスコスモス|生成AIの応対支援でエスカレーション率を低減
トランスコスモスは、生成AIを活用し、コールセンター業務の効率化と応対品質の向上を図っています。オペレーターが難しい問い合わせに直面した際、生成AIがFAQや製品仕様書を参照して即座に回答を提示。
これにより、上位スタッフへのエスカレーションを約6割削減し、顧客の待ち時間短縮にもつながっています。マイクロソフトの「Azure OpenAI Service」を活用し、専門スタッフの負荷軽減と全体のサービス品質向上を実現しています。
出典元:日経XTECH「コールセンターが生成AIで効率化、トランスコスモスは「エスカレーション」6割削減」
事例18.富士通 Voice BOT|金融機関向け24時間自動応答システム
富士通の「Voice BOT」は、24時間365日対応可能なAI音声自動応答システムで、特に金融機関など大量の電話対応が求められる業界で導入が進んでいます。ノーコードでシナリオを作成できるため、問い合わせ内容に応じた柔軟な応答が可能です。
SMS送信によるWeb誘導、音声内容のテキスト化・確認機能、アウトバウンド通話対応など、幅広い機能を備えています。チャットボットやCRMとの連携も可能で、業務の効率化と顧客満足度の向上に貢献しています。
AIをコールセンターに導入する際に注意すべき4つの課題

AIコールセンターは業務効率化や顧客満足度向上に貢献しますが、導入時にはさまざまな課題も発生します。特に運用面や精度、コストに関する悩みは多くの企業が直面するポイントです。次に、導入時によくある4つの課題とその具体的な対策をご紹介します。
1.個人情報保護とセキュリティ対策を徹底する
AIコールセンターでは、顧客の氏名や住所、契約内容などの機微情報を扱うことが多いため、情報漏洩リスクへの対策が必須です。通信の暗号化やアクセス制限、ログ監視といった基本的なセキュリティ対策に加え、AIの応答ログや学習データに対する適切な管理も求められます。
また、プライバシーマークやISMS認証の取得など、第三者機関による信頼性の証明も導入時の信頼構築に役立ちます。
2.初期設計とデータ整備がAI活用の成否を分ける
AIの性能を最大限に引き出すには、学習用データの整備と正確なシナリオ設計が鍵を握ります。誤ったFAQや曖昧な応答フローでは、かえってユーザーの混乱を招くかもしれません。
そのため、過去の問い合わせ履歴を分析し、よくある質問や重要なキーワードを抽出する必要があります。さらに、AIが正確に意図を読み取れるよう、最適化されたデータ構造を構築することが重要です。
3.段階的な導入でリスクと負担を最小化する
AIの全面導入はシステム面・業務面での負荷が大きく、現場オペレーターの混乱や顧客体験の低下につながる恐れがあります。まずはFAQ対応や一次受付など、業務負荷の少ない領域から導入し、運用データを蓄積しながら段階的に範囲を拡大するのが効果的です。
スモールスタートにより、トラブルを最小限に抑えつつ、現場への浸透もスムーズに進められます。
4.オペレーターとの連携と教育体制の整備が重要
AIだけではカバーできない複雑な対応や感情面への配慮など、人ならではの対応も引き続き求められます。そのため、AIとオペレーターの役割を明確に分け、切り替え時のスムーズな引き継ぎ体制を整えることが不可欠です。
また、AIの活用方法や対応フローを正しく理解するための研修やマニュアル整備も必要です。人とAIの協働によって、より高品質な顧客対応が実現します。
AIをコールセンターに導入させるための4つのSTEP

AIコールセンターの導入を成功させるには、事前準備から運用・改善までのステップを丁寧に進めることが大切です。以下では、導入を円滑に進めるための4つの基本ステップを紹介します。
STEP1:現場の課題を可視化する
AI導入の前に、現場が抱える課題や業務の流れを丁寧に把握することが不可欠です。
通話内容や対応フロー、問い合わせ傾向などを分析し、どこに時間や人手がかかっているかを可視化します。このプロセスにより、AIが支援すべき業務や導入による効果を明確にできます。
STEP2:目的に応じたAIツールを選定する
AIと一口に言っても、音声認識・FAQ自動提示・チャットボットなど機能はさまざまです。自社の業務課題や改善したいプロセスに合わせて、最適な機能や精度を持つツールを選定することが重要です。実績やサポート体制も併せて確認しましょう。
STEP3:テスト運用で効果を確認する
本格導入の前に、小規模な範囲でのテスト運用を行うことで、AIの精度や実運用における課題を確認できます。導入効果を数値で検証し、改善点を洗い出すことで、現場に適した形での導入が可能です。関係者の理解も得やすくなります。
STEP4:現場定着までサポートする
AI導入後は、操作方法の研修や問い合わせへの対応ルール整備など、現場への定着を丁寧にサポートする必要があります。導入初期に戸惑いが生じないよう、マニュアル整備や継続的なフィードバック体制も重要です。人とAIの共存体制を築くことが成功の鍵となります。
まとめ:コールセンターのAI導入事例をヒントに、スモールスタートから始めよう

AIコールセンターは、単なる業務の自動化にとどまらず、顧客対応の質や従業員の働き方までを変える可能性を秘めています。しかし、いきなりの全面導入はリスクも伴います。そのため、まずは成功事例を参考に、対応件数の多い問い合わせや定型業務などから小さく始めるのが現実的です。
導入後も現場との連携や運用改善を重ねることで、AIの活用効果を着実に高められます。業務と顧客体験の両面を向上させるAIコールセンターをぜひご検討ください。
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。











