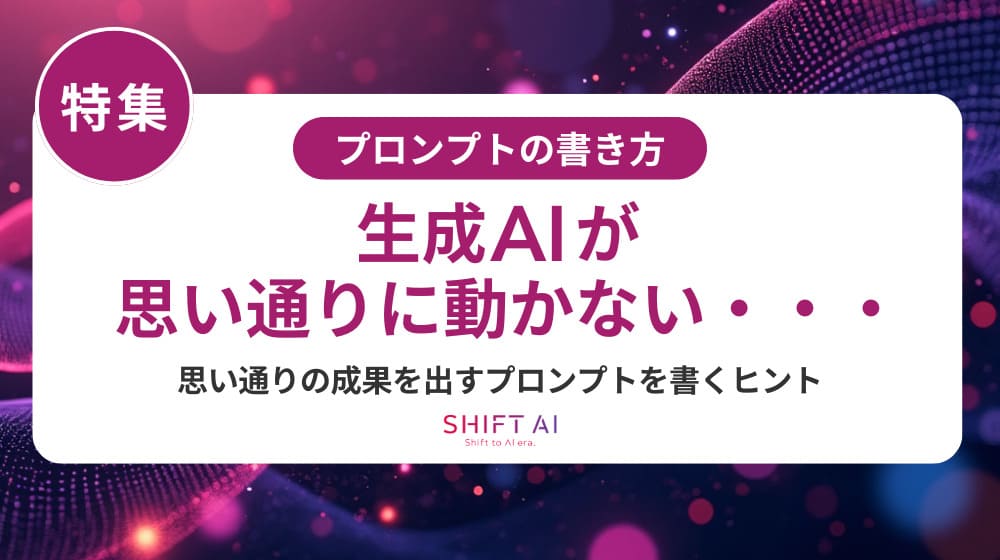「動画生成AIを使ってみたけれど、イメージ通りの映像が作れない…」こんな経験はありませんか?
人物の動きが不自然になったり、背景が思ったものと違ったり、結果がバラついてしまう原因の多くは「プロンプト(指示文)」にあります。
生成AIは魔法のように見えますが、実際には入力されたテキストを“設計図”として映像を組み立てています。つまり、どんな映像を作れるかは、プロンプト設計力で決まると言っても過言ではありません。
この記事でわかること
- 高品質な動画を作るためのプロンプトの基本構造
- 日本語と英語で精度に差が出る理由と使い分け
- よくある失敗例と改善プロンプト
- 広告・教育・社内研修などビジネス活用の具体事例
「独学で試行錯誤するより、最短ルートで“思い通りの動画”を作れるようになりたい」
そんな方に役立つ内容です。
あわせて読みたい:生成AIプロンプトとは?正確な回答を引き出す書き方・成功事例・研修導入のポイント
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
動画生成AIとプロンプトの関係を理解しよう
動画生成AIで狙った映像を生み出すには、まず「プロンプト」がどのように機能しているのかを理解することが重要です。プロンプトはAIにとっての映像制作の設計図であり、ここでの工夫が結果の良し悪しを左右します。特に動画の場合は「動き」や「時間軸」といった要素を含める必要があり、画像生成AIのプロンプトとは考え方が異なります。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
ここでは、動画生成AIのプロンプトを理解するうえで押さえておきたい基本の視点を2つに分けて解説します。
プロンプトは映像の設計図である
動画生成AIは、入力されたテキストをもとに「誰を登場させるのか」「どのように動かすのか」「背景や雰囲気をどう演出するのか」を判断します。つまりプロンプトは、映像を組み立てるための最初の指示書です。
例えば「ビジネスパーソンが会議室でプレゼンをする動画」と入力すれば、被写体・場所・行動までが組み込まれます。しかし、時間やカメラワークを明示しなければ「静止した映像」や「不自然な動き」が生成されてしまうことも少なくありません。
このように、動画生成AIでは「動作」や「時間指定」までを含めてプロンプトを組み立てることが不可欠です。
画像生成AIとの違いを理解する
静止画を対象とする画像生成AIと、連続する映像を扱う動画生成AIでは、プロンプトの重要度が異なります。
- 画像生成AI:1枚の完成度を重視 → 色味・構図・被写体の詳細などを丁寧に指定する
- 動画生成AI:連続性や動作の自然さを重視 → 「誰が、どう動き、どの視点で映すか」を明確に指示する
例えば、同じ「人物が歩く」でも、画像では「歩いている瞬間の一枚」を作りますが、動画では「数秒間で歩く動作が続く」ことを表現する必要があります。この違いを意識しないと、意図と異なる映像が出てきてしまうのです。
関連記事:画像生成AIで理想のイメージを実現!プロンプトの基本構造・失敗改善・活用法まとめ
高品質な動画を作るプロンプトの基本構造
動画生成AIで思い通りの映像を得るためには、プロンプトを「場当たり的に書く」のではなく、一定の構造に沿って組み立てることが大切です。
ここでは、動画プロンプトに必須となる基本要素を分けて解説します。
被写体と行動を明確にする
動画生成AIにとって、最初に必要なのは「誰が登場し、何をしているのか」という情報です。例えば「男性が歩く」では漠然としていますが、「スーツを着た男性が、会議室でプレゼン資料を指差しながら説明する」と書けば、一気に具体性が増します。
被写体と行動をセットで指定することで、AIは「対象の人物像」と「動きの内容」を理解しやすくなり、映像全体の再現度が高まります。
背景やスタイルで雰囲気を決める
次に重要なのが、映像をどのような場面・雰囲気で表現するかです。「白い背景」や「ビジネスオフィス」とだけ指示すれば単調になりますが、「近未来的なガラス張りの会議室で、自然光が差し込む」と書けば、映像全体のトーンが際立ちます。
さらに「リアル調」「アニメ調」「映画のようなシネマティック」などスタイルを付け加えると、表現の幅を広げつつ、一貫性のある映像が生成されやすくなります。
このように、プロンプトは「被写体+行動」「背景+スタイル」を組み合わせて構成するのが基本です。ここを押さえておけば、後に紹介する「日本語と英語の違い」や「失敗を避けるコツ」も理解しやすくなります。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
日本語 vs 英語プロンプト|どちらが適している?
動画生成AIを使うとき、多くの方が迷うのが「日本語で入力すべきか、それとも英語で入力すべきか」という点です。実際、AIの学習データの多くは英語ベースで構成されているため、英語の方が精度や再現性が高いケースが目立ちます。
しかし、日本語でも工夫次第で十分に質の高い動画を作ることが可能です。ここでは、それぞれの特徴と活用のコツを解説します。
英語プロンプトを使うメリットと注意点
英語での入力は、AIの学習データと親和性が高く、細かなニュアンスまで伝わりやすいという利点があります。
例えば「cinematic lighting」「slow motion」など、動画制作に特化した表現は英語の方が圧倒的に豊富です。
- メリット:再現性が高く、専門的な映像表現もカバーできる
- 注意点:英語の知識がないと表現が限定される/直訳的に入力すると意図とズレることがある
つまり、英語プロンプトは強力ですが、映像制作の専門用語をある程度理解して使うことが前提になります。
日本語プロンプトを活かすコツ
一方で、日本語入力の強みは「直感的に書ける」点です。初心者や現場の非エンジニアでも扱いやすく、社内での共有や教育にも向いているのが特徴です。
ただし、日本語のみでは曖昧に解釈されやすいため、補助的にカタカナ英語や短い英語フレーズを混ぜると精度が上がります。
- 「オフィスの会議室で、スーツ姿の男性がプレゼンする」
- → 改善例:「オフィスの会議室で、スーツ姿の男性がプレゼンする、cinematic lighting」
このように日本語で大枠を指定しつつ、キーワード部分に英語を組み合わせると、誰でも扱いやすくなり、結果の安定性も増します。
結論として、英語は「高精度・専門的な表現向け」、日本語は「わかりやすさ・共有しやすさ向け」と棲み分けられます。
ビジネスの現場では、日本語で骨格を作り、必要な部分に英語を補強するハイブリッド型が最も実用的です。
生成AIの理論やノウハウだけでなく、「実際の現場で生成AIがどう活用されているか」気になりませんか?
■生成AI法人活用事例データベースで「自社に合う事例を知る」
各社が「なぜその生成AI・LLMを選んだのか」「どうルール化したのか」。ツール選定や運用設計の迷いをなくすための「他社の意思決定プロセス」がわかります。
よくある失敗プロンプトと改善例
動画生成AIを使う人の多くが「なぜか思った映像にならない」と感じるのは、プロンプトの書き方に原因があります。実は、失敗には共通するパターンがあるため、それを知っておくだけでも結果は大きく変わります。ここでは、代表的な失敗例と、それをどう改善すべきかを見ていきましょう。
曖昧すぎる指示で失敗するケース
初心者に多いのが「曖昧な言葉」で指示してしまうケースです。
例えば「人が歩いている動画」では、AIは人物の年齢・服装・背景を解釈できず、結果として不自然な映像になりがちです。
失敗例:「人が歩いている動画」
改善例:「スーツ姿の30代男性が、オフィスの廊下をゆっくり歩く動画、cinematic lighting」
このように被写体+行動+背景+スタイルを具体化するだけで、映像の精度は格段に上がります。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
指示を盛り込みすぎて破綻するケース
逆に、欲張って要素を詰め込みすぎると、AIが処理しきれず破綻することがあります。例えば「女性が街を歩きながら歌って、同時に犬を散歩して、カメラがドローン視点で…」といった複雑な要求は、一度の生成では再現が難しいのです。
失敗例:「女性が街を歩きながら歌って犬を散歩している、ドローン視点、夕焼け、リアル調、アニメ調」
改善例:「女性が街を歩く動画、夕焼けの背景、リアル調、ドローン視点」→別シーンとして「歌うシーン」「犬を散歩するシーン」を分けて生成し、後で編集で統合する
つまり、一つのプロンプトで全てを完結させようとせず、場面を分ける発想が重要です。
このように「曖昧さ」と「盛り込みすぎ」は、動画生成AIプロンプトの典型的な失敗です。改善のポイントは、必要な要素を具体化し、優先度を整理して分割すること。これを意識すれば、狙った映像に近づける確率は一気に高まります。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
業務シーン別|動画生成AIプロンプト活用事例
動画生成AIは個人のクリエイティブ用途だけでなく、企業活動のさまざまな場面で実用化が進んでいるのが特徴です。特に、広告・教育・社内コミュニケーションといった領域では、プロンプト設計力が成果に直結します。ここでは、代表的な3つの活用事例を紹介します。
広告・マーケティング動画での活用
SNS広告や商品PRでは、短尺でインパクトのある映像が求められます。動画生成AIを使えば、限られた予算と時間でも高品質なビジュアルを量産できるのが強みです。
- 例:「新発売のドリンクを持った女性が、都会の夜景を背景に笑顔で立っている、シネマティック映像」
- プロンプトで被写体・背景・雰囲気を具体的に指定することで、実写CMに近いイメージを低コストで再現可能
広告代理店や企業のマーケティング部門にとって、映像制作の内製化を進める大きな武器となります。
教育・研修コンテンツでの活用
研修やマニュアル作成の現場でも、動画生成AIは強力なツールになります。従来は撮影や編集に多大なコストがかかっていた教育用コンテンツも、プロンプト次第で短時間で作成可能です。
例:「工場の安全ヘルメットを着用した作業員が、正しい器具の使い方を説明している、ナレーション付き教材映像」
社員教育動画や手順マニュアルを効率的に制作できるため、人材育成のスピードと質が向上します。
ここでのポイントは「現場に合わせたリアルなシーンを指示する」こと。曖昧な背景では臨場感が伝わらず、教育効果が下がるため、詳細なプロンプト設計が求められます。
社内コミュニケーションでの活用
経営メッセージや全社イベントのイントロ映像など、社内広報にもAI動画は活用可能です。文字情報だけでは伝わりにくいビジョンや理念を、映像としてインパクトを持って届けられる点が魅力です。
例:「未来的なオフィスを背景に、経営者が社員に向けて力強くメッセージを語る動画」
これにより、社員のエンゲージメントを高める効果も期待できます
このように、動画生成AIのプロンプトは広告・教育・社内広報など幅広い業務シーンで成果を生み出せます。特に教育や研修分野は、組織的なスキル定着に直結するため、プロンプト設計を体系的に学ぶ研修の価値が高まっています。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
応用テクニック|プロンプトの精度をさらに高める方法
基本構造を理解して使えるようになったら、次のステップは「精度をさらに高める工夫」です。プロンプトを少し変えるだけで、映像のクオリティや再現性が一段階アップします。ここでは、実務でも役立つ応用テクニックを紹介します。
リファレンス素材を組み合わせる
テキストだけでなく、画像や音声をリファレンスとして組み合わせることで、生成結果は一気に安定します。
例:特定の商品写真をリファレンスとして添付し、「その商品を手に持つ人物がカメラに向かって笑顔で話す動画」と指示する
音声の場合はナレーションやBGMの雰囲気を指定でき、映像と音の統一感を高める効果があります。
この方法は、マーケティング素材や研修教材など「正確さ」が求められるシーンで特に有効です。
シーンを分割して統合する
一つのプロンプトで複雑な動作を再現しようとすると破綻しやすいため、シーンを分けて生成し、後から編集で統合する発想が重要です。
例:「人物が会議室に入るシーン」と「プレゼンを始めるシーン」を別々に作成し、編集ソフトで接続する
こうすることで、AIに無理をさせず自然な映像の流れを再現可能になります。
特に教育動画や研修コンテンツでは、手順を分けて動画を作った方が理解度も高まるため、業務活用に直結します。
高度な書き方を取り入れる
基本的な文章だけでなく、構造化された記述方法を取り入れるのも有効です。
- YAML形式やS.P.A.C.Eモデルなどを使うと、要素を整理しながら体系的にプロンプトを設計できる
- 複雑なシーンでも、要素を分解して組み立てることで再現性が安定する
上級者向けではありますが、BtoBでの本格的な導入を考えるなら、こうした高度な手法も知っておくと競合優位性につながります。
このように、リファレンスの活用・シーン分割・高度記述フォーマットを使うことで、単なる生成から「実務で使える映像制作」へとステップアップできます。
まとめ|動画生成AIは「プロンプト設計力」で成果が変わる
動画生成AIは、誰でも簡単に映像を作れる便利なツールに見えます。しかし実際には、プロンプト設計力の差がそのまま成果の差となります。
この記事では、
- プロンプトの基本構造(被写体+行動、背景+スタイル)
- 日本語と英語の使い分け方
- よくある失敗と改善のポイント
- 広告・教育・社内広報など業務別の活用事例
- 精度を高める応用テクニックとFAQ
を解説しました。ここまでの内容を押さえれば、「なぜ思い通りの動画が出ないのか」という疑問は解消できるはずです。
プロンプト指示について、生成AIのそもそもの構造や、構造から理解するからこそわかる「正確な回答を得られるプロンプトの考え方」やチェックリストなど、DX推進部門・生成AI人材育成担当が社内利用を推進する上で必要な情報をまとめた資料をご用意しております。プロンプト指示について正しい考え方を知りたい方は、お気軽にご覧ください。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
しかし、独学で学ぶには限界があります。特に企業で導入する場合、組織的にプロンプトを理解し、社員全体にスキルを定着させる仕組みが欠かせません。
👉 SHIFT AIでは、動画生成AIを含む生成AI活用を「研修プログラム」として体系的に提供しています。マーケティングや研修現場で「再現性のある成果」を出したい方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
動画生成AIプロンプトに関するFAQ
ここまで基本から応用までを解説してきましたが、実際に業務で使う場面では細かい疑問が生まれます。ここでは、読者から特に多い質問を取り上げ、具体的に答えていきます。
- Q動画生成AIは無料ツールでも使える?
- A
無料で使えるサービスもありますが、多くは生成できる動画の長さや解像度に制限があります。本格的に業務利用するなら有料プランや法人契約が現実的です。マーケティング動画や研修教材のように「一定の品質」が必要な場合は、安定性の高い有料版を検討すべきでしょう。
- Q商用利用は可能ですか?
- A
ツールごとに利用規約が異なるため、一律に「商用OK」とは言えません。Adobe Fireflyのように明確に商用可としているサービスもあれば、条件付きや制限がある場合もあります。必ず利用規約を確認し、法的リスクを避けることが重要です。特にBtoB用途では、研修動画や広告素材が法的に安全であることが前提になります。
- Qプロンプトは日本語だけで十分?
- A
日本語だけでも動画生成は可能ですが、英語を部分的に混ぜると精度が上がるのが一般的です。例えば「リアル調」「シネマティック」など、映像制作に近い用語は英語の方が表現力が豊かです。社内共有や教育では日本語中心に、品質を高めたい場面では英語を補強する「ハイブリッド型」がおすすめです。
- Q動画の長さはどのくらいまで作れる?
- A
多くの動画生成AIは数秒から十数秒程度に制限されています。長尺の教材や広告を作る場合は、複数の短尺動画を生成して編集でつなぐのが現実的な方法です。この点は「応用テクニック」で紹介した「シーン分割→統合」とも連動します。