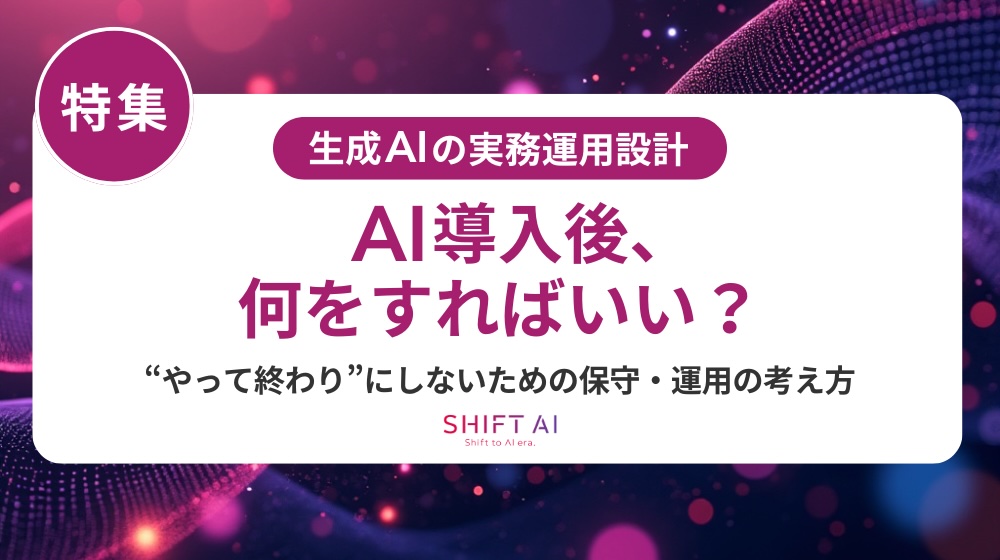「働き方改革だから、残業は減らしてくれ」
そう言われても、業務の量も質も変わらないのにどう減らせというのか。
このような“無理ゲー感”に、日々悩んでいるマネージャーや業務担当者の方も多いのではないでしょうか。
リスキリングだ、業務棚卸だと言われても、時間がないから残業しているのが現実。
そんな中、にわかに注目されているのが「生成AIによる業務効率化」です。
ChatGPTなどの生成AIを使えば、議事録作成やメール文面のドラフト、業務フローの整理など、これまで人が時間をかけていた仕事の一部を“瞬時に”“そこそこ高精度で”肩代わりしてくれるようになってきました。
すでに一部の企業では、月30時間以上の残業削減を実現した例も出始めています。
とはいえ、
「何をどう使えばいいのか分からない」
「ウチの業務でも本当に使えるのか?」
「結局、使いこなせずに終わるのでは?」
という不安も根強いのが現場の本音です。
この記事では、そうした不安を抱える方に向けて、生成AIで本当に残業を減らせる理由と、導入を成功させる実践ノウハウをお届けします。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ生成AIが“残業削減”に効くのか?3つの本質理由
業務効率化ツールは数多くありますが、「生成AI」が残業時間の削減に直結する理由は、その“本質的な変化”にあります。
ここでは、単なるツール導入では得られない、生成AIならではの時短効果を3つの観点から解説します。
単純作業の自動化|「手数」の削減
残業が発生する大きな要因のひとつが、手間が多い定型業務です。
たとえば以下のような作業に、多くの企業で1日1〜2時間が費やされています。
- 議事録の清書
- 社内報告書の定型フォーマット作成
- メール文の言い回しや表現の調整
- 社内通知や案内文のテンプレート作成
これらの業務は、生成AIを活用することで“たたき台”を瞬時に出力できるようになり、
従来より60〜90%の時間短縮を実現した企業もあります。
ポイントは、「ゼロから自分で書く」のではなく、AIにドラフトを任せて“最後に整えるだけ”にする発想です。
この変化により、1タスクごとの所要時間が数十分単位で削減されるため、
1日あたりの残業を大幅にカットすることができます。
思考の高速化|「迷う時間」の削減
単純作業だけでなく、“考える業務”にも時間がかかるのが現実です。
たとえば、
- 提案書の構成が思いつかない
- 企画の切り口に悩んでいる
- 伝わるタイトルや見出しが決まらない
このような“思考のスタート地点”で詰まる時間は、本来の価値創出に結びつかない残業を生みがちです。
生成AIを活用することで、これらの業務も「壁打ち相手」を即座に持てるようになります。
たとえばChatGPTに対して「このサービスを魅力的に伝える提案書の構成案を出して」と聞くだけで、
複数の構成素案や切り口が瞬時に返ってくるのです。
結果として、判断の起点が早まり、検討・作成の時間も短縮されるため、
“考える業務”もスムーズに終えられるようになります。
属人知の補完|「人に聞く」時間の削減
もうひとつの隠れた時間泥棒が、「あの人に聞かないと分からない」業務です。
たとえば、
- 複雑なExcel関数の使い方
- 社内申請ルールの細かい規定
- 過去の会議で使われた文言や資料
こうした知識は形式知化されていないことも多く、問い合わせや調べ物に時間がかかりがちです。
生成AIはこうした“属人知”の一部を自然言語で補完してくれるため、「人に聞かなくても答えにたどりつける状態」をつくることが可能になります。
特に社内ナレッジをAIに学習させる仕組みを組み込めば、社内ヘルプデスクやベテラン社員の“分身”として機能し、全社的なタイパ向上にも貢献します。
このように、生成AIは「手数を減らす」「迷いを減らす」「人に頼らず進める」ことで、
1人あたり1日1時間以上の時短につながる可能性を持っています。
残業が減った!業務別ユースケース5選
「本当に効果があるのか?」
そう感じる方にこそ届けたい、実際に“残業削減”に直結した業務別の生成AI活用事例を5つ紹介します。
それぞれの業務において、どんな作業をどう短縮できたのかがイメージできる内容になっています。
営業|報告書・提案書の時短で「1件90分→30分」
営業職では、提案書やヒアリング報告のドキュメント作成に追われる時間が残業の温床になりがちです。
ある企業では、
- 音声メモや議事録をAIで要約し、報告書の下書きを自動生成
- 顧客ニーズに応じた提案文を、AIに“たたき台”として出力させる
といった活用により、提案書1件あたりの作成時間を60%以上短縮しました。
総務・人事|社内文書の作成効率化で“繰り返し業務”を削減
総務や人事では、毎月のように必要となる
- 通達文・案内文・通知メールの作成
- 社内FAQの対応文面作成
といった定型業務の“文言づくり”が、想像以上に時間を取ります。
これらの業務に対して、生成AIを使ってテンプレート化+カスタマイズ文案の自動化を行うことで、
月10〜15時間程度の残業削減に成功した事例があります。
情シス・管理部門|社内問い合わせ対応の自動化で“人手対応”を軽減
情シスや管理部門には、「◯◯ってどう申請するの?」「このフォーマットどこ?」といった
“細かいが頻繁な問い合わせ対応”が集中しがちです。
こうした部門で生成AIを導入した企業では、
- よくある社内FAQをベースにAI回答ボットを作成
- 過去の質問・資料を学習させ、社員向け“社内チャット窓口”を構築
という施策により、問い合わせ対応時間を50%以上削減しています。
現場管理職|部下の成果物レビューの“目処”を立てやすく
資料作成や報告のレビューが遅れ、その分だけ帰宅が遅れる──。
そんな「仕上がりが読めない部下のアウトプット」による残業を軽減するために、生成AIを“レビュー支援ツール”として使うケースも増えています。
具体的には、
- AIに「伝わりやすさ」「ロジックの流れ」をざっくり確認させる
- 不明点や改善点を指摘させ、レビューの指針にする
ことで、レビュー時間の短縮&内容の質向上につながっています。
経営企画・バックオフィス|リサーチ業務の効率化で“前準備時間”を半減
戦略立案や施策企画などを担う企画職・バックオフィスでは、
調査・情報収集・要約といった“下ごしらえ”に多くの時間を要します。
生成AIを活用すれば、
- 競合情報の要約・比較
- 公開レポートの要点抽出
- 施策案に対するフィードバック出力
が自動化され、1回あたりのリサーチ時間を半分以下にできたケースも出ています。
関連記事:中小企業の生成AI活用ガイド|段階的活用で業務効率化を実現
生成AI導入だけでは“残業削減できない”理由
生成AIに期待して導入したものの、「現場では使われていない」「残業が減るどころか変わらない」といった声も少なくありません。
なぜ、せっかくの最新ツールが活かしきれないのか?
そこには多くの企業が見落としがちな3つの落とし穴があります。
「導入しても使われない」問題
最も多い課題は、現場にツールを配って終わってしまうケースです。
たとえば「ChatGPTのアカウントを配布した」「Slackに連携した」というだけでは、
社員が自ら能動的に活用できるようにはなりません。
現場の声としても、
- 「どの業務に使えばいいか分からない」
- 「使って怒られたらどうしよう」
- 「誰も使っていないから手を出しづらい」
といった不安や遠慮が根強く、結局“使われないツール”になってしまいます。
ツールの操作より「活用思考」が欠けている
導入支援では、ツールの基本操作を教えるだけで満足してしまうケースも多く見られます。
しかし本当に必要なのは、
- 「この業務の、この作業にAIをどう使うべきか?」
- 「どんな指示を出せば、時間が短縮できるか?」
といった活用設計力と“プロンプト思考”です。
たとえば、「議事録を要約して」と依頼するのではなく、「5W1Hでまとめて/次回アクションを抽出して/箇条書きで30秒以内で読める形に」と指示できるかどうかで、成果の質と時間短縮効果は大きく変わります。
「社内文化」やルール整備が追いつかない
さらに見落とされがちなのが、AI活用に関する“社内の合意形成”と“ルール設計”です。
AI活用を進める中で、以下のような不安が現場で噴出します。
- 情報漏えいのリスク(社外ツールへの入力)
- 正確性への不安(間違った出力を信じてしまう)
- 評価基準の不明確さ(使っても評価されない)
- 利用が一部メンバーに偏ってしまう(属人化)
こうした不安を放置すると、せっかく導入した生成AIが「怖くて使えないもの」になりかねません。
だからこそ、「どこまで使ってよいか」「成果はどう測るか」「使い方を共有する仕組み」など、運用ルールや文化醸成の整備が欠かせないのです。
残業削減につながる“生成AI研修”の設計とは?
「生成AIを導入したけれど、現場で使われない」
「結局、慣れた人しか使っておらず、残業も変わらない」
こうした声の背景には、使い方を教えていない/使う環境を整えていないという課題があります。
つまり、生成AIを本当に業務に定着させ、残業削減という成果につなげるには、単なる“ツール導入”ではなく“社内浸透の仕組み”が必要不可欠なのです。
ここでは、残業削減を目的とした生成AI研修の設計ポイントを、3つのステップに分けてご紹介します。
STEP1|業務棚卸:どの業務が“AI化できるか”を可視化する
いきなり「AIを使いましょう」と言っても、現場の多くはピンときません。
まず必要なのは、現状の業務の中で「時間がかかっている」「繰り返しが多い」業務を棚卸しすることです。
具体的には、以下のような観点で洗い出しを行います。
- 毎日・毎週のルーティン業務(例:議事録、報告書、通知文)
- 時間はかかるが創造性は求められない業務(例:マニュアル更新、定型メール)
- 思考時間が長いが、構造は決まっている業務(例:企画書、比較表の作成)
この棚卸によって、「AIで置き換えられるかもしれない業務のリスト」が明確になります。
STEP2|ユースケース別のプロンプト研修で“使い方”を定着させる
次に行うべきは、「業務ごとに最適なプロンプトの型」を実践しながら学ぶ研修です。
これにより、社員は単なる操作方法ではなく、“業務でどう使えば効率化できるか”という視点を身につけられます。
たとえば
| 業務カテゴリ | 研修で扱うプロンプト例 |
| 議事録要約 | 「この議事録を5W1Hで要約し、次回アクションを抽出して」 |
| 通知文作成 | 「以下の内容を、社内メール形式で300文字以内に整えて」 |
| アイデア出し | 「この商品を訴求する3つの切り口と、それぞれのメリットを挙げて」 |
こうした“型”を実務とセットで習得することで、日常業務への応用が加速し、使いこなす社員が一気に増えていきます。
STEP3|KPIと仕組み化で“活用を続けられる環境”をつくる
最後のポイントは、「一度研修して終わり」にしない仕組みづくりです。
以下のような運用設計が重要になります。
- 活用KPIの設定(例:業務1件あたりの所要時間/活用頻度)
- プロンプト共有の文化(例:社内で“使えるプロンプト”を投稿・共有する)
- AI活用委員会の設置(例:活用状況をレビュー・改善)
- 業務ごとの活用マニュアル整備(属人化防止)
このように、「活用を当たり前にする仕掛け」を仕込むことで、生成AIが一過性ではなく“残業削減の仕組み”として根づいていくのです。
まずはどの業務から始めるべき?チェックリスト付き診断
「なるほど、生成AIが残業削減に効くことは分かった」
「でも、自社のどの業務に使えばいいの?」
そんな声に応えるために、まずは“AIで置き換えやすい業務”を簡単に見極めるチェックリストをご用意しました。
以下に該当する業務があれば、それが“時短インパクトのある最初の一歩”になる可能性大です。
AI導入の効果が出やすい業務チェックリスト
| チェック項目 | 該当すれば…? |
| □毎週・毎月、定期的に発生している | 業務の繰り返し性が高い=自動化の対象にしやすい |
| □テキスト中心のアウトプットが必要 | 文書作成・要約・ドラフト生成などにAI活用可 |
| □手順やフォーマットがある程度決まっている | プロンプトで再現しやすく、定型化が容易 |
| □考える時間が多く、進行が止まりやすい | “壁打ち”としてのAI活用で思考を高速化可能 |
| □他部門からの問い合わせが頻繁に来る | AIによるFAQ回答やナレッジ補完が有効 |
3つ以上該当すれば、すぐにAI活用による残業削減が期待できます。
「すぐに始めたい」なら、小さく始めるのがコツ
すべての業務を一気にAI化する必要はありません。
まずは1つ、「これは負担が大きい」と感じている業務に対して、生成AIを試験導入してみるのがおすすめです。
たとえば
- 「会議議事録の要約だけは毎回時間がかかる」→AIに下書きを作らせてみる
- 「毎月のレポート作成がつらい」→過去データをもとに骨子だけAIに出させてみる
こうしたスモールスタートから“成功体験”を積み重ねることが、活用定着の最大の近道になります。
まとめ:生成AIは「残業削減」のための経営ツール
生成AIは、単なる「話題のツール」ではありません。
現場の時間を取り戻し、残業を削減し、働き方そのものをアップデートするための“経営ツール”です。
もちろん、ツールを導入するだけで自動的に残業が減るわけではありません。
大切なのは、
- どの業務に使うかを見極め
- 現場で使えるように教育し
- 活用が継続する仕組みを整えること
この3ステップを丁寧に行うことで、生成AIは“使える”だけでなく“役立つ”存在になります。
すでに月30時間以上の残業削減に成功している企業も登場しており、今こそ、「うちにはまだ早い」と言っていたら乗り遅れる時代です。
まずは、自社にとって
「どの業務に使えそうか?」
「どこから始めるべきか?」
を整理し、スモールスタートで成功体験を積むことが鍵です。
- Q本当に生成AIで残業は減らせるのでしょうか?
- A
はい、業務の種類によっては大幅な時短が可能です。
特に議事録・報告書・通知文などの定型作業では、1件あたり60~90%の時間短縮を実現した事例もあります。
ただし、“使い方”が重要であるため、現場に即した研修や定着支援が成功のカギになります。
- Qうちの会社は中小企業ですが、導入するメリットはありますか?
- A
むしろ中小企業ほど、効果が出やすいケースが多いです。
限られた人手で多くの業務を回している企業では、生成AIの活用によって1人あたりの生産性を底上げできます。
小規模だからこそ、導入から定着までのスピードも速く、効果が見えやすいのが特徴です。
- QITツールが苦手な社員でも活用できますか?
- A
はい、生成AIは“誰でも使える業務支援パートナー”です。
ChatGPTなどは自然な日本語で指示でき、特別な操作スキルは不要です。
また、研修では「プロンプトの型」を覚えるだけで効果的な活用が可能になります。
- Qセキュリティ面が不安です。業務で使っても問題ありませんか?
- A
安全に使うためには“社内ルール整備”が必須です。
社外ツールの利用にあたっては、個人情報や機密情報の取り扱い方針を明確にし、ツールの選定・設定を見直すことが重要です。
研修では、そうした情報管理ルールの整備ポイントも解説しています。
- Qどの業務から始めればよいか分かりません…
- A
簡単なチェックリストで判断できます。
記事内でもご紹介したように、「定型的」「テキスト中心」「思考停止ポイントが多い」業務から着手するのがおすすめです。
まずは資料で“AI化しやすい業務”の傾向と導入ステップをご確認ください。
- Q導入支援や研修はお願いできますか?
- A
はい、法人向けの生成AI研修・導入支援プログラムをご用意しています。
業務棚卸・活用設計・定着支援まで、貴社の状況に合わせてカスタマイズ対応が可能です。