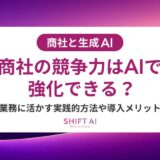「もう無理かもしれない」——
会議の帰り道、何気なくスマホで「中間管理職辞めたい」と検索したあなたは、きっと今、とても疲れているのだと思います。
責任は重いのに裁量はない。
部下からの不満に挟まれ、上からは数字だけを求められる。
成果を出しても褒められず、評価も曖昧。
このまま続けていたら、自分が壊れてしまう——
そんな不安を抱えていませんか?
でも、辞めることへの迷いや、家族や部下のことを考えると、すぐに決断するのも難しい。
「この気持ちはただの甘えなのでは?」
そう自分を責めてしまう方も多いはずです。
この記事では、そんなあなたに向けて、
- なぜ“中間管理職”が限界を感じやすいのか
- 辞める/辞めない以外の“第三の選択肢”とは?
- 辞めずに「楽になる」ための具体的な手段
をわかりやすく解説していきます。
これは、“逃げ”ではありません。
あなた自身を守るための、前向きな整理です。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
辞めたいと思った瞬間——それはどんなとき?
「もう限界かもしれない」
「このまま続けるのは無理だと思った」
中間管理職として働くなかで、こうした“辞めたい”という感情がこみ上げてくる瞬間は、ある日突然訪れます。
しかも、それは決して特別な事件が起きたときではありません。
ごく普通の1日の中に、ふとした“引き金”が潜んでいます。
この章では、実際に多くの中間管理職が感じている「辞めたい瞬間」を3つのシーンで紹介します。
「このままだと壊れるかも」と思った夜
終業時間をとうに過ぎたオフィスで、明かりがついているのは自分の席だけ。
部下たちは帰宅し、他部署も静まり返った中で、プレゼン資料の最終チェックや翌朝の報告資料を必死で仕上げている——
そんな日常を、あなたも過ごしていませんか?
ようやく仕事を終えて家に帰ると、家族はすでに就寝。
夕食もひとり、会話もない。
翌朝もまた早く出社しなければならないと考えると、眠りも浅くなる。
こうした日々が積み重なると、あるときふと、
「これ、あと何年続けられるんだろう……」
「このまま働いていたら、どこかで心か体が壊れる気がする」
と、漠然とした危機感が押し寄せてくるのです。
それは“弱さ”ではなく、あなたの体と心が発する自然な防衛反応です。
業務も人間関係も、全部自分が回している気がした
中間管理職に求められる役割は、近年ますます増えています。
目の前の実務に加え、部下の育成・評価・トラブル対応。
さらにはチーム全体の士気や心理的安全性にも気を配らなければならない。
一方で、上司からは売上・目標・生産性・人件費削減などの数字で追い込まれ、
「自分が止まったらすべてが止まるのでは」と錯覚するほど、
業務も人間関係も、全部自分の肩に乗っているような感覚に陥ることがあります。
そうした重圧の中で、
- 本当はやるべきではない雑務を引き受けてしまう
- 誰かのフォローに回り続けて、肝心の自分の業務が後回しになる
- 部下の代わりに謝ることが常態化している
といった状況が続けば、心はどんどん消耗していきます。
「これ以上、背負いきれない」と思ったときが、まさに“限界”のサインです。
相談相手が誰もいない、と気づいたとき
責任ある立場に就けば就くほど、「本音を話せる相手」がいなくなっていきます。
部下に弱みは見せられない。
同僚には競争意識がある。
上司には「甘えている」と思われたくない——
そんな思いから、相談や悩みの共有を自分の中で封じてしまう人が多いのです。
ある日、何気なく自分のスマホを見て、
「愚痴を言える人がいない」
「誰にもこのしんどさを話せない」
と気づいたとき、胸にぽっかりと穴が空いたような感覚を覚えるかもしれません。
孤独は、目に見えないストレスです。
そしてそれは、あなたが責任感を持って日々を乗り越えてきた“証”でもあるのです。
「辞めたい」は、決して珍しい感情ではない
ここで紹介したシーンは、どれも中間管理職なら誰もが経験しうるものです。
一見小さなきっかけに見えても、疲労やストレスが積み重なった末の“心の限界点”は、その一瞬に顔を出します。
だからこそ、「辞めたい」と感じる自分を責める必要はありません。
それは、あなたの心が「このままではまずい」と教えてくれているサインなのです。
「甘え」なのかもしれないと感じてしまうあなたへ
「この程度でしんどいなんて、自分が甘いのかもしれない」
「周りの管理職はもっと頑張っているのに、どうして自分は……」
そうやって、誰にも相談できずに自分を責めてはいませんか?
中間管理職としての“辞めたい”という気持ちは、決して特別なことでも、あなたの心が弱いからでもありません。
実は、あなたが感じているしんどさには、中間管理職というポジション特有の“構造的な負荷”が関係しています。
中間層に集中する「板挟み構造」の罠
中間管理職は、組織の中で非常に難しい位置にいます。
- 上司からは、業績や成果に対するプレッシャー
- 部下からは、相談・不満・指導への期待
- 同僚との間には、暗黙の比較や競争
- 現場の実務も自分で抱えながら、マネジメントまで求められる
いわば、「上からも下からも押しつぶされやすいポジション」であり、
そのプレッシャーは、経営者でも一般社員でもなかなか実感できないものです。
プレイングマネージャーとして「現場を回しつつ、チームも見ろ」という無理筋な役割設定も、近年の中間管理職が疲弊している一因となっています。
この構造は、あなた一人の問題ではなく、組織や働き方の設計上の問題なのです。
関連記事:中間管理職が辞める会社に共通する特徴とは?構造的な問題と“変われる組織”への第一歩
真面目な人ほど「自分が頑張ればいい」と抱え込む
特に真面目で責任感が強い人ほど、「他の人に迷惑をかけてはいけない」「自分が頑張れば回る」と考えてしまいがちです。
でもそれは、短期的には良くても、長期的には心身をすり減らす危険な考え方です。
“頑張りすぎた人ほど、限界を超えてしまいやすい”というのは、心理学的にもよく知られた傾向です。
「甘え」ではなく、「早めのセルフケア」
「辞めたい」と感じるのは、あなたが怠けているからでも、逃げたいだけでもない。
むしろ、組織の中で孤立しやすいポジションにいて、かつ責任感を持って働いてきたからこそ、心がSOSを出しているのです。
この気持ちに気づくのが遅れると、うつ・バーンアウト・慢性的な体調不良など、もっと大きな代償につながる可能性もあります。
だからこそ、「限界を感じる前に、環境や働き方を見直す」ことは、自己管理の一部であり、決して甘えではありません。
「辞める/辞めない」の2択で消耗していませんか?
「もう辞めるしかない」
「でも辞めたら、迷惑をかけるかもしれない」
「とはいえ、このまま続けるのもしんどい…」
こうして毎日、頭の中で「辞めるor辞めない」の間をぐるぐると行き来して、
気づけば何日も、何週間も、時間とエネルギーだけを消耗してしまっていませんか?
その2択は、本当に“唯一の選択肢”ですか?
私たちはつい、状況が苦しいときほど「白か黒か」で答えを出したくなります。
けれど、キャリアや働き方に正解は一つではありません。
ましてや、辞めるか続けるかという“0か100か”の思考は、視野を狭くしてしまいます。
今のあなたに必要なのは、「辞めるか、辞めないか」を問うことではなく、
“他にどんな選択肢があるか”を見つけることかもしれません。
辞める覚悟を持つことが、心の余白を生む
意外に思うかもしれませんが、「辞めてもいい」と思えるようになると、人は少しラクになります。
それは「逃げる準備」ではなく、「自分の意思で選べる」と感じられることで、状況に主体性を取り戻せるからです。
辞めることをタブー視せず、まずは“選択肢のひとつ”として冷静に整理してみる。
すると、そのうえで「辞めずにやれること」も見えてくるようになります。
「辞める/辞めない」以外にも、選べる道はある
ここで考えてみてください。
- 自分の業務負荷を減らせたら?
- 毎日繰り返す“しんどさ”が仕組みで軽くなったら?
- 部下育成や報告業務など、一部をツールに任せられたら?
これらが実現できるなら、「辞めずに済む」可能性もあるのではないでしょうか。
この後の章では、そうした“辞めずにラクになる”ための具体策を紹介していきます。
無理を前提とした努力ではなく、「楽になる努力」で、今の働き方を見直してみませんか?
辞めずにラクになるための、具体的な選択肢
「辞めるしかない」と思っていたのに、実は、辞めずに現状を変えられる方法があるとしたら——。
それが、“業務そのものの負担を軽くする”という発想です。
中間管理職の疲弊の多くは、「仕組み」ではなく「根性と気合い」で回している業務の積み重ねによって起きています。
だからこそ、そこに仕組みやテクノロジーを導入することが、有効な解決策になるのです。
プレイングマネージャー業務を“AIで手放す”という選択
会議の議事録作成、報告書のドラフト、メンバーの目標管理、チャット対応…。
こうした繰り返し作業・情報整理系の業務を一つひとつ手作業でこなしていると、
本来注力すべきマネジメントや意思決定に集中する時間が奪われてしまいます。
実際に、近年では以下のような活用事例が急速に増えています。
- ChatGPTなどのAIで報告書のたたき台を自動作成
- RPAツールで定型の数値レポートや進捗メールを自動送信
- 部下との1on1内容を自動でメモ・要約して蓄積
- チャットボットで問い合わせや業務フローの一次対応を代替
こうした“業務のスリム化”は、中間管理職にとって「辞めなくても働き方を変える」大きな突破口になります。
属人化していたマネジメントを「仕組み化」する
「自分がやらないと回らない」
「育成や指導がうまくいかない」
そう感じている業務の多くは、実はナレッジや仕組みの整備不足が原因です。
たとえば
- 新人教育のナレッジが属人化している
- 指示の伝え方が人によってバラバラ
- 定例業務の手順が口頭ベースでしか共有されていない
これらは、AIを使った研修設計やマニュアル化支援によって標準化・自動化することが可能です。
SHIFTAIforBizでは、こうした「中間管理職の業務を軽くする」ための研修・支援ソリューションを提供しています。
「頑張る」から「ラクに進める」へ、働き方の軸を変えよう
あなたの「辞めたい」という感情は、もしかすると“過重な業務”と“孤独なマネジメント”による、蓄積された疲労の表れかもしれません。
だからこそ、今の業務そのものを仕組みで見直すという視点は、「辞める」という極端な選択をせずとも、自分を守る有効な手段になりえます。
今の自分を整理するためのセルフチェックリスト
「辞めたいけど、どうしていいかわからない」
「モヤモヤしたまま、ただ時間だけが過ぎていく」
そんな状態が続いているなら、一度立ち止まって、今の自分を“見える化”してみることをおすすめします。
悩みや感情を整理するだけでも、次の一歩が見えてくることは少なくありません。
ここでは、中間管理職として限界を感じているあなたのために、心と業務の棚卸しチェックリストをご紹介します。
1.「つらい」の正体を言葉にする
まずは、感じているストレスや違和感を具体的な言葉にしてみましょう。
- いつ、どんな場面で「辞めたい」と感じたか?
- それは誰との関係、どんな業務が原因か?
- 何が“耐えられない”と感じるのか?
感情を抽象的なままにしておくと、行動に移すことが難しくなります。
手帳でもスマホのメモでも構いません。「この瞬間が苦しかった」と書き出すことが第一歩になります。
2.自分が“抱えすぎている”業務はどれか?
中間管理職は、気づかないうちに「他人の業務」まで請け負ってしまうことがあります。
- 本来、部下に任せるべき仕事を自分でやっている
- 曖昧な指示や不完全なタスクを、最後まで仕上げてしまっている
- 他部署や取引先との調整役を、すべて引き受けている
こうした業務を棚卸しすることで、「どこに負担が集中しているのか」「何を“手放す”べきか」が見えてきます。
3.頼れる人・頼れる仕組みはあるか?
仕事の悩みを話せる人はいますか?
困ったとき、迷ったときに相談できる相手やツールはありますか?
「孤独なマネジメント」から抜け出すには、人間関係の棚卸しも必要です。
- 職場で信頼できる同僚や上司は?
- 外部に話を聞いてくれるキャリア相談窓口は?
- 業務の負担を軽減するツールや制度は?
ひとりで抱え込まない体制をつくることも、“辞めずに働き続ける”ための大きな鍵になります。
このように、少しずつでも自分の状況を言語化し、把握できるようになると、
「どうすれば楽になれるか」「何を変えればいいか」の糸口が見えてきます。
それでも辞めたいなら、それも正しい選択
ここまで、辞めたいと思ったときの感情や構造、
そして「辞めずにラクになる選択肢」について見てきました。
しかしそれでも、「やっぱり辞めたい」という気持ちが拭えないのであれば、
それはあなたの中で十分に考え抜いた末の、正当な結論かもしれません。
「撤退」は敗北ではない。未来への“再構築”である
「辞めること=逃げ」「続けること=強さ」
そんな価値観に縛られていませんか?
でも、現実には“壊れるまで我慢する”ほうがリスクが大きいというのが、現代の働き方です。
うつやバーンアウト、人間関係の断絶。
そうなってしまってからでは、立て直すのに何倍もの時間と労力がかかってしまいます。
だからこそ、限界を感じた時点で立ち止まり、自分の人生を“戦略的に組み直す”決断としての退職は、むしろ賢明な選択肢です。
辞めたあとに後悔しないために、今やるべきこと
退職はゴールではなく、新しいスタートのための通過点です。
そのスタートをポジティブに切るためにも、以下のような“事前準備”をおすすめします。
- 「何がつらかったか」「何を変えたいか」を言語化しておく
- 今後やりたいこと・興味のあることをリストアップする
- 転職支援サービスやキャリア相談を活用する
- 家族やパートナーに、素直な気持ちを共有する
- スキルアップや学び直しの計画を立ててみる
辞める決断は一時的に不安も伴いますが、それ以上に“自分で未来を選び取った”という感覚が、後の自信へとつながっていきます。
あなたがどんな選択をしても、それは間違いではありません。
大切なのは、「もう無理だ」と思った自分の気持ちを否定せず、そこから“どう生き直すか”を見つけることです。
【まとめ】——「辞めたい」と感じたあなたへ、最後に伝えたいこと
「辞めたい」と思ったあなたは、決して甘えているわけでも、弱いわけでもありません。
それは、自分の限界に正直になれた証拠です。
むしろ、誰にも相談できず、重責を抱えながら、それでも今日までなんとか踏ん張ってきたあなたは、本当にすごい人だと思います。
本記事では、中間管理職として働くなかで、
- なぜ「辞めたい」と感じるのか
- それが個人の問題ではなく構造的なものであること
- 辞める/辞めない以外に、「辞めずに変える」という選択肢があること
をお伝えしてきました。
あなたはもう、頑張り続けるしかない働き方から解放されていいのです。
今後も管理職として働き続けるなら、“無理を前提にした根性論”ではなく、仕組みでラクになる選択を検討してみませんか?
- Q中間管理職を辞めたいのは「甘え」なのでしょうか?
- A
決して甘えではありません。
中間管理職は、上と下に挟まれる構造的に負荷の高いポジションです。
実務・マネジメント・部下対応・目標責任などが一手に集中しやすく、
「辞めたい」と感じるのは、ごく自然な反応です。
まずは自分を責めるのではなく、「今の働き方が続けられる状態か」を客観的に見直すことが重要です。
- Q中間管理職を辞めるとキャリアに悪影響はありますか?
- A
退職や異動はキャリアを“立て直す機会”にもなります。
近年は、マネジメント以外の専門職やプロジェクトベースの働き方を選ぶ方も増えています。
また「プレマネ→再学習→別領域マネジメント」など、戦略的なキャリア再構築も可能です。
大切なのは、自分に合った役割や環境を選ぶことです。
- Q上司にも部下にも相談できないのですが、どうすればいいですか?
- A
第三者の視点を借りるのが有効です。
社外のキャリア相談、産業カウンセラー、人事との個別面談、または信頼できる社外の知人など、
「利害関係のない相手」に話すことで整理できるケースが多くあります。
また、記事内で紹介したような仕組みによる負担軽減を検討することで、
無理に一人で抱え込まなくても良い状態を作ることも可能です。
- Qどうして中間管理職ばかりが疲弊してしまうのですか?
- A
中間層に“組織の矛盾”が集中しやすいからです。
経営と現場、戦略と実務、理想と現実の間に立つポジションであるため、
意思決定も、現場の不満も、自分を通って流れてきます。
さらに近年は「プレイングマネージャー化」が進み、業務の肥大化も深刻化しています。
これは個人の能力ではなく、構造の問題として認識すべきです。
- Q辞めずに業務をラクにする具体策は本当にありますか?
- A
はい、あります。
AIの活用・業務の自動化・ナレッジの標準化などによって、
中間管理職が担っている負荷を仕組みで分散・軽減する取り組みが進んでいます。
たとえば、報告書作成のAI支援、部下指導のテンプレート化、チャット対応の自動化など。
詳しくはSHIFTAIforBizの資料をご覧ください。