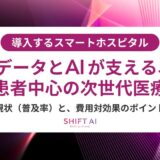中小企業には売上やアンケート、問い合わせなど、経営に使えるデータがそろっています。しかし「分析できる人がいない」ことで活用されずに終わる場面が多くあります。
ChatGPTを使うと、Excelや自由記述を読み込ませるだけで、傾向や原因、改善のヒントを短時間で整理できます。ただし、データの渡し方が適切でないと要約に留まり、十分な示唆は得られません。
この記事では、売上・アンケート・問い合わせの3種類をもとに、ChatGPTで“実務に使える分析”を行う手順をまとめました。意思決定につながる形でデータを読み解く方法を紹介します。
- ChatGPTで“中小企業のデータ分析”はどこまでできる?
- 分析品質が劇的に変わる“データの渡し方”|売上・顧客・問い合わせの3類型別テンプレ
- AIの回答が安定する“前提条件の与え方”|分析の精度を決める4つのポイント
- 売上データ × ChatGPT|“次の一手”を見つける経営企画レベルの分析フロー
- 顧客アンケート × ChatGPT|自由記述を“示唆”に変える4ステップ
- 問い合わせ・クレーム × ChatGPT|現場改善につながる原因分析と再発防止案の作り方
- 構造化プロンプト術(事実 → 解釈 → 課題 → 示唆 → アクション)|“誰が使っても同じ質”をつくる最強フレーム
- AIで作った分析を“経営会議で通る資料”に変える方法
- まとめ|“解釈できる組織”が、データの価値を最大化する
- 中小企業のChatGPTデータ活用に関するFAQ(FAQ)
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
ChatGPTで“中小企業のデータ分析”はどこまでできる?
ChatGPTは便利な分析ツールと思われがちですが、実際にはExcelやBIとは役割が異なります。
特徴を正しく理解して使うことが、継続運用の前提になります。
ChatGPTが得意なのは、売上データやアンケート、問い合わせ内容などを読み込み、傾向整理・要因の推測・改善のヒントの言語化 といった“解釈の作業”です。
人が時間をかけて行うまとめや示唆出しを、短時間で再現性ある形に整えてくれます。
一方で、複雑な統計モデルの構築や大量データの高速処理は不得手です。
そのため、精密な数値分析はExcelやBIと併用する必要があります。
とはいえ中小企業では、精度の高い予測よりも“手元のデータから次の一手を素早く整理できること” が圧倒的に重要です。
ChatGPTはまさにこの領域と相性が良く、専門人材がいなくても経営判断の土台をつくれます。
イメージとしては、
・数値加工(Excel/BI)
→ ChatGPTで解釈・課題抽出・改善策
→ 会議や現場の意思決定に展開
という流れがもっとも自然で、実務にフィットします。
すでに多くの企業が、売上原因の整理、アンケート自由記述の構造化、問い合わせの傾向分析などに活用しています。
分析担当がいなくても “最初の一歩をつくるパートナー” として大きな役割を果たします。
分析品質が劇的に変わる“データの渡し方”|売上・顧客・問い合わせの3類型別テンプレ
ChatGPTにデータを読み込ませても、期待した答えが返ってこない理由の多くは、「データの整理が十分でない」 この一点に尽きます。
分析の質は、データの渡し方で大きく変わります。
とくに中小企業で扱うデータは、売上・顧客アンケート・問い合わせの3種類に集約されるため、ここを“ChatGPTが理解しやすい形”に整えることが最も重要です。
売上データ|“表形式”+“分解可能な項目”が鍵
売上データは、ChatGPTが最も扱いやすいデータの一つです。ただし、日付と金額の羅列だけでは、深い分析は難しくなります。
チャットに渡す理想の形式
日付 | 商品カテゴリ | 商品名 | 客数 | 単価 | 売上
2024/01/01 | 飲料 | コーヒー | 120 | 380 | 45,600
2024/01/02 | 飲料 | コーヒー | 98 | 380 | 37,240
...ポイントは 「客数 × 単価」で分解できる項目を入れること。
これだけで、ChatGPTに「客数が落ちているのか、単価が下がっているのか」を判断させられます。
ChatGPTへ渡す前に整えること
- 商品カテゴリを統一する(表記ゆれをなくす)
- 空欄は「0」か「不明」と明示
- 日付形式を揃える
この3つだけで、分析の精度が目に見えて変わります。
顧客アンケート|自由記述は“単純なテキストのまとまり”でOK
アンケートの自由記述は、ChatGPTの得意領域です。ただし、形式がバラバラだと分析に一貫性が出ません。
渡すときの理想の形式
Q1:当店の満足度を教えてください(1〜5)
5
4
3
5
...
Q2:理由を教えてください(自由記述)
・店員の対応が丁寧で安心できた
・レジ待ちの時間が長かった
・商品の説明がわかりやすかった
...「質問 → 回答」という形で揃えることで、ChatGPTが “質問の意図に合わせて分析する” のが圧倒的に簡単になります。
分析の質が上がる前処理
- 改行を整える
- 攻撃的なコメントは伏せ字にする(ChatGPTが暴走しにくくなる)
- 複数質問がある場合は「Qごと」に仕分ける
問い合わせ・クレーム|“分類できる単位”で渡すと原因分析が深くなる
問い合わせやクレームは、会社の改善ヒントが大量に詰まっているデータです。
ただし、原文を雑多なまま渡すと、ChatGPTは文脈を誤解しやすくなります。
渡す形式の最適解
発生日 | お客様属性 | 問い合わせ内容 | チャネル
2024/03/10 | 30代女性 | 予約フォームが開けない | WEB
2024/03/12 | 40代男性 | 商品の到着が遅い | 電話
...ChatGPTが深く読み解けるポイント
- 発生日:急増タイミングの特定
- お客様属性:特定セグメントの課題発見
- チャネル:改善対象の絞り込み
- 内容:分類・要因分析の素材になる
問い合わせは“構造化の度合い”で分析の深さが決まります。
個人情報を含むデータはどう扱う?(実務で最も聞かれるポイント)
ChatGPTにアップロードする場合は、次の対策が現実的です。
- 氏名・住所・電話番号などは伏せ字(XXXX)に置き換える
- 予約番号や顧客IDもランダム値に変換
- 生年月日は年代のみ残す(例:1980年代)
これだけで匿名性が担保され、ChatGPT側も十分に分析可能です。
3種類のデータが揃うと、分析の“相互補完”ができる
- 売上データ → 実数の動き
- アンケート → 顧客の感情と理由
- 問い合わせ → 不満や改善点
ChatGPTは、これらを同時に読み込み、「数値の変化」「顧客の声」「不満の傾向」 を横断で整理できます。
これこそが、中小企業にとって最も価値の高い“実務的なデータ分析”です。
AIの回答が安定する“前提条件の与え方”|分析の精度を決める4つのポイント
ChatGPTに「このデータを分析して」とだけ投げると、多くの場合“要約だけ”になり、深い示唆に辿り着きません。
精度を大きく左右するのは データそのものより、与える前提条件 です。
中小企業の実務で使う場合、押さえておくべき前提は次の4つに絞られます。
① 期間|どの範囲を分析対象にするか
期間が曖昧だと、ChatGPTはすべてを均等に扱ってしまいます。
指示の仕方の例
- 「対象期間は2023年1月〜12月」
- 「直近3ヶ月の変化を重視して整理」
- 「季節性を考慮したい」
期間を明示するだけで、分析の粒度と視点が揃います。
② 目的|何を知りたいのかを明確にする
目的が曖昧だと“広い要約”が返ってきがち。
与えるべき目的の例
- 売上低下の要因を特定したい
- 顧客の不満の傾向を知りたい
- 問い合わせの改善優先順位をつけたい
目的を1〜2行で書くだけで、回答の深さが大きく変わります。
③ 対象データ|どれを根拠に判断すべきか
複数のデータを渡す場合、重みづけを示さないとAIが誤解します。
指示例
- 「カテゴリAの売上を優先して分析」
- 「自由記述のみを使用」
- 「電話問い合わせの内容を中心に原因を抽出」
“何を基準に話すべきか”を明確化するのがポイント。
④ 背景情報|企業文脈を共有する
データだけでは企業固有の事情が伝わりません。
共有すると効果的な背景の例
- 競合が新規出店した
- スタッフ不足の日がある
- 新商品の投入で問い合わせが増えている
背景があるだけで、一般論ではなく“自社に合った示唆”に変わります。
売上データ × ChatGPT|“次の一手”を見つける経営企画レベルの分析フロー
売上データは、ChatGPTが扱えるデータの中で最も即効性が高いジャンルです。
とくに「客数 × 単価」という基本構造が明確なため、ChatGPTにとっても“解釈しやすい”データの一つです。
ここでは、中小企業がそのまま再現できる形で、売上データを使った分析フローを具体的に整理します。
① 売上を “客数 × 単価” に分解すると、課題が一瞬で見える
売上の変動は 客数の変化 と 単価の変動 のどちらか(もしくは両方)で必ず説明できます。
ChatGPTにこの構造を学習させると、売上低下の要因が明確になります。
入力例
この売上データを、客数と単価の変動に分解し、
「客数」「単価」「商品の構成比」の観点でどこに変化が起きているか整理してください。ChatGPTが引き出せる示唆の例
- 客数は安定しているが、単価が下がっている
→ 低価格帯商品の購入比率が増えている可能性 - 単価は変わらないが、客数が急減している
→ 来店導線(広告・店舗動線)の問題 - 特定カテゴリだけ売上が落ちている
→ 商品入れ替え・在庫・競合影響の可能性
“売上をどう読むべきか”が瞬時に整理されるのがChatGPTの強みです。
② トレンド・季節性・前月比をセットで読み取ると精度が上がる
経営判断に使うには、単月の数字だけでは不十分です。
ChatGPTには「長期と短期」を同時に解析させることで、より正確な示唆が得られます。
促し方の例
・月次の推移(トレンド)
・季節性(過去同月)
・直近3ヶ月の変動(短期)
この3つを比較しながら、売上の変化要因をまとめてください。これだけで ChatGPT は「長期的な構造なのか」「直近の一時的な現象なのか」を自動で分けて分析できるようになります。
③ ChatGPTに“改善仮説”まで出させると、意思決定が一気に早くなる
分析だけで終わるのではなく、次のアクション案まで生成するのがポイントです。
プロンプト例
売上変化の原因として考えられる仮説を5つ挙げ、
そのうち実行しやすい施策を優先度順に並べて提示してください。ChatGPTは“施策の優先度づけ”が得意なので、
- 費用のかからない施策
- 短期で効果が出やすい施策
- 現場で実行しやすい施策
のように、実務に近い視点で整理してくれます。
④ 経営会議ですぐ使える“要点整理”のテンプレがあると最強
ChatGPTは、数字の理由を言語化するのが得意です。
経営会議や社内共有には、要点だけ抽出させると非常に使いやすい資料になります。
テンプレート
以下の形式で、「経営会議用」の要点だけを抜粋してください。
1)数字の変化(事実)
2)変化の背景(解釈)
3)考えられる要因(仮説)
4)優先度の高い改善案(実務で動ける案)この形式で出力させると、「読みやすい → すぐ動ける → 会議がスムーズ」という好循環がつくれます。
⑤ ChatGPTは“月次レビューの型”づくりにも向いている
毎月同じフローで分析したい場合、ChatGPTに 標準プロンプト を作らせるのも有効です。
この売上データを使い、
来月以降も繰り返し使える「標準分析プロンプト」を作成してください。
目的は、売上の変化要因を毎月同じ基準でチェックすることです。これで「ぶれない分析」が毎月継続できるようになります。
関連記事:中小企業が生産性向上すべき理由とは?実践的な方法と成功のポイント
顧客アンケート × ChatGPT|自由記述を“示唆”に変える4ステップ
顧客アンケート、とくに自由記述の回答には「顧客の本音」が詰まっています。
しかし、内容がバラバラで量も多いため、担当者だけで読み解こうとすると時間がかかり、どう整理すべきか迷ってしまうケースが多くあります。
ChatGPTは、こうした“非構造データ”の整理が非常に得意です。
ポイントは、自由記述をただまとめるのではなく、「経営判断につながる示唆」へ落とし込ませること。
そのために必要な4ステップを整理します。
STEP1|自由記述を“感情”で分類させる|顧客の温度感をつかむ
まず行うべきは、自由記述の文章を ポジティブ/ネガティブ/ニュートラル の三段階で分類させることです。
プロンプト例
以下の自由記述を、
・ポジティブ
・ネガティブ
・ニュートラル
の3つに分類し、割合と特徴をまとめてください。ChatGPTは文章のトーンを正確に読み取るため、「顧客が何に満足しているのか」「どこに不満が溜まっているのか」が一目でわかります。
STEP2|似た内容を“テーマごと”にグループ化する|解決すべき課題を見える化
感情の次は、内容をテーマ別にクラスタリングさせます。
これは人間がやると膨大な時間がかかる作業ですが、ChatGPTなら短時間で整理できます。
テーマの例
- 接客
- 待ち時間
- 価格
- 商品のわかりにくさ
- 店舗の清潔感
- サイトの操作性
プロンプト例
以下の自由記述を、内容の近さに応じてテーマ別に分類し、
テーマ名と件数、特徴をまとめてください。この時点で、改善対象の優先順位が見えてきます。
STEP3|“なぜそう感じたのか”を抽出させる|根本原因に迫る
自由記述の価値は「事実」ではなく、“顧客がそう感じた理由” にあります。
ChatGPTに理由の抽出を行わせることで、表面的な不満ではなく、根本の要因が見えてきます。
プロンプト例
各テーマについて、顧客がそのように感じた理由を
文章の内容から推測し、3〜5つの根本原因としてまとめてください。ChatGPTはこの“解釈”が非常に得意で、
- スタッフ不足による行列
- 案内不足による不安感
- 商品説明の複雑さ
など、「確かにあるかもしれない」要因を自然に提示します。
STEP4|“打つべき一手”に落とし込む|経営会議で使える形に仕上げる
分析の最終目的は、施策につなげることです。
ChatGPTには“改善案まで出させる”ところまでセットにすると、読み手の行動が一気に早くなります。
プロンプト例
各テーマごとに、改善施策を3つずつ提案し、
その中から「実行しやすく効果が大きい」施策を優先順に並べてください。
フォーマット:
1)テーマ
2)現状の問題
3)実行可能な改善案
4)期待できる効果 するとChatGPTは、
- 現場で今すぐ実行できる施策
- コストをかけずに改善できる施策
- 優先すべき根本対応
を体系的にまとめてくれます。このまま経営会議資料として活用できるレベルになるため、
「アンケートの分析に時間がかかる」という課題を大幅に短縮できます。
問い合わせ・クレーム × ChatGPT|現場改善につながる原因分析と再発防止案の作り方
問い合わせやクレームは、中小企業にとって“改善の宝庫”ともいえるデータです。
ところが、現場が忙しいと 「対応して終わり」になりがち で、蓄積した情報が企業の改善サイクルに生かされていないケースが多く見られます。
ChatGPTは、この“バラバラに散らばった声”を構造化し、原因の傾向から改善策まで整理するのが得意です。
ここでは、どの会社でも再現できる分析フローを具体的にまとめます。
① 問い合わせ内容を“分類できる単位”にそろえると、分析の深さが変わる
問い合わせデータは形式がまちまちになりやすいため、まずはChatGPTが理解しやすいように整えます。
理想的な渡し方(例)
発生日 | お客様属性 | 問い合わせ内容 | チャネル
2024/03/10 | 30代女性 | 商品が届かない | WEB
2024/03/12 | 40代男性 | 返品したい | 電話
...この4項目だけで、
- 増えているタイミング(発生日)
- 特定層の問題(属性)
- 根本の不満(内容)
- どこに改善余地があるか(チャネル)
が読み取りやすくなります。
② ChatGPTに“テーマ別に分類”させる|改善の焦点を絞るための第一歩
問い合わせ内容を分類させるのはChatGPTの得意領域。
プロンプト例
以下の問い合わせ内容を、テーマごとに分類し、
テーマ名・件数・代表的な内容をまとめてください。分類の例
- 商品トラブル
- 配送遅延
- 操作方法の不明点
- 返品・交換
- 支払い関連
- スタッフ対応
分類されたテーマは、そのまま改善計画の“骨格”になります。
③ ChatGPTに“原因の仮説”を出させる|表面的な不満を深掘りする
問い合わせは「起きた事実」しか書かれません。
しかし、経営に必要なのは “なぜそうなったのか” という背景です。
プロンプト例
各テーマの問い合わせが発生している理由を、
文章内容から推測される「根本原因」として整理してください。
例)業務プロセスの欠陥、情報不足、操作性の問題、外部要因などChatGPTが出せる原因の例
- オンライン注文画面のボタンがわかりづらい
- 返品プロセスが複雑で、案内が統一されていない
- ピークタイムに人手が足りていない
- FAQやマニュアルが古い
AIは“文章に含まれる微細な兆候”から理由を拾い上げるのが得意なため、ここで一気に精度が高まります。
④ 改善施策を“実行しやすい順”に並べさせる|現場で動ける計画に変える
改善策を出すだけでは「いい案」で終わってしまいます。
ChatGPTには“優先度づけ”までセットで行わせることで、現場がすぐ動ける状態に変わります。
プロンプト例
各テーマごとに改善案を3つずつ出し、
「費用が少ない」「短期で実行できる」「影響範囲が大きい」などの基準で
優先度順に並べてください。ChatGPTが出せる改善案の例
- FAQを最新化し、わかりやすい表現に変更
- 注文画面のラベルを改善
- 返品フローを簡略化したガイド作成
- ピークタイムのスタッフ配置見直し
- 電話→チャットへの誘導で対応負荷軽減
“優先順位”があるだけで、経営者・現場どちらにとっても意思決定が圧倒的にしやすくなります。
⑤ 問い合わせ急増の“兆し”を見つける|現場で気づけない変化が見える
問い合わせは「急に増えた問題」をいち早く検知するためのデータです。
ChatGPTに時系列を読ませることで、「予兆レベル」の変化も拾えるようになります。
プロンプト例
問い合わせ件数の増減を時系列で読み取り、
急増しているテーマや時期を特定し、
考えられる外部要因・内部要因を整理してください。たとえば、
- 新商品の発売直後だけ特定の不具合が急増
- チャネル別で見ると電話だけ増加
- 特定年代からの同じ問い合わせが集中
など、“どこで何が起きているのか”が短時間で見えてきます。
構造化プロンプト術(事実 → 解釈 → 課題 → 示唆 → アクション)|“誰が使っても同じ質”をつくる最強フレーム
ChatGPTを使ったデータ分析は、ツールではなく “プロンプトの構造” で成果が決まります。
とくに中小企業では、「人によって解釈がバラバラ」「会議で話が合わない」「結局どの施策が正しいか迷う」 という問題が起きがちです。
こうした“人依存の判断のバラつき”は、ChatGPTを 構造化されたフレームで使う ことで、ほぼゼロにできます。
① 事実(Fact)|まず「起きていること」だけを整理させる
多くの人は、いきなり原因や施策を考えようとしますが、ChatGPTはまず“事実の抽出”から行わせることで精度が上がります。
促し方の例
データから読み取れる「事実のみ」を箇条書きで整理してください。
原因推測や解釈はまだ行わないこと。✔ “事実と解釈の混在”がなくなる
✔ 数字・傾向・分布などの「変化点」がクリアに見える
これだけで分析の土台が安定します。
② 解釈(Meaning)|事実をどう読み取るか、AIに言語化させる
次に行うのが、事実に対する ChatGPT の 意味づけ(解釈) です。
プロンプト例
整理した事実をもとに、その状況が示している意味を言語化してください。
「〜が続いている理由」「〜と考えられる背景」など推測のレベルで構いません。ChatGPTは「理由の推測」が得意なため、
- 需要の変化
- 顧客心理の変化
- 内部オペレーションの問題
- 商品ラインナップの偏り
など、人では気づきにくい視点を拾ってくれます。
③ 課題(Issue)|“本質的に直すべき点”を抽出させる
解釈が出揃ったら、そこから “根本課題” を抽出させます。
プロンプト例
解釈から導かれる「本質的な課題」を3〜5点抽出してください。
原因ではなく、改善すべき状態の定義として書いてください。例
- 来店導線が弱く、新規顧客の流入が減っている
- 説明不足で顧客の不安が拡大している
- 商品単価を維持できる価値が伝わっていない
“課題の定義”が明確になれば、施策は自然と絞り込めます。
④ 示唆(Insight)|「この状況は何を教えているのか」を深掘りする
示唆とは、データが企業に伝えているメッセージのことです。
視点が深いほど、意思決定の精度が大きく上がります。
プロンプト例
上記の課題について、
「この状況から読み取れる重要な示唆」を企業側の視点で3つ書いてください。示唆の例
- 高単価商品の継続強化より、導入商品の改善が急務
- 顧客満足度向上より、情報設計の再構築のほうが費用対効果が高い
- 再来店率より、初回体験の印象改善のほうが効果が大きい
示唆が得られれば、「何に集中すべきか」が明確になります。
⑤ アクション(Action)|経営判断につながる“次の一手”を並べる
最後に行うのが、行動レベルへの落とし込みです。ChatGPTには“優先順 × 実行可能性”の視点で出させるのが重要。
プロンプト例
示唆をもとに、実行しやすく効果が高い施策を
「短期」「中期」「長期」に分けて提案してください。このフレームで出力させると、
- すぐ着手する施策
- 現場改善でできる施策
- 経営が投資判断すべき施策
が明確になり、意思決定が圧倒的に早くなります。
このフレームをそのままChatGPTに渡せるテンプレート
【目的】
データから経営判断に必要な示唆を得たい
【フォーマット】
1)事実(Fact)
2)解釈(Meaning)
3)課題(Issue)
4)示唆(Insight)
5)アクション(Action)
【出力条件】
・事実と解釈を混ぜない
・原因と課題を混ぜない
・施策は「短期」「中期」「長期」で分けるこの構造で分析すれば、“誰が実行しても同じ品質でまとめられる仕組み” が完成します。
中小企業にとっての「再現性」は、まさに競争力そのものです。
AIで作った分析を“経営会議で通る資料”に変える方法
ChatGPTの分析結果は読み物としては十分でも、そのままでは経営会議で使える資料になりにくいことがあります。
ポイントは “資料の型を最初からAIに指定しておくこと” です。
ここでは、最低限抑えておくべき3つの型だけに絞って紹介します。
① 会議用の要点を1枚にまとめる|“結論・根拠・示唆”だけに整理
資料の冒頭には、判断に必要な情報だけをシンプルに揃えることが重要です。
ChatGPTには、次の3点だけを出すように指示します。
フォーマット
1)今回の結論(判断ポイント)
2)そう考える根拠(数字の事実)
3)重要な示唆(今後に関わる気づき)
この1枚があるだけで、会議がスムーズに進みます。
② 「事実 → 解釈 → 課題」だけ明確に分ける
読みやすい資料は、必ず 事実(数字)と解釈(推測)が混ざらない 構造になっています。
ChatGPTへの指示例
・まず「事実のみ」を箇条書きで整理
・次に「解釈(背景の推測)」を分けて記載
・最後に「本質的な課題」を3点抽出この3段構造を作るだけで、読み手が迷わない資料になります。
③ 改善策は“短期・中期・長期”で提案させる
施策が時系列で整理されていると、経営側・現場側どちらも動きやすくなります。
ChatGPTへの指示例
改善案を「短期(すぐできる)」「中期(3ヶ月以内)」「長期(投資が必要)」に分けて提示してください。優先度づけまで含めてAIに出させると、意思決定に直結する資料が簡単に作れます。
経営会議用テンプレ
【経営会議サマリー(1ページ)】
1)結論(今回の判断ポイント)
2)根拠(数字の変化)
3)示唆(重要な気づき)
4)課題(構造的に直す点)
5)アクション(短期・中期・長期)まとめ|“解釈できる組織”が、データの価値を最大化する
ChatGPTを使ったデータ分析は、特別なスキルを必要としません。
売上データ、アンケート、問い合わせなど、これまで読み解くのに時間がかかっていた情報を、数分で整理し、示唆まで導き出せる仕組みに変えることができます。
中小企業の現場で本当に価値があるのは、「データを集めること」ではなく、“データの意味を解釈し、すぐに行動に移せる状態” をつくることです。
今回紹介したフローは、そのまま明日から社内で使える内容です。
- 売上データを「客数 × 単価」で分解
- アンケートの自由記述を構造化
- 問い合わせ・クレームから再発防止案を導出
- 経営会議が10分で意思決定できる資料づくり
- 継続できる運用ルール(プロンプト・フォーマット・会議アジェンダ)
ChatGPTは、分析スキルを持つ人がいなくても、“経営の判断スピードを底上げするパートナー” に変わります。
AI経営総合研究所では、生成AIを導入だけで終わらせず、成果につなげる「設計」を無料資料としてプレゼントしています。ぜひご活用ください。
■AI活用を成功へ導く 戦略的アプローチ5段階の手順をダウンロードする
※簡単なフォーム入力ですぐに無料でご覧いただけます。
中小企業のChatGPTデータ活用に関するFAQ(FAQ)
- QChatGPTだけで本格的なデータ分析はできますか?
- A
ChatGPTは「解釈」「示唆出し」「構造化」に強みがあり、高度な統計処理や大容量データの高速分析は専門ツールのほうが向いています。
中小企業に必要な分析(売上の要因整理、顧客の声の傾向把握、改善策の抽出)はほぼChatGPTでカバーできます。
- Qデータの量が少なくても分析に使えますか?
- A
使えます。
むしろ、中小企業では「少量データ × 解釈の質」のほうが意思決定に直結しやすく、ChatGPTはこの“解釈の質”を底上げするのに向いています。
小規模な問い合わせ履歴やアンケート回答だけでも、改善につながる示唆が得られます。
- Q自社のデータをAIに読み込ませると情報漏えいは大丈夫?
- A
ChatGPTのビジネス版(ChatGPT Team / Enterprise)や自社内Microsoft環境のCopilotを使えば、学習に使われない・外部に出ない という安全な環境でデータを扱えます。
機密データを扱う場合は、ツールの利用ポリシーを整えるのが前提です。
- Qどの部署がデータ分析を担当すべきですか?
- A
最適なのは、“意思決定に近い部署×現場を理解している人” の組み合わせです。
経営企画・営業企画・マーケティング・管理部門などが中心となり、現場の担当者が補助的に関わる形が運用しやすいです。
ChatGPTは分析の「作業」を代替してくれるため、担当者は“判断”に集中できます。
- Qプロンプトを作るのが難しそうです。誰でも使えるようにできますか?
- A
できます。
プロンプトを “標準テンプレート化” し、月次分析・アンケート分析・問い合わせ分析の3本を揃えておくだけで、誰が使っても同じ質のアウトプットを得られる仕組みが作れます。
研修やマニュアル化と併用すると、社内展開がスムーズになります。