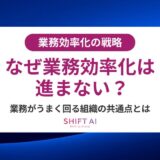中小企業でマーケティングを続けるのは簡単ではありません。
「SNSを更新しないと…」「ブログを書かないと…」とわかっていても、実際には営業・採用・事務など、他の業務が常に優先され、気づけば更新が止まってしまう。そんな状況は多くの企業で起きています。
本質的な問題は、“人がいない”ことではありません。
マーケティングを継続させるための仕組みがないことです。
ChatGPTは、中小企業が抱えてきたこの壁を大きく変えられる存在です。
文章を作るだけでなく、企画のアイデア出し、構成の作成、SNSの投稿案、広告コピーのバリエーション、LP改善案まで、マーケティングの流れを丸ごと支える「運用エンジン」として活用できます。
しかし、多くの情報は “何ができるかの紹介” にとどまり、マーケティングの現場で“どう運用として組み込むか”までは語られていません。本記事では、ブログ・SNS・広告コピーという中小企業にとって最も重要な領域に絞り、ChatGPTで“続けられるマーケティング”を作る方法を体系的にまとめます。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
中小企業のマーケティングが進まない“本当の理由”
中小企業の多くが抱えるマーケティングの課題は、「担当者がいないから」「文章が得意な人がいないから」といった“スキルの問題”だと思われがちです。しかし、実際に多くの企業を見ていると、問題の核心はもっと別のところにあります。
それは、マーケティングを動かす“運用設計”が存在しないことです。
ブログやSNSを更新するたびに、
「何を書けばいいんだろう」
「どんな構成にしよう」
「投稿ネタが思いつかない」
とゼロから考える状態では、どれだけモチベーションがあっても継続は困難です。
さらに、中小企業特有の問題として──
- マーケ専任がいない(兼務になる)
- 日々の業務が優先されて後回しになる
- 担当者が変わるとノウハウが消える
- すべて“属人的なやり方”になりがち
- PDCAを回す余裕がない
こうした構造が重なり、マーケティング施策は「始めるのは簡単、続けるのは難しい」状態になります。
本来、マーケティングに必要なのは「継続」と「改善」です。
しかし、企画→文章化→投稿→振り返りの流れが仕組みとして整っていなければ、担当者の負荷はどんどん積み上がり、やがて活動そのものが止まってしまいます。
ここで初めて、ChatGPTが効いてきます。
文章を書くのが得意かどうか、マーケの経験があるかどうかに関係なく、“誰でも回せる運用”をAIで設計できるからです。
ChatGPTが“中小企業のマーケと相性が良い”理由
ChatGPTは「文章を作る便利ツール」という印象が強いですが、実は最も大きな価値はそこではありません。
中小企業のマーケティングが抱える“構造的な課題”を根本から補完できる点にあります。
中小企業のマーケティングでは、企画 → ライティング → 修正 → SNSやLPでの出し分け → 改善
という一連の流れを、一人で/兼務でこなすケースがほとんど。
この“多工程を少人数で回す”という状況に、ChatGPTは驚くほどハマります。
① アイデア生成〜文章作成〜改善まで、全部ひとつのエンジンで動かせる
マーケティングには「考える」「書く」「検証する」の3つの力が求められます。
ChatGPTはこれらを同時に行えるため、
- ブログのテーマを出す
- 構成案を作る
- 見出し候補を考える
- 本文の下書きを作る
- SNS用に短文化する
- 広告用にキャッチコピー化する
- 改善点を洗い出す
という一連の工程を1つのツールで完結できます。
これにより、担当者が“企画をゼロからひねり出す時間”を大幅に削減できるようになります。
② 企画力・文章力の差を埋める
中小企業では、「マーケが得意な人」が必ずしもいるとは限りません。
誰が担当になっても、一定のアウトプットを出せる状態をつくるには、ChatGPTが支える“型化”が必要です。
- 書きたいことを箇条書きにするだけで構成案を作れる
- 文章の方向性を揃えられる
- ターゲットに合わせて調整できる
こうした機能が、担当者ごとのスキル差をほぼゼロに近づける役割を果たします。
③ PDCAのスピードが圧倒的に上がる
通常、PDCAは以下の理由で止まりがちです。
- 分析に時間が割けない
- 振り返る習慣がない
- 「どこを直すべきか」が分からない
ChatGPTは、出した文章やSNS投稿、広告コピーを読み込み、
- わかりにくい箇所
- 筋が通っていない部分
- 刺さりにくいコピー
- ターゲットとのズレ
- 改善案のリストアップ
まで自動で出してくれます。
これにより、改善(Check・Act)が高速化し、施策の質が安定します。
④ 社内ルールを覚えさせれば、品質が安定する
ChatGPTは「学習済みデータを更新する」という意味の学習はできませんが、
プロンプト内に
- 禁止ワード
- 使用すべき語彙
- 参考にすべき文章
- 自社のトーン
- 過去記事のスタイル
をセットにしておけば、ほぼ“社内向けの専用AIライター”として動くようになります。
担当者が変わっても品質が崩れないため、属人化を避けたい中小企業ほど、大きな価値があります。
ブログ運用|SEO記事を継続するための“量産プロセス”づくり
中小企業のブログが続かない最大の理由は、毎回ゼロから考える構造になっていることです。
テーマを考え、構成を作り、文章を書き、読み返し、SEOを整え──
これをすべて手作業で繰り返すのは、兼務の担当者には明らかに重すぎます。
ChatGPTを活用すると、この一連の流れを“型”として仕組み化できます。
このセクションでは、ブログを無理なく量産し、品質を保ちながら継続するためのプロセスを具体的にまとめます。
① テーマ・切り口を“無限生成”する型を持つ
ブログ運用の最大の壁は「書くネタがない」です。
ChatGPTに以下のような条件を渡すと、一度に数十〜数百のテーマを生成できます。
- ターゲット
- 提供する商品・サービス
- 過去に読まれた記事
- 競合の傾向
- 業界トレンド
ChatGPTは、それらを組み合わせた新しい切り口まで提案してくれるため、ネタ切れが起こりにくくなります。
② 検索意図に沿った“構成案”を自動生成する
構成が弱いと、どれだけ書いても検索順位が上がりません。
ChatGPTに競合ページやSEOキーワードを渡すと、検索意図を踏まえた「負けない構成案」を作成できます。
ポイント
- 上位10記事の“共通点”
- 取りこぼされている“抜け要素”
- 独自性を追加するポイント
- 必要なH2・H3の網羅性
ChatGPTはこれを一覧化できるため、記事の“勝ち筋”を最初から掴めます。
③ 下書きの7割をAIに任せる(仕上げ3割を人間が担当)
文章を書くときに最も時間がかかるのは、“白紙”を前にした最初の一歩です。
ChatGPTは構成が固まった段階で、一気に本文の下書きを7割程度まで書き上げられます。
担当者はその後、
- 外してはいけない情報を追記
- 誤情報がないかチェック
- トーンを整える
- 自社の視点を追加する
この“仕上げの3割”に集中できます。これにより、記事作成の負荷が大きく下がり、量と質を両立した運用が可能になります。
④ 品質を担保するためのチェックリストを用意する
AIの文章は便利ですが、そのまま使うと「読みやすいが浅い記事」になりやすいです。
以下をチェックリスト化し、ChatGPTの出力を一定レベルに整えると品質が安定します。
- 主語と述語がズレていないか
- 説明が重複していないか
- 専門的な誤りはないか
- 対象読者とズレた表現はないか
- 検索意図が外れていないか
- 具体例・理由の深さが足りない箇所はないか
- 自社視点(独自性)が入っているか
このチェック項目自体をChatGPTに覚えさせれば、記事の“監修助手”として運用できます。
⑤ ChatGPTで使えるブログ用プロンプト(高品質テンプレ)
記事の型を社内で共有しておくことで、担当者が変わっても品質が揃います。
テーマ生成プロンプト
「中小企業○○業界向けに、顧客の悩みを軸にしたSEO記事テーマを30個出してください。
競合が扱っていない切り口があれば優先してください。」
構成案生成プロンプト
「以下のキーワードで上位10記事を分析し、
・共通点
・不足箇所
・独自性の入れどころ
を踏まえて、検索意図に合ったH2・H3構成案を作成してください。」
本文生成プロンプト
「この構成案に沿って、H2→H3の順に本文を生成してください。
専門性・読みやすさ・流れを重視し、重複と抽象表現を避けてください。」
ChatGPTを「記事の作成者」にするのではなく、
“記事を継続する仕組み”の一部として組み込むことが、ブログ運用の成功につながります。
SNS運用|ネタ枯れを防ぐ“投稿ストック生成”の仕組み
SNSは「毎日更新したほうがいい」と言われながら、実際には 投稿ネタが思いつかない/時間がない/書いても反応がないという理由で止まってしまうことが多い領域です。
ChatGPTを活用すると、SNS運用そのものをストック型の仕組みとして回せるようになります。
① 媒体別の“型”を決めておくとブレない
Instagram、X(旧Twitter)、Facebookでは、求められる語り口・情報量・構成が違います。
ChatGPTに最初に「媒体別の型」を覚えさせておくと、誰が作ってもブレない投稿が作れます。
Instagramの型(例)
- 1枚目:結論・メッセージ
- 2〜5枚目:理由・事例・手順
- 最終ページ:行動導線(保存・来店・問い合わせ)
Xの型(例)
- 結論(1行)
- 理由(1〜2行)
- 具体例(1行)
- 行動を促す短文
Facebookの型(例)
- 背景・課題提示
- 解決策の説明
- 詳細情報
- CTA(次の動き)
型があることで、投稿内容が安定し、担当者が変わっても“企業アカウントとしての世界観”が保てます。
② 投稿ストックを月単位で“自動生成”する
ChatGPTに、「今月のキャンペーン」 「何を売りたいのか」 「どんな人に届けたいか」 を渡しておくだけで、
- 月間投稿カレンダー
- 30本のSNS原稿案
- リール企画
- ハッシュタグ案
まで一括生成できます。
特に忙しい兼務担当者にとって、“今日の投稿を今日考えないといけない地獄”から抜け出せるのは非常に大きな価値です。
③ 画像案・カルーセル案・世界観の方向性まで作れる
SNSは文章だけでは成立しないため、ChatGPTには「画像案」や「構図案」も出させておくと便利です。
- 写真:どんなシーン?どんな色味?
- 図解:どんな構造?どんな要素?
- カルーセル案:各ページのメッセージはどうする?
みたいな“デザインの方向性”までセットで出せます。
これにより、デザイナーや担当者は企画の芯だけ押さえればよくなるため、制作負担が減ります。
④ “AIっぽい文章”を避けるための社内ルールを作る
SNSは特に、AI特有の
- 敬語が堅すぎる
- 表現がキレイすぎる
- 文章が長い
- 体温がない
といった“AI臭さ”が出やすい領域です。これを避けるための、社内表現ルール(スタイル辞書)を作ると効果的です。
例
- 「〜しましょう」「〜できます」は使わない
- 感情語は控えめ
- 語尾は短く
- 1投稿の文字数は○○文字以内
- 体験談形式はOK
- 結論は最初に書く
この辞書をChatGPTに読み込ませれば、企業アカウント特有の世界観が保たれたままSNS運用ができます。
⑤ SNS特化のプロンプトテンプレ(実務で使える型)
以下は社内で共有しておくと、誰が使っても一定品質で出せるテンプレ。
SNS投稿カレンダー生成プロンプト
「今月の目標(例:○○の認知拡大)を踏まえ、 Instagram/X/Facebook 各5本ずつ、投稿案とハッシュタグ案を作成してください。」
Instagramカルーセル案プロンプト
「以下のテーマで、7枚構成のカルーセル案を作成してください。
1枚目は“結論とメッセージ”。
2〜6枚目は“理由・具体例”。
7枚目は“保存・お問い合わせ”を促す内容にしてください。」
X投稿文章化プロンプト
「以下の内容をもとに、130字以内で、本文→理由→一言アドバイスの順に投稿文を作成してください。」
ChatGPTをSNS運用の“アシスタント”ではなく、“仕組みそのもの”として組み込むことで、担当者が疲弊せず、更新が止まらない運用に変わります。
広告コピー|USP抽出・ABテスト・LP改善まで一気通貫で行う方法
広告コピーは「センスの勝負」に見えがちですが、中小企業では担当者が兼務であることが多く、コピーの質が安定せず、改善の方向も定まらないという課題が生まれます。
ChatGPTを活用すると、広告の企画から改善までをひとつの統合プロセスとして扱えるようになります。
① USP(強み)を抽出するところから始めると、コピーがブレない
広告コピーは「何を書くか」より、「どこを軸に書くか」が重要です。
ChatGPTは、以下の情報をもとにUSP(独自の強み)を抽出できます。
- 商品・サービスの特徴
- 競合の訴求軸
- ターゲットの悩み
- 実際の顧客の声
- 他社にはない“感情的価値”
これにより、コピーが毎回バラバラになる問題を防ぎ、訴求軸を一本化できます。
② ターゲット別にコピーを展開する
USPをもとに、ChatGPTはターゲットごとにコピーを作り分けられます。
- 不安型の顧客向けのコピー
- 価値を重視する顧客向け
- とにかく手軽さを求める層
- 初心者向けの安心設計
- 既存顧客向けのアップセル
ターゲットが変われば言葉も変わります。
AIに作り分けさせれば、数分で複数のコピーを比較できるため、試行回数が圧倒的に増えます。
③ ABテスト用の“差分コピー”をまとめて生成
ChatGPTは小さな表現違いだけでなく、訴求軸ごとの異なるコピーを大量に作れます。
例
- 価格訴求
- スピード訴求
- 信頼性訴求
- サービス範囲訴求
- 導入企業数訴求
- ベネフィット訴求
これらを同時に出すことで、ABテストの幅が一気に広がり、勝ちパターンが見つかりやすくなるのがポイント。
④ LP改善案をChatGPTに出させると“盲点”が見つかる
広告の成果はLP(ランディングページ)の質に左右されます。
ChatGPTはLPを読み込ませるだけで、
- 無駄な情報
- 説得力が弱い部分
- 伝わっていないベネフィット
- ターゲットの期待とズレる箇所
- CTAの明確さ
- 配置上のボトルネック
など、改善点をチェックリスト形式で返してくれます。
担当者一人では気づきにくい“盲点”が浮かび上がるのが大きな強みです。
⑤ 広告コピー向けプロンプトテンプレ(実務仕様)
以下は、広告担当者なら必ず持っておきたい型。
USP抽出プロンプト
「以下の情報から、競合と比べて優位性のあるポイントを5つ抽出し、それぞれの“感情的価値”と“機能的価値”に分けて整理してください。」
コピー案生成プロンプト
「抽出したUSPを軸に、ターゲット別に3パターンずつ、短めの広告コピー案を作成してください。
視覚的な強さと読みやすさを優先してください。」
ABテスト案生成プロンプト
「訴求軸を変えた広告コピーを10個作成してください。①信頼性 ②価格 ③スピード ④価値訴求 ⑤悩み特化の5カテゴリで2案ずつ用意してください。」
LP改善プロンプト
「以下のLPを読み込み、ユーザー視点・心理的動線・情報の説得力の観点から、
改善点を15個提示してください。」
広告運用の本質は、“良いコピーを作ること”ではなく、改善し続ける仕組みを作ること。
ChatGPTが、この“改善の回転数”を飛躍的に高めてくれます。
ChatGPTマーケを成功させる“社内運用設計”
ChatGPTを使ってブログやSNSの投稿、広告コピーを作るだけでは、マーケティングは長続きしません。
中小企業で成果が出ている企業には、共通して「運用の仕組み」が存在します。
ここでは、少人数でもマーケティングが回り続けるための“設計図”をまとめます。
① 週次で動く“固定スケジュール”をつくる
まず必要なのは、「誰が・何を・どれくらい」つくるかを固定化することです。
例
- 月:ブログ1本のテーマ決め
- 火:ブログ構成案+下書き
- 水:SNS3本の投稿案作成
- 木:広告コピーの差分案作成
- 金:翌週の投稿スケジュール作り
ChatGPTをこの流れに組み込むと、“思いつき運用”が消え、担当者の負荷が一気に軽くなります。
② 企画→制作→投稿→分析まで“ひとつの流れとしてAIに統合”する
マーケが止まる原因の多くは、作業が分断されること。
例えば、企画担当 → ブログ担当 → SNS担当 → 分析担当のように工程が分かれると、引き継ぎが増え、改善が遅れます。
ChatGPTは、この分断をなくせる存在です。
- 企画案
- 構成案
- 下書き
- SNSへの切り出し
- 広告コピーへの展開
- 改善点の洗い出し
すべてを1つのスレッドで完結できます。
工程が一気通貫になれば、担当者は「判断」と「最終調整」に集中でき、マーケ活動のスピードが上がります。
③ 社内ナレッジを“AIに蓄積する形”で整理する
ChatGPTに読み込ませて運用に使うための、“社内専用のスタイル辞書”を作ると運用が劇的に安定します。
辞書に入れるべき内容は
- 表現ルール(語尾・トーン・NG表現)
- 過去記事・広告の成功パターン
- 使いたい語彙(ブランドワード)
- 使わない語彙(禁止ワード)
- よく使う例文のテンプレ
- ターゲット像
- 自社サービスの特徴(USP)
これを毎回プロンプトに渡せば、「誰が担当しても同じ品質で出せるマーケティング体制」になります。
④ 成果が安定する“成功・失敗ログ”を作る
中小企業では、担当者が変わるとノウハウがゼロになる問題が頻発します。
これを防ぐため、ChatGPTで「成功ログ」と「失敗ログ」を作っておくと効果的です。
- クリック率が上がった投稿の共通点
- 読まれたブログ記事の要素
- 反応が薄かった投稿
- 問い合わせにつながった広告コピー
- うまくいかなかった施策の理由
これらをChatGPTにまとめさせれば、翌月の施策にそのまま活かせる“改善の知恵”になります。
⑤ 情報統制・AIガイドラインをつくり、安心して使える環境を作る
ChatGPTの社内利用で不安なのは、
- 情報漏えい
- プロンプトに入れていい情報の境界
- 不正確な情報の扱い
など、リスク面です。
以下を明確にしておくだけで、社内の不安が大幅に減り、使いやすくなります。
- 入力していい情報/NG情報
- 機密情報の扱い
- 出力内容のチェック基準
- 有料版の利用範囲
- プロンプトの保管ルール
ガイドラインがある=安心して使えるという状態になるため、社内定着が早くなります。
⑥ ChatGPTを“追加のメンバー”として扱う視点を持つ
最も重要なのは、ChatGPTを単なるツールとしてではなく、“社内のもう1人のメンバー”として運用する意識です。
- 企画担当
- コピーライター
- 編集者
- アイデア出しの相棒
- 分析補助
これらの役割をChatGPTが担えるようになると、少人数の会社でも“大きな企業と同じようなマーケ体制”を再現できます。
こうした運用設計を入れることで、
ChatGPTを使ったマーケティングは「続かないもの」から「仕組みで回るもの」に変わります。
ChatGPTマーケティングが定着する組織の特徴
ChatGPTを導入しても、成果が出る企業と続かずに終わる企業にはっきり分かれます。
両者の違いは「担当者のスキル」ではなく、組織としての“構え方”にあります。
中小企業でChatGPTを軸にしたマーケティング運用が定着している企業には、いくつか共通する特徴があります。
① 判断の基準が明確に共有されている
マーケティングは「何を作るか」「どの方向で訴求するか」の判断が曖昧になると一気に迷走します。
定着している組織は、
- ターゲット像
- 伝えたい価値
- 使うべき表現・避ける表現
- どんな投稿を“良い”とするか
などの基準がチーム内で統一されています。ChatGPTはこの基準をプロンプトに組み込むことで、担当者が替わってもアウトプットがブレない仕組みを作れます。
② 属人化せず“型”に沿って動く運用ができている
成功している企業には、必ず“型”があります。
- ブログの作成手順
- SNS投稿のフォーマット
- 広告コピーの作り方
- 改善のフロー
- 週次運用の流れ
この型があると、ChatGPTがそのまま作成工程を補助でき、「人に依存しない運用」=継続できる運用が成立します。
③ ChatGPTのアウトプットを“そのまま使わない文化”がある
AIの文章は滑らかですが、企業の実感や温度感までは反映されません。
成功している企業ほど、
- AIが書いたものの“要点”を抽出して整える
- 自社ならではの視点や事例を後から付け足す
- 誤情報がないか必ずチェックする
という “AI×人の二段構え” を自然に行っています。これにより、AI活用の弱点を最小化できます。
④ 改善がルーチン化され、PDCAが止まらない
ChatGPTは改善点の抽出が得意ですが、それを使い続けるかどうかは組織次第です。
定着している企業には、
- 毎週どこかで改善ミーティングを入れる
- 投稿・記事の振り返りをChatGPTにまとめさせる
- “次はこうする”まで決めて翌週に回す
といった習慣があります。
これは“手間のかかる改善”ではなく、“AIが全部まとめてくれるからこそ可能になった改善文化”です。
⑤ ChatGPTを“作業ツール”ではなく“運用エンジン”として扱う意識がある
成功している企業の共通点は、AIを「文章作成ツール」ではなく、
- アイデア担当
- ライター補助
- 編集者
- 広告の差分案担当
- 分析補助
と、人員の一部として組織に組み込んでいるところです。
この意識の違いこそが、“導入して終わる企業”と“成果に変換できる企業”の決定的な差になります。
ChatGPTは単体では魔法のツールではありません。
しかし、こうした“ ChatGPTが活かされる環境 ”を整えることで、中小企業のマーケティング運用は、驚くほどスムーズに回り始めます。
まとめ|ChatGPTで“動き続けるマーケティング体制”をつくる
中小企業のマーケティングは、人手不足や属人化の影響を受けやすく、ブログ・SNS・広告のどれもが“始めるのは簡単、続けるのは難しい”領域です。
この課題は、担当者の熱意だけでは解決できません。
本記事で見てきたように、ChatGPTを活用すると──
- ブログは構成案〜下書きまで一気通貫で生成される
- SNSは月間ストックを自動化し、ネタ切れから解放される
- 広告コピーはUSP抽出からABテスト案まで短時間で作れる
- 改善の振り返りまでAIが支援し、運用の質が底上げされる
- 属人化せず、誰でも“同じ品質”のマーケが再現できる
つまり、ChatGPTは作業を効率化するツールではなく、“マーケティングを動かし続けるための運用エンジン”になります。
中小企業にとって重要なのは、「人が頑張る」ではなく「仕組みで回す」マーケティング体制を作ること。
この視点をもつだけで、マーケ活動の継続率も成果も大きく変わります。
ChatGPTを組織の中に“仕組みごと”導入できれば、少人数の会社でも、情報発信・集客・改善が自然に循環する状態をつくれます。
中小企業がChatGPTを導入するときによくある疑問(FAQ)
- QChatGPTに詳しくない担当者でも本当に使えますか?
- A
tGPTの利用には専門知識は不要で、最初に使う“型”だけ整えれば、誰でも同じ品質で出力できます。
記事で紹介したように、
- テーマ生成のテンプレ
- 構成案生成テンプレ
- SNS投稿テンプレ
- 広告コピー生成テンプレ
など、必要なプロンプトをあらかじめ揃えておけば、担当者のスキルに依存しない運用が可能です。
- テーマ生成のテンプレ
- QAIに任せると、文章が“それっぽくて浅い”ものになりませんか?
- A
AIの文章には“パターン的な書き方”が出やすいのは事実です。
ただし、それを防ぐ方法があります。- 自社の“スタイル辞書”を読み込ませる
- NG表現・NGトーンを最初に指定する
- 語彙・トーン・文体を社内用に固定する
- 人間が3割だけ仕上げを行う
この4つが揃えば、“AI臭さ”を最小限に抑えた自然な文章が完成します。
- 自社の“スタイル辞書”を読み込ませる
- Q情報漏えいが心配です。どこまでAIに入力していいのでしょうか?
- A
社内で明確な“AI利用ガイドライン”を作れば安心して使えます。
一般的には以下を避ければ問題ありません。
- 個人情報
- 契約情報
- 金額、顧客名、企業秘密
- 公開されていない内部資料
一方で、マーケティングに必要な情報(ターゲット像・サービス概要・実績など)は十分に扱えます。 不安がある場合は、公開情報だけをAIに渡し、社内固有情報は手動で追加する方式が安心です。
- 個人情報
- QChatGPTは無料版でも大丈夫ですか?それとも有料版が必要?
- A
マーケティング運用(ブログ・SNS・広告コピー)の中心で使うなら有料版(GPT-4.1 / GPT-4oクラス)を強く推奨します。
理由
- 情報の正確性が高い
- 構成案の質が圧倒的に違う
- SNS向け短文の自然さが高い
- 長文処理・複数プロンプトの精度が高い
- 書き直しに強い
無料版は簡易的な相談には便利ですが、継続運用にはパワーが不足します。
- 情報の正確性が高い
- Qまず何から導入すればいいですか?
- A
以下の順番で始めるのが最もスムーズです。
- ブログの構成案生成(最も効果が大きい)
- SNS投稿の型づくり(迷いが消える)
- 広告コピーのUSP整理(成果に直結)
- 週次での改善サイクルの構築(止まらなくなる)
この順番で進めると、“AIを使い始めただけで終わる”のではなく、 “仕組みとして定着するマーケティング”になります。
- ブログの構成案生成(最も効果が大きい)