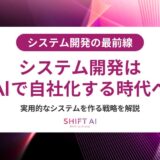中小企業の経理では、請求書の不備チェックや仕訳の相談対応など確認作業に多くの時間がかかるうえに担当者の経験へ依存しやすく、ミスの再発や業務停滞につながることもあります。
また近年では人手不足が深刻化し、業務の標準化と効率化が急務になっています。
こうした課題を解決するのが、ChatGPTの活用です。
ChatGPTは情報整理や抜け漏れの指摘が得意で、定型作業のサポートだけでなく、判断が伴う業務でも候補提示により作業の精度を高められます。
本記事では、経理部門がChatGPTを実務へ取り入れる方法を分かりやすく整理しているので、ぜひ参考にしてください。
- 経理業務のどこにChatGPTが適しているか
- 経理担当者がすぐに使える実務的なプロンプト
- 経理特有のチェック作業(請求書・経費精算・仕訳)を効率化する方法
- ChatGPTと会計ソフト・RPAを組み合わせて半自動化する流れ
- 経理部門にChatGPTを浸透させるための導入手順と標準化の進め方
- AI任せにできない税務判断や情報管理の注意点
- 中小企業の経理でChatGPT活用が進む背景
- ChatGPTで効率化できる経理業務マップ
- 経理担当者が今すぐ使えるChatGPTプロンプト【シーン別】
- 活用例でわかる!ChatGPTを使った経理業務の劇的効率化
- ChatGPTだけでは不十分?会計ソフト・RPAと組み合わせた半自動化設計
- 中小企業の経理にChatGPTを導入する手順
- 経理特有のリスクとAI任せにできない領域の線引き
- ChatGPTを経理に浸透させた企業の共通点
- まとめ:経理のAI活用は標準化と段階的な導入が鍵になる
- 中小企業の経理にChatGPTを導入する際によくある質問
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
中小企業の経理でChatGPT活用が進む背景
経理は定型作業が多く、限られた人数で正確な処理が求められます。
また、人手不足や属人化の課題が目立ち、日々の確認作業にも時間を取られがちです。
この状況に対して、ChatGPTを使うと情報整理やチェック作業を短時間で進められます。
担当者の負担を軽くしながら業務の品質を保てる点が、中小企業の経理でChatGPT活用が進む大きな理由です。
関連記事: 働き方改革が進まない中小企業の課題とは?生成AI活用で実現する改革戦略
ChatGPTで効率化できる経理業務マップ
経理でChatGPTを使うときは、業務を「定型作業」と「判断作業」に分けると適性が分かりやすくなります。
業務ごとにAIがするべき役割が異なるため、整理して理解することが大切です。
定型業務(AIが得意)
定型作業は手順が決まっており、判断の幅が大きくありません。
ChatGPTは情報整理や抜け漏れの指摘を得意としており、経理の作業時間を短くできます。
ここでは、実務で使いやすい領域を整理します。
- 請求書の不備チェック
必須項目の有無や金額の整合性など、ルールが決まっている点をAIが確認できます。人が見落としやすい細かな記載もチェックできるため、作業の安定性が向上します。
- 経費精算の内容確認
申請内容の要約と妥当性の整理を任せられます。経費区分の候補提示にも対応でき、担当者の初期確認の負荷を軽くできます。
- メール文の作成
取引先や社内への連絡文を短時間で作れます。伝えるべき要点を整理したいときにも役立ちます。
- マニュアルやQ&Aの作成
作業手順やよくある質問をまとめるときに効率的です。説明の流れを整えられるため、引き継ぎの負担を軽減できます。
- 書類内容の要約
契約書や申請書の内容を簡潔にまとめる用途で役立ちます。要点を確認する時間を短くでき、判断へ向けた準備が進めやすくなります。
定型作業ではChatGPTの得意領域が多く、日々の確認作業を効率化しやすい点が特徴です。
判断業務(AIが“候補提示”で強力に支援)
判断業務は担当者の知識や経験に左右されやすく、確認に時間がかかる場面があります。
しかし、ChatGPTを取り入れることで数値や状況を整理し、複数の選択肢を示してくれるので判断スピードの向上が期待できます。
最終判断は人が行う必要がありますが、検討材料を素早く揃えられる点が大きな利点です。
- 勘定科目の候補提示
取引内容を入力すると、科目候補と理由が並びます。担当者は妥当性を確認するだけで済み、迷う時間を削減できます。
- 振替や前払計上の判断整理
会計処理の方向性を判断する場面は、担当者によって解釈が揃いにくい場合があります。ChatGPTに取引内容を説明すると、考慮点を含めて候補をまとめられます。
- 税務区分の検討材料
税率や非課税区分に関する整理を任せると、検討が進めやすくなります。複雑な判断は専門家による確認が必要ですが、初期整理として役立ちます。
- 月次レビューの指摘抽出
異常値の傾向や仕訳のばらつきを説明させると、確認項目が明確になります。担当者が見落としやすいパターンも示されるため、締め作業の負担を軽くできます。
判断業務ではChatGPTが整理役として機能し、担当者の検討負荷を下げられる点が重要です。
関連記事:中小企業のChatGPT活用法15選|導入方法から業務別プロンプト例まで徹底解説
経理担当者が今すぐ使えるChatGPTプロンプト【シーン別】
経理は確認作業が多く、手順が固まっている場面が多い領域です。
ChatGPTに送るプロンプト(指示文)を工夫すると、書類チェックや仕訳相談などの業務を短時間で進められます。
ここでは日々の業務へそのまま使える形式で、テーマごとに実務的なプロンプトをまとめたので、参考にしてみてください。
請求書の不備チェックプロンプト
請求書は項目数が多く、抜け漏れが起きやすい書類です。
しかし、ChatGPTへ内容を読み込ませると、必須項目の不足や金額の不整合を短時間で確認できます。
■ 不備チェック(基本)
以下の請求書データをチェックしてください。
不足している項目、金額や税率の不整合、日付の矛盾、担当者が確認すべき点を一覧でまとめてください。
【請求書データ】
(ここにテキストまたはOCR結果を貼り付け)
■ 金額・税率の整合性チェック
請求書の金額・税率・小計・合計が正しく計算されているか確認してください。
計算が合わない場合は、どの数字が原因かを明確に示してください。
■ 取引内容の妥当性チェック
以下の請求内容について、一般的な取引として妥当かどうか判断材料を教えてください。
同種業務の一般的な内容もあわせて整理してください。
【記載内容】
(内容を貼り付け)
請求書のチェック作業はChatGPTと相性が良く、一定の精度を保ちながら短時間で確認できる点が大きな利点です。
仕訳候補生成プロンプト(判断理由つき)
取引内容を入力すると、勘定科目の候補と採用理由が整理されます。
ChatGPTは複数の候補を並べられるため、担当者の判断材料を揃えやすくなります。
■ 基本の仕訳候補生成
以下の取引内容について、仕訳の候補を複数提示してください。
各候補ごとに勘定科目を選ぶ理由と注意点も示してください。
【取引内容】
(内容を貼り付け)
■ 振替・前払・未払の判断整理
次の取引について、前払・未払・振替のどれに該当する可能性があるか整理してください。
それぞれの処理を選ぶ場合の理由と判断材料も示してください。
【取引内容】
(内容を貼り付け)
■ 税区分の判断材料を含めた仕訳案
以下の内容について、仕訳候補とあわせて税区分の候補も提示してください。
消費税の扱いで注意すべき点があれば、判断材料としてまとめてください。
【取引内容】
(内容を貼り付け)
■ 例外処理の可能性チェック
以下の取引に例外的な処理が必要になる可能性がある場合は、そのパターンも整理してください。
一般処理と例外処理の違いも比較できるように提示してください。
【取引内容】
(内容を貼り付け)
仕訳の候補と理由を整理できると、判断の根拠が明確になり、担当者同士の解釈差も小さくできます。
経費精算の妥当性確認プロンプト
経費精算では、領収書の内容や用途の説明が不足している場面が多く、担当者が確認に時間を取られやすくなります。
しかし、ChatGPTへ申請内容を入力すると金額や取引内容の妥当性、社内規程と照らした注意点を短時間で整理できます。
■ 経費内容の要点整理
以下の経費申請について、内容の要点と確認すべきポイントを整理してください。
金額・日付・用途の整合性が取れているかもあわせて確認してください。
【経費申請内容】
(内容を貼り付け)
■ 経費として妥当かどうかの初期判断
次の経費申請について、一般的なビジネス経費として妥当かどうか判断材料を示してください。
確認すべき観点を箇条書きで整理し、妥当性が判断しづらい点も指摘してください。
【申請内容】
(内容を貼り付け)
■ 領収書の不足情報の指摘
以下の領収書情報に不足がある場合は、追加で確認すべき内容を一覧化してください。
用途説明や金額の妥当性に関する指摘も含めて整理してください。
【領収書情報】
(内容を貼り付け)
■ 社内規程との差異チェック
次の経費申請について、一般的な社内規程と比較した場合に注意点があれば整理してください。
判断に迷う部分がある場合は、その理由もまとめてください。
【申請内容】
(内容を貼り付け)
経費精算の確認作業は負荷がかかりやすい領域であり、ChatGPTを使うと初期確認を効率化できる点が大きな利点です。
メール文作成(督促・依頼・確認)プロンプト
経理では取引先や社内への連絡が多く、文面の作成に時間がかかります。
しかし、ChatGPTへ背景や目的を伝えると、要点が整理された文章を短時間で作成できます。
口調や丁寧さの調整でばらつきも抑えられるので、文章作成の負担が軽くなり、確認作業へ集中しやすくなる点が強みです。
■ 請求書再送依頼(取引先向け)
以下の状況に合う請求書再送依頼メールを作成してください。
丁寧な表現で、必要事項が明確に伝わる形にしてください。
【状況】
・請求書が未着
・月末締めの都合で確認を急ぎたい
・添付形式での再送を希望
■ 支払い予定日の確認依頼
次の状況に合う支払い予定日の確認メールを作成してください。
相手に負担をかけない表現で、必要な情報を整理してください。
【状況】
・支払予定日が不明
・月次締めの関係で確認が必要
■ 経費精算に関する追加情報の依頼(社内向け)
以下の経費申請について、担当者へ追加情報を依頼するメール文を作成してください。
不足情報が明確になるように案内してください。
【申請内容】
(内容を貼り付け)
■ 入金遅延に関する丁寧な督促メール
次の状況に合う入金督促メールを作成してください。
強い表現を避け、事務的かつ丁寧な文章にしてください。
【状況】
・入金予定日を過ぎている
・取引継続に支障はない
・確認をお願いしたい
■ 問い合わせへの返答文作成
以下の問い合わせに対する返答メールを作成してください。
必要な情報が明確に伝わるように構成してください。
【問い合わせ内容】
(問い合わせを貼り付け)
メール文は要点整理と表現の調整に時間がかかるため、ChatGPTを活用すると短時間で一定品質の文章を作成できます。
経理マニュアルを高速で作るプロンプト
経理は手順が複雑になりやすく、担当者ごとにやり方がばらつくケースがあります。ChatGPTへ作業内容や目的を伝えると、流れを整理したマニュアルを短時間で作成できるので、引き継ぎや教育の負担を減らせます。
■ 基本のマニュアル作成
以下の作業手順をマニュアル化してください。
新人でも理解しやすい構成で、工程ごとの目的や注意点も記載してください。
【作業内容】
(内容を貼り付け)
■ ステップごとのチェックリスト付きマニュアル
次の作業内容をもとに、ステップごとのチェックリスト付きマニュアルを作成してください。
確認漏れを防ぐために、各工程で見るべき項目も整理してください。
【作業内容】
(内容を貼り付け)
■ 社内向けQ&A形式の手順書
以下の業務について、社内向けのQ&A形式で手順書を作成してください。
よくある質問や注意点も追加してください。
【業務内容】
(内容を貼り付け)
■ トラブル時の対応フローを含むマニュアル
次の業務について、通常手順とあわせてトラブル発生時の対応フローも整理してください。
担当者が迷わないように、判断基準も記載してください。
【業務内容】
(内容を貼り付け)
■ マニュアルの文章を読みやすく再構成
以下のマニュアル文章を読みやすい形に再構成してください。
冗長な表現を整理し、手順の順番が分かる構成にしてください。
【マニュアル原文】
(テキストを貼り付け)
マニュアル作成へChatGPTを活用すると、担当者ごとの手順の差を小さくでき、作業品質を一定に保ちやすくなります。
社内問い合わせ対応テンプレート生成
経理には、経費規程、支払い方法、振込スケジュールなど、社内からの問い合わせが多く寄せられます。
毎回ゼロから説明すると負担が増えやすく、内容の統一も難しくなります。
ChatGPTはよくある質問を整理し、丁寧で分かりやすい回答文を短時間で作成可能です。
■ よくある質問(FAQ)テンプレート生成
経理部門に寄せられる質問への回答テンプレートを作成してください。
短文と長文の2種類を用意し、担当者の負担が軽くなる構成にしてください。
【質問】
(質問を貼り付け)
■ 経費規程の説明テンプレート
以下の経費規程について、社内へ案内するための説明文章を作成してください。
規程の要点と、注意すべき点を簡潔にまとめてください。
【規程内容】
(内容を貼り付け)
■ 支払スケジュールの案内文
次の内容をもとに、支払スケジュールを説明する社内向け文章を作成してください。
担当者が理解しやすいように、項目別で整理してください。
【スケジュール情報】
(内容を貼り付け)
■ 問い合わせ内容の要点整理
以下の問い合わせに対して、担当者が回答を作りやすいように要点を整理してください。
追加で確認した方が良い点があれば、その項目も提示してください。
【問い合わせ内容】
(内容を貼り付け)
■ 回答文の丁寧さ・表現調整
以下の回答文を、社内向けとして丁寧で理解しやすい表現に整えてください。
長さは原文と同程度で構いません。
【回答文】
(回答文を貼り付け)
問い合わせ対応用のテンプレートを整備すると、経理部門全体の応対品質を一定に保ちやすくなり、担当者の作業負荷も削減できます。
活用例でわかる!ChatGPTを使った経理業務の劇的効率化
ここでは、ChatGPTを使って経理業務改善につながったユースケースを紹介し、活用イメージをつかみやすくまとめます。
実際に直面しやすいシーンを取り上げ、ChatGPTがどのように業務を支援できるかを解説するので参考にしてみてください。
請求書チェックで人的見落としが減ったケース
請求書は必須項目の多さから確認負荷が高く、担当者による見落としが起きやすい書類です。
ChatGPTへ項目を読み込ませる運用に切り替えると、確認すべき点が一覧化され、作業のばらつきが抑えられます。
人によって抜けやすい箇所も指摘されるため、作業品質が安定しやすくなります。
仕訳判断のスピードが向上したケース
仕訳は担当者ごとの解釈が分かれやすく、相談対応に時間がかかりがちです。
ChatGPTに取引内容を説明すると複数の科目候補と理由が整理され、担当者は候補の中から妥当な選択肢を判断するだけで済むため、作業時間が短くなります。
さらに経験の差によるスピードの違いも小さくできます。
属人化していたExcel処理が標準化されたケース
経理では担当者ごとにExcelの操作手順が異なり、共有が難しくなる場面があります。
ChatGPTを使い、手順の文章化や関数の整理を進めると、作業手順が明確になります。
マニュアルを整えやすくなるため、引き継ぎがスムーズになり、担当者間の作業品質の均一化が可能です。
ChatGPTだけでは不十分?会計ソフト・RPAと組み合わせた半自動化設計
経理業務は手作業が多く、ChatGPTだけでは完全自動化が難しい場面があります。
会計ソフトやスプレッドシート、RPAと組み合わせると処理が安定し、より作業効率を上げられます。
ここではツール同士の役割を整理し、中小企業でも導入しやすい半自動化の流れをまとめました。
スプレッドシート連携で実現する半自動ワークフロー
スプレッドシートは柔軟に扱えるため、ChatGPTとの相性が良いツールです。
OCRで取得した請求書データや経費明細を表形式へ整理し、ChatGPTへ必要な部分だけ渡すと、仕訳候補やチェック内容を効率よく生成できます。
生成結果をそのままシートへ戻す運用にすると、確認作業が一連の流れで進められます。
担当者に高度なスキルが不要な点も利点です。
Power AutomateやMakeを使った簡易RPAの例
手作業で繰り返す処理は、RPAと組み合わせると自動化しやすいです。
例えば、メールに届いた請求書ファイルを指定フォルダへ保存し、OCR処理を自動実行する仕組みを作るとChatGPTへの入力準備が早くなります。
データの移動や整形をRPAへ任せておくことで、担当者は判断が必要な作業へ集中できます。
会計ソフトとChatGPTの役割分担
会計ソフトは仕訳の登録やレシート読み取りに強く、ChatGPTは改善提案や判断材料の整理に強みがあります。
それぞれ得意領域が異なるため、併用すると効率が上がります。
例えば、会計ソフトへ取り込む前の整理作業をChatGPTへ任せ、仕訳登録の品質を保ちながら作業時間を短くし、会計ソフトの機能を補完する役割として活用するなどです。
中小企業の経理にChatGPTを導入する手順
経理へChatGPTを導入する際は、作業内容を整理し、段階的に取り入れることが重要です。
最初に業務を見える化し、プロンプトを標準化するとスムーズに活用できます。
実務へ浸透するまでの流れを分かりやすく整理します。
ステップ1|経理業務の棚卸し(AI適性の可視化)
最初に業務を分解し、AIを使いやすい領域を把握します。
単純な確認作業や整理作業は導入効果が出やすいため、優先度を高く設定して進めると効率的です。
業務の流れを整理すると、プロンプトを作るときにも役立ちます。
ステップ2|プロンプトの標準化と共有
ChatGPTの活用効果を安定させるには、プロンプトを標準化することが重要です。
担当者が同じ形式で使えるようにテンプレート化すると、作業品質が揃います。
共有フォルダへ保管し、適宜更新すると改善が進めやすくなります。
ステップ3|AIガイドラインの作成(情報漏洩の防止)
経理では機密情報を扱うため、AIへの入力内容の整理が必要です。
外部へ出せない情報をルール化し、利用時の注意点をまとめておくと安心して活用できます。
ガイドラインを作成すると、部門全体で安全に使い続けられます。
ステップ4|RPAや会計ソフトとの連携で半自動化へ進める
ChatGPTとRPAや会計ソフトを組み合わせると、処理の一部が自動化されます。
データの受け渡しや整形を機械へ任せることで、担当者は判断が必要な作業へ集中できます。
ステップ5|経理チームへのAI研修で習熟度を底上げする
活用を部門全体へ広げるには、担当者の習熟度を揃える取り組みが必要です。
基礎的な使い方やプロンプト作成のポイントを共有すると、運用が安定します。
また、研修を通じて改善が継続できる体制を整えると、より業務改革が進みます。
関連記事:中小企業の生成AI社内展開ガイド|全社員が使いこなすための導入ステップとは?
経理特有のリスクとAI任せにできない領域の線引き
経理は機密情報や税務処理を扱うため、ChatGPTの活用には注意が必要です。
確認作業の効率化には役立ちますが、判断をすべて任せることはできません。
安全に活用するにはリスクを理解し、対応すべき手順を整えておく必要があります。
税務判断は必ず人による最終チェックが必要
消費税や法人税の判断は要件が複雑で、ChatGPTが示す案だけでは十分ではありません。税務処理は最終確認を担当者が行い、必要に応じて専門家へ相談する体制が必要です。
AIは判断材料の整理役として活用することが安全です。
個人情報や機密情報の取り扱いルールを明確にする
ChatGPTへ入力する情報は、内容を分類して扱う必要があります。
取引先情報や個人情報をそのまま入力しないように注意し、抽象化や伏せ字を使うことでリスクを下げられます。
無料版ではなくTeamやEnterpriseの利用を検討する理由
無料版は入力内容が学習に利用される可能性があり、経理業務に適しません。
TeamやEnterpriseでは情報が学習へ使われない設定を前提に活用できます。
セキュリティを確保しながら業務へ利用できる点が安心材料になります。
AIの出力をそのまま使わず記録を残す運用を行う
AIの出力内容は参考材料であり、最終的な確認は担当者が行う必要があります。
判断の根拠が分かるようにメモやログを残しておくと、後から内容を振り返りやすくなります。
監査対応の準備にも役立つ運用です。
ChatGPTを経理に浸透させた企業の共通点
経理業務へChatGPTを取り入れる企業は増えていますが、成果が出ている企業には明確な共通点があります。
仕組み作りや改善の進め方が整理されており、担当者が迷わず使える状態を整えています。継続して活用するための基盤が整っている点が成功の大きな要因です。
プロンプト集を部門の資産として管理している
成功している企業は、担当者ごとのプロンプトを集めて整理しています。
用途別にフォルダへ分けたり、注意点を追記したりする運用が定着しています。
全員が同じ形式で使えるため作業品質が揃い、担当者ごとの差も小さくできるので、プロンプトは整理するようにしましょう。
改善ループを回す仕組みがあり運用が安定している
業務へ活用している企業は、使いながら改善する流れができています。
定期的に振り返りを行い、良かったプロンプトや活用例を共有すると効果が高まります。
改善を続けて、運用が自然と定着しやすくするのが重要です。
研修を通じてチーム全体の習熟度を揃えている
担当者ごとに知識の差があると、業務への取り入れ方が不安定になります。
研修を実施し、基礎的な使い方や考え方を揃えると、活用が一気に進みます。
習熟度が揃うと改善の質も高まり、部門としての効率化が進むのです。
関連記事: 中小企業でもできるAIトランスフォーメーション|DXの次に来る“業務改革”の進め方
まとめ:経理のAI活用は標準化と段階的な導入が鍵になる
経理業務は確認作業が多く、担当者の負担が大きくなりやすい領域です。
しかし、ChatGPTを活用すると請求書チェックや仕訳候補の整理を効率化でき、作業品質を一定に保ちやすくなります。
また、定型作業だけでなく判断が伴う作業でも候補を出す役割を担えるため、業務の属人化を抑える効果があります。
ただし、安全に活用するにはガイドラインの作成や、プロンプトの標準化が重要です。
段階的に導入を進めると経理部門の負担が軽くなり、継続的な改善が行いやすくなります。
SHIFT AIでは、AI導入を成功させる手順を解説した資料を無料で提供しているので、ぜひお気軽にダウンロードしてくださいね。
中小企業の経理にChatGPTを導入する際によくある質問
- Q請求書や領収書の内容をそのままChatGPTへ入力しても問題ありませんか?
- A
経理が扱う情報は機密性が高いため、外部へ直接入力する運用は避ける必要があります。伏せ字や抽象化を行うか、ChatGPT TeamやEnterpriseなど情報が学習されない環境で活用する方法が安全です。入力ルールを決めておくと安心して利用できます。
- Q仕訳判断はどこまでAIへ任せられますか?
- A
仕訳候補の提示や考慮すべき観点の整理は任せられます。一方、最終的な勘定科目の選択や税務区分の判断は、担当者が確認したうえで決定する必要があります。AIは判断を補助する役割として使うと精度が上がります。
- Q経理部門でChatGPTを導入する際の注意点は何ですか?
- A
入力情報の管理、AI出力の最終確認、税務判断の線引き、ガイドラインの整備が重要です。特に情報漏洩のリスクを避けるため、入力不可の情報や取り扱いルールを明確にしておく必要があります。安全性を確保しながら活用することが長期的な運用につながります。
- Q補助金を使ってChatGPT導入を進めることはできますか?
- A
ツール導入や業務改善が対象になる補助金があります。申請できる制度は事業内容によって異なるため、制度内容を確認しながら検討する必要があります。
中小企業向けの制度は「中小企業の生産性向上を支援する補助金・助成金制度|種類から申請方法まで」で詳しく解説しています。