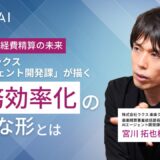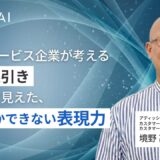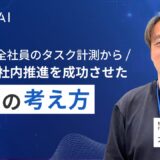「パートナーエージェント」をはじめ婚活事業を展開するタメニー株式会社は、“人と人の出会い”というもっとも人間的な領域にAIを活用してきた企業です。
同社がAIを使う目的は、人間の価値観や相性を客観的に分析し、自然な出会いを後押しするため。その代表的なシステムが、心理学・コミュニケーション学の専門家とともに開発した「EQアセスメント(価値観マッチング)」です。
100問以上の心理テストのような質問に回答することで、自分自身の価値観がデータ化され、AIがそのデータをもとに相性の良い相手を導き出す仕組みとなっています。
今回は広報の平田氏に、長年にわたり自社サービスにAIを組み込んできた同社の歩みと手応えを伺いました。

タメニー株式会社
コーポレート本部 経営企画部
経営企画・IR広報グループ
2016年、株式会社パートナーエージェント(現:タメニー株式会社)に入社。未経験から広報業務を担当し、会社の成長とともに広報体制の立ち上げやメディア対応に携わる。現在は社内外への情報発信を中心に、コミュニケーション活動全般を担っている。AI婚活についても数多くのメディアで取材対応や情報発信を行っている。
※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
15年前からAIを導入──“出会いの質”を高めるための最適解
「昔は、職場や地元のつながりの中で自然に出会って結婚する人が多い時代でした」そう語るのは、タメニー株式会社で広報を担当する平田氏。婚活事業を手がける同社は、社会の変化に歩調を合わせながら、時代に沿った出会いの形を提供してきました。
セクハラやパワハラのリスクがある職場恋愛が敬遠され、女性の都市部進出によって地方の男性余りも増加傾向にある昨今、「結婚を望んでいるのに出会う機会がない」という悩みを抱える方は増える一方です。
同社はこの社会的課題に応えるべく、「いかにして出会いの質を高めるか」という問いに真摯に向き合い、早期からAIの活用を進めてきたのです。
同社がAIを取り入れたのは、「生成AI」や「ChatGPT」という言葉がメジャーになるずっと前のことです。前述のEQアセスメント(価値観マッチング)は15年ほど前に開発されましたが、当時は「AI」や「人工知能」という言葉自体が一般的ではなかったため、サービスにAIを活用していることを売りにはしていませんでした。
転機が訪れたのは2020年。深刻な少子化を背景に政府が婚活支援により力を入れ始め、高度なマッチングシステムが採用された婚活サービスを利用する自治体への補助金制度が整備されていきました。

「2018年頃にAIと婚活に関して発信をはじめました。そのため2020年に、“AI 婚活システム”などとネットで検索すると、当社しか出てこなかったんです。また、すでに多くの自治体様との取り組みもあったので、結果的に、もともと活用していた技術が“AI”というトレンドワードにフィットして、一気に注目を集めました」
AIブームに乗ったというより、時代の流れとうまくタイミングが合ったというのが正確かもしれません。同社のAI活用は、あくまで「サービス向上の最適解」であり、決して流行を追うためのものではありませんでした。
成婚率を高める鍵は、人の経験値とAIの客観性にあり
タメニーが婚活事業を展開するうえで常に意識しているのは「人と人の相性とは何か」という根源的な問いです。

「私たちが提供するEQアセスメント(価値観マッチング)は、心理学・コミュニケーション学の専門家とともに開発したものです。男性、女性ともに、本人の価値観と相手に求める価値観を測定し、それらの掛け合わせによりマッチングしている点が特徴です。一般的には価値観が同じ人の方が相性が良いと言われていますが、たとえばお話好きな女性の場合、同じように話好きな男性が良いという人がいる一方で、話を聞いてくれる男性の方が合うという人もいます。心理学の研究では、自分の価値観と相手に求める価値観は必ずしも一致していないという結果があるんです」
EQアセスメントでは、価値観に関する100個以上の質問に回答してもらい、自身の傾向を深掘りしていきます。こうして得られたデータをAIが分析し、価値観の合う相手を導き出します。
精度を重視すると質問は200個以上設けるのが理想的でしたが、ユーザーである回答者の負荷とのバランスを考慮して質問数を最適化していきました。
婚活業界全体では、主に「条件マッチング」という手法が用いられています。たとえば、相手の条件を「身長170cm以上」「年収500万円以上」と設定すれば、それを満たす相手だけが候補に出てくる仕組みです。一見合理的ですが、ここには見えない“落とし穴”があります。

「条件マッチングでは、ほんの少しでも条件を満たしていないとその相手が候補に出てこないんです。他がすべて理想的でも、その人の身長が169cmだとマッチングしないということです。ですが、AIは過去の膨大なデータを参照し、“条件が完全に一致していなくてもうまくいきそうな例”を見つけ出してくれます」
また、人がマッチングを行うとこれまでの経験に基づいて「このタイプとは合わない」と無意識的に判断してしまうこともありますが、AIの提案によってそうした先入観を覆す成功例も数多く生まれました。
当然、人間にしかわからない機微も大切です。人の経験値とAIの客観性が補い合うことで、成婚率の向上を実現してきました。
成功事例がAI活用の連鎖を生む
AIが活躍するEQアセスメント(価値観マッチング)は、タメニーで働く婚活コンシェルジュにも大きな影響を与えました。

「EQアセスメントが導入された当初は、コンシェルジュによる活用の度合いに個人差がありました。お客様とのコミュニケーションに上手に取り入れるコンシェルジュもいれば、そうでない方もいたのですが、成婚事例が増えるにつれて自然と定着していきました。誰かがAIを使ってうまくいくと、周りも『やってみよう』と動き始める。そうやって広がっていった感じですね」
サービスの提供先である自治体の反応も非常に前向きでした。AIを用いたマッチングサービスは地域からも「最先端の取り組み」として注目され、自治体の評価向上にも繋がっているといいます。
一方で、結婚を望んでいるユーザー本人の反応にも興味深いものがあります。多くのユーザーは手段には固執しておらず、「運命の相手に出会う」という目的を重視しています。自分とマッチングした相手がAIによって選ばれたかどうかは関係ないという考えの方が多数派です。
このようにEQアセスメントが自然に受け入れられている背景には、サービス自体の質の高さがあります。「AIを使っているから」というよりも、「このサービスを使うと良い出会いがある」という信頼を得ていることこそが、同社の最大の強みといえます。
個人の好奇心が組織を動かす──平田氏が実践するAI活用の姿勢
広報担当の平田氏自身もまた、AIを積極的に活用する一人です。

「生成AIの台頭により、広報の在り方も大きく変わりつつあります。最近ではGoogle検索にも『AIモード』が追加されましたよね。AIの進化はSEOをはじめとするマーケティングの観点でも見逃せないと思います。AIを活用できなければ、変化の波に置いていかれてしまうかもしれない…なんて危機感を持っています」
平田氏は、個人的な興味からAIツールを試し、学びを社内へ還元しています。社内のイントラネット上で「こんなAIツールがありました」と共有したり、セミナーで得た知見を発信したりと、積極的に活用の幅を広げています。
AIは企業の成長に欠かせない存在であると同時に、個人のキャリアの共創パートナーでもあります。使い方次第で、発想力を広げ、成果の質を高め、自身の強みを再認識するきっかけにもなります。
平田氏のように、日々の業務の中でAIを学び、試し、共有する姿勢こそが、組織と個人の双方に新たな可能性をもたらしているのです。
タメニーから学ぶ「真似するべき」5つのポイント
タメニー株式会社のAI活用は、婚活という人の感情や価値観が大きく関わる領域で培われてきたものです。
しかし、同社の取り組みの本質は“高度な技術”ではなく、“人を理解して支える仕組みづくり”にあります。多くの企業に通じる再現性の高い実践を、5つのポイントに整理しました。
- AI導入は「課題解決」から始める
同社がAIを活用したのは、トレンドに乗るためではなく、「いかにして出会いの質を高めるか」という明確な課題に応えるためでした。どんな企業であっても、導入目的を“話題性”ではなく“成果の向上”に置くことが、持続的な活用の第一歩です。 - 人の経験値とAIの客観性を組み合わせて意思決定を磨く
AIだけに頼るのでも、人の経験値だけで判断するのでもなく、両者の強みを掛け合わせることが成果を高めます。同社では、人間の経験値とAIの分析を組み合わせることで、より精度の高い意思決定を実現しました。 - ユーザーの体験を最優先に設計する
同社は、心理テストの質問数を“精度”と“負担”の両面から見直し、最適なバランスを探りました。機能の多さよりも、使う人にとって「ちょうどいい」を追求する姿勢が、長く愛されるサービスにつながっています。 - 成功事例を共有し、自然に広がる文化をつくる
誰かがAIを使って成果を上げると、その成功が周囲の行動を変えていく──同社では、そうした“自走する学びの連鎖”が生まれています。無理にルールで縛るのではなく、良い事例が人を動かす仕組みづくりがポイントです。 - AIを「個人の成長の味方」として位置づける
AIは企業の生産性を高めるツールであると同時に、個人の成長を支えるパートナーでもあります。社員が自ら試し、学び、共有する環境を整えることが、組織と個人の双方に新たな価値をもたらします。
もちろん、ここで紹介した取り組みは、タメニーの企業文化や事業特性があってこそ実現できたものでもあります。
重要なのは、「仕組みそのものを真似ること」ではなく、自社の目的や文化に合った形でAIの活用を設計することです。AIを導入すること自体がゴールではなく、社員一人ひとりが自然に使いこなせる環境を整えることが本当の成果につながります。
しかし、実際に自社でこれを実践しようとすると、
「うちの組織に合ったAIの活用方法は?」
「社内に広げるには、どんな人材が必要?」
「成果をどうやって可視化すればいい?」
といった壁に直面する企業も少なくありません。多くの組織が同じ悩みを抱えています。
私たちSHIFT AIは、こうした「導入したが定着しない」という課題解決を得意としています。
貴社の文化や業務内容に合わせた浸透施策の設計から、社員のスキルを底上げする伴走型研修、活用成果を“見える化”する仕組みづくりまで──AI活用の定着に必要なプロセスを一気通貫で支援します。
「AIを導入したのに現場で使われていない」「成果をどう評価すればよいかわからない」──そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。