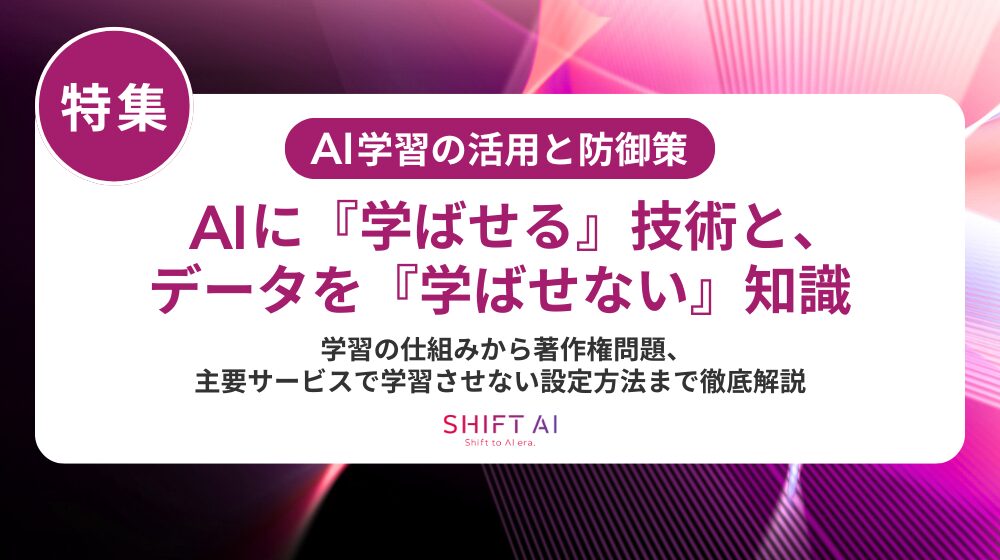「ChatGPTに社内資料を入力したけど、この情報は大丈夫?」「AIが勝手に学習して、うちの機密情報が他社に漏れたらどうしよう…」
そんな不安を抱えている企業担当者の方は多いのではないでしょうか。
実際に、生成AIは初期設定のまま使うと、入力したデータを学習に利用してしまいます。つまり、あなたが入力した顧客情報や企業秘密が、他のユーザーへの回答に使われる可能性があるのです。
しかし「オプトアウト設定」で、AIに学習させないようにできます。
本記事では、主要AIサービスの具体的な設定手順から、企業で実践すべき包括的な対策まで解説します。設定は5分程度で完了するので、読みながら実際に手を動かしてみてください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
AIに学習させない理由|なぜ企業にオプトアウト設定が必要なのか
企業がAIのオプトアウト設定を行う必要がある理由は、入力したデータが無断で学習に利用され、重大な情報漏洩リスクを招く可能性があるからです。
💡関連記事
👉AI学習の基本を徹底解説|仕組み・種類・ビジネス活用まで網羅
機密情報が他社に流出するから
AIに学習されたデータは、他のユーザーへの回答生成に使われてしまいます。
生成AIは、ユーザーが入力した内容をモデルの改善に活用しています。つまり、あなたが入力した顧客リストや新商品の企画書が、競合他社の質問に対する回答として出力される危険性があるのです。
実際に、OpenAIのChatGPTでは、無料版・有料版ともにデフォルト設定でデータが学習に使用されます。Google Geminiも同様で、会話内容がモデルのトレーニングに利用される仕組みです。
このような無断学習を防ぐため、企業はオプトアウト設定を必須で行う必要があります。
法的責任を問われるリスクがあるから
個人情報保護法やGDPRなどの法規制に違反し、企業が損害賠償責任を負う可能性があります。
顧客の個人情報をAIに入力し、それが学習データとして使われた場合、個人情報の第三者提供に該当する恐れがあります。特に、医療機関が患者情報を、金融機関が顧客の資産情報をAIに入力するケースでは、業界固有の規制に抵触するリスクが高まります。
コンプライアンス違反による社会的信用の失墜と、高額な制裁金を避けるためにも、オプトアウト設定は不可欠です。
競争優位性を失う可能性があるから
企業独自のノウハウや戦略がAIを通じて拡散され、競争力の源泉を失ってしまいます。
製造業の技術仕様書や、マーケティング戦略の詳細をAIに入力すると、それらの情報が学習データに組み込まれます。その結果、競合他社が類似の質問をした際に、あなたの企業の機密情報をベースとした回答が提供される可能性があります。
企業の持続的成長を守るため、AIに学習させない設定は経営戦略の一環として位置づけるべきでしょう。
企業でAI学習させない体制を作る方法|社内ガイドライン策定
個人の設定だけでなく、組織全体でAI学習を防ぐ体制構築が必要です。社内ガイドラインの策定から運用まで解説します。
AI利用ポリシーを作成する
入力禁止情報の明確化と、使用可能なAIサービスの限定を盛り込んだポリシーが必要です。
まず、AIに入力してはいけない情報を具体的にリストアップします。顧客の個人情報、財務データ、未発表のプロジェクト情報、技術仕様書などを明文化しましょう。
次に、使用を許可するAIサービスと禁止するサービスを定めます。オプトアウト設定が確実に行えるサービスのみを許可し、設定が困難なサービスは使用禁止とする方針が安全です。
違反時の対応手順や報告ルートも併せて定めることで、インシデント発生時の迅速な対応が可能になります。
利用状況を監査する
定期的な監査により、ガイドライン遵守状況を確認し、必要に応じて改善策を講じます。
IT部門による利用ログの確認や、従業員へのアンケート調査を通じて、実際の運用状況を把握しましょう。特に、オプトアウト設定の実施率や、禁止情報の入力事例がないかを重点的にチェックします。
監査で発見された問題点は、速やかにガイドラインの見直しや追加研修に反映させることが重要です。また、優良事例の共有により、組織全体のリテラシー向上を図りましょう。
四半期ごとの定期監査に加え、重要プロジェクト開始時などの臨時監査も実施することをおすすめします。
従業員に研修を実施する
全従業員がAIのリスクを理解し、正しい設定方法を習得できる研修プログラムが重要です。
研修では、まずAI学習による情報漏洩のリスクを具体例とともに説明します。実際の設定手順をハンズオン形式で練習し、従業員が確実に操作できるようにしましょう。
定期的な理解度チェックやアップデート研修も欠かせません。新しいAIサービスが登場したり、既存サービスの仕様が変更されたりした際は、速やかに追加研修を実施します。
部署ごとに扱う情報の機密度が異なるため、役職や業務内容に応じたカスタマイズ研修も効果的です。
オプトアウト設定の限界とAI学習を完全に防ぐ追加対策
オプトアウト設定だけでは完全にリスクを排除できません。より確実な情報保護のための追加対策を解説します。
設定だけでは情報漏洩は防げない
オプトアウト設定後も、一定期間データがサーバーに保存され、人間による確認が行われる可能性があります。
多くのAIサービスでは、オプトアウト設定を行っても、会話データが24時間から72時間程度サーバーに保存されます。この期間中に不正アクセスが発生するリスクは残存するのです。
また、サービス品質向上のため、一部の会話が人間のレビュアーによって確認される場合があります。この確認用データは通常3年程度保管され、ユーザーが削除することはできません。
さらに、設定ミスや仕様変更により、意図せずデータが学習に使用されてしまう可能性も考慮する必要があります。
技術的なセキュリティ対策を追加する
VPN接続、データ暗号化、アクセス制限などの技術的対策で、多層防御を構築しましょう。
まず、AI利用時のネットワーク環境を制限します。VPN経由でのアクセスを必須とし、社外からの利用を制御することで、通信経路のセキュリティを強化できます。
入力データの事前暗号化や、機密部分の自動マスキング機能を導入することも効果的です。また、特定のユーザーやデバイスからのみAIサービスにアクセス可能にする制限も重要な対策となります。
ログ監視システムにより、異常なデータ入力や大量アクセスを検知し、迅速に対応できる体制も整備しましょう。
プライベートAIツールに切り替える
企業専用のAI環境を構築することで、外部への情報流出リスクを根本的に排除できます。
Microsoft Azure OpenAI ServiceやAWS BedrockなどのエンタープライズAIサービスは、顧客データを学習に使用しない契約になっています。これらのサービスへの移行を検討しましょう。
オンプレミス環境でのAI構築も選択肢の一つです。初期投資は大きくなりますが、完全に自社管理下でAIを運用できるため、最高レベルのセキュリティを実現できます。
クラウドとオンプレミスのハイブリッド構成により、用途に応じて最適な環境を使い分けることも可能です。
業界別AI学習防止の重要ポイント|金融・医療・製造業の対策
業界特有の規制や要求事項に応じた、きめ細かなAI学習防止対策が必要です。主要業界での重要ポイントを解説します。
金融業界は法規制を遵守する
金融商品取引法や銀行法などの厳格な規制要件を満たすAI利用ルールの策定が必要です。
金融機関では、顧客の資産情報や取引履歴などの機密性が極めて高い情報を扱います。これらの情報がAIに学習された場合、金融商品取引法の「顧客情報の適切な管理」義務に違反する可能性があります。
また、マネーロンダリング対策の観点からも、取引パターンの分析結果がAIを通じて外部に漏洩することは避けなければなりません。監督官庁への報告義務や、監査法人による検査にも対応できる管理体制が求められます。
オプトアウト設定に加え、金融専用のAIサービスや完全オンプレミス環境の導入を強く推奨します。
医療業界は患者情報を保護する
医療法や個人情報保護法の特別規定に基づく、患者プライバシーの厳格な保護が必要です。
医療機関では、患者の診療記録や検査結果などの要配慮個人情報を扱います。これらの情報は、患者本人の明示的な同意なしに第三者に提供することが法的に禁止されています。
AIに患者情報を入力し、それが学習データとして使用された場合、実質的な第三者提供に該当する恐れがあります。特に、遺伝子情報や精神的疾患に関する情報は、より慎重な取り扱いが要求されます。
医療AI専用のプラットフォームや、HIPAA準拠のクラウドサービスの利用を検討することが重要です。
製造業は技術情報を守る
特許情報や製造ノウハウなどの知的財産を、競合他社への流出から確実に保護する必要があります。
製造業では、製品の設計図や製造プロセス、品質管理手法などが企業の競争力の源泉となっています。これらの技術情報がAIに学習され、競合他社の質問に対する回答として提供されることは、重大な競争上の不利益をもたらします。
特に、新製品開発や特許出願前の技術情報は、絶対に外部に漏洩させてはいけません。また、サプライチェーン全体での情報管理も重要で、協力会社との間でAI利用に関する取り決めを明確化する必要があります。
技術部門専用のプライベートAI環境の構築や、知財管理システムとの連携を検討しましょう。
まとめ|AIに学習させない設定で企業の機密情報を守ろう
AIに学習させない対策は、現代企業にとって必須のリスク管理です。ChatGPTやGeminiなどの主要サービスでオプトアウト設定を行い、社内ガイドラインを策定することで、機密情報の漏洩リスクを大幅に軽減できます。
ただし、設定だけでは完全にリスクを排除できないため、技術的なセキュリティ対策や業界特有の規制への対応も重要になります。特に金融・医療・製造業では、より厳格な管理体制が求められるでしょう。
最も重要なのは、組織全体でAIのリスクを正しく理解し、継続的に対策を更新していくことです。技術の進歩に合わせて、常に最新の防護策を講じる必要があります。
AIを安全に活用しながら競争優位を築くためには、全社的なリテラシー向上が欠かせません。

AIに学習させない方法に関するよくある質問
- Qオプトアウト設定をしても完全に安全ではないのですか?
- A
オプトアウト設定だけでは完全にリスクを排除できません。 設定後も24時間から72時間程度データがサーバーに保存され、サービス品質向上のため人間のレビュアーによる確認が行われる場合があります。より確実な保護には、VPN接続やデータ暗号化などの追加対策、またはプライベートAI環境の構築が必要です。
- Q無料版と有料版でAI学習の扱いに違いはありますか?
- A
有料版の方が学習に関する制御オプションが充実しています。 ChatGPT Plusでも初期設定では学習が有効ですが、設定変更が可能です。一方、Claude ProやChatGPT Enterpriseでは自動的に学習がオフになります。企業利用では、より安全性の高い有料プランの選択を強く推奨します。
- Q設定を忘れて機密情報を入力してしまった場合はどうすればよいですか?
- A
速やかにIT管理部門に報告し、可能な限りデータ削除を試みてください。 まず該当する会話履歴を削除し、必要に応じてAIサービス提供者のサポートに連絡して状況を説明しましょう。今後の再発防止のため、社内ガイドラインの見直しや追加研修の実施も検討することが重要です。
- Q社内でAI利用を完全に禁止するべきでしょうか?
- A
完全禁止よりも、適切なルールと教育による安全な活用を目指すべきです。 AIは業務効率化や競争力向上に大きく貢献する技術です。オプトアウト設定の徹底、利用ガイドラインの策定、定期的な従業員研修により、リスクを最小化しながらAIのメリットを享受することが可能になります。