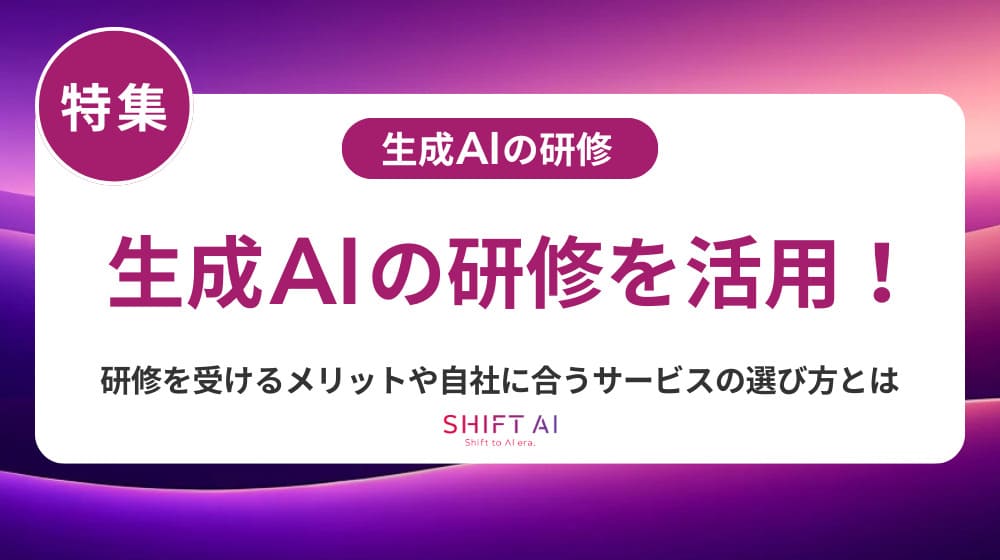「生成AIを社内で活用したいけれど、何から始めればいいのか分からない」
そんな悩みを抱える企業が、今急速に増えています。
ChatGPTやMicrosoft Copilot、そしてGoogleのGeminiなど、生成AIツールは着実に進化を遂げ、誰でも使える環境が整いつつあります。
しかし、それを「業務で使いこなせる人材」がいるかどうかは、まったく別の問題です。
実際、生成AIの活用に踏み出した企業の多くがこう語ります。
「研修を実施したが、現場ではほとんど使われていない」
「一部の推進担当者しか活用しておらず、広がらない」
「情報漏洩や誤用のリスクが気になって、全社展開に踏み切れない」
──これらの課題を解決する鍵となるのが、戦略的な生成AI研修です。
単なる“勉強会”ではなく、実務に根づき、現場が自走する状態をつくる。それが、今求められている研修の姿です。
本記事では、
- なぜ今、生成AI研修が必要なのか
- どのような種類があるのか
- 失敗しないための選び方や導入ステップ
を徹底的に解説します。
さらに、研修を「やって終わり」にしないための仕組みや成功事例にも触れていきます。
✅「検討はしているが、まだ一歩を踏み出せていない」
✅「どの研修会社を選べばよいか迷っている」
✅「研修後の定着・展開まで考えたい」
そんな方にこそ読んでいただきたい内容です。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今、生成AI研修が必要なのか?
かつては一部のエンジニアやデータサイエンティストが扱う専門技術だったAI。
しかし、ChatGPTやCopilot、Geminiといった生成AIの登場により、誰もが自然言語でAIを扱える時代が到来しました。
実際に多くの企業で、「情報収集の自動化」「議事録の作成」「業務マニュアルの要約」「資料の下書き生成」といった用途で、生成AIが日常業務に活用され始めています。
ではなぜ、今「研修」という形での取り組みが求められているのでしょうか?
1. “使える人”と“使えない人”の差が広がっている
生成AIの最大の特長は、「誰でも使えること」。
一方で、業務で成果を出せるほど“使いこなせる人”はごく一部に限られています。
- ツールの活用方法を知らない
- 誤った使い方でリスクを生む
- 活用できる業務が思いつかない
こうした“使えない層”を放置すると、社内の生産性格差・情報格差が広がり、組織の分断すら生みかねません。
2. 誤用・情報漏洩などの“リスク”に気づいていない層も存在
生成AIは便利な反面、以下のようなリスクも存在します。
- 顧客情報や機密情報の誤入力による情報漏洩
- 不適切な回答をそのまま使ってしまう“信頼性”の問題
- 誤った使い方で社外への影響が出るリスク
このようなリスクを“知らないまま使っている社員”がいる状態こそ、最も危険です。
そのためにも、最低限のリテラシー教育はすべての企業に必要不可欠となっています。
3. 全社展開の足場をつくる“共通言語”としての研修の役割
生成AIの活用を全社に広げていくには、共通の前提知識や使い方の型が必要です。
研修を通じて、
- AI活用に対する社内理解を統一する
- 成果の出し方やプロンプト設計の基本を共有する
- 情報管理のガイドラインを浸透させる
といったベースを整えておくことが、その後のスムーズな展開や自走に直結します。
生成AIは、個人で使うだけなら“ツール”ですが、組織で使えば“競争優位をつくる戦略資産”になります。
その第一歩が、全社的な研修を通じた基盤づくりなのです。
生成AI研修にはどんな種類がある?
一口に「生成AI研修」といっても、その内容や目的はさまざまです。
業務で成果を出すためには、単にツールの使い方を学ぶだけでなく、「誰が、何のために、どう使うか」に合わせて設計された研修が求められます。
ここでは、代表的な研修の種類を目的別に整理します。
1. AIリテラシー研修(全社向けの基礎教育)
- 対象者:全社員(非エンジニア・非IT部門含む)
- 主な内容:
- AIとは何か(機械学習・生成AIの基礎)
- ChatGPT・Copilot・Geminiなどの特徴と使い方の違い
- 情報漏洩・ガバナンス・社内ルールの整備
- 目的:
- AIに対する不安の解消
- 社内での“最低限の安心感”を作る
⚠️ 初心者向けながら、社内展開の「土台」となる重要な研修です。
2. ツール操作研修(生成AIを“実際に使ってみる”研修)
- 対象者:情報システム部門/実務部門の担当者
- 主な内容:
- ChatGPTのプロンプト活用法
- Microsoft CopilotでのExcel・PowerPoint支援活用
- Google Geminiのマルチモーダル入力やチーム業務での使いどころ
- 目的:
- 実務での活用シーンを体感させる
- 部門ごとのPoCを支援する人材の育成
📌 “触って終わり”ではなく、業務適用までを視野に入れるのがポイントです。
3. 業務活用研修(PoCを見据えた実践型研修)
- 対象者:営業/人事/管理部門などの業務担当者
- 主な内容:
- 業務フローの洗い出しとAI適用可能箇所の特定
- 部門別プロンプト設計ワークショップ
- 成果検証のためのKPI設計とPoC計画づくり
- 目的:
- 現場の業務に即した“使いどころ”の発見
- 自走的な業務改善の仕組み構築
💡 “研修がそのまま業務改善の起点になる”設計が理想です。
4. 推進人材向け研修(全社展開を担うキーパーソン育成)
- 対象者:情シス/DX推進室/経営企画部門など
- 主な内容:
- 社内ルール整備のポイント
- 部門横断の体制構築法
- 利用促進のための“共有文化”づくり(Slack/Notion活用など)
- 目的:
- 生成AIを全社レベルに定着させる体制構築
- 「使う人を増やす仕組み」の設計者を育てる
🏁 単発ではなく“社内浸透を支える人材”をつくることがゴール
複数の研修を組み合わせる「カスタム設計」が主流に
導入フェーズや職種によって必要な研修は異なるため、近年では対象者・目的別に研修を組み合わせるカスタマイズ型が主流になっています。
📘 どんな組み合わせが効果的かを知りたい方は、以下のホワイトペーパーもご参考ください。
よくある失敗パターンとその対策
生成AI研修を導入したものの、現場でうまく活用されていない・成果につながっていないという声も少なくありません。
その多くは、研修設計や導入プロセスに原因があります。
ここでは、企業が陥りがちな失敗パターンと、その対策を紹介します。
❌ 失敗1:“1回きりの研修”で終わってしまう
ありがちな状況:「全社員向けに研修を1回実施したものの、その後は何もフォローがない」
- インプットだけで終わり、現場での活用に結びつかない
- 時間が経つほどに記憶が薄れ、形骸化していく
✅ 対策:継続的なフォロー体制の構築(Slack相談窓口など)
研修後に「業務で使ってみて分からないこと」を気軽に相談できる環境を用意しましょう。
社内ナレッジの共有・蓄積も、定着には不可欠です。
❌ 失敗2:業務とのつながりが薄い“汎用的な内容”
ありがちな状況:「AIの歴史や生成技術の仕組みは学んだが、明日からの仕事に活かせる気がしない」
- 現場が“自分ごと”として捉えられない
- 学んだことをどこで使えばいいか分からない
✅ 対策:部門ごとの業務課題に即したカリキュラム設計
たとえば営業部であれば、「提案資料の自動生成」「商談準備のプロンプト設計」など、リアルな業務に落とし込んだ演習を入れることで、学びが定着します。
❌ 失敗3:活用が“一部の推進担当者”にとどまる
ありがちな状況:「情報システム部やDX推進室だけが使っていて、現場に広がらない」
- 全社浸透せず“部分導入”で止まる
- 「あれって情シスの取り組みだよね」で終わってしまう
✅ 対策:部門横断のプロジェクト体制 × 自走支援の文化づくり
- 各部門に“AIチャンピオン”を設けて推進役を配置
- SlackやNotionで活用事例・Tipsを共有
- 毎月の活用報告やベストプロンプト共有などを制度化
❌ 失敗4:KPIが曖昧で成果が評価されない
ありがちな状況:「研修後にどう評価すればいいのか分からず、経営層に報告できない」
- 投資効果が不明確で“研修=コスト”扱いに
- 次回以降の予算化・展開が難航
✅ 対策:事前に“定量+定性”の評価指標を設計しておく
- 利用者数・活用件数・改善された業務時間などの数値
- 社内サーベイによる“リテラシー実感”の把握
- 部門ごとのPoC成果を共有する場づくり
実際に生成AIを社内で定着させている企業では、社内研修を起点に文化や行動を変える仕組みを設けています。
たとえばみらいワークスでは、新卒社員が生成AIを使いこなすことで、先輩社員と対等以上に働ける組織文化が育ち始めています。
📘 参考資料あり!
実際に生成AI活用を社内に定着させた企業に共通する取り組みを、以下にまとめています。
【無料資料】なぜ?AIが社内で使われない本当の理由ツールを導入しただけではAI活用は進みません。2,500社の支援で見えた、成功企業に共通する「3つの秘訣」をまとめた資料で、貴社の次の打ち手を見つけませんか?
▶︎ 詳しい内容を確認する!
生成AI研修の選び方【比較ポイント付き】
生成AI研修を提供する会社は年々増えていますが、価格や知名度だけで選ぶと失敗のもとです。
重要なのは、「自社にとって成果が出る設計がなされているか」。
ここでは、研修を比較・選定する際に見るべき5つの評価ポイントを紹介します。
✅ 比較のための5つの観点
| 比較軸 | 確認ポイント | 自社での重要度 |
| 対象別カリキュラム | 部門・役職・リテラシーごとにカスタマイズ可能か | □ 高 □ 中 □ 低 |
| 実務接続度 | ただの座学ではなく、業務に落とし込めるか | □ 高 □ 中 □ 低 |
| 導入後のフォロー体制 | Slack相談・PoC支援・継続学習の仕組みがあるか | □ 高 □ 中 □ 低 |
| 導入実績と業種対応 | 同業・同規模企業での導入事例があるか | □ 高 □ 中 □ 低 |
| セキュリティ・ガバナンス対応 | 利用ルール、ポリシー整備支援などに対応しているか | □ 高 □ 中 □ 低 |
単発研修だけで終わるか、定着まで設計されているか
導入初期にありがちな失敗は、「とりあえず研修だけやる」というケース。
それでは、現場は何も変わりません。
研修選びの際には、次のような視点で問い直してみましょう:
- この研修は、研修後に“社内で何が起きること”をゴールにしているか?
- 実際に成果を出す企業は、どんな支援を受けているか?
📘 参考資料あり!
2,500社の支援から厳選した、17社の導入成功事例をまとめています。実際に効果が出た企業の「選定軸」「活用ポイント」をご覧ください。
導入前に整理しておくべきこと【チェックリスト】
研修会社を選定する前に、自社の状況や目的をしっかり整理できているかどうかが、研修の成果を左右する最大の要因です。
「どれにするか」よりも先に、「なぜ、何のために行うのか」を明確にしましょう。
以下のチェックリストを活用し、自社の現状と目的を可視化してみてください。
✅ 生成AI研修 導入前チェックリスト
| 項目 | 確認ポイント |
| 目的は明確か? | リテラシー向上/PoC支援/定着支援など、何をゴールとするかを定めているか |
| 対象者は誰か? | 部門単位/職種別/リテラシー階層別など、研修対象の絞り込みができているか |
| 研修対象ツールは? | ChatGPT/Copilot/Geminiなど、自社で活用したいツールに研修が対応しているか |
| 研修後の活用イメージは? | 学んだ内容をどう現場に落とし込み、どのような業務改善につなげるか |
| KPIは設計済みか? | 研修の成果をどう測るか(定量・定性)の指標が明確になっているか |
| 社内フォロー体制の準備は? | 研修後の相談窓口やナレッジ共有、活用促進の仕組みは想定できているか |
このチェックリストをもとに設計を行うことで、「とりあえずやってみる研修」から「定着させる研修」への一歩が踏み出せます。
📘 関連記事:
生成AI研修が定着しない企業の特徴と対策は、以下の記事でも詳しく解説しています。
👉 定着しない研修の特徴とは?忘れられる前提で設計しているか
📘 さらに実践的に設計したい方へ:
生成AI活用を5段階で戦略的に設計するための手順をまとめたホワイトペーパーをご用意しています。
👉 生成AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ5段階を読む
導入成功に向けた“仕組みづくり”とは?
生成AI研修は「やって終わり」では意味がありません。
むしろ本質的には、研修後に“どのように活用が広がり、定着するか”の仕組みこそが成果の鍵になります。
ここでは、研修効果を最大化し、全社展開まで見据えた“仕組みづくり”のポイントをご紹介します。
1. 社内に「相談できる場」をつくる
現場の誰もが最初からAIを使いこなせるわけではありません。
最も効果的なのは、研修後すぐに“相談・共有の場”を社内に設けることです。
- Slack上に「AI活用相談」チャンネルを開設
- 日々の活用Tipsや成功例を共有
- 分からないことはすぐに聞ける雰囲気づくり
この仕組みが“実践→疑問→相談→再実践”という活用サイクルを生み出します。
2. 社内ナレッジを集約し、再利用可能にする
活用ノウハウを属人化させず、組織の資産として蓄積することも不可欠です。
- Notionや社内Wikiに“プロンプト事例集”を蓄積
- 部門ごとのPoC成果をテンプレ化
- 新たな活用方法をリストアップして汎用展開
成果や知見が「見える化」されることで、後続のメンバーも使いやすくなります。
3. 文化として“活用が当たり前”になる空気をつくる
最終的なゴールは、「AIを使っている人が目立つ」のではなく、“使っていないと遅れている”という空気を醸成することです。
- 毎月“生成AI活用報告”を発表(部門単位でもOK)
- 成果が出たPoCを表彰する制度設計
- 管理職が率先して活用していることを社内に発信
AI活用を「新しいスキル」ではなく「標準スキル」として位置づけることが大切です。
4. 定着と成果を評価できる“見える化”の仕組み
経営層や他部門を巻き込むには、KPIや成果指標が必要です。
- 利用率(部署ごとの利用人数やツール使用頻度)
- 定性評価(業務改善の体感/現場の声)
- 業務改善インパクト(例:資料作成工数が30%削減)
- 社内サーベイによる活用実感の定期把握
このような「成果の可視化」が、次年度以降の研修予算確保や社内展開の鍵になります。
「研修から成果へ」を実現するには、伴走支援も視野に
SHIFT AIでは、こうした仕組みの整備も含め、“生成AI活用を組織に根づかせる支援”を行っています。
「研修で終わらせない」「業務変革につなげたい」とお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
❓ FAQ|よくある質問
- Q生成AI研修は全社員に必要ですか?
- A
はい、特にAIリテラシーに関する基礎研修は、全社員向けに実施することを推奨しています。特定の部門や職種だけでなく、誰もが生成AIを使える環境になりつつある今、「誤用を防ぐ」「社内ガバナンスを徹底する」ためにも全社での理解統一が不可欠です。
- Q実務に直結するような研修は可能ですか?
- A
可能です。部門別・業務別に設計された研修では、実際の業務に落とし込める内容(例:営業資料の自動作成、人事通知文の生成など)を扱います。
PoC(試行導入)を組み込んだ研修設計も可能です。
- Qリモート環境でも実施できますか?
- A
はい、オンライン・オフライン・ハイブリッド形式いずれも対応可能です。
複数拠点がある企業様でも、柔軟な開催方法をご提案できます。
- Qどのツール(ChatGPT/Copilot/Gemini)に対応していますか?
- A
SHIFT AIが提供する研修では、主要な生成AIツール(ChatGPT/Microsoft Copilot/Google Gemini)にすべて対応しています。
自社で利用中または今後導入を検討しているツールに合わせた内容にカスタマイズ可能です。
生成AI研修は「始まり」であり、「組織変革の第一歩」
生成AI研修は、ただの教育施策ではありません。
社員一人ひとりが生成AIを“使える人材”になり、組織全体で成果を出していくための土台づくりです。
- 使いこなせる人と使えない人の差をなくす
- 現場の業務に根ざした活用を実現する
- 社内に相談と共有の仕組みをつくる
- 成果を可視化して“継続投資できる状態”を生む
こうした流れを実現するには、単なる座学型の研修では不十分です。
目的設計・カリキュラム・体制支援まで含めた“戦略的な導入”こそが鍵になります。
そして、すでに多くの企業が、生成AI活用を“全社戦略”として展開し始めています。
- 丸紅:90万時間の業務削減に成功。現場主導で活用文化を醸成
- LINEヤフー:全社員活用を義務化し、生産性2倍を目指す取り組みを展開中
👉 丸紅の全社展開施策を読む
👉 LINEヤフーの制度設計とKPI設計を読む
生成AI研修について、まずは相談してみませんか?
SHIFT AIでは、
✅ 各社に合わせたカスタマイズ研修
✅ 社内定着を支援するフォロー体制
✅ 成果創出につながるPoC支援・人材育成 など
“やって終わり”ではない、成果志向の研修サービスをご提供しています。