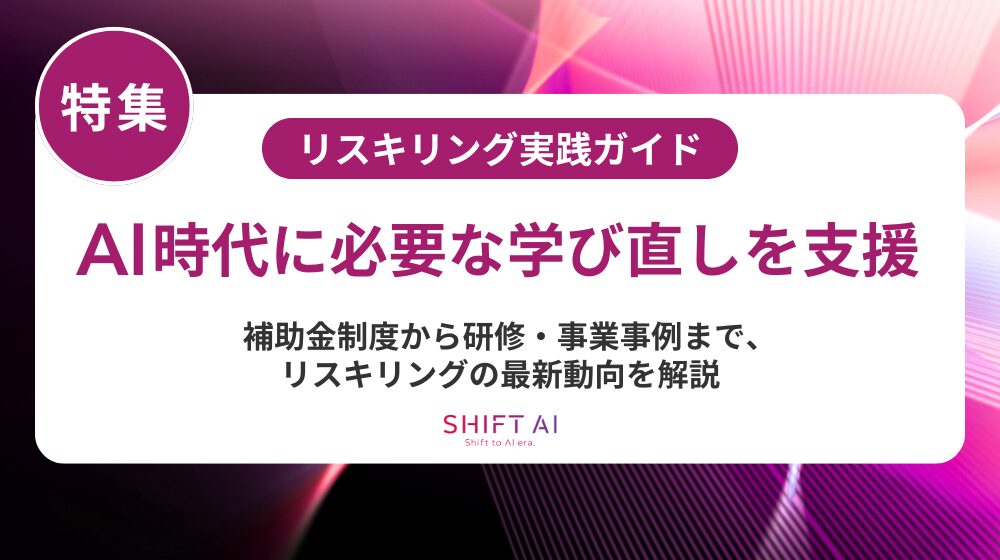DXや生成AIの普及により、社会人に求められるスキルは急速に変化しています。
こうした中で注目されているのが「リスキリング支援」です。
政府は「人への投資」を成長戦略の柱に掲げ、厚生労働省や経済産業省を中心に補助金や助成金を拡充。さらに自治体や企業も独自の取り組みを進めています。
しかし制度の種類が多く、「どれを使えるのか?」「自社や自分に適した支援はどれか?」 と迷う人も少なくありません。
本記事では、国・自治体・企業のリスキリング支援制度を2025年最新情報として整理し、比較表や事例を交えてわかりやすく解説します。
支援を上手に活用することで、学び直しにかかる費用や負担を大幅に軽減できます。
リスキリングそのものの意味や背景について知りたい方は、リスキリングとは?意味・背景・企業導入のメリットと成功ポイントを徹底解説 もあわせてご覧ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜリスキリングに支援が必要なのか
リスキリングが「個人や企業の努力」だけではなく、国や自治体から強力に支援されているのには理由があります。
社会や産業の変化が加速する中で、スキルの陳腐化や人材不足といった課題が深刻化しているからです。
ここでは、その背景を3つの視点から整理してみましょう。
DX・AIでスキルの陳腐化が加速
デジタル化や生成AIの普及により、これまでのスキルが短期間で通用しなくなるケースが増えています。
たとえば事務作業や情報整理などはAIが代替できるようになり、人材にはより高度なデータ活用力や企画力が求められるようになっています。
このような スキルの急速な陳腐化 が、リスキリングを「待ったなし」の課題にしています。
少子高齢化と人材不足 → 政府が「人への投資」を成長戦略に据える背景
日本では少子高齢化に伴い労働人口が減少し、企業は「限られた人材で成果を上げる」ことを迫られています。
こうした状況を受け、政府は労働市場の競争力を高めるために 「人への投資」=リスキリング支援 を成長戦略の柱に掲げています。
企業だけでなく、個人が主体的にキャリア形成を行うことも国の重要課題と位置付けられています。
補助金・助成金が企業や個人の負担を軽減する役割
とはいえ、リスキリングには受講料や人件費などのコストが発生します。
ここで活用できるのが補助金や助成金です。制度を利用すれば、研修費や受講料の一部が支給され、費用負担を抑えながら学び直しを実現できます。
リスキリングの基本的な意味や背景については、リスキリングとは?意味・背景・企業導入のメリットと成功ポイントを徹底解説 で詳しく紹介しています。
国のリスキリング支援制度【2025年版】
リスキリングに取り組む際、まず押さえておきたいのが国による代表的な支援制度です。
ここでは、企業・個人の双方が活用できる主要制度を整理し、助成率や対象の違いを比較します。
厚労省「人材開発支援助成金」
- 企業が社員向けに実施する研修を支援
- 研修経費の一部+受講中の賃金の一部を助成
- DX・生成AI・デジタル分野の研修も対象
- 中小企業の方が助成率が高い傾向
「業務直結のスキル習得」に最も活用しやすい制度
経産省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」
- 個人が直接利用可能な制度(企業利用も可)
- 生成AIやDX関連講座など、時代に即した研修が対象
- 受講料の一部を補助
- 転職・キャリアチェンジを目指す個人にも対応
「企業主導」ではなく「個人主導」のリスキリングを後押しする制度
教育訓練給付金制度
- 雇用保険加入者を対象に、個人の学び直し費用を支援
- 大学院・専門学校・資格取得などの長期的な学習に利用可能
- 給付率は最大70%(条件による)
- リスキリングというよりも「リカレント教育」に直結
個人が主体的に学び直しをしたい場合に有効
制度ごとの比較表
| 制度名 | 主体 | 対象 | 助成率・給付率 | 特徴 |
| 人材開発支援助成金(厚労省) | 企業 | 社員研修 | 経費・賃金の一部助成(中小優遇) | DX・AI研修に強い |
| キャリアアップ支援事業(経産省) | 個人・企業 | 個人受講+企業研修 | 講座受講料の一部補助 | 生成AI・DX講座が対象 |
| 教育訓練給付金制度 | 個人 | 社会人全般 | 最大70%給付 | 大学院・資格など長期学習に対応 |
制度ごとに対象や助成内容が異なるため、「企業主導でDX研修を進めたいのか」「個人主導でキャリアアップを目指すのか」 に応じて使い分けることがポイントです。
自治体のリスキリング支援策
国の制度に加えて、自治体独自のリスキリング支援も拡充しています。
地域産業や人材ニーズに合わせた制度が多いため、自社や自分の所在地に応じてチェックすることが重要です。
東京都:デジタル人材育成助成
- 都内企業を対象に、デジタルスキル習得研修の受講費用を助成
- DX推進に直結するプログラムを支援対象としており、生成AIやクラウドサービス関連も対象になるケースあり
- 中小企業が利用しやすい設計になっているのが特徴
大阪府:地域産業に即したリスキリング研修支援
- 製造業やサービス業など、地場産業のニーズに合わせた研修支援を実施
- IoTやAI活用スキル、現場改善につながるデジタル研修が多い
- 府内の教育機関や民間スクールと連携した取り組みが進んでいる
その他地域:自治体ごとに制度が異なる
- 各自治体が独自に設ける支援制度は多様
- 例:福岡市のITスキル育成補助、愛知県の次世代産業人材育成事業など
- 自治体サイトや商工会議所での最新情報確認が必須
自治体の支援は「地域密着」であることが最大の強みです。
国の補助金と組み合わせて活用すれば、費用負担をさらに抑えた学び直しが可能になります。
企業によるリスキリング支援の動き
国や自治体の制度に加えて、企業自身によるリスキリング支援も加速しています。特に大手企業では福利厚生制度を活用し、社員のキャリア形成を後押しする事例が増えています。
大手企業の福利厚生での学習支援
- 例:IT企業が社員のオンライン学習サービス受講料を補助
- 外資系企業が社内eラーニングプラットフォームを全社員に提供
- 自発的な学習を促しつつ、会社の戦略に沿ったスキル習得を支援
企業研修と補助金制度を組み合わせた導入事例
- ある製造業では、厚労省の人材開発支援助成金を活用しながらAI研修を導入
- 社員の賃金助成も受けられるため、費用を抑えて全社的なスキル転換を実現
- 制度を組み合わせることで、企業単独では難しい取り組みを可能にしている
中小企業の課題と解決策
- 課題:研修費用の確保が難しい、講師や教材のノウハウ不足
- 解決策:
- 外部研修やeラーニングを活用してコストを抑える
- 国や自治体の補助金制度を積極的に組み合わせる
- 例:中小企業が「IT導入補助金」を利用してSaaS型学習ツールを導入し、低コストで全社展開に成功
大手と中小企業でアプローチは異なりますが、共通するのは「外部リソースや制度を活用して費用を抑えることが成功のカギ」という点です。
生成AIとリスキリング支援の最新動向
政府が生成AIリテラシーを重点支援分野に指定
2024年以降、政府はDX人材育成に加えて生成AIリテラシーの習得を重点政策に位置づけています。
「誰もがAIを適切に活用できること」が競争力強化に直結するとされ、補助金や助成金の対象分野にもAI関連研修が多く含まれるようになりました。
生成AI研修が補助金対象になるケースが拡大
- 厚労省「人材開発支援助成金」でも、生成AIを活用した業務改善研修が対象に
- 経産省「キャリアアップ支援事業」では、AI活用講座の受講費用が補助されるケースが増加
- 今後はAIスキルが「標準的なリスキリング領域」として位置づけられる見込みです
AI経営総合研究所ならではの視点:生成AIを活用した学習効率化・研修設計
生成AIは「学ぶ対象」だけでなく「学び方そのもの」を変えています。
- AIコーチによる個別最適化された学習指導
- AI教材生成による効率的なカリキュラム設計
- スキル習得状況の自動評価
これにより、従来よりも短期間・低コストでのリスキリングが可能になります。
AI経営総合研究所では、補助金対象となる生成AI研修プログラムを通じて、企業と個人の学び直しを実践的に支援しています。
支援制度を活用する流れ【図解フローチャート】
補助金や助成金を活用する際は、制度ごとに細かなルールがあるものの、基本的な流れは共通しています。
ここでは代表的なステップを整理し、申請時に注意すべきポイントも補足します。
Step1:対象制度を選ぶ
- 自社や個人の状況に合う制度を選択
- 「企業主導の研修」なら厚労省の人材開発支援助成金
- 「個人で学び直し」なら経産省キャリアアップ支援事業や教育訓練給付金が有力
Step2:研修計画・見積書を用意
- 研修内容、対象人数、期間を明記した計画書を作成
- 見積書やカリキュラム資料を添付するケースが多い
- 計画と実施が乖離しないよう、現実的な内容にすることが重要
Step3:申請・審査
- 所定の申請書を提出(オンライン申請対応の制度も増加)
- 不備があると差し戻されるため、提出前のダブルチェックが必須
- 申請期限は制度ごとに異なるため、スケジュール管理が重要
Step4:研修実施・実績報告
- 研修を実施後、成果や受講状況を報告
- 受講記録、請求書、領収書などのエビデンス資料を添付する必要あり
- 実績報告が不十分だと助成金が不支給になるリスクがある
ポイント: 支援制度は「計画通りに実施 → 証拠を残す」ことが最大の注意点です。
図解フローチャートを添えることで、読者が手順を直感的に理解できるようになります。
よくある失敗と注意点
補助金や助成金の申請は、多くの企業や個人にとって初めての経験です。
そのため、ちょっとした不備や計画ミスが原因で「不採択」になってしまうことも少なくありません。
ここでは、よくある失敗例とその対策を紹介します。
要件を満たさず不採択になる
失敗例
- 研修内容が制度の対象外だった
- 対象となる従業員の雇用形態が条件に合わなかった
対策
- 制度ごとの「対象スキル」「対象従業員」を事前に確認する
- 不明点は必ず事務局や自治体に問い合わせてから申請する
申請期限を過ぎる/書類不備
失敗例
- 締切直前に申請しようとして不備に気づき、間に合わなかった
- 添付書類の押印漏れ・記入漏れ
対策
- スケジュールを逆算し、最低でも2週間前に書類を完成させる
- ダブルチェック体制を敷き、必ず第三者に確認してもらう
実施計画と実績が乖離する
失敗例
- 計画した受講人数に満たなかった
- 実際の研修内容が計画と異なり、助成金が支給されなかった
対策
- 初めから「実現可能な計画」を立てる
- 研修内容に変更が生じた場合は、速やかに事務局へ相談する
まとめポイント
制度を活用するうえで一番大切なのは「要件の確認」「期限管理」「計画と実績の一致」。
事前準備と丁寧な運用が、支援制度を確実に活かすカギになります。
まとめ|支援を活用してリスキリングを加速する
リスキリングは、もはや一部の先進企業だけの取り組みではありません。
DX・生成AIの普及や人材不足の中で、あらゆる企業や個人にとって不可欠な戦略となっています。
その一方で、研修には時間や費用といった負担も伴います。
だからこそ、国の補助金・助成金、自治体の制度、さらには企業自身の支援策を組み合わせることで、コストを抑えながら効果的に進めることが可能です。
重要なのは、常に最新の制度情報を確認し、自社や自身のキャリアに合った最適な学び直しを選択すること。
支援を上手に活用すれば、学び直しのハードルは大きく下がり、結果としてキャリアや組織の成長を加速できます。
- Qリスキリングとリカレント教育の違いは何ですか?
- A
リスキリングは「新しい職務や業務への対応」を目的としたスキル再習得で、企業主導が多いのが特徴です。
一方、リカレント教育は「生涯学習」を意味し、個人が主体的にキャリアを広げるために行うケースが一般的です。
詳しくは リスキリングとは?意味・背景・企業導入のメリットと成功ポイント で解説しています。
- Q補助金・助成金はどんな企業でも利用できますか?
- A
中小企業向けの優遇制度が多いですが、大企業も対象となる制度があります。
ただし、対象となる研修分野や雇用形態に制限があるため、制度ごとの要件を確認することが必要です。
- Q個人でもリスキリング支援を受けられますか?
- A
受けられます。
経産省の「キャリアアップ支援事業」や、厚労省の「教育訓練給付金制度」は個人が利用できる代表的な制度です。社会人大学院や資格取得の費用に使える場合もあります。
- Q申請手続きは難しいですか?
- A
書類の準備や期限管理に注意が必要ですが、流れ自体はシンプルです。
フローチャートで整理すると「制度選択 → 計画書・見積作成 → 申請・審査 → 研修実施・報告」という4ステップになります。
不安があれば、外部コンサルや専門機関のサポートを受けるのも有効です。
- Qどのスキル分野が補助金対象として注目されていますか?
- A
DX推進、生成AI活用、データ分析、IoTなどのデジタルスキル領域が特に重視されています。
これは国が重点投資分野に指定しているためで、今後も補助率が高い状態が続くと予想されます。