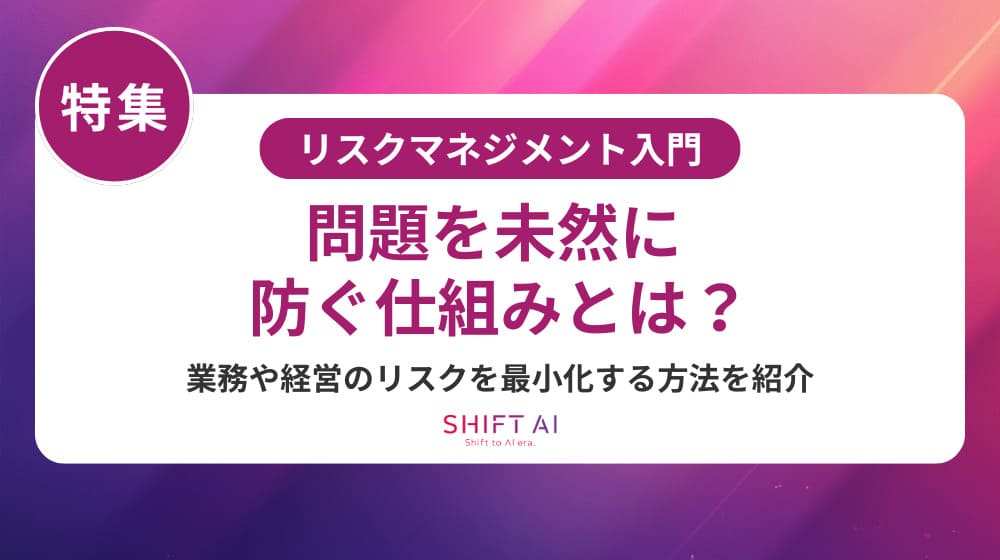企業におけるガバナンス強化や不祥事防止の文脈で、「内部統制」と「リスクマネジメント」という言葉は頻繁に登場します。両者は密接に関連しながらも、本来の目的や役割は異なり、混同されやすい領域です。
内部統制はあくまで仕組みの整備を通じて業務の信頼性を担保するものであり、リスクマネジメントは不確実性に向き合い、組織の持続可能性を守る活動です。この違いを正しく理解し、両者を一体的に運用することで、形骸化した統制から脱却し、業務改善や効率化にもつなげられます。
本記事では、内部統制とリスクマネジメントの関係を整理し、実務に落とし込むためのステップや最新トレンドを解説します。
\ 生成AI研修の選定に必要な考え方がわかる /
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
内部統制とリスクマネジメントの基本整理
内部統制とリスクマネジメントは、どちらも企業の健全な経営に欠かせない取り組みです。しかし、似た文脈で語られることが多いため、両者の役割を整理することが出発点になります。
内部統制とは、組織の業務を適正かつ効率的に遂行するための仕組みです。会社法や金融商品取引法(J-SOX)で整備が求められ、業務の有効性・財務報告の信頼性・法令遵守・資産保全という4つの目的を持ちます。統制環境や職務分掌、承認プロセス、IT統制などを通じて「ルールに沿って業務が進められているか」を担保します。
一方、リスクマネジメントは、不確実性によって企業活動に影響を与える要因を特定・評価し、対応する一連の活動です。自然災害、法令違反、サイバー攻撃、経営判断の誤りなど、幅広いリスクが対象になります。
両者を整理すると、以下のように位置づけられます。
| 観点 | 内部統制 | リスクマネジメント |
| 目的 | 業務の適正性・信頼性を担保する | 不確実性に備え、損失や機会を管理する |
| 対象 | 組織内の業務プロセス | 内部・外部を含む広範なリスク要因 |
| 手法 | 承認、職務分掌、IT統制、モニタリング | リスク特定、分析、評価、対応、モニタリング |
| 根拠 | 会社法、金融商品取引法、COSOフレームワーク | ISO31000、COSO-ERM など国際基準 |
| 特徴 | 「仕組み」を整える | 「運用」でリスクに対応する |
このように、内部統制=統制の枠組み、リスクマネジメント=その枠組みを活用した運用と考えると整理しやすいでしょう。
関連記事:
【2025年版】リスクマネジメント完全ガイド|種類・プロセス・AI活用まで徹底解説
内部統制の枠組みとリスクマネジメントの位置づけ
内部統制を理解する上で欠かせないのが、国際的に広く参照される COSOフレームワーク です。COSOでは、内部統制を以下の5要素に分けて整理しています。
- 統制環境:経営者の姿勢や倫理観、組織文化
- リスク評価:組織目標の達成を阻害する要因の特定と分析
- 統制活動:承認手続きや職務分掌、IT統制など具体的な仕組み
- 情報と伝達:正確かつタイムリーに情報を共有する仕組み
- モニタリング:統制が有効に機能しているかを継続的に検証
このように、内部統制は「企業を守る仕組みの土台」として設計され、法制度でも整備が義務づけられています。日本では会社法や金融商品取引法(いわゆるJ-SOX法)がその根拠となっており、特に上場企業では内部統制報告制度が必須です。
一方でリスクマネジメントは、この枠組みの中で実際にリスクを洗い出し、評価し、対応する「運用のプロセス」にあたります。内部統制が 「仕組みを整える」 のに対し、リスクマネジメントは 「その仕組みを活用してリスクを管理する」 役割を担います。
たとえば、不正会計を防止するために承認フローを整備するのは内部統制ですが、そのリスクをどこまで許容し、どの水準でチェックを行うかを決めるのはリスクマネジメントの領域です。両者を分けて考えるのではなく、統制=器、リスクマネジメント=中身 として連携させることが重要です。
内部統制の観点からみたリスクマネジメントの実務ステップ
リスクマネジメントは単なる「リスク対応」ではなく、内部統制の枠組みを活かしながら段階的に進める必要があります。実務に落とし込む際の流れを、5つのステップで整理します。
ステップ① リスクの特定
- 業務プロセスを洗い出し、どこに不備や不正の余地があるかを明確化
- 外部リスク(自然災害、サイバー攻撃、法規制の改正など)も併せて把握
- 内部統制の観点では、「発生可能性がある事象」を抜け漏れなく記録することが重要
ステップ② リスクの分析と評価
- 発生頻度と影響度をかけ合わせて評価する「リスクマトリクス」を用いる
- 財務的損失だけでなく、企業ブランドや法令遵守への影響も考慮
- 内部統制の目的(財務報告の信頼性や資産保全など)との関連性を確認
ステップ③ 対応策の設計
- 回避:その活動を停止する
- 低減:統制手続きや教育でリスクを減らす
- 移転:保険や契約によって外部に委ねる
- 受容:発生確率が低い場合は許容する
- 内部統制は特に「低減」のための具体的な仕組み(承認フロー、職務分掌、アクセス制御など)として機能する
ステップ④ コントロール活動の実施
- 日常業務に統制手続を組み込み、属人化を防ぐ
- IT統制(システムアクセス権管理、入力チェック)や自動化ツールを活用
- 組織全体で徹底するため、マニュアル整備や教育も不可欠
ステップ⑤ モニタリングと改善
- 内部監査や定期レビューを通じて統制の有効性を検証
- 改善点が見つかれば迅速に統制を修正し、次のサイクルへつなげる
- リスクマネジメントは一度で終わらず、継続的なPDCA が重要
このように、リスクマネジメントのステップは内部統制と不可分です。統制を「枠組み」として活かしつつ、運用を回すことで、実効性のあるリスク管理が実現できます。
内部統制を強化しつつ業務改善につなげるポイント
内部統制は「不祥事防止の仕組み」として整備されることが多い一方で、現場からは「負担ばかり増える」という声も少なくありません。統制が目的化してしまうと、業務改善につながらず形骸化してしまいます。ここでは、内部統制を強化しながら同時に業務改善を進めるための視点を整理します。
1. 守るだけでなく「活かす」統制へ
内部統制を単なるチェックリストではなく、業務プロセス改善の仕組みとして捉えることが重要です。たとえば承認フローを可視化すれば、業務のボトルネックや無駄な手続きも浮かび上がります。
2. 属人化を防ぎ標準化を進める
担当者の経験や勘に依存する業務は、統制の抜け穴になりやすい領域です。マニュアル化や業務フローの標準化により、誰が担当しても一定水準の統制が効く体制を整えることが、効率化にも直結します。
3. IT統制とデジタルツールの活用
システムによるアクセス制御や入力チェックなど、IT統制は人的負担を減らす有効な方法です。さらにRPAによる定型業務の自動化、生成AIを活用した文書レビューや不正兆候の検知など、最新ツールを組み込むことで統制の質とスピードを高められます。
4. コスト削減とガバナンス強化の両立
統制の目的は「コストをかけて守る」ことではなく「効率的にリスクを減らす」ことです。優先度の低い統制を見直す一方で、重大なリスクには重点的にリソースを投入することで、ガバナンス強化とコスト最適化を両立できます。
関連記事:
【2025年版】リスクマネジメント効率化の全手法|標準化・自動化・AI活用で成果を出す
よくある課題と失敗パターン
内部統制とリスクマネジメントは、制度として整えて終わりではありません。現場で形骸化しやすく、運用の仕方によっては逆効果になることもあります。代表的な失敗パターンを整理します。
1. 書類作成やチェックが形骸化する
「証跡を残すこと」が目的化し、膨大な書類やチェックリストの作成に追われてしまうケースです。記録は整っていても、実際にはリスクの低減につながっていないことがあります。
2. 部門横断でのリスク共有が進まない
各部門が個別にリスク管理を行うと、全社的な視点での優先度付けができません。部門ごとに最適化された統制は、かえってサイロ化を助長し、重大なリスクを見落とす原因になります。
3. 現場の負担感が強く、改善が進まない
「統制=監視」と受け止められると、従業員のモチベーションが下がり、必要な情報が上がってこなくなります。結果として、経営層が実態を把握できず、統制が形だけのものになってしまいます。
4. 改善サイクルが回らない
リスク対応は一度で完了するものではなく、PDCAを回し続けることが不可欠です。モニタリングや内部監査を形だけで終わらせると、統制の効果が持続しません。
こうした課題を乗り越えるには、「仕組みを強化する」だけでなく「現場が活用できる統制」へ設計し直す視点 が求められます。その際、生成AIやデジタルツールを用いた効率化が有効です。
関連記事:
リスクマネジメントが失敗する5大理由と改善策|形骸化を防ぐ実践ステップ
内部統制リスクマネジメントの最新動向
内部統制とリスクマネジメントの枠組みは長く活用されていますが、近年は企業を取り巻く環境が大きく変化し、新たな課題が浮かび上がっています。特に注目されるのは、ESG・サステナビリティリスク、サイバーリスク、デジタル統制の進化です。
ESG・サステナビリティリスクの重視
気候変動や人権問題といった非財務リスクは、投資家や規制当局からの注目度が高まっています。内部統制においても、これらの要素をリスク評価に組み込み、持続可能性の観点から企業活動を見直す動きが広がっています。
サイバーリスク・情報漏えいへの対応
リモートワークやクラウド利用の拡大に伴い、情報セキュリティの脅威は増大しています。従来のアクセス管理や承認フローに加え、AIによるログ分析や異常検知を導入することで、内部統制の実効性を高める企業が増えています。
デジタルツール・AIによる統制の高度化
内部監査やリスクモニタリングの領域では、AIを活用した自動レビューや不正検知が実用化されています。これにより、従来は人手で膨大なサンプルチェックを行っていた作業が効率化され、リスク対応のスピードも向上しています。
国際的フレームワークとの整合性
COSO-ERMやISO31000といった国際基準は、企業のリスク対応力を評価するベンチマークになりつつあります。日本企業にとっても、グローバルな事業展開を意識した統制・リスク管理が求められています。
内部統制とリスクマネジメントは、従来の「法令対応」から「経営戦略の一部」へと進化しています。最新動向を踏まえた仕組みづくりこそが、企業の持続可能性と競争力を高める鍵になります。
内部統制とリスクマネジメントを全社展開するためのポイント
内部統制やリスクマネジメントを仕組みとして整えても、特定の部門だけで運用されている状態では十分な効果を発揮できません。全社的に定着させるには、以下の3つのポイントが重要です。
経営層からのメッセージ発信経営層からのメッセージ発信
トップマネジメントが「統制とリスク管理は企業戦略の一部である」と繰り返し示すことで、各部門が主体的に取り組みやすくなります。
教育・研修による共通認識の醸成
従業員一人ひとりが統制の意味やリスク感度を理解していなければ、形骸化は避けられません。Eラーニングやワークショップ形式の研修を通じて、共通言語を持つことが効果的です。
AIやデジタルツールの活用
リスク検知やモニタリングをAIで自動化することで、人的負担を減らしつつリアルタイムに状況を把握できます。たとえば生成AIによる不正兆候の検知や、ケーススタディを活用した研修プログラムは、効率的な全社展開を後押しします。
全社的な仕組みとして定着させることで、内部統制とリスクマネジメントは「監視の仕組み」から「企業の成長を支える基盤」へと進化します。
SHIFT AI for Biz の研修では、こうした全社展開に不可欠な教育・AI活用を体系的に学べます。
\ 組織の“生成AI実践力”を高める法人研修プログラム /
中小企業・ベンチャーにおける実践の工夫
内部統制やリスクマネジメントは、大企業や上場企業だけの課題ではありません。中小企業やベンチャーでも、限られた人員や予算のなかでリスクに対応しなければ、事業継続や成長が難しくなります。とはいえ、大企業と同じ水準の統制を一度に整備するのは現実的ではありません。ここでは、リソースの限られた企業が取り組む際の工夫を整理します。
1. 最小限の統制から始める
まずは全社的なリスクを洗い出し、影響度の高いものに絞って統制を設計します。たとえば資金管理や契約承認といった「事業の根幹」に直結する領域から整備すれば、負担を抑えつつ効果を発揮できます。
2. 優先度を明確にする
リスクは無数に存在しますが、すべてに対応することは不可能です。リスクマトリクスを用いて「発生頻度×影響度」で優先順位をつけることで、限られたリソースを有効活用できます。
3. 外部リソースを活用する
社内に専門人材がいない場合は、外部コンサルタントや研修プログラムを活用するのも有効です。最新の知見を取り入れることで、短期間で実効性のある仕組みを導入できます。
4. デジタルツールの積極活用
クラウド型の会計システムやワークフロー管理ツール、生成AIによる文書レビューなどは、中小企業でも導入しやすいコスト帯で提供されています。これらを組み合わせることで、大企業並みの統制水準を効率的に実現できます。
内部統制とリスクマネジメントは、規模の大小にかかわらず企業の持続性を左右します。中小企業こそ「シンプルかつ効果的」な方法で実践し、経営基盤を強化することが重要です。
まとめ|内部統制とリスクマネジメントを実務に活かすために|
内部統制とリスクマネジメントは、似て非なるものですが、どちらも企業の信頼性と持続的成長を支える基盤です。内部統制は「仕組みを整える」役割を担い、リスクマネジメントは「不確実性に対応する運用」を担います。両者を切り離さず一体で進めることで、形骸化を防ぎ、実効性あるガバナンスを実現できます。
本記事では、定義や違いの整理、実務ステップ、業務改善のヒント、そして最新トレンドまで幅広く解説しました。重要なのは、統制を単なるチェックリストにとどめず、業務効率化や企業価値向上につなげる視点です。
内部統制とリスクマネジメントを「守りの仕組み」から「攻めの仕組み」へと進化させることは、どの規模の企業にとっても避けられない課題となっています。次の一歩として、体系的に学べる研修や実践的なツールを取り入れることが効果的です。
SHIFT AI for Biz では、生成AIを活用した 内部統制・リスクマネジメント研修 をご提供しています。
- 内部統制を「形骸化させない仕組み」として根付かせたい
- リスクマネジメントを効率化し、業務改善とガバナンス強化を両立したい
- AIやデジタルツールを取り入れ、現場に定着する運用を実現したい
SHIFT AI for Biz では、生成AIを活用した 内部統制・リスクマネジメント研修 をご提供しています。
- 内部統制を「形骸化させない仕組み」として根付かせたい
- リスクマネジメントを効率化し、業務改善とガバナンス強化を両立したい
- AIやデジタルツールを取り入れ、現場に定着する運用を実現したい
SHIFT AI for Biz の生成AI研修で、実務に直結する最新ノウハウを習得しませんか?
\ 生成AI研修の選定に必要な考え方がわかる /

内部統制とリスクマネジメントに関するよくある質問
- Q内部統制とリスクマネジメントの違いは何ですか?
- A
内部統制は、業務を適正かつ効率的に進めるための「仕組みづくり」を指します。一方でリスクマネジメントは、不確実性による損失や機会を管理する「運用プロセス」です。内部統制は枠組み、リスクマネジメントはその中で動く実践活動と考えると整理しやすいです。
- Qリスクマネジメントの手順はどのように進めればよいですか?
- A
一般的には以下の5ステップで進めます。
- リスクの特定
- リスクの分析・評価(発生頻度 × 影響度)
- 対応策の設計(回避・低減・移転・受容)
- コントロール活動の実施
モニタリングと改善
内部統制はこれらのステップを支える「仕組み」として機能します。 - リスクの特定
- Q中小企業でも内部統制やリスクマネジメントは必要ですか?
- A
必要です。特に資金管理や契約承認など、事業の根幹に直結する領域ではリスクが顕在化すると大きなダメージになります。中小企業ではリソースが限られるため、優先度の高いリスクに絞り、シンプルな仕組みから整備することが効果的です
- Q内部統制が形骸化する原因は何ですか?
- A
書類作成やチェックが目的化すること、部門横断の連携不足、現場の負担感が強いことなどが主な要因です。改善には、実際の業務改善につながる仕組みに再設計し、IT統制やAIを活用して効率化することが有効です。
- Q最新のリスクマネジメントで注目される領域は?
- A
ESG・サステナビリティリスク、サイバーリスク、AIを活用した自動モニタリングなどが注目されています。従来の法令遵守に加えて、社会的責任やデジタルリスクへの対応が求められています。