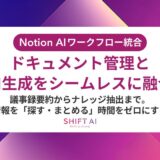「研修を外注する予算も人手もない。けれど、育成は待ったなし」
——そんな悩みを抱える中小企業の人事・教育担当者は少なくありません。
特に近年は、業務が高度化・複雑化する中で、汎用的な外部研修では対応しきれず、
「現場の実情に合った研修を、社内でつくりたい」というニーズが高まっています。
一方で、「教材をつくるノウハウがない」「講師を担う余裕がない」など、
研修の“内製化”には多くのハードルもあるのが実情です。
しかし近年、こうした課題を解決する手段として注目されているのが生成AIの活用です。
企画構成から教材づくり、フィードバックまで——AIを味方につければ、
少人数の中小企業でも、研修の内製化が現実的な選択肢になります。
本記事では、中小企業が生成AIを活用して研修を内製化するための考え方や手順、
実際のユースケースを、わかりやすく解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今「研修の内製化」が注目されているのか
かつては、社員研修といえば外部講師や専門機関に委託するのが一般的でした。
しかし近年、中小企業を中心に「研修は社内で作る」流れが強まっています。
その背景には、いくつかの時代的な要因があります。
コストを抑えつつ、効果的な育成を実現したい
外部研修は1人あたりの単価が高く、参加人数に比例してコストも増大します。
特に中小企業では、「全社員に受けさせたいが、予算が足りない」というケースも少なくありません。
内製化することで、繰り返し使える研修資産を蓄積し、長期的なコスト削減が可能になります。
自社業務に即した内容でなければ意味がない
外注研修はどうしても一般論や抽象的な内容になりがちです。
たとえば「生成AI活用研修」でも、自社の業務フローに即していなければ、現場に定着しません。
内製化であれば、自社の実務・課題にピンポイントで合わせた内容にできます。
DX・AI活用時代に、社内教育のスピードが問われている
変化の激しい時代、研修を数か月前から企画して外注していてはスピードが追いつきません。
社内で柔軟に企画・実施できる体制を持つことは、変化に強い組織づくりにも直結します。
とくに生成AIやDXなど、旬のテーマこそ社内で即時対応できる体制が求められます。
内製化したいけどできない…中小企業が直面する3つの壁
研修の内製化には多くのメリットがありますが、実行に移せている企業はまだ限られています。
とくに中小企業では、「やったほうがいい」と分かっていても進まない理由が明確です。
ここでは、内製化を阻む代表的な3つの課題を見ていきましょう。
1.教材をつくるノウハウがない
まず最初の壁が「何から始めていいかわからない」という教材設計の知識不足です。
育成担当者が必ずしも教育の専門家とは限らず、いきなりスライドを作り始めても内容が定まりません。
結果として、「結局まとまらない」「形にならない」といった声がよく聞かれます。
2.講師を担える人がいない
講師役を任せようにも、「教えることに慣れている人材が社内にいない」という悩みもよくあります。
また、現場のリーダー層に頼もうとすると、日常業務が忙しくて時間が取れないという問題も。知識はあるが教えるスキルや余裕がない、というギャップは中小企業ほど深刻です。
3.リソースが足りず、継続できない
仮に一度だけ内製化できたとしても、継続的に回す体制が作れないという課題もあります。
毎回一から作り直すのでは工数がかかりすぎ、形骸化するケースも少なくありません。
人手が限られる中で、「効率的に内製化できる仕組み」が求められています。
こうした壁をどう乗り越えるか——そのヒントが、生成AIの活用にあります。
生成AIを使えば、研修内製化の“壁”はこう超えられる
教材づくりのノウハウも、講師役の不在も、リソースの制約も——
生成AIを活用すれば、これらの課題は乗り越えられる可能性があります。
ここでは、研修内製化における3つの壁を生成AIでどう乗り越えられるのかを整理します。
教材構成はChatGPTが5秒で提案
「何から作ればいいかわからない」という悩みには、生成AIが即戦力になります。
たとえばChatGPTやClaudeに「〇〇研修の構成案を出して」と入力するだけで、
対象者・ゴールに応じた章立て、ステップ構成、学習項目を自動で提示してくれます。
過去の議事録やマニュアルを流し込み、内容を要約・整理して構成化することも可能です。
これにより、ゼロから考える手間が減り、「たたき台」をもとに短時間で教材を形にできます。
スライド・ナレーション・クイズも自動で生成可能
構成が決まったあとは、生成AIでスライド原稿やスピーキング台本を自動生成できます。
PowerPointやNotionとの連携も容易で、文章→スライド化もスムーズです。
さらに、ナレーション文をAI音声に読み上げさせれば、「動画教材化」も最短1日で実現します。
クイズや確認テストも自動生成できるため、学習定着度のチェックにも活用できます。
講師不足も「AIアシスタント」で補完できる
「教える人がいない」という課題にも、生成AIは強力なサポーターとなります。
たとえばChatGPTを“仮想講師”として社員に対話型で問いかけさせることもできます。
「分かったつもり」を防ぐ反復学習や、理解度に応じたヒントの提示もAIに任せられます。
また、資料の事前レビューにも使えるため、人間講師の準備工数も大幅削減できます。
AIで仕組み化すれば、少人数でも“回せる”教育体制に
生成AIの活用は、単発の作業効率化にとどまりません。
一度作った教材や構成をベースに、反復可能な内製研修の“仕組み化”ができるのです。
教材テンプレートやプロンプトを蓄積すれば、新しい研修も短期間で量産可能になります。
社内に教育の専門家がいなくても、教材や講師リソースが不足していても、生成AIを活用すれば、「内製化できない理由」は一つずつ解消できます。
関連記事:部署別にわかる生成AI活用事例|活用レベル別診断&導入の進め方【法人向け】
AIを使った研修内製化の進め方|スモールスタートで成果を出す4ステップ
生成AIを使えば、研修をゼロから内製するハードルは大きく下がります。
ただし、いきなり全社展開を目指すのではなく、小さく始めて、回しながら改善していくのが成功のカギです。
ここでは、AIを活用した研修づくりの実践ステップを4段階でご紹介します。
ステップ1:まずは「研修のテーマとゴール」を明確にする
最初にやるべきことは、「誰に」「何を」「なぜ」教えるのかを明確にすることです。
対象者の職種・スキルレベル、研修後にどうなっていてほしいか(ゴール)を決めましょう。
例:「新人営業が1か月以内に自社サービスを説明できるようになる」
このように目的を明確にすれば、AIへの指示(プロンプト)も的確になります。
ステップ2:生成AIに構成案を出させ、教材のたたき台を作る
ChatGPTやGeminiなどの生成AIに対し、以下のようなプロンプトで指示を出します。
「新人営業向けに自社製品を理解させる研修の構成案を出して。所要時間は90分程度で、章立てと目標も含めてください。」
このように入力することで、構成案・章立て・内容ポイントを自動で提示してくれます。
内容がざっくりしていてもOK。出力されたたたき台を社内で調整すれば、初期設計の手間が大きく省けます。
ステップ3:スライドや台本、クイズをAIで生成し、試験的に実施
構成が決まったら、次は教材の具体化です。以下のようなアウトプットがAIで生成可能です。
- スライド本文(プレゼン資料向け原稿)
- 説明ナレーションの台本
- 確認テストやクイズ(〇×、選択式など)
これらをNotion、Googleスライド、PowerPointなどで形式化し、まずは少人数チームでトライアルを実施してみましょう。
ステップ4:フィードバックをAIと一緒に分析し、改善する
実施後は参加者からのフィードバックを集め、AIに分析させてみましょう。
「以下の自由記述を要約し、共通する改善点を挙げてください」
といった指示で、改善点や気づきを抽出できます。
改善した教材はテンプレートとして保存しておけば、次回以降の制作にも活用できます。
この4ステップを繰り返すことで、無理なく・着実に「AI活用型の研修内製プロセス」が構築できます。
実際に“AI×内製化”で成果を出している中小企業の事例紹介
「生成AIで本当に研修の内製化なんてできるのか?」
そう感じた方にこそ知っていただきたいのが、実際に成果を出している中小企業の事例です。
ここでは、AI活用で研修づくりを成功させたリアル&モデルケースを紹介します。
製造業A社|現場の声を反映した“安全研修”を内製化
従業員50名ほどの地方製造業A社は、毎年実施していた外注の安全研修に課題を感じていました。
内容が実情に合わず、現場からの納得感が得られていなかったためです。
そこでChatGPTを活用し、過去のヒヤリハット報告をもとに構成案を作成。
スライドやクイズも自動生成し、現場リーダーが講師を担当する形式で内製研修を実施しました。
結果、受講者アンケートの満足度は前年比で20%以上向上。
「自分たちの現場に合っていた」「覚えやすい構成だった」といった声が多く寄せられました。
IT企業B社|AIとLMSを連携し、新人研修を毎年効率化
社員数100名規模のIT企業B社では、新人研修の準備に毎年多くの工数がかかっていました。
特にスライド作成や講義台本の更新に時間を取られていたため、ChatGPTとNotionAIを導入。
前年の研修内容をベースに、構成案・スライド・台本をAIが自動生成し、微修正で完成。
LMSと連携させて、オンデマンド+テスト形式のハイブリッド研修として提供しました。
初年度で約50時間分の作業時間を削減し、研修の質も均一化。
「属人性を排除できたのが大きい」と担当者も語ります。
仮想事例|講師がいない企業でも“AI講師”で研修運用
講師経験者が社内におらず、内製化を諦めていたサービス業C社。
生成AIと音声合成ツールを活用し、スライド+AIナレーション動画を制作することで、
「人が登壇しなくても研修が成立する」モデルを構築しました。
AIが問いかける形式の復習パートも導入し、理解度テストも自動でフィードバック。
少人数企業でも“自走型教育”を実現する仕組みづくりに成功しました。
これらの事例から分かるのは、生成AIは大企業だけのツールではないということ。
むしろリソースが限られた中小企業こそ、AIの力を借りることで一歩を踏み出しやすくなるのです。
内製化を成功させるための3つのポイント
生成AIを活用すれば、研修の内製化は十分実現可能です。
しかし、単に「AIで教材を作る」だけでは、継続的な運用にはつながりません。
ここでは、中小企業が無理なく、着実に内製化を進めるためのポイントを3つご紹介します。
1.小さく始めて、段階的に改善する
最初から完璧な研修を目指す必要はありません。
むしろ、小さなテーマで“試作→実施→改善”のサイクルを回すことが成功への近道です。
たとえば、「5名のチームに対して1時間の業務マナー研修を実施する」など、規模と時間を絞ることでスピーディに実行でき、改善点も見つけやすくなります。
このPDCAを積み重ねることで、自然と“型”が蓄積されていきます。
2.社内ナレッジとAIを掛け合わせる
AIは万能ではありません。
AIが出す情報や構成案も、社内の文脈や実務知見と組み合わせてこそ意味を持ちます。
たとえば、AIが作った教材案に対し、現場のリーダーがコメントするだけでも質は大きく向上します。
また、過去の社内資料やマニュアルをAIに渡してカスタマイズさせれば、属人知を再活用する武器にもなります。
3.教育を「仕組み」として捉え、属人化させない
せっかく研修を内製しても、それが特定の社員に依存していては継続性がありません。
AIを活用したテンプレートや教材、プロンプト、スクリプトは再利用しやすい形で整理・保存しましょう。
また、LMSや社内ドライブ、Notionなどを活用して研修を“資産化”することで、
新任者でも回せる内製教育の仕組みが社内に根づきます。
こうした工夫を積み重ねることで、内製化は一過性の取り組みではなく、自社の成長を支える“文化”へと育てることができます。
まとめ|中小企業でも“AIの力”で研修の内製化は可能になる
中小企業が研修を内製化するには、ノウハウやリソースの壁が確かに存在します。
しかし、生成AIを活用すれば——教材づくりも、講師役の補完も、改善の仕組み化も、
無理なく・効率よく進められる現実的な選択肢になります。
特別なスキルがなくても、AIの提案力や自動化機能をうまく活用することで、社内に合った育成プログラムを、自分たちの手で作っていくことが可能です。大切なのは、「完璧に始めること」ではなく、「小さく試し、回しながら改善すること」。
生成AIは、そのチャレンジを支えてくれる強力な味方です。
- Q研修を内製化するのは、大企業じゃないと難しいのでは?
- A
いいえ、中小企業こそ内製化のメリットが大きいです。
外注に比べてコストを抑えやすく、自社の課題に即した内容にできるため、
育成の成果を実感しやすいのが特長です。生成AIを活用すれば、少人数でも教材作成や運用の負担を大きく減らすことができます。
- Q教材づくりの経験がないのですが、AIだけで作れるのでしょうか?
- A
はい、生成AIを活用すれば、研修の構成案・スライド原稿・ナレーション・テストまで自動で作成できます。
「こういう人に、こういう内容を教えたい」と指示するだけでたたき台が生成され、
あとは社内で調整するだけで教材として仕上げられます。
- QAIを使った社内研修はどんなテーマで作れるのでしょうか?
- A
多くの企業で以下のようなテーマで活用が進んでいます。
- 新人向けマナー研修
- 社内システムの使い方ガイド
- 情報セキュリティ研修
- 生成AIの業務活用リテラシー研修
- 現場作業における安全教育 など
業務に関わるナレッジを教材化したい場合には、非常に相性が良いです。
- Q社内に講師がいない場合でも内製化できますか?
- A
はい、可能です。
ナレーションや進行はAI音声で代替できるほか、対話形式の復習や確認テストもAIに任せられます。
また、説明資料を読み上げるだけのスタイルでも十分な研修効果を出すことが可能です。
- Q研修の効果測定やフィードバックにもAIは使えますか?
- A
はい、参加者のアンケート結果や自由記述をAIに分析させることで、改善点を素早く抽出できます。
また、テスト結果をもとに再学習が必要な箇所を提示するなど、研修のPDCAを回すツールとしてもAIは活用できます。