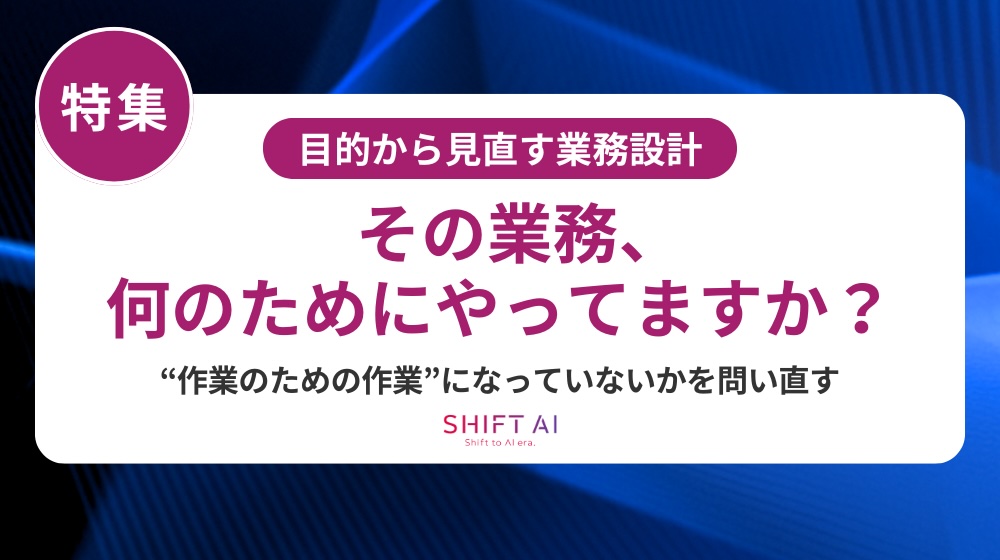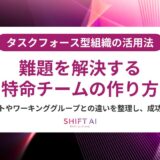「言われたことしかやらない」「仕事の意味を理解していない」
部下のそんな姿勢に、頭を抱えていませんか?
実は、「もっと目的意識を持って!」と伝えるのは逆効果かもしれません。
目的とは他人から与えられるものではなく、本人が納得して初めて生まれるものだからです。
この記事では、部下が自発的に動かない構造的な原因を解明し、明日から実践できる「5つのステップ」や、本音を引き出す「問いかけリスト」を紹介します。
精神論ではなく、具体的な仕組みで自走するチームを作る方法をぜひ持ち帰ってください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
そもそも「目的意識」とは?部下が自走する定義と誤解
「目的意識を持て」と部下に伝えるとき、その言葉の意味を正しく共有できているでしょうか。
多くの現場で、「目的意識」は「やる気」や「熱意」といった精神論と混同されがちです。しかし、ビジネスにおける目的意識とは、「なぜその仕事を行うのか(Why)」を理解し、自分の行動が最終的なゴールにどう繋がっているかを認識できている状態を指します。
ただがむしゃらに頑張ることではなく、「何のために」が明確になっているからこそ、自分で判断し、工夫する余地が生まれます。これが「自走する」ということです。まずは上司自身が、目的意識を「個人の資質」ではなく「情報の繋げ方」の問題として捉え直す必要があります。
なぜ部下は目的を持てないのか?3つの構造的要因
部下が目的を持てないのは、本人の能力不足ではありません。多くの場合、組織の構造や情報の伝え方に原因があります。ここでは代表的な3つの要因を解説します。
1.Whyの欠如|仕事の全体像や意義が共有されていない
日々の業務指示において、「何を(What)」「いつまでに(When)」「どうやって(How)」やるかは伝えられていても、「なぜ(Why)」やるのかが抜け落ちているケースです。
全体像が見えないままパーツの作業だけを任されても、部下は「作業をこなすこと」自体を目的にせざるを得ません。これでは、トラブルが起きた際の応用も利かず、改善提案も生まれてきません。
関連記事
目的が共有されていない職場の特徴と解決策|生成AIで成果のばらつきを改善する方法
2.貢献の実感不足|誰の役に立っているか見えない
自分の仕事が、最終的に「誰の」役に立ち、「どんな」喜びを生んでいるのかが見えない状態です。
特にバックオフィス業務や分業化が進んだ組織では、顧客の顔が見えにくくなります。自分の仕事の結果がどう役立ったのかというフィードバックがないと、「自分は歯車の一つに過ぎない」と感じ、目的を見失ってしまいます。
3.押し付けられた目標|自分ごとにならない数値設定
会社から降りてきた数値目標を、そのまま部下の目標として設定していませんか?
「売上〇〇万円必達」と言われても、部下にとっては他人が決めた数字でしかありません。その数字を達成することが、自分にとってどんな意味があるのか、キャリアや成長にどう繋がるのかという「自分ごとの意味」と接続されていない限り、本当の意味での目的意識は生まれません。
無理に目的を持たせるのは逆効果!上司が陥るNGマネジメント
部下に自発的に動いてほしい一心で、「もっと目的意識を持ちなさい」と指導していませんか?実はその言葉こそが、部下の思考を停止させ、受動的な姿勢を強めている可能性があります。なぜ精神論での指導がうまくいかないのか、良かれと思って上司が陥りがちなNGパターンを解説します。
精神論での押し付けは「やらされ仕事」を生むだけ
上司から「目的を持て」と命令されても、部下は「やらされ感」を抱くだけで逆効果です。
なぜなら、目的意識とは本来、本人の内側から湧き上がるものであり、他人から強制されるものではないからです。無理に持たされた目的はただの「ノルマ」になり、部下は上司の顔色を伺って仕事をするようになります。これではいつまで経っても自走する組織にはなりません。
有名な「レンガ職人」の話でも、「レンガを積んでいる(作業)」としか捉えていない職人は、ただ辛そうにレンガを積むだけでした。言葉で強要するのではなく、本人が仕事の意義に気づけるような「環境」を作ることが上司の役割です。
関連記事
指示待ち新人の特徴と改善法|生成AI活用で確実に変わる育成術
「失敗への恐怖」が部下の思考を停止させている
目的意識を持てない部下の中には、「失敗するのが怖い」からあえて思考を止めているケースが少なくありません。
自ら目的を設定して行動すると、うまくいかなかったときの責任も自分で負わなければならないとプレッシャーを感じるからです。特に心理的安全性が低い職場では、部下は「言われた通りにやるのが一番安全だ」と考え、指示待ちの状態に逃げ込んでしまいます。
かつて新しい提案をして否定された経験がある部下ほど、この傾向は顕著です。まずは「失敗しても大丈夫」という安心感を与え、小さな挑戦を認める土壌を作ることからはじめましょう。
部下に目的を持たせる方法|明日から実践できる5つのステップ
それでは、具体的にどうすれば部下は目的を持てるようになるのでしょうか。明日からマネジメントに取り入れられる5つのステップを紹介します。
ステップ1.Whyの共有|仕事の“意味”を共に再発見する
業務を依頼する際は、必ず「背景」と「目的」をセットで伝えます。「なぜこの仕事が必要なのか」「これが完了すると、会社やチームはどうなるのか」というストーリーを共有してください。
また、一方的に話すのではなく、「この仕事はどんな意味があると思う?」と部下に問いかけ、一緒に意味を再発見するプロセスを踏むことが重要です。
ステップ2.自己理解の支援|価値観・キャリア観を引き出す1on1
部下自身の「Will(やりたいこと)」や「Value(大切にしている価値観)」を知る時間を設けます。
定期的な1on1ミーティングで、業務の進捗確認だけでなく、「どんな時にやりがいを感じるか」「将来どうなりたいか」といったテーマで対話します。部下が自分の価値観を言語化できれば、今の仕事との接点を見つけやすくなります。
ステップ3.成果の可視化|貢献実感を味わえる仕組みを作る
部下の仕事が誰の役に立ったのか、フィードバックが届く仕組みを作ります。
- お客様からの感謝の言葉を共有する
- 後工程の担当者から「助かった」という声を伝える
- チーム内でのサンクスカードを導入する
「自分の仕事は価値がある」と実感できる機会を意図的に増やすことで、前向きな目的意識が育ちます。
ステップ4.ゴールベースで任せる|タスクでなく“意義”を託す
仕事の任せ方を「手順(How)」から「ゴール(What・Why)」に変えていきます。「この資料をこの手順で作って」ではなく、「来週の会議で〇〇を決裁してもらいたいから、説得力のある資料がほしい」と伝えます。
ゴールと意義さえ共有できていれば、プロセスは部下に任せます。自分で考え、工夫する余地があることが、主体性を引き出す鍵となります。
関連記事
なぜ若手に任せられないのか?責任感の強い管理職が陥る7つの理由と対処法
ステップ5.成長の承認|成果だけでなくプロセスを評価する
結果が出た時だけでなく、そこに至るまでの「試行錯誤」や「成長」を承認します。
目的意識を持って動くことは、失敗のリスクも伴います。たとえ結果が伴わなくても、「自分で考えて動いたこと」自体を評価することで、部下は「次も自分で考えてみよう」と思えるようになります。安心感が挑戦を支えます。
目的意識を引き出す「問いかけ」リスト|1on1で使える具体例
部下の目的意識を引き出すには、指示ではなく「問い」によって本人の思考を促すことが効果的です。日々の1on1や面談で使える、部下の視座を高める具体的な質問例を紹介します。これらを活用して、部下が自ら答えを見つける手助けをしてください。
「もし制限がなかったら?」──視座を上げる質問
目の前の業務に追われている部下には、一度枠を外して考えさせる質問が有効です。
- 「もし予算や人員の制限がなかったら、どんなプロジェクトをやってみたい?」
- 「今の仕事がすべて自動化できたら、空いた時間で何をする?」
- 「社長の立場だったら、今のチームをどう変える?」
このような「仮定」の質問を投げかけることで、部下は現状の制約から離れ、本来やりたかったことや理想の状態をイメージしやすくなります。視座が上がることで、日々のルーチンワークの中にも新たな改善点や目的を見出せるようになるでしょう。
「誰にありがとうと言われたい?」──貢献をイメージさせる質問
仕事の意義が見えなくなっている部下には、具体的な「相手」を想像させる質問をしてみましょう。
- 「この仕事が完了したら、一番喜ぶのは誰だと思う?」
- 「将来、どんなお客様から『ありがとう』と言われたい?」
- 「チームメンバーの誰の役に立っていると感じる?」
抽象的な「社会貢献」よりも、具体的な「誰か」の顔を思い浮かべる方が、モチベーションは高まります。自分の仕事が誰かの笑顔や助けにつながっていると実感できれば、自然と「もっとこうしたい」という能動的な目的意識が芽生えてきます。
「この仕事が得意な理由は?」──強みを自覚させる質問
自信を失っている部下には、過去の成功体験や強みに焦点を当てた質問で自己効力感を高めます。
- 「この業務がうまくいった要因は何だと思う?」
- 「他の人よりもスムーズにできたのはなぜだろう?」
- 「自分が夢中になれるのはどんな瞬間?」
自分の強みや得意なパターンを言語化させることで、「自分には価値がある」「この仕事は自分に向いている」という前向きな認識が生まれます。自己理解が深まることで、自分の強みを活かした目標設定ができるようになり、主体的な行動へとつながっていきます。
目的を持たせる鍵は“言語化”にあり|生成AI活用のススメ
実は、目的意識を持てない最大の理由は、「自分の考えを言葉にできないから」かもしれません。モヤモヤとした思いを言語化する手段として、生成AI(ChatGPTなど)の活用が注目されています。
AIで“目的”を言語化する──思考の外部化ツールとしての活用
部下が自分の考えを整理する際、AIを壁打ち相手に使う方法です。
「今の仕事のやりがいは何だと思う?」「このタスクの目的を3つ挙げて」とAIに問いかけさせることで、自分では思いつかなかった視点や言葉を得られます。AIは評価も批判もしないため、心理的安全性を保ちながら深い思考整理が可能です。
チームで目的を共有するワーク設計も可能に
チーム全体の目的意識を醸成するワークショップにもAIは活用できます。
例えば、会社のビジョンと個人の業務の繋がりをAIに図解させたり、チームのミッションステートメントをAIと一緒に作成したりすることで、「目的」について語り合う場を効果的に作れます。
現場浸透のための“仕組み化”も可能に
AIを使えば、目的意識を持つための「振り返り」や「目標設定」を仕組み化することも容易です。
日報や週報にAIからのフィードバック機能を組み込み、「今週の業務でどんな価値を提供できましたか?」と自動で問いかける仕組みを作ることで、自然と目的を意識する習慣が定着します。
関連記事
「業務の目的化」が組織を破綻させる理由とは?生成AIで本質を見抜く解決法
まとめ|目的は“押し付ける”ものではなく、“共に探す”もの
部下に目的意識を持たせる方法は、決して上司が一方的に「目的」を与えることではありません。精神論で押し付けても、部下の心は離れていくだけです。
まずは「NGな指導」を止め、日々の問いかけや対話を通じて、部下自身の中にある「Will(やりたいこと)」や「強み」を引き出すことから始めましょう。そして、会社の目指す方向性(Why)と個人の想いが重なるポイントを一緒に見つけることが、自走するチーム作りの第一歩です。
言語化が難しい場合は、生成AIを活用して思考を整理するのも一つの有効な手段です。新しい技術も柔軟に取り入れながら、部下一人ひとりが納得感を持って働ける環境を整えていきましょう。

- Q部下が全く目的を持っていないように感じます。どこから始めればいいですか?
- A
まずは「目的がない」のではなく、「言葉にできていないだけ」と捉えましょう。
1on1で「最近やっていて嬉しかった仕事は?」といった問いかけから始めるのが有効です。
自分の中にある価値観や強みに気づける設計が、目的形成の第一歩となります。
- Q目的意識を研修で身につけさせることは可能なのでしょうか?
- A
可能です。ただし座学だけでは定着しにくく、実際の業務との接続や内省の仕組みが重要です。
近年は、生成AIを活用して個々の価値観や貢献意識を“可視化”する研修が注目されています。
実務との接続がある研修を選ぶことが、成果に直結します。
- Q自分の目的を語るのが苦手な部下には、どう接すればいいですか?
- A
「目的を語ること=正解を出すこと」と思い込んでいる可能性があります。
まずは安心して話せる場づくりを心がけましょう。
生成AIを活用した自己対話や価値観マップなど、非対面での支援ツールも有効です。
- Q目的意識を高めるために、マネージャーが避けるべき行動はありますか?
- A
“目的の押しつけ”や、“成果のみで評価する”ことは避けましょう。
また、タスク単位での指示だけでは部下は目的を実感しにくくなります。
「なぜそれが必要か」「誰に価値を届けるのか」を、上司自身が語る姿勢が重要です。
- Q目的意識を持たせる仕組みづくりに、AIの活用は本当に効果がありますか?
- A
はい。生成AIは、価値観や業務の意義を言語化するプロセスを支援できます。
特に“自己理解が苦手な層”にとっては、AIとの対話が気づきのきっかけになることも。
当社の研修プログラムでは、こうしたAI活用事例も多数導入しています。