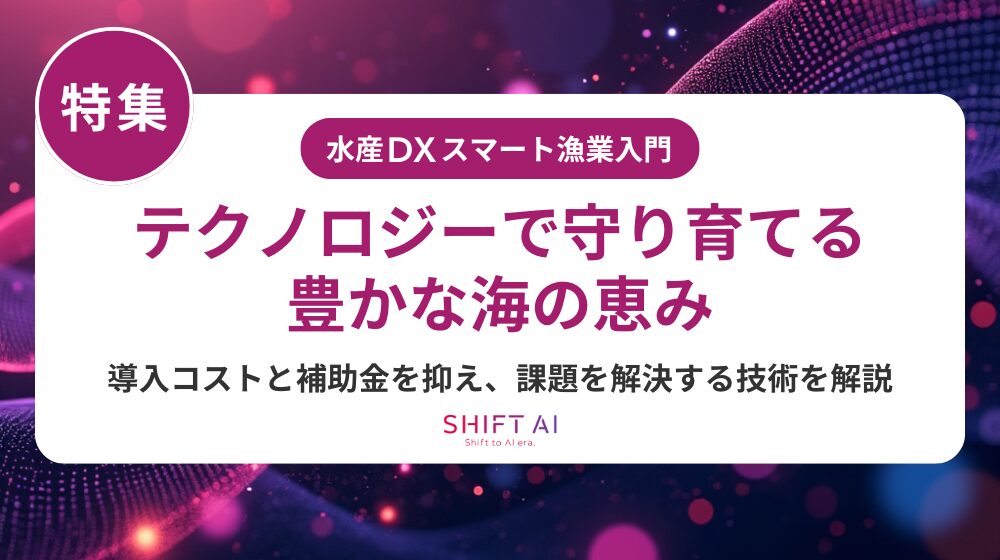燃料高騰や人手不足、環境変化への対応――。
水産業を取り巻く課題は深刻化し、現場の持続性が問われています。
こうしたなかで国や自治体が進めているのが、AI・IoTなどを活用した「スマート水産業」の推進です。
漁場のモニタリングや自動給餌、AI魚群探知など、デジタル技術の導入を支援するための補助金制度が、全国で次々に整備されています。
この記事では、令和7年度版のスマート漁業・水産業向け補助金の最新情報をわかりやすく整理し、申請手順や採択のコツ、地域別の支援例までを解説します。
さらに、補助金を活かして導入した後に成果を出すための“AI活用・人材育成”の重要性にも触れます。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
スマート漁業とは?補助金が注目される背景
水産業は、少子高齢化や燃料費の高騰、気候変動による漁場環境の変化など、これまでにない課題に直面しています。
これらの課題を解決する切り札として注目されているのが、AI・IoT・ロボティクスを活用した「スマート漁業(スマート水産業)」です。
スマート漁業では、センサーや通信機器で漁場データをリアルタイムに収集し、AIが最適な操業や給餌を判断します。
漁獲量の安定化や燃料消費の削減、省力化による人手不足の解消など、多くの効果が報告されています。
たとえば、AI魚群探知機や自動給餌システムを導入することで、経験や勘に頼っていた判断がデータに基づいた“科学的操業”へと変わりつつあります。
こうしたデジタル化の波を後押しするために、国は「スマート水産業推進事業」や「水産業・漁村活性化交付金」など、AI・IoT導入を支援する補助金制度を整備しています。
単なる設備投資ではなく、持続可能で稼げる水産業の仕組みをつくることが、その狙いです。
関連記事:
スマート漁業とは?AI・IoTで進化する持続可能な漁業と導入ステップを解説
国の主要なスマート漁業向け補助金一覧(2025年度版)
スマート漁業の普及を後押しするため、国や自治体では複数の補助金・交付金制度が用意されています。
ここでは、令和7年度(2025年度)に活用できる主要な制度を紹介します。
制度によって対象・補助率・上限額が異なるため、自社や漁協の状況に合わせて選定することが重要です。
スマート水産業普及推進事業(農林水産省・水産庁)
概要
AI・IoT機器を活用した漁業のスマート化を現場レベルで進めることを目的とした、国の中核的支援事業です。
漁業者、漁協、企業、研究機関などが連携して行う「実証・普及」を支援します。
主な支援内容
- スマートブイや自動給餌機、AI魚群探知機などの導入費
- データ共有基盤や通信システムの構築
- 実証実験・効果測定のための経費
補助率・上限額
- 補助率:2/3以内
- 上限額:数千万円規模(年度・事業区分により変動)
対象者
- 漁業協同組合、漁業者団体、漁業法人、大学・研究機関、自治体など
特徴
全国で採択実績が多く、AI・IoT導入に直結する代表的な制度。
特に「地域内のデータ共有」や「波及効果のある取り組み」が評価されやすい傾向があります。
水産業・漁村活性化交付金(デジタル対応枠)
概要
地域の漁村活性化や所得向上を目的に、スマート技術導入を支援する自治体連携型の制度です。
地域一体での生産性向上や販路拡大などを図る取り組みが対象となります。
主な支援内容
- 環境モニタリングセンサーやIoT通信機器の導入
- 水産資源データの可視化・分析基盤整備
- 省力化機器の導入、AI給餌の自動化など
補助率・上限額
- 補助率:1/2~2/3以内
- 上限額:事業内容により異なる(数百万円~数千万円)
特徴
地域単位での取り組みが前提のため、漁協や自治体と連携して申請するケースが多い。
単独事業ではなく「地域波及型」の計画が採択されやすい点がポイントです。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(中小企業庁)
概要
製造・加工・流通分野の中小企業を対象とした代表的な補助金で、水産加工業や流通業でも利用可能です。
支援内容
- AIによる品質検査システム導入
- 生産ラインの自動化・データ化
- 在庫管理・需要予測システムの導入
補助率・上限額
- 補助率:1/2~2/3以内
- 上限額:最大1,250万円(事業類型により変動)
特徴
水産加工・流通・販売など“ポスト漁獲領域”のスマート化に適しています。
申請数が多いため、「現場課題の明確化」+「効果の定量化」が採択のカギになります。
地方創生推進交付金・自治体独自補助制度
概要
各自治体が、地域の水産業振興を目的に独自で設けている助成制度です。
国の交付金を活用しながら、上乗せ補助や独自支援を行うケースもあります。
例
- 北海道:AI魚群探知機導入助成、スマートブイ実証支援
- 宮城県:養殖業向けIoT給餌システム導入補助
- 長崎県:データ連携プラットフォーム整備
- 鹿児島県:AI活用型スマート養殖実証支援
特徴
自治体によって補助上限・申請時期が異なるため、地域の水産課や産業振興課への確認が必須です。
自治体サイトの公式情報を随時チェックしましょう。
比較表(例)
| 制度名 | 主な対象 | 補助率 | 上限額 | 特徴 |
| スマート水産業普及推進事業 | 漁協・企業連携 | 2/3以内 | 数千万円 | 実証・普及型の中核制度 |
| 水産業・漁村活性化交付金 | 自治体・地域団体 | 1/2~2/3以内 | 数百万~数千万円 | 地域波及効果重視 |
| ものづくり補助金 | 水産加工・流通企業 | 1/2~2/3以内 | 最大1,250万円 | 加工・販売分野に最適 |
| 自治体独自補助 | 各地域の漁業者・団体 | 変動 | 変動 | 地方創生連動の支援枠 |
どの補助金を使うべき?制度比較チャート
補助金制度は複数ありますが、「自分の立場」や「導入目的」によって最適な制度は異なります。
ここでは、漁業者・企業・自治体それぞれに合った選び方を整理します。
対象別に見るおすすめ補助金
| 立場・組織タイプ | 適した補助金 | 主な支援内容 | ポイント |
| 個人漁業者・小規模漁協 | 水産業・漁村活性化交付金(地域申請) | IoT給餌機・センサー導入など | 自治体と連携して申請 |
| 中規模漁協・漁業団体 | スマート水産業普及推進事業 | スマートブイ・AI魚群探知・データ共有 | 実証型プロジェクトで採択率高い |
| 水産加工・流通企業 | ものづくり補助金 | AI品質検査・自動梱包・データ管理 | 水産加工業の効率化・省人化に最適 |
| 自治体・連携組織 | 地方創生推進交付金 | データ基盤整備・地域波及型支援 | 他地域との連携で評価が上がる |
目的別に見る補助金の使い分け
| 導入目的 | 向いている制度 | 活用例 |
| 作業の自動化・省力化 | スマート水産業普及推進事業 | 自動操船・AI給餌装置導入 |
| 漁場環境データの可視化 | 水産業・漁村活性化交付金 | IoTセンサー・水温/塩分モニタリング |
| 水産加工・販売の効率化 | ものづくり補助金 | AI検品・ロス削減・需要予測 |
| 地域全体のスマート化 | 地方創生交付金・自治体補助 | データ連携・スマート漁港構想 |
このように整理すると、「自社・自団体がどの制度を使えるか」が明確になります。
一方で、採択されるためには事業計画書の完成度やAI活用の波及効果が大きなカギになります。
補助金申請を成功させる企業や漁協は、単に「設備導入」だけでなく、“現場課題のデータ化 → 改善提案 → 教育・定着”までを一体で計画しています。
- 現場の課題を数値化して説明する
- AI・IoT導入による改善効果を可視化する
- 事業計画書に「人材育成」「継続的運用」を含める
補助金の申請ステップと採択のコツ
スマート漁業の補助金は、設備や技術導入を支援する強力な制度ですが、採択されるためには「明確な目的」と「波及効果を示す事業計画」が欠かせません。
ここでは、一般的な申請の流れと、採択されやすいポイントを解説します。
申請から交付までの流れ
| ステップ | 内容 | 重要ポイント |
| ① 公募情報の確認 | 農林水産省・水産庁・自治体のサイトをチェック | 年度・締切・様式の最新版を確認 |
| ② 事業計画書の作成 | 導入目的・課題・費用対効果を明確化 | “データで課題を可視化”する記載が有効 |
| ③ 申請・審査 | 書類審査・ヒアリング | 採択率を上げるには波及性と地域連携を強調 |
| ④ 交付決定・契約 | 交付決定後に正式発注 | 決定前に発注すると対象外になるため注意 |
| ⑤ 実施・実績報告 | 補助金支出後の報告書提出 | 期限遵守・領収書整理が必須 |
補助金は年度ごとに公募時期が異なり、募集期間が短いことも多いため、早めに事業計画を準備しておくことが採択への第一歩です。
採択される事業計画書の3つの共通点
- 課題がデータで説明されている
「燃料費高騰」「労働時間の増加」などを定量化して示すと説得力が高まります。 - AI・IoT導入による効果が明確
「作業時間を◯%削減」「漁獲量を◯トン増加」など、成果指標を設定しましょう。 - 地域波及効果がある
自団体だけでなく、地域の他漁協や若手漁業者への波及を意識した構成が評価されやすいです。
補助金は“実証”と“普及”を重視するため、AI活用・人材育成・データ共有を盛り込むと採択率が上がります。
申請でよくあるミスと注意点
- 交付決定前に発注してしまう
→ 対象外経費になる可能性。契約・購入は交付決定後に行う。 - 経費区分の誤り
→ 機器費・委託費・旅費など、明確に区分して計上。 - 報告書の不備や提出遅延
→ 期日を守らないと補助金の返還対象になる場合あり。
採択率を上げる“AI視点”の活用
AIやデータ分析を事業計画に組み込むことで、「単なる設備導入」から「現場改革」への一歩を示すことができます。
- AI魚群探知・自動操船による省力化
- IoTセンサーで漁場データを蓄積・分析
- 生成AIで報告書・日誌を自動化し、事務負担を軽減
このような“デジタル活用+省人化+教育”のセットを描くことで、採択の評価が高まりやすくなります。
導入して終わりにしないために|“人材育成”が成功を左右する
補助金を活用してAI・IoT機器を導入しても、「それを使いこなせる人がいない」という壁に直面するケースは少なくありません。
センサーやAIがデータを収集しても、現場で分析・判断できなければ、真の意味での“スマート化”は実現しないからです。
たとえば、スマートブイが漁場の水温や潮流を自動で測定しても、そのデータを「どう漁獲判断に活かすか」は人の理解とスキルにかかっています。
つまり、機械の導入と同じくらい重要なのが、現場でデータを読み解く力=AIリテラシーなのです。
AIリテラシーを持つ“現場の人材”が鍵になる
スマート漁業の実証事業で成果を上げている地域では、現場スタッフ自身がAIを操作・分析できる仕組みを整えています。
たとえば、漁獲データをAIで可視化し、最適な操業スケジュールを判断する、あるいは、給餌の自動制御データを基に飼育環境を改善するなど、日常業務の中でAIを“相棒”として活かしているのです。
こうしたスキルを持つ人材が増えることで、 補助金で導入した設備が単なる“展示物”ではなく、利益を生む仕組みとして定着します。
補助金×AI教育=持続可能な水産業への第一歩
スマート水産業のゴールは、設備導入ではなく持続可能な経営モデルの構築です。
AI技術を扱える人材を育てることで、現場の判断力とスピードが高まり、次の補助金申請や新技術導入にもスムーズに対応できるようになります。
まとめ|補助金を活かして“持続可能なスマート水産業”へ
スマート漁業を支援する補助金は、AI・IoT導入の大きな追い風になります。
しかし、本当のスタートは“導入が終わってから”です。
データを活かし、現場が自立して運用できる体制をつくることこそが、 補助金を「一過性の支援」ではなく「持続的な成長戦略」に変える鍵です。
国や自治体の制度を活用しながら、AI技術と人材育成を組み合わせた“仕組みの変革”を進めることで、
漁業の未来はより安定し、次世代へつながる形へと進化していきます。
設備 × データ × 人材育成
この3つをバランスよく整えることで、補助金の効果は何倍にも広がります。
スマート水産業は、単なる技術導入ではなく――
「現場を変える経営改革」そのものです。
よくある質問|スマート漁業・水産業の補助金申請で知っておきたいポイント)
- Qスマート漁業・水産業の補助金は、個人でも申請できますか?
- A
個人漁業者でも申請可能な制度があります。
たとえば「水産業・漁村活性化交付金」は、自治体や漁協を通じての共同申請が前提となるため、
単独ではなく「地域単位」での応募が基本です。
一方、「ものづくり補助金」は中小企業・個人事業主も対象になるため、水産加工・販売などを営む場合は活用できます。申請前に、所属する漁協や自治体の水産課に相談するとスムーズです。
- QどんなAI・IoT導入が補助金の対象になりますか?
- A
対象は幅広く、「生産性向上」「省力化」「データ活用」につながる技術が対象になります。
主な例として、- スマートブイや水質モニタリングシステム
- AI魚群探知機・自動操船システム
- AI給餌機や水産データ共有プラットフォーム
- 漁獲データのAI解析、業務報告の自動化
などが挙げられます。
機器だけでなく、「データ分析・教育・運用管理」を含む取り組みも補助対象になる場合があります。
- スマートブイや水質モニタリングシステム
- Q補助金の公募はいつ頃行われますか?
- A
国の事業(スマート水産業推進事業など)は、毎年春〜夏にかけて公募されるのが一般的です。
自治体独自の補助制度は、年度予算の成立後(4月〜6月)に募集が始まることが多いです。
ただし、補正予算による追加公募もあり、時期は毎年変動します。最新情報は、水産庁や各自治体の公式サイトで必ず確認しましょう。
- Q申請書類の作成は難しいですか?支援してくれる機関はありますか?
- A
事業計画書の作成には専門的な知識が求められますが、各地域の「地方水産研究センター」や「漁協連合会」、「商工会議所」などで相談窓口が設けられています。
また、AI導入や人材育成を含む場合は、専門企業や研修会社にサポートを依頼するケースも増えています。
- Q導入後に成果を出すには、何を意識すればよいですか?
- A
補助金は「導入支援」であって、成果を保証するものではありません。
最も重要なのは、データを活かして改善を続ける文化をつくることです。
AI・IoTを導入しただけで終わらせず、現場のスタッフが自分たちでデータを分析・判断できるようになることで、補助金の効果は継続的に発揮されます。