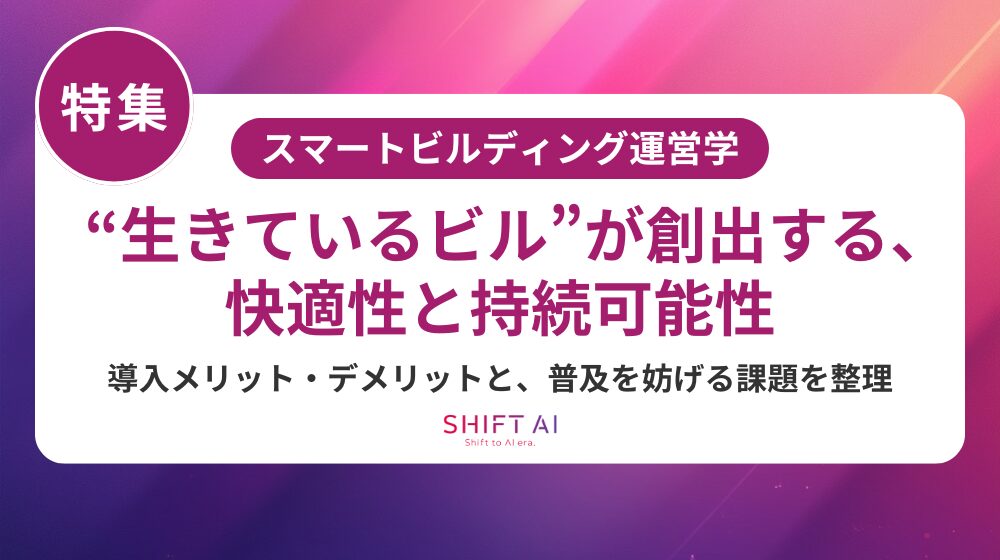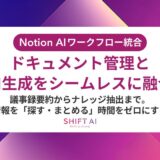スマートビルの導入は、エネルギー効率化・働きやすさ・BCP強化など、多面的な価値をもたらす“未来への投資”です。
しかし、現場で導入を検討する際に必ず直面するのが、初期費用の高さ。
AI・IoT機器やBEMS、再エネ設備を組み合わせた高機能なビルは、一般的なオフィスビルよりもコストが数割高くなります。
そのため、今、多くの企業が注目しているのが「補助金・助成金を活用したスマートビル導入」。
国のGX政策やZEB推進により、経産省・環境省・自治体が補助金制度を拡充しており、うまく活用すれば導入コストの2〜3割を公的支援で賄うことも可能です。
ただし、制度ごとに対象要件や申請時期、審査ポイントが異なり、理解が浅いまま進めると「せっかく準備したのに対象外だった…」という失敗も少なくありません。
本記事では、
- 2025年度に利用できる主要なスマートビル関連補助金の一覧
- 採択される企業が押さえている申請のコツ
- 導入後のROIを高めるための“AI×人材育成”戦略
を実務目線で解説します。
単なる制度紹介ではなく、「補助金をどう使えば経営インパクトを最大化できるか」まで掘り下げます。
関連記事:
スマートビルディング(スマートビル)とは?AI×IoTで変わる次世代ビル管理の仕組みと導入メリット
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
スマートビルと補助金の関係|なぜ今“政策対象”になっているのか
スマートビルは、単なる「高機能ビル」ではありません。
省エネ・デジタル制御・快適性の向上を同時に実現する“次世代型インフラ”として、いま国の主要政策のひとつに位置づけられています。
その背景には、政府が掲げる「ZEB(ゼロエネルギービル)」推進や「GX(グリーントランスフォーメーション)」、そして2050年カーボンニュートラル達成という大きな流れがあります。
ZEB・GX政策・カーボンニュートラルが後押し
日本政府は建築分野を「エネルギー消費削減の主戦場」として位置づけ、 ZEB化(建物の年間一次エネルギー収支ゼロ化)を2030年までに標準化する方針を明確にしています。
この動きを受けて、経産省・環境省・国交省では以下のようなスマートビル関連補助金を継続的に拡充しています。
- 省エネルギー投資促進支援事業(経産省)
- ZEB実証事業(環境省)
- 建築物省エネ改修推進事業(国交省)
つまり、スマートビル化は国のエネルギー政策そのものの一部であり、補助金はその推進装置として機能しています。
スマートビル=「省エネ+デジタル制御+快適性向上」の総合施策対象
かつては「高断熱・高効率設備」が中心だった補助金も、今ではAIやIoTを用いたデジタル制御・自動最適化を含むものが増えています。
BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)、人感センサー、CO₂濃度連動空調など、AIを活用した自律的制御があるほど評価が高まる傾向にあります。
そのため、スマートビルの導入は「補助金の対象」になるだけでなく、 “AI活用の進捗度”が採択評価に影響する時代に入っています。
関連記事:スマートビルディング(スマートビル)とは?AI×IoTで変わる次世代ビル管理の仕組みと導入メリット
→ “補助金が適用されるスマート機能”を理解するのに最適な基礎解説
補助金を使うとROI(投資回収率)が大幅に変わる理由
スマートビル導入は、設備費用だけで数千万円規模に及ぶケースが一般的です。
しかし、国や自治体の補助金を活用することで実質投資額が2〜3割軽減され、 ROI(投資回収率)は大きく改善します。
例えば、省エネ性能の高い空調やBEMSの導入で年間光熱費を10〜20%削減できる場合、
補助金によって初期費用を抑えることで、回収期間を5年から3年に短縮できることも珍しくありません。
単なる“コスト削減”ではなく、「持続的な経営投資」として機能するのです。
各自治体がスマートビル建設を後押しする“経済活性化”の狙い
北九州市や新潟市をはじめ、地方都市でも「スマートビル建設促進補助金」が相次いで創設されています。
背景には、地域経済の活性化・オフィス需要の再生・脱炭素都市の実現という明確な目的があります。
自治体としても、企業誘致や再開発の呼び水としてスマートビル建設を支援することで、
人材・資本を呼び込み、都市競争力を高める狙いがあります。
今後もこうした補助金は全国に拡大していくと見られ、 「どの地域で、どんな制度を組み合わせられるか」が企業の戦略的判断材料になっています。
補助金を活かして“導入で終わらせないスマートビル化”を実現するには、 導入後にAIを使いこなす人材育成が欠かせません。
【2025年度版】スマートビル関連の主要補助金・助成制度一覧
スマートビル導入を検討する際、最も気になるのが「どんな補助金が使えるのか」。
しかし、実際には制度が複数の省庁・自治体にまたがり、対象や補助率がバラバラなため、全体像を把握しにくいのが実情です。
ここでは、2025年度に利用可能な主要な国の制度と地方自治体の代表的な補助金を横断比較形式で整理しました。
とくにAI経営総合研究所として注目したいのは、AI制御・BEMS・IoT設備など“デジタル制御型の省エネ設備”が補助対象に含まれるかどうかです。
この観点を明示することで、経営層が「どの制度を優先すべきか」を判断しやすくします。
国の主要補助金制度(経産省・環境省・国交省)
| 制度名 | 所管 | 補助率 | 主な対象 | ポイント |
| 省エネ投資促進支援事業(SII) | 経済産業省 | 最大1/2 | BEMS、AI制御照明、空調、IoT計測 | スマート制御設備・AI連携に強く、最も汎用性が高い制度。中堅・中小企業も対象。 |
| ZEB実証事業 | 環境省 | 最大2/3 | 新築・改修時のZEB化プロジェクト | CO₂削減率・AI制御度が採択評価に直結。設計段階からZEBプランナー関与が必要。 |
| 建築物ストック活用推進事業 | 国土交通省 | 1/3〜 | オフィス・商業施設の改修、設備更新 | 既存ビルのスマート化・省エネ改修向け。IoT空調やエネルギー監視システムも対象。 |
ポイント解説:
この3制度は相互補完的に活用できるのが特徴です。
例えば、既存オフィス改修では「建築物ストック活用推進事業」で躯体改修を、AI制御設備導入では「省エネ投資促進支援事業」で設備費を補助、といった組み合わせも可能。
また、ZEB実証事業は採択率が低めですが、採択されれば補助率・効果ともに圧倒的です。
地方自治体の注目制度(2025年度公募予定含む)
| 自治体 | 制度名 | 対象・要件 | 補助率・上限 | 特徴 |
| 北九州市 | 次世代スマートビル建設促進補助金 | 小倉・黒崎地区で延床500坪以上の新築ビル | 20%・上限10億円 | AI制御・環境性能を重視。都市再生型スマートビルを後押し。 |
| 新潟市 | スマートビル建設促進補助金 | 新潟都心地域での新築・建替え。天井高・OA床・面積要件あり | 固定資産税課税標準額の20%・上限10億円 | 建築仕様中心。ZEBでなくとも都市機能高度化目的で対象。 |
| 東京都 | 中小企業等脱炭素化促進事業 | 中小ビル・店舗のスマート制御、省エネ設備導入 | 最大1/2(上限2,000万円) | BEMS、AI照明、IoT空調など“デジタル制御型省エネ”も対象。 |
補助金制度の俯瞰比較と選定のコツ
他メディアが「制度名の紹介」で止まっている中、AI経営総合研究所では以下の視点で整理しています。
| 比較軸 | 国系補助金 | 自治体系補助金 |
| 対象範囲 | 全国(中小〜大企業まで) | 指定地域・市内限定 |
| 対象分野 | 省エネ・ZEB・スマート制御 | 建築・都市再生・地域振興 |
| AI/BEMS対応度 | 高(ZEB・SIIなどで評価項目) | 地域による(北九州・東京が高評価傾向) |
| 補助率・上限 | 高い(最大2/3) | 中程度(上限1〜10億円) |
| 採択率の傾向 | 書類精度が重要。技術評価中心 | 地元事業・再開発案件に有利 |
選び方のヒント:
- AI・データ活用を含めた総合的スマート化を目指すなら「SII」「ZEB実証事業」。
- 地域再開発・新築ビル建設なら「北九州・新潟」などの自治体系補助金。
- 中小規模・省エネ改修型なら「東京都事業」などが狙い目。
申請前に押さえておくべき実務チェックリスト
- 対象期間:公募時期(例:2〜5月)が集中。年度計画に余裕を。
- 対象設備:AI制御・IoT機器の補助可否を要確認。
- 社内体制:設計・設備・経理・情シスの連携体制が必須。
- 効果測定:CO₂削減・光熱費削減の見込みを数値化。
- 運用フェーズ:導入後の人材育成・運用設計を事前に想定。
補助金は「導入支援」で終わりではありません。
AI制御設備を最大限に活かすには、運用を担う人材のAIリテラシーが不可欠です。
補助金の申請ステップと実務フロー|採択率を上げる3つのコツ
スマートビル関連の補助金は、設備投資額が大きいだけに申請から採択・交付までのプロセス管理が極めて重要です。
「書類を出せば通る」と思われがちですが、実際は書類精度と事業計画の“定量性”が採択率を大きく左右します。
ここでは、主要制度に共通する申請の流れと、採択率を高める実務ポイントを整理します。
申請の流れ(共通プロセス)
スマートビル導入に活用できる補助金(経産省・環境省・自治体系)は、基本的に以下のフローで進行します。
途中で「申請書を作ったのに提出できない」「交付決定が間に合わない」といったトラブルを防ぐためにも、全体像を俯瞰して準備を進めることが肝心です。
- 公募要領を確認
- 各制度(SII・環境省・自治体サイトなど)の公募要領・交付規程を精読。
- 補助対象経費・申請期間・事前協議要否などを早期に確認します。
- 特に自治体系は「着工前30日までの事前協議」が必須の場合があるため要注意。 - 事業計画書・見積書の作成
- 補助金の審査では、CO₂削減効果・省エネ効果・費用対効果の定量データが求められます。
- 見積書は内訳明細付きで提出が必要。BEMSやIoT機器の構成を明示しておくと評価されやすいです。 - 電子申請
- 経産省・環境省案件は 「jGrants」、自治体補助金は専用フォームや郵送提出が中心。
- 電子申請アカウントの発行・電子署名登録など、前準備にも数日を要します。 - 採択・交付決定
- 審査は通常1〜2か月。CO₂削減率・AI制御度・費用対効果が主な評価項目です。
- 交付決定後に契約・着工が可能になります。 - 実績報告・補助金交付
- 工事完了後、実績報告書・検収書類・効果測定結果を提出。
- 不備があると交付が遅延するため、現場写真・計測データ・稼働ログの保存が重要です。
採択率を高める3つのポイント
① 省エネ・CO₂削減効果を“数値”で示す
補助金の審査では、「どれだけの効果を得られるか」を定量的に説明できるかが最大のカギです。
例:
- BEMS導入で空調稼働率を20%削減
- AI照明制御により年間電力使用量15%削減
- 再エネ併用でCO₂排出を年間30t削減
こうした数値を事業計画書に明示し、グラフやシミュレーション図で視覚化することで採択率は格段に上がります。
② AI・IoT活用計画を盛り込む
最近の制度では「AI・IoTによる自動最適化」「データ分析による省エネ効果検証」などが加点要素として明記されています。
単なる設備更新だけでなく、“データ活用設計”を含めた提案が評価されやすい傾向にあります。
例:
- AI学習による空調制御の自動最適化
- IoTセンサー連携によるリアルタイム監視
- エネルギーデータをクラウド蓄積して経営層へレポート
“AI活用の仕組み”を明確に書けるかが、同業他社との差を決めます。
③ 運用フェーズの「人材育成計画」を添付する
見落とされがちですが、導入後にシステムを運用できる人材体制をどう構築するかも評価ポイントの一つです。
特に国系の補助金では「省エネ効果の持続性」を重視するため、 AI活用・データ分析を担う人材育成プランを添えるとプラス評価になります。
たとえば、AI経営総合研究所が提供する生成AI研修・AI活用人材育成プログラムを活用し、
「導入後も継続的に効果検証と改善を行う体制を構築」と示すだけでも、採択側に“持続的運用意識”を印象づけることができます。
補助金活用で見落としがちな“3つの注意点”
補助金はうまく使えば初期投資を大幅に抑えられる一方、 「制度の細部を見落としていた」「報告対応が想定外に大変だった」など、
運用フェーズでつまずくケースも少なくありません。
ここでは、現場で起こりやすい3つの注意点を押さえておきましょう。
① 対象外設備に注意(既存改修や一部ソフトウェアは非対象)
多くの制度で補助対象となるのは「新規導入する省エネ・AI制御設備」に限られます。
既存設備の軽微な改修や、クラウド利用料・ソフトウェア単体などは対象外となる場合が多く、 申請段階で“どこまでが対象経費か”を精査することが不可欠です。
特に注意が必要なのは以下のケースです。
- 既存空調にセンサーだけ追加 → 非対象の可能性大
- SaaS型エネルギー管理ツール → ソフト単体では対象外
- リース契約・中古機器 → 多くの制度で補助不可
補助金の対象範囲は「設備の新規導入+付帯工事+設計費」が中心。
導入効果を最大化するためにも、申請前に設備構成を整理しておくことが重要です。
② 申請タイミングを逃すと翌年度まで待つ(多くは年度初公募)
スマートビル関連補助金は、年度初(例年2〜5月)に公募が集中します。
締切後は次の募集まで約1年待ちとなるケースも多く、タイミングを逃すと導入計画全体が後ろ倒しになります。
特にZEB実証事業やSII補助金は、設計段階から申請書を用意する必要があり、 「工事計画が固まってから動く」では間に合わないこともしばしば。
経営会議で導入が検討され始めた時点で、 補助金スケジュールを並行管理する体制を整えておくことが成功の鍵です。
③ 報告・監査対応の負担(運用ルールの社内整備が必要)
採択後に待っているのが、「実績報告と監査対応」。
工事完了後には、機器導入の証憑書類、エネルギー使用量の報告、稼働データの提出など、 複数の報告業務が発生します。
このとき課題になるのが、社内のデータ収集・記録体制の不備です。
多くの企業では現場担当者がExcelや紙で管理しており、報告ミスや二重入力が発生しがちです。
ここで有効なのが、
- AIによる自動データ集計ツール(稼働ログやCO₂削減量を自動算出)
- クラウド上の報告テンプレート管理(部署間でのデータ共有効率化)
など、補助金運用フェーズを見据えたデジタル管理体制の導入です。
AI経営総合研究所では、こうした報告負担の軽減に直結するAIリテラシー研修・運用設計支援も提供しています。
補助金の“書類通過”だけでなく、“成果を出す運用体制”まで構築できることが、長期的なROI最大化につながります。
補助金は“申請して終わり”ではありません。
導入後にデータを正確に扱い、成果を検証できる人材と仕組みこそが本当の成功要因です。
補助金×AI活用で実現する“ROI最大化スマートビル”
補助金の目的は「導入コストを減らす」ことではありません。
本来の価値は、データを活かしたビル経営の基盤をつくる“初期投資”にあります。
スマートビルは、省エネ設備を入れただけでは成果が出ません。
AIとセンサーがつながり、リアルタイムで最適制御を行い、 その結果がデータとして蓄積され、経営判断や設備保全に還元されてはじめて“投資効果”が生まれます。
補助金は単なる費用削減ではなく、データ駆動型ビル経営の初期投資
多くの企業は「補助金=助成金=安くする手段」と捉えがちです。
しかし本質は、“AIで自律的に学習・最適化する仕組み”を組み込む初期投資にあります。
BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)やIoTセンサーは、 導入後の運用データを資産化できるという点で、ROIを年々拡大させる設備です。
たとえば、
- 照明・空調のAI制御による電力使用量削減
- 利用率データに基づくフロア再配置でオフィス稼働効率UP
- 設備の異常検知によるメンテナンスコスト削減
これらの効果を定量的に可視化できる環境を整えることこそ、補助金を“経営投資”に変える鍵です。
省エネ・快適性・人材定着・設備保全すべてをAIが最適化
スマートビルの価値は、省エネだけにとどまりません。
AIによって以下のような領域が最適化され、総合的な経営効果が得られます。
| 領域 | AI活用による効果 |
| 省エネ | 照明・空調の自動最適制御で電力コスト削減 |
| 快適性 | 温湿度・CO₂・照度データによる空間環境の均質化 |
| 人材定着 | 快適なオフィス環境と柔軟な働き方の両立で満足度向上 |
| 設備保全 | センサー連携で異常を予兆検知し、修繕コスト削減 |
補助金で導入した設備を“運用フェーズ”で最大限に活かすためには、 データの読み解き方を理解し、改善を継続できるAIリテラシーを持つ人材が不可欠です。
成功する企業の共通点:「導入→運用→教育」の3ステップでROIを高めている
上位採択企業や成功事例を分析すると、どの企業にも共通しているのが 「導入 → 運用 → 教育」という3ステップの継続的サイクルです。
- 導入:補助金を活用してAI・BEMS・IoT基盤を整備
- 運用:データ分析で最適化を繰り返し、省エネ・快適性・生産性を数値で可視化
- 教育:現場・管理職・経営層がデータを活用できるようAI研修を実施
この「教育」フェーズが欠けると、AI制御設備の真価は発揮されません。
逆にここを強化できた企業ほど、補助金終了後も高いROIを維持しています。
地域別制度の比較と選び方|北九州・新潟・東京の違い
スマートビル関連の補助金は、国の制度だけでなく、自治体ごとに条件や狙いが大きく異なります。
ここでは、実際に注目度の高い北九州市・新潟市・東京都の3制度を比較し、 「自社に最適な制度はどれか?」を判断できるように整理しました。
地域別比較一覧
| 項目 | 北九州市 | 新潟市 | 東京都 |
| 補助対象 | 新築・建替え | 新築・建替え | 改修・設備更新 |
| 対象機能 | ZEB・AI制御 | 都市機能高度化 | 省エネ制御・IoT |
| 補助率 | 20%(上限10億円) | 固定資産税課税標準額の20% | 最大1/2(上限2,000万円) |
| 特徴 | 都市再生型・大規模案件向け | ハード仕様中心・建築要件重視 | 中小企業・既存ビル対応・省エネ効果重視 |
| 想定企業規模 | 大企業・開発事業者 | 地場ゼネコン・都市開発事業者 | 中堅・中小企業、ビルオーナー |
| AI/BEMS適用性 | 高(AI制御・ZEB設計で加点) | 低〜中(AI要件なし) | 中(BEMS・IoT対象) |
| 制度目的 | 都市再生・企業誘致 | 都心機能強化 | 中小の脱炭素化・省エネ支援 |
制度の狙いと適用イメージ
■ 北九州市:都市再生型スマートビルモデル
北九州市は、「中心市街地の再生・企業誘致」を目的とした大規模開発型の補助金制度。
延床500坪以上・高環境性能・AI制御設備などが条件で、スマートビルのショーケース化を狙っています。
AI活用・ZEB設計を重視しており、最もスマートビルらしい“未来志向型”補助金です。
推奨対象:デベロッパー・不動産企業・大企業の本社ビル開発案件
■ 新潟市:都市機能高度化を目的とした“ハード仕様型”
新潟市は「新潟都心地域での建築物性能向上」を目的とし、 OA床・天井高・面積など建築仕様のハード要件を重視しています。
ZEBやAI制御がなくても申請可能ですが、逆に言えばIoT・AI導入を加点要素として活かせる余地があるとも言えます。
推奨対象:地場建設業・設計事務所・民間オフィス再開発プロジェクト
■ 東京都:中小企業の“既存ビルスマート化”支援
東京都の「中小企業等脱炭素化促進事業」は、全国でも数少ない既存建物改修対応型の補助金。
AI制御照明、BEMS、IoT空調などデジタル制御型設備導入に強い制度です。
中小ビルオーナーや店舗事業者でも利用しやすく、実務的・短期回収型の支援策といえます。
推奨対象:中堅・中小企業、既存オフィス・店舗をスマート化したい企業
どの制度を選ぶべきか?経営判断の3軸
AI経営総合研究所では、制度選定を「規模・目的・運用体制」の3軸で考えることを推奨しています。
| 判断軸 | 適した制度 | ポイント |
| ① 規模 | 大規模新築なら「北九州」/中小改修なら「東京」 | 投資額と補助上限を照合してROIを算出 |
| ② 目的 | 都市再生・象徴性重視=北九州/地域機能強化=新潟/コスト削減=東京 | 制度目的と企業の経営課題を一致させる |
| ③ 運用体制 | AI運用人材が社内にいない場合は「東京型」で小規模導入→段階拡大 | 補助金後の運用まで見据えた体制設計が重要 |
補助金を“投資”に変えるための社内準備
補助金は「申請して終わり」ではなく、企業の経営戦略に組み込むことで初めて真価を発揮するものです。
採択される企業ほど、単なる制度活用ではなく、“経営計画の一部として補助金を位置づけている”のが特徴です。
ここでは、社内で稟議を通しやすくするために押さえるべき3つの要素を整理します。
社内稟議を通すための3要素
① 補助金概要+ROI試算
まずは「どんな補助金を活用すれば、どの程度の投資回収効果があるか」を明確に示します。
- 補助金の名称・補助率・上限額
- 投資額と補助後実質負担の比較
- 光熱費・メンテナンス費削減によるROI改善シミュレーション
経営層は“制度の複雑さ”よりも“投資の回収見通し”に関心を持っています。
数値で投資効果を見せることが、稟議を通す第一歩です。
② 設備+AI活用構想(データ利活用設計)
次に必要なのが、「補助金で導入する設備をどう活かすか」のストーリーです。
AIやIoTを活用したビル制御をデータ経営の一部として組み込む構想を描くことで、 単なる「省エネ設備導入計画」から「経営DXの一環」へと格上げできます。
例:
- BEMSデータを経営ダッシュボードに統合
- 設備稼働ログをAI分析し、稼働率・快適度を定期レポート化
- テナント満足度向上と同時にエネルギーコスト削減を実現
こうした“データ利活用設計”があるだけで、補助金活用の説得力が大きく高まります。
③ 人材育成計画(AI人材/ビル運用担当)
設備がどれほど高性能でも、運用できる人材がいなければROIは生まれません。
導入初期から「運用・分析・改善」を担う担当者を定め、AI活用スキルを育成しておくことが不可欠です。
AI経営総合研究所では、 スマートビル運用に必要なデータ分析・AI制御理解・改善提案力を育てる 生成AI活用研修プログラムを提供しています。
補助金を活かしきるための“最後のピース”が、この人材育成計画です。
「補助金を取るための書類」ではなく「経営計画の一部」にする発想
多くの企業が陥るのが、「補助金申請書=補助のための書類」として扱ってしまうこと。
しかし本来は、中期経営計画やGX戦略の延長線上にある“投資計画書”として整理することが重要です。
補助金の採択基準も年々「経営への波及効果」や「継続的な省エネ効果」など、経営的視点を重視する方向にシフトしています。
つまり、“制度を取る”のではなく、“経営を変えるために制度を使う”という発想が必要なのです。
導入後の活用まで見据えた“攻めの補助金戦略”へ
スマートビル導入は、設備を入れて終わるものではありません。
補助金を起点に、AIを使いこなし、データを経営に還元できる組織に進化することが、
ROIを最大化する唯一の道です。
今こそ、「コスト削減」から「投資拡張」へと視点を切り替え、 AI×人材育成による“攻めの補助金戦略”を社内に根付かせましょう。
まとめ|補助金を活用して“未来志向のスマートビル化”を実現
スマートビル導入における補助金は、単なるコスト削減の手段ではありません。
それは、AI・IoT・省エネ制御といった新しい技術を活用し、 企業の生産性を未来志向で高めるための“戦略的投資”です。
成功している企業に共通するのは、 補助金で設備を整えるだけでなく、AI・人材・運用体制を三位一体で整備している点。
設備がデータを生み、AIが最適化し、人がその結果を読み解く。
この循環ができたとき、初めて「補助金がROIを生む投資」に変わります。
そしてもう一つ忘れてはならないのが、導入後の“運用定着”です。
AI制御やデータ活用の成果を継続的に出し続けるには、 社内のAIリテラシーを高め、運用担当者が自律的に改善できる体制を築くことが欠かせません。
AI経営総合研究所では、 こうしたスマートビル導入後のフェーズを支援する生成AI活用人材育成研修を提供しています。
「導入して終わり」ではなく、「運用で成果を出す」ための体制づくりを、今こそ始めましょう。
- Qスマートビル導入で使える補助金にはどんなものがありますか?
- A
経済産業省の「省エネ投資促進支援事業」、環境省の「ZEB実証事業」、国交省の「建築物ストック活用推進事業」などが代表的です。
また、北九州市・新潟市・東京都など自治体でも独自のスマートビル支援制度があり、地域と目的に応じて複数制度の併用も可能です。
- QAI制御やBEMSの導入も補助対象になりますか?
- A
はい。最近の制度では、AI・IoT・BEMSなどデジタル制御による省エネ最適化設備が対象になるケースが増えています。
ZEB実証事業やSII補助金では、AI制御を活用することで採択評価が上がる傾向もあります。
- Q補助金は中小企業でも申請できますか?
- A
可能です。中小企業向けに特化した「中小企業等脱炭素化促進事業(東京都)」など、中小ビルや既存オフィスの改修支援も拡大しています。
設計事務所や施工業者と連携すれば、初めての申請でも対応可能です。
- Q申請から交付までどれくらい時間がかかりますか?
- A
申請から採択までは通常1〜2か月、交付まで含めると3〜5か月程度が目安です。
ただし、申請時期や審査件数により前後するため、年度初(2〜5月)の公募スケジュールを把握して早めに準備することが重要です。
- Q既存ビルを改修する場合でも補助金は使えますか?
- A
はい。新築だけでなく、既存ビルの改修・省エネ設備更新も対象になる制度があります。
特に「建築物ストック活用推進事業」や「東京都中小企業等脱炭素化促進事業」では、既存設備をAI制御型に更新する改修工事も対象です。