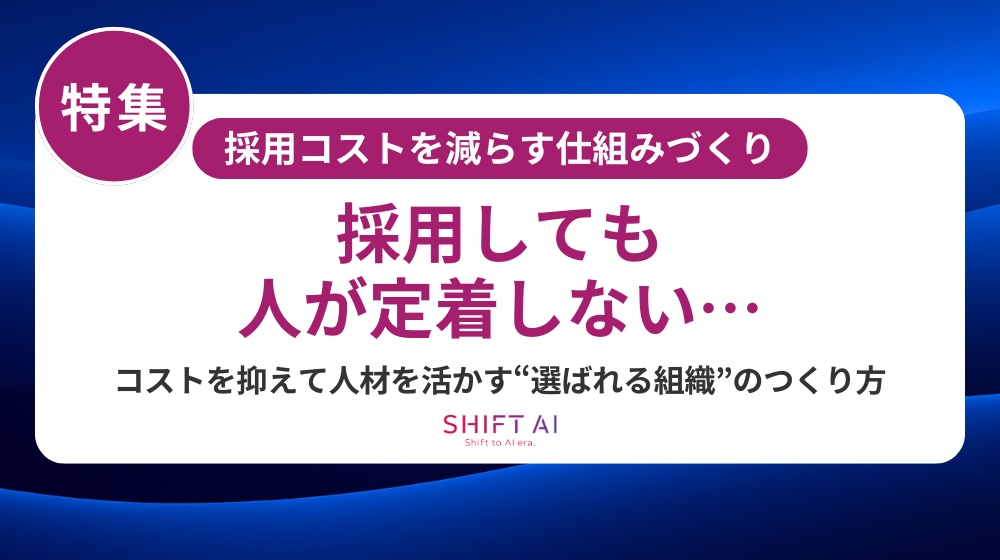採用コストが年々増えている。けれど、応募数は減る一方。
そんな声を、人事や経営層からよく耳にするようになりました。特に中小企業やベンチャーでは、広告費や人材紹介料が大きな負担となり、採用活動そのものが立ち止まってしまうケースも少なくありません。
しかし、採用コストは「かける/削る」の二択ではなく、「最適化する」時代へと変化しています。
そこで本記事では、
- 採用コストが膨らむ原因は何か?
- どこをどう見直せば、無理なく削減できるのか?
- 実際に成果を上げている企業は、何をしているのか?
…といった疑問に答えながら、「今日から実践できる12の削減策」をわかりやすく解説します。
また、最近注目されている生成AIを活用した採用業務の効率化や、採用コスト削減と相性の良い研修導入についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- なぜ採用コストが年々高騰しているのか?
- なぜ採用コストが年々高騰しているのか?
- 採用コストを削減する考え方|間違った節約で失敗しないために
- 採用コストを削減する具体的な方法12選【今すぐ実践できる現実解】
- 採用コスト削減の落とし穴とよくある失敗
- 採用コスト削減を成功に導く5つの実践ステップ【即実行できるロードマップ】
- まとめ:採用コストを削る前に、AIを活用して成果の出る仕組みを整えよう
- AI採用コストに関するよくある質問(FAQ)
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ採用コストが年々高騰しているのか?
人材採用にかかるコストは、近年ますます上昇傾向にあります。とくに中小企業やスタートアップにとっては、「1人採用するためのコスト=経営を左右する重大な投資」と言っても過言ではありません。
では、なぜこれほどまでに採用コストが高騰しているのでしょうか?その背景を、3つの視点から紐解いてみましょう。
① 求人広告費・紹介手数料が高騰している
有料の求人媒体は、掲載期間や表示回数に応じて課金されるモデルが主流です。しかし競合企業がこぞって広告費を増額している現在、市場全体の単価が上がっているため、これまでと同じ予算では「見つけてもらえない」状況が続いています。
さらに人材紹介会社経由の採用は、年収の30%前後が紹介料として発生するため、1名の採用で数十万円〜百万円単位の支出が必要になるケースも。
採用手段の選び方を誤ると、成果が出ないまま予算だけが消えていくリスクが高まります。
② 採用担当者の工数が肥大化している
広告出稿や応募者対応、日程調整、面接、評価、内定通知。採用活動は多岐にわたり、人事部の多くの時間が「事務作業」に取られているのが現実です。
特に少人数体制の企業では、「採用担当が別業務と兼務」というケースも多く、非効率なワークフローが慢性的な人件費増を招いています。
実際に、月20〜30時間以上の工数を定型業務に費やしている企業も少なくありません。
③ 出せば集まる時代の終焉
従来は「とりあえず大手求人媒体に出せば、一定数の応募が来る」時代でした。しかし現在では、求職者が情報を選別し、企業を比較・評価するのが当たり前になっています。
つまり、媒体に載せるだけでは母集団が形成できず、「採れないのにコストだけは増える」構造になっているのです。
加えて、若年層ほどSNSや動画コンテンツ経由で企業を探す傾向が強まり、媒体頼みの戦略は徐々に機能しなくなりつつあります。
採用コストの高騰は、単なる「費用の問題」ではなく、採用活動そのものの構造課題です。解決するには「仕組み」から見直す必要があります。
なぜ採用コストが年々高騰しているのか?
採用コストの増加は、単なる費用問題ではなく、事業成長・組織戦略そのものに深く関わる経営課題になりつつあります。
では、なぜここまで深刻化しているのか。その背景には、大きく3つの構造的な変化があります。
① 広告・紹介手数料の「単価インフレ」が止まらない
近年、求人広告の出稿単価は上昇の一途をたどっています。とくに有名媒体や人材紹介を活用する場合、1名の採用につき30万〜100万円超が相場となるケースも珍しくありません。
その理由は以下の通りです。
- 採用競争の激化による掲載枠のプレミア化
- 媒体側の値上げ(インプレッション・掲載料)
- ターゲット母数の減少による「競り負けリスク」
など、供給サイドと市場構造の変化が大きいのです。
結果として「コストをかけても人が集まらない」「無駄打ちで予算が消える」状況が続出してしまいます。
② 採用担当のリソースが分断型ワークで非効率になっている
実際の採用現場を覗くと、以下のような非効率な業務が生まれています。
- 求人票の作成(毎回ゼロから)
- 候補者対応やリマインド連絡
- 面接官との調整や議事録の共有
- 内定通知・書類送付…
上記のように、定型業務が膨大かつ属人的に積み上がっていることがわかります。
多くの企業ではこの業務に月30時間以上を要しており、人的コストとしては数十万円規模にのぼる計算です。特に「Excel・メール・人手」で回している企業ほど、コストが見えにくく、蓄積しやすい隠れ支出になっています。
③ 出せば集まる採用手法が崩壊し、戦略の更新が追いついていない
かつては「媒体に出せば数十件の応募」が当たり前でした。しかし今、求職者の行動は完全に変化しています。
- 情報の取得元:求人媒体 → SNS・動画・企業HP
- 判断軸:給与・待遇 → 働き方・企業の文化・ミッション
- 応募動機:募集内容 → 共感・ストーリー・人の魅力
これに対して、多くの企業は戦略を昔のまま続けてしまっているため、 「応募がこない」→「出稿額を上げる」→「費用は増えるが成果は出ない」という悪循環に陥っています。
今の採用は見つけてもらうだけでなく、選ばれる理由を構築する必要がある時代です。
採用コストの高騰=「仕組みの老朽化」が引き起こす必然
コストが高騰している理由は、単なる価格上昇ではなく、「採用チャネルの変化に対応しきれていない」「担当者のリソース設計が属人的かつ非効率」などの構造的な問題の集合体にあります。
だからこそ、ただコストを削るのではなく、「仕組みを見直し、戦略をアップデートする」ことが唯一の解決策なのです。
採用コストを削減する考え方|間違った節約で失敗しないために
「コストを削る」。言葉としてはシンプルですが、その選択にはリスクも責任も伴います。
とくに採用の現場では、「今月の広告を減らしたら応募がゼロになった」「紹介会社を切った途端、誰も来なくなった」というように、即効性の高い施策ほど、副作用も大きくなりがちです。
では、何を基準に「削る」「維持する」「投資する」を判断すべきか?ここでは、採用コスト削減の“考え方の軸”を、3つの観点から掘り下げていきます。
「安く済ませる」ではなく、「効果を最大化する」
削減という言葉に引っ張られて、「とにかく安く」という発想に偏ると、採用は必ず崩れます。
たとえば、広告費を月50万円→10万円に減らしたとします。
費用は減るかもしれませんが、それで応募がゼロになったら?
現場が人手不足のまま稼働し、他の社員が疲弊し、離職率が上がったら?
浮いた40万円どころか、数百万円規模の損失につながる可能性すらあるのです。
一方で、「1人あたりの採用コストは高かったけど、成果を出す人材が定着した」「媒体を見直して半額で同じ数を採れた」。こうした例も少なくありません。
つまり、削減とは「費用を切る」ことではなく、「費用対効果を引き上げる行動」なのです。
どこを削るべきかは、「見える化しないと判断できない」
採用にかかっている費用は、意外なほど把握されていません。求人媒体の出稿費や人材紹介料は見えやすいですが、以下の項目に注意が必要です。
- 採用担当の稼働時間
- 外部に発注している説明会スライドや動画の制作費
- スカウト送信の工数
こうした目に見えにくい工数や時間コストが積もっているのです。さらに悪いのは、「このへん、なんとなく高そうだから減らすか」と勘で削ることです。
こうして削ってはいけない部分を切り、放置していた無駄が残る。この逆転現象こそ、コスト削減失敗の最大要因と言えるでしょう。
だからこそまずやるべきは、分解して、分類して、把握する。見えなければ、精度の高い判断は絶対にできません。
コスト削減の本質は、「仕組みの再設計」にある
たとえばあなたの会社では、求人票をつくるとき、毎回1から文章を考えていませんか?説明会資料は、去年のパワポを引っ張り出して、人の手で直していませんか?
候補者とのやりとり、スケジュール調整、面接官への情報共有……すべて人力になっていませんか?
もし心当たりがあるなら、それは費用をかけていないように見えて、最大級のコストを払っている状態です。理由は、それらの業務は、仕組みによって自動化・内製化できるものだからです。
生成AIの活用、採用DXツールの導入、プロセス設計の見直し。これらは「何か特別なこと」ではありません。「人がやらなくてもいいことを、仕組みにやらせる」ただそれだけの発想なのです。
削減とは、節約ではなく戦略である
採用コストを削る。それは、未来の事業を守るための戦略です。
だからこそ、目先の「いくら浮いたか」だけで評価するのではなく、何を変え、何が持続するようになったかを軸に判断すべきです。
仕組みを変え、判断軸を変えれば、採用はもっと強く、持続的なものになります。「採用コストを減らす」ではなく、「採用の戦闘力を上げる」という考え方に近いのかもしれません。
採用コストを削減する具体的な方法12選【今すぐ実践できる現実解】
採用にかかるコストを減らしたい。そう願ってはいても、現場は日々の対応に追われて、なかなか改善に踏み出せない。
さらに、「何を削れば、成果が下がらないのか?」「どこまで削っていいのか?」などの判断に迷っている方も多いはずです。
そこでこの章では、中小企業・ベンチャーでもすぐ始められる12の具体策を厳選してお届けします。
単なる費用カットではなく、質・効率・定着を高めながら“最適化”する本質的な方法を、4つのカテゴリで整理しました。
カテゴリ1|採用チャネルを見直す(広告費・紹介料の抑制)
「求人広告を出す」「人材紹介会社に頼む」。これらは最も一般的な採用手段ですが、同時に最も高コストな手段でもあります。このカテゴリでは、今あるチャネルを見直すだけで、ゼロ円採用も目指せる方法を紹介します。
① リファラル採用を“仕組み”として制度化する
「誰か良い人いたら紹介して」では、リファラルは根付きません。制度として設計することで、ゼロ円で高精度な人材を採れるチャネルへと変わります。
紹介者へのインセンティブだけでなく、
- 過去の成功事例の社内共有
- 社員が使いやすい紹介テンプレートの配布
- 定期的なキャンペーン設計
など、「紹介したくなる仕掛け」がカギです。うまく仕組み化できれば、媒体広告に依存せず、カルチャーフィットする人材が集まりやすくなります。
② SNS(X・Instagram)で共感で集める採用広報を展開する
求人媒体では伝えきれない、企業の空気感や価値観です。それをダイレクトに届けられるのが、SNSの最大の武器です。
特にZ世代・ミレニアル世代の求職者は、求人票よりも「その企業で働く人たちのリアルな発信」に惹かれます。
- 社員インタビューのショート動画
- 現場風景のカジュアル投稿
- ストーリーズでの1日密着企画
こうした取り組みは、広告費ゼロでも“共感ドリブン”の母集団形成が可能です。予算が限られていても、SNSは立派な勝ち筋になります。
③ 求人媒体は使い続けるより見直して選ぶ
「昔から使ってるから」「営業に勧められて」。そんな理由で続けている媒体、ありませんか?
成果が出ていない広告に毎月数十万円かけるよりも、
- 直近半年の“応募数と採用数”を媒体別に振り返る
- CPA(1人あたりの採用コスト)を出してみる
- 成果が出ていない媒体は一時停止 or 成功報酬型に切り替える
といった見直しを行うだけで、ムダを削りながら成果を落とさないバランス設計が可能です。
カテゴリ2|プロセスを効率化する(人的コストの圧縮)
採用活動で最も見落とされがちなコストが、人事の時間です。1件ごとの日程調整、資料作成、連絡対応……。
こうした裏側の作業に膨大な人件費がかかっていることに、あなたは気づいていますか?このカテゴリでは、そうした人の手がやる前提の業務を効率化・自動化する方法をまとめました。
④ 採用資料や求人票は、生成AIで「内製×高速化」する
毎回、求人票や会社説明スライドをゼロから作っていませんか?
それ、もうAIが得意な仕事になっています。
たとえばChatGPTのような生成AIを使えば、
- 会社説明スライドの骨子を15分で作成
- 応募者対応メールを用途別にテンプレ化
- スカウト文面のA/Bパターンも即生成
というように、制作コストと時間を一気に圧縮できます。
⑤ 面接日程調整や連絡業務は、ツールで自動化できる
「面接の候補日を聞いて、調整して、リマインドして…」。人事が日々費やしているこの工数、実はまるごと自動化できます。
- ATS(採用管理システム)を活用して日程調整・進捗管理
- チャットボットによるリマインド・質問対応
- 一括メール送信で漏れを防ぐ
こうした仕組みを導入することで、採用1人あたりにかかる手間を半分以下に抑えられることもあります。人力からシステムへ。これもまた、コスト削減の王道です。
⑥ オンライン選考・録画選考で「時間」と「物理コスト」を省く
面接対応における、移動・会場・スケジュール調整の手間が問題です。これをオンライン選考に切り替えるだけで、1人あたりの採用コストを30%以上圧縮できる可能性があります。
さらに、一次面接を「録画提出→社内でまとめて評価」とすれば、
- 評価者の時間をスロットで分けて最適化
- 面接官複数名で一斉チェックが可能
- 候補者との接点も広がる
という、コストと質の両立が実現可能になります。選考のリアルにこだわる理由は、本当に必要か? 一度問い直してみてください。
カテゴリ3|人材のミスマッチを防ぐ(採用後の損失を減らす)
採用活動の最終ゴールは、「入社」ではなく「定着と活躍」です。どれだけ応募があっても、採った人がすぐ辞めてしまえば、それは失敗と同じです。
このカテゴリでは、採用後のロスを減らし、コストパフォーマンスを高める仕組み作りに焦点を当てます。
⑦ 採用要件を「戦略的に」見直す
応募が来ない、定着しない。このとき、安易に「媒体が悪い」「待遇を上げよう」と考えていませんか?
実は、そもそもの採用要件がズレているケースは少なくありません。
- 「求める人物像」がふわっとしている
- 現場と人事の評価基準がバラバラ
- スキル要件が過剰で母集団が狭まっている
採用要件は、職務設計 × 組織戦略 × 将来ビジョンの交差点です。ここを見直すことで、採るべき人材の解像度が上がり、無駄な応募も、早期離職も、減らせます。
⑧ 内定辞退・早期離職を防ぐオンボーディング設計
「採ったのに辞めた」ほど高い採用コストはありません。採用単価はゼロにできても、離職コストは倍になって返ってきます。
そこで重要なのが、オンボーディング(入社後の立ち上がり支援)です。
- 入社初日の不安を減らす事前フォロー
- 上司・先輩との1on1体制
- 評価制度やキャリアロードの明確化
これらが整っているかどうかで、定着率と戦力化スピードは大きく変わります。コスト削減の最終ラインは、「長く活躍してもらうこと」です。ここを忘れてはいけません。
カテゴリ4|組織・チーム体制を見直す(仕組み化・ナレッジ蓄積)
コストを削減するには、やり方を変えるだけでなく、「それを誰がどう回すか」まで設計することが不可欠です。
このカテゴリでは、採用を属人化から脱却させ、再現性のあるチーム運営へと進化させる考え方と手法を紹介します。
⑨ 採用代行(RPO)を一時的に活用して内製化を進める
「外注は高いから使わない」。そう決めつける前に、使い方を見直してみてください。
採用代行(RPO)は、すべてを任せる必要はありません。
- スカウトだけ任せる
- 日程調整だけ任せる
- 説明会の運営だけ任せる
といったパーツ委託で“ボトルネックだけ”を補う運用なら、無駄な採用媒体を続けるよりも、コスト効率は高くなる可能性大です。さらに、運用ノウハウを吸収すれば、将来的に完全内製化も視野に入ります。
⑩ 採用チームの内製化とスキル育成
属人化している採用業務。 「◯◯さんじゃないと求人票が書けない」 「面接の評価って、なんとなくで決まってる」そんな状態では、どれだけコストをかけても成果は出にくいのです。
採用力は、組織としてのスキルに変換することで初めて資産になります。
- 採用基準を明文化し、誰でも評価できるようにする
- スクリプトやテンプレートを整備して属人性を排除
- 面接官トレーニングを定期的に実施
こうした積み上げが、採用精度の向上とコスト効率を両立させるカギになります。
⑪ 採用活動のKPIを「コスト視点」で再設計する
あなたの採用KPIは、「応募数」や「面接設定数」で止まっていませんか?これからは、工数あたりのコスト効率をKPI化する視点が必要です。
- 1採用にかかった総時間 → 目標:〇〇時間以内
- スカウト返信率 → 効率化ツール導入で改善
- 採用単価 → 過去平均と比較して推移を追う
KPIにコスト軸を入れることで、手段ではなく成果へのコスト効率に目が向く組織文化が生まれます。
⑫ 生成AIを活用して「人がやらなくていい仕事」を手放す
採用業務には、
- 掲載文や社内メールのテンプレート作成
- 応募者管理台帳の更新
- 選考スケジュールの連絡
など、人がやらなくても回る仕事が山ほどあります。
ここを、生成AIで仕組み化するのです。AIは「人を減らす」ためではなく、「人を活かす」ために使える重要なソリューションです。
関連記事
「形だけの業務効率化」を脱却するには?改善の再設計ステップと生成AI活用術
採用コスト削減の落とし穴とよくある失敗
いい話ばかりではない。削減の裏にある見えない代償とは何でしょうか。
採用コスト削減に取り組む企業が増える一方で、「やってみたけど逆効果だった」「現場が混乱しただけだった」という声も少なくありません。
なぜそのような事態が起きるのでしょうか?そこには、3つのよくある落とし穴が存在します。
落とし穴①コストを“数字”だけで判断し、質が落ちる
たとえば、「媒体費を減らす」「広告掲載数を絞る」など、数字の削減だけを優先すると、母集団の質・量ともに低下するリスクがあります。
結果として、
- 応募者数が減る
- 条件に合う人が集まらない
- 再度広告出稿や人材紹介に頼ることになり、かえってコスト増に
削減=費用を抑えるではなく、費用対効果を高めるが本質であることを忘れてはなりません。
落とし穴②内製化を急ぎすぎて、現場が回らなくなる
「採用は社内でやれば安く済む」という考えで、採用代行や媒体依存をやめた結果、人事部がパンクし、かえって業務効率も成果も悪化したというパターンは多発しています。
内製化には、
- ノウハウの蓄積
- リソースの確保
- 運用体制の構築
この3つが欠かせません。これを怠ると、安くなった分、疲弊が増すという本末転倒に陥ります。
関連記事
生成AIを導入したのに仕事が増えた?原因と対策をわかりやすく解説
落とし穴③安かろう悪かろうなツールや代行業者を選ぶ
生成AIやRPAツールの選定、人材紹介業者の乗り換え時などによくあるのが、価格の安さだけで判断して失敗するパターンです。
- 精度が低く、かえって作業が増えるAIツール
- レスポンスが悪く、候補者体験を損なう外注先
- 導入後にカスタマーサポートがまったく機能しないケース
導入コストだけでなく、使いこなせるか・現場と連携できるかも見極めて選ぶ必要があります。
削減はゴールではありません。むしろ、正しく整えた先にある結果として削減があるというのが本質です。
採用コスト削減を成功に導く5つの実践ステップ【即実行できるロードマップ】
採用にかかるコストをただ減らすだけでは、長期的に意味のある成果にはつながりません。それどころか、母集団の質が落ちたり、現場の負担が増えて逆効果になったりするケースも珍しくありません。
だからこそ大切なのは、「どこをどう整えれば、自然とコストも最適化されるか」を戦略的に捉えることです。
ここからは、実際に多くの企業が成果を出している5つの実践ステップを、ストーリーに沿って詳しく紹介していきます。
ステップ①まずはどこにお金をかけているのかを把握する
何より先に必要なのは、現状の採用コストの内訳を洗い出すことです。求人広告や人材紹介にいくら使っているのか、自社内の人事工数はどれだけかかっているのか。あいまいなまま施策を打っても、どこがムダでどこが必要経費かが見えず、成果もブレてしまいます。
採用単価の変化やCPA(Cost Per Acquisition)の可視化も含めて、今のコスト構造を見える化することが出発点です。
ステップ②削る・活かすを見極めて、投資判断をつける
次にやるべきは、ただ安く済ませようとするのではなく、何にコストをかけるべきかを再定義すること。
「この媒体は応募数は多いが質が悪い」「人材紹介の成功率は高いが費用対効果は低い」
そんな視点で、削るべきもの、強化すべきもの、見直すべき運用を明確にしていきます。
特に注意したいのは、削るだけで満足しないことです。 必要な投資はしっかり残すことで、採用力そのものの底上げにつながります。
ステップ③属人化した業務を見直し、仕組み化へ
コストがかさんでしまう要因の多くは、業務の属人化や手作業の多さにあります。
- 求人票やスカウト文を毎回ゼロから作っていないか
- 候補者とのやりとりがすべて手動で行われていないか
こうした作業は、生成AIやRPAを使うことで効率化が可能です。マニュアルやテンプレート、ツールを活用しながら、再現性ある運用へと移行していくことが、コストの持続的な最適化につながります。
ステップ④改善を“運用の一部”として組み込む
施策は打った後が本番です。やりっぱなしにせず、定期的な効果測定と見直しを運用に組み込みましょう。
たとえば、施策ごとの採用単価や歩留まりを数値で追うことで、「何が効いているのか/いないのか」を早期に発見できます。
週次・月次でのチーム振り返りも効果的です。改善が習慣になれば、コストは自然と調整できるものになります。
ステップ⑤関係者と納得感のある変化を共有する
最後に大切なのは、チームや社内関係者と、変化の意図や成果をしっかり共有することです。
「なぜこの施策をやるのか」
「何がどう良くなったのか」
「どこを今後調整していくのか」
こうした共有を積み重ねることで、一過性ではない“文化としてのコスト最適化が根づいていきます。
まとめ:採用コストを削る前に、AIを活用して成果の出る仕組みを整えよう
採用コストの削減とは、単なる節約ではなく、採用そのものを見直し、成果の出る仕組みを整えることに他なりません。
- まずは現状を「見える化」し、ムダと必要な投資を切り分ける
- 属人的な業務をなくし、AIや仕組みで効率化する
- 定期的に見直しながら、継続的に最適化していく
この流れを実践できれば、採用コストの削減だけでなく、人事が攻めの役割を果たせる体制が整っていきます。採用改革の第一歩を、生成AI研修からはじめませんか?
AI採用コストに関するよくある質問(FAQ)
- Q採用コスト削減は、どの業界・規模の企業にも効果がありますか?
- A
はい。業種や企業規模を問わず効果は見込めますが、「どこを削るか」「何に投資するか」の戦略設計が重要です。
たとえば中小企業であれば、媒体費や紹介手数料の見直しが即効性のある対策になりますし、大手企業では業務の仕組み化や内製化による工数削減のインパクトが大きくなります。
どのフェーズにいるかによって最適なアプローチは異なりますが、「費用対効果を見直す」視点がすべての企業に共通します。
- Q採用代行や求人媒体をやめると、応募が減るのでは?
- A
単純な“脱・外注”はリスクですが、「内製+自動化」を組み合わせることで、むしろ質が上がる事例もあります。
ポイントは、“やめること”ではなく、“無駄な使い方を見直すこと”。求人票やスカウト文の質を高めたり、ターゲットに適した媒体へ絞り込むことで、応募数以上に採用の成功率が上がることも珍しくありません。
- QAI導入と聞くとハードルが高そう…。何から始めればいいですか?
- A
最初の一歩は「求人票やスカウト文のAI自動生成」など、身近な業務からのトライアルです。実際、導入が進んでいる企業の多くが「まずは一部の採用業務からAIを使ってみた」という流れで進めています。複雑な設定やIT知識がなくても使えるツールも増えており、“業務改善の手段”としてAIを自然に取り入れる時代になっています。
- Q採用コスト削減で社員のモチベーションが下がることはありませんか?
- A
コスト削減そのものよりも、“削減の伝え方・進め方”がモチベーションに大きく影響します。
「予算が減ったから業務が大変になる」
「人手もツールもなくなって負担が増えた」そうした状態を避けるためにも、“目的の共有”と“業務の仕組み化”がカギです。たとえばAIの活用で事務的な作業が減り、面談やフォローなど“人間にしかできない仕事”に集中できるようになると、むしろやりがいは高まります。