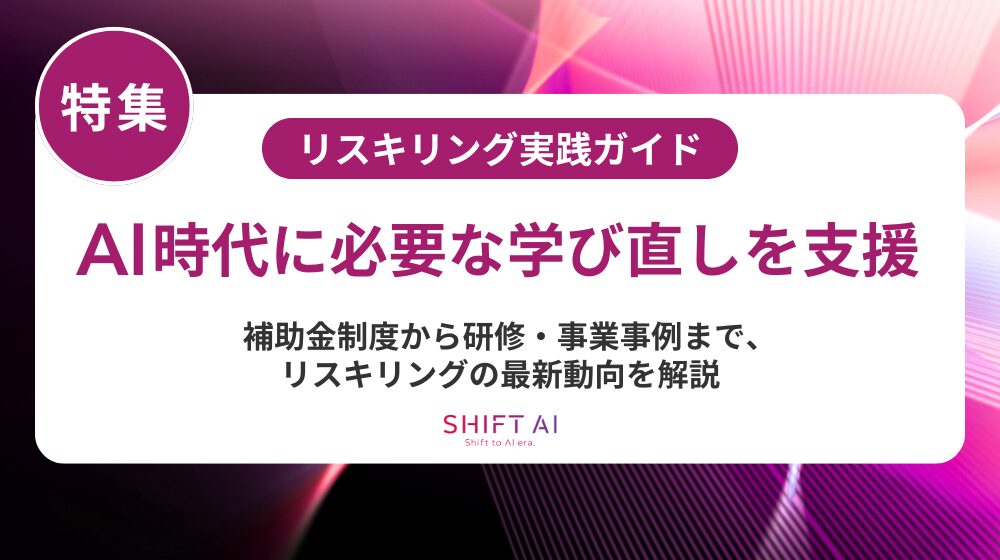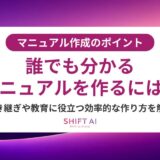「リスキリングを導入したいが、どこから始めればよいかわからない」「社内でリスキリングを推進しようとしても、なかなか進まない」——こうした悩みを抱える企業は少なくありません。
デジタル化や業務変革が加速する中、従業員の新しいスキル習得は企業の競争力維持に不可欠です。しかし、多くの企業がリスキリング推進において様々な課題に直面しているのが現実です。
本記事では、企業がリスキリング導入時に遭遇する具体的な課題を、企業側・従業員側・導入段階別に整理し、それぞれの解決策を詳しく解説します。
課題の根本原因を理解し、自社に最適なアプローチを見つけることで、リスキリングを確実に成功に導くことができるでしょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
リスキリングが進まない企業の課題と現状
多くの企業でリスキリングの必要性は認識されているものの、実際の取り組みは思うように進んでいません。導入への障壁や社内体制の問題が、リスキリング推進を困難にしているのが現状です。
取り組み企業が限られている現実
リスキリングに本格的に取り組んでいる企業は、まだ一部に限られています。
多くの企業が「リスキリングは必要」と考えている一方で、実際に体系的な取り組みを始められている企業は少数です。特に中小企業では、リスキリングの重要性を理解していても、具体的な行動に移せずにいるケースが目立ちます。
また、取り組みを始めた企業でも、単発の研修実施にとどまり、継続的な人材育成プログラムとして定着させられていない場合が多くあります。
中小企業ほど導入が遅れている理由
企業規模が小さいほど、リスキリング導入へのハードルが高くなっています。
中小企業では、リソースの制約が大きな要因となっています。限られた人員で日常業務を回している中で、新たに研修時間を確保することは容易ではありません。
さらに、専門的な指導ができる人材の不足や、研修プログラムを企画・運営するノウハウの欠如も課題です。大企業と比べて教育予算も限られており、外部研修の活用にも慎重にならざるを得ないのが実情です。
失敗企業に共通する課題パターン
リスキリングに失敗する企業には、いくつかの共通した課題パターンが見られます。
最も多いのは、明確な目的設定なしに「とりあえずリスキリングを始めた」というケースです。何のためのスキル習得なのか、習得後にどう活用するのかが不明確だと、従業員のモチベーションは上がりません。
また、経営層の理解不足も大きな問題となります。リスキリングを人事部門任せにし、全社的な取り組みとして位置づけられていない企業は、継続的な成果を上げることが困難です。さらに、短期間での成果を求めすぎて、途中で取り組みを断念してしまうパターンも少なくありません。
企業がリスキリング推進で直面する課題
企業側の視点から見ると、リスキリング推進には三つの大きな課題があります。予算・時間の制約、指導人材の不足、学習内容の選定といった根本的な問題が、多くの企業の取り組みを阻んでいるのが現状です。
予算と時間を確保できない
リスキリング実施に必要な予算と時間の確保が、最大の課題となっています。
研修実施には、教材費や講師費用、会場代などの直接的なコストがかかります。さらに、研修期間中は従業員が通常業務から離れるため、その分の機会損失も発生します。特に人員に余裕のない中小企業では、この時間的制約が深刻な問題です。
また、リスキリングは継続的な取り組みが必要なため、単発の研修費用だけでなく、長期的な教育投資を考慮する必要があります。しかし、成果が見えにくい人材育成への投資は、経営判断として優先度が下がりがちです。
指導できる人材がいない
社内にリスキリングを指導できる専門人材がいないという課題があります。
新しいスキルを教えるには、その分野の専門知識に加えて、教育・指導のスキルも必要です。しかし、業務に精通している社員が必ずしも教育上手とは限りません。効果的な研修を実施するには、適切な指導方法や学習プロセスの理解が不可欠です。
特にデジタル分野のスキルなど、急速に進歩する技術領域では、最新の知識を持った指導者の確保がより困難になります。外部講師を招くという選択肢もありますが、コスト面での負担が大きくなってしまいます。
何を学ばせるべきかわからない
従業員にどのようなスキルを習得させるべきか判断できない企業が多くあります。
リスキリングの効果を最大化するには、自社の事業戦略と連動したスキル選定が重要です。しかし、将来必要となるスキルを正確に予測することは容易ではありません。技術の進歩や市場環境の変化により、今重要だと思われるスキルが数年後には陳腐化している可能性もあります。
また、現在の業務で必要なスキルと、将来的に必要になるスキルのバランスを取ることも難しい課題です。短期的な業務改善を重視するか、長期的な変革に備えるかで、学習内容の方向性が大きく変わってきます。
従業員のリスキリング参加を阻む課題
従業員側にも、リスキリングへの積極的な参加を妨げる要因が存在します。モチベーションの問題、重要性認識の不足、時間的制約が主な課題として挙げられます。
モチベーションが上がらない
従業員のリスキリングに対するモチベーション不足が深刻な問題となっています。
新しいスキルの習得には相当な努力と時間が必要です。しかし、その努力に見合うメリットが明確でないと、従業員は学習に対して消極的になってしまいます。特に、習得したスキルが現在の業務や将来のキャリアにどう活かされるのかが不透明な場合、やらされ感が強くなります。
また、学習の進捗が遅い従業員や、新しい分野への適性に不安を感じる従業員は、途中で挫折してしまうリスクが高くなります。個人の学習ペースや理解度に配慮した支援体制がないと、モチベーション維持は困難です。
学習の重要性を理解していない
なぜリスキリングが必要なのか、従業員が十分に理解していない場合があります。
現在の業務に支障がない状況では、新しいスキルの必要性を実感することは困難です。特に安定した業界で働く従業員は、変化への危機感が薄く、スキルアップの緊急性を感じていません。
企業側が将来のビジョンや戦略変更について十分に説明していない場合も問題です。従業員が会社の方向性を理解していなければ、リスキリングの意味を見出すことはできません。単なる「会社の方針」として受け取られ、主体的な学習姿勢につながらないのです。
忙しくて学習時間を作れない
日常業務の忙しさにより、学習時間を確保できない従業員が多くいます。
多くの職場では、従業員が既存業務で手一杯の状況が続いています。そこにリスキリングという新たなタスクが加わると、時間的負担が増大します。特に残業が常態化している職場では、業務時間外での学習は現実的ではありません。
また、家庭の事情により、勤務時間外の学習が困難な従業員もいます。子育てや介護などの責任を抱えている場合、自己学習に充てられる時間は限られています。こうした個人の事情に配慮した学習環境の整備が求められています。
リスキリング導入段階別に発生する課題
リスキリングの導入プロセスでは、各段階で異なる課題が発生します。検討段階、実施段階、継続段階それぞれの課題を理解し、適切に対処することが成功の鍵となります。
導入検討時に経営層を説得できない
リスキリング導入の必要性を経営層に理解してもらえない課題があります。
経営層にとって、リスキリングの投資対効果は見えにくいものです。研修費用や時間的コストは明確である一方、得られる成果や収益への影響は不確実で、測定も困難です。短期的な業績向上を重視する経営者にとって、人材育成への投資は優先度が低くなりがちです。
また、リスキリングの効果が現れるまでには時間がかかるため、即効性を求める経営陣の理解を得ることは容易ではありません。競合他社の動向や業界トレンドを具体的に示し、リスキリングを行わないリスクを明確化する必要があります。
実施中に社内の協力を得られない
リスキリングプログラムの実施段階で、社内の協力体制が整わない問題があります。
現場管理職の中には、部下が研修に参加することで業務に支障が出ることを懸念する人がいます。特に忙しい部署では、研修参加を快く思わない雰囲気が生まれやすく、従業員が参加しづらい状況となります。
また、リスキリング対象者以外の従業員から、「なぜ特定の人だけが研修を受けられるのか」という不公平感の声が上がることもあります。こうした社内の理解不足や協力不足は、プログラム全体の効果を大きく損なう要因となります。
継続時に効果を実感できない
リスキリング継続段階で、期待した効果が見えずに挫折してしまう課題があります。
スキル習得には時間がかかるため、短期間では目に見える変化は現れません。しかし、成果が見えない期間が続くと、投資の妥当性に疑問を持つ声が社内で高まります。特に費用対効果を重視する企業では、継続への支持が得られなくなるリスクがあります。
また、習得したスキルを実際の業務で活用する機会がないと、学習の意味を見失ってしまいます。学んだ知識を実践に移せる環境や業務の整備が不十分だと、せっかくのリスキリングも形骸化してしまうのです。
リスキリングの課題を解決する方法
これまで見てきた課題を克服するには、体系的なアプローチが必要です。自社分析による方向性の明確化、外部パートナーの活用、段階的な導入という三つの方法が効果的な解決策となります。
自社分析で学習内容を明確化する
まず自社の現状と将来像を分析し、必要なスキルを特定することが重要です。
事業戦略と人材戦略を連動させ、今後の事業展開で必要となるスキルを洗い出します。現在の従業員が保有するスキルとのギャップ分析を行うことで、リスキリングの優先順位が明確になります。また、業界動向や競合他社の取り組みも参考にしながら、学習内容を決定します。
重要なのは、抽象的な目標ではなく、具体的な業務やプロジェクトでの活用を前提としてスキルを選定することです。「将来役立ちそう」ではなく、「この業務で必要」という明確な根拠があれば、従業員の理解と協力も得やすくなります。
外部パートナーを活用して指導力不足を補う
社内リソースの限界を認識し、外部の専門家を活用することが効果的です。
研修会社や教育機関との連携により、専門的な指導力と体系的なカリキュラムを確保できます。外部パートナーは豊富な実績とノウハウを持っており、効率的な学習プログラムの提供が可能です。また、社内講師では対応困難な最新技術分野の教育にも対応できます。
外部活用のメリットは、指導の質の向上だけではありません。社内のリソースを通常業務に集中できるため、業務への影響も最小限に抑えられます。さらに、客観的な視点からの指導により、社内では見落としがちな課題の発見にもつながります。
段階的導入でリスクを最小化する
小規模なパイロットプログラムから始め、段階的に拡大していく方法が安全です。
いきなり全社規模でリスキリングを開始するのではなく、限定的な部署や職種から試験導入します。この方法により、プログラムの有効性を検証し、問題点を早期に発見・修正できます。成功事例を積み重ねることで、社内の理解と協力も得やすくなります。
また、段階的導入により、予算や時間的負担を分散できます。初期段階で大きな投資を行うリスクを避けながら、着実に成果を積み上げていくことが可能です。各段階での学びを次のフェーズに活かし、より効果的なプログラムへと発展させていきましょう。
まとめ|リスキリング課題は段階的アプローチで解決可能
リスキリング推進における課題は、企業側の予算・人材・方針の問題と、従業員側のモチベーション・理解・時間の問題に大別されます。これらの課題は導入段階ごとに異なる形で現れるため、一律の解決策では対処できません。
成功の鍵は、自社の現状を正確に把握し、最も影響の大きい課題から優先的に取り組むことです。社内リソースだけでは限界がある場合、外部の専門パートナーを活用することで、効率的かつ確実な課題解決が可能となります。
リスキリングは企業の将来を左右する重要な投資です。しかし、適切なアプローチを選択すれば、必ず成果につながる取り組みでもあります。まずは自社の課題を整理し、最適な解決策を見つけることから始めてみませんか。

リスキリングの課題に関するよくある質問
- Qリスキリング導入にどのくらいの予算が必要ですか?
- A
予算は実施規模や内容により大きく異なりますが、まずは小規模なパイロットプログラムから始めることが重要です。 外部研修を利用する場合、1人あたり数万円から数十万円程度を目安に考え、段階的に拡大していく方法が効果的です。初期投資を抑えながら、自社に最適なプログラムを見つけることができます。
- Q従業員がリスキリングに参加したがらない場合はどうすれば良いですか?
- A
参加のメリットを具体的に示し、キャリアとの関連性を明確化することが大切です。 学習内容が将来の業務や昇進にどう役立つかを説明し、段階的な目標設定で達成感を味わえる仕組みを作ります。また、業務時間内での研修実施や、学習成果に対する適切な評価制度の導入も効果的です。
- Q何から学習を始めれば良いかわからない場合はどうしますか?
- A
事業戦略と現在の業務内容を分析し、最も緊急性の高いスキルから特定します。 まず現在の従業員スキルを棚卸しし、将来必要となる能力とのギャップを明確化します。デジタルスキルやコミュニケーション能力など、汎用性の高いスキルから着手するのも一つの方法です。
- Qリスキリングの効果が見えない場合はどうすれば良いですか?
- A
効果測定の指標を事前に設定し、定期的な評価を行うことが重要です。 スキル習得には時間がかかるため、短期的な変化だけでなく、中長期的な視点で評価します。学習進捗の可視化や、習得したスキルを実務で活用する機会の創出により、効果を実感しやすい環境を整えましょう。
- Q中小企業でもリスキリングは実施できますか?
- A
限られたリソースでも、工夫次第で効果的なリスキリングは可能です。 eラーニングの活用や業務時間内での短時間研修、外部研修機関との連携により、コストを抑えながら質の高い教育を提供できます。また、従業員同士の知識共有や、段階的なスキルアップ制度の導入も有効な手法です。